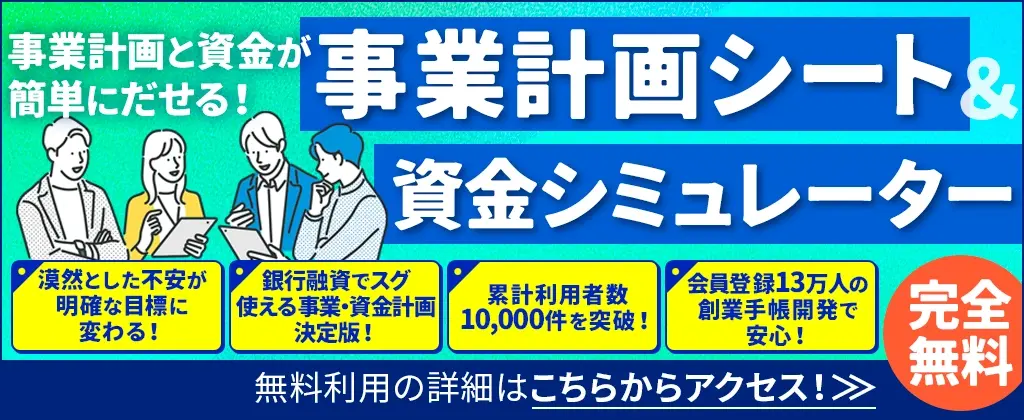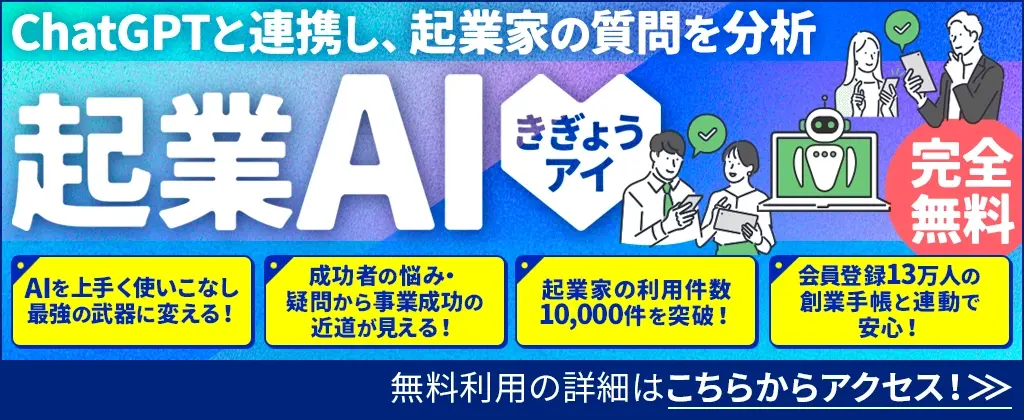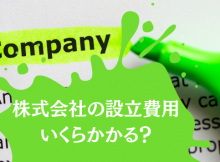起業に必要な費用は?いつ・何が・いくらかかるか、資金調達の方法も解説
登記から準備・運営まで、実際はいくらかかる?

いざ起業を志したとき、一番の不安要素になるのが「お金」です。いくら事業のビジョンがしっかりしていても、必要な費用が準備できなければ、起業することはできません。
今回は、起業および会社設立に必要な費用について具体的にご紹介します。いつどんな費用がいくらかかるのかを明確に把握し、資金計画をクリアにしておきましょう。
起業にまつわるお金の不安、その原因はズバリ情報不足です。「創業手帳(無料)」では、会社設立費用や起業後のランニングコスト、資金調達の方法まで、起業×お金の「今すぐ知りたい!」をギュッとまとめました。250万人もの起業家が手に取り、次の一歩を踏み出しています。
創業手帳が作成した「事業計画シート&資金シミュレーター(無料)」では、スマホからも手軽に資金計画を作成できます。何度も編集可能ですので、ぜひこの機会にご活用ください。
起業家の質問1万件分を分析した「起業AI(無料)」に起業の悩みや疑問を聞いてみるのもおすすめです。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【法人・個人】起業の費用目安
日本政策金融公庫の2024年度新規開業実態調査によると、開業費用の中央値は580万円となっています。
具体的にどのような費用が必要か、法人として複数人で開業する場合と、個人事業主の場合とで目安を比べてみましょう。
| 項目 | 法人(株式会社・3人の場合) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 手続き | 17万~26万円 | 0円 |
| 事務所 | 50万円(賃料月10万円、敷金礼金各2カ月分の場合) | 0円~ |
| パソコン | 10万~15万円(1台3万~5万円の場合) | 3万~5万円 |
| デスク・イス | 75,000~9万円(1セット25,000~3万円の場合) | 0円~ |
| 通信費 | 25,000円~(月5,000円、開設費2万円の場合) | 0円~25,000円(月5,000円、開設費2万円の場合) |
| 人件費 | 90万円~(1人30万円の場合) | 0円~ |
| 資本金 | 1円~ | 0円 |
| 運転資金 | 300万円~600万円(予備費込みで3~6カ月分) | 75万~150万円(予備費込みで3~6カ月分) |
| 合計 | 約505万~816万円 | 約78万~157万円 |
個人の場合、起業の際に必要な手続きは開業届の提出です。開業届を出すのに費用はかからず、税金や資本金も必要ありません。
また、自宅開業の場合はほとんどの費用を節約できます。パソコンやインターネットも自前なら、数カ月先までの生活費(運転資金)を準備しておくだけでいい場合が多いでしょう。
株式会社として開業するには登録免許税や定款認証手数料などがかかります。人数が多いほど備品などの費用も増えるので、資金を出し合ったり、削る費用を相談したりするなどの調整が必要です。
今回の表では、資本金は最低額の1円からで計算していますが、信用問題などを現実的に考えると、100万円以上は用意することをおすすめします。
【法人形態別】起業時の設立費用を一覧
株式会社や合同会社などの法人を設立して起業する場合は「登記」をしなくてはならず、登記には費用が必要です。法定費用とも呼ばれ、会社設立にかかる費用のほとんどを占めます。
法人として起業する際にかかる、会社形態別の設立費用の目安を見ていきましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 以下の高いほう ・15万円 ・資本金の0.7% |
以下の高いほう ・6万円 ・資本金の0.7% |
6万円 | 6万円 | 不要 |
| 謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 | 約2,000円 | 約2,000円 | 不要 |
| 定款認証手数料 | 15,000〜5万円 | 不要 | 15,000〜5万円 | 15,000〜5万円 | 不要 |
| 印紙代 | 4万円 (電子定款は不要) |
4万円 (電子定款は不要) |
不要 | 不要 | 不要 |
| 資本金または拠出金 | 別途必要 (1円以上) |
別途必要 (1円以上) |
不要 | 300万円以上の財産拠出 | 不要 |
| その他費用 | 約1万円 | ||||
| 合計費用目安 | 約16万7,000〜25万7,000円 (資本金は別途) |
約6万〜10万円 (資本金は別途) |
約7万7,000〜11万2,000円 | 約7万7,000〜11万2,000円 (+拠出300万円) |
約1万円 |
登記必要以外にかかる「その他の費用」とは、
- 会社の実印作成代
- 個人の印鑑証明書取得費
- 登記簿謄本の取得費
などの雑費が合計1万円程度かかると考えてください。
また、会社設立を専門家に依頼する場合、費用が別途かかります。専門家によりますが、設立のみを依頼する場合(約25万円~30万円)と、税理士の顧問契約(会社設立+年間顧問料で約50万円)を含む場合とでは、費用が大きく変わるので、予算や起業後に欲しいフォローに合わせて選ぶといいでしょう。
株式会社の場合
会社形態として一般的な「株式会社」で起業する際にかかる設立費用は、「約17万〜約25万円+資本金」がかかります。
法定費用(必ず必要な費用)の内訳は以下のとおりです。
| 法定費用の項目 | 費用概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 15万円か、資本金の0.7%の額の、どちらか高い方 |
| 謄本手数料 | 約2,000円(1ページ250円) |
| 定款認証手数料 | 15,000~5万円 |
| 印紙代 | 4万円(電子定款認証の場合は不要) |
| 合計 | 約16万7,000~25万7,000円(資本金は別途必要) |
定款認証手数料とは、作成した定款が適切であることを公証人に認証してもらうための費用で、資本金額によって料金が変動します。
株式会社では法定費用に加えて「資本金」が必要です。資本金は1円からでも設立できますが、会社の運営や社会的信用のことを考えると、一定額は準備するほうが無難です。
資本金額は事業によって違いますが、資金調達を検討している場合は銀行などに与える印象を考慮して、100万円ほどは必要とも言われています。
合同会社の場合
合同会社は、出資者の少ない個人経営に適した会社形態です。「約6万〜10万円+資本金」で設立できます。
| 法定費用の項目 | 費用概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円か、資本金の0.7%の額の、どちらか高い方 |
| 印紙代 | 4万円(電子定款認証の場合は不要) |
| 合計 | 約6万~10万円(資本金は別途必要) |
株式会社との大きな違いは、登録免許税の額と、公証人の定款認証がいらない点です。資本金やその他の費用の考え方は株式会社やほかの形態と同じになります。
初期費用が低く手続きも簡単なので、小規模にスタートしたい個人にもハードルの低い形態です。合同会社の特徴や株式会社との違いも知った上で選択することをおすすめします。
一般社団法人の場合
一般社団法人は、営利を目的とせず、人の集まりを基盤とする法人です。法人自身の財産は不要=設立時の資本金の払い込みは不要という特徴があります。設立費用の目安は「約8万~11万円」です。
| 法定費用の項目 | 費用概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円 |
| 謄本手数料 | 約2,000円(1ページ250円) |
| 定款認証手数料 | 15,000~5万円 |
| 合計 | 約77,000~11万2,000円 |
一般社団法人は印紙税が非課税なので、電子定款でも、紙の定款でも、印紙代はかかりません。
なお、一般社団法人には、税法上の区分として普通型(営利型)と非営利型があります。設立費用はどちらも同じですが、非営利型に区分されると税制優遇が受けられるため、税金面でのメリットが大きいと言えます。
一般社団法人はやや公共性が高いイメージがあり、会員ビジネスや検定ビジネスなどで起業したい場合に親和性が高い会社形態です。
一般財団法人の場合
一般財団法人は、設立者の財産を基盤にして事業を行う法人です。法定費用は一般社団法人と同じ「約8万〜11万円」ですが、設立者による財産の拠出が最低でも300万円求められます。
| 法定費用の項目 | 費用概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円 |
| 謄本手数料 | 約2,000円(1ページ250円) |
| 定款認証手数料 | 15,000~5万円 |
| 合計 | 約77,000~11万2,000円(財産の拠出は別途300万円必要) |
ほかの会社形態と違って資本金ではなく設立者の財産が必要であり、最低金額も大きく設定されています。
株式会社や合同会社などは状況に応じて資本金を設定すればいいため、起業時は法定費用を中心に計画を立てやすいですが、一般財団法人の場合は300万円を含めた費用を考えておくべきでしょう。
NPO法人の場合
NPO法人は、特定非営利活動法人と呼ばれ、社会的貢献活動を行い、団体の構成員に収益を分配することを目的にしていない法人です。
NPO法人の設立には、資本金、登録免許税、定款認証手数料などはかかりません。印鑑作成や証明書取得などの費用のみで設立できます。
「申請→認証→登記」のステップを経て設立するため、すべてを完了させるのに2〜3カ月前後かかる点に注意が必要です。
NPO法人として活動できるのは、法律で20種に限られており、該当する活動を目的としていれば設立できます。
タイミング別:起業に必要なお金
起業には、会社設立そのものにかかる費用だけではなく、実際に事業を行うために必要な費用も多数あります。いつどのような費用がかかるのか、タイミング別にみてみましょう。
起業前~起業時に必要な費用
起業するまでの準備物に支払う費用、法人の設立など起業時に必要となる主な費用をそれぞれまとめました。
| 主な費用 | 内訳・費用の目安 |
|---|---|
| 設立費用(法定費など) | ・個人:0円
・法人:0~約27万円 |
| 事務所・店舗の費用 | ・賃貸:敷金礼金を数カ月分
・購入、新築、リノベなど:購入総額の数割の頭金(ローン) |
| 備品類の費用 | ・パソコン:1台3万~5万円
・デスク、イス:1セット25,000~3万円 ・その他:業種に応じて機械設備、材料仕入れなど |
事務所や店舗を契約する場合、賃貸なら初期費用として家賃数カ月分の敷金礼金が必要なことが一般的です。
店舗などの購入をローンで考えていても、事業用の不動産は頭金を求められることが想定されるので、購入総額の何割かは用意しておくべきでしょう。また、公庫の事業融資では不動産の契約済みを前提に話が進むため、起業前からの準備が欠かせません。
業種に応じて変動が大きいのが備品類です。IT系ならパソコンさえあればどうにかなっても、飲食店だと厨房やテーブル、レジ周りの設備も必要など、費用が全く異なります。
起業前〜起業時に必要な費用は、業種に応じて余裕を持たせることが大切です。
起業後に必要な費用
起業の直後、ビジネスをスタートさせてからすぐにかかる主な費用は次のとおりです。
| 主な費用 | 内訳・費用の目安 |
|---|---|
| 人件費 | ・個人(1人で起業):0円(自身の生活費は別途)
・雇用:月10万~30万円 ・業務委託:月数万円~ |
| 通信費 | ・開設費:2万円~
・使用料:月5,000円~ |
| 賃貸料 | ・事務所:5万円~
・実店舗:10万円~ ・バーチャルオフィス:約1,000~5,000円(初期費用は別途) |
| 広告宣伝費 | ・名刺の作成費:500円~(100枚)
・ホームページの作成費:5万~30万円 ・ホームページの運用費:年5,000円~ ・チラシ、Web広告制作費:1回1万円~ |
| 専門家費 | ・月1~2万円 |
もっとも大きな費用は人件費で、従業員を雇う場合は一定額が継続的にかかります。賃貸料は場所や物件内容、広告宣伝費は何にどこまでかけるかで費用が大きく左右されるでしょう。
こうした費用を抑えるコツは「創業手帳(無料)」で紹介しています。例えば多くの人に見てもらえるホームページの作り方、シェアオフィスやコワーキングスペースなど新しい拠点の形なども詳しく解説中です。
起業資金の集め方・調達方法
ここまで見てきたように、起業する際にはさまざまなお金が必要になります。とはいえ、数百万〜数千万円といった資金は簡単には用意できないもの。最後に、こうした起業にかかる費用はどのようにして集めることができるのか解説します。
自己資金
最も安全でトラブルにもなりにくいのは、自己資金を準備して起業に充てることです。自己資金を準備する方法としては、たとえば次のようなものがあります。
- 貯金
- 生命保険の解約
- 退職金
- 株式や投資信託、不動産の売却
会社員として勤めながら将来の起業に向けて準備をする方も多いと思います。この準備期間中に自己資金を増やせるよう、上記のようなことを検討してみてください。
補助金・助成金
起業前後の資金調達に補助金・助成金を活用する方法があります。要件を満たす必要はありますが、原則として返済不要なため、低リスクで資金調達が可能です。
起業時に活用できる補助金・助成金には以下のような制度があります。
- 小規模事業者持続化補助金:補助上限200万円(創業枠)
- 起業支援金:最大200万円(詳細は自治体による)
国や地方自治体から多くの制度が提供されています。起業時に活用できる補助金・助成金をチェックして、事業のスタートや拡大に役立ててください。
融資
まとまった事業資金を調達する手段としてオーソドックスなのが融資です。融資は大きく2つに分けられ、日本政策金融公庫の公的融資と、民間銀行の創業融資などがあります。
| 融資の提供機関 | 主な融資 | 融資限度額 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金(国民事業) ・女性、若者/シニア起業家支援関連 ・中小企業経営力強化関連 |
7,200万円 (うち運転資金4,800万円以内) |
| 銀行 | 銀行ごとの創業融資、事業融資など | 数百万~数千万円 |
日本政策金融公庫は、国の政策のもと民間の金融機関の補完を行う金融機関であり、起業時の基本的な資金調達先の一つです。
代表的な「新規開業・スタートアップ支援資金」は低利率で融資を受けやすく、女性やシニアの優遇枠、新たな分野に挑戦する中小企業を支援する枠などがあります。
民間銀行が独自に提供する融資を利用する手もありますが、公庫の融資制度に比べると審査が厳しい傾向にあるため注意が必要です。銀行によっては公庫と連携した創業融資を提供していることもあるので確認してみましょう。
融資を基本から知りたい方は融資ガイドがおすすめ。以下のバナーから!
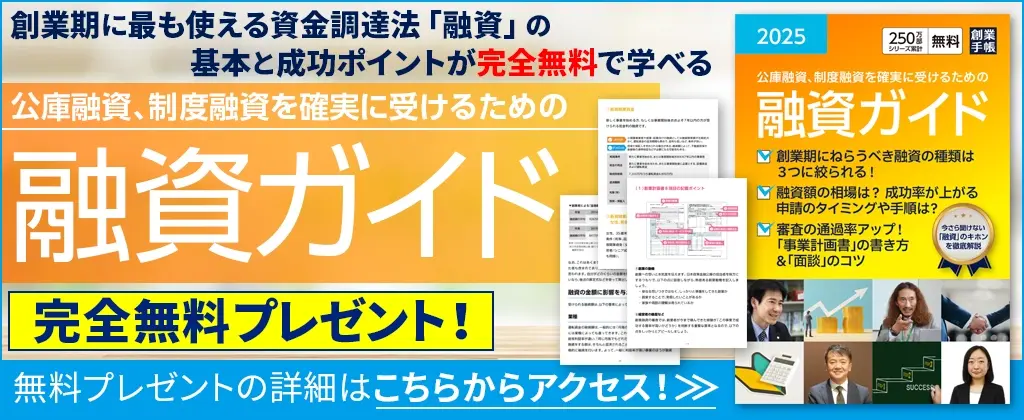
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、実現したい事業や夢を掲げ、インターネットなどを通じて個人から少額ずつお金を集めることができる仕組みです。
特徴的な商品・サービスや強い共感を呼ぶストーリーがあれば、数百万円規模の資金を集められる可能性もあるなど、実績の少ない起業初期でもチャンスがあります。
CAMPFIRE(キャンプファイヤー)やMakuake(マクアケ)など、サービスも増えているので一度覗いてみると良いかもしれません。
エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)
投資家からの出資を受ける方法もあります。投資家によって調達額はさまざまですが、返済不要のお金を数十万円〜数百万円の規模で調達可能です。
ただし、出資した投資家が経営に介入してくる可能性もあるので、場合によっては起業後に自由な経営がしづらくなってしまうこともあります。
事業売却やIPO(株式公開)を目指して起業する場合には、投資家やVCからの資金調達がおすすめです。逆に、そうしたものを目指さない起業であれば、融資で安定的に経営していく方が良いでしょう。
エンジェル投資家とベンチャーキャピタル(VC)は性質が違うため、状況や目的に応じて使い分けるために、それぞれの特徴も事前に知っておくのもポイントです。
まとめ・起業の費用を計算して資金計画を立てよう
起業する際には、予想していない部分でお金がかかることが多いですが、必要なお金をあらかじめ知っておけば、計画的に資金調達が可能です。
個人と法人との費用差、法人形態による設立費用の違いなどを理解した上で、起業資金を準備してください。
資金繰りを甘く見ていると、起業後に後悔する恐れがあります。「創業手帳(無料)」では、お金の流れが一目でわかる資金繰り表の作り方をまとめました。起業前に一つ用意しておくだけで、お金の不安解消に役立ちます。
スマホからも使える「事業計画シート&資金シミュレーター(無料)」では、事業計画だけでなく、資金計画も一緒に作成可能です。詳しくは以下のバナーから!
また、「起業AI(無料)」では、「よくある質問のランキング」や、「おすすめの質問」などを確認できます。
詳しくは以下のバナーから!
(執筆:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「資金調達手帳」は資金調達の方法をはじめとし、キャッシュフロー改善のマル秘テクニックや創業計画書の書き方も充実。無料でお届けいたしますのでご活用ください。