法人の印鑑証明書の取り方 | 手数料は?どこで?郵送は可能?
会社(法人)における印鑑証明書取得方法や、発行の仕方を解説します

皆さん、一度は印鑑証明書を取得したことがあるのではないでしょうか。しかしそれは、個人の話。法人の印鑑証明書の取得方法には、いくつか異なる点があります。手数料は?どこで取得するのか?郵送は可能か?など印鑑証明書を取得する際の疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、印鑑証明書の取得について具体的な手順を解説します。
会社設立時の手続きにおいて法人印鑑は必須です。冊子版の創業手帳(無料)では、設立時に準備しておくべき3つの法人印鑑について詳しく解説しています。併せて、契約書の基本についても解説していますので、チェックしてみてください。
また、法人設立時に準備すべきことを時系列にまとめた創業カレンダー(無料)もご用意しております。設立1年前から1年後に「やるべきこと」が時系列で分かります。準備をスムーズに、効率的にすすめるために、是非ご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人における印鑑証明書とは
印鑑証明書とは法人の代表印が本物の実印であると証明する書類で、個人の実印を登録した書類は印鑑登録証明書と呼びます。
印鑑証明書には、代表印・本店所在地・商号・代表者の役職名・氏名・生年月日・発行年月日を登録します。
「印鑑証明が必要」と言われた場合、法人は「印鑑証明書が必要」ということです。
法人印鑑証明書の必要性
印鑑証明書は代表印が本物だと証明する書類です。代表印を押した書類に添えて提出することで、取引きの安全性を確保する目的があります。
印鑑証明書があると代表印の偽装を防げるため契約時のリスク回避にも役立ち、お互いを信用するに足る根拠になります。
個人の本人確認には顔写真付きの証明書などを使いますが、法人には顔写真がありません。その代わりに印鑑証明書を用います。
どんなときに法人印鑑証明書が必要になる?
法人の設立においては、法務局に法人の印鑑を登録することが必須となりますが、登録後はどのような場合に使用するのでしょうか。
具体的には、法人口座開設のときに「印鑑証明」が必要になります。書類に不備があると口座開設は難しくなります。他にも、不動産の売買契約、所有権の移転登記、取引先の契約書に実印を求められたときなどが想定されます。いざ、必要となったときに迅速に対応できるよう印鑑証明の取得の手続きを事前に把握しておくことが望ましいですね。
事前準備|まずは、法人の印鑑登録をしよう。
法人印鑑の登録方法
法人の印鑑証明書の取り方を解説する前に、まず印鑑登録をしていない方向けに、簡単に登録方法を解説しておきます。
ご存知の通り、個人における印鑑登録は、市区町村の役所の窓口で行うことができます。一方、法人の印鑑登録は、法務局に「印鑑届書」というものを提出する必要があります。登録には、本人による届出のほか代理人による届出も可能です。本人が法人の印鑑登録を行う場合、個人の実印も必要となります。また、代理人の場合は、認印でも可能です。一般的には、法人登記時に印鑑登録を済ませている方が多いかと思いますので、届出書の詳細は法務局のホームページをご参照ください。
法人印鑑登録するときの注意点
「法人印鑑」と言われるとなんだか立派な印鑑を作らなければと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、実際は業務のデジタル化が進んできており前ほど「印鑑」そのものはなんの素材でもよいという風潮にあります。
印鑑にこだわる必要はありません。象牙ではないからと言って、それによる信用性が落ちることはありません。
なお、法人の印鑑をつくる場合には、次の3セットが必要となります。
- 実印(代表者印、法人実印、角印)→法務局に登録手続きをします。
- 銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)→法人口座開設、小切手の発行に必要です。
- 社印(角印)→請求書、領収書、見積書などに押印する通常使いのもの
事前準備|法人の印鑑証明書 取得の基礎知識

全く事前知識がないものと仮定し、印鑑証明書を取得する際に「まず把握しておきたいポイント」を質問形式で解説していきます。
法人の印鑑証明書は、どこで取得するの?
まず出てくる疑問が、「法人の印鑑証明書をどこで取ればよいか」ということです。法務局の窓口に直接行くか、オンラインでの請求も可。法務局の窓口に行く場合全国の法務局のどこでも手続きが可能です。以前は、印鑑証明書を請求するには、指定された特定の法務局での手続きのみでしたが、いまでは会社の所在地に関わらず、どこでも可能となっています。また、事前に法人の電子証明をしている場合、オンラインでいつでも印鑑証明書を取得できます。
マイナンバーカードがあればオンライン請求をして窓口受取を選ぶと、窓口請求よりも安く印鑑証明書の取得が可能です。手順は、後ほど詳しく説明します。
法人の印鑑証明書を請求するのは、社長じゃなきゃだめ?
法人の印鑑証明書を取るには、最寄りの法務局に行くもしくはオンラインで取得すれば良いことがわかりました。では、誰が行けば良いのでしょうか。
印鑑証明書は、実は代表以外の代理人でも請求が可能で、委任状なども必要ありません。しかし、気をつけなければならないのが、「印鑑カードが必要」だという点です。また、オンラインで印鑑証明書を請求する場合は、「公的個人認証サービス電子証明書」が必要になりますので注意が必要です。具体的には「セコムパスポートfor G-ID」といった提携先の外部サービスに氏名や住所を登録して利用するなどがあります。どのような証明書が必要なのかは、法務省のページに詳細がありますので参考にしてください。
印鑑カードとは
印鑑カードとは、文字通り法人の印鑑証明書を発行する際に必要となるカードです。会社設立・法人登記が完了し、実印を作ると印鑑カードが貰えます。代理人に委託する際は、忘れずに持参しましょう。
なお、印鑑カードも郵送で交付の請求・取得することができます。法務局のホームページに申請書があるので、ダウンロードして必要事項を記入して送付しましょう。その際には、返信用封筒や切手も忘れずに!
法人の印鑑証明書を請求する時、手数料はいくらかかるの?
法人の印鑑証明書を取得するには、手数料が必要です。窓口で1通450円と安価ですが、現金でないと支払いができない(印紙が買えない)ので、気をつけてください。なお、オンラインで請求すれば価格も少しお得になります!
| 種別 | 冊数 | 金額 |
| 会社・法人の登記簿謄抄本又は登記事項証明書 | 1通 | 600円 オンライン請求・交付 500円 オンライン請求・窓口交付 480円 |
| 登記事項要約書の交付 | 1通 | 450円 |
| 登記簿又は登記申請書の閲覧 | 1登記用紙 | 450円 |
| 資格証明書の交付 | 1通 | 450円 |
| 印鑑証明書の交付 | 1通 | 450円 オンライン請求・送付 410円 オンライン請求・窓口交付 390円 |
法人の印鑑証明書を請求するときに使う印鑑は?
法人の印鑑証明書を請求するときに必要な印鑑は、「代表者印」です。登録時には、以下を確認しておきましょう。
- 登記所に提出する印鑑の大きさは、一辺の長さが1cmから3cmの正方形に収める必要がある
- 印鑑は照合に適するものである必要がある
- 登録できる印鑑は商業登記規則第9条に定められている
- ゴム印やインク式スタンプ印は劣化が生じやすいため不可
登録できる代表印のサイズに幅がありますが1.8cmで作成する場合が多く、一般的な会社実印は、二重の丸印の真ん中へ「代表取締役の印」と入れます。
一般的な代表者印であれば、まず問題はないでしょう。
法人印鑑については、下記記事で詳しく説明しています。
>>法人印鑑|会社設立時に準備すべき実印・銀行印・角印
いざ取得|法人の印鑑証明書の取り方

さて、これまでの章で、印鑑証明書を取得するときに「どこに、だれが、何を持って」行けば良いかが分かったと思います。この章では、実際に法人の印鑑証明書の取り方を具体的に解説します。いくつか手段があるので、ご自身に適した方法で取得してみてください。
法人の印鑑証明書 取得方法1:窓口で申請する
最も一般的な方法が、窓口での申請です。
法務局窓口で申請すれば、印鑑証明書の即日発行を受けられます。
申請書は備え付けのものに記入するか、あらかじめホームページでダウンロードし記入したものを持参してください。
印鑑証明書交付申請書へ以下の記入をします。
- 会社の商号
- 会社等の住所
- 印鑑提出者の資格
- 氏名
- 出生年月日
※代理の場合は印鑑カード番号を書くのもお忘れなく!
そして、手数料額の収入印紙または登記印紙を申請書へ貼り付け、法務局の窓口まで提出します。
証明書発行請求機で請求できる場合もある
証明書発行請求機がある場合のみとなりますが、先程述べた「登記事項証明書等交付申請書」の記入を省略できる場合があります。証明書発行請求機の有無は、最寄りの窓口まで問い合わせてみるのが良いでしょう。
発行請求機の使い方は、印鑑カードを挿入し、請求情報を入力して整理券を発券します。その後窓口で呼ばれたら収入印紙を購入し、提出すれば取得できます。
法務局だけでなく最寄りの市役所庁舎に法務局証明サービスがあれば、そちらでも印鑑証明書の取得が可能です。
法人の印鑑証明書 取得方法2:郵便で請求する
窓口に行くよりは時間がかかる方法となりますが、印鑑証明書は郵便で請求することができます。申請には「申請書」「収入印紙」「返信用の封筒」「郵便切手」「印鑑カード」が必要となります。郵送での場合は、必要書類を漏れ無く入れて、請求しましょう。
注意!郵送の場合は書留で送ろう
印鑑証明書などの重要書類を郵便で請求する際には、機密情報保持の観点からセキュリティには気を使いたいですね。安全面から考えて、配達の記録が残る書留などを付けておくのが良いでしょう。
法人の印鑑証明書 取得方法3:オンライン申請
印鑑証明書をオンライン申請し取得する方法は複数あります。ここでは、法務局とマイナンバーカードでの請求方法をそれぞれ解説します。
個人の印鑑登録証明書は近くのコンビニで請求・取得できる場合がありますが、法人の印鑑証明書はどのコンビニでも請求・取得はできないので注意しましょう。
申請用総合ソフト
「申請用総合ソフト」とは、法務局が提供する登記・供託オンラインシステムです。
専用のソフトを法務局のホームページからダウンロードしパソコンへインストールするためには、環境設定と利用方法の習得が欠かせません。
印鑑証明書が必要になったときに初めから準備していると間に合わない可能性があるので、余裕のあるときに用意しておきましょう。
手数料は、インターネットバンキングで支払います。印鑑証明書の交付は、郵送か法務局で直接受け取るかのどちらかから選ぶようになります。
なお、受付時間は平日の8:30〜21:00と制限があるため、朝早くや夜遅く、土日の申請はできないので注意しましょう。
マイナンバーカード
マイナンバーカードで申請する場合、電子証明書を搭載したマイナンバーカードを用意します。
マイナンバーカードの発行時に電子証明書が不要だと申請していなければ、電子証明書は搭載された状態です。
申請方法は、パソコンのブラウザやソフトから、またはスマホのブラウザやアプリからのどちらかを選びます。
その後、JPKI利用者ソフトをダウンロードして電子申請を行います。
JPKI利用者ソフトとは公的個人認証サービスを使った電子申請の際に、マイナンバーカード搭載の電子証明書を使って証明を付与するものです。
このように起業関係の手続きがオンラインで行えると非常に便利です。冊子版の創業手帳では、登記書類をオンラインで自動作成してくれるサービスを紹介しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。要点を押さえれば、印鑑証明書の取得は意外と簡単ですよね。状況に応じた取得方法で、スムーズな手続きをしましょう。
印鑑証明書の取得など、起業時にはさまざまな手続きが必要となってきます。冊子版の創業手帳では、起業するにあたってやらなくてはならない手続きなどをまとめたスケジュール表を掲載しています。また、起業後に必要となる税務関係の手続きについては特に詳しく解説しています。
また、創業カレンダー(無料)では、日付を書き込めるので、自分だけの起業スケジュールが確認できます。具体的に起業への準備を進めたい方、起業前後の流れを把握したい方は、併せてご活用ください。
初めての起業・会社経営に!基礎知識をまとめたガイドブックプレゼント中
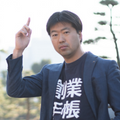 創業手帳 代表・大久保の解説
創業手帳 代表・大久保の解説
(執筆:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。


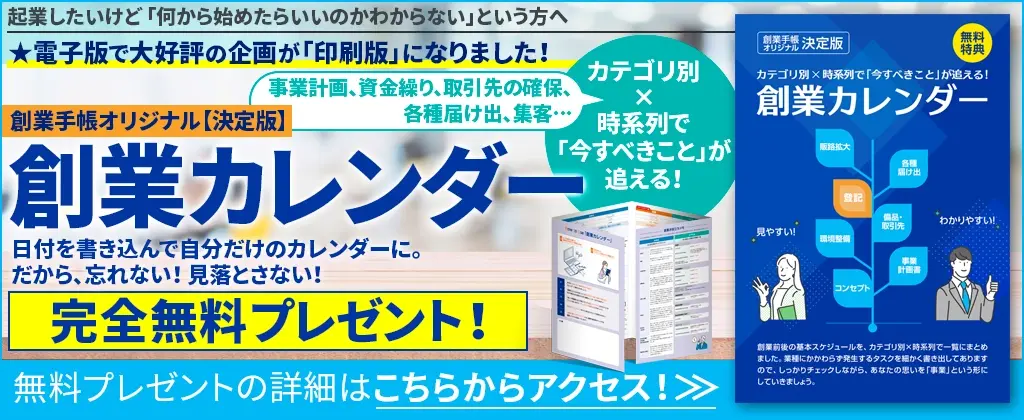
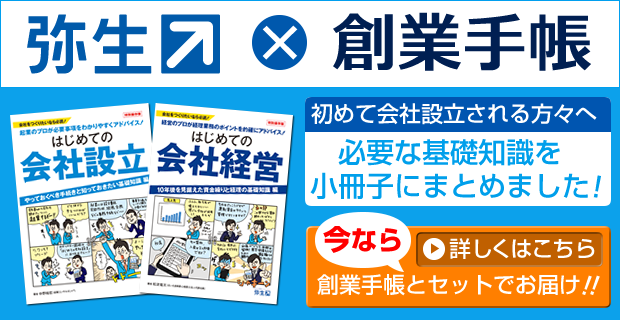
















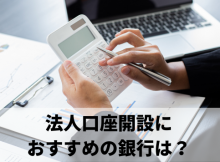





















創業手帳の代表・大久保です。
自分も起業時や起業を手伝うときに何かと出てくるのが印鑑登録証明書です。
法人登記や発起人、取締役なども必要だったり、銀行口座開設など何かと必要になってきます。
日本では未だにハンコ文化のため、現実問題として必要になるケースが多いです。
今ではマイナンバーカードがあればコンビニでも取れるなど簡略化が進んでいますが、期限までに印鑑登録証明書が間に合わない!というケースもあるので、早めに準備しておきましょう。