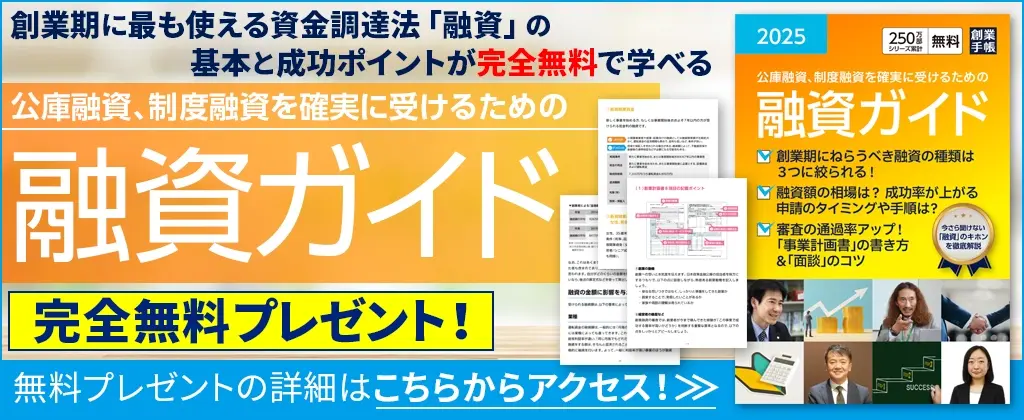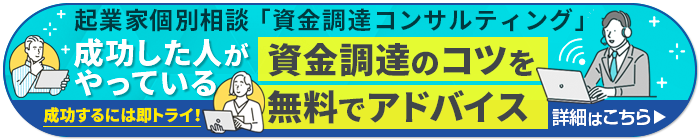【2025年最新】クラウドファンディングのやり方とは?仕組み・種類・始め方の手順ガイド
クラウドファンディングのやり方をわかりやすく徹底解説!

●クラウドファンディングの仕組み:種類ごとの違いや流れを解説。
●支援者を集めるためには、共感を生むプロジェクト紹介やSNS活用の重要
●プロジェクトの成功事例から、成功のポイントを分析
●魅力的なリターンを選ぶことで支援増加を狙う
●リスクや注意点として資金未達や手数料などを紹介
クラウドファンディングとは、インターネットを活用して「自分が立ち上げたプロジェクトに賛同してくれた人」から資金を調達することです。
今回は、クラウドファンディングをビジネスに活かす方法をみていきましょう。単にネット上で資金を募るだけでは成功しません。具体的なやり方や最適な種類を知ることで、クラウドファンディングでの目標達成が見えてきます。
クラウドファンディングの成功には、経験者の声を聞くのが近道です。資金調達手帳では、クラウドファンディングを立ち上げた起業家にインタビューを行い、成功の秘訣について伺っています。
クラウドファンディング以外にも、補助金ガイドで補助金や助成金の情報をチェックしたり、補助金AIで自分に合った制度を把握したりするのがおすすめです。すべて無料でご利用できます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは、「地域の社会問題を解決したい」「商品やイベントを事前にPRしたい」「テストマーケティングに活かしたい」など、実現させたい目標や夢のプロジェクトを公開して、支援者から資金を募る仕組みです。
漫画の原作を人気女優で映画化したり、アイドルの解散を惜しむ新聞全面広告を出したりという個人的なものから、へき地医療に使うヘリコプターを買ったり、待機児童の多い地域に保育所をつくったりという社会派なものまで、さまざまなプロジェクトがあります。
クラウドファンディングの仕組み
クラウドファンディングの仕組みの根幹にはインターネットがあります。ネット上にプロジェクトの概要や目的を掲載し、共感した人(個人・法人)に出資してもらう資金調達の方法です。
インターネットを用いることで、全世界の不特定多数から資金を集められます。1人あたりの支援が少額でも募集範囲が広大なため、プロジェクト次第では大規模な調達ができるほか、宣伝効果の期待も可能です。
一般的には、専用のクラウドファンディングサイトを通じて募集を行います。
融資や寄付との違い
起業や経営維持に必要な資金調達の方法として、融資や寄付もあげられます。クラウドファンディングとは何が違うのか、三者の主な差を以下にまとめました。
| 比較項目 | クラウドファンディング | 融資 | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 返済、リターンの必要性 | 種類によってリターンや返済が必要になる | 元本の返済と利息を支払う | 基本は必要ない |
| 資金の利用目的 | 支援者のつく目的が必要になる | 融資によって制限される場合もある | 支援者のつく目的が必要になる |
| 資金の規模 | 小~大まで期待できる | 企業価値などによって変動する | 小~大まで期待できる |
| 審査の有無 | 利用サイトの審査がある | 金融機関の審査がある | 基本はない |
| 資金調達以外の効果 | 宣伝やテストマーケティングに使える | 第三者が介入しない | 社会貢献活動との相性が良い |
クラウドファンディングは寄付に近いタイプが定番ですが、プロジェクトの成果に応じて商品やサービスを提供したり、融資のように返済義務が発生したりするものもあります。
プロジェクトの目的は基本的に自由なものの、支援者の目にとまるようなアイデアがないと資金が集まりません。
ネットを利用するので調達規模が大きくなる可能性があるほか、宣伝やファンの獲得といった副効果が期待できるのは、通常の融資や寄付にはない特徴です。
クラウドファンディングは個人でもできる
クラウドファンディングは、種類によっては個人でも実施可能です。必ずしも、法人や開業届を提出した個人事業主である必要はありません。
個人がクラウドファンディングを実施する場合、以下のようなプロジェクトが発案されています。
- 起業に向けた試作品の開発
- 古民家を改装した店舗づくり
- 地域を巻き込んだ街づくり
- アマチュアアーティストのCDやMVの制作
- 平和、平等などをテーマにしたアート制作
こうしたアイデアをもとに、クラウドファンディングを足がかりとし、個人でもビジネスに繋げられます。
創業や起業の前に、自分の持っているアイデアがビジネスとして通用するのかの力試しとして活用することも可能でしょう。
クラウドファンディングの種類と参加条件

クラウドファンディングには大きく「非投資型」「投資型」の2種類があり、さらに細かく分類できます。
| 種類 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 非投資型 | 購入型 | 商品やサービスの購入で支援する方式 |
| 寄付型 | 資金で支援する方式 | |
| ふるさと納税型 | ふるさと納税で支援する方式 | |
| 投資型 | 融資型 | 資金の融資で支援する方式 |
| 株式投資型 | 株式の売買で支援する方式 | |
| ファンド型 | 事業への投資で支援する方式 | |
非投資型は、金銭的なリターンではなく商品やサービスといった見返りを用意します。
投資型は明確に金銭的なリターンがあるため制約が厳しく、個人では扱えないものが多い方式です。特定の事業者登録が必要になるので、専門家に相談して活用しましょう。
ほかにも特徴が異なるので、1つずつ詳しく解説していきます。
【非投資型】購入型クラウドファンディング
クラウドファンディングと聞いて、最もイメージしやすいのが「購入型クラウドファンディング」です。
支援者に商品やサービスを買ってもらい、購入代金として資金を調達します。
支援者はまだ販売していない商品を先行して買えるほか、お得に商品を購入できる場合が多いのも特徴です。
支援に対してわかりやすいリターンがあるため、クラウドファンディングの中では最も支援者を集めやすくなります。
【非投資型】寄付型クラウドファンディング
寄付型クラウドファンディングは、文字通り寄付によって資金を集める方式です。寄付をした人に商品やサービスなどの明確なリターンはありません。
商品やサービスを返礼することはありますが、購入型クラウドファンディングのように特別なメリットやお得感は強調せず、感謝の気持ちがメインになります。メールや手紙での活動報告をリターンとするのも一般的です。
多くの場合は募金と同様の性質で、発展途上国や被災地などを応援する内容のプロジェクトが寄付型クラウドファンディングに適します。
【非投資型】ふるさと納税型クラウドファンディング
ふるさと納税の仕組みをそのままクラウドファンディングに活かしたのが、ふるさと納税型クラウドファンディングです。
ふるさと納税の納税地となる自治体に寄付してもらうことで、地方の事業開発やプロジェクトの資金を調達できます。支援者へのリターンはふるさと納税の返礼品です。
ふるさと納税を活用することから使うのは主に自治体ですが、認可された団体などがプロジェクトの主体者となれば資金調達に利用できます。
【投資型】融資型クラウドファンディング
小口の資金貸付で支援してもらうのが、融資型クラウドファンディングです。
発案には金融商品取引法の登録が必要となり、調達側は元本の返済と利息の支払いが求められます。支援した人は数%程度の利回りが得られます。
融資型クラウドファンディングで資金を調達できるのは、金融商品取引業を行う企業に限られるため、個人で行うことはありません。
【投資型】株式投資型クラウドファンディング
株式投資型クラウドファンディングは、クラウドファンディングとして未上場株式を発行し、出資者を公募する方式です。
成長が期待される企業において強い資金調達の手段となる可能性があります。一方、投資家にとって魅力的でない場合は資金が集まりにくいでしょう。
株式投資型については、議決権の保有割合にも注意が必要です。多くの株式が第三者に渡ることで経営の議決権が分散し、企業の方向性が揺れる恐れがあります。
【投資型】ファンド型クラウドファンディング
ファンド型クラウドファンディングとは、事業に対して資金提供してもらう方式です。企業ではなく事業に対する出資を募ります。
リターンは事業計画の達成度合いに応じて設定が必要です。配当金はもちろん、商品も見返りに付属するケースがあります。
企業として認知度が低くても、事業が魅力的であれば出資の可能性が膨らむ方式です。その分、出資したくなるような説得力のある事業をPRしなくてはなりません。
クラウドファンディングは、理解ある投資家との出会いが重要です。無料で読める「出資ガイド」では、投資家との出会い方、出資したい起業家の条件などを記載しています。
クラウドファンディングのやり方・始め方の手順
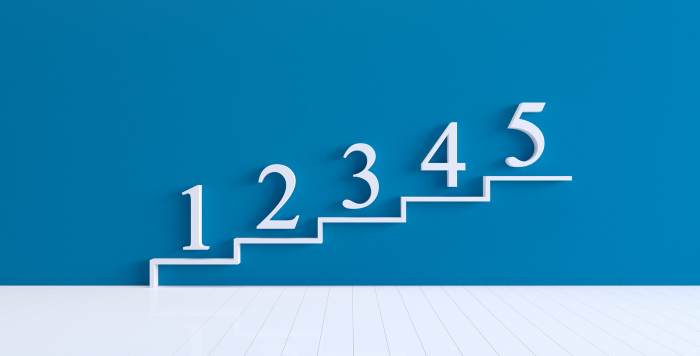
クラウドファンディングには様々なプラットフォームがありますが、どこも基本的には同じような流れで資金を調達しています。ここからは、大まかなプロセスをみていきましょう。
手順1:プロジェクトを企画する
クラウドファンディングの主な目的となるプロジェクトを企画します。以下の要素が例です。
- 資金調達の目的
- 目標金額
- リターン
- プロジェクトの進行プラン
いつまでにいくら必要なのか、どんなことに使いどう役立つのか、どんなリターンがあるのかなど、客観的に理解できるプロジェクトを考えます。
「何から始めたらいいのか・・・」と悩んでいる方は、成功した過去のクラウドファンディングを参考にしてみてください。自分がやりたいことと似ているプロジェクト、同業種の事例を中心にチェックしてみましょう。
手順2:クラウドファンディングサイトを選ぶ
次に、どのサイトのサービスを利用するのかを決めます。例えば、国内のクラウドファンディングサイトでは、それぞれ強い分野やプロジェクトの手数料が違います。
- 国内のクラウドファンディングサイト
-
- Ready for
- Makuake
- CAMP FIRE
こちらの記事(新しい資金調達、クラウドファンディングとは?3つの種類と選び方のポイントまとめ)を参考にして、自分が叶えたいプロジェクトに合ったサービスを選択してみましょう。
手順3:プロジェクトを投稿する
企画したプロジェクトをクラウドファンディングサイトに投稿します。具体的に行うのは、プロジェクトの情報が閲覧できるページの制作です。
魅力的でわかりやすいページを作るために、ストーリー性のある文章、プロジェクトの内容が伝わる画像や動画をうまく使います。リターンはわかりやすく明記し、支援者にもメリットがあることをアピールしましょう。
ポイントは、プロジェクトの発案経緯に自分の原体験を書くなど、共感できる内容を盛り込むことです。自然と支援したくなるよう、共感性の高いPRページを作成しましょう。
手順4:プロジェクトの審査を待つ
クラウドファンディングサイトにプロジェクトを登録後、運営者側での審査があります。どんなプロジェクトでも通るわけではなく、サイトごとの規約やルールを守った上で審査に通ったプロジェクトのみが掲載されるのです。
サイト運営者側から「ここをこういう風に変えられますか」「画像を変更することは可能でしょうか」といった提案をしてくることがあります。
クラウドファンディングのプロの視点でのアドバイスは真摯に受け止め、運営者と良好な関係を保つためにも密に対応しましょう。
手順5:資金調達の活動を始める
いよいよ資金集めが始まります。募集期間中はただ金額に目を向けるだけでなく、さらなる集客に向けた以下の活動が必要です。
- SNSなどでプロジェクトをアピールする
- 定期的に経過報告する
- 期間に応じて発信内容を工夫する
自分のSNSで協力を呼びかけ、積極的に広報活動を進めていきます。閲覧者を増やすことで共感を広めましょう。
プロジェクトの経過報告も重要です。「あと○○円で達成できそうです!」「△△人の皆様に応援していただいています」などと途中経過をお知らせすることで支援者同士の連帯感が生まれ、集客力がアップします。
手順6:募集を終了し支援者にお礼をする
クラウドファンディングの募集期間が終了し、目標金額に達した場合は手数料を差し引いた金額が入金されます。達成できなかった場合は、支援金は支援者に返金されてプロジェクトそのものが終了となります。
目標金額の達成・未達成に関わらず、お礼の文章をきちんと掲載し、メールや手紙で感謝の気持ちを伝えましょう。事前に約束した支援者への特典を送るほか、許可を得られた支援者一覧をHPに載せる方法もあります。
資金調達を達成した後、実際にプロジェクトが行われている様子をブログなどで公開すると、資金の透明性の観点からも喜ばれます。プロジェクトの行く末が見届けられるようにすると、いつまでも「プロジェクトへの連帯感」から温かく見守ってもらえるでしょう。
クラウドファンディングのやり方についてさらに詳しく知りたい方は、資金調達手帳をチェックしてください。資金調達のノウハウもまとめています。
クラウドファンディングで資金調達を成功する6つのコツ

クラウドファンディングを成功させるためには、様々な工夫が必要です。
その中でも、クラウドファンディングの成功に効果的な6つのコツをご紹介します。
支援者にプロジェクトの成功をイメージさせる
クラウドファンディングで支援者を集めるためには、支援を検討している方に、このプロジェクトが成功しそうだと思ってもらう必要があります。
明らかに失敗しそうなプロジェクトを支援する人はほとんどいません。
プロジェクトの成功をイメージしてもらうためには、スケジュールや予算の使い道、メンバー構成、課題と解決策といった全体像を明確にし、成功の根拠を具体的に示す必要があります。
発案者やプロジェクトに共感を集める
クラウドファンディングの成功にとって、非常に重要な要素に「共感」があります。支援したいと思う動機の多くに共感があるためです。共感には以下のようにさまざまな切り口があります。
- 同じ悩みや課題を持つ人にアプローチする
- 賛同してもらえる理想や未来像を提示する
- 距離の近さ、親近感をアピールする
これらをプロジェクトの目的やビジョンに盛り込むほか、PRページにも共感を呼ぶ要素を活用しましょう。
うまく共感を集められれば、世界一周に行きたい、音楽ライブを主催したいなど、個人的な思いのプロジェクトでも成功できる可能性はあります。
動画を効果的に活用する
多くの支援者からの共感を集めるためには、画像や動画を使うのが効果的です。
画像は文字の7倍、動画は文字の5,000倍もの情報を伝えられると言われています。
きれいな写真やデザイン性の高い画像、活動内容がリアルにわかる動画を発信して共感を集めましょう。
画像や動画を組み合わせて、プロジェクトにかけた思いや成功した後のビジョンを熱く語ることで、文章だけでは伝わらない感情が伝わりやすくなります。
継続的に途中経過を報告する
クラウドファンディングにおいて、途中経過の報告は重要視されます。クラウドファンディングの目的は資金調達だけでなく、ファンの獲得も含まれているからです。
継続的に途中経過を報告すると、支援者の記憶に残りやすくなります。また支援数などの達成状況が可視化されれば、支援者は自分の支援が役立っているという達成感を得られ、熱心なファンとなりさらなる後押しが期待できるのです。
資金を多く集めるためには、多くのユーザーにアプローチしなくてはなりませんが、接触回数が少ないと人は忘れやすくなります。定期的な経過報告はユーザーとの接点を増やし、ファンを効率的に増やすために欠かせません。
魅力的なリターンを用意する
クラウドファンディングの支援理由として多いのが、リターンに対する期待です。魅力的なリターンであるほど支援が集まりやすくなります。
多くの支援者が「欲しい」と思うリターンを考えなくてはなりません。単にモノやサービスを紹介するだけでなく、手にすることでどんな風に役に立つのかや、どんなメリットがあるのかを具体的に説明しましょう。
また、リターンの金額設定は「3,000円以下」「3,000〜10,000円」「10,000円以上」と、最低でも3パターンに分けることで、どの支援者でも手が出しやすくなります。
プロジェクト開始前にSNSなどで支援者を集める
クラウドファンディングで資金を集めるなら、プロジェクトを開始する1ヶ月前くらいにはページを作り、事前にSNSやリアルの場で告知を行いましょう。
クラウドファンディングサイトでプロジェクトを立ち上げたら、勝手に支援者が集まってくるわけではありません。成功には数々の工夫や仕掛け、泥臭い宣伝活動が必要になります。
プロジェクトを開始して3日以内に目標金額の30%以上の支援を集められれば、クラウドファンディングの成功確率が大きく高まります。
クラウドファンディングの成功事例

プロジェクトの発案には、クラウドファンディングの成功事例を参考にしましょう。具体的な内容はそれぞれ別記事にて紹介しています。
釣り×アパレルブランドの組み合わせで注目された事例
1つ目の事例は、釣りに特化したアパレルブランドです。アウトドアファッションブランドは増えていますが、釣りとの組み合わせは少ないことからクラウドファンディングで商品をアピールしました。
- 達成率は3152%
- 調達資金630万円以上
GOODIE 岸原 秀行|クラウドファンディングで成功!「釣り×アパレル」という新たなニーズの開拓に挑戦
地元愛がぎっしり詰まったプロジェクトが目を引く事例
2つ目の事例は、愛媛・宇和島の真珠ネックレスブランドです。募集ページにある発案者の原体験を記したストーリーが印象的で、地元への愛やこだわりが深く感じられる内容に仕上がっています。
- 目標の支援額を5日で達成
- クラファン限定プチアクセサリーを用意
愛媛宇和島の真珠がクラファンで人気沸騰!元コンビニの敏腕マーチャンダイザー中山香織さんに聞く「事業の強みの伸ばし方」
強い理念に共感する支援者が集まった事例
3つ目の事例は、海外のマイクロファイナンスです。海外の貧しい人に無担保で少額の融資を行う事業のことで、事業拡大に使う資金集めにクラウドファンディングを利用しました。理念に共感してくれた投資家や出資者との出会いがターニングポイントだったと、発案者は語っています。
- 調達資金約6,000万円
- 理念への共感を得たことで高額調達に成功
海外マイクロファイナンス・ワラム 加藤 侑子|高卒派遣から勤め先を買収し社長に!
クラウドファンディングのメリット

クラウドファンディングは、プロジェクトを公開する「提案者側」と、プロジェクトに共感した「支援者側」にそれぞれメリットがあります。以下に立場ごとのメリットをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
提案者側のメリット
-
- 大きなプロジェクトにも挑戦できる
- ファンの獲得や宣伝といった副効果が得られる
- ネットから広範囲に支援者を募ることができる
- 融資が難しいプロジェクトやテストマーケティングにも活用できる
クラウドファンディングが成功すれば大きな資金調達が可能です。単独では困難なプロジェクトや金融機関からの融資が難しい事業でも、立ち上げられる確率が高まります。
また、プロジェクト自体が宣伝効果をもたらすため、新商品やサービスを幅広い層に認知させることができます。開発段階から参加できて成功までの経緯を一緒に楽しめることから、熱心なファンを獲得できる可能性があるのです。
SNSを始めインターネット上で募集するため、世界規模での資金調達が低コストで行えます。
支援者側のメリット
-
- 少額からでも気軽に参加できる
- 特別なリターンが得られる
- 寄付型を選ぶと所得税や住民税を節税できる
支援者にとってのクラウドファンディングは、魅力的なリターンが最大のメリットです。新商品を購入できたり、なかなか買えないサービスがあったりし、支援以上の満足を得られることも考えられます。
また、投資型は支援した資金に応じて金銭的なリターンがあるため、金融商品以上の利回りも期待可能です。審査があるため一定基準以上の信用があり、投資に不安がある人でも比較的安心して行えます。
ほかにも、支援すると寄付金控除が受けられる点もメリットでしょう。支援すると節税対策になります。
クラウドファンディングのデメリット

クラウドファンディングのデメリットを確認することで、提案者側・支援者側の注意点やリスクを把握しておきましょう。
提案者側のデメリット
-
- 競合相手に自社のアイデアを知られてしまう
- 失敗のリスクがある
- 手数料とリターンでマイナスになることがある
クラウドファンディングを活用すれば多くの人に知られることとなり、アイデアが盗まれる恐れがあります。
また、募集しても希望の資金が集まるとは限らないため、失敗するリスクも考慮する必要があるでしょう。
クラウドファンディングに参加するだけで10%~20%の手数料がかかり、さらに支援者へのリターンを考えると、マイナスとなる場合があります。
支援者側のデメリット
-
- 支援をキャンセルできない
- 資金の使い道の確認が難しい
- 投資型は元本割れのリスクがある
支援者のデメリットは、一度申し込みすればキャンセルできない点です。途中経過の段階で成功が難しそうでも多くの場合は支援を取り消せず、資金の使い道が不明瞭なケースもあります。
また、投資型は元本割れリスクを考慮しなければなりません。申請したプロジェクトは審査するため詐欺のリスクはかなり低いといえますが、きちんとした会社の投資プロジェクトであっても元金割れリスクはあるでしょう。
起業時にクラウドファンディングの活用がおすすめな理由

これから創業を考えているなら、資金集めとしてクラウドファンディングを活用してみてはどうでしょうか。クラウドファンディングと聞くと既存企業の商品やサービスを打ち出すイメージがありますが、創業と合わせて活用することもできます。
低リスクに資金調達ができる
クラウドファンディングは起業時の資金調達に活用できます。非投資型を選べば返済の必要がないため、低リスクでの資金調達が可能です。
金融機関からの融資だと返済リスクがつきまとう上、起業時は信用がないため思った金額を調達しにくくなります。しかし、クラウドファンディングなら魅力的な事業アイデア次第であるほか、少額から支援できるため、出資を募りやすいのも利点です。
利用サイトごとの規約をよく読み、審査に通るような事業計画を立てるといいでしょう。申請は個人であっても構わなく、これから創業する会社でも問題ありません。
見込み顧客の要望が起業前にわかる
クラウドファンディングでは、自社商品を使ってくれた人から直接意見を聞ける機会があります。使用者から寄せられた感想は、市場ユーザー全体の要望の一部を反映しているため、とても参考になる情報です。
事前の評価はモニターからも得られますが、モニターは自社商品に必ずしも興味があるとは限りません。一方、クラウドファンディングの支援者は自社商品に共感して購入してくれた方々なので、より深い情報を聞けるメリットがあります。
リリース前の商品に対する感想は、良い部分だけでなく、悪い点もわかる意味で非常に重要です。悪い点があればリリース前に改善することでより良い商品となり、多くの見込み客の希望を満たす商品になる可能性が高まります。
将来の顧客獲得につながる可能性がある
クラウドファンディングで自社商品に対し興味を持ってくれた方や実際に支援してくれた方は、将来の顧客になる可能性があります。支援に至らなかった方も、商品に触れることで記憶に残り、リリース時の購入者となるかもしれません。
さらに、支援数はそのまま将来の売上数と比例するので、売上数の予測や事業規模の把握にも役立てることが可能です。
例えば、思ったより支援数が少なければ製造数を少なくしたり、広告費を縮小したりする判断ができます。
加えて、クラウドファンディングの支援数は、商品価格が適正であるかどうかの判断にも役立ちます。支援数が多ければ適正価格であったと判断できますが、予想より少なければ価値に見合っていなかったということです。
まとめ・起業時にクラウドファンディングも検討してみよう
夢をかなえたいけれどお金がない、人脈がない・・・ないない尽くしの救世主になり得るのがクラウドファンディングです。
あなたに合ったクラウドファンディングサイトを探してみましょう。サイトを見ているうちに応援したいプロジェクトや、似たことをやりたいと考えている人に出会えるかもしれません。
資金繰りに悩んだときは冊子版の創業手帳を手に取ってください。キャッシュフローを健全にするノウハウをやさしく解説しています。
その他にも、補助金・助成金の正しい活用法がわかる補助金ガイド、自分の条件にマッチした補助金・助成金情報が届く補助金AIもご用意しています。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
融資の基本から初心者向けに解説した融資ガイドでは、融資の審査通過のためのポイントなども確認できます!
(執筆:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。