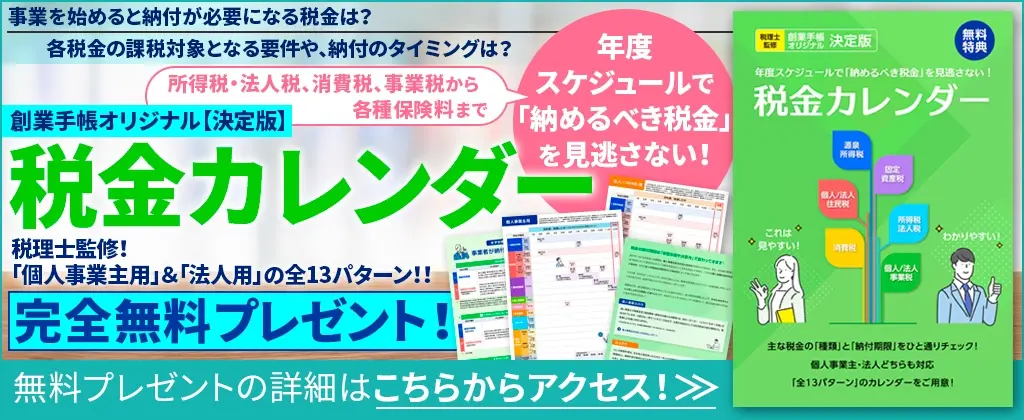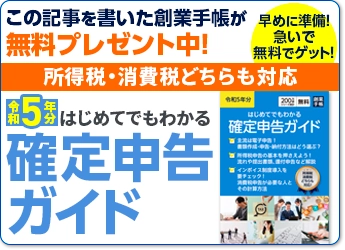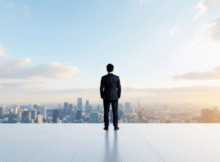個人事業主の節税裏技18選!経費・控除・確定申告で手取りアップ!
納税で損しない為の節税テクニックを網羅してご紹介!

・個人事業主は個人事業税や所得税など5つの税金がある
・節税には経費と控除の活用が重要
・確定申告時に様々な節税対策がある
・個人事業主には多くの控除制度がある
・専門家に相談し最適な節税方法を見つけよう
起業しても、事業が軌道に乗るまで、以下のように、様々な働き方が普及してきました。個人で仕事をすれば個人事業主になり、会社員とは納税方法も異なります。
-
- 個人事業主として事業を行う方
- ITの発達により会社勤めをやめて、パソコンやスマートフォンを使った事業で起業される方
- 副業として休日や深夜などに行う方
- 家事の合間にネットで仕事をする主婦の方
「個人事業主で節税でできるのか?」と思っておられる方も多いでしょうが、合法的な裏技がありますので、節税方法を公開します。
ちなみに節税対策のためには、税金チェックシートがおすすめです。税理士等の専門家に取材し、税金で損をしない方法をまとめました。書き込めるExcelシートになっており、無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
創業手帳では、この度税金カレンダーをご用意しました。主な税金をカレンダー形式にして見える化しました。納付期限を事前に把握して、キャッシュを確保しておきましょう。
この記事の目次 個人事業主が納める税金は、所得税・復興特別所得税・住民税・消費税・個人事業税の5つがあります。ここで詳しく内容を見ていきましょう。 ・所得税 ・復興特別所得税 ・住民税 ・消費税 ・個人事業税 所得税と住民税は、課税所得金額に対して算出されます。 個人事業主が節税する方法として、「経費」と「控除」の2つを利用したやり方があります。 経費は事業によって計上できる費用の種類が異なっており、事業とは関係ない費用や、個人の支出は経費に含められないので注意してください。たとえば、税金・水道光熱費・交通費・宣伝費・福利厚生費・外注費などが経費で、経費になるものは漏れなく申告することで所得が減り、節税対策になります。 控除は、医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除など、所得から一定額を引くことができる節税対策です。すべての人に当てはまる基礎控除以外にも、個人事業主は小規模企業共済やふるさと納税の控除も見逃せません。 個人事業主の節税対策のひとつ、経費にかかわる裏技を紹介します。 1.事業の経費化できる支出を見直す それぞれ詳しくみていきましょう。 個人事業主の事業経費は私用支出と事業支出の割合の基準は、合理性があれば、何を基準に割合を決めるかは自分で決められます。 ☑裏技1 業種によれば、遠くの取引先への出張とか取材とかで、交通費・宿泊費が多くある場合は経費化できる範囲が広いです。 ☑裏技2 個人事業主の方で自宅を事務所として使っているときは、自宅の家賃・水道光熱費・通信費・車関係の費用を「家事按分」として経費計上できます。家事按分とは、自宅の床面積・使用時間・コンセントの数などにより、生活と仕事で使う割合を分けることです。 ☑裏技3 さらに家事按分の詳細を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。 個人事業主の場合は、20万円未満の減価償却資産を全額経費として計上、または3年で償却する制度があります。30万円未満の場合でも一定条件を満たすと経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」があるため節税対策として活用してください。 少額減価償却資産の特例の適用を受けられるのは青色申告をしている個人事業主のみで、確定申告書に明細書を添付しなければなりません。また、2025年度末(2026年3月31日)までと期限が決められているため注意しましょう。特例で経費計上した場合には、固定資産台帳に記載が必要で、固定資産税の課税対象となる点にも注意が必要です。 【対象の少額減価償却資産】 経理処理をするとき、前払費用は「資産」に計上します。 しかし、前払費用でも一定の条件を満たすことで、短期前払費用として計上可能となる「短期前払費用の特例」があります。具体的な条件は以下のとおりです。 短期前払費用として計上すると、支払った時点で損金にできるため、節税になります。 税金の中には、租税公課(そぜいこうか)の勘定項目を利用して、経費に計上できるものがあります。 【経費にできる税金】 租税公課とは、税金や公的負担金のうち経費計上できるものを指します。 個人事業税がかかる方や事業に自動車を利用している方などは、忘れずに租税公課の項目で経費計上しましょう。 個人事業主の節税対策の2つ目「控除」にかかわる裏技を具体的に紹介します。 7.医療費控除を受ける 「医療費控除は、医療費が年10万円を超えていないと認められない」と思い込んでいませんか? 個人事業主でも公的な共済制度に加入することで、保険支払費が控除されるので、節税になります。 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
個人事業主が納める5つの税金
所得税は、年間所得に対し課税される税金となり、国税のひとつです。納税額を計算するため確定申告が必要で、確定申告の申告期限内までに納税します。
2013年~2037年までは、所得税とあわせて2.1%の復興特別所得税が課税されます。
住民税は、地方自治体に納める地方税です。
各自治体が確定申告の内容をもとに、前年の所得に対し税金を算出します。個人に支払い通知が来るので、期限内までに納税しなければなりません。
前々年の売上げ、または前年の1~6月の売上げが1,000万円を超えたら課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。自分で申告と納税が必要です。
個人事業税は、事務所や事業所がある都道府県に納付する地方税の1つです。誰にでもかかるわけではなく、法律で定められた職種(70種)に該当し、所得が290万円を超える場合に納税義務が発生します。 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」個人事業主の納税額の仕組みや計算方法
どちらも所得が大きくなるほど納税額が増える仕組みのため、必要経費や各種控除は漏れなく申告し、課税所得金額を減らすことが節税では重要です。
なお、それぞれの計算式は以下のとおりです。
所得金額=収入金額-必要経費
課税所得金額=所得金額-各種控除
所得税=課税所得金額×税率-税額控除
住民税=課税所得金額×税率-調整控除-税額控除+均等割額
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」節税の裏技である「経費」と「控除」について
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」個人事業主必見!節税方法〜経費編~
2.業種により経費となる支出を見直す
3.家事按分を活用する
4.少額減価償却資産の特例を活用する
5.短期前払費用の特例を利用する
6.税金を経費として計上する1:事業の経費化できる支出を見直す
2:業種により経費となる支出を見直す
温泉地への取材旅行のついでに家族も同行すれば、自分の出費は経費に出来ます。
例えば、芸能人やモデル業なら健康維持・リフレッシュに掛かる経費に出来ます。
その他の仕事でも考え方を理解して、自分の仕事に当てはめて考えてみて、私用支出と事業支出の割合の基準を決めれば良いのです。3:家事按分を活用する
たとえば、自宅の一室を事務所として使っているなら、自宅の床面積から事務所分を割り出し経費計上します。賃貸住宅なら家賃が経費となりますが、持ち家なら固定資産税・住宅ローン金利・火災保険料も経費に計上可能です。水道光熱費・通信費は時間換算で、車関連の費用は走行距離や時間などを目安に仕事の割合を決めるといいでしょう。4:少額減価償却資産の特例を活用する
5:短期前払費用の特例を利用する
前払費用とは、数カ月または1年継続して利用するサービス料を先払いすることです。
支払い時に「資産」に計上してから、実際にサービスを受けたときに経費に振り替えます。
・事業年度末までに支払っている
・継続して役務の提供を受ける
・継続して同じように経理処理をする
6:税金を経費として計上する
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」個人事業主必見!節税方法~控除編~
8.保険で節税する
9.税金額の控除は最大限に活用する
10.所得控除を受ける
11.法人化を考える7:医療費控除を受ける
☑裏技7
「医療費が年10万円」を超えていなくても、「その年の総所得金額等が年200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」という条件がありますので、「年収311万6000円未満のサラリーマン」等の給与所得者であれば、給与所得控除後の総所得が200万円以下なので、医療費が年10万円以上なくても、医療費控除は受けられるということです。8:保険で節税する
☑裏技8
毎月一定額(1,000円~70,000円)の掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。この、共済は事業主の退職金を積立てるという制度で、将来65歳以上でかつ15年以上払い込んでいる場合、又は事業を廃業した場合に一時金又は年金として給付を受けることとなります。
取引先事業者の倒産の影響で、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、最高8,000万円の共済金の貸付を受けられます。一定額(月5,000円~200,000円)を掛金として支払うことで、年間最大240万円まで費用計上が可能となります。
この制度は掛金の上限が800万円迄で、40カ月(3年4ヶ月)以上掛金の納付を続けると、支払額の100%が解約手当金として、払い戻される点が特徴です。
9:税金額の控除は最大限に活用する
税金額が控除の種類は、次の4つです。
2)給与所得控除額 55~195万円
3)所得税基礎控除 95~58万円
4)消費税の免税 基準期間の課税売上高1000万円以下の場合
個人事業では対象になるのは、1)、2)だけです。
☑裏技9
究極の裏技、事業を分けて、A事業は個人事業で、B事業は法人を設立して行う。
それにより、1~4の4つの控除が使用可能となります。1)の控除を取りながら、法人から給与の支給を受けて、2)の適用を受ける。個人事業と法人事業の2つに分散させることで、年度毎の売上高を1000万円以下に抑えることができれば、消費税の納税義務が発生しないので、4)の生じないという恩恵を享受できます。
10:所得控除を受ける
個人事業主は受けられる控除が多いほど、節税効果が大きくなります。所得控除が大きくなるほど課税所得が減る仕組みで、使える所得控除があれば漏れなく申告しましょう。個人事業主が使える所得控除には、以下のものがあります。
適用となる控除がないか確認しましょう。
- 基礎控除:合計所得金額に応じて95~58万円控除
- 寄附金控除:ふるさと納税などで受けられる控除
- 生命保険控除:支払った掛け金に応じて受けられる
- 社会保険料控除:社会保険料を支払った費用
- 医療費控除:一定額を超えた医療費で受けられる
- 地震保険料控除:支払った掛け金に応じて受けられる
- 配偶者控除:配偶者の合計所得が48万円以下
- 配偶者特別控除:納税者の合計所得が1,000万円以下、配偶者の合計所得が48~133万円以下
- 雑損控除:災害、盗難、横領による損金
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛け金
- 障害者控除:納税者、控除対象配偶者、扶養親族が障害者
- ひとり親控除:納税者がひとり親
- 勤労学生控除:合計所得金額75万円以下で、学校に行きながら働いている
- 扶養控除:16歳以上の子ども、両親を扶養している
- 寡婦控除:夫と離婚・死別した方で、合計所得金額が500万円以下などの条件を満たした場合に受けられる
11:法人化を考える
個人事業主は、課税所得に応じて最大45%の所得税がかかります。
一方で、法人化すると法人税がかかりますが、最大23.20%が上限のため、課税所得が一定額を超えたら法人化を考えるといいでしょう。
法人化する目安は、課税所得が800万円を超えてからとされています。
800万円を超えると法人化した場合と比べて個人事業主のほうが、所得税が数千円高くなります。
そのため、課税所得が800万円に近づいてきたころに法人化を検討するのがおすすめです。
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
個人事業主必見!節税方法~確定申告編~

個人事業主は、前年の所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。(開始日・期日が土日の場合は月曜日に変更)
確定申告時の注意点や利用できる節税方法を解説します。
12.無申告加算税は避ける
13.扶養家族を変えて申告する
14.純損失の繰越しをする
15.小規模企業共済に加入する
16.経営セーフティ共済に加入する
17.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
18.ふるさと納税を利用する
それぞれ詳しくみていきましょう。
確定申告の最新情報をまとめた確定申告ガイドを無料配布中!詳しくは以下のバナーから!

12:無申告加算税は避ける
確定申告は0円でもする。実際に事業していたら、時間に追われ確定申告が出来ない時もありますが、確定申告は期限内に行いましょう。
☑裏技12
名前だけ書いて、所得は0円でだせば、無申告加算税は逃れられます。但し、後で修正申告で正しく計算して提出しないと脱税になりますし、早くださないと、延滞税も取られますので、注意してください。
13:扶養家族を変えて申告する
サラリーマンの方は、年末調整時に扶養家族を会社に申請していますが、確定申告時に扶養家族数が変えられます。
☑裏技13
夫婦共働きでこどもが2人いて、ご主人が子ども2人を扶養にし、奥さんは「扶養なし」と会社の年末調整をしていたとします。これを、ご主人と奥さまそれぞれが子ども1人ずつを扶養するに変えて確定申告をすると、奥さんのほうで扶養分の税金還付があります。
しかし、ご主人の所得、奥さんの所得により、節税にならない場合もありますので、国税庁のホームページで試算が出来ます、それで、判断してください。
14:純損失の繰越しをする
個人事業主として開業したばかりの頃は、初期費用がかかるため赤字になりやすいでしょう。
赤字の場合は確定申告をする必要はありませんが、確定申告で損失申告すると、翌年以降3年間繰り越しが可能で、節税対策になります。
ただし、3年間の繰り越し控除ができるのは、青色申告を行う場合です。また、青色申告を行うと、純損失の繰り越し還付も受けられます。
15:小規模企業共済に加入する
「小規模企業共済」は、個人事業主の退職金代わりとして加入できる制度です。毎月掛け金を支払うことで、事業終了時や引退時にまとまったお金を受け取り退職金代わりとすることができます。月々の掛け金は1,000円~7万円まで自由に決めることが可能で、掛け金は全額所得控除できるため節税対策としておすすめです。
たとえば、7万円の掛け金なら年間84万円、1年の前払いを利用すると年間168万円の所得控除が受けられることになります。掛け金は増減が可能で、経営状況が悪ければ一時的に支払いをやめることも可能です。さらに掛け金の範囲内で貸し付けも受けることができます。
ただし、12か月未満は掛け捨てとなり、加入期間が20年未満だと元本割れするので注意してください。また、受取時には雑所得などとして課税されます。
16:経営セーフティ共済に加入する
「経営セーフティ共済」は、取引先の倒産で中小企業が連鎖倒産とならないよう、万が一に備える制度です。担保と保証人なしで掛け金の10倍まで借り入れが可能で、解約時に解約手当金が受け取れます。月々の掛け金は5,000~20万円まで自由に決められて、掛け金は経費に計上できるため節税対策としておすすめです。
赤字年度に解約して確定申告すれば、ほとんど課税されないこともあります。12か月未満は掛け捨てですが、40か月以上なら掛け金全額が戻るため節税対策におすすめです。万が一の事態に備えたい場合で節税も希望するなら、経営セーフティ共済の加入を検討してみましょう。
17:個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
個人事業主が個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用している場合、掛け金の全額を所得控除として申告できます。また、運用益も非課税です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金を所得控除として適用するには、確定申告が必要です。
運用益を受け取るときは、退職所得控除・公的年金等控除の対象となります。
18:ふるさと納税を利用する
「ふるさと納税」は、生まれ育ったふるさとや応援したい土地の自治体を任意で選択して、寄付できる制度です。
寄付金額のうち2,000円を超える部分に関しては、自分が住んでいる自治体の住民税の控除や所得税の還付を受けられます。
ふるさと納税で利用できる控除額は無限ではなく、所得に応じて変化し、所得が増えるごとに控除額も増加します。
税金が減るわけではありませんが、本来なら住民税や所得税で払うだけだったお金で、返礼品を受け取ることができる点がふるさと納税の大きなメリットです。
ふるさと納税の寄附金控除の申請方法は「確定申告」「ワンストップ特例制度」の2種類があります。
しかし、個人事業主は「ワンストップ特例」を利用できないため、確定申告時に計上するのを忘れないようにしましょう。
節税方法~確定申告編~まとめ
このように節税では、様々な控除を利用します。確定申告の時、計算しなくてはならない項目が増え、複雑になります。計算ミスや思い違いをしていた場合、正しく節税できなくなります。なので、個人事業主であっても、会計ソフトを利用するとよいでしょう。250万部を突破した冊子版の創業手帳(無料)では、会計ソフトの選び方や導入について詳しく解説しています。
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
個人事業主の年収別・おすすめ節税戦略【300万/500万/800万の場合】
「自分の年収(所得)だと、どの節税策が効果的なのか分からない…」という方のために、年収別におすすめの節税戦略例をまとめました。
※扶養状況・居住地・控除の有無・業種・経費率などにより大きく異なります。あくまで一般的な目安としてご活用ください。
【年収300万円台の方】
- 青色申告特別控除(最大65万円) を確実に適用
- 家事按分・必要経費 をしっかり申告
- 課税所得を抑えるため、扶養控除や社会保険料控除も漏れなく申告
- ふるさと納税・医療費控除 なども活用して、少しでも可処分所得を増やす。
【年収500万円台の方】
- iDeCo(月額6.8万円まで※/全額所得控除)を併用
- 小規模企業共済(月額7万円まで/全額所得控除)への加入も有効
- 経費+控除の2段活用 で課税所得を大きく圧縮
- 短期前払費用の特例や少額減価償却資産の特例 など、やや高度な節税テクも取り入れる
※国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠
このあたりから節税の効果額が実感しやすくなります。
【年収800万円超の方】
- 課税所得が800万円を超えたら法人化(法人成り)を本格的に検討
- 所得分散(配偶者・家族に給与支給)なども視野に入れる
- 消費税納税義務 が発生(課税売上高1,000万円超)している場合は、インボイス制度対応とあわせた節税プランニングが重要
節税における「攻め」と「守り」の両面で、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
個人事業主の節税でよくある質問
こちらでは、個人事業主の方からの節税に関するよくある質問を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 個人事業主が一番得する年収はいくらですか?
A. 一概に「この年収が一番得」とは言い切れませんが、2025年の税制改正により基礎控除が大幅に引き上げられたことで、課税所得200〜400万円程度のゾーンは「手取りの効率が高い」と考えられます。
課税所得が330万円を超えると所得税率が10%から20%に上がるため、それ以降は税負担の増加率が高くなります。また扶養状況や居住地、社会保険料の負担によっても変わるため、個別の状況に応じた試算を行うことが重要です。
Q2. 個人事業税を安くする方法は?
A. 「事業所得290万円以下に抑える」「経費や控除を漏れなく申告する」ことで税負担を軽減できます。事業税は特定業種(70業種)にのみかかるため、自分の業種が対象かを確認しましょう。
個人事業税=(事業所得-事業主控除290万円)×税率
※事業所得 =事業収入-必要経費(青色申告特別控除は含めない)
個人事業税では、青色申告特別控除や基礎控除は適用されず、事業主控除290万円のみが控除されます。これは、個人事業税が「事業による純粋な利益」に対して課税するためです。
Q3. 個人事業主で住民税をゼロにすることはできますか?
A. 住民税の所得割は合計所得金額が45万円以下になると非課税となります。ただし、自治体によっては45万円以下の場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などを組み合わせ、所得を抑えることがポイントです。
Q4. 個人事業主で税金がゼロになるのはいくらまでですか?
A. 2025年の税制改正により所得税が大幅に変更されました。
所得税について(2025年適応)
- 合計所得金額132万円以下:基礎控除95万円が適用され、所得税はゼロ
- 合計所得金額132万円超336万円以下:基礎控除88万円が適用
- 合計所得金額336万円超:段階的に基礎控除が減額
※令和9年度分以後は一部改訂あり
住民税について(変更なし)
合計所得金額45万円以下:住民税はゼロ(自治体により異なる場合あり)
社会保険料控除などその他の控除に加え、個人事業主の場合は必要経費や青色申告特別控除も考慮すると、事業収入150万円前後までは所得税・住民税ともに非課税になるケースが多くなります。ただし、経費の額や扶養家族の有無、地域差がありますので、詳細は税務署や市区町村にご確認ください。
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
まとめ・個人事業主は正当な裏技(経費・控除)で賢く節税しよう
事業を始められる方や始めた方は少しでもご参考になったでしょうか?
裏技と説明しながら、驚くようなテクニックはありません。基本的には、節税は事業が大きく成長してからです。
事業を開始した時は、税を収められる企業になったと喜ぶ方が多いです。
事業を始めて間もない方は、事業が安定した時に、この内容を参考にして頂ければ幸いです。
また、創業手帳では、節税対策にも繋がる「税金チェックシート」をご用意しました。税理士をはじめとした専門家の方々の声を集め、損をしない税金の納め方が分かります。無料ですので、ぜひお気軽にお役立てください。
さらに、税金カレンダーも配布中!主な税金情報がカレンダー形式で確認できます。全13タイプの中からあなたに合ったカレンダーを選択できますので、この機会にぜひご利用ください。