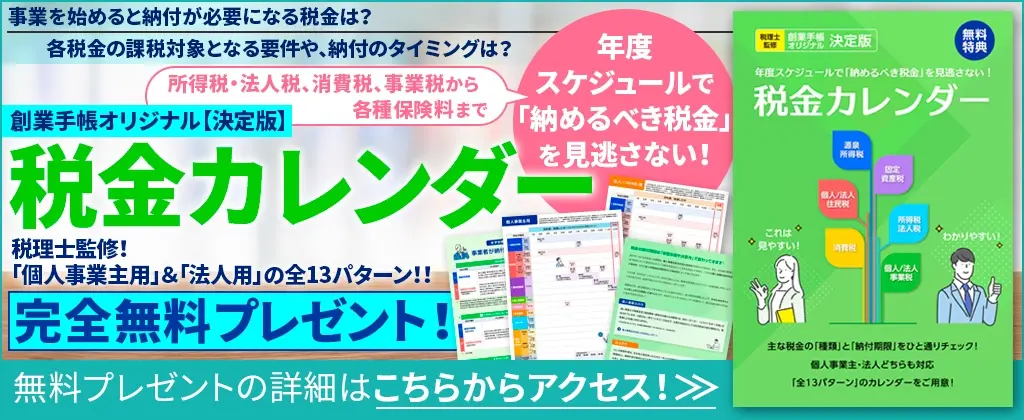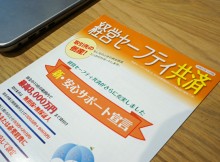小規模企業共済とは? 危ないって本当?3つのデメリット・6つのメリットをわかりやすく解説
小規模企業共済とは『貯金のつもりで節税になる』『共済金は退職所得となる』制度
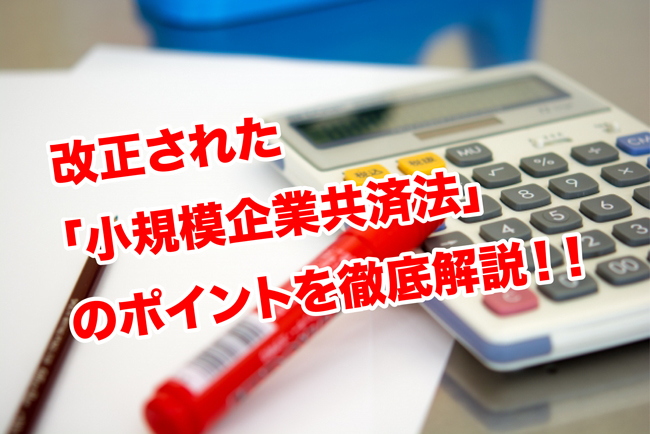
(執筆:渋谷税理士法人 中村剛士)
「小規模企業共済って、元本割れするって聞いたけど大丈夫?」
「途中解約すると損するって本当?」
ネット上では“小規模企業共済は危ない”というネガティブな情報が散見されます。しかし実際のところ、制度を正しく理解し、自分に合った使い方をすればリスクは十分回避できます。
本記事では、「小規模企業共済の制度概要」とともに、「なぜ“危ない”と言われるのか」「そのリスクをどう避けるか」、さらに「向いている人・向いていない人」や、倒産防止共済との違いも解説します。
小規模企業共済だけでなく、起業にまつわる制度や情報は日々更新され続けています。創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブック「創業手帳」を毎月1.5万部発行しています。毎月の発行ごとに、専門家・起業家のリアルな声を反映し、アップデートをくり返しています。法人設立後の全法人に発送していますが、資料請求することでも無料でもらえます。
また、創業手帳では、「税金チェックシート」もご用意。税金の支払いや経費の使い方のコツなど、節税のためのノウハウを分かりやすく解説しています。こちらも無料ですので、ぜひあわせてご利用ください。
更に、「税金カレンダー」も新たにご用意しました。所得税や法人税だけでなく、各種保険料まで、収めるべきタイミングを逃さず確認できます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、昭和40年に発足しました。運営は公的機関である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」です。
共済に加入すると、共済金を月々積み立てることができます。積み立てた共済金は解約時に受け取れるため、退職金代わりに活用する場合も少なくありません。また、貸付制度が利用できる特徴もあります。
小規模企業共済の基本
以下では小規模企業共済の対象者や掛金など、制度の基本について解説します。
加入資格や掛け金の設定、受け取れる共済金などについて見ていきましょう。
小規模企業共済の加入資格のある対象者
小規模企業共済では、下記のいずれかに該当する方に加入資格があります。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
引用元:共済サポート navi「中小機構共済FAQ」
小規模企業共済という名前の通り、小規模のビジネスを行なっている方に加入資格があります。
また個人事業主・法人役員のほか、個人事業主の共同経営者も加入可能です。
たとえば、個人事業を配偶者と共同で経営している場合には、下記の条件を満たすことで配偶者も共同経営者として小規模企業共済に加入できます。
- <配偶者が共同経営者となるための要件>
-
- 事業における重要な意思決定に関与しているまたは事業資金を負担している
- 業務に対して報酬を受け取っている
節税や妻の老後資金の形成などを目的にする場合には、共同経営者になってもらう選択もできるでしょう。
一方、規模が大きい企業の経営者や特定の職業に従事している方は加入できないので注意してください。
社団法人やNPOなどの非営利企業の経営者、生命保険外務員などが加入できない方に該当します。
小規模企業共済の主な特徴
小規模企業共済ではいくつかのプランが用意されているわけではなく、自分で掛金を設定して積み立てをしていきます。
掛金額や納付方法といった主な特徴を見てみましょう。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 掛金額 | 1,000~70,000円/月から500円単位で設定可能 |
| 納付方法 | 月払い、半年払い、年払いのいずれかを指定可能 |
| 共済金の受け取り方法 | 一括、分割、一括と分割の併用のいずれかを指定可能(分割と併用は要件を満たす必要あり) |
掛金は月々1,000円〜70,000円まで、500円単位で指定可能です。掛金の増額・減額も可能で、自分の所得状況に合わせ掛金をコントロールできます。
納付方法は月払い・半年払い・年払いから選べ、毎年手続きを行うことで翌年分の前納ができるのも特徴です。
共済金(解約手当金)の受け取り方法は一括・分割・一括と分割の3種類から選択可能で、どれを選ぶかで必要な要件が異なります。
多少の制限はあるものの、個人事業主などが自由に掛金を積み立てられる仕組みが整えられています。
小規模企業共済で受け取れる共済金
受け取れる共済金は「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類です。どの事由に該当するかに応じ、貰える共済金等の額が変動します。
(例)掛金月額1万円の場合
| 掛金納付年数/掛金額合計 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年/60万円 | 62万1,400円 | 61万4,600円 | 60万円 | 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80~120%相当額を支給 |
| 10年/120万円 | 129万600円 | 126万800円 | 120万円 | |
| 15年/180万円 | 201万1,000円 | 194万400円 | 180万円 | |
| 20年/240万円 | 278万6,400円 | 265万8,800円 | 241万9,500円 | |
| 30年/360万円 | 434万8,000円 | 421万1,800円 | 383万2,740円 |
出典:中小機構「共済金(解約手当金)について」「小規模企業共済 制度のしおり」
基本的に、貰える共済金等の額は「共済金A」>「共済金B」>「準共済金」となっています。
小規模共済金の種類を決める共済事由
4種類の共済金は、どのような理由で支給されるか、いわゆる「共済事由」によって決定します。
具体的に「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」に当てはまる共済事由を見ていきましょう。
・個人事業主
| 共済金A | すべての個人事業の廃業 共済契約者の死亡 |
|---|---|
| 共済金B | 老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を支払い済) |
| 準共済金 | 個人事業の法人成り後、加入資格がなくなり解約 |
| 解約手当金 | 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納) 個人事業の法人成り後、加入資格を持ったまま解約 |
・法人の役員
| 共済金A | 法人の解散 |
|---|---|
| 共済金B | 病気や怪我または65歳以上での役員の退任 共済契約者の死亡 老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を支払い済) |
| 準共済金 | 法人の解散・病気・怪我以外の理由または65歳未満での役員の退任 |
| 解約手当金 | 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納) |
・共同経営者
| 共済金A | 個人事業主の廃業による共同経営者の退任 病気や怪我による共同経営者の退任 共済契約者の死亡 |
|---|---|
| 共済金B | 老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を支払い済) |
| 準共済金 | 個人事業の法人成り後、加入資格がなくなり解約 |
| 解約手当金 | 任意解約 機構解約(掛金を12カ月以上滞納) 共同経営者の任意退任による解約 個人事業の法人成り後、加入資格を持ったまま解約 |
各出典:中小機構「共済金(解約手当金)について」
任意や滞納での解約といった解約手当金に該当する請求事由以外は、掛金と同等額となる準共済金、もしくは掛金以上の額が受け取れる共済金A・Bになります。
小規模企業共済は危ない?6つのデメリットと注意点
「小規模企業共済は危ない」と言われる背景には、以下のようなデメリットや注意点が存在します。なぜ危ないと言われるのか、順に確認していきましょう。
- 1.掛け捨てのリスクがある
- 2.元本割れのリスクがある
- 3.共済金の受け取り時に課税される
- 4.インフレリスクに対応していない
- 5.任意解約時の税制上の不利
- 6.死亡保障の制限
1.掛け捨てのリスクがある
小規模企業共済の共済金は、請求事由によって4種類に分かれています。
種類ごとに掛け捨て扱いになる期間が定められており、具体的な期間は以下のとおりです。
- 共済金A・共済金B:掛金の納付が6カ月未満
- 準共済金・解約手当金:掛金の納付が12カ月未満
加入期間が短いと掛け捨て扱いになり、各共済金を受け取れないため注意しましょう。
2.元本割れのリスクがある
小規模企業共済では、下記2つのいずれかに該当する場合に、元本割れしてしまう可能性があります。
- 20年未満で任意解約した
- 掛金を減額した
小規模企業共済では「共済金が100%を超えるのは240カ月(20年)以上」となっているため、20年未満で任意解約すると元本割れのリスクがあります。
ただ、20年未満であっても「任意解約」でなく「廃業」であれば元本割れしない場合も。このケースでは廃業手続きを終えてから貰える廃業届を提出する必要があります。
そして、掛金を減額した場合にも元本割れするリスクがあるので気をつけましょう。小規模企業共済では途中で掛金を減額してしまうと、減額した分がその後運用されなくなってしまいます。
減額した分にかける割合はその時点で決定してしまうため、元本割れを起こしてしまう可能性があるのです。
3.共済金の受け取り時に課税される
共済金の受け取り時に課税される点にも注意が必要です。廃業せざるを得ない状況で税金の支払いとなると、負担が大きくなりかねません。
ただ、小規模企業共済の共済金は「退職所得」または「公的年金等の雑所得」になるためほとんど税金はかからず、そこまで大きなデメリットではないでしょう。
危ないといわれるデメリットは存在しますが、事前に共済金が増えていく仕組みを理解していればリスクを軽減可能です。
4.インフレリスクに対応していない
小規模企業共済における注意点として、インフレリスクに対応していない点が挙げられます。近年は物価が高騰し、生活面に影響を及ぼしていますが、この物価が上がる現象を「インフレーション」と呼び、お金の価値が下がることを意味しています。
小規模企業共済で長期間にわたり積み立ててきた場合、多くの共済金を受け取れると期待する方も多いでしょう。しかし、インフレリスクには対応していないため、将来インフレリスクが起きてしまった場合、自分がこれまで積み立ててきた共済金も価値が下がり、受け取る金額が目減りする可能性があります。
5.任意解約時の税制上の不利
小規模企業共済の共済金を受け取るためには、廃業または65歳に達する必要があります。この共済金は退職所得扱いとなり、控除額も大きくなることから税制上有利です。
一方、任意解約や法人成りなどでこれまでの掛金を受け取りたい場合、解約手当金として受け取れます(法人成りの場合、準共済金となる場合もある)。解約手当金は一時所得扱いとなり、他の所得と合算して所得税が決定する「総合課税」の対象になってしまいます。
6.死亡保障の制限
小規模企業共済には死亡保障が設けられていますが、加入した時の年齢や掛金の納付期間によって受け取れる金額が異なります。年齢が上がれば上がるほど死亡保障が低くなってしまうのです。
また、一般的な生命保険だと死亡保険金の受取人を指定できます。しかし、小規模企業共済の死亡時共済金は受取人を事前に指定できないので注意が必要です。
小規模企業共済の6つのメリット
小規模企業共済は、以下の6つのメリットがあります。
- 1.6カ月以上継続で共済金を受け取れる
- 2.掛金の全額が控除として利用できる
- 3.退職金と同じ控除が使える
- 4.無理のない掛金に調節できる
- 5.一括・分割・併用の受け取り方法から選べる
- 6.低金利の貸付制度が使える
メリットの詳細を順に解説します。
1.6カ月以上継続で共済金を受け取れる
1つ目は「6カ月以上継続で共済金を受け取れる」点です。
長期継続を前提としなければデメリットが大きいと思われがちな小規模企業共済ですが、それは主に任意解約のケースに言えます。共済金Aや共済金Bに当てはまれば、6カ月以上の継続で共済金を受け取ることが可能です。
短期間の加入でも、やむを得ない請求事由であれば共済金を受け取れる仕組みになっています。
2.掛金の全額が控除として利用できる
2つ目は「掛金の全額が控除として利用できる」点です。このことから節税の目的だけでも、小規模企業共済を活用するメリットがあると言えます。
今年度の所得が多く税金が心配という場合には、12月に翌年分を一括で払うことで、最大84万円分の控除が適用可能です。
3.退職金と同じ控除が使える
3つ目は「退職金と同じ控除が使える」点です。解約時に税金を支払う必要がありますが、個人事業主であれば「退職所得」扱いになります。
退職所得には退職所得控除が適用され、事業所得と比べて税金の負担が低いため、個人事業主であれば節税対策になるでしょう。
4.無理のない掛金に調節できる
4つ目は「無理のない掛金に調節できる」点です。毎月の掛け金は1,000円~70,000円までで、500円単位で自由に設定できます。
売り上げが落ちて余裕がないときは掛け金を減額できて、余裕があるときは増額して積立金を増やせます。
5.一括・分割・併用の受け取り方法から選べる
5つ目のメリットは、共済金の種類によって受け取り方法を「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べる点です。
分割または併用を選択したい場合は、請求事由などにおいて特定の要件を満たす必要があります。要件さえ満たせば、今後のライフプランなどに合わせて選択が可能です。
なお準共済金と解約手当金は一括受け取りのみとなっています。
6.低金利の貸付制度が使える
最後に、低金利の貸付制度が利用できる点も挙げられるでしょう。借りられる金額は積立金の範囲内という制限はありますが、年利0.9~1.5%の低金利です。
一般貸付制度のほかにも、病気や災害時、福祉目的、創業資金、廃業準備などさまざまな目的で融資が利用できます。
また、節税対策には税金チェックシート(無料)がおすすめです。税理士など専門家による事例を集めました。税金で損をしない方法が学べます。
小規模企業共済に向いている人・向いていない人
小規模企業共済を利用することでさまざまなメリットが得られますが、どんな人にも適した制度とは言えません。そこで、小規模企業共済が向いている人と向いていない人の特徴を解説します。
向いている人
・自営業やフリーランスで将来の退職金を自力で準備したい人
自営業やフリーランスといった個人事業主は、企業に勤める会社員とは異なり退職金がありません。そのため、老後の生活資金を自力で準備したい人には小規模企業共済が向いています。
・年間所得が多く、節税策を探している人
小規模企業共済の掛金は全額所得控除になることから、所得が高ければ高いほど節税効果も期待できます。すでにある程度の売上げが見込める個人事業主や、高収入の状態にある人は小規模企業共済の活用がおすすめです。
・事業を長く続ける予定がある人(20年以上)
事業を20年以上続ける予定がある人も、小規模企業共済で有利になります。加入月数が20年未満だと解約時に掛金合計額を下回ってしまうためです。
ただし、これはあくまでも任意解約や掛金滞納による機構解約の場合にのみ当てはまり、廃業やケガ・病気で退任することになった場合は、共済金の元本割れは起きません。
・廃業や老後資金を考えた堅実な資産形成を望む人
小規模企業共済は元本割れを起こすリスクが低いことから、廃業や老後資金なども見据えた上で、堅実な資産形成を望む人にも向いているでしょう。
株式や投資信託などの金融商品と比べるとリターンは低くなるものの、長期的かつ安定した資産形成をするなら小規模企業共済がおすすめです。
向いていない人
・数年以内に解約する予定がある人
小規模企業共済は20年未満で任意解約すると元本割れのリスクがあることから、数年以内に解約する予定がある人には向いていません。また、加入期間が6カ月未満、または12カ月未満だと納付した掛金はすべて掛け捨てになるケースもあります。
・収入が不安定で掛金を継続できるか心配な人
収入が不安定な状況の中で、毎月掛金を支払うのが難しくなるケースも考えられます。そのような不安があるなら、利益が上がった時点で小規模企業共済を利用するか考えた方が良いでしょう。
・複数の制度を使い分けるのが面倒な人
例えば小規模企業共済とiDeCoは併用でき、どちらも掛金が全額所得控除になるため、高い節税効果が期待できます。しかし、複数の制度を利用していると手続きや管理が煩雑になってしまう可能性もあります。
・貯蓄性よりも柔軟な流動性を重視したい人
小規模企業共済では納付した掛金の一部を引き出せなかったり、解約手当金が振り込まれるまで最短でも約3週間かかったりします。そのため、貯蓄性よりも資金の流動性を重視したい人には向いていません。
平成28年4月から小規模企業共済が改正。どう変わった?
平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、小規模企業共済法の一部が改正されました。
改正によって変わったポイントは、大きく以下2つに集約されます。
- 共済金の額と受け取りの範囲拡大および柔軟化
- 各種手続きの手間を削減
いずれも加入の間口を広げ、ハードルを下げている傾向が見て取れます。
具体的な改正内容とともに、変わったポイントについて詳しく見ていきましょう。
共済金額の上昇
一部の共済事由の範囲が変更になり、受け取れる共済金額の上昇が実現しました。
例えば個人事業主の場合、以前は「配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由は準共済事由でしたが、改正によってA共済事由となっています。
共済金額は通常「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の順に金額が大きいため、受取金額が増える結果となったのです。
共同経営者と会社等役員の場合にも、一部において共済事由の範囲変更が図られています。
分割受け取り回数の見直し
共済金を分割で受け取る回数について、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に見直しが行われました。
これまでは年4回の受け取りだったため、お金の使い方にはある程度の計画性が必要だったものの、6回に増えたことで計画の柔軟性が向上します。
受け取れる遺族の範囲拡大
契約者が亡くなったときに共済金を受け取れる遺族の範囲ですが、改正に伴い「ひ孫」および「甥・姪」が追加されています。
契約者ごとの多様な家族環境に配慮し、共済金の受け取り対象が拡充されました。
申込金の撤廃
共済契約の申し込み時に必要だった現金での申込金ですが、制度改正で不要になりました。これまで以上に契約のハードルが下がり、多くの人が利用しやすくなっています。
掛金減額手続きの緩和
共済金の掛金を減額する際に必要な手続きが緩和されています。
具体的には、これまで必要だった「委託機関(金融機関等)による減額理由の確認」が不要となり、減額が容易になりました。
掛金の金額を動かしやすくなったので、キャッシュの状況に応じて素早い対応を取ることができます。
共同経営者独立時の契約継続
共同経営における共済の契約についても見直され、共同経営者が独立した後も契約の継続が可能になっています。
1年以内に新たに加入資格を満たすなどの条件があるので、詳細を確認した上で活用しましょう。
滞納時の解約扱いの緩和
12カ月分以上の滞納があると共済契約が解除されますが、災害などのやむを得ない事情があれば継続できるよう改正されました。
余儀なく発生した場合に適用となるため、基本は滞納しないように注意しましょう。
貸付金制度の拡充
共済金の契約者が利用できる貸付制度ですが、借り入れ限度額の上限引き上げが行われています。さらに特定の人が利用できる「廃業準備貸付け」も設けられました。
廃業準備貸付けは、個人事業の廃止または会社の解散のための貸付制度です。廃止や解散を円滑に行うためにはさまざまな費用がかかりますが、その資金として利用できます。
創業期においては黒字倒産しないために、キャッシュフローが特に重要となってきます。冊子版の創業手帳(無料)では、キャッシュフローの見極め方や、改善する方法について詳しく解説しています。また、日々の記帳を自動化してくれる会計ソフトも経営において便利になってきますので、詳しく解説しています。
小規模企業共済への加入方法
小規模企業共済に加入する方法をチェックしましょう。手続きの流れと必要な書類について解説します。
小規模企業共済への加入手続きの流れ
小規模企業共済に加入する際は、以下の流れに沿って準備を進めます。
-
- 必要な書類を準備・作成する
- 窓口またはネットから申し込む
- 掛金を納付する
契約申込書や口座振替の申請書をはじめ、共済加入に必要な書類を用意しておきます。個人事業主や共同経営者など、申請者の立場によってやや書類が変わるので注意しましょう。
書類がそろったら、中小機構のオンライン手続きポータルからネット申し込みをするか、窓口にて直接申請します。ネット申し込みにはマイナンバーカードが必須です。窓口は中小機構から委託を受けている団体や金融機関となります。
加入手続きが済んだら掛金の納付です。口座振替または現金で納付できます。選択した支払い方式に応じた金額を準備しましょう。
小規模企業共済への加入に必要な書類
小規模企業共済に加入する際に準備すべき書類をまとめました。誰もが必要な共通書類と、契約者別に求められる書類があります。
| 契約者 | 必要書類:契約者別 | 必要書類:共通 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | ・所得税の確定申告書の控え、開業届の控えのいずれか | ・契約申込書
・預金口座振替申出書 |
| 会社等役員 | ・商業登記簿謄本など(役員登記されていることが確認できる書類) | |
| 共同経営者 | ・個人事業主の所得税の確定申告書の控え、開業届の控えのいずれか ・個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(金銭消費賃借契約書・出資契約書の写しなど) ・報酬の支払い事実が確認できる書類(社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳など) |
どの契約者でも「契約申込書」と「預金口座振替申出書」は必須です。あとの書類は、個人事業主・会社等役員・共同経営者のどの立場かによって異なります。
個人事業主や小規模事業に携わる共同経営者の場合、確定申告書の控えが必要です。開業したばかりで確定申告が済んでいなければ、開業届の控えを提出しましょう。
共同経営者は加入要件を満たす複数の書類が求められるので、余裕をもって準備してください。
まとめ・小規模企業共済の今後の展望
労働の多様化が進んでいる現代において、今後も小規模企業共済は重要な共済制度に位置づけられるでしょう。
高齢化はこれからも進んでいくので、老齢給付(現在65歳以上)の年齢引き上げや月額の限度額の上昇(現在は月7万円まで)などは検討される可能性もあります。
何にせよ、共済金を積み立てておけば『貯金のつもりで節税になる』『退職金となる』といったメリットがあります。
少額から掛けられるため起業時から入るのも難しくありません。一方で安定してきたタイミングで考えるというのもよいでしょう。
この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
また、節税対策については、税理士などの専門家に相談する必要があるでしょう。冊子版の創業手帳の請求時に、Web版の創業手帳の無料会員登録が行えます。創業手帳では、専門家紹介や、創業コンサルティングを会員向けに行っています。これらのサービスを受けるに際して、料金は一切無料です。
税金に関する項目は、起業する際には十分に確認する必要があります。まずは、税金チェックシート(無料)で、税理士など専門家の声を確認してみましょう。起業したら最初にやるべき税金の手法がチェックできます。
新リリースした「税金カレンダー」もぜひ合わせてご利用ください!詳しくは以下のバナーから!
(監修:渋谷税理士法人 中村剛士)
(編集:創業手帳編集部)