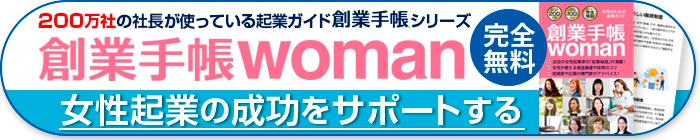主婦が起業で失敗しないために|成功への7ステップとアイデア紹介
主婦の起業に必要なのは、地に足の着いた学び

家庭と仕事を両立できる「主婦の起業」。起業家としてバリバリと仕事をし、格好よく輝く自分になれたら、日々が充実します。
一方で、家族やお金のことが心配、自信のあるスキルがないなど、主婦ならではの悩みもつきものです。
この記事では、ゼロスタートの主婦でも一歩を踏み出せる、失敗しないための起業ステップをまとめました。扶養に入っている主婦が気になるお金の話から起業のアイデアまで、起業の基本がわかります。
家事に育児に…自分のことはいつも後回し。このままでいいのかな、と思っているあなたのために「創業手帳woman(無料)」があります。起業の夢をカタチにした女性たちのリアルな声、ビジネスのヒントが詰まった一冊です。家族を大切にしながらでも、夢や挑戦に手は伸ばせます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
主婦で起業!成功の鍵をにぎる3つのポイント
主婦から起業を成功させるには、大きく3つのポイントを押さえてプランを練る必要があります。
目的をハッキリさせる
起業の目的は主婦に限らず、全ての起業志望者に必要なことです。キラキラした起業家主婦のイメージだけで始めず、ハッキリした目的をかかげましょう。
具体的に思いつきにくいときは、起業して得たいことやなりたい自分をイメージします。その実現のために必要な内容を起業の目的にすえると、経営の軸がはっきりし、事業展開しやすくなるのです。
小さく始める
主婦の起業は、在宅業などから小さく始めるのが基本です。いきなり大きな融資を受けたり、自己資金で多額の仕入れをしたりするのはおすすめしません。
小さく始められるビジネスなら、万が一失敗したときのリスクも最小限に済みます。時間や体力、精神的な健康の観点からも、家庭との両立がしやすい現実的なビジネスプランです。
起業では、しっかりとした「計画」が欠かせません。安定して事業を継続していくためにも、まずはスモールビジネスやプチ起業といったスタイルから始めましょう。
家事や育児とのバランスをとる
主婦が起業で成功するには、仕事をする時間と家事の時間とのバランス作りが欠かせません。夫の協力がどれだけ得られるか、実家のサポートはどうかなど、周囲と話し合ってみましょう。
家事や育児をこなした上で、事業に使える時間をどれだけ捻出できるか考えると、現実的な起業規模や事業プランが見えやすくなります。
主婦の起業におすすめのアイデア

主婦が起業するメリットは、主婦目線のビジネスができることです。家事や育児などの経験を活かし、同じような境遇の主婦を幸せにするビジネスができるでしょう。
具体的にどんなビジネスができるのか、主婦におすすめのアイデアを参考にしてみてください。
在宅でできる仕事
主婦の起業アイデアとして人気が高いのが、在宅でできる仕事です。以下のようなものがあげられます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 物販・せどり | 商品を仕入れて販売する |
| ブロガー、Webライター | ブログ記事や企業のWeb記事を執筆する |
| イラストレーター | アイコンやLINEスタンプなどのイラストを描く |
| ネットショップ | ハンドメイド品などをネット上で売る |
在宅でできる仕事の多くは、資格や資金が必要ありません。たとえば趣味のハンドメイドアクセサリーをネット上で売る場合、いつも作っている作品を用意すれば、あとはスマホ1台でネットショップをひらけます。
多くは低リスクで始められる上、在宅であることから家事や育児の合間にも作業しやすい起業スタイルです。
スキルや経験が活かせる仕事
社会人の頃に培ったスキル、主婦として積み上げた経験を武器に起業するのも、アイデアの一つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| おうち教室 | 料理、ピアノ、ヨガなどの教室を家でひらく |
| サロン | エステ、ネイルなどのサロン施術をする |
| オンライン講座 | YouTubeやSNSなどで講座をひらく |
| ノウハウ販売 | noteやKindleなどでスキル、ノウハウを販売する |
持っている資格や経歴、実績を活かした仕事は信頼度が高く、需要があれば利益も大きく期待できます。人と接する仕事が多いので、コミュニケーションが好きな主婦にもおすすめです。
オンラインでスキルや情報を販売するスタイルなら、家事や育児との両立がしやすくなります。初期投資も限りなく少なくて済むので安心です。
せどりって儲かる?仕入れから販売まで副業でせどりを始める方法を紹介します
Webライターになるには?Webライターの魅力と起業独立するために必要なスキルやツールを紹介
サポート付きで始められる仕事
売れるスキルがない、設備や場所が用意できない。そんな主婦には、初めからサポートを受けられる起業スタイルがいいでしょう。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| フランチャイズ経営 | コンビニやサロンなどの名前を借りて経営する |
| 代理店 | 企業の商品やサービスを代理で販売する |
| シェアキッチン | 設備の整ったキッチンをシェアして店をひらく |
フランチャイズや代理店は、提携元の企業に経営をサポートしてもらえます。特にフランチャイズはノウハウや商品がそろっているので、未経験でも安心です。反面、加盟金や売り上げの一部を本部に支払わなくてはなりません。
シェアキッチンには許認可の申請に必要な設備が整っているので、大きな事前準備が不要になります。ほかの利用者との交流の場にもなることから、ビジネスの情報交換ができるのも魅力でしょう。
主婦におすすめの在宅ワーク15選|未経験でも安全に高収入を目指せる仕事
主婦の起業で気をつけたい「扶養」の範囲

夫の扶養に入っている主婦が起業する場合は、働くことで扶養の対象外になる可能性を考慮しておかなくてはなりません。
いくら稼ぐと扶養から外れる?
主婦が起業して収入を得た場合、以下のタイミングで扶養から外れます。
| 扶養の種類 | 扶養から外れるタイミング |
|---|---|
| 所得税・住民税の扶養 | 年間所得48万円超(配偶者控除) 年間所得133万円超(配偶者特別控除) |
| 社会保険・年金の扶養 | 年間収入130万円超 |
扶養には、所得税や住民税に関わる「税法上の扶養」、社会保険や年金に関わる「社会保険上の扶養」があります。税法上の扶養は所得で決まり、社会保険上の扶養は収入で決まる点に注意が必要です。
純粋に得た金額を収入、収入から控除や必要経費などを差し引いたあとの金額を所得といいます。
所得は48万円を超えたら配偶者控除の対象外となり、さらに133万円を超えると配偶者特別控除から外れる仕組みです。年収は130万円がボーダーラインとなります。
いくら稼ぐと損になる?
主婦が起業して稼いだとき、一般的には社会保険上の扶養から外れる「年収130万超の付近」が損をしやすくなります。
| 主婦の年間収入が130万円の場合 | |
|---|---|
| 負担が増えるもの | 年間の負担金額(目安) |
| 国民健康保険料 | 約9万円 |
| 国民年金保険料 | 約20万円 |
| 住民税・所得税 | 約5,000円 |
健康保険料や年金保険料のほうが、負担額が多いことがわかります。年収130万円超ギリギリの微妙なラインだと保険料の負担が大きく、労働に見合わない収入になるかもしれません。
給与所得と違い、起業で得た事業所得は経費によって所得額が大きく変わります。「社会保険上の扶養からは外れるけど税法上の扶養には入れる」といったことも十分にあるので、少しでも損するリスクを抑えたいなら経費をしっかり計上しましょう。
実際は住んでいる地域によって料率などが変わるので、管轄の年金事務所や税務署などに問い合わせてください。
主婦で起業したいなら必要になる7つのステップ
主婦がゼロから起業を目指す上で、必要になるステップを7つに分けて紹介します。いきなり思いついたものから始めず、順序を踏んで着実に進みましょう。
1.やりたいこと・できることを書き出す
起業の目的をハッキリさせるために、やりたいことやできることを紙に書き出してみましょう。主婦目線での気づきや特技など、どんなに些細なことでもかまいません。
| やりたいことの例 | できることの例 |
|---|---|
| ・収入を増やしたい ・夢を叶えたい ・社会とのつながりがほしい ・人の役に立ちたい |
・社会人の頃に営業を経験 ・お菓子作りが趣味 ・絵を描くのが好き ・掃除が得意 |
書き出した中から、需要の有無、起業に必要なもの、予算や準備にかかる期間などを調べ、具体的なプランに落とし込んでいきます。
目的がハッキリしないままでは、今後どう動くべきかも見えません。家族の協力も得られにくくなる恐れがあるので、しっかり準備しましょう。
2.家族に相談して理解を得る
主婦にとって家族の理解なしで起業することは難しいため、事前に入念な話し合いが必要です。
起業することで起こり得る家事や育児への影響、ライフスタイルの変化なども含め、働き方や役割分担を考えます。その上でいかに対応していくか、具体的なプランをパートナーと相談し決めておきましょう。
3.無理しない範囲で自己資金を貯める
家族の理解を得たら、次に考えるのは「お金」です。初期投資がほとんどいらない起業方法もあるものの、実際の事業ではまとまった自己資金があるほうが、事業の可能性が広がります。
自己資金は、日々の家計とのバランスをとりながら貯めるのが現実的です。無理のない範囲から始めるほか、1年で30万円貯めるなど、ある程度の期限や目標を決めておくとよいでしょう。特に子どもがいる場合は出費がかさむので、中長期的な積み立てを考えるのがおすすめです。
4.無料・少額の学びから始める
起業前に必要なのが、学びのフェーズです。ただ学びにいきなり高額投資するのではなく、無料や少額の範囲から始めてみましょう。Web記事や動画など、無料でも有益な情報はたくさんあります。
最初にたくさん投資をするとリスクが増すのはもちろん、「お金をかけたから学ばないと」という気持ちが先行しがちです。起業のためではなく投資の回収が目的になり、本質を見失いかねません。
まずは低コストからスタートし、徐々に投資を増やしていくのがいいでしょう。同じように主婦から起業した人の事例を調べ、そこから学ぶのもおすすめです。
知識やノウハウは起業したら自然に身につくものではなく、時間をかけて学ばなくてはなりません。「創業手帳セミナー(無料)」では、起業に必要な知識・ノウハウを実践的にお届けしています。参加者の満足度93%!全国どこからでもオンラインで参加可能です。
5.身近なところから小さく試す
スモールビジネスから始めるのは、主婦起業の基本です。本格的に起業する前に、身近なところで試してみてはいかがでしょうか。
たとえば夫や子ども、友人にサービスを体験してもらいます。SNSにアイデアを投稿してみて、反応を見るのもいいでしょう。メルカリなどのフリマアプリを使えば、1点からでもハンドメイド品や仕入れた商品を売ることが可能です。
試した結果から自分の商品・サービスの差別化を検討したり、改善点を見つけたりもできます。アイデアが決まったから、資金が集まったからすぐ起業するのではなく、小さく試して足元を固めるのが現実的です。
6.使えるサポートや支援を調べる
補助金や助成金など、起業に使えるサポートがないか、自治体のホームページを調べておきましょう。問い合わせ窓口がある場合は電話で確認するのが確実です。
女性活躍を国が推し進める中、各自治体も女性の起業をサポートするさまざまな取組みを実施しています。事業計画のブラッシュアップのアドバイスを行ったり、創業費用の助成を行ったり、自治体によってさまざまです。
社会課題に絡めた補助金・助成金も多く、やりたいことにハマれば資金調達に役立ちます。支援制度に合わせて事業計画を検討してみるのもよいでしょう。
7.開業手続きや税務の準備をする
事業開始に必要な準備が整ったら、開業手続きや税務の準備も進めておきましょう。初めて起業する主婦が準備すべきものは以下の3つです。
| 準備するもの | 目的・概要 |
|---|---|
| 開業届 | 個人事業主や自営業者として起業するための提出書類 |
| 確定申告関連 | 帳簿付けの準備、青色申告を選ぶ場合は事前の届け出 |
| 事業用の口座 | プライベート用ではない事業だけで使う銀行口座 |
起業したビジネスで得た所得などは、確定申告で毎年申告しなくてはなりません。そのための帳簿付けや収支管理に必要な口座を準備しておくと、税務処理がスムーズになります。
開業届を出せば、節税に有利な青色申告が利用可能です。本格的な簿記の知識がいるものの、会計ソフトを使えばある程度はサポートを受けられます。
会社(法人)を設立する場合、株式会社、一般社団法人など法人形態を選んだり、定款など34種類の書類を作ったりしなくてはならないので、事前に確認しておきましょう。
成功事例に学ぶ!主婦の起業で成功した経営者
実際に主婦から起業し成功した例を4つ紹介します。成功事例を学んで、夢を現実にしましょう。
・青木水理氏
昼寝する赤ちゃんの周りを装飾する「おひるねアート」の先駆者で、趣味で撮り始めた写真が人気を集めて写真集を出版。現在ではおひるねアート専門スタジオも開設し、活動を続けています。
・たむら紗桜姫氏
子育てしながらヨガを学んで「Happy&Happyヨガ教室」を主宰し、子連れOKのヨガ教室などを開いています。「一般社団法人日本おしゃべり体操協会」を設立しました。
・西浦明子氏
主婦として子育てをし落ち着いたとき、周りに活用されていない空き物件の多さに気づいてビジネスを企画しました。空き物件を活用する「軒先パーキング」は登録数2,500件を超え、現在も増え続けています。
・高田麻衣子氏
働くママを支えるシェアオフィスの一例を以下のリンク先で紹介しています。代表の高田麻衣子氏も仕事と子育ての両立に苦しんだ経験があり、主婦の起業の参考になる内容です。
マフィス 高田麻衣子|バリキャリでも専業主婦でもない「第三の働き方」
まとめ:起業を選ぶなら「夢」ではなく「現実」を直視して挑むこと
このように、主婦が起業するまでにはたくさんの知識が必要ですし、準備に時間がかかります。起業後も事業継続や納税などやることは尽きません。
キラキラして見える起業家たちも、見えないところで努力を続けて幾度も困難を乗り超えてきたのでしょう。
イメージだけに影響されず、難しい局面を乗り越えるだけの熱意や覚悟が自分の中にあるか、自問してみてください。その上で起業に必要な準備を整えることが、成功への近道になるはずです。
「時間がない」「家族に迷惑をかけそう」
今成功している主婦起業家たちも、最初は同じ気持ちだったに違いありません。「創業手帳woman(無料)」には、主婦起業の先輩たちがどんな工夫で家庭と両立したのか、リアルな知恵が満載です。シリーズ累計250万部を超える信頼の一冊で、起業への一歩を踏み出してみませんか?
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「創業手帳woman」のミッションは「女性の起業失敗のリスクを軽減させる」とこを掲げています。そのために女性起業家ならではの起業時におさえておきたいポイントを一冊にまとめています。無料でお届けします。