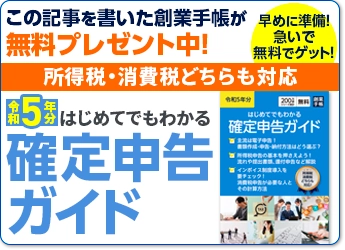【個人事業主】家賃はどこまで経費になる?按分や割合の考え方
自宅兼事務所やワンルームも。「家事按分」で家賃を経費に

個人事業主が借りている住居を事業に使用している場合、疑問になるのが「家賃の扱いはどうなるか」です。
賃貸の家を個人事業で使っている場合には、家賃のすべてまたは一部を経費にすることで、節税できる可能性があります。
この記事では、個人事業主の家賃を経費にするための条件や、住宅にかかる費用の経費算入のポイントを紹介します。
「確定申告ガイド(無料)」は、確定申告の進め方で悩んでいる方、初めて消費税の確定申告が必要になった方など、さまざまなニーズにおこたえします。基本を網羅していますので、はじめの一歩にオススメです。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主の家賃はどこまで経費で落とせる?

個人事業主にとって経費は節税のために重要なポイントです。なかでも家賃は高額であるため、経費として計上できれば節税に大きくつなげられます。
ただし家賃はどんな場合でもすべてを経費にできるわけではありません。どんなときに、どこまでを経費にできるのか、できないケースはあるのかを説明します。
一部を経費で落とせる場合
個人事業主が家賃の一部のみを経費にできるのは、以下のようなケースです。
- 自宅の中に仕事部屋がある場合
- 自宅兼事務所、自宅兼店舗の場合
自宅の区切られた一画や自宅兼事務所の家賃を経費とする際は、実際に事業で使用している分のみを計上しなくてはなりません。事業で使う割合は家事按分で算出します。
プライベートでしか使わない部屋は経費の対象とはならないほか、自宅としての役目が少しでもあれば100%は経費にできません。家事按分で正確な割合を出し、事業で使った分のみを計上しましょう。
全額を経費で落とせる場合
家賃の全額を経費で落とせるケースには、以下のようなものがあります。
- 自宅とは別にある仕事場の家賃の場合
- バーチャルオフィスの場合
自宅とは別に事業用の事務所を構えている場合やバーチャルオフィスを借りた場合など、100%事業に使っている場所の家賃は全額経費にできます。
経費で落とせない場合
家賃の一部、または全額を経費で落とせない場合は、次のケースが当てはまります。
- 同一生計者と賃貸契約を結んだ場合
賃貸契約を結んだ相手、つまり家賃を支払う相手が個人事業主と同一生計者である場合、家賃を経費で落とすことはできません。
ともに生活している親からマンションを借りたり、配偶者が運営する物件を事務所とした場合などが例です。
逆に言えば、契約相手が親族であっても生計が別々であれば家賃は経費にできます。
個人事業主が事務所を借りる際に、親族を含めた知り合いを頼ることもあるでしょう。事務所の家賃を計上したければ、自身とは生計が異なる親族に相談するのが妥当です。
創業手帳では、個人事業主の方へおすすめの「経費で損しないチェックリスト(無料)」をご用意しています。人件費や交際接待費など、23種類の経費項目についてわかりやすく説明しています。ぜひこちらを活用して、経費管理や、利益の最大化、効果的な節税を実現しましょう。

経費にできる割合は?個人事業主が知るべき「家事按分」

自宅兼事務所など、家賃の一部を経費にするには「家事按分」が必要です。家事按分とは、プライベートとの兼用がある家事関連費について、事業用に使った割合のみを抽出する計算方法を指します。
按分できるのは、実際に事業で使っている割合のみです。家賃の割合は「事業で使用する面積」か「事業で使用する時間」のどちらかで考えます。
面積から割合を出す
家賃を按分する場合、部屋の面積をもとに使用している割合を決めることができます。
自宅の総面積のうち、事業用に使う面積をパーセンテージで出して家賃にかけると、経費にできる金額を算出可能です。
10㎡ ÷ 50㎡ = 0.2(20%)
15万円 × 20% = 30,000円(経費計上できる家賃の目安)
6畳=約10㎡なので、総面積の約5分の1=20%を事業で使っていることになり、家賃15万円に20%をかけた金額3万円を経費にできます。
時間から割合を出す
事業に使用している時間から按分し、経費分の家賃を出すことも可能です。
1日のうち何時間を仕事に使用しているかで計算するため、事業用とプライベート用の空間がハッキリ分かれていない自宅兼事務所などでも使えます。
8時間 ÷ 24時間 = 0.33…(約33%)
15万円 × 33% = 49,500円(経費計上できる家賃の目安)
1日24時間を労働時間で割った分が経費になる考え方です。ワンルームに住んでいて面積で出すのが難しい場合には、時間から按分するといいでしょう。
家賃の「勘定科目」と経費にする際の「記帳方法」
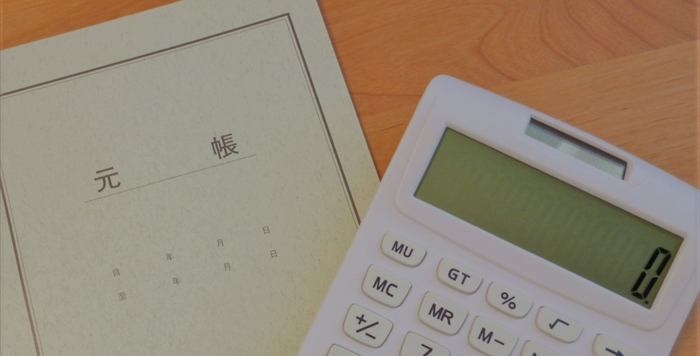
家賃を記帳するとき、経費としての勘定科目は基本的に「地代家賃」です。
| 勘定科目 | 家賃の性質 |
|---|---|
| 地代家賃 | 事業用分の家賃(按分した場合も含む) |
| 支払手数料 | バーチャルオフィスの家賃 |
| 事業主貸 | 経費にできないプライベート用分の家賃 |
バーチャルオフィス料金のうち、電話対応などのオフィス業務に関するサービス料は「外注費」としても処理が可能です。課税仕入取引として処理する科目であるため、仕入税額控除にも活用できます。
これらの勘定科目を使って、実際にどう記帳するかを見ていきましょう。
1カ月単位で按分する方法
1カ月単位で家賃の家事按分と記帳を行います。事業に割く時間が月によって大きく変動する場合に向いている方法です。
家賃が月10万円、事業用割合が50%の場合には、以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 地代家賃50,000円 | 普通預金100,000円 |
| 事業主貸50,000円 |
事業で使った割合が20%まで減った月は、次のように仕訳が変わります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 地代家賃20,000円 | 普通預金100,000円 |
| 事業主貸80,000円 |
月々の事業用割合に応じて、地代家賃と事業主貸(個人の出費)に分けます。この方法には、確定申告ソフトの家事按分機能を使えないため、自分で毎月の仕訳が必要です。
1年分をまとめて按分する方法
経費にできる家賃を12カ月分をまとめて按分し、記帳することも可能です。
この場合、まずは家賃を支払った仕訳を月ごとに行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 地代家賃100,000円 | 普通預金100,000円 |
さらに年末の仕訳で、年間の家賃額を使用割合に応じて家事按分します。下記は事業用の割合が50%の場合です(10万円 × 12カ月 × 50%)。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 事業主貸600,000円 | 地代家賃600,000円 |
最後にまとめて按分する方法は、月ごとに使用割合が変わらない場合に使えます。毎月の家賃の仕訳ごとに按分の必要がないので簡単です。
個人事業主が家賃を経費にするときのポイント

個人事業主が家賃を経費計上する際には、いくつかの注意点があります。経費にできる範囲や必要な書類など、押さえるべきポイントを紹介します。
敷金・礼金は処理が異なる
個人事業主の借りている賃貸の費用のうち、敷金は経費にできません。敷金はもともと費用ではなく、いずれ戻ってくるお金として扱うため、資産として処理します。
礼金は経費にできますが、20万円以上であれば減価償却が必要です。減価償却する際には礼金を資産として処理し、数年に分けて経費計上します。その年にまとめて計上できませんが、経費にすること自体は可能です。
更新料や共益費なども経費にできる
賃貸物件にかかる更新料のほか、管理費や共益費なども家賃と同様の考え方で経費にできます。
物件のすべてが事業用なら全額が経費となり、プライベートと共用する部分があれば家賃と同じ割合を家事按分して計上しましょう。
自分名義でなくても計上できる
夫名義のマンションで妻が個人事業主として働く場合も、賃借契約の相手が同一生計の親族でなければ、按分による計上が可能です。
必ずしも借主の名義が個人事業主本人でなくても構いませんが、家賃の支払先が同一生計者でないことが重要になります。
契約相手の生計が事業主と同一だと、名義や事業割合に関係なく家賃の経費計上はできません。
契約書や明細が必要となる
自宅家賃の一部を家事按分によって経費計上する場合には、事業用であることや按分の根拠となる資料が必要です。
資料となるものには、賃貸借契約書や家賃を引き落としている通帳などがあげられます。借りている人がわかるもの、家賃を支払っていることの証明となるものをそれぞれ保管してください。
毎年、確定申告書類を記載する際にも家賃の支払先情報を書かなければいけないので、常に手元に揃えておきましょう。更新の際に家賃の値上げや値下げがあったら、その金額も計算に反映させる必要があります。
青色・白色で按分の許容範囲が異なる
家賃を家事按分する際に気をつけたいのが、青色と白色のどちらで確定申告しているかで、家事按分の許容範囲が異なる点です。
| 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|
| 事業用の割合に決まりはない | 事業用の割合が50%を超えるものしか家事按分できない |
青色申告では、按分できる家事関連費の事業割合に制限はありません。しかし白色申告だと、事業用割合が50%を超えていないと、家事按分による計上ができなくなります。
自宅面積100㎡のうち事業で使う部分が40㎡しかない場合、白色では按分や経費計上ができないのです。
ただし明確に事業用であると証明できれば、割合が50%未満の白色申告でも按分が認められることがあります。事業用であることを論理的に説明できるように按分し、領収書などの証拠も保管しておきましょう。
税務署に正当な事業関連性を主張できるようにする
個人事業主が家賃などの家事按分をする際には、税務署に指摘を受けた時に提示できる客観的な根拠を準備しておくことが大切です。契約書や領収書だけでなく、事実に基づいて計算したことがわかるように記録しておきましょう。
確定申告の内容次第では、税務調査が入ることも想定されます。内容に不備があれば、追加の納税や追徴課税の支払いが生じかねません。思わぬ出費となる恐れがあるため、曖昧な経費計上は避けるよう気をつけましょう。
税務署から指摘を受けた際に、正当な事業関連性を主張できるように、必要な資料や計算の根拠を揃えておいてください。また、正確な家事按分を心がけることも大切です。
家賃以外も!個人事業主が経費にできる家事関連費
家事按分の対象となるのは「家事関連費」と呼ばれる、事業とプライベートで共用することの多い費用です。
家賃はもちろん、住宅に関連するほかの費用も按分によって経費にできます。
代表的なものから、意外と見落としがちなコストまで、さまざまな費用を紹介します。個人事業主にとっては大きな節税対策にもなり得るため、家事按分で経費にできる費用を把握しておきましょう。
倉庫の賃料
個人事業主が借りている倉庫の賃料は、事業に使っている割合分を経費にできます。
個人的な荷物と、事業で使う仕入れや材料を一緒に保管しているなど、プライベートと共用している場合は家事按分を行います。
100%事業にしか使っていなければ、全額を経費として計上しましょう。
水道光熱費
事務所として自宅を使用している場合、電気代やガス代、水道代などの光熱費も家事按分によって経費計上できます。
ただし、経費計上できる範囲には仕事の内容によって限りがあります。実際に事業用として使っていない、事業に不可欠であると認められないものは経費にできません。
例えば、自宅で料理教室をしていれば水道代やガス代も経費になりますが、パソコンだけでできる仕事の場合には難しいでしょう。
通信費
スマホ料金やインターネット回線の利用料なども経費の対象です。スマホやパソコンを事業とプライベートで兼用している場合、家事按分によって経費にできる金額を算出します。
1日あたりの使用時間のほか、日数から求める方法もあるでしょう。家事按分する際には客観的かつ正当性のある理由が必要なため、不安であれば事業用の端末を用意するのが無難です。
自動車関連費
自家用車を営業車として使うなど、自動車に関する費用も経費になります。購入費用や駐車場代をはじめ、ガソリン代や自動車税、車検代も経費計上が可能です。
これらの費用を家事按分する際には、走行距離で計算します。自動車の購入費用は資産計上した上で減価償却するのが一般的です。
社宅の家賃
従業員を雇用する際の社宅についても、その家賃を経費として計上できます。
持ち家を社宅とする場合は、対象の社員との賃貸借契約が必要です。賃貸物件を個人事業主が借り、さらに従業員に提供する「転貸借」では、事業主や会社が家賃の一部を負担しなくてはなりません。新たに購入する物件を社宅とする際は、減価償却で処理します。
事業の発展が見込まれており、社宅の用意まで検討している個人事業主は念頭に置いておきましょう。
持ち家の購入費
個人事業主の持ち家の購入費用も、事業用分を減価償却によって経費にできます。元本の支払いではなく、減価償却した資産や金利分を経費計上できる仕組みです。
家賃と同じく事業用と生活用に家事按分して、事業用のみを経費計上します。
持ち家の費用を経費にする際は、住宅ローン控除の要件に注意してください。「床面積の2分の1以上は居住用であること」「全額控除を受けるには事業用割合が10%以下であること」といった要件があります。
事業用割合に注意し、ほかの節税方法に支障をきたさないようにしましょう。
まとめ・個人事業主の家賃は家事按分で経費計上して節税しよう
個人事業主の家賃は、賃貸物件を事業用として使っている場合、経費にできます。生活スペースがある場合には、根拠のある家事按分を行うことが必要です。
適切な方法で事業用と生活用の費用を分け、節税を目指してください。
「確定申告ガイド」では、効率的な電子申請について、申告書の作成から納税までをフロー図でわかりやすく解説しています。家賃などの経費計算も楽に済ませることが可能です。
創業手帳(冊子版)は、資金調達や節税など起業後に必要な情報を掲載しています。起業間もない時期のサポートにぜひお役立てください
(編集:創業手帳編集部)