創業手帳が選ぶ起業経営ニュース
2020年9月11日前橋市がJR東日本、NTTドコモ等と組み、次世代モビリティサービスの協議会を設置

2020年9月4日、前橋市やJR東日本高崎支社、NTTドコモなど10団体は、複数の移動手段を一つの交通サービスに統合する「MaaS(マース)」を実現するためのコンソーシアム、「前橋市新モビリティサービス推進協議会」を設立しました。
新しい移動手段の実現を支援する経済産業省・国土交通省の「スマートモビリティチャレンジ」事業に採択されたことを受けた取組です。前橋市での実証実験は約3,000万円規模で行われる見通しで、約800万円を国が負担します。
経済産業省・国土交通省は2020年7月、「令和2年度スマートモビリティチャレンジ」の取組として、新しいモビリティサービスの社会実装に挑戦する合計52の実証地域を選定しました。各地域で新しいモビリティサービスの実証実験や事業性分析等を実施し、ベストプラクティスの抽出や横断的課題の整理等を行うことを通じて、地域モビリティの維持・強化、さらには移動課題の解決、地域経済の活性化を推進することを目指すものです。
同協議会にはこの他、ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構(同市)や群馬大学、NTTデータ、配車システムを手掛ける未来シェア(北海道函館市)、群馬県バス協会、前橋地区タクシー協議会、上毛電気鉄道(前橋市)が参加しています。
実証実験の柱の一つは2019年度に住民を対象にアプリを使って実験したMaaSの機能拡張です。今回はJR東が観光客向けに開発した「ググっとぐんMaaS」を基にして住民向け機能を加える予定です。市民だけでなく、市外の旅行者が市内をスムーズに移動できるかを検証して、同市の観光産業発展に寄与する形を模索します。
2021年4月以降には、前橋版MaaSの実現に向けて路線バスのダイヤ見直しなどを段階的に実施していく方針も打ち出しています。前橋市の山本龍市長は「高齢者や障害者ら様々な人に外出機会を与えられる公共インフラ提供に向けた第一歩」と意義を語りました。
2020年12月から約3カ月かけて実証実験を行い、2021年度以降に前橋版MaaSの実現を目指します。
編集部のコメント
| カテゴリ | 便利なサービス |
|---|---|
| 関連タグ | IT MaaS アプリ インフラ タクシー テクノロジー ビジネスモデル ベンチャー まちづくり ライフスタイル 交通 経済産業省 |
便利なサービスの創業手帳ニュース
関連するタグのニュース
2018年12月23日、株式会社ジェネシア・ベンチャーズは、2号ファンドとなる「Genesia Venture Fund 2 号投資事業有限責任組合」を設立したことを発表しました。 1次募集では、総額…
7月26日に出たニュースの中で、起業家が注目したいニュースをまとめました。 クラウドサービス中国大手テンセント参入 日本企業への影響は クラウドサービス市場に、中国大手のテンセントが参入しました。日本…
2023年4月10日、株式会社SmartRydeは、総額約4億5,000万円の資金調達を実施したことを発表しました。 また、新プロダクト「Demand Partner API」を公開したことも発表しま…
2022年3月14日、Appright Entertainment株式会社は、「ONE RECO(ワンレコ)」をリリースしたことを発表しました。 「ONE RECO」は、声優・俳優・アイドル・ミュージ…
2024年4月24日、株式会社primeNumberは、総額20億円超の資金調達を実施したことを発表しました。 primeNumberは、データ基盤の総合支援サービス「trocco(トロッコ)」の開発…
大久保の視点
2025年3月14日(金)に明治大学・御茶ノ水キャンパスで第3回明治ビジネスチャレンジ(明治ビジチャレ)が明治大学経営学部主催で行われました。 明治大学の各…
日本国内で唯一のサブスクリプション特化型イベント「日本サブスクリプションビジネス大賞2024」が、2024年12月4日(水)にベルサール六本木で開催されまし…
パネルセッション例:中村幸一郎(Sozo Ventures ファウンダー・著名な投資家)、ヴァシリエフ・ソフィア市副市長(ブルガリアの首都) 「Endeav…



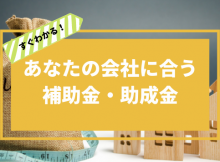



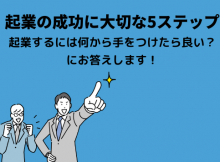


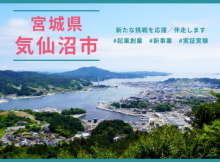













経済合理性はもちろんですが、交通やITインフラ、ライフスタイル、人々の価値観など、時として合理性だけでは論じられないさまざまな要因が複合的に噛み合うことが、スマートモビリティシステムの自律自走には不可欠です。壮大なテーマだけに産官学の知恵と資本を集約させて、世界に発信できる日本モデルの確立に至ることを期待したいものです。
スマートシティ、スマートモビリティは大きな方向性は見えているものの、個別のソリューションやサービスレイヤーではスクラッチで構想を描くところからチャレンジが行われています。そうした意味ではベンチャー企業の活躍の余地は大きいと言えるでしょう。新たなテクノロジーや斬新なビジネスモデルの提案がいま待たれています。