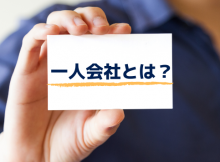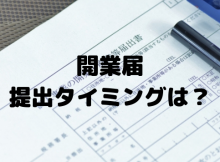個人事業主に法人番号はある?個人番号の取り扱いについて解説
個人事業主は法人番号・個人番号などの理解を深めよう

法人番号は、法人の名称と所在地に紐づけられた1法人にひとつ割り当てられる番号です。
会社の所在地が移転した場合でも法人番号は変更にならないため、取引先の管理コードとしても活用されています。
同じように個人の識別番号としてマイナンバー(個人番号)がありますが、マイナンバーは利用する手続きが限定されていて、プライバシーの観点から人に教えるケースは多くありません。
個人事業主も仕事の中で法人番号やマイナンバーに触れる可能性はあります。それぞれの違いや扱い方を理解しておくようにしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人番号とは

法人を立ち上げたり、開業して個人事業主になったり新しいことをはじめた時には、見知らぬ言葉にも出会います。そのひとつが法人番号です。
まず、法人番号の基本的な知識を紹介します。
マイナンバーの法人版
法人番号を簡単に説明すると、マイナンバーの法人版といえます。個人にマイナンバーが割り当てられているように法人には法人番号が振り分けられています。
マイナンバーが12桁であるのに対して、法人番号は13桁であるという点がわかりやすい違いです。
法人番号は12桁の基礎番号とその前の1桁の検査用数字(チェックデジット)で構成されています。
1法人につき1番号だけ割り当てられ、法人の支店や事業所、店舗には付番されません。法人番号もマイナンバーと同じように2015年10月からスタートしました。
法人番号は書面で通知され、税務手続きや社会保険関連の手続きなどで使われています。
法人番号制度の目的
法人番号制度をはじめた目的は、行政の効率化です。法人番号があれば、法人に関する授受や照合が簡便化して行政での手続きの効率が良くなります。
税務や行政の手続きがより早く便利になれば、企業や個人も恩恵を受けられます。
また、法人番号で行政機関同士の情報連携も強化される点もポイントです。申請手続きを簡素化して、国民の事務負担を減らすことができます。
以前は、法人名と住所から法人を特定していて、情報もバラバラに管理されていました。
それを法人番号を導入することで、国や地方自治体、法人も情報管理や共有がスムーズになりました。
法人番号の導入によって、民間企業での情報管理や手続きも効率化できます。
例えば、取引先の名称や所在地が変更になった時に、国税庁の法人番号に紐づけされた情報にアクセスすればより簡単に管理できます。
法人番号がない法人もある
法人番号は、1法人に1番号の割り当てがされますが、法人番号を付与されない法人もあります。法人番号を付与されるのは、原則として以下の団体です。
-
- 商業登記を行った設立登記法人
- 国の機関や地方公共団体
- 法人格を持たない社団等であっても、税務署への申告義務がある場合
上記に当てはまらない団体は法人番号が付与されません。具体的には、町内会や同窓会といった人格なき社団や任意団体は法人番号が付与されないことがあります。
ただし、法人番号が付与されない団体としてスタートしても税務署への申告義務が発生するなど条件が満たされれば法人番号が指定されることもあります。
また、要件を満たしていれば申請によって法人番号を取得可能です。
個人事業主に法人番号は付与される?

一定の法人は、必ずひとつの法人番号が付与されます。マイナンバーが個人を識別できる番号であるのと同様に法人番号は法人を識別するための番号です。
では、個人事業主に法人番号は割り振られるのでしょうか。
個人事業主に法人番号は付与されない
法人番号は、あくまで法人に対して発行される番号です。そのため、法人を設立していない個人事業主には法人番号は付与されません。
法人は、法人となるために様々な文書申請を経ています。一方で、個人事業主は開業届を出すだけであり規制もほとんどありません。
個人事業主は、個人なので割り振られているのはあくまで個人のマイナンバーだけです。
法人番号と個人のマイナンバーの違いを理解していないと、行政手続きなどで混同するケースがあります。
個人事業主が取引きした時に、取引先から法人番号を求められる可能性もあります。しかし、個人事業主には法人番号はないので間違って記載しないように注意してください。
マイナンバーを記載してしまうと、プライベートの情報を閲覧されるリスクもあります。
法人番号と個人番号(マイナンバー)の違い
マイナンバーは個人番号とも呼ばれ、国内の市区町村に住民票があるすべての個人に割り当てられている12桁の番号です。
マイナンバーを使うのは、社会保険や税、災害対策分野での行政手続きのみです。それ以外の目的で利用したり収集、提供は許されません。
民間企業で従業員や顧客の行政手続きのためにマイナンバーを収集するケースはありますが、それを従業員番号や顧客番号に使うこともできません。
マイナンバーは紛失や盗難が発生しないように第三者へ提供する時には、必ず利用目的を確認します。
一方で、法人番号は各法人の名称や所在地とともに国税庁の「法人番号公表サイト」で公表される番号です。
各法人で従業員や顧客の行政手続きで法人番号を使用するほか、取引先企業の管理番号として利用できます。
法人番号とマイナンバーはどちらも識別のために割り振られた番号ですが、法人番号は公表されていて誰でも自由に利用できる点が大きな違いです。
個人事業主が仕事を受注した時の番号の取り扱い
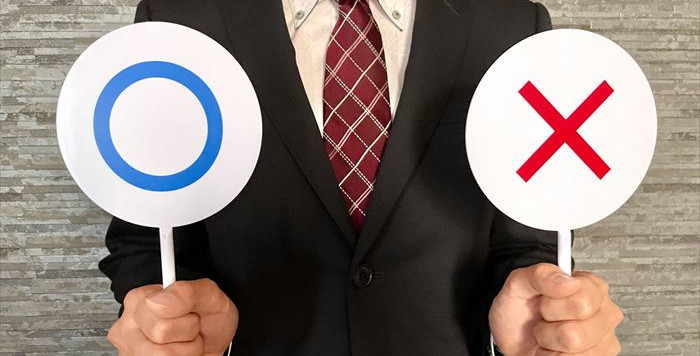
個人事業主に法人番号を割り当てられることはありません。では個人事業主が仕事を受注した時には、どのように取り扱えばいいのでしょう。
取引書類には個人番号を記載してはいけない
個人事業主が、法人から仕事を受注した時に取引書類に法人番号を記載する欄があるかも知れません。この場合、マイナンバーを記載してはいけません。
マイナンバーは、目的が社会保険と税、災害対策に制限されている上、法人番号の代わりにはなりません。
ただし、個人事業主が法人番号にまったく関わらないわけではなく、支払先にマイナンバーを伝えるケースはあります。
以下では、法人番号やマイナンバーが関わるケースについて紹介します。
取引先の法人番号が必要になるケース
個人事業主であっても取引先の法人番号が必要なケースはあります。よく発生するケースが支払調書を作成する時です。
支払調書とは、誰にどのような内容でいくら支払ったのかを税務署に報告するための書類です。
個人事業主であっても、顧問の税理士への報酬や不動産や建物の使用料を支払うケースはあります。
支払調書は、支払先が法人の場合には法人番号を記載する必要があります。つまり、個人事業主であっても取引先の法人番号は必要になることがあるということです。
法人番号の検索方法
支払先の法人番号を記載しなければいけないとしても、支払先に連絡して尋ねる必要はありません。
企業の名称や所在したわかっている時には、「国税庁法人番号公表サイト」で検索すれば法人番号がわかります。
多くの場合は、「国税庁法人番号公表サイト」を使ってすぐに法人番号を確認できますが、もしも検索しても該当法人が出ない場合は検索条件を変えてみてください。
例えば、社名の前後の「株式会社」を省いてみたり、所在地の表記にある「丁目」や「ハイフン」を入れ替えたりすることで検索で見つかることがあります。
また、検索対象除外法人である可能性もあります。この場合には、条件設定で「検索対象除外法人を検索対象に含める」にチェックをしてみてください。
どうしても見つからない時には、そもそも法人番号が付与されていない可能性も疑ってみてください。
発注者に個人番号を伝えるケース
個人事業主が取引書類でマイナンバーを記載することはありません。しかし、発注者にマイナンバーを伝えるケースはあります。
具体的には、税務に関する手続きが発生した時です。
支払内容を税務署に報告する時に使用する支払調書では、個人のマイナンバーを記載する欄があります。
また、原稿料や講演料、税理士や弁護士への報酬も支払調書作成時にマイナンバーを記載する可能性もあります。
さらに、勤務先から給与や退職金を受け取る場合や金融機関との取引き、税務署や地方公共団体で手続きを行う時にマイナンバーが求められことがあります。
個人事業主の個人番号管理における注意点

個人事業主であってもマイナンバーの管理が必要になるケースもあります。マイナンバーは、一般校に公開されているものではなく管理は慎重に行わなければいけません。
どういった点に注意して管理すればいいのかまとめました。
従業員がいる場合は個人番号の管理に注意
従業員を雇用している時には、従業員のマイナンバーを取得する必要があります。これは従業員の源泉徴収手続きなどが発生した場合です。
前述したように、マイナンバーは公表するものではないため、収集と管理には細心の注意が必要です。
収集、つまり従業員のマイナンバーを知るには、一般的にはマイナンバーカードのコピーを提出させる方法があります。
しかし、扶養家族の分も必要になるため、収集も保管も手間がかかります。
マイナンバー法の罰則を理解する
マイナンバーは、マイナンバー法によって保護されています。マイナンバー法とは、マイナンバーや法人番号を活用した効率的情報管理を目的とした法律です。
マイナンバーは、重要な個人情報であり、個人情報の取り扱いはコンプライアンス遵守の面からも重要です。
マイナンバー法では、禁止されている行為や罰則も定められています。
禁止されているのは以下の行為です。
-
- 不正な利益を図る目的で個人情報の提供または盗用すること
- 特定個人情報ファイルの提供
- 情報提供ネットワークシステムの情報漏洩
- 特定個人情報記録文書の収集
個人事業主に付与される番号
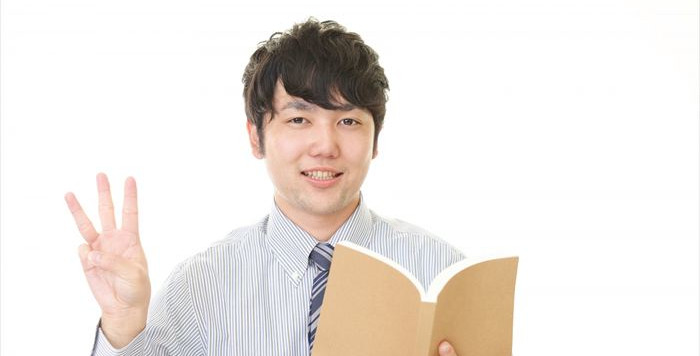
個人事業主には、法人番号が付与されることはありません。しかし、法人番号以外に番号が付与される可能性はあります。個
人事業主に付与される番号にどういったものがあるのかを紹介します。
利用者識別番号
利用者識別番号は、法人や個人事業主に割り当てられた16桁の数字です。利用者識別番号は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する時に使われます。
e-Taxを使うと自宅や職場から確定申告や納税など各種の申告手続きでき、時間や手数料を削減できます。
e-Taxを使う時に、他社からのなりすましを防止する目的で導入されたのが利用者識別番号です。
利用者識別番号は、一度取得すれば継続して同じ番号が利用可能です。所在地が変更や移転したとしても同一の番号を使い続けられます。
利用者識別番号は、マイナンバーカードを使ってアカウントを登録するか、Webから利用者識別番号を取得するもしくはマイナポータルや窓口を利用した手続きなど複数の方法があります。
それぞれの手続きはe-Taxのホームページから確認できるので、手続きしやすい方法を選びんでください。
個人事業主管理番号
個人事業主管理番号は、GビズIDという法人や個人事業主向けの共通認証システムで使われる管理番号です。
GビズIDは、ひとつのIDとパスワードで複数の行政サービスの電子申請やサービス自体を利用できるアカウントです。
個人事業主には8桁英数字の個人事業主管理番号を付与しています。
個人事業主管理番号は、助成金や補助金の申請や社会保険の手続き、自治体へのオンライン申請などで使われています。
GビズIDを作成するには、書類郵送申請とオンライン申請が可能です。
書類郵送申請は申請から発行までに1週間程度かかりますが、オンライン申請なら最短で即日発行可されます。
インボイス登録番号
2023年10月からスタートしたインボイス制度では、個人事業主にもインボイス登録番号を付与しています。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者と認められた事業主はT+13桁」の番号が付与されます。これがインボイス登録番号です。
インボイス登録番号は、取引先が仕入税額控除を受けるために必須の項目です。
このインボイス登録番号が記載されていない請求書は適格請求書とは認められないので、原則として消費税の仕入税額控除を適用できません。
インボイス登録番号も法人番号と同じように、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すれば基本情報を確認できます。
インボイス登録番号を取得するには、郵送かe-Taxから登録申請を行ってください。初めてe-Taxを使う場合であれば、先に利用者識別番号を取得しなければいけません。
まとめ・法人番号は取引きで必要になるため検索方法を理解しておくと安心
個人事業主は、法人格はなく法人番号も割り振られることはありません。しかし、個人事業主はであっても法人との取引きで法人番号が求められるケースもあります。
法人番号は、国税庁の「国税庁法人番号公表サイト」で調べられます。
必要になった時のためにどうやって法人番号を検索するのか知っておけば、必要な時に慌てることはありません。
加えて、混同しないようにマイナンバーや利用者識別番号との違いも理解しておくようにしてください。
創業手帳(冊子版)は、フリーランスや個人事業主に向けた記事を多数掲載しています。仕事の進め方で悩んだ時には創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)