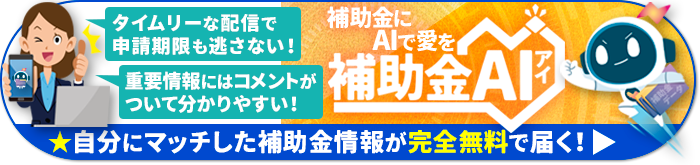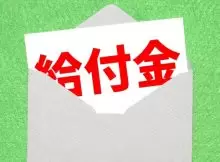【2025年最新版】DX推進におすすめの補助金・助成金|中小企業のデジタル化
DXにより、大企業に負けない競争力をつけましょう!設備投資等には国や自治体の補助金・助成金が使えます

DXに取り組まなければと感じながらも、コストを理由に後回しにしていませんか?
実は今、ITツール導入や業務のデジタル化を支援する補助金・助成金が充実しています。資金に不安がある中小企業でも、制度を活用してDXを推進し、競争力を高めるチャンスです。
この記事では、DX推進に使える補助金・助成金と活用例をまとめました。制度をうまく使ってDXを進める流れがわかり、業務効率や生産性の向上を目指せます。
DXを進めたいけど、補助金の探し方がわからない。そんな悩みを自動で解決してくれるのが「補助金AI(無料)」です。地域・業種・金額など、あなたにぴったりの補助金が届くので、申請に間に合わず手遅れ……なんてこともありません。
最大数百万円の支援も狙える今こそ、制度を探す手間から自由になりましょう。
また、創業手帳では、「補助金ガイド」という補助金の基本や最新情報、申請のコツなどを分かりやすく解説したガイドブックを提供しています。ぜひあわせてご利用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【一覧】DXに使える補助金・助成金

DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略で、直訳すれば「デジタルな変革」です。ITなどのデジタル技術を用いて会社を改革する取り組みを指します。
DXは、単にITシステムを導入することではありません。システムによって商品やサービス、ビジネスモデル全体が改良され、企業の競争力が上がる。ここまで達成されてはじめてDXだといえます。
これからDXを推進する中小企業は、以下の補助金・助成金を活用するのがおすすめです。それぞれ内容や活用例、給付額などを紹介するので、使えそうなものを検討してみてください。
IT導入補助金
IT導入補助金は、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する中小企業・小規模事業者を支援する制度です。卸・小売業から介護業・医療、製造業、宿泊業まで、さまざまな業種・組織形態で下記のように活用できます。
会計ソフトや受発注ソフト、パソコンやタブレットといったIT関連の経費について、幅広く補助対象とする制度です。DX推進との相性が良く、システム化を進めるのにもってこいの補助金となります。
- 紙ベースの受発注業務をクラウドシステムで自動化
- 複数拠点の売上・在庫を一元管理するPOSレジの導入
- インボイス対応の会計ソフトを導入して経理を効率化 など
会計ソフトや受発注ソフト、パソコンやタブレットといったIT関連の経費について、幅広く補助対象とする制度です。DX推進との相性が良く、システム化を進めるのにもってこいの補助金となります。
申請にはGビズIDプライムアカウントやSECURITY ACTION宣言の実施が不可欠です。そのほか、枠ごとに必要な要件を理解した上で申請を進めましょう。
| 申請枠 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1プロセス以上:5万円以上150万円未満 4プロセス以上:150万円以上450万円以下 |
中小企業:1/2以内または2/3以内 |
| インボイス枠(インボイス対応類型) | インボイス制度対応のソフト: 350万円以下 PC・ハードウェア: PC・タブレット等 10万円以下 レジ・券売機等 20万円以下 |
インボイス制度対応のソフト: 【50万円以下】 中小企業 3/4以内 小規模事業者 4/5以内 【50万円超〜350万円以下】 2/3以内 PC・ハードウェア: 1/2以内 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 350万円以下 | 中小企業、小規模事業者等 2/3以内 その他事業者等 1/2以内 |
| セキュリティ対策推進枠 | 5万円以上150万円以下 | 中小企業 1/2以内 小規模事業者 2/3以内 |
| 複数社連携IT導入枠 | 基盤導入経費: ・ソフトウェア 50万円以下×グループ構成員数 50万円超~350万円以下×グループ構成員数 ・ハードウェア 【PC・タブレット等】 10万円×グループ構成員数 【レジ・券売機等】 20万円×グループ構成員数 消費動向等分析経費:50万円以下×グループ構成員数 ※基盤導入経費と消費動向等分析経費の合計額の上限は3,000万円 その他経費:200万円以下 |
基盤導入経費: ・ソフトウェア 50万円以下×グループ構成員数 3/4以内(小規模事業者は4/5以内) 50万円超~350万円以下×グループ構成員数 2/3以内(小規模事業者は4/5以内) ・ハードウェア 1/2以内 消費動向等分析経費:2/3以内 その他経費:2/3以内 |
| DXに関する補助対象経費 | ||
| ソフトウェア購入費(受発注ソフトなど)、クラウド利用料、導入関連費(オプション、導入コンサルティング、マニュアル作成、保守サポート、セキュリティなど)、ハードウェア購入費(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等)、その他経費 | ||
要件・補助額等の出典:「IT導入補助金2025」
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、DXやインボイスといった、中小企業や小規模事業者が直面している制度変更等を意識した補助金です。新たな商品やサービスの開発、生産プロセスの改善などのために行う設備投資等が支援されます。
この補助金は機械装置・システム構築費を含むことが必須なため、DXとも好相性です。例えば以下のようなDXに活用できます。
- 製造ラインへのロボット導入
- 検品の画像処理システム化
- 生産・在庫・販売を一元管理する業務システムの構築 など
賃上げや付加価値額の増加といった基本要件を押さえるほか、特例要件も満たすことで上限額や補助率の上昇も狙えます。対象要件などの詳細をよく確認しておきましょう。
| 申請枠 | 上限額※カッコ内は大幅賃上げを行う場合 | 補助率※カッコ内は最低賃金引き上げ特例を適用する場合 |
|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 5人以下 750万円(850万円) 6~20人 1,000万円(1,250万円) 21~50人 1,500万円(2,500万円) 51人以上 2,500万円(3,500万円) |
中小企業 1/2(2/3) 小規模・再生 2/3 |
| グローバル枠 | 3,000万円(3,100万円~4,000万円) | 中小企業 1/2(2/3) 小規模 2/3 |
| DXに関する補助対象経費 | ||
| 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 など | ||
要件・補助額等の出典:ものづくり・商業・サービス補助金事務局(全国中小企業団体中央会)「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領 (第20次公募)」
中小企業新事業進出補助金
中小企業新事業進出補助金は、既存事業とは異なる新たな市場への進出や、高付加価値事業への転換を目指す中小企業を支援する制度です。
DX投資にも対応しており、デジタル技術による新サービスの提供や業務の再設計に活用できます。事業転換の一歩を後押しする支援策として、以下のようなDX投資の検討が可能です。
- 店舗販売からECサイトでのオンライン販売に販路を拡大
- 買い切り型プロダクトをサブスク型に再構築し、新規顧客層へ展開
- IoTを活用した自社ブランドの開発で新市場を開拓 など
DXを軸に新しい市場で勝負したい企業にとって、本格的な転換とチャレンジを支える選択肢となります。
| 上限額※カッコ内は大幅な賃上げに取り組む場合 | 補助率 |
|---|---|
| 従業員数により以下のように変動 20人以下 750万円~2,500万円(3,000万円) 21~50人 750万円~4,000万円(5,000万円) 51~100人 750万円~5,500万円(7,000万円) 101人以上 750万円~7,000万円(9,000万円) |
1/2 |
| DXに関する補助対象経費 | |
| 機械装置・システム構築費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 など | |
参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業新事業進出促進補助金 公募要領 (第1回)」
小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)
小規模事業者持続化補助金は、これからさまざまな制度変更に直面する小規模事業者を支援するための補助金です。販路開拓や業務効率化を目指してDXを推進する際には、関連経費が補助されます。
一部を除く商業・サービス業で5人以下、それ以外の対象業種で20人以下の小規模な企業を対象とした制度です。DXに取り組む余裕がない小さな店や会社が活用することで、次のように販路開拓や効率化を目指せます。
- クラウド予約・顧客管理ツール導入で少人数経営の体制を構築
- 電話注文からネット受付へ切り替えて人手不足に対応
- 紙チラシからSNS広告に移行し、地方にいながら販路を拡大 など
事業の要件のほか、資本金の規模や過去の補助金の申請歴に関する事項など、補助対象者となる複数の要件も満たさなくてはなりません。詳細は申請予定の公募要領をチェックし、対象に入っているかを調べておきましょう。
| 上限額 | 補助率 |
|---|---|
| 50万円 ※インボイス特例 上限額に50万円を上乗せ ※賃金引き上げ特例 上限額に50万円を上乗せ |
2/3 ※賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4 |
| DXに関する補助対象経費 | |
| 機械装置等費、ウェブサイト関連費、資料購入費、借料、委託・外注費など | |
要件・補助額等の出典:小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第17回公募 公募要領」
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを後押しするための制度です。正社員化や賃上げなどの取り組みを実施した企業に対して、一定金額が助成されます。
DXに直接使えるわけではありませんが、キャリアアップを通じたDX人材の育成などの形で活用が可能です。デジタル業務の中核を担う人材育成を促し、人によるDXを強化しましょう。
- 非正規のIT担当を正社員化し、デジタル業務を内製化
- 現場を知るアルバイトを正社員化し、SNSマーケティングを強化
- 熟練のパートを正社員化し、顧客対応ツールの改善に参画 など
コースによって助成を受けられるシーンが異なるので、DX推進の際は各趣旨に沿った施策を講じることがポイントです。
正社員化コースおよび賃金規定等改定コースにおいては「加算額」が設けられており、講じた措置内容に応じて助成金が増えます。
| 申請枠 | 助成額 |
|---|---|
| 正社員化コース | いずれかの雇用形態から正社員化し、12カ月雇用した場合: 有期雇用 80万円 無期雇用 40万円 (いずれも1人あたり) ※上記に加算額最大60万円 |
| 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給を3%以上増額・適用した場合: 3%以上4%未満 4万円 4%以上5%未満 5万円 5%以上6%未満 6万5,000円 6%以上 7万円 (いずれも1人あたり) ※上記に加算額最大40万円 |
| 賃金規定等共通化コース | 1事業所あたり 60万円 |
| 賞与・退職金制度導入コース | 賞与または退職金制度を導入した場合: どちらかのみ導入 40万円 どちらも導入 56万8,000円 (いずれも1事業所あたり) |
| 社会保険適用時処遇改善コース | 手当等支給メニュー: 1、2年目 40万円 3年目 10万円 労働時間延長メニュー: 30万円 (いずれも1人あたり) |
要件・助成金等の出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)」
DXに使えるその他の補助金・助成金一覧
そのほか、行政組織や地方自治体が独自に実施している補助金・助成金もDX推進に役立てることができます。
- DX推進助成金(東京都)
- みどりの食料システム戦略実現技術開発・社会実装促進事業(委託プロジェクト研究)
- 成長型中小企業等研究開発支援事業
- 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(東京都)
- 福島県建設業バックオフィス研修費補助金(福島県)
全国各地には、DX推進に活用できるさまざまな施策があります。気になる方は、お住まいの自治体へお問い合わせください。
なお、税額の控除を受けられる「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」は2025年3月31日で廃止されました。
DXに踏み切れない経営者の本音は「資金が足りない」です。自社に合った制度を自動で見つける「補助金AI(無料)」を使えば、悩みを解消するための一歩が踏み出せます。1日がかりの資料作成がわずか数分で終わる、そんな未来を補助金+DXで掴みにいきましょう。
補助金・助成金を使ったDX推進の流れ
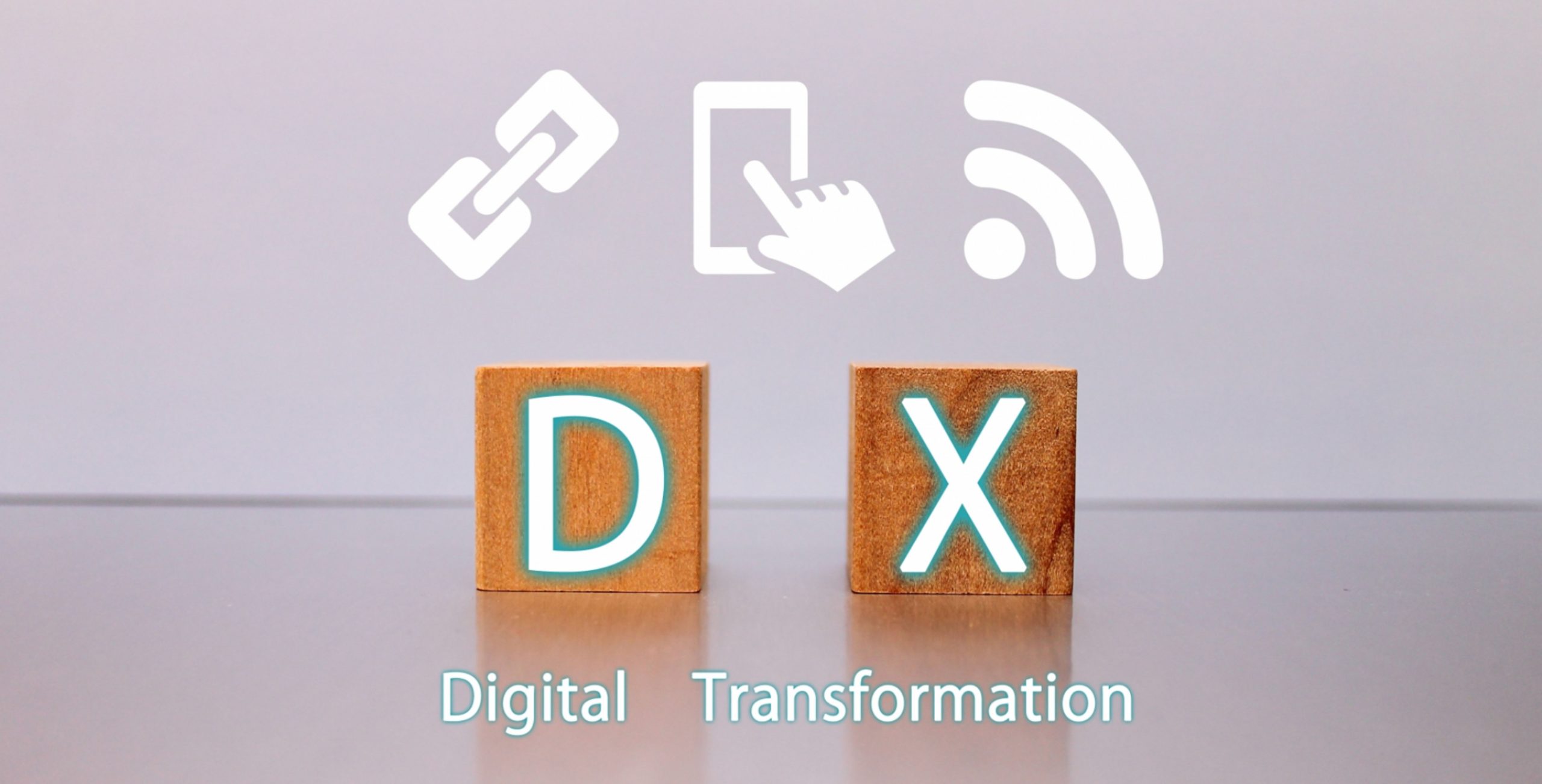
補助金や助成金を使ってDXに取り組むには、申請時期に合わせた計画的な進行が不可欠です。
具体的にどのような流れを想定しておけばいいのかを解説します。
1. やりたいDXが補助対象か確認する
自社で取り組みたいDXが補助対象になるか、補助金・助成金ごとに確認が必要です。
ハードウェアやソフトウェアなどのデジタルツール導入をどこまで支援してもらえるかは、制度によって異なります。研修費や外注費といった、取り組みの過程で生じる間接的なコストまで含めて確認しましょう。
自社ニーズが公募要領や事業の目的に合致しているかも照らし合わせ、どこで折り合いをつけるかがポイントです。
2. 資金繰りや導入のスケジュールを立てる
補助金や助成金の活用を前提としてDXに取り組む場合、適切にスケジュールを組む必要があります。
多くの補助金・助成金は「後払い」方式です。つまり、一旦は自己資金で立て替えなくてはなりません。制度の中には、交付決定前に事業に着手すると補助対象外になるものもあるため、注意が必要です。
制度の効果を最大化するためにも、DXの資金繰りと導入スケジュールとをセットで計画しておきましょう。
3. DXによる成果報告を行う
補助金や助成金を受け取るには、ほとんどの場合「成果報告」が必要です。導入したDX施策などが実際に効果を発揮したことを報告する義務があります。
業務時間の削減や売り上げアップなど、定量的な改善を証明するデータや記録を残しておきましょう。
申請前から成果の見せ方を意識してDXに取り組むと、成果報告がスムーズになり、補助金の支給まで滞りなく進みやすくなります。
DXに補助金・助成金を使う場合の注意点やポイント

DX推進に補助金・助成金を活用しようとお考えの方は、以下の内容に注意するほか、うまく活用するポイントも押さえておきましょう。
融資の必要性を考慮しておく
補助金や助成金は、原則として後払いです。DXに取り組む資金がない場合、一般的には融資を利用することになります。
融資は審査などのために3週間〜1カ月半程度の時間がかかるため、補助金の申請期日に間に合うよう前もって準備が必要です。また、資金繰りに無理が出ないように気をつけなければなりません。
期日に間に合わなかったり、資金繰りが悪化したりしては意味がなくなります。十分な計画を立てた上で、DX推進に制度をうまく活用しましょう。
事務処理にかかるコストも加味しておく
補助金・助成金は、税金を財源としていることもあり、支給にいたるまでに多数の書類の提出を求められます。事務処理は比較的わずらわしいものになると予想されるので、十分な時間と労力を確保しておくことが必要です。
事務処理がずさんだと、支給が受けられない恐れもあるので気をつけてください。場合によっては、人員体制を改めたり、通常業務が落ち着くタイミングを見極めたりといった工夫をするのも良いでしょう。
実際の事例を参考にする
DXは、他社の成功事例を参考に取り組むのがおすすめです。
例えば、経済産業省が選定した「DXセレクション2025」でグランプリに輝いた株式会社後藤組の場合、以下のようなことに取り組んでいます。
- ノーコードツールを用いた業務アプリの内製化
- 部、課、チーム単位で毎月1つのアプリ制作を義務付け
- 「DX大会」「DXワークショップ」など社員参加型の取り組みを開催
- 社内独自のDX資格制度と奨励金制度の設置
- 作業工程表やマニュアル、チェックリストの電子化
こうした取り組みにより、DXツールを使わざるを得ない環境を作ることで、デジタル化に対する抵抗感の抑制に成功しています。資料作成の時間を大幅に短縮するアプリを開発するなど、DXによる業務効率化も果たしました。
他社の成功事例をヒントに、補助金や助成金を活用して実現できるかも踏まえてDXの計画を練りましょう。
参考:経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025 (DXセレクション2025選定企業レポート)」
中小企業がDXをやるべき理由・メリット

DXにメリットが多いからです。DXを実現することで、中小企業は以下のようなメリットを得られます。
- 生産性が向上することで利益が上がる
- 効率化の実現によってコストを削減できる
- 新しい商材・サービス、ビジネスモデルを開発するきっかけになる
- テレワークや電子化などで働き方改革につながる
- DX推進事業者として企業の知名度が上がる
DXでは、データやデジタル技術を活用することによって、業務の生産性アップや効率化がもたらされます。それが売り上げやコスト削減に好影響を与え、利益が向上するでしょう。
そもそもDXは、商品やサービス、ビジネスモデルの開発、競争力の強化を目的とするものなので、DXの推進はそれの実現も意味します。
さらに経済産業省の「DX認定制度」や「DX Selection」をはじめ、DXを推進する中小企業を公表・表彰する取り組みも多々あります。そのため、DXに成功した企業は、知名度の向上やイメージアップといった恩恵を受けることも可能です。
DXの必要性として「DXを推進しない企業は生き残れないかもしれない」ということもいえます。昨今は、データやデジタル技術を活用した革新的なビジネスがどんどん成功するようになっています。もはやアナログ業務やレガシーシステム(古いシステム)だけで競争するのは難しいといえるでしょう。
この先10年、20年を見据えて企業の生存率を高めるために、DXに取り組むのもおすすめです。
DXにかかる費用の目安

DXにかかる費用項目や金額の目安を以下にまとめました。
| DX規模 | 費用項目の例 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 小規模 | ・クラウドサービス利用料 ・業務支援アプリの導入費 |
数万〜数十万円 |
| 中規模 | ・業務システムの刷新費 ・プロジェクト立ち上げ費 |
約100万〜500万円 |
| 大規模 | ・基幹システム構築費 ・AI、IoT機器の導入費 ・ITコンサル等の外部人材活用費 |
約500万〜数千万円 |
これらの総額がどれほどの金額になるかは、推進するDXの規模によって異なります。新しく業務システムを開発したり、ビジネスモデルを根本的に変えたりするのであれば、数百万円〜数千万円の規模になるでしょう。
一方、月額数千円で使えるクラウド型のITツールもあることから、限られた予算の範囲内で数万〜数十万の小規模なDXを目指すことも可能です。また費用負担は、後述の補助金・助成金をうまく活用することで、大きく軽減できます。
東京商工リサーチが2023年に行ったアンケート調査によると、DXに取り組んだ中小企業のうち、DX投資の予算は「500万円未満」が約4割となっています。また、今年度のDX投資の予算額に関する質問には「100万円未満」との回答が18.50%、「100万円以上500万円未満」が22.77%という結果です。
結果から、おおよそ500万円までをDX予算として見込んでいる中小企業が多いことがわかりました。
補助金や助成金の一般的な補助率・助成率を考慮すると、費用の半分ないし3分の2ほどが支給対象と想定されます。仮に予算500万円であれば250万円〜300万円が給付額の目安で、残りが自己負担額です。
あくまでも一般的な制度内容に当てはめたケースで、実際の支給率や上限額は制度ごとに変わるため、内容をよく理解した上で予算設計を行いましょう。
まとめ・補助金や助成金を活かして中小企業のDXを推進しよう
DXの推進には、ものづくり補助金やIT導入補助金などを活用できます。DXにかかる経費の多くを国や自治体に負担してもらえるので、コストを抑えて会社を変革することが可能です。
DXを推進し、競合より優位に立つには、補助金や助成金が充実している今がチャンスだといえます。これを機会にぜひ、補助金・助成金を活用したDXについて前向きに検討してみてください
補助金を使えばよかった……と後悔する前に、今すぐ「補助金AI(無料)」で業種・地域・目的に合った支援策を受け取りましょう。DXに使える制度を自動で通知するので、探しに行く手間はいりません。公開からわずか数日で200万インプレッションを超えた、話題のツールです。
創業手帳では、補助金の基本や最新情報、申請のコツなどがわかる「補助金ガイド(無料)」を提供しています。詳しくは以下のバナーからどうぞ。


(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。