【2026年版】会社設立のやること・流れ・費用をチェックリストで完全解説
【保存版】会社設立の流れを設立準備から登記後まで解説|初心者でも安心の完全ガイド

・株式会社設立には最低18万円程度の費用が必要
・合同会社なら最低6~7万円程度で設立可能
・設立には定款認証や登記など複数の手続きが必要
・設立後も税務署や年金事務所への届出が必須
・税制優遇や資金調達で個人事業主より有利
会社設立は手続きが多く複雑に感じるかもしれませんが、正しい手順を踏めば誰でも設立できます。
この記事では、創業手帳創設者・大久保の実体験をもとに、会社設立の全手順を初心者にもわかりやすく解説します。設立準備から完了後の手続きまで、必要な情報をすべてまとめました。
忙しい方は目次から必要な箇所をクリックしてお読みください。
創業手帳では、「起業をしたいけど何から始めればいいかわからない」という方に、『創業カレンダー』を無料でお配りしています。創業日を書きこめば、その前後に何を準備しておく必要があるのかカレンダー方式でわかるものになっています。是非あわせてご活用ください。
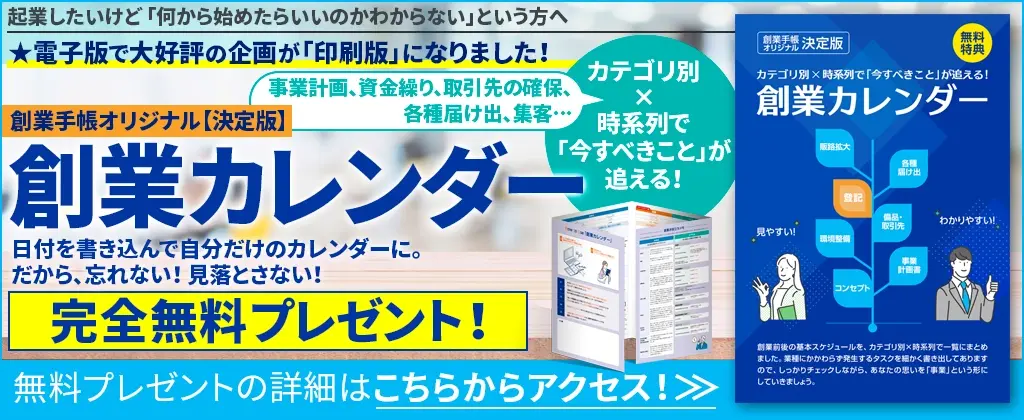

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
会社設立とは?やることの全体像を把握しよう
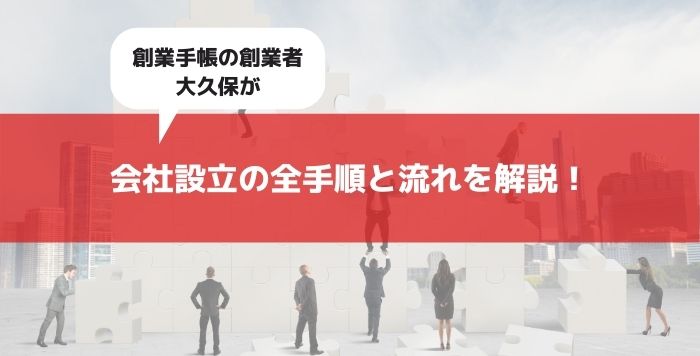
事業を始める方法には、「個人事業」と「法人(会社)」の2種類があります。
会社設立とは、このうちの法人を新たに立ち上げることを意味します。法人格を持つことで、契約の履行や取引の責任を“会社”として担えるようになるのが特徴です。
事業が大きくなったり、人を雇うようになったりすると、自然と法人化を検討するタイミングが訪れます。
「手続きが難しそう」「リスクが大きいのでは?」と不安に感じる方も少なくありませんが、実際には法人化によって個人のリスクを抑え、挑戦しやすい環境を整えられるという側面もあります。
法人化には、会社の基本ルールとなる「定款」の作成・認証や、法務局での登記、資本金の準備など、いくつかのステップが必要です。
また、税務申告や会計処理なども、個人事業より手間がかかるのは事実です。
それでも、会社という形を整えることで社会的な信用力が高まり、取引先から信頼される存在になれるという大きな利点があります。
会社設立は、「個人事業から一歩進んで、本格的なビジネスを展開するためのステップ」と言えるでしょう。
法人化の主なメリット
法人化には、次のような3つのメリットがあります。
1. 信頼性の向上
法人は社会的な信用が高く、取引先や金融機関からの評価も上がります。
大企業や行政との取引では「法人であること」が前提になるケースが多く、ビジネスチャンスを広げることにつながります。
2. 節税効果
法人化すると経費に計上できる範囲が広がり、所得分散による税負担の軽減も期待できます。
さらに、一定の条件を満たせば各種の税制優遇措置を受けられる場合もあります。
3. 資金調達のしやすさ
法人になると、銀行融資や補助金、投資など、多様な資金調達手段を利用できるようになります。
信用度が高まることで、将来的な事業拡大もしやすくなるでしょう。
会社設立とは、単に法人格を得ることではなく、事業をより大きく、安定的に成長させるための重要な一歩です。
「信頼」「節税」「資金調達」という3つの観点から見ても、法人化には多くの価値があります。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【設立前】会社設立までの準備・やることリスト

ここからは、実際に会社を設立する流れについて解説していきます。
初めてのことばかりで戸惑うかもしれませんが、こちらの記事を確認しながら実行していけば問題ありません。
創業手帳の場合、準備から会社設立までに要した期間は、3週間程度でしたので、大体1カ月くらいかかると想定しておきましょう。
設立前の流れ5ステップ
会社設立の全体像をつかむには、まず大まかな流れを理解することが大切です。
以下の5つのステップを押さえておけば、必要な作業や手続きの順番が明確になります。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1:基本事項の決定 | 商号(会社名)、本店所在地、資本金、役員報酬額などを決定。 | 類似商号がないか法務局で確認。不正競争防止法にも注意。 |
| 2:定款の作成・認証 | 会社の基本ルールを定めた「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける。 | 絶対的記載事項(商号・事業目的など)の漏れに注意。電子定款なら印紙代4万円が不要。 |
| 3:資本金の払込み | 定款認証後、自分名義の口座に資本金を振込む。 | 通帳コピーを保存し、払込証明書を作成。1,000万円超は初年度から消費税課税対象。 |
| 4:登記書類の作成 | 登記申請に必要な書類一式を作成・製本する。 | 書類形式や添付書類の不備に注意。すべてA4サイズに統一。 |
| 5:法務局への登記申 | 資本金払込後2週間以内に法務局へ登記申請。 | 提出日が「会社設立日」になる。郵送の場合は到着日が基準。 |
5つの流れを把握しておけば、全体のスケジュールが立てやすく、抜け漏れの防止にもつながります。
費用の目安
定款認証は公証役場、法人登記は法務局で行います。
会社設立には、手続きごとに費用が発生しますが、あらかじめおおよその金額を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
| 区分 | 主な費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 公証役場 | 定款認証手数料:1.5〜5万円 印紙代:4万円 |
合同会社は定款認証不要。電子定款なら印紙代不要 |
| 法務局 | 登録免許税: 株式会社15万円~、合同会社6万円~ |
資本金額により異なる |
| その他 | 印鑑作成費、証明書発行費など | 1〜3万円程度 |
株式会社を設立する場合、実費の総額は最低18万円程度~設立できます。
一方、合同会社を選ぶと手続きが簡略化され、6~7万円程度まで費用を抑えることが可能です。
これらの費用は会社の種類や手続き方法によって変動するため、事前に見積もりを立てておくことが大切です。
会社設立の効率化ポイント
会社設立の手続きは、慣れていないと想定以上に時間がかかるでしょう。公証役場での定款認証や法務局への登記申請では、書類不備による差し戻しもよくあります。
また、印鑑作成や資本金の払込みなど、各工程には待ち時間も発生します。余裕を持って1カ月程度のスケジュールを確保し、慌てずに準備を進めることが成功のポイントです。
余裕を持ったスケジュールを立てる
登記前後に複数の機関での手続きが発生するため、想定より時間がかかるケースもあります。全体で1カ月程度を目安に計画を立てると、トラブルが起きても柔軟に対応できます。
オンライン申請を活用する
定款申請は電子定款で行うことも出来ます。紙の定款より手続きがスムーズで、印紙代4万円を節約できる点が大きなメリットです。電子化により、公証役場への持ち込みや修正対応もスピーディになります。
また、法人の登記申請もインターネットで行うことも可能です。株式会社の場合、代表取締役本人のマイナンバーカードの読み取りが必要なため、ICカードリーダライタの用意が必要ですが、一部の添付書類の提出が不要になるメリットもあります。
専門チェックリストやテンプレートを利用する
チェックリストやテンプレートを使えば、手続き漏れを防げます。
特に初めて会社を設立する人にとっては、書類の順序や提出先を明確に把握できる有効な手段です。
創業手帳では会社設立に使えるチェックリストも無料で配布しています。司法書士などプロが使っているチェックリストを参考にして作成しました。
創業手帳の無料会員に登録後、その他の役立つテンプレートもダウンロードできるのでご活用ください。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【設立後】登記完了後に必要な届出・手続き・やることリスト

会社設立が完了してひと休みしたいところですが、会社設立後にもいくつかの手続きを行わなければなりません。
POINT
・会社設立後の手続きは「印鑑カードの交付を受ける」「税務署への届出/申告」「社会保険関係の手続き」の3つがある
印鑑カードの交付を受ける
会社設立手続き時に届出を行った「印鑑カード」の交付を受けておく必要があります。印鑑カードは、会社の印鑑証明書の取得時に法務局の窓口で提示するものです。
交付を受けるには、法務局で「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に持参します。
銀行口座の開設など、会社の設立時にはなにかと印鑑証明書が必要になります。数枚まとめて発行しておくと便利です。
また、法務局に行った際には、まとめて用事を済ませておくことをおすすめします。印鑑証明書と一緒に「登記簿謄本の取得」もしておきましょう。発行には印鑑証明書のように印鑑カードなどは必要ありません。
こちらも会社設立後の手続きや口座開設などで必要になるため、5枚ほど取得しておくと時間の節約になります。
税務署への届出/申告
法務局での手続きが完了したら、次は会社の所在地を管轄する税務署へ届出を行いましょう。会社には様々な税金がかかるため、会社設立後の手続きの中でもっとも重要な手続きといえます。
届出に必要な書類はおもに次の6つです。
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
通常は、1〜4の提出で間に合いますが、不明な点は税務署の窓口でしっかりと確認しましょう。
必要な書類に記入・押印したらコピーを1部ずつとり、税務署に持参します。税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。
都道府県税事務所・市町村役場への届出も忘れずに
税務署への届出が完了したら、都道府県税事務所、市町村役場への届出も行います。税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のものを提出すればOKです。
税務署の窓口で設立届出書の用紙を受け取った場合には、複写式になっているので、2枚目以降を自治体に提出するだけで大丈夫な場合もあります。
また、税金関係は起業直後だけでなく、経営していく上で重要なイベントとなります。
社会保険関係の手続き
そして最後に「社会保険関係の手続き」をします。会社設立時に資金の関係で加入していない会社は多いのですが、加入は義務づけられています。
最初にまとめて手続きしてしまった方が楽なので、一気に終わらせてしまいましょう。
| 手続き場所 | 内容 |
|---|---|
| 年金事務所 | 厚生年金、健康保険 |
| 労働基準監督署 | 労災保険 |
| ハローワーク | 雇用保険 |
年金事務所
たとえ社長1人の会社であっても「社会保険」には加入する必要があります。厚生年金は「日本年金機構」、健康保険は「全国健康保険協会」が運営しています。
日本年金機構の事務所である年金事務所では、健康保険の加入手続きも一括で行うことが可能です。
労働基準監督署
ここでは「労災保険」の加入手続きを行います。ただし、従業員がいない場合には加入の必要はありません。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)では、「雇用保険」への加入手続きを行います。こちらも従業員が居ない場合には加入する必要はありません。
もし従業員が入ってきたら、すぐに手続きを行なうようにしましょう。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【準備品チェック】設立後に用意しておきたいツール・書類

ここまでは、会社設立の公的な手続きなどについて解説しました。しかし、そういった手続き以外でも、会社設立にあわせて用意しなければならないものがあります。
会社設立前、会社設立後それぞれの段階で用意しておいた方がよいものをご紹介します。
会社設立前に用意しておきたいもの
会社設立後にあわてないためにも、登記の準備とあわせて用意しておいた方がよいものがいくつかあります。登記後すぐに営業・PR活動ができるように、以下のものは優先的に準備しておきましょう。
- 企業ロゴ
- 名刺
- ホームページ
- 挨拶状
- 会社概要チラシ
- 営業資料
- 経営管理体制
>>起業後に絶対必要なもの7選! 起業前から準備したら失敗なし!
会社設立後に必要になるもの
「会社設立が終わって、一安心!」ではなく、いざ営業が始まれば必要なものがたくさん出てきます。会社設立後に必要となるものを3つご紹介します。
各種契約書
会社運営では人を雇ったり、取引先と契約を結んだりと、様々な場面で契約書が必要となります。急いで用意する必要はありませんが、なるべく早めに用意しておくとよいでしょう。
- 雇用契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書
- オフィス賃貸契約書
各種契約書の書き方を知りたい方は、下記の記事で確認しておきましょう。
>>【保存版】会社設立後に必要になる「契約書」をまとめました
法人用銀行口座・クレジットカード
法人登記をしたら、個人用の銀行口座やクレジットカードを使うというわけにはいきません。
会社や個人事業主の経費処理のポイントは、法人と個人のお金の出入りをしっかりと分けることです。法人向けカードを使うことで、お金の出入りを分けられるほか、カード会社が発行する明細が経費処理に使えるので経費の管理にも便利です。
法人用の口座開設には手続きの上で注意するポイントがあるので、そういったことを知っておくことも大切です。
また、会社設立当初はクレジットカードの審査に通りにくい場合もありますが、なかには設立して1カ月で審査を通すことができるものもあります。どういったカードが審査に通りやすいのかも把握しておきましょう。
オフィス関係
個人事業主から法人成りした方は、自宅にオフィスを構えてしまう場合も多いですよね。
いざ仕事を開始すると、商談場所に困ったり、プライベートとの区別がつかなくなり、オフィスを構えたくなるものです。
しかし、オフィスを構えるといっても、会社設立直後はあまりお金が無いと思います。
そんなときには「コワーキングスペース」がおすすめです。借りる人や目的によって一長一短ありますが、どんなものか知っておいて損はないはずです。
一定の期間だけ契約しておきたいという方は「シェアオフィス」もよいでしょう。オフィスを他者とシェアして使う形になるので、費用の負担をかなり抑えることができます。
また、一般的な賃貸契約を結ばずに、もっとシンプルな形で利用したい方は「レンタルオフィス」も検討してみてはいかがでしょうか。費用はかさむけれど、最初から落ち着けるオフィスで仕事がしたい方は「賃貸オフィス」も有効な選択肢の1つです。
自宅で仕事を行う場合であっても、揃えたほうがよいものはたくさんあります。冊子版の創業手帳では、起業する際に必要なアイテムのチェックリストや、会社設立のためのチェックシートを掲載しています。見逃してしまいがちな項目がありますので、ぜひ目を通してみてください。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
会社設立前に知っておきたい基礎知識5点
こちらでは、会社設立前に知っておきたい基礎知識を5点ご紹介しておきます。
1.起業初期に使える助成金/補助金は主に4種類
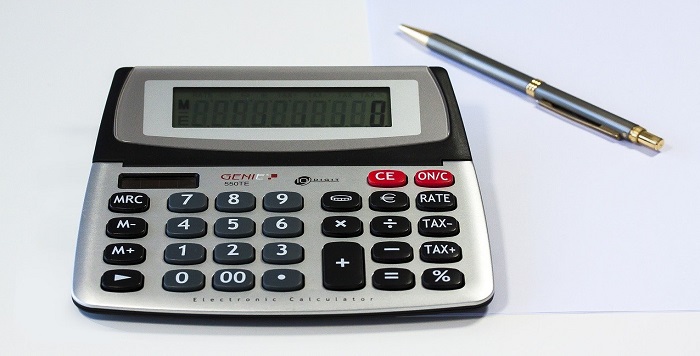
起業したばかりのときに使える助成金や補助金には、下記の4つがあります。
・ものづくり補助金
・小規模事業者補助金
・キャリアアップ助成金
それぞれの補助金・助成金については、下記の記事で詳しくご紹介しています。
キャッシュフロー健全化のためにも、返す必要のないお金があれば、積極的に活用しましょう。
創業手帳の別冊、補助金ガイド(無料)でも、最新の補助金・助成金について詳しく解説しています。
また補助金AI(無料)では、たくさんある補助金・助成金情報の中で、ご自身にあったものをメールで情報をお届けします!情報の取りこぼしをせずに補助金・助成金を活用することが可能です。
2.株式会社と合同会社はどちらを選ぶべき?
会社設立時に多くの起業家が迷うのが、「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶかです。結論から言うと、以下の基準で選ぶのがおすすめです。
| 項目 | 株式会社が向いている | 合同会社が向いている |
|---|---|---|
| 費用重視 | - | 設立費用を抑えたい |
| 信頼性重視 | 取引先・融資で信頼が欲しい | - |
| 経営スタイル | 将来的に上場・投資を検討 | 自由度の高い経営がしたい |
| 事業規模 | 大規模事業・BtoB中心 | 小規模・個人向けビジネス |
ちなみに筆者は出資を検討していたので、資金調達と信頼性においてメリットがある株式会社を選択しました。
主な違いと特徴
株式会社と合同会社は、主に以下のような違い・特徴があります。
株式会社: 出資者(株主)と経営者(取締役)が分離。出資比率に応じて議決権が決まり、将来的な資金調達や上場が可能
合同会社: 出資者自身が経営を行う。出資比率に関係なく経営の自由度が高く、迅速な意思決定が可能
設立費用・手続きの違い
設立の手続きで最低かかる費用と設立期間を表にしました。合同会社の方が8万円安く、定款認証が無い分、数日早く設立できるでしょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 最低設立費用(合計) | 18万円〜 | 6万円〜 |
| 定款認証 | 必要(1.5〜5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
| 設立期間 | 2週間〜 | 1週間~ |
法人設立の登記を電子認証することで、印紙代4万円が無料かつ、問題がなければ基本的に24時間以内の認証が可能です。合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要はないので、その分費用も抑えられて期間も短く済みます。
ただし、書類作成などの準備や修正に時間が掛かることもあると考えられるので、期間に余裕を持って対応することが大切です。
それぞれに向いている事業・人
株式会社、合同会社におすすめの事業や人をご紹介します。
| 株式会社がおすすめ | ・大企業との取引がメイン ・将来的に株式上場や投資家からの資金調達を検討 ・金融機関からの融資を積極活用したい ・許認可が必要な事業 |
| 合同会社がおすすめ | ・設立費用を抑えて早期に事業開始したい ・飲食店や美容室など屋号重視の事業 ・フリーランスの法人化 ・迅速な意思決定を重視する小規模事業 |
迷った場合は将来のビジョンで判断しましょう。 小規模で始めて徐々に拡大予定なら合同会社、最初から大きな成長を目指すなら株式会社がおすすめです。
3.会社設立を専門家に依頼するメリットとは?

POINT
・会社設立は税理士だけではなく、様々な専門家に依頼するメリットがある!
・各士業に依頼するメリット・デメリットを確認しておこう
「会社設立」=「株式会社」とイメージする人が多いように、「誰に手続きを頼もうか?」と考えたとき、真っ先に税理士が頭に浮かぶ人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には税理士だけではなく、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった様々な専門家に依頼することができます。それぞれの専門家に依頼するメリット・デメリットを表にまとめてみました。
| 士業名 | メリット |
|---|---|
| 税理士 | ・税務関係の届出の作成や提出を代行してもらえる ・税金を抑えたいときに相談できる ・会社設立後の会計記帳や決算、申告などがセットになっている場合もあり、費用が安く抑えられる |
| 社労士 | ・会社設立後の社会保険、厚生年金、雇用保険の加入手続きと一緒に依頼できる ・助成金の手続きも一緒に依頼できる |
| 司法書士 | ・法人の登記手続きを代行してもらえる(司法書士にしかできない) ・会社設立だけ依頼する場合は報酬4万円以下と一番コストが抑えられる |
| 行政書士 | ・建設業、運送業、飲食業などの業種では許認可手続きを一緒に依頼できる |
より詳しく各士業のメリット・デメリットについて知っておくことで、より選択しやすくなるでしょう。
筆者は税理士と司法書士に会社設立を依頼しました。創業手帳では、税理士や司法書士など専門家を無料でご紹介しております。ぜひご利用ください。
会社設立の基礎知識をまとめたガイドブック(無料)は必読です!⇩
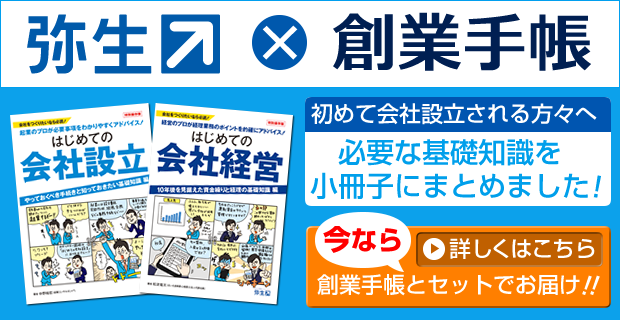
4. 会社と個人事業主はどちらがお得か
起業時に多くの方が迷うのが、「個人事業主として開業するか、最初から会社を設立するか」という選択です。ここでは税金面や信用度の違い、法人化を検討すべきタイミングについて解説します。
基本的な違いと判断基準
まずは個人事業主と法人の基本的な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 開業手続き | 開業届のみ(無料) | 登記申請(6〜15万円程度) |
| 税金 | 所得税、住民税、個人事業税など | 法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税など |
| 信用度 | 低い | 高い |
| 経費範囲 | 限定的 | 幅広い |
法人化を検討すべきタイミング
多くの起業家が採用するのが「個人事業主でスタート→利益800万円を超えたら法人化」というパターンです。初期費用を抑えて事業をスタートし、成長に応じて最適なタイミングで法人化できます。
始めは個人事業主からスタートする方も少なくありません。個人事業主から法人化への切り替えを検討すべきタイミングは主に3つあります。
・年間利益800万円超:法人税の方が税負担が軽くなる
・年間売上1,000万円超:法人化で消費税が最大2年間免除
・信用力が必要:大企業取引や融資を検討する場合
5.一人で会社設立する際の費用と注意点
「一人でも会社は設立できるの?」という疑問をお持ちの方も多いですが、一人でも会社設立は可能です。ここでは一人で会社を設立する際の具体的な費用や手続き時の注意点について解説します。
一人会社設立の費用
一人で会社を設立する場合の具体的な費用を会社形態別に比較してみましょう。
| 会社形態 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 最低費用(合計) | 18万円~ | 6万円~ |
| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
| 定款認証 | 1.5~5万円 | 不要 |
上記のほか、電子定款の認証でない場合は印紙代4万円、実印作成、印鑑証明や資本金などが必要です。
一人会社設立時の注意点
一人で会社を設立する際に特に注意すべきポイントをご紹介します。事前に把握しておくことで、スムーズな設立手続きが可能になります。
1.資本金の設定
資本金1円も可能ですが、初期費用+運転資金3か月分程度は用意しておくのがおすすめ。資本金1,000万円未満で設立すれば、設立から2年間は消費税の納税義務が免除されます。
2.社会保険の義務
法人は従業員の有無に関わらず、厚生年金・健康保険への加入が必須です。
3.電子定款の活用
電子定款を利用すれば印紙代4万円を節約でき、合同会社なら約6万円で設立可能になります。
手続きに時間をかけたくない場合や専門知識に不安がある場合は、専門家への依頼も有効な選択肢です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
会社を設立する際に注意したいこと
会社設立にはあらゆるメリットがありますが、注意すべき点もあります。
メリットを生かすためにも、次の4点に気を付けて進めましょう。
赤字であっても納税が必要
個人事業主は赤字の場合、住民税は非課税ですが、法人住民税は納税しなければなりません。
なぜなら法人住民税の均等割は、資本金・従業員数によって課税されるからです。
会社とプライベートの財布は分ける
会社を設立したあとは、会社の預金と個人の預金をはっきりと分けて、別々に管理します。
代表者がひとりの会社も事業用口座を早めに開設し、事業資金とプライベートのお金を区別しましょう。
法人口座で資金を分けて管理すると、会社の信用につながります。
会社設立は早くても2週間は必要
会社設立には提出する書類が10種類あり、提出できる状態にする準備期間も必要です。
登記完了までに2週間はかかるため、それ以上余裕を持って設立を進めましょう。
設立にかかる法定費用は、株式会社設立で約22万円以上、合同会社設立では約10万円以上です。
法定費用の他に資本金などの準備も必要なため、設立したい会社の種類によって資金調達の期間も考慮し、事業開始時期を決めましょう。
会社の解散にともなう手続きがある
個人事業は廃業届を出すのみですが、会社を解散するには所定の手続きがあります。
解散するために、解散・清算人選任登記と清算結了登記が必要で、それぞれ登録免許税を納めます。
ちなみに解散・清算人選任登記は、解散登記が3万円、清算人選任登記が9千円で、清算結了登記は2千円です。
加えて会社が解散したことを、官報へ解散公告として掲載しなくてはなりません。
掲載費用は4万円程度です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
まとめ・会社設立の流れを把握して成功率をあげよう!
会社設立は、事業を拡大し夢を実現するための大切な第一歩です。手続きは多いものの、流れを正しく理解すれば着実に進められます。
税制面のメリットも活かしながら、慎重かつ前向きに準備を進めていきましょう。
また、創業手帳オリジナル創業カレンダーでは、日付を書き込んで会社設立の必要な手続きや手順が自分だけのスケジュールで把握できるようになっています。会社設立の流れを把握できるようになっており、こちらも無料でのご提供になりますので、ぜひご活用ください。
会社設立の基礎知識をまとめたガイドブックを無料プレゼント中!⇩
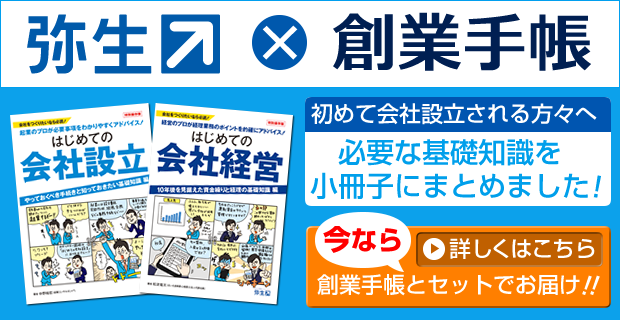
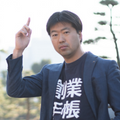 創業手帳・創業者の大久保が会社設立登記の6つのポイントを解説
創業手帳・創業者の大久保が会社設立登記の6つのポイントを解説
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。


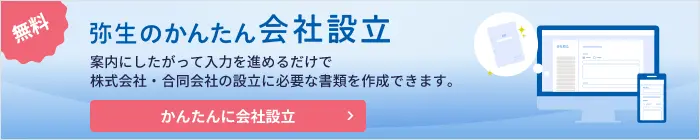









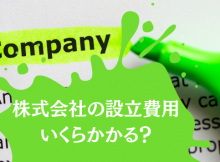

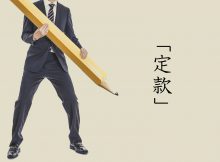























下記の6つはよく間違えるのでチェックしておきましょう。
1・登記簿謄本・印鑑証明書は何通必要?
登記完了時の登記簿謄本・印鑑証明書は銀行用など6通程度必要になることが多いです。
会社の証明書で何かと求められるので、多めに取得しておくことをおすすめします。
また、登記の際の発起人は印鑑証明書が2通、発起人ではないが役員になる方は、印鑑証明書が1通必要となります。
印鑑証明書は発行から3か月以内なので、発行日付に注意しましょう。
2・建物名、部屋番号は登記簿に記載する?
建物名、部屋番号は登記簿に記載しないのが一般的です。ビル名変更や部屋番号が変わった場合、登記変更が必要というデメリットがあります。
3・事業内容はどこまで書く?
事業内容は定款変更をしなくて済むように広めに書いておくのが一般的です。また、「前各号に付帯関連する一切の業務」と入れておくのがちょっとしたコツで、一般的なのでおすすめです。
なぜかというと隣接しているような仕事をせざるえない場合が出てくるので、その時に「付帯する一切の業務」という文言が効いてきます。
4・1株いくらにするべきか?
1株あたりの金額は1万円や5万円にすることも多いですが、ストックオプションなどで細かく分割して配布することを考える場合は、やや小さめにしておいたほうが扱いやすいです。
決算期(会社の開始から終わりをどうするか)ですが、日本では4月1日で始まって3月末で締めるパターンが最も多いです。他にも年単位(1月1日から12月31日まで)、もしくは多い期に合わせると税理士や公認会計士の繁忙期に当たるので、あえてそれを避けるケースもあります。印象では結構、事業を始められる最短で設定するケースが多いので思ったよりバラける印象です。
5・株の譲渡について
株式会社では、譲渡制限のありなしをつけるケースがあります。
株式を第三者に譲渡する際に会社の承認を必要とする規定のことで、設立時には「あり」が多いです。
要は勝手に株式を不都合な人に売られたくないですよね。それを避ける条項です。
6・取締役、監査役はどうしたら良い?
承認機関として株主総会、取締役の過半数、取締役会、代表取締役などがありますが、基本的には株主総会が承認機関となります。
ただ、上場を目指すなどの場合、取締役会設置会社にするケースが有り、譲渡制限なしの場合は設置が義務です。
設置する場合は取締役3名、監査役1名が必要です。
しっかりした体制を目指す場合は取締役会設置会社にしますが、個人経営的なコンパクトな体制の場合は必ずしも取締役設置会社にする必要はないです。
ややこしいのですが、取締役3名+監査役1名以上が取締役設置会社の要件ですが、取締役会設置会社でなくても、取締役は必要になります。
また、監査役は会社の安定性確保のために任期が長めの原則4年になっています。取締役は原則2年です。
取締役は任期途中で必ずしも辞めさせることができない場合があり揉めるケースがあるので割と短めにしておくのがおすすめです。
ただ、再任が面倒などで長くする場合があり、譲渡制限ありの場合は最長10年になります。
創業手帳では、こうした会社設立チェックシートや定款雛形も創業手帳と一緒に無料で配布しています。
無料登録後、会員画面のマイページ「お役立ち無料テンプレート」からダウンロードし放題なのでぜひ使ってみてくださいね。