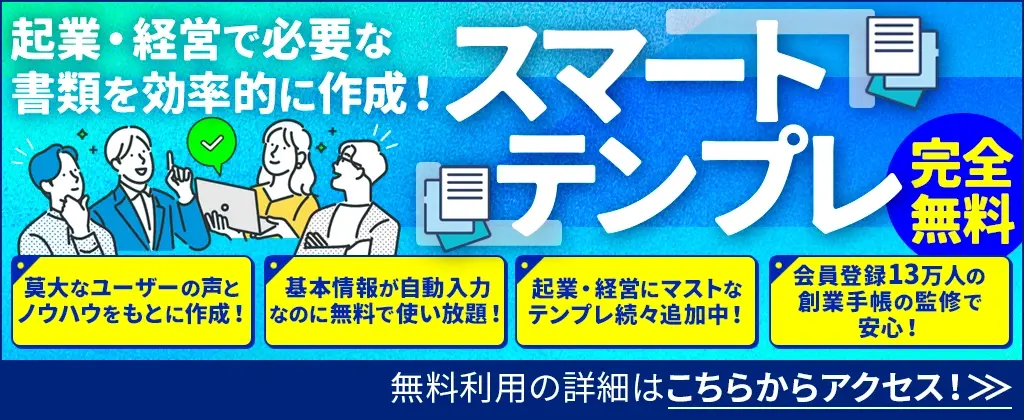会社設立する時の定款の書き方や注意点などを解説
株式会社を設立する時の、正しい定款の書き方・記載事項とは
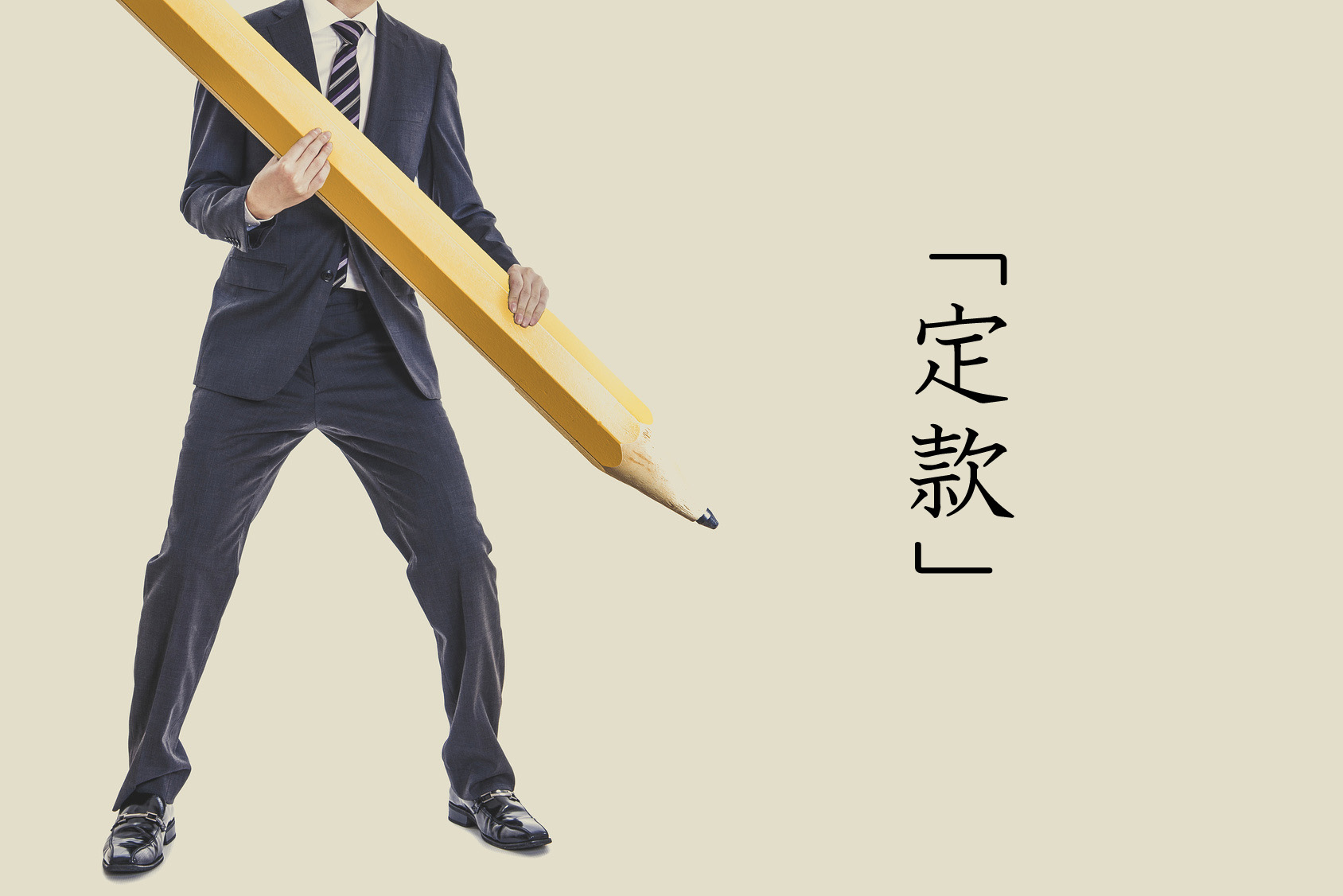
●定款の役割と3種類の記載事項(絶対的・相対的・任意的)
●会社名、事業目的、本店所在地など重要な要素の記載方法
●記載ミスが引き起こす費用や手間を避けるための対策
●公証役場やインターネットで定款を認証する手続き方法
●取締役会の設置や会社形態による手続きの違い
会社設立において「定款」は避けては通れません。会社の事業内容や目的など、重要な事柄を記載した文書です。
この記事では、起業・開業時に作成すべき定款について、基本の書き方を項目ごとに解説しています。定款の書き方を誤ると、余計な費用や手間が発生する恐れがあるため、慎重な作成が必須です。
注意点も押さえて定款作りをマスターし、円滑にスタートアップしましょう。
また、創業手帳では、「定款ひな形」など会社設立後に重宝する各種テンプレをご用意しました。無料会員登録するとダウンロードできますので、ぜひご活用ください!
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
定款とは
「定款」とは、会社設立時に必ず作成するもので、会社の事業目的、構成員など様々な項目で成り立つ、会社の基本的な規則が記載された文書を指します。
ネットで検索すればひな形もたくさんあり、穴埋めするだけで簡単に定款の作成が可能です。ただし、この方法で出来上がるのは、あくまで基本形です。会社設立後の運営をスムーズに進めるためには、本当に必要な事項、適切な事項が記載されている定款が求められます。
定款の記載事項とは
定款の記載事項には、次の3つがあります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
それぞれ何を意味し、何を記載すればいいのか、概要や注意点を解説します。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、名称の通り定款への記載が絶対に必要な項目です。以下の項目があげられます。
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 発起人の住所氏名
絶対的記載事項に書き漏れや不足があれば、定款として意味をなしません。定款の効力も左右する可能性があるため、確認を徹底してください。事業内容に違法性が認められる場合も無効となります。
発行可能株式総数を書く場合もありますが、設立登記申請までに定款へ記載すればよいため、まずは5つの要素を押さえておきましょう。
絶対的記載事項について、さらに詳しくみていきます。
商号
絶対的記載事項のうち、最初に決めるのは商号=会社名です。商号をつける際には注意点があります。
- 同じ所在地に同じ商号の会社がないか
- 商標登録されている商品名がないか
- 有名企業と同じ会社名ではないか
1については法務局の「商業調査簿」で調べられ、3は「特許電子図書館」のホームページでチェックできます。
2についてはインターネットで検索しましょう。「不正競争防止法」にあたるものであれば使用できないので、きちんと調べることを心がけてください。
事業目的
次に考えるべきことは「事業目的」です。あなたの会社が何をしている(していく)会社なのかを記載する必要があります。注意すべきポイントは次の4つです。
- 許認可の要件を満たすように書く
- 予定のある事業目的だけ書く
- 事業目的によっては融資が難しいものを把握しておく
- 営利性のある目的を書く
許認可の必要な事業の場合、定款の事業目的を見られる可能性があります。記載がなければ許認可が下りない可能性があるので注意が必要です。誰が見てもわかりやすいよう、予定している事業のみを記載しましょう。
3に関しては、例えば「金融業」「遊興娯楽事業」「風俗営業業種」などが事業目的に入ると、金融機関からの融資が受けにくくなるケースがあります。
また事業目的は、営利性がないものは避けてください。営利性のないものにはボランティア活動や慈善団体への寄付などがあげられます。
本店所在地
本社の住所を指す「本店所在地」も、絶対的記載事項です。自宅兼事務所、賃貸店舗などを用いるケースが多く、最近はバーチャルオフィスも普及しています。
定款の本店所在地をバーチャルオフィスにする場合は、法人口座の開設の際に金融機関からNGが出るかもしれません。バーチャルオフィスを本店登記している法人口座は、振込詐欺などの犯罪に多用されるためと考えられます。
資本金額
定款に書く「資本金額」は、会社設立における出資額と同じです。出資財産の総額をそのまま書くか、○○円以上といった記載もできます。
発起人の住所氏名
会社の設立に関わった発起人の住所と氏名を書きましょう。主に出資者が該当します。発起人が複数人いる場合、全員分の住所氏名を書いてください。
相対的記載事項
絶対ではないものの、必要に応じて記載すべきなのが相対的記載事項です。何らかの効力を持たせたい事項を記します。相対的記載事項は書いていなければ無効となるため、注意してください。
取締役会や監査役会の設置についてや、株式発行に関する取り決めなどは、相対的記載事項の一例です。
法律の範囲内で、会社として定めておきたい決まりごとや規範があれば、相対的記載事項として定款に記載しましょう。
任意的記載事項
定款の任意的記載事項は、記載の有無によって定款やその内容の効力が左右されない要素です。定款に書いていなくても無効にはならず、定款以外で定めることもできます。
任意的記載事項の例は、定時株主総会の招集時期や取締役の員数などです。違法ではない任意的記載事項なら、書くのも書かないのも自由となります。
定款の書き方・作り方
定款の書き方・作り方を具体的に解説します。絶対的記載事項など漏れなく記載すべき事項に注意し、定款を作成していきましょう。
また、創業手帳会員になると、定款を始め、様々なテンプレート(雛形)をダウンロードする事が可能です。是非この機会にご登録ください。
最初の記入事項
実際に書き進めていきましょう。定款の最初に書く事項は2つです。
会社名の記入
株式会社の定款を例に作成していきます。冒頭の「株式会社○○○○定款」という部分に、会社名を入れてください。
作成日の記入
次に下記に作成日を記入しましょう。下の2つの記入は不要です。
令和○年 ○月 ○日 作成
令和○年 ○月 ○日 公証人認証
令和○年 ○月 ○日 会社設立
定款の条文を記入
定款の条文を書いていきましょう。通常は記載事項ごとに以下のような章立てをし、章の内容に沿って条文を作成します。
- 第一章 総則:商号・事業目的・本店所在地・公告の方法など
- 第二章 株式:発行可能株式総数・認証機関など
- 第三章 株主総会:招集手続きの省略・決議など
- 第四章 取締役:取締役任期など
- 第五章 計算:事業年度など
- 第六章 附則:一~五章以外の記載事項
今回は一例に沿って、条文の書き方を解説します。実際に何を定款に含めるかは、任意で調整してください。
第一章 総則:商号・事業目的・本店所在地・公告の方法
最初は「総則」です。商号や事業目的など絶対的記載事項を中心に記載します。
第1条 当会社は,株式会社○○○○○と称する。
上記○の部分に、会社名を入れてください
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
(1) 例:飲食店の経営
(2) ○○○○○○○○○○
(3) ○○○○○○○○○○
(4) ○○○○○○○○○○
(5) ○○○○○○○○○○
(6) 全各号に附帯又は関連する一切の事業
例を参考に、事業目的を入れてください
第3条 当会社は,本店を○○に置く。
上記○の部分に、本店住所を入れてください
第4条 当会社の公告は,官報公告により行う。
公告方法を入れてください。例として「官報公告」と記載しています。
「公告」とは、債権者や取引先などに大きな影響を与える事項を、広く一般に知らせることをいいます。これは法令上義務付けられており、違反すると100万円以下の罰金があります。
第二章 株式:発行可能株式総数・認証機関
つぎは「株式」に移ります。株式会社ならではの記載項目です。
第5条 当会社の発行可能株式総数は,1,000株とする。
例の数字を入れていますが、自社で定める発行可能株式総数を入れてください。
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには,株主総会の承認を受けなければならない。
認証機関を入れてください。例では株主総会としていますが、「取締役会」「代表取締役」などと定めることもできます。
第三章 株主総会:招集手続きの省略・決議
続いて「株主総会」に移ります。株主総会の規定について、定款に記します。
書面投票、電子投票の制度を利用しているときは、招集手続きの省略ができません。
「決議の省略(簡略化)」をしている場合、招集手続を省略してしまうと、株主の意思表示の機会を奪うことになりかねないからです。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
株主総会の議決の「出席した当該株主の議決権の過半数」は、過半数以下に下げて定めることもできます。ただし、役員選任の決議は3分の1未満に下げることはできません。
また、会社法第309条第2項に定める決議とは特別決議を指します。
第四章 取締役:取締役任期
「取締役」に関する事項です。代表取締役の場合もここに書きましょう。
第7条 取締役の任期はその選任後○○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
上記○の部分に、取締役の任期を入れてください。通常は2年、非公開会社であれば10年まで延長が可能です。
第五章 計算:事業年度
「計算」の記載事項です。決算の指標となる事業年度などを書きます。
第8条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年○月○日から翌年○月○日とする。
上記○の部分に、事業年度を入れてください。
第六章 附則:決算日・発起人の氏名・住所・株式数
「附則」では、五章までに掲載していない規定を書きます。今回は決算日や発起人にまつわる情報などの記載例です。
第9条 当会社の設立後の資本金の額は,金500万円とする。
例として500万円としていますが、実際の資本金額を入れてください。
第10条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から令和○年○月○○日までとする。
(設立時の役員)
第11条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は,次のとおりとする。
設立時取締役 ○○○○
同 □□□□
設立時代表取締役 ○○○○
(発起人)
第12条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。
住所 ○県○市○町○丁目○番○号○○○
氏名 ○○○○ 250株 金250万円
住所 ○県○市○町○丁目○番○号○○○
氏名 □□□□ 250株 金250万円
(法令の準拠)
第13条 この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他法令に従う。
以上,株式会社○○○○の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名押印する。
令和○年○月○日
発起人 ○ ○ ○ ○ ㊞
発起人 □ □ □ □ ㊞
㊞ ㊞ ㊞
それぞれ発起人の氏名、住所、株式数などを入れてください
創業手帳では会社設立後に役立つ「定款ひな形」などの各種テンプレートを提供しています。無料会員に登録するだけでダウンロードが可能ですので、ぜひこの機会にご利用ください!
定款を書く際の注意点
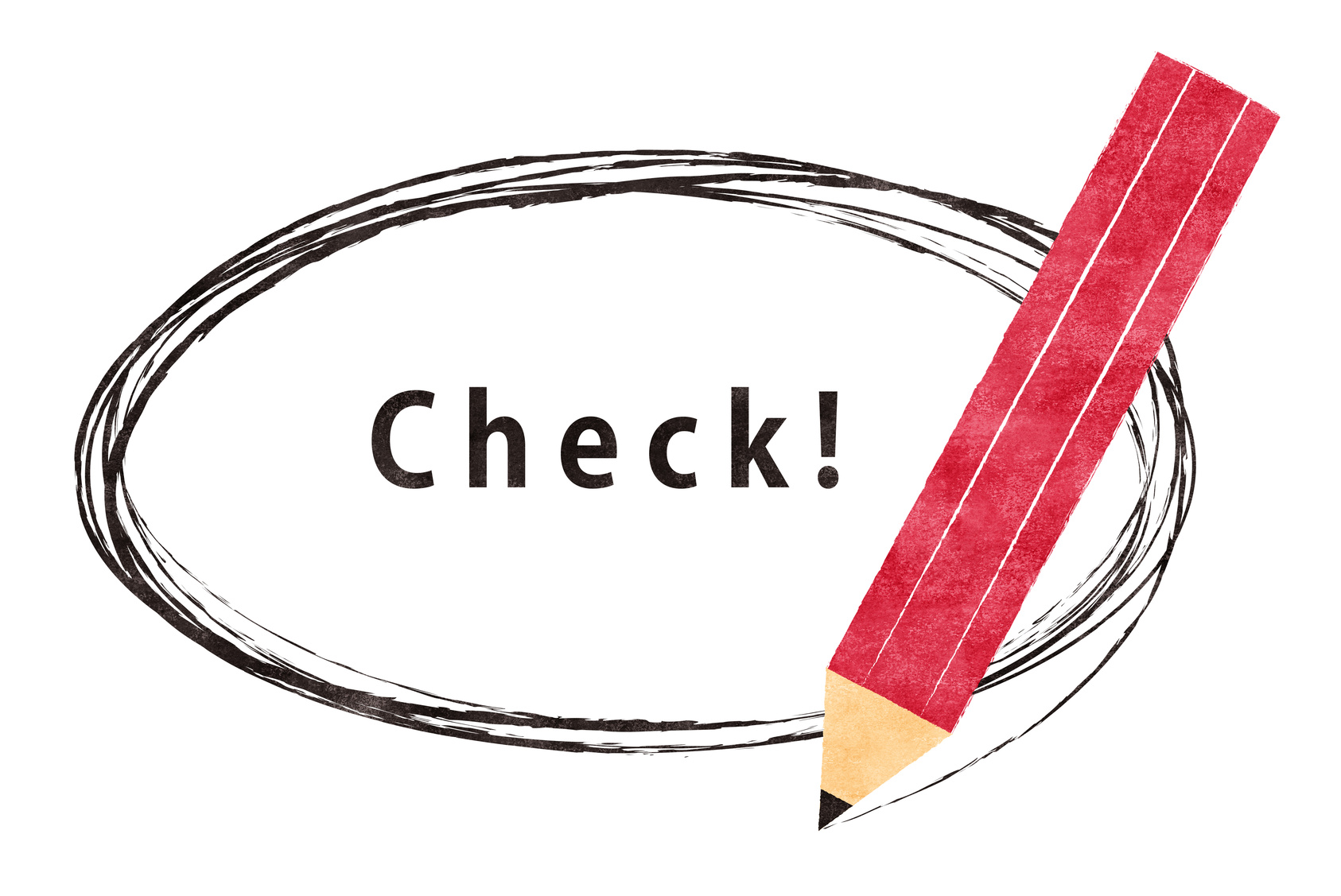
ネットで検索すればひな形がたくさん出てくるので、穴埋め程度で基本の定款が出来上がってしまいます。しかし、ひな形はあくまでひな形。会社にピッタリ合った定款を作ることが求められます。
次の注意点を押さえた上で定款を作り、自分の会社に適した内容に仕上げてください。
後からの変更には費用がかかる
後から定款の内容を変える場合、登録免許税として3万円が必要です。本店の移転を伴うときにはさらに3万円かかり、計6万円の出費となります。
変更手続きに伴う手間も含め、余計な費用をかけないためにも、定款を作る前に内容の精査を徹底しておきましょう。最低限決めておくべきことや作成方法を理解し、必要な事項が網羅されている定款を作ることが大切です。
会社ごとに手続きや作り方が違う
定款は、会社設立のパターンによって手続きや作り方が違います。
例えば株式会社の場合、定款を作成しただけでは効力を生じません。公証役場での手続きが必要になり、これを認証といいます。しかし合同会社の場合には、定款を作った時点で効力が生じます。
自分の会社形態と定款の手続き・作り方を確認の上、正しく把握しておきましょう。
取締役会を置くか・置かないかを考えておく
取締役会の設置について定款にも記載します。公開会社には取締役会を置くことが義務付けられており、設置には3人以上の取締役が必要です。非公開会社であれば設置の義務はありません。
取締役会を設置した場合には、さらに監査役を置く必要があります。意思決定を取締役会だけでできるので、取締役がきちんとその役割を果たしているのかどうかを監視する必要があるからです。
取締役会を置かない場合には、監査役を置くかどうかは任意となります。通常は置きません。
取締役会を設置すると、株主総会を待たずに決議できるようになり、経営スピードが上昇するメリットがあります。デメリットは取締役や監査役における人員の確保です。
特徴を理解した上で設置・非設置を検討しましょう。
定款の提出方法
株式会社の場合には、定款作成で終了ではありません。提出をもって、公証役場での「認証」が必要になります。定款認証時に必要な基本の準備物は下記の通りです。
- 定款(印刷したものを合計3部、または電子データで用意)
- 発起人全員の印鑑証明書(原本を各1枚)
- 身分証明書
- 収入印紙(4万円分)
- 発起人の実印(発起人以外は認め印でよい)
- 各種手数料(資本金額によって※3~5万円+定款謄本発行手数料約2,000円/部)
- 代理人による申請の場合には委任状
※2022年に改定。更に、法務省は12月からの最低手数料を現行3万円から1万5,000円に引き下げる予定。
電子定款の場合、収入印紙は不要です。必要なものを準備して、認証手続きを進めましょう。
主な提出方法は下記の2つです。
公証役場に出向く
直接公証役場に出向き、定款認証を受ける方法です。アナログながら、確実に提出して認証を受けられる方法となります。
公証役場に出向く場合の具体的な流れも押さえておきましょう。
公証役場に予約を入れておく
会社の本店所在地を管轄する公証役場に、必ず予約を入れておきます。自分の地域の公証役場は、日本公証人連合会のホームページから確認可能です。
予約していない場合、定款の認証手続きができません。書類などの準備とあわせて忘れずに予約しておきましょう。
公証役場にて認証手続きをする
準備物を持参の上、公証役場にて認証を受けます。基本的にはすべての発起人の参加が理想です。
用意した3部の定款のうち、1部は公証役場の控えとなり、2部は戻ってきます。1部は次の手続きである登記申請用、残りの1部が会社保管用で、原始定款という位置づけの書類です。
原始定款は、会社設立後に行う税務署への開業届、銀行口座の開設手続きなどに必要になるので、大切に保管しておきましょう。
大きな不備がなければ、公証人による確認後に認証が完了します。その場で修正が難しい不備があった場合、改めて認証手続きが必要となるため、準備を万全にしてから訪問してください。
インターネット上で認証を受ける
電子定款であれば、インターネット上から認証手続きが可能です。紙で作成した後にPDF化し、電子署名を入れておきます。一連の処理には電子証明書つきのマイナンバーカード、ICカードリーダライタが必要です。
電子認証の準備が整ったら、手続きに進んでください。
メールやFAXで電子定款を送る
作成した電子定款をメールやFAXで公証役場に送り、内容を確認してもらいます。この際に不備がないかチェックが入り、問題がなければ次の手順へと進みます。
事前登録を済ませ認証手続きを行う
電子定款の認証は総務省のオンラインシステムから行いますが、利用には事前登録が必要です。利用者情報の登録を済ませた後、専用ソフトをダウンロードして電子定款の認証申請をしましょう。
公証役場にて電子定款を受け取る
電子定款の場合でも、認証後の定款を受け取るには公証役場に直接出向かなくてはなりません。予約を入れた上で訪問してください。
予約時に必要な持参物を確認し、電子データを受け取れるよう準備してから向かいましょう。
まとめ・定款の基本的な書き方、作り方や内容を把握しておこう
定款は会社設立時に必ず必要となります。記載すべき事項を把握し、基本的な書き方を身につけておきましょう。
株式会社や合同会社などの設立形態によって、必要な手続きが異なります。手間や費用にも差が生じるため、事前に確認してから作業を進めてください。
適切な定款を用意しておけば、問題が起こった際も定款に基づいて対応が可能です。後から変更の必要がないように、内容の精査も十分にした上で作っておきましょう。
また、創業手帳では、会社設立後に大変便利な「定款ひな形」など各種テンプレートを利用できる「スマートテンプレ(無料)」をリリースしました。基本情報の自動入力機能や、各文書の解説などもございます。ぜひご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。