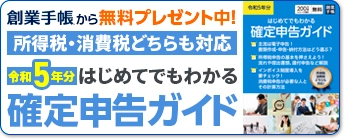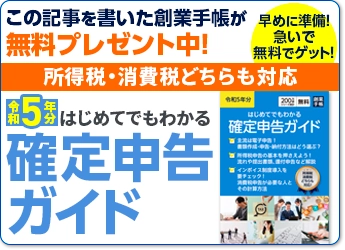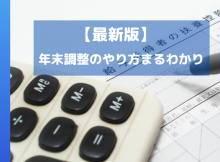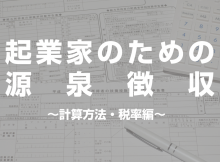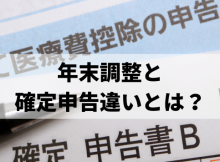退職後に確定申告はするべき?必要・不要なケースやメリットなどを解説
退職後に確定申告が必要になるケースがあるため注意

働いていた職場を辞めた後、確定申告が必要になるのか気になる方もいるでしょう。退職後に確定申告が必要かどうかは、状況によって異なるため注意が必要です。
確定申告を放置すると、ペナルティの対象となる恐れがあります。
今回は、退職後に確定申告が必要になるケースと不要なケースを紹介し、必要な書類・申告の流れについて解説します。
創業手帳では、確定申告の基本から解説した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。どのような場合に確定申告が必要になるのかから、今年の変更点などについても解説。ぜひこちらもあわせてご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
退職後に確定申告が必要となる8つのケース
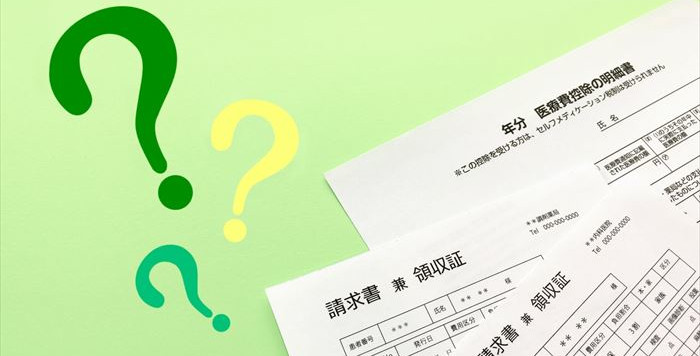
退職後には年末調整を受けられません。そのため、確定申告をすることになりますが、退職後に確定申告が必要かどうかは人によって異なります。
退職後に確定申告が必要となる8つのケースは以下のとおりです。
転職先で年末調整をしていない場合
退職後にほかの企業へ転職したものの、年末調整をしなかった場合は確定申告の対象です。
年度の途中に退職すると年末調整を受けられない状態となります。
転職後に年末調整を受けられなかった場合には、自分で確定申告を行わなければなりません。
また、アルバイトを複数掛け持ちしている場合も注意が必要です。給与所得が2ヵ所以上あっても、年末調整を受けられるのは1ヵ所のみとなります。
アルバイト・副業を複数していたり、新しい職場で年末調整が受けられなかったりした場合も確定申告が必要です。
年度の途中で退職して再就職しなかった場合
年度の途中で退職して再就職しなかった場合には自分で確定申告をしなければなりません。
また、再就職をしない人は収入が少なくなることもあるため、今まで給料から天引きされていた所得税を払い過ぎている可能性があります。
払い過ぎた分の還元を受けるためには確定申告が必要です。
退職後に個人事業主・フリーランスになった場合
退職後に個人事業主やフリーランスとして働く人は確定申告の対象です。
例えば、年度の途中で退職してフリーランスに転向した場合、年末調整を受けていない状態になります。
企業への転職であれば、新しい職場で年末調整を受けられる可能性がありますが、個人事業主・フリーランスには年末調整がありません。
そのため、会社員の時の給与所得と事業所得の2種類の所得を獲得していることになります。
給与所得に対する税金は源泉徴収されていますが、事業所得分は自分で納めなければならず、確定申告が必要となるのです。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職をする際に、退職金を受け取ることがあります。退職時に退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には確定申告が必要です。
退職金にも所得税と住民税がかかります。退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、退職金を支給される際に税金が源泉徴収されるので、確定申告は不要です。
反対に、退職所得の受給に関する申告書を提出せずにいると、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれます。
確定申告をすれば、払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。
公的年金の収入合計が400万円以上の場合
退職後に公的年金を受け取る場合に、公的年金の収入合計が400万円以上となると確定申告が必要です。
国民年金や厚生年金などの公的年金は、受給額が一定以上であれば所得税が源泉徴収されます。
公的年金に対して年末調整はされないため、過不足がないか求めるために確定申告が必要です。
なお、確定申告不要制度によって、公的年金の収入合計が400万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、400万円以上の収入がある人は制度の対象とはならないため、確定申告をすることが求められます。
公的年金以外の所得を20万円以上受け取っている場合
退職後に公的年金を受け取る人の収入が400万円以下であっても、公的年金以外の所得が20万円以上あれば確定申告不要制度の対象から外れます。
公的年金以外の収入には、以下のものが挙げられます。
-
- アルバイト・パートの給与所得
- 個人年金
- 株式の配当金
- 生命保険の満期保険金
など
上記のような所得が合算して20万円以上あれば、確定申告をしなければなりません。
各種所得控除を利用したい場合
所得税の負担を抑えるために、様々な控除制度があります。退職後に各種所得控除を受ける時も確定申告が必要です。
各種所得控除には、以下のものが挙げられます。
-
- 医療費控除(年間で負担した医療費が10万円以上の場合)
- 寄附金控除(ワンストップ特例を使わずふるさと納税した場合)
- 生命保険料控除(退職後に支払った医療保険・生命保険の保険料)
- 雑損控除(盗難や災害による損害を受けた場合)
- 配当控除(株式の配当を受けた場合)
- 外国税額控除(外国株式の配当があった場合)
- 住宅特定回収特別税額控除(特定のマイホーム改修工事を行った場合)
など
これらの控除により税金の還付を受けるのであれば、忘れずに確定申告をしてください。
退職後に不動産所得や事業所得などで赤字が発生した場合
不動産の貸付けや事業経営によって不動産所得や事業所得などを得ており、退職した年や退職後に赤字が出た際は確定申告が必要です。
確定申告をすれば、退職所得によって赤字を相殺する損益通算ができます。
損益通算をすることで、所得税の負担を軽減できる可能性が高いです。
なお、給与所得や配当所得、雑所得と損益通算をして相殺できない赤字がある時に限り、退職所得との損益通算ができます。
退職後に確定申告が不要な2つのケース

退職後に確定申告が不要なケースもあります。続いては、確定申告が不要な2つのケースを紹介します。
年末調整や所定の手続きを済ませてから退職した場合
年末調整や所定の手続きを済ませた上で退職していれば、基本的に確定申告は不要です。会社と雇用契約を結んでいる間は、10月~翌年1月にかけて年末調整をしてもらえます。
年末調整を行えば、その年に源泉徴収された所得税の過不足が調整された状態になるため、確定申告をする必要がありません。
また、退職金を受け取った際に退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、退職所得に対する所得税の確定申告は不要です。
基本的には、会社側から退職所得の受給に関する申告書の提出を求められます。確定申告の手間を省きたい時は忘れずに提出してください。
再就職先で年末調整ができる場合
退職した年に転職・再就職するケースで、新しい職場で年末調整を受けられるのであれば確定申告は不要です。
新しい職場に前の職場から受け取った源泉徴収票を提出することで、まとめて年末調整をしてもらえます。
ただし、医療費控除や寄付金控除などの一部所得控除は年末調整の対象外となるため、適用する場合は確定申告をしてください。
退職後の確定申告に必要な書類と申告の流れ

今まで確定申告をしたことがない人は、手続きに不安を抱えているものです。ここでは、確定申告に必要な書類や申告の流れを紹介します。
確定申告に必要な書類
確定申告を行うにあたっては、申告書の作成や添付に必要な書類を集めなければなりません。
人によって用意するべき書類は異なりますが、主に必要となる書類は以下のとおりです。
-
- 確定申告書
- マイナンバーを確認できる本人確認書類
- 銀行口座番号や名義がわかるもの
- 申告する年分の所得を証明できる書類(給料所得や公的年金などの源泉徴収票、事業などの収入・必要経費がわかる書類)
- 各種控除証明書
確定申告書は、税務署・市区町村の窓口で受け取ったり、国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)や確定申告ソフトからダウンロードしたりして入手できますが、税務署に連絡して郵送してもらう方法もあります。
印刷や電子申請が可能であれば、確定申告書等作成コーナーや確定申告ソフトを活用するのがおすすめです。
なお、確定申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
また、窓口で確定申告書を提出する際は、身元や番号を確認できる書類が必要です。マイナンバーカードがあれば十分といえます。
さらに、還付金は指定した銀行口座に振り込まれるため、預金通帳といった口座番号や申告者本人の名義を確認できるものが必要です。
ほかにも、申告の根拠を示す所得を証明できる書類、各所から郵送される所得控除証明書も準備してください。
退職後の源泉徴収票はいつ、どこでもらう?
確定申告を行うと、1月から12月の1年間の給与明細の合計所得税額から源泉徴収税額を差し引いた金額が還付されます。
そのため、確定申告書を作成する際には、源泉徴収票が必要になります。
退職後に源泉徴収票が必要になった場合、前の職場に依頼すれば発行してもらうことが可能です。
確定申告のステップ
確定申告の流れは以下のとおりです。
1.確定申告書を作る
確定申告に必要な書類を集めたら、確定申告書の作成を開始してください。
手書きの書類でも問題ありませんが、手間をかけたくない時には確定申告ソフトを利用したり、国税庁のホームページにある確定申告書等コーナーで作成したりすることがおすすめです。
PCとスマートフォンを使える確定申告書等コーナーであれば、必要事項を入力するのみで確定申告書を作成できます。
確定申告書等コーナーは、無料で利用できる点が大きなメリットです。
自分で確定申告書を作ることに不安があったり、時間が取れなかったりする際は税理士に依頼するのもひとつの手段です。
税理士に報酬の支払いが必要ですが、プロが適切な申告書を作成してくれます。 確定申告書の作成手段は、人によって最適な方法が異なります。
自分に合う方法を選んでください。
2.所轄の税務署に書類を提出する
確定申告書が完成したら、申告する年の翌年2月16日~3月15日までに所轄の税務署に提出をしてください。
書類を提出する方法には、以下の3つの手段があります。
-
- 窓口
- 郵送
- オンライン
税務署の窓口であれば、その場で書類の不備がないか確認してもらうことが可能です。
なお、確定申告の期間は混雑する傾向にあり、予約しないと対応してもらえないこともあります。また、開庁時間に訪れなければ手続きできない点に注意が必要です。
郵送であれば、ポストに投函するだけなので手間なく提出ができます。
確定申告書の控えを受け取りたい時は、切手を貼った返信用封筒を同封しなければなりません。
なお、現在はe-Taxを使ってインターネットから気軽に確定申告書を提出することが可能です。
利用者識別番号の取得や電子証明書の発行などの手間がかかりますが、窓口への訪問や郵送の手間を省けます。
添付書類の提出を簡略化できたり、比較的還付金を早く受け取れたりすることもメリットです。
3.税金の納税や還付を受ける
確定申告を行えば、税金の納税や還付を受けられます。納めなければならない所得税を計算して、不足していれば納付書を使って納税をしてください。
現金で納付する場合の期限は3月15日であるため、確定申告と納税は早めに行いましょう。
現金納付が面倒な時は、納付期限に自動的に所得税が届け出た銀行口座から引き落とされる振替納税がおすすめです。
振替納税の場合、例年4月下旬頃に引き落としされるため、納税資金の準備に猶予がほしい時にも適しています。
反対に、税金を払い過ぎている場合には還付を受けられます。還付されるまでの期間には個人差がありますが、1~2カ月程度で届け出た銀行口座に入金されます。
なお、電子申告であれば、2~3週間程度で還付金を受け取ることが可能です。
退職後の確定申告をし忘れたらどうなる?

確定申告の対象でありながら、期限内に手続きや納税を行わなかった場合、ペナルティの対象となることに注意してください。
申告義務を怠った場合、行政制裁として以下の附帯税が課せられます。
| 無申告課税 | 3月15日までに確定申告をしなかった場合、15~30%の附帯税が課せられる |
| 延滞税 | 期限内に申告をしても、所得税の納税を怠ると2.4%または8.7%の附帯税が課せられる |
| 重加算税 | 事実の隠ぺいなどで所得の過小申告や無申告など、悪質と判断された場合に35%または40%の附帯税が課せられる |
課税割合は状況によって異なりますが、本来支払う税金額よりも多くなってしまうため、金銭的な負担が発生します。
ほかにも、住民税が未納付になったり、住宅ローンや事業用資金の申し込みなどで必要となる所得証明書を発行できなくなったりします。
これらのペナルティを回避するためにも、確定申告の対象となる際は忘れずに確定申告を行ってください。
まとめ・退職後の確定申告で払い過ぎた税金を取り戻そう
年度の途中で退職して個人事業を始めたり、再就職先で年末調整が行われなかったりする場合は自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告をすれば、払い過ぎた分の税金が戻ってきます。
確定申告の対象でなくても、各種所得控除の適用や公的年金の収入額などによっては確定申告が必要です。
退職する際に、自分が確定申告の対象かどうかを確認しましょう。
創業手帳では、確定申告の基本から解説した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。どのような場合に確定申告が必要になるのかから、今年の変更点などについても解説。ぜひこちらもあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)