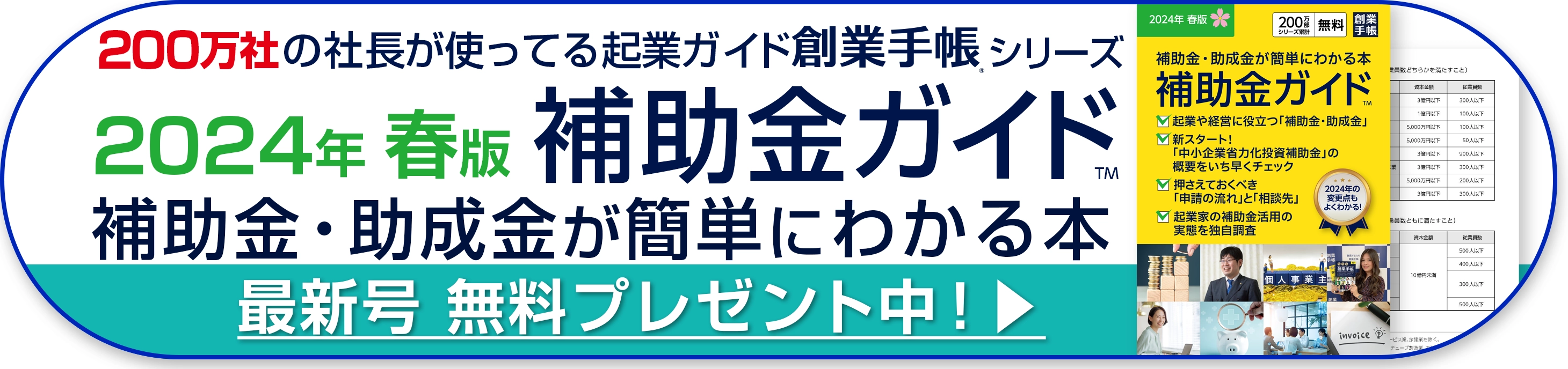【2026年最新】個人事業主が使える給付金まとめ|返済不要の補助金・助成金など一覧
個人事業主が利用できる給付金とは?対象者や申請期限に注意して申請を
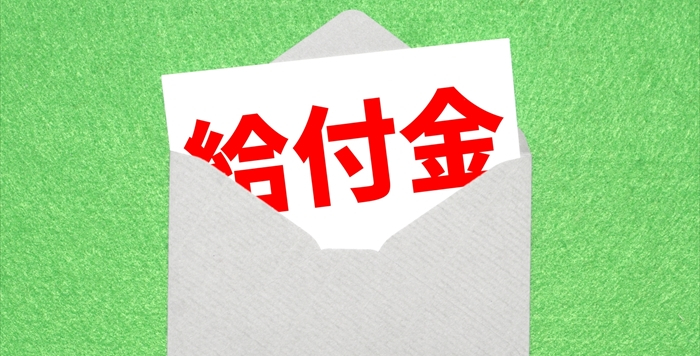
- 個人事業主・フリーランスが利用できる給付金の種類
- 各給付金の申請条件や金額、活用できるシーン
- 各給付金受給のメリットと注意点
- 個人の生活支援に役立つ公的制度
個人事業主やフリーランスが利用できる「給付金」は、制度ごとに条件や対象が異なり、自分が使えるものを見つけにくいのが現状です。
この記事では、給付金(補助金・助成金を含む公的支援)の中から 個人事業主でも申請できる制度だけを整理し、特徴や注意点をまとめて紹介します。
事業への投資に使える制度はもちろん、個人事業主の生活面を支える支援まで幅広く解説しているため、今の状況に合う制度を比較しながら確認可能です。
気になる支援制度が多く、どれが自分に当てはまるのか判断が難しい場合は、「補助金AI(無料)」を使うと条件に合う制度が自動で届きます。
申請の基礎を短時間で把握できる「補助金ガイド(無料)」も併用すると、手続きの準備がスムーズです。

 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主・フリーランスが申請できる給付金一覧

個人事業主・フリーランスが申請できる給付金(補助金・助成金も含む)には以下のようなものがあります。
| 制度名 | 給付額の規模 | 個人事業主視点でのポイント |
|---|---|---|
| 中小企業新事業進出補助金 | 最大9,000万円 | 申請要件等が厳しい傾向、入念な準備が不可欠 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大200万円(一般型通常枠) | 小規模向けで最も現実的 |
| IT導入補助金 | 最大450万円(通常枠) | IT化を進める個人と好相性 |
| ものづくり補助金 | 最大4,000万円 | 事業計画の作りこみなど、念入りに準備が必要 |
| 事業承継・M&A補助金 | 最大1,150万円 | 活用場面が限定的 |
| 雇用調整助成金 | 休業手当・賃金の一部を助成 | 従業員を雇っている場合のみ |
※“給付額”とは制度によって補助上限額・助成額を含む概算です
それぞれの給付金には、条件や申し込みの期限が定められており、当てはまらない場合には申請できません。
対象となる条件や期限を吟味し、利用できるものをピックアップしてみましょう。
中小企業新事業進出補助金(2026年度からものづくり補助金と統合予定)
中小企業新事業進出補助金は、新規事業への挑戦を行う個人や中小企業をサポートする補助金です。
新しい商品やサービスの開発、既存分野とは全く異なる新市場への参入などを狙う個人事業主にとって、大きな資金調達の手段になり得ます。
2026年度(令和8年度)からは「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり補助金」が統合される予定です。 統合後は「新事業進出・ものづくり補助金」(仮称)として、新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善、新市場への挑戦を一括して支援する枠組みに一本化される見通しです。
第3回公募(締切:2026年3月26日)までは現行制度が適用されますが、それ以降の申請を検討している場合は、統合後の新要件に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 | 750万~3,000万円(従業員数20人以下の場合) |
| 公募・申請期間 (目安) |
公募回数:年3~4回 申請受付期間:2~3カ月 |
| 最新回 | 第3回公募申請受付期間:2025年12月23日(火)~2026年3月26日(木)18:00 |
| 活用例 |
|
基本的には従業員数によって補助上限額が変わり、個人で経営している事業主の場合は20人以下の規模の金額に当てはまります。
機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが対象経費に含まれる必要があるため、事業計画を練る上でしっかり組み込んでおきましょう。
参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業新事業進出補助金」
小規模事業者持続化補助金
今後の制度変更などに対応し、販路開拓や生産性向上に取り組む小規模事業者のための制度が小規模事業者持続化補助金です。
一部の申請枠では「インボイス特例」や「賃金引き上げ特例」などの要件を満たすと補助上限額が上がります。
対象者は小規模事業者なので、個人事業主も利用可能です。
ここでは、幅広い個人事業主が活用しやすい「一般型通常枠」の概要を紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 | 50万~200万円(一般型通常枠) |
| 公募・申請期間 (目安) |
公募回数:年3~4回 申請受付期間:2~3カ月 |
| 最新回 | 第19回公募申請受付期間:2026年5月頃~2026年6月頃 |
| 活用例 |
|
一般型通常枠には、免税事業者からインボイス発行事業に転換する事業者を対象に50万円を上乗せする「インボイス特例」や、事業場内最低賃金を50円以上引き上げる事業者を対象に150万円を上乗せする「賃金引き上げ特例」もあります。
ほかにも、これから事業を立ち上げる人向けの「創業型」、複数の事業者が参画して取り組む「共同・協業型」などがあるため、状況に応じて活用を検討してください。
参考:小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第18回公募 公募要領」
デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)
 デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)は、ITツールやAIソリューションの導入費用の一部を補助する制度です。パソコンやタブレットなどのハードウェア、会計ソフトといったソフトウェアに加え、AI機能を搭載した最新の業務効率化ツールの導入費用やクラウド利用料(最大2年分)も補助対象となります。
デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)は、ITツールやAIソリューションの導入費用の一部を補助する制度です。パソコンやタブレットなどのハードウェア、会計ソフトといったソフトウェアに加え、AI機能を搭載した最新の業務効率化ツールの導入費用やクラウド利用料(最大2年分)も補助対象となります。
通常枠(デジタル化支援)のほか、インボイス対応枠、セキュリティ対策推進枠、そして新たに強化されたAI導入・DX推進枠などが用意されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 補助額 | 5万~450万円(複数社連携枠を除く) |
| 公募・申請期間
(目安) |
公募回数:未定
申請受付期間:順次開始予定 |
| 最新回 | 未定 |
| 活用例 |
|
通常枠の補助額を例に紹介すると、1プロセス以上につき5万円以上150万円未満、4プロセス以上で150万円以上450万円以下が補助の範囲となります。補助率は原則1/2以内ですが、最低賃金引き上げに取り組む事業者は2/3以内に引き上げられます。
参考:中小企業庁「生産性向上を目指す皆様へ「デジタル化・AI導入補助金」でIT導入・DXによる生産性向上を支援!」
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金・2026年度から中小企業新事業進出補助金と統合予定)
ものづくり補助金は、個人事業主や小規模事業者が制度変更に対応するためのさまざまな取り組みを支援する制度です。
生産性の向上を目的としたプロダクトの開発や事業の省力化に際し、必要な設備投資等の費用を給付してもらえます。
ものづくり補助金は、2026年度(令和8年度)より「中小企業新事業進出補助金」と統合される予定です。今後は、新製品開発と新市場開拓をより一体的に支援する枠組みへと移行します。2025年度中の公募については現行通りの内容で実施されますが、次年度以降の申請を検討されている方は、統合後の新要件に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 | 100万~4,000万円 |
| 公募・申請期間 (目安) |
公募回数:年2~3回 申請受付期間:1~4カ月 |
| 最新回 | 22次公募期間:2025年10月24日(金)~1月30日(金)17:00 |
| 活用例 |
|
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は電子申請が必要です。申請に使うGビスIDアカウントは発行に一定期間がかかります。
交付が決定したら、計画に基づいた事業の実施と実績報告もしなくてはなりません。要件未達成の場合は補助金の返還義務があるため、事前の計画を入念に立てましょう。
参考:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事務局「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領 (第22次公募)」
事業承継・M&A補助金
個人事業主が事業を引き継いだり、売却したりするときに使えるのが事業承継・M&A補助金です。事業を引き継ぐ側、譲渡する側のどちらも利用できます。
事業の承継・統合・再編の支援により経済の活性化につなげることが制度の主な目的です。
「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠から、状況や用途に応じて申請できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 | 100万~1,000万円(廃業費上乗せ額+150万円以内) |
| 公募・申請期間 (目安) |
公募回数:年2~3回 申請受付期間:約1カ月 |
| 最新回 | 13次公募期間:2025年10月31日(金)~11月28日(金)17:00 |
| 活用例 |
|
申請枠によって補助対象の範囲や経費が異なります。例えば「専門家活用枠」の枠であれば、M&Aの仲介業者やアドバイザーを利用した費用などが対象です。
事業承継をきっかけに新商品の開発や販路拡大を狙う個人事業主は、活用を検討しましょう。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、労働者に支払う休業手当を助成する制度です。
事業の縮小にともなってやむを得ず休業してもらうなどの場合に、労働者を雇用する事業者に給付されます。教育訓練や出向にかかった費用も助成の範囲です。
企業はもちろんのこと、従業員のいる個人事業者も対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 | 休業手当負担額、賃金負担額の相当額に2/3を乗じた額(1人あたり上限8,870円/日) ※教育訓練実施率や教育訓練加算額による変動あり |
| 申請期間 | 常時 |
| 活用例 |
|
先に雇用調整の計画策定と計画届の提出を行い、調整が実施されてから申請する流れです。休業や教育訓練など、自社に必要な雇用調整を計画します。
令和6年4月に、教育訓練を促す内容の見直しが図られました。教育訓練実施率が5分の1以上なら、支給金の加算額が通常の1,200円から1,800円に上がります。ただし実施率が一定以下だと、助成率が従来より低くなるので注意しましょう。
参考:厚生労働省「雇用調整助成金」「雇用調整助成金ガイドブック」
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主におすすめの「地域の給付金」
給付金は国が実施しているものもありますが、自治体が独自に行っている制度もあります。以下に地方自治体の制度の一例を紹介しましょう。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 大府市ふるさと納税特産品開発補助金 (愛知県大府市) |
ふるさと納税の返礼品を開発する事業者に対し、開発に係る費用の一部を上限20万円まで補助する |
| 高性能林業機械等購入事業補助金 (岡山県真庭市) |
高性能林業機械等を購入する費用を上限1,000万円まで補助する |
| 深浦町小規模事業者持続化補助金 (青森県西津軽郡深浦町) |
小規模事業者持続化補助金を活用する事業者を上限10万円まで補助する |
| 大分市中小企業者設備投資補助金 (大分県大分市) |
経営の改善・革新・競争力の強化のための設備投資に係る費用の一部を上限150万円まで補助する(通常枠) |
地域の給付金制度を見つける主な方法は、地元の自治体のホームページなどをチェックすることです。
県や市区町村などで管轄が分かれるため付近のエリアは一通り検索してみるといいでしょう。
地域の制度は情報が分散しており、自治体ごとに条件も大きく異なるため、探すのは手間がかかります。
「補助金AI(無料)」なら、地域別に制度を絞って検索可能です。金額や募集中のものだけの抽出もできるため、「見つけたのに終わっていた」「地域外だった」などのミスマッチで疲弊せずに済みます。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主の生活を支える給付金、減免・猶予制度

個人事業主が使える給付金等の制度には、生活維持・支援に役立つものもあります。
事業に直接働きかけるものではありませんが、廃業や休業に伴う収入の減少を補う制度として、参考のために紹介します。
住居確保給付金
住居確保給付金は、収入が減った人に対して住居の安定を図る制度で、個人事業主やフリーランスも対象です。
対象となるのは、離職や事業の廃業から2年以内の人や、収入が廃業と同等まで減少している、または一定額を超えていない人です。廃業して個人事業主ではなくなった人も対象となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要件 |
|
| 給付額 | 在住の市区町村や世帯人数による |
| 申請期間 | 常時 |
給付額は市区町村や世帯の人数によって異なり、世帯収入額などをもとに算出されます。東京都特別区の例では、1人の場合の上限額が53,700円、2人だと64,000円です(2025年11月時点)。
要件や金額などの詳細については、居住地域の自立相談支援機関に相談しましょう。
参考:厚生労働省「住居確保給付金」
中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成
個人事業主が加入できる中小企業退職金共済制度(中退共)の掛け金を支援してもらえる制度です。月々の掛け金の一部を国が助成してくれるほか、掛け金は経費として計上もできます。
中退共は個人事業主や小規模事業者向けの退職金制度です。定期的に積み立てておくことでまとまったお金が受け取れ、個人事業主自身はもちろん従業員を雇用している場合にもメリットがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 給付額 |
新規加入:月額掛け金の2分の1(従業員ごと上限5,000円) ※パートタイマーの特例掛け金については上乗せ助成あり 掛け金の増額:増額分の3分の1 |
| 申請期間 | 常時 |
新規加入の場合は加入後4カ月目から、掛け金増額の場合は増額月からが助成対象となります。新規加入の個人事業主は条件を理解した上で契約を検討しましょう。
助成の形で掛け金の一部が給付される当制度ですが、中退共そのものも個人事業主の助けになります。万が一に備えとして積み立てておくのがおすすめです。
参考:厚生労働省「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」
国民健康保険料(税)の減免
国民健康保険料・保険税については、軽減や減免の制度が設けられています。定められている条件の該当者として認められると、軽減や減免、納付猶予を受けることが可能です。
事業の悪化などで保険料・保険税の支払が難しくなったときには、制度の対象となるかを確認してみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 軽減額 | 対象者要件によって2割、5割、7割のいずれかの割合を減額 |
| 申請期間 | 常時 |
軽減については、対象者の要件によって7割、5割、2割のいずれかの減額を受けられます。減免や納付猶予については個別に問い合わせが必要です。具体的な要件や金額については、地域の国民健康保険窓口にて確認を行いましょう。
参考:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金を支払っている個人事業主は少なくありませんが、保険料の支払いが困難な場合は免除制度および納付猶予制度が利用できます。
個人事業主本人や配偶者の所得が一定以下になった場合に申請可能です。
手続きせず未納になると、支払っていない期間の年金は減額されるため、必ず申請しておきましょう。
常時受け付けている制度ですが、対象となる申請期間には限りがあります。すでに支払いが遅れている人は早期に手続きしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 |
|
| 軽減額 |
前年所得に応じて以下のどれかが適用
|
| 申請期間 | 保険料の納付期限から2年経過していない期間であれば常時 |
申請できるのは、保険料の納付期限が2年以上過ぎていない期間の保険料です。申請時点で期限が2年1カ月を超えていると申請できないので注意してください。
当制度は給付される老齢年金の受給資格期間や年金額にも影響を与えます。軽減額に応じても影響の範囲が異なるため、事前に確認が必須です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が給付金を受ける際のポイント

個人事業主が給付金を利用する際には、手続きや書類作成が無駄にならないように、効率的に手続きを進めることが大切です。
給付金申請で押さえておきたいポイントを紹介します。
対象者に個人が入っているかチェックする
事業用の助成金や補助金など、多くの給付金は法人が対象です。個人事業主が対象者になっているものは限られているため、まずはしっかりと対象の範囲をチェックしましょう。
また、はっきりと「個人事業者向け」と書かれていない場合も多いため、どのように表現されていたら当てはまるか理解しておくことも必要です。
基本的には、募集要項に「個人を含む」などと追記されている場合は、個人事業主・フリーランスも使えます。「小規模事業主」などと書かれているときも、多くの場合が個人事業主やフリーランスも対象です。
申請期限から逆算して計画的に申請する
補助金や給付金の多くは、それぞれに申請期限が定められており、期限を過ぎたらいくら条件に該当しても申し込めないため、まずは期限から逆算して計画的に準備してください。
給付金の種類によっては何度も公募が行われる場合もありますが、その回を見逃すと、もうチャンスが来ないこともあります。
また、給付金は申請してすぐに受け取れるものではありません。入金には数カ月から1年ほどかかることがあるため、受給までの期間を踏まえて資金計画を立てておきましょう。
電子申請の準備を整えておく
近年、給付金の電子申請化が進んでおり、制度の中には電子申請でのみ受け付けているものもあります。
電子申請には「GビズID」と呼ばれる、行政サービス用認証システムへのアカウント登録が必要です。3種類のアカウントがありますが、補助金などの申請に求められる種類は「プライム」のみのケースもあるため、注意してください。
プライムの取得には、場合によっては2週間ほどかかります。申請期間が限られている制度を検討する際は、締め切りに間に合うよう準備しましょう。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
まとめ・個人事業主が使える給付金を把握して事業に有効活用しよう
個人事業主が利用できる給付金の種類は意外と多くありますが、申請前には十分な調査が必要です。個人が対象でも、条件や申請期限がある場合、条件外や期限を過ぎた場合は利用できません。
個人事業主やフリーランスが給付金を利用する際は、条件や期限が当てはまるかを吟味し、余裕をもって申し込みましょう。国だけでなく、地方自治体の制度を活用するのもおすすめです。
各制度の情報は年度や公募ごとに変更になる可能性があるため、申請時には公式サイトなどで最新情報を確認してください。
補助金や給付金は、制度ごとに条件や期限が大きく変わるため、個人で探し続けると時間を無駄に浪費しがちです。
時間がない、とにかく早く・効率的に探したい場合は「補助金AI(無料)」がおすすめ。最新の募集情報から条件に合う制度だけを自動で受け取れます。
基礎知識を短時間で押さえられる「補助金ガイド(無料)」とあわせて使えば、初めて給付金を申請する人でも迷いが減ってスムーズです。


(編集:創業手帳編集部)