個人事業主が受け取れる給付金まとめ!助成金・補助金との違いも解説
個人事業主対象の給付金を利用して負担を軽減しよう!

世の中には多くの給付金があり、個人事業主を対象としたものも存在しています。
給付金を受け取ることができれば、事業を今まで以上に円滑に進めやすくなります。
そのため、受け取りたいと考える個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
給付金と似たもので助成金や補助金もあり、これらの違いを把握しておくことも大切です。
そこで今回は、個人事業主が受け取れる給付金の詳細や、助成金や補助金との違いについて解説します。
創業手帳では、補助金ガイドをご用意しています。補助金・助成金の最新情報や、活用法、申請のコツなどが分かりますので、ぜひご活用ください。
また、補助金AIという新たなサービスを開始しました。ご自身だけの助成金や補助金情報がメールで届きますので、時間をかけずに情報収集が可能です。無料ですので是非ご利用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
そもそも「給付金」とは?

給付金は、国や地方自治体などが支出します。定められた状態になった時、申請すると受け取れるものです。
給付金には、特別定額給付金や持続化給付金といったものがあります。
特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大による困難を克服するため、住民基本台帳に記録されている国民全員に10万円が給付されました。
持続化給付金は、法人や個人事業主を対象としていて、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の支援を受けられました。
助成金・補助金との違い
給付金・助成金・補助金はよく似ていますが、異なる点もあります。どのような相違点があるのかを以下にまとめました。
・給付金
給付金は緊急事態が発生した時の救済措置です。法人や個人事業主だけではなく、個人も対象となります。審査はそこまで厳しくありません。
経済的に困窮した方への救済措置でもあります。そのため、審査は比較的易しくなっています。
・補助金
補助金は、経済産業省が管轄しているケースが多く、予算が決められています。審査も厳しく、対象者を絞っていることも給付金と異なる点です。
設備の導入や産業の活性化を目的とした法人や個人事業主は利用できますが、個人は対象となりません。
・助成金
助成金は、厚生労働省が管轄しているケースが多く、要件を満たせば支給してもらえるものが多くあります。
しかし、厚生労働省の管轄にあるため、雇用保険の加入や雇用関係などは厳しくチェックされます。雇用や労働環境の改善を考えている法人や個人事業主が対象です。
補助金AIで実際の補助金を見てみよう
まず創業手帳で無料で提供している補助金マッチングエンジンの補助金AIを見てみましょう。

日本には3000もの補助金があり、一方で自分にあうものが少ないので、エリアや業種で絞り込めます。

色々出てきますね。
条件やキーワードを入れておくと自動的に募集されているものがメールで通知されてきます。
補助金は多すぎるので絞り込みが重要になってきます。
またさらに分かりやすいように補助金ガイドという本も無料で差し上げています。
AIと本の両方で情報を収集している創業手帳が、その中でもおすすめのものを下記で紹介していきますね。
個人事業主が受け取れる給付金まとめ

2023年8月現在、個人事業主が申請できる給付金はなくなりました。以下では、過去の個人事業主向け給付金についてご紹介します。
また、給付金以外の個人事業主が利用できる補助金や助成金なども後ほどご紹介していきます。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
※申請受付は2022年12月末日で終了しました。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、厚生労働省が一定の条件を満たす世帯に対して支援を行うための給付金です。
支給対象者や支給額・期間、手続きに関しては以下のとおりです。
支給対象者
支給対象となるのは、緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で、要件を満たしている場合です。
・収入に関する要件
月額の収入が、市町村民税均等割非課税額の1/12と、生活保護の住宅扶助基準額の合算額を超えないことが条件となっています。
東京都の23区の場合だと、単身世帯は13万8,000円、2人世帯は19万4,000円、3人以上の世帯は24万1,000円が基準です。
・資産に関する要件
預貯金が、市町村民税均等割非課税額の1/12の6倍以下なら利用できます。ただし、100万円以下でなければ対象となりません。
・求職に関する要件
ハローワークなどで誠実かつ熱心な求職活動を行っていること、就労による自立が難しいことのいずれかを満たすことも条件となっています。
支給額・期間
毎月の支給額は、単身世帯が6万円、2人世帯が8万円、3人以上の世帯が10万円です。
住居確保給付金との併用も可能となっているため、いずれかを受給している場合でも申請して問題ありません。
支給期間は、2021年7月以降の申請月から3カ月です。この期間中に事業を立て直したり、職に就いたりできるのが理想的です。
しかし、給付終了後も生活に困窮すると予想される場合は、生活保護の申請を行う必要があります。
手続きについて
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、現在住んでいる自治体に申請する必要があります。
申請書類のほかに、添付書類も用意しなければいけないため、忘れないように注意が必要です。申請窓口などに関しては、自治体のホームページで確認できます。
申請時に用意する添付書類は以下のとおりです。
-
- 本人確認や世帯構成を確認できる書類(住民票の写し)
- 収入がわかる書類(給与明細などの写し)
- 資産を確認できる書類(世帯員全員の通帳の写し)
- 求職活動に関する書類(申請書に求職番号などを記載。生活保護申請中の方は、保護申請書の写しが必要)
- 振込先口座がわかる書類(支給口座として活用する通帳の写し)
- 再貸付などの終了や不承認、過去の貸付の状況を確認できる書類(借用書など)
※申請受付は2022年12月末日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
※申請受付は2023年5月31日で終了しました。
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は、委託を受けて個人で仕事をしている方を支援するための給付金です。
支給対象者や支給額・期間、手続きについて解説します。
支給対象者
支給対象となるのは、以下の条件すべてに該当する方です。
-
- 保護者(親権者・未成年後見人・里親・祖父母など子どもの監護をしている方や一時的に子どもの世話を手伝う親族)である
- 新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業をした小学校に通う子どもや新型コロナウイルスに感染して学校を休まなければいけない子どもの世話をする
- 小学校などが臨時休校する前に業務委託契約などを締結している(契約を締結している方が個人で契約に基づいて業務を行うこと、臨時休業以前から契約を結んでいること、業務従事・業務遂行の態様・業務の場所・日時などが指定されていること、業務の時間などを前提とした報酬となっていること)
- 予定していた日に仕事ができなくなった
支給額・期間
支給額は、1日あたり4,177円となっています。どのような状況であっても、支給額は定額です。
子どもの世話で仕事ができなくなり、収入が途絶えてしまうことを防ぐために役立ちます。
支給期間は、2023年3月31日までです。
2022年10月1日~11月30日までの分は2023年1月31日まで、2022年12月1日~3月31日までの分は2023年5月31日が申請期限となっています。
いずれも必着となっているため、遅れないように書類などを準備してください。
※申請受付は2023年5月31日で終了しました。
手続きについて
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」を受け取るためには、必要な書類の準備や申請書の記入をしなければいけません。
準備が終わったら、学校等休業助成金・支援金受付センターに送付します。
必要な書類は以下のとおりです。
-
- 保護者だと証明する書類(住民票記載事項証明書の原本)
- 振込口座を確認する書類(口座番号が確認できる書類の写し)
- 子どもの世話をしていることを証明する書類(小学校などの臨時休業期間などを証明する書類の写し、「新型コロナウイルスに感染した子ども」であることを理由に登校しないことを認めた書類の写し)
- 業務委託契約を証明する書類(業務委託契約を証する書類の写しや契約申立書(様式第3号)原本など)
助成金・補助金も活用しよう!

給付金のほか、助成金や補助金もあります。これらをうまく活用すれば、事業を円滑に進めやすくなります。
以下に、個人事業主が利用できる助成金・補助金にはどのようなものがあるのかをまとめました。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、事業を拡大させるために活用できます。非正規雇用の労働者が企業内でキャリアアップを図る際に利用可能となります。
正社員化や処遇改善などの取組みを行った法人や個人事業主に対して助成金を支給し、円滑な事業拡大を支援することが目的です。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、事業計画を策定し、認定支援機関と協力しながら進める場合に利用可能となります。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に対応できるように、中小企業などの事業再構築をサポートすることが目的です。
新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換などのチャレンジをしたいと考えているのであれば、利用を検討してみてください。
小規模事業者持続化補助金(一般型)
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」は、小規模事業者や一定の要件を満たしている特定非営利活動法人が直面する制度の変更(インボイス制度など)に対応するためのサポートを行うことが目的です。
販路開拓などの取組みを行う際の経費を一部補助塑、地域の雇用促進や生産性の向上、持続的な発展を図れるように支援します。
対象となるのは、商工会議所や商工会のアドバイスを受けて経営計画を作成し、地道な販路開拓を行っているフリーランスです。
支援額は最大で200万円となっています。経営計画書や補助事業計画書などの提出が必要です。
一般枠のほか、インボイス制度の対応費も支援対象となるインボイス枠もあります。
インボイス制度のスタートが不安な場合は、こちらの枠を狙ってみても良いかもしれません。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業や小規模事業者などがインボイス制度などに対応し、革新的なサービスの開発などを行うための設備投資をサポートします。
生産性の向上を目指すために活用できる補助金です。個人事業主の場合は、補助率が2/3になります。
申請時には、以下の書類が必要です。
-
- 事業計画書
- 補助経費に関する誓約書
- 賃金引上げ計画の誓約書
- 確定申告書など
- 所得税青色申告決算書もしくは所得税白色申告収支内訳書の写し
再生事業者や回復型賃上げまたは雇用拡大枠・グリーン枠・大幅な賃上げを行う場合、グローバル市場開拓枠などの状況により、必要な書類が異なります。
申請前に確認しておいてください。
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資等の費用の一部を助成するものです。
生産性の向上は、売上増加やコスト削減につながります。戦略的に企業の成長を実現していきましょう。
給付金や助成金などを利用するメリット・デメリット

給付金や助成金などを利用すると、法人でも個人事業主でもメリットを享受できます。しかし、メリットだけではなくデメリットだと感じてしまう部分も少なからずあります。
最後に、どのようなメリット・デメリットがあるのをまとめました。
メリット
メリットには、返済する必要がないこと、事業を維持できること、設備・人材への投資にも活用できることなどが挙げられます。
1.返済する必要がない
給付金や助成金は、基本的に返済する必要がありません。融資だと返済しなければいけませんが、その負担を回避できるのは大きなメリットです。
例えば、雇用関係の助成金は小規模保険の一部が原資になっているため、返済しなくても問題ありません。
これまでに負担した雇用保険の一部が還元されたようなイメージです。そのため、必要な金額を惜しむことなく使えます。
融資の場合、受けた後の返済が苦しくなってしまう恐れもありますが、そのような不安も払拭できます。
2.事業を維持できる
事業を維持できることも、給付金などを受けることで得られる大きなメリットです。
小規模事業者持続化補助金のように事業を維持するための販路開拓などを支援するものもあるので、状況に合わせて選択できれば効果を感じやすくなります。
販路の開拓や事業転換を行う場合、多額のコストがかかってしまうケースも珍しくありません。
しかし、給付金などを使えば負担を抑えられるため、事業の維持や継続にも役立つといえます。
3.設備・人材への投資にも活用できる
給付金や補助金は、設備や人材への投資にも活用可能です。
事業規模が小さい個人事業主などは、設備投資や人材育成にお金を使いたくても資金不足から実現できないケースも多くあります。
しかし、給付金などを使えば資金調達の悩みを解消でき、理想を具現化しやすくなるので前向きに検討する価値があります。
全額給付はしてもらえませんが、負担は大幅に軽減可能です。事業拡大にも役立つので、利用する個人事業主も少なくないでしょう。
デメリット
メリットだけではなくデメリットもあります。デメリットにはどのような点が挙げられるのかをご紹介します。
1.手続きが面倒
申請する給付金や補助金によりますが、手続きが面倒だと感じてしまうものもあります。必要な書類が多い場合は、特に面倒と感じてしまう場合が多くなるようです。
個人事業主やフリーランスとして仕事をしている方が手続きをしようとすると、大きな負担になるケースは珍しくありません。
給付金などを申請する機会が少ないことも、手続きに手間がかかる要因のひとつです。利用を考えている場合は、早めの準備を心掛けてください。
2.必ずしも受給できるとは限らない
給付金などは、申請すれば必ず受給できるわけではありません。予算額や採択件数が決められているものも多いためです。
申請したとしても、審査に落ちてしまったり需給を却下されてしまったりするケースもあります。
申請者が多い給付金や助成金は、特に競争率が高いので、ハードルが高くなります。手間などを加味した上で、申請すべきか否かをよく考えてみてください。
3.制度の数が少ない
給付金は、緊急事態の対処として支給されるケースが多くなっています。そのため、補助金や助成金と比べると制度の少ないことがデメリットといえます。
また、申請期限も定められているものが多く、期限を過ぎた場合は利用できません。
どのような給付金があるのかしっかりとリサーチし、利用可能か確認した上で申請することがポイントです。
申請期限や要件などもしっかり確認し、ミスがないように確認することが大切です。
まとめ
給付金の中には、個人事業主が利用できるものもあります。しかし、緊急事態の支援として支給されることが多いので、申請期限などに気をつけなければいけません。
また、メリットやデメリットも把握しておくと、申請後に後悔せずに済むため、申請前に確認しておくことをおすすめします。
また、資金調達全般について掲載している資金調達手帳もご用意しています。そもそも自分に最適な資金調達方法はどれなのか、融資を成功させるためのポイントなどを解説。ぜひお手にとってご利用ください。
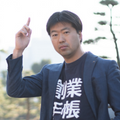 創業手帳・代表 大久保の解説
創業手帳・代表 大久保の解説
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。


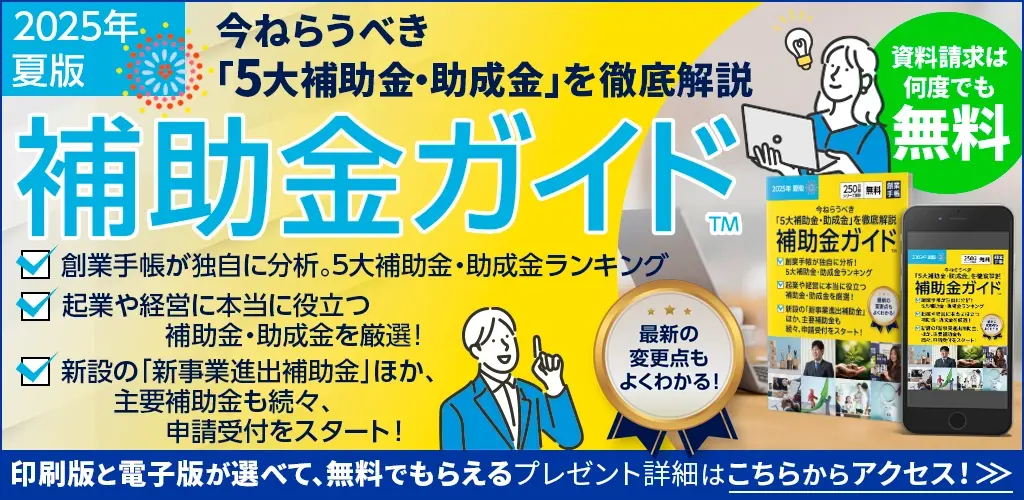

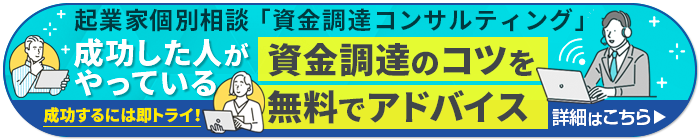












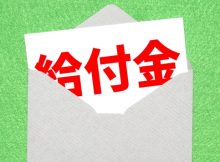























この記事はお役に立てましたでしょうか。
創業手帳は起業や開業された方が同じことに困る、つまづくという声から、共通で困る内容をまとめた創業手帳を発行している他、補助金が分かりにくすぎる!という声から補助金ガイドの発行、さらに補助金をタイムリーに教えてほしい!という声から補助金AIを開発しました。
創業手帳は日本で最もみられている起業家メディアで銀行や官公庁、大手企業などがこぞってスポンサーしていただいているため、全て安心して無料で使えます。ぜひ、使ってみてくださいね。
また、創業手帳では多くの個人事業主の方から補助金・助成金や給付金の相談を受けることがあります。
多くの方から相談される内容からポイントを絞って解説しますね。
まず、最近のトレンドと補助金の背景を解説します。
給付金や補助金・助成金を出している側、つまり政府や自治体の背景を知ると、対応や書類の書き方が理解しやすくなります。
トレンドとしては今までコロナの緊急対策がありましたが、コロナ系の助成金が落ち着いてきました。
反面、現在は、物価高やそれに伴う賃上げが課題になってきています。
補助金のお金の出し手は誰でしょう?それは政府ですね。
自治体のケースもありますが、基本的に政府の動きと足並みをそろえています。
その政府が最も力を入れているのは賃金上昇です。
賃金上昇は、国民の暮らしや政治家の人気取りだけではなく、経済成長の原資を企業に負担させる、物価高騰への対応などが根底にある事情としてあります。
その賃金上昇の鍵が「特に中小企業や個人事業主の生産性を上げる」ということです。
賃金上昇が補助金を出す側の大きなテーマとしてあり、政府の様々な報告書や発表、補助金情報を日々読み解いている立場からすると、繰り返し出てくるなあ、と感じるキーワードです。
賃金を上げるには、どうしたら良いかというと、高めの価格設定、革新的な商品開発、教育、販路開拓などが自分は本質的に有効だと思いますが、相応に時間がかかります。
そのため、すぐに企業が取り組め、補助金や給付金の支給要件となりやすいのが下記です。
・経営計画を作り経営改善を図る
・賃金を上げやすい環境を整える
こちらが「補助金を出す側の着目点で、取り組みたいポイント」です。
この3点をしっかり抑えることが、最近の補助金や助成金、給付金を通すコツと言えます。
特に金額が大きいものは経営計画、生産性、賃金アップが条件としてセットになっているものが多いです。この3つは急に付け焼き刃的に対応できないものなので、早めに長期的な手を考えて対応していきましょう。
個人事業主も経営者ですので、こうした経営の改善・生産性アップというのは重要なテーマになり、こうした給付金・補助金助成金は、チャレンジの絶好のタイミングになります。
補助金目当てになるのは良くないものの、実際に相談を受けた方や、取材先では、こうした資金を上手く使って、厳しい状況を乗り越えて、新しいチャレンジを成功させたような方が多くいます。
コロナの時のようにとにかくお金を早くばらまいて、倒産を防ぐじゃぶじゃぶ・ゆるゆるの緊急融資と違い、本質的な改善や対策が最近の潮流です。
また、日本では補助金助成金は3000もあると言われており、自分にあった情報を探すのが難しく、気づいた頃には募集期間が終わっている、そもそも重要なものが分かりにくいということがありますので、創業手帳では分かりやすく解説した補助金ガイドや、自動で自分にあった補助金を選んで届けてくれる補助金AIなどいずれも無料で提供しているので積極的に使ってくださいね。
上手く補助金・助成金や給付金、そしてこうした良質な無料ツールを使いこなしてこの時代を乗り切っていきましょう。