【2026年最新】個人事業主が開業に使える助成金・補助金は?審査通過のコツも
個人事業主の開業資金にもできる助成金・補助金

- 個人事業主が利用できる助成金・補助金・支援金の違い
- 開業前~開業1カ月までにおすすめの助成金や補助金
- 開業1カ月以降、事業の加速や再構築に使いたい助成金や補助金
- 申請時のポイントと審査を通過するためのコツ
「個人で開業したいけど資金が足りない」
「個人事業主の開業時に利用できる助成金や補助金はないだろうか」
開業する際に資金面が不安になる個人事業主の方は多いのではないでしょうか。このような不安を解決する方法が助成金や補助金の活用です。一般的には法人だけが対象と思われがちですが、個人事業主も利用できる助成金・補助金があります。
この記事では、開業前後に使いやすい助成金・補助金についてまとめました。うまく活用すれば開業費用の負担が減り、リスクも抑えられます。
創業手帳では、自分にぴったりの補助金・助成金をメールでお知らせする「補助金AI」をリリースしました。膨大にある補助金・助成金の情報をキャッチできます。さらに大人気の「補助金ガイド」では、個人事業主が利用しやすい補助金・助成金をわかりやすく確認可能です。どちらも無料で使えます。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主が開業前~開業直後に使える助成金・補助金

主な助成金や補助金の中から、個人事業主が活用できる制度を紹介します。なかでも開業前や開業直後に使える制度を中心にまとめました。
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、地域における求職者の雇用環境の改善を目的とし、事業所の設置と人材雇用を行う際に活用できる助成金です。雇用機会が少ない特定地域にて新たなビジネスを開業・創業する事業主が対象となります。
同地域での開業に際し事業所を設け、求職者を雇うことが主な要件です。設置にかかった費用や従業員数の数に応じた助成金が受け取れ、設置・整備が完了した日から1年ごとに最大3回支給されます。ただし、毎年の支給申請による審査が必要です。
個人事業主でも申請できますが、従業員が必要な規模のビジネスを計画してから申請しましょう。
また、創業時には特例措置があり、初回支給時に通常額の2倍を受け取れます。例えば、設置費用300万円以上1,000万円未満、増加人数3〜4人の場合、通常50万円に対し創業であれば100万円です。
48万~760万円(事業所の設置・整備費用、対象従業員の増加人数に応じて変動)
ただし、創業の特例が適用される場合は最大1,600万円となり、大規模雇用開発特例の場合は1億円から2億円
助成対象:事業所の工事費、購入費、賃借費など
小規模事業者持続化補助金(創業型)
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主や小規模な法人が販路開拓や生産性向上に取り組む費用を支援する制度です。
「通常枠」のほか、重点的に支援を行う「特別枠」があり、その一つに「創業枠」が設けられています。
2025年度の創業枠の主な要件は、公募締切時から過去3年以内に、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者であることです。自治体の創業塾や個別相談を完了し、証明書を取得している必要があります。
2025年の創業型枠の対象要件は、公募締切時から過去3年間に、産業競争力強化法に基づく認定市区町村などが実施した特定創業支援事業による支援を受けた小規模事業者です。
補助対象経費:機械装置等費、広告費、ウェブサイト関連費など
※ウェブサイト関連費のみでの申請はできず、他の経費との組み合わせが必要。
※商工会・商工会議所の支援を受けながら事業計画書を作成し、確認書(様式4)の発行を受けることが必須となります。
「冊子版創業手帳」では、商工会議所を活用した販路拡大の事例を掲載しているので、補助金申請の参考になります。
起業支援金と移住支援金
起業支援金と移住支援金は特定地域での起業・創業に活用できます。東京圏ではない地方でビジネスをおこす際、起業や移住に必要な資金が支給されます。
起業支援金と移住支援金の違いを表にまとめました。
| 項目 | 起業支援金 | 移住支援金 |
|---|---|---|
| 対象事業 | 地方創生起業支援事業 | 地方創生移住支援事業 |
| 目的 | 地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」の観点をもった起業等(社会的事業)を支援 | 地域の重要な中小企業等への就業や社会的起業をする移住者を支援 |
| 起業・移住元の要件 | 起業地の都道府県内に居住しているか、居住予定 | 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤(直近1年以上が必要) |
| 事業活動要件 | 国の交付決定日以降に個人開業届または法人設立を行う |
|
実施期間や支給額、申請書類、受付期間等の制度の詳細は自治体ごとに違うので、開業予定の自治体に問い合わせた上で申請しましょう。
- 起業支援金200万円(起業等に必要な経費の2分の1に相当する額を交付)
- 移住支援金100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算される)ただし、単身の場合は60万円以内
支援対象:事業費など
地域の創業向け助成金・補助金
地方創生起業支援事業のほかにも、地域の自治体ごとに提供している創業支援を活用すれば、開業時の資金になる可能性があります。
例えば、次のような制度が例です。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 笠間市創業支援事業 (茨城県笠間市) |
創業時の店舗建築、改装などの対象事業費を最大50万円 |
| 岡山市創業促進助成金 (岡山県) |
市内で株式会社を設立した場合に10万円、合同・合名・合資会社の場合に5万円を支給 |
| 高知県空き店舗対策事業費補助金 (高知県) |
空き店舗を活用した出店で、最大100万円を支給 |
こうした制度は運営元の自治体・団体が独自に提供する、起業支援金の枠を超えた内容が魅力です。
個人事業主にもチャンスがあるので、地元の支援制度をくまなく調べてみましょう。
どの制度を使うか迷ったら、無料の「補助金ガイド」をご覧ください。利用しやすい助成金・補助金だけをまとめています。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が開業後に活用できる助成金・補助金
開業から1カ月以上がたった後も、個人事業主におすすめしたい助成金・補助金もあります。開業後を見据えて把握しておくと、資金調達したくなった際に役立つでしょう。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
2026年度より、従来の「ものづくり補助金」と「中小企業新事業進出補助金」は、『新事業進出・ものづくり補助金(仮称)』として一つの大きな制度に統合・再編される予定です。詳しい情報が公開され次第、こちらに記載します。
これにより、従来の「生産プロセスの改善(設備導入)」だけでなく、「新業態への転換(新事業進出)」をより強力に支援する枠組みとなります。
個人事業主にとっても、これまでの事業とは異なる新しいジャンルへの挑戦や、大幅な賃上げを伴う設備投資が対象となるため、事業拡大の大きなチャンスです。
申請締切日から3年以内に事業承継・創業した場合は加点対象となるため、第二創業や事業引継ぎ後の個人事業主にも有利な仕組みです。
省力化(人手不足解消)やDXへの投資がより重視されています。審査には入念な事業計画の策定が必須です。開業間もない場合は、実現可能性や革新的なアイデア、数値目標の妥当性が厳しく評価されます。
以下は、2025年度のものづくり補助金の情報になります。
- 従業員数に応じた補助上限額が見直し
- 「従業員21人以上」の区分が、「21〜50人」と「51人以上」に細分化
上限額:750万~4,000万円(申請枠によって異なる)
下限額:100万円
補助対象:設備・システム投資の費用など(申請枠によって異なる)
中小企業新事業進出補助金
2026年度に、「ものづくり補助金」と「中小企業新事業進出補助金」が再編され、『新事業進出・ものづくり補助金(仮称)』として生まれ変わる予定です。詳しい情報につきましては公開されましたら、こちらに記載いたします。
中小企業新事業進出補助金は中小企業等が、新しい事業にチャレンジすることで企業規模の拡大や賃上げを目的として創設されました。個人事業主も対象ですが、応募申請時点で従業員を雇用している必要があります。
事業計画期間中に従業員の賃上げなどの要件を満たせば、最大で9,000万円の補助を受けられます。3〜5年の事業計画への取り組みなど必要な要件を確認し、新規事業の設備投資等に活用してください。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用従業員の正社員化や処遇改善を行った事業主に支給されます。2025年4月より「正社員化コース」が大幅に拡充され、特に多様な正社員(勤務地限定・職務限定等)への転換支援が強化されています。
受給には、コース実施前日までに「キャリアアップ計画」を提出する必要があります。2026年現在は、賃上げ要件の緩和や、人材開発支援助成金との連携による加算措置など、より柔軟な活用が可能になっています。
デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)
デジタル化・AI導入補助金は、インボイス制度への対応やDX推進を目的としたITツールの導入を支援します。2026年度は、IT導入補助金から名称が変更され、安価なSaaSツールの導入から、AIを活用した高度なシステム構築まで幅広く対応しています。
個人事業主が申請する場合、直近分の納税証明書と確定申告書の控え(受付印のあるもの等)が必須です。そのため、開業後少なくとも1回目の確定申告を終えてから申請可能となります。
両立支援等助成金
両立支援等助成金は育児や介護、不妊治療と仕事の両立を支援する制度です。2025年以降、「育児休業等支援コース」の加算額が拡充されており、特に男性従業員の育休取得を促進した事業主への支援が手厚くなっています。
個人事業主でも従業員(パート含む)が育休を取得し、職場復帰支援などを行うことで受給可能です。事前に「育休復帰支援プラン」の策定など、計画的な取り組みが求められます。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、従業員の雇用を維持するための制度です。景気の変動、他の経済上の理由により事業を縮小する際の休業手当など、雇用維持のための手当の一部を助成します。
開業後に人を雇ったものの、事業の停滞や見直しが必要になった際に雇用を維持するために活用したい助成金です。
雇用関係の助成金は、就業規則の作成など社内制度の整備が必要となることがあります。起業ノウハウ集「冊子版創業手帳」では、人事・労務の仕組みを整えるためのノウハウを掲載しているので、申請が通る社内制度の組み立て方がわかります。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
助成金・補助金・支援金は何がどう違う?

個人事業主が開業時に活用できる公的な資金支援制度があります。
「助成金」「補助金」「支援金」の3つの支援制度の違いを知り、最適な方法を選びましょう。
| 比較項目 | 助成金 | 補助金 | 支援金 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 雇用や労働改善を助ける制度 | 製品やサービスの開発費など、必要な経費を補助する制度 | 災害や経済危機などへの緊急的な支援制度 |
| メリット | 要件を満たせば受給できる | 対象となる範囲が広く、支給額が大きい | 比較的早く支給される |
| デメリット | 使える範囲が狭いことが多い | 制度によって採択率に差があり、申請期間が短い | 限定的なものが多く、継続的な支援にはならない |
| 管轄 | 厚生労働省など | 経済産業省、地方自治体など | 国、地方自治体など |
いずれも原則として返済不要です。個人事業主が対象に入っていれば、要件を満たすことで申請できます。3つの制度の目的や役割も簡単に知っておきましょう。
助成金とは
助成金とは主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働環境の改善を目的とした支援金制度です。要件を満たすと原則として受給できます。助成金により企業の経営を助け、雇用を維持、促進させます。
具体的には、雇用の維持・新規雇用・人材育成・中途採用とUIJターン雇用・障害者の職場定着支援など、従業員の雇用を前提とした制度です。また、就業規則の改善や介護、育児休暇の導入といった労働環境の整備を目指す助成金もあります。
補助金とは
補助金は、主に経済産業省や地方自治体が実施し、新製品や新技術、新サービスの開発費など、さまざまな費用を補助する制度です。予算が定められており、要件を満たしていても審査を通過しなければ支給されません。
制度によるので一概には言えませんが、助成金や給付金に比べて活用範囲の幅が広い傾向にあり、柔軟に活用が可能です。対象に個人事業主が含まれるか、開業時に活用可能かなど、要件をよく確認して申請しましょう。
支援金とは
支援金とは、主に地震などの災害や経済危機などで、経営に影響を受けた企業や個人事業主を救済するための資金を指します。
緊急性の高い課題への支援なので比較的早く対応してもらえますが、一時的な支援であるため、継続的な資金調達の手段にはなりません。
内容は管轄元によって大きく異なるため、制度内容をよく理解してから申請しましょう。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が開業に助成金や補助金を使うなら?申請のポイント

個人事業主も助成金や補助金の申請が可能ですが、採択されなければ受給できません。開業・創業に利用したい個人事業主は、審査を無事通過するためのポイントをチェックしておいてください。
法人向けと個人事業主向けを見分ける
まず、制度によって法人向けと個人事業主向けがあるため、申請できるものを見分けるのが重要です。
公的な制度である助成金や補助金は、要件が厳しい場合もあります。個人の開業や創業に使える制度なのかも含め、徹底的に読み込みましょう。
対象が曖昧なら、担当部署に問い合わせるなどして個人事業主が申請できるかを確認してください。
要件と期限を厳密に守る
個人事業主が申請を通過するには要件と期限を厳密に守ることが前提です。細かい条件を満たしていない、申請中に状況が変わったなどで審査に通らない可能性もあります。
なかでも繰り返し募集している制度の場合、1回目より2回目の方が枠が狭くなることも少なくありません。申請は早めを心がけ、すべての要件を満たすよう漏れなく準備しましょう。
事業計画書を作りこむ
助成金や補助金の審査に通過するには、事業計画書を通じて事業の内容や魅力をいかに伝えるかが大切です。
特に個人事業主が開業に利用する場合、事業実績が乏しかったり、実現可能性が証明しにくかったりします。事業計画書が求められる制度だと不利になりやすいため、計画書の作りこみが欠かせません。
例えば、他社と比べて自社が優れている点をアピールすることがあげられます。サービスや商品の質、需要の有無や将来性などを具体的に記入すると相手にも伝わりやすいでしょう。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が開業前後に助成金・補助金を使うメリット・デメリット

個人事業主にとって助成金や補助金は、さまざまなメリットがあります。一方で、注意すべきデメリットもあります。それぞれの内容を見ていきましょう。
個人事業主が助成金・補助金を使うメリット
個人事業主が助成金や補助金を使うメリットは、以下の点が挙げられます。
- 返済義務がない
- 事業の信用力向上につながる
- 事業を見直す機会になる
返済不要であるため、資金繰りを圧迫しません。公的機関の審査を通過した実績は信用度の向上を期待できます。また、補助金申請の多くは事業計画書の提出が必要になるため、事業について見つめ直す機会になるでしょう。
個人事業主が助成金・補助金を使うデメリット
個人事業主が開業時に助成金・補助金を使うデメリットは以下のとおりです。
- 要件が厳しい
- 受給まで時間がかかる
- 申請期間が決まっている場合がある
助成金や補助金の支給制度は、開業前後の個人事業主には要件を満たすことが難しい場合があります。
また基本的に後払いで、すぐに受給できるわけではありません。さらに申請期間が決まっている場合もあり、開業や新事業に合わせて使いたくても間に合わないケースがあります。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
まとめ・個人事業主も助成金や補助金を活用しよう!
助成金や補助金には個人事業主が使える制度もあります。
開業・創業に役立てるには、事前に要件や期日をしっかり確認し、審査に通るような内容で申請することが大切です。それぞれの開業に使える制度を検討し、資金調達の手段としましょう。
申請書類の作成は多くの時間がかかり、個人事業主にとって大きな負担です。「補助金ガイド」では、手間を削減するための具体的な方法を紹介しています。採択率を上げたい人も必見です。
開業に使える制度を効率良く探したいなら「補助金AI」を使いましょう。目的に合った制度がメールで届き、無料で利用できます。
個人事業主OKの助成金や補助金を使ってみた
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。





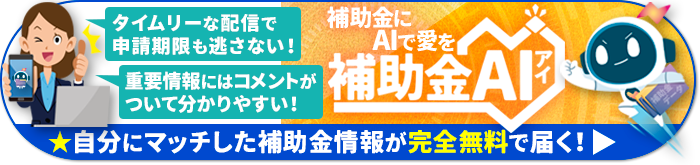









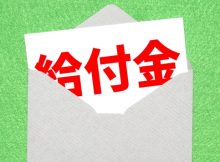























事業再構築補助金を弊社で使ってみた感想ですが、業態変換を図ろうとしている事業者にとってメリットがあります。ポイントは長期的な事業計画を書けるかどうかです。
もう一つの制度である助成金は、補助金に対して成功率が高い傾向があり、金額が大きい、コンスタントに受給できるといったメリットがあります。正社員雇用の増大やスキルアップ、労働環境の整備などを目的としている制度です。
助成金を管轄する厚生労働省は、労働環境をよくするなどの政策的な目標があり、その達成のために助成金を出しています。
そのため、事業のベースとして正社員化や労働環境の整備、スキルアップ・リスキリングに真剣に取り組み、その過程で助成金をもらうという考え方が好相性です。
補助金・助成金はキャッチアップが難しいので、創業手帳の発行している『補助金ガイド』や『創業手帳』で情報を入手してください。