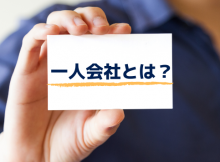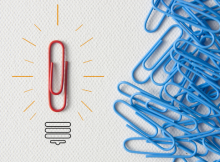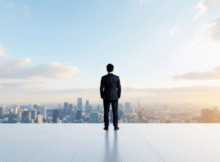【初心者向け】ドロップシッピングとは?仕組みやメリット・デメリットなどを解説
ドロップシッピングは在庫ゼロで物販を始められるビジネスモデル

ネットショップ運営は法人・個人を問わず開設することができ、副業でも取り入れられているビジネスです。
しかし、ネットショップを運営する際には、仕入れ・在庫管理・梱包・発送作業などもすべて自分でこなす必要があります。
コストもかかってくることから、諦めてしまう人もいるかもしれません。
そのようなネットショップ運営を諦めてしまった人におすすめしたいのが、「ドロップシッピング」です。ドロップシッピングは在庫なしで販売事業を始めることができます。
そこで今回は、初心者向けにドロップシッピングの特徴や仕組み、メリット、注意点などを解説します。
ドロップシッピングが気になるものの、どういった仕組みで販売することになるのか知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ドロップシッピングの特徴・仕組み

ドロップシッピングとは、注文が入ったらメーカーや商品を保有する企業に問い合わせ、顧客に直接送付してもらうEコマースのモデルを指します。
ショップを運営している個人または企業は商品の仕入れから在庫管理までを行う必要がなく、また、梱包・発送作業も不要です。
商品販売の仕組み
ドロップシッピングによる商品販売の具体的な流れは、まず運営しているネットショップに出品した商品を顧客が注文します。
注文情報はネットショップの運営者からサプライヤー(卸売業者)へすぐに送信、または自動的に送信されます。
サプライヤーは受け取った注文情報をもとに、保管していた商品を梱包し、顧客宛てに発送する仕組みです。
このような仕組みにより、ネットショップの運営者は在庫を抱えなくても商品販売が可能となります。
無在庫販売との違い
在庫を保有しない販売方法として「無在庫販売」があります。ドロップシッピングも在庫を持たないため、無在庫販売の一種といえるでしょう。
ただし、異なる部分もあり、例えば、ドロップシッピングは在庫を完全に保有しておらず、注文が入ったらその情報をサプライヤーに渡します。
無在庫販売の場合も在庫は保有していませんが、注文が入った段階で都度仕入れており、自分または代行業者が顧客に向けて商品を発送することになります。
ドロップシッピングの始め方

ドロップシッピングを始めるにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、ドロップシッピングの始め方として、3つの方法を解説していきます。
方法1:卸売業者やメーカーと直接交渉・契約を結ぶ
1つ目の方法として、卸売業者やメーカーと直接交渉し、契約を結ぶという方法です。この方法は、すでにネットショップで取り扱い商品が決まっている場合に適しています。
まずは自分のネットショップを準備しておき、ネットなどから取り扱いたい商品を見つけます。
商品が見つかったらその卸売業者またはメーカーに直接問い合わせ、自分のショップで販売させてほしい旨を伝えてください。
ただし、メーカーでは個人のネットショップとの直接交渉に応じるケースはかなり少ないです。
特に実績がほとんどない個人とは、メーカーだけでなく卸売業者も契約してもらえません。
さらに、交渉できたとしても企業と契約を結ぶことになるため、販売だけでなく法律の知識も必要となってきます。
方法2:DSP(ドロップシッピング・サービス・プロバイダ)に登録する
法人としてすでに大規模なネットショップを運営している場合は、DSPへの登録がおすすめです。
DSPはドロップシッピングサービスを提供する業者を指しており、ネットショップのオーナーと卸売業者との仲介を担っています。DSPの登録自体は無料で行うことが可能です。
DSPにも様々な種類があり、既存の商品を取り扱っているものと、オリジナル商品を中心に手がけているものにわかれます。
ほかにもDSPによって特色や強み、取り扱う商品などが違っているため、目的に合わせてDSPを選んでください。
方法3:ドロップシッピング対応サイトを利用する
個人または小規模企業でネットショップを運営する場合は、ドロップシッピング対応サイトの活用がおすすめです。
ドロップシッピング対応サイトとは、ドロップシッピングが行える商品を数多く取り扱っているサイトになります。
ショップのオーナーは対応サイトの中から好きな商品を選び、ネットショップで販売するだけです。
商品の注文が入ったら、対応サイトに受注した旨を知らせるだけで、梱包・発送作業もすべて代行してもらえます。
AmazonなどのECサイトはドロップシッピングに対応していないため、個人でドロップシッピングを始める際には対応サイトを活用してください。
ドロップシッピングのメリット
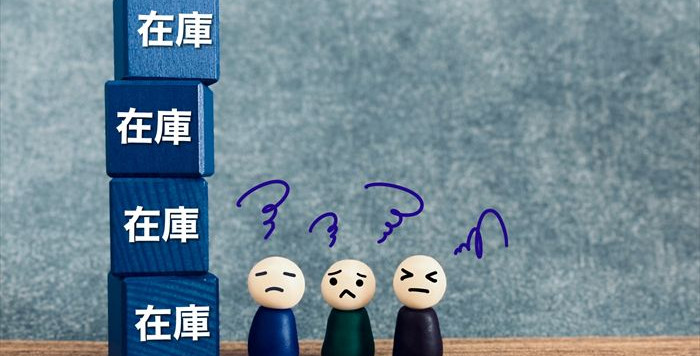
一般的なネットショップ運営と異なり、ドロップシッピングにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここで、ドロップシッピングのメリットを解説します。
在庫を抱えるリスクがない
ドロップシッピングは無在庫販売の一種ということもあり、在庫を抱えるリスクがありません。通常、ネットショップを運営する際には、在庫管理が重要となってきます。
在庫が少なすぎると商品がすぐに売り切れて機会損失を招くだけでなく、商品の発送が遅れてしまうことから顧客満足度が下がってしまう可能性が高いです。
逆に在庫が多すぎても売れ残ってしまい、利益が上がりません。しかも在庫を保管するための人件費や場所代なども必要となってくることから、多大なコストを要します。
ドロップシッピングであれば商品自体は卸売業者やメーカーが保有しているため、商品が売れ残ってしまう心配もありません。
梱包・配送などの作業が不要
ドロップシッピングでは注文情報を卸売業者やメーカーに渡すまでで、その後の梱包・配送などの作業はすべて卸売業者やメーカーが担当しています。
自分でネットショップを運営するとなると、梱包・配送などの作業まですべて自分が担うことになり、その分手間がかかってしまいます。
また、梱包をするための資材コストや、作業する人の人件費も必要です。
梱包や配送などの作業がなくなれば、時間とコストを削減でき、商品の選定や登録に時間を割けるようになります。
低コストで始められる
上記でも説明したように、ドロップシッピングは基本的に梱包・配送の作業にかかる資材コストや人件費などが不要になります。
また、商品を仕入れるためのコストや、在庫を保管するための場所代などもかかりません。
このような理由から、一般的なネットショップ運営と比較して低コストで始められます。
ネットショップ運営を始めたいものの、初期費用をできるだけ抑えたいという人には特におすすめのビジネスモデルです。
販売価格は自由に設定可能
ドロップシッピングは仕入価格に基づき、商品の販売価格を自由に設定できます。
購入金額から卸売価格・販売手数料などを差し引いた金額が利益となるため、販売価格を設定する際に高めにすることで利益を増やせます。
逆に競合が多い商品の場合は、値段を極力下げて購入してもらうといった販売戦略を立てることも可能です。
ただし、仕入価格に関しては固定されているのが一般的なので、安く設定しすぎるとたくさん売っても利益を上げるのが難しくなる点には注意が必要です。
ドロップシッピングを始める際の注意点

ドロップシッピングには様々なメリットがありますが、実際に始める際にはいくつか注意すべきポイントもあります。ここで、注意点を把握しておいてください。
在庫・品質管理が難しい
ドロップシッピングは在庫を持たないビジネスモデルになるため、在庫・品質管理が不要と考える人もいるでしょう。
しかし、実際には自分の目で商品を確かめて発送するわけではないため、場合によっては品切れ状態がずっと続いてしまったり、品質の低い商品が顧客のもとに届いたりするケースも少なくありません。
そのため、ドロップシッピングは一般的なネットショップ運営よりも在庫・品質管理が難しいとされています。
この問題を解決するためにはサポート体制を見直したり、信用できるサプライヤーを見つけたりすることが大切です。
競合が多く価格競争が激しい
ドロップシッピングはすべての商品に対応しているわけではありません。そのため、販売可能かつ人気のある商品には多くの競合が存在することになります。
競合が多くなってしまうと価格競争が激しくなり、利益を上げるのが難しくなってしまう可能性が高いです。
また、ドロップシッピングは同じ卸売業者から仕入れているケースもあり、競合と商品のラインナップも被りやすい傾向にあります。
競合に負けないネットショップにしていくためには、顧客のニーズや市場のトレンドなどを常に探り、売れそうな商品をリサーチすることが大切です。
また、ネットショップのデザインやUX/UIを定期的に見直してユーザーファーストのサイトにしたり、SNSなどで情報を発信しファンを増やしたりする方法もおすすめです。
利益率を上げるのに工夫が必要
一般的なネットショップの場合は、商品を大量に仕入れることによって割引サービスを受けることもできます。
しかし、ドロップシッピングの場合は在庫を保有しないためそのようなサービスが受けられません。
また、商品1点から販売可能となりますが、その分仕入価格が高くなりやすいです。仕入価格が高くなると、利益を出しにくくなってしまいます。
利益率を上げるためには、購入してもらうための工夫が必要です。
例えば、商品をニーズの高いものから厳選して仕入れたり、購入したユーザーに特典を加えたりするなど、付加価値をつけることがポイントになります。
DSP型では販売商品が限定される
DSPと契約する場合、販売商品はDSPに登録されているものに限定されてしまいます。
例えば、販売したい商品がDSPで取り扱われていない場合、DSP経由で販売できなくなります。
DSPにおける注意点を解消するためには、DSPでどのような商品を取り扱っているのかを事前に確認しておくことが大切です。
ドロップシッピングを成功させる5つのポイント

ドロップシッピングを成功させるためには、以下の5つのポイントを押さえておくことが大切です。
1. 利益率を事前にシミュレーションする
既存の商品をドロップシッピングで取り扱う場合、他社と販売する商品が被ってしまう可能性があります。
しかし、だからといって安易に商品価格を下げてしまうと、利益率が上がらず赤字になる恐れもあります。
ドロップシッピングを成功させるためには、利益率について事前にシミュレーションをしておくのがおすすめです。
仕入価格や販売価格、手数料、広告費なども踏まえた上で、どれくらいの利益が残るか計算してみてください。
目安としては利益率が10%を下回ってしまうと、広告費などの影響で赤字になるリスクが考えられます。
2. ニッチなジャンルや特定の顧客層に特化する
成功させるポイントとして、ジャンルや特定の顧客層に特化したネットショップにするのもおすすめです。
お目当ての商品を探しているユーザーが自分のネットショップを訪問した場合でも、商品一覧のラインナップに統一感がないことで商品が見つかりづらくなってしまい、すぐに離脱されてしまうかもしれません。
また、人気のある商品ばかり選定しても、競合が多く価格競争に巻き込まれる傾向にあります。
このようなリスクを回避するためにも、特定の顧客層を意識したニッチなジャンルに特化することで、商品が探しやすくなるだけでなく、商品の魅力も伝わりやすくなり購買意欲を高められます。
例えば、マタニティ用品やペット用品、サウナ用品などは一定の需要がありつつ特定の顧客層を意識したジャンルになるのでおすすめです。
3. 信頼できる仕入先・配送体制を確保する
在庫数の状況や品質管理はサプライヤーに依存することから、徹底した管理体制を敷いている仕入先を見つけておく必要があります。
また、万が一配送の時点で問題が発生した際には、顧客からの信頼を失いかねないため、信頼できる配送体制を確保することも重要です。
信頼できるサプライヤーを選ぶ際には、事前に商品の管理体制や発送までどのような流れで行われているのか、どういったプロセスで顧客の手元にまで届けられるのか、などを確認することが大切です。
納期や在庫管理、返品対応などの詳細な部分まで確認しておいてください。
4. 集客力のあるECサイトやSNS運用に力を入れる
いくらドロップシッピングを始めたからといっても、すぐに顧客が集まるとは限りません。
特にネット上で無数にあるショップの中から、自分が運営するサイトを見つけてもらうのは難しいものです。
そのため、ドロップシッピングにより商品の発送・管理の手間が省けた分、集客に力を入れると良いでしょう。
例えば、ECサイトが検索結果で上位表示されるようにSEO対策を講じたり、SNS(InstagramやX(旧Twitter))を運用して情報の発信や広告の出稿などを行ったりすることで、成果につながりやすくなります。
5. 商品数やラインナップを定期的に見直す
ネットショップを運営するにあたって、商品数やラインナップは定期的に見直すことをおすすめします。
商品数の少ないショップよりも商品数が多いショップのほうが新たな商品の発見につながることもあり、ユーザーは買い物をより楽しめます。
商品数やラインナップを定期的に見直し、充実させていくことで、多くのユーザーが集まるネットショップにしていけるかもしれません。
また、季節やトレンドに合わせた商品を随時取り入れることで、ユーザーがいつアクセスしても新鮮な感覚になります。
いつまで経っても売れない商品も放置せず、売れ筋商品に絞って商品を入れ替えることで、収益の改善につながるでしょう。
まとめ・ドロップシッピングの理解を深めて成功しよう
ドロップシッピングは無在庫販売の一種ということで初期費用を抑えられることから、ネットショップ運営を始めるハードルは低くなります。
一方で、価格競争が起こりやすい点や在庫・品質管理が難しい点などもあることから、取り入れるだけで成功できるものではありません。
今回紹介した注意点や成功ポイントも押さえつつ、ドロップシッピングを成功させましょう。
創業手帳(冊子版)では、ドロップシッピングを含む販売事業に関する様々な情報も掲載しています。仕組みから成功ポイントまで、事業主にとって知りたい情報を取り扱っているので、ぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)