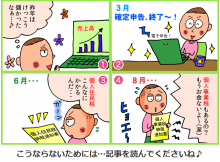青色専従者給与はいくらまでが得?金額を決めるポイントや必要な手続きを解説
青色専従者給与額がいくらまで得なのか把握しよう

生計をともにする親族を従業員に雇用して給与を支払う場合、経費にはできません。
しかし、青色専従者給与制度を活用することで、家族に給与を支給しながら節税効果が期待できます。
家族であっても労働に対する対価は支払う必要があります。いくらまで支払うのがお得なのか気になる人もいるでしょう。
そこで今回は、青色専従者給与額の決め方や節税シミュレーションをはじめ、節税対策の注意点や必要な手続きなどについて紹介します。
創業手帳では、無駄な税金の支払いをしていないかどうか確認できる「税金チェックシート」を無料で提供しています。税金の知識はあるかないかで、場合によっては数十万円も支払い金額に違いが出ることもあります。ぜひこちらをご活用いただき、無駄な出費を減らしていきましょう。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
青色専従者給与とは?

青色専従者給与は、配偶者や子などの親族を従業員にした時、支払った給料を必要経費に算入できる制度です。
本来、生計を一にする親族に支払われる給与は経費にならず、税制上では給与を支払われた家族側の所得とみなされません。
しかし、個人事業主が「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告を行っていれば、青色専従者給与を活用して給与の全額を経費に計上できます。
青色専従者給与を利用するためには、以下の条件を満たさなければなりません。
-
- 青色申告者と生計をともにしている配偶者または親族
- 申告する年の12月末時点で15歳以上になっている
- 申告する年のうち6カ月以上、青色申告者の事業に専従している(学生や他の仕事をしていない)
- 労働の対価として妥当な給与額である
妥当な給与額や上限
青色専従者給与が認められる要件のひとつに、「労働の対価として妥当な給与額である」ことが挙げられます。この給与額に上限は決まっていません。
しかし、仕事内容に対して過度な高額な給与を支給すれば、青色専従者給与を適用できません。
そのため、一般常識の範囲で決めることが求められます。仕事内容から妥当であるのか、他の従業員の給与と比較して高すぎる設定になっていないのかなど、多方面から適切に評価して妥当な金額に設定することがポイントです。
白色申告の事業専従者控除との違い
白色申告には事業専従者控除という制度があります。青色申告と同じく、一定条件を満たしていれば、生計をともにする親族に支払う給与を経費に計上することが可能です。
青色申告との大きな違いは控除額です。
事業専従者控除では、以下2つの条件のうち金額が低いほうを経費にできます。
-
- 事業専従者が事業主の配偶者なら86万円、それ以外の親族なら専従者1人につき50万円
- 「控除前の事業所得等の金額÷(専従者の数+1)」で計算した金額
事業専従者控除では、最大86万円まで控除されます。
しかし、青色事業専従者給与は条件を満たせば給与の全額を経費にできるため、事業専従者控除よりも控除額の差が大きいです。
青色専従者給与の最大のメリットは節税効果!
青色専従者給与を活用する最大のメリットは、事業主の所得税を節税できることです。
本来であれば、生計を一にしている親族に給与を支払っていても事業主の所得として扱われるため、所得税が増えてしまいます。
青色専従者給与を活用して親族に支払った給与を経費にできれば、事業主の所得が分散され、所得税・住民税の軽減につながるのです。
青色専従者給与は給与の全額を経費にできるため、、節税効果も大きくなります。
青色専従者給与額はいくらまでが得なのか?決め方について

何も考えずに青色専従者給与額を設定すると、他の所得控除を活用したほうがお得になったり、給与を受け取った親族の住民税・所得税の負担が増えたりする可能性があるため、慎重に選ぶことが求められます。
なお、配偶者控除の控除額は最大38万円です。専従者に支払う給与が配偶者控除額を上回るようであれば、青色専従者給与のほうが節税効果は大きいといえます。
ただし、専従者の年間収入が100万円以上となれば住民税、103万円以上になると所得税を納税しなければなりません。
この負担を増やさないためには、納税が発生するラインも意識して給与額を設定することが求められます。
青色専従者給与額を設定する手順
青色専従者給与を決定する際は、以下の手順から検討してみてください。
1.年間38万円以上の目安で仮の給与額を設定する
2.仮の給与額に考慮して、事業主の利益を計算する
3.事業税が発生する利益になっているのか、事業主の税率と専従者の税率ができるだけ近くなっているか確認する
事業税は個人事業主にかかる税金です。年間所得が290万円以下であれば事業所得がかかりません。
そのため、専従者給与額を事業者の利益が290万円以下になるように設定すれば、事業税の発生を回避できます。
また、事業主の所得に対する税率と専従者給与の所得に対する税率がなるべく近いかどうかもチェックしてみてください。
大差がないほうが、トータルで見た時の納税額が少なくなるのでお得です。
青色専従者給与額を決めるポイント

青色専従者給与額は妥当性が重要となってくるため、慎重に検討しなければなりません。
ここで、青色専従者給与額を決める上で押さえておきたいポイントを紹介します。
同業同職種の給与を参考にする
青色専従者給与額を設定する際は、同業同職種の給与をチェックしてみてください。
業務内容と給与額の相場が乖離(かいり)していると、一般的に妥当な金額とみなされず、経費計上できません。
同業同職種の賃金水準を参考にすれば、妥当な金額であるかどうかを判断しやすくなります。賃金水準は求人情報などを参考にしてみてください。
源泉徴収が不要な金額にする
専従者の給与を源泉徴収が不要になる金額に設定するのもおすすめです。
所得税や住民税が発生する給与額にしてしまうと、家族に納税義務が発生してしまいます。
また、事業主は源泉徴収する必要があり、手取り金額の計算や納付手続きなどの手間がかかります。
一方、源泉徴収に考慮した金額に設定すれば、煩わしい事務負担も軽減することが可能です。
一般的に源泉徴収が必要となる金額は、社会保険料を控除した月額8万8,000円以上となります。
源泉徴収が発生しない範囲で設定したい時は、給与額を月額8万8,000円以下で検討してみるのがおすすめです。
事業所得や事業主本人の所得に考慮する
事業の売上と事業主と専従者の収入のバランスに考慮して給与額を決めることも大切なポイントです。
事業主の所得が年間290万円以下であれば、事業税がかかりません。290万円になるように専従者の給与を調整すれば、税金の負担を軽減することが可能です。
ただし、専従者の所得が事業主の収入よりも多額になるとバランスが不適正と判断され、経費計上を認めてもらえない可能性があるので注意してください。
例えば、年間600万円の売上が見込まれ、専従者の年間給与が200万円、他の必要経費が250万円と想定します。
この場合、事業主本人の所得は150万円となり、専従者の所得よりも割合が小さくなるので、バランスが不適正と判断される可能性が高いです。
事業税の負担軽減だけではなく、事業主と専従者の所得のバランスが取れているかどうかもチェックしてください。
青色専従者給与の節税シミュレーション

事業主の所得総額は、「所得×所得に応じた税率-所得に応じた控除額」で計算可能です。
以下の条件で、どれだけの節税効果があるのかシミュレーションしてみます。
-
- 年間売上:800万円
- 青色専従者給与:300万円
(800万円-300万円-基礎控除48万円)×20%-42万7,500円=所得総額47万6,500円
上記の条件であれば、青色専従者給与や基礎控除を差し引くと課税所得は452万円です。そのため、2025年1月時点の税率は20%、控除額は42万7,500円になります。
計算すると、所得総額は47万6,500円となりました。
青色専従者給与ではなく配偶者控除38万円の場合、所得総額は以下のようになります。
(800万円-38万円-基礎控除48万円)×23%-63万6,000円=所得総額100万6,200円
配偶者控除と基礎控除額を差し引くと、課税所得は714万円となります。そのため、税率は23%になり、控除額は63万6,000円です。所得総額は100万6,200円となりました。
青色専従者給与は全額経費にできる分、配偶者控除よりも大幅に節税できます。
青色専従者給与適用時と配偶者控除適用時を比較すると、その差は「100万6,200円-47万6,500円=52万9,700円」になります。
実際には他の必要経費や各種所得控除などが適用されるため、細かくシミュレーションを行い、青色専従者給与がお得かどうか判断してください。
青色専従者給与で節税対策する場合の注意点

節税効果に期待できる青色専従者給与を活用する場合、以下のことに注意してください。
給与支給者になると配偶者控除などが適用されない
青色専従者給与によって親族が給与支給者となると、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなります。
親族に支払う給与がこれらの控除額を下回る場合、損をする可能性が高いので注意してください。
各種所得控除の控除額上限は以下のとおりです。
| 所得税の最大控除額 | 住民税最大控除額 | |
| 配偶者控除 | 38万円 (70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円) |
33万円 (70歳以上の老人控除対象配偶者は38万円) |
| 扶養控除 | 38~63万円 | 33~45万円 |
配偶者控除などでどのくらいの控除を受けられるのか確認した上で、青色専従者給与のほうが得なのか検討してみてください。
税負担を比較して検討が必須
青色専従者給与で親族に給与を支払うと、金額次第で専従者に所得税と住民税の納税義務が発生する点にも注意してください。
専従者の年収が100万円以上になると住民税、103万円以上で所得税を納めなければなりません。
所得税には累進課税が採用されているため、収入が多いほど税率が高くなり、納税する所得税の金額が高くなります。
事業主の所得税を減らせたとしても、家族の税金が増えれば、結果的に節税効果が薄れてしまう可能性があります。
専従者が支払う税金と事業主が控除できる金額を比較して、損をしていないか確認してください。
青色専従者給与を支給する場合に必要な手続き

青色専従者給与を支給するためには、事前に3つの手続きを行う必要があります。必要な手続きは以下のとおりです。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の提出
「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」は、親族に支払う給与を青色専従者給与にするために必要な手続きです。
提出期限は、青色専従者給与を経費計上する年の3月15日までです。
開業日が経費計上する年の1月16日以降の場合や、新しく専従者を追加する場合は、開業日や追加した日の2カ月以内に提出してください。
期限内に提出しないと青色専従者給与を経費にできない可能性があります。
提出方法は、納税地を管轄する税務署の窓口や郵送、e-Taxによるオンラインの3通りです。
郵送の場合、一部の対象地域では業務センターが受付先になるので、事前に確認してください。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇用する際に行う手続きです。
給与が少額で源泉徴収が不要な時、法人の一人社長で役員報酬を支払う時、家族を青色専従者として雇用する際に届出が必要になります。
届出する目的は、従業員の給与から源泉徴収するためです。届出を提出すると税務署から送付される所得税の納付用紙で納税を行います。
青色専従者給与を源泉徴収税が発生する月額8万8,000円以上で支給する場合、忘れず届出書を提出をしてください。
提出期限は従業員を雇用して1カ月以内で、所轄の税務署に提出してください。
ただし、開業届に「給与等の支払の状況」を記載している場合は、提出を省略できます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も源泉徴収に関わる手続きです。
源泉徴収税の納付期限は、原則徴収した日の翌月10日となっています。この申請書を提出すると、半年ごと(年2回)にわけてまとめて納付できます。
ただし、特例を利用できるのは、従業員が常時10名未満となる事業所です。
こちらの手続きは提出期限が決まっていないので、任意のタイミングで提出できます。申請書を提出すると、翌月分の給与から特例が適用されます。
提出先は納税地を管轄する税務署です。窓口への持参や郵送、e-Taxによるオンラインで申請できます。
青色専従者給与額を変更する場合に必要な手続き

青色専従者給与は、手続きの際に決めた金額を上回らなければ、毎月異なる給与額でも支給できます。
例えば、業績悪化によって一時的に減額したり、その後元に戻したりすることも容易です。
しかし、届出に記載した金額以上で支給する場合、納税地を管轄する税務署に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければなりません。
届出書には、新しい給料の金額と変更の理由を記載する必要があります。
事業主の所得を不当に減額する目的など不当な理由でない限り、年度の途中でも給与額の変更は可能です。
まとめ・青色専従者給与の活用で節税につなげよう
たとえ家族であっても、一緒に仕事をしていれば給与の支払いが必要です。
しかし、家計が一緒の家族に支払われる所得は経費の対象にならなず、事業主の所得税の負担を大きくしてしまいます。
一方、青色専従者給与の手続きを行い、給与を支給することで経費計上が可能となり、節税効果を得られます。
青色専従者給与は、妥当な金額でないと経費計上が認められないため、節税ばかりを重視しないように注意してください。
なお、配偶者控除や扶養控除のほうがメリットにつながるケースもあるので、節税シミュレーションを行って判断することも大切です。
創業手帳では、「税金チェックシート」を無料で提供しています。税金の知識はあるかないかで、場合によっては数十万円も支払い金額に違いが出ることもあります。ぜひこちらをご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)