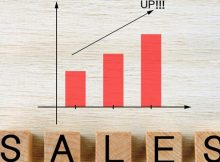販売価格の決め方を解説。商品の価値に合う正しい価格設定とは
販売価格の決め方で売上と利益が変わる?原価や利益・顧客心理を考えて価格設定しよう

販売価格の決め方は事業戦略としてとても重要です。正しい方法で設定しないと売れ行きに悪影響が出ることもあり、利益を得られないこともあります。
販売価格は売るほうも買うほうも納得できるよう、様々な観点から適切に設定しなければいけません。
販売価格の考え方を理解した上で、根拠のある設定を心がけましょう。販売価格を決める際に押さえておきたいことや販売価格の決め方の種類を紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
販売価格の基本

販売価格の決め方を知るためには、販売価格に関する用語と価格設定の基本的な考え方を理解しておくことが大切です。
商品の価格が決まる過程を理解するために、必要な基礎知識として押さえておきましょう。
販売価格の関連用語
販売価格を決める過程では、いくつかの難しい関連用語が出てきます。販売価格を決める際に計算などで使うため、詳しく知っておきたい重要な言葉です。
なんとなく聞いたことがあり漠然と知っているだけでなく、きちんと使いこなせるように理解しておきましょう。
原価・原価率
原価・原価率とは、商品やサービスを提供するためにかかった費用とその比率です。基本的には、販売価格が原価よりも低いと利益は出ません。
また、反対に販売価格が原価を大きく上回れば利益は大きくなります。非常に単純なことですが、販売価格を決める際にこの仕組みはとても重要です。
原価は大きく分けると材料費・労務費・製造費の3種類となります。材料費とは原材料をはじめ、部品や消耗品の購入費用です。
労務費は人件費のことであり、雇用した従業員などにかかる費用を指します。製造費はそのほかの金型・工具・外注費・水道光熱費など、製造に必要な設備や備品の費用です。
原価率はこれらの原価が商品価格の何割占めているかを示す指標となります。ひとつの商品で原価率を下げれば利益の割合が上がりますが、一方で販売価格は高くなります。
このバランスを取り、利益を出しつつも売りやすい価格に設定することが大切です。
利益率
利益率は、販売価格に対して利益の占める割合です。売上に対して何パーセントの利益が残るかがわかります。
利益率は販売価格と原価から計算できますが、それをもとに販売価格を決定する際に原価と利益率を使う方法もあります。
利益率の計算式は、利益÷販売価格×100(%)となるため、販売価格を出す場合の計算式は、原価÷(100‐利益率)です。
販売価格を決める3つの考え方
販売価格を決める際には、主に以下の3つの考え方を押さえておく必要があります。
販売価格は利益を出すために決めますが、売れるかどうかも考えておかなければいけません。
そのため、販売価格を決める際には以下の3つの考え方をすべてバランス良く取り入れることが必要です。
ひとつの方法の問題点をほかの方法で補うことによって、利益を出せてよく売れる販売価格を決めてください。
原価を商品価格の何割にするか決める
原価をベースにする考え方で、商品の販売価格の何割を原価にするか、つまり原価率を使う方法です。
原価をもとに販売価格を決めるため、計算が単純で誰でも価格設定がしやすい方法だといえます。
しかし、その反面、原価や設定した原価率によっては販売価格が高くなり、競合に価格競争で負けることもあります。
また、購入する側の感覚や相場を反映していないため、市場価格とかけ離れ、顧客から敬遠されるかもしれません。
どれくらい利益がほしいか決める
販売価格を決める際には、利益をベースに考えることもできます。この場合には、利益率をもとに販売価格を決めていきます。
上記で述べた計算式を利用することで、比較的簡単に価格設定が可能です。
ただし、この方法は売る側の希望だけを反映した方法で、顧客の希望や市場価格相場などが反映されていません。
そのため、原価をもとにする考え方と同じリスクを負うことになります。
競合や市場と比較する
競合や市場と比較することも販売価格を決める際には重要です。この考え方を取り入れることで、上記2つの考え方では不足している部分を埋められるでしょう。
自社商品と同じジャンルの市場を見て、競合の商品や販売価格と比較すれば、いくらなら売れるか予測しやすく、価格相場も反映できます。
ただし、この方法は上記2つの考え方よりも戦略が必要となります。
競合と比較はしても、同じ金額に揃えるのではなく、競合や市場を参考にいくらにしたら市場で勝てるか検討することが大切です。
競合が販売しているのと同じような商品を、競合より高く販売すると売れないこともあります。また、安すぎる価格も品質を疑われ、敬遠されるかもしれません。
しかし、だからといって競合と同じ金額にしても、後発となる自社商品は注目されないこともあります。
販売価格の決め方-基本的な方法5つ-

販売価格の決め方にはいくつもの方法があります。販売価格は、上記の考え方も抑えながら、実際にはマーケティング戦略を踏まえて決定していきます。
まずは、基本となる5つの価格設定方法をチェックしてみましょう。どちらかというとシステマティックに設定できる方法です。
コストプラス法
コストプラス法とは、一定の利益率や利益額を商品の製造コストに加えて、販売価格を設定する方法です。コストプラス法の計算式は、製造原価+利益です。
コストを上回る適正価格を出しやすく、シンプルに価格を決められる反面、顧客の希望や競合、市場の状況は反映されません。
そのため、コストプラス法を使う際には、商品に付加価値を付け、それを顧客に伝えて価格に納得してもらうことが大切です。
マークアップ法
マークアップ法とは、卸売業者や小売店が行う販売価格の決定方法です。製造コストをもとにするコストプラス法の変種であり、製造原価ではなく仕入れ原価をもとにします。
基本的にはコストプラス法と同じ仕組みの計算方法であり、業種によって使い分けます。
市場価格追随法
市場価格追随法は、市場に出回っている競合の商品を基準に価格を決める方法です。
すでに市場に出ている競合の商品と差別化できる場合には、競合以上の価格を設定し、売上を増やせます。
ただし、競合との差別化ができない商品は価格を下げて設定しなければならず、売れ残るリスクも出てきます。
プライスリーダー追随法
市場価格追随法と同じく、同業者の価格を基準にする方法ですが、プライスリーダー追随法では業界に大きな影響力を持つリーダー企業の販売価格を基準とします。
市場で高いシェアを持ち、価格への影響力が高い企業に追随して価格を決める方法です。
市場でシェアを持つリーダー企業は顧客の信頼も厚く、その企業の価格より高い金額を付けても売れません。
また、リーダー企業より安い価格にすれば販売数は稼げますが、その場合にはコストも抑えなければ利益が減ります。
そのため、リーダー企業の力が大きいジャンルでは、よほど差別化された商品でない限り価格設定も追随するしかありません。
この方法を用いるかどうかを決める際には、自社商品が参入する業界にプライスリーダーがいるか、影響力はどれくらいあるかを見極める必要があります。
慣習価格法
慣習価格法とは、長期にわたって慣習的に決められてきた価格に従って設定する方法です。伝統的な価格帯のあるジャンルの商品を販売する場合に用いられます。
例えば、ペットボトルの飲み物やガムなどは慣習価格のある商品です。こうした商品ジャンルは、その価格より安い価格で販売しても販売数が伸びにくい特徴を持っています。
また、反対に値上げしても、品質が同じ場合には敬遠されて売れにくくなります。
販売価格の決め方-消費者心理に基づいた方法4つ-

販売価格の決め方には、消費者心理に基づいて柔軟に設定する方法もあります。
商品の独自性や価格相場も大切ですが、それ以外で賢く利益を上げる戦略も取り入れてください。
名声価格法
名声価格法とは、品質の違いや付加価値の違いを打ち出し、その違いや特徴をプレミア化してあえて高い販売価格を付ける方法です。
ぜいたく品や希少価値の高い商品などで、この販売価格の決め方は功を奏します。
消費者は価格が安いものばかり購入するのではなく、価格が高く品質も高いと感じる商品にも魅力を感じやすいものです。
商品ジャンルによっては、普通の価格の商品以上に高い価格の商品をほしいと感じることもあります。
ブランド品や宝石などに効果的ですが、ラインナップの中に特別なシリーズやプレミアムブランドを作ることでも実現できる方法です。
端数価格
端数価格とは、1,000円、2,000円のようにキリの良い価格ではなく、980円、1,980円のようにほんの少しだけ値下げして端数を作る方法です。
1,000円と980円ではほんの20円の違いですが、980円のほうがお買い得に見えるため、多くの店でこうした価格設定を行っています。
商品の品質や独自性に関係なく、消費者心理に基づき売上を伸ばすためのちょっとした工夫です。
段階価格
段階価格とは、複数のラインナップで活用できる販売価格の決め方です。
この方法を用いることで、一番売りたい商品や一番利益率の良い商品をより効果的に販売できるでしょう。
段階価格は、人の心理である「極端の回避性」を使った戦略です。
人は「松竹梅」のような3段階に分かれた選択肢から選ぶ時に、上と下を避けて真ん中の商品を選びやすい心理を持っています。
そのため、ある商品を売りたい場合には、その価格より高い商品とその価格より安い商品を一緒に並べるのが効果的です。
抱き合わせ価格
抱き合わせ価格とは、商品を組み合わせることで割引する販売価格の設定方法です。メインの商品とサブの商品などを組み合わせます。
セット価格で販売することで、割引するため単価は下がりますが、客単価がアップするため売上も上がります。
販売価格の決め方の注意点

販売価格を決める際には、自社の利益や顧客・消費者のニーズなど、いくつもの観点から価格を検証することが必要です。
価格設定をしたら、以下の注意点を参考に適切な販売価格が設定できているか確認してみてください。
顧客目線で検討できているか
販売価格の決め方の重要なポイントは、顧客や消費者が購入したいと思うかどうかです。
どれくらい良い商品やサービスだったとしても、それに見合った価格でなければ消費者は購入したいとは思わないでしょう。
販売価格を高くすれば販売した時の利益は増えますが、消費者が手に取らなければ、もとも子もありません。
また、販売価格と商品が合っているだけでなく、お買い得であることが伝わるようなPRをすることも大切です。
販売価格が妥当である、お買い得であると感じさせることで売上は伸びます。
市場価格とかけ離れていないか
販売価格を決める上では、市場価格との乖離(かいり)も気にしたいポイントです。
市場価格と自社の商品価格がかけ離れていた場合、高すぎても安すぎても売上のチャンスを逃しやすくなります。
販売価格が市場価格より高すぎた場合には顧客は競合の商品へ流れてしまい、安すぎても品質を疑われる恐れがあります。
顧客目線で価格を決めるとできるだけ安くしようと思いがちですが、ブランディングや信頼性という点では市場とのバランスを見ることも忘れてはなりません。
仕入れや時給以外にかかった費用は反映されているか
販売価格を決める際には、商品を販売するまでにかかった費用をすべて反映する必要があります。
特に、材料費や仕入れにかかった費用、時給などの人件費以外にかかった費用も含んで計算することが大切です。
営業費や広告宣伝費など、目に見えにくい費用も含めて反映されているか、最終チェックしてください。
また、原材料費などは不景気や気候、社会情勢などの影響で高騰するリスクもあります。そのため、ある程度のリスクも見据えて見積もっておくことも大切です。
さらに、販売したあとにアフターサービスなどが必要な商品の場合には、その費用も原価として組み込む必要があります。
まとめ
販売価格は単純に原価や利益率だけで決められるものではありません。
販売価格の決め方にはいくつもの種類があり、商品のジャンルや市場の状況などを総合的に見てどのような方法で決めるか考える必要があります。
一度決めた販売価格はなかなか変えられるものではなく、最初に安く設定してしまうとあとから値上げするのは大変です。
販売価格を決める際には、無理なく販売し続けられるか十分に検討しましょう。
(編集:創業手帳編集部)