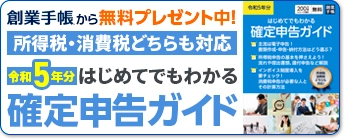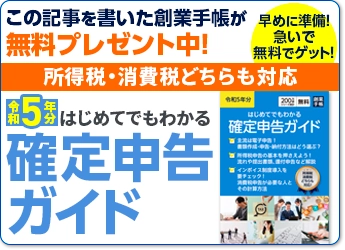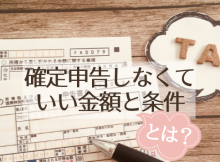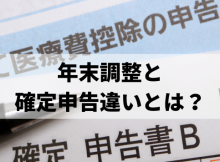【2025年分最新】個人事業主・フリーランスに年末調整が必要なケースを徹底解説!
個人事業主・フリーランスが年末調整する場合や確定申告との違い、基本ルールとは?

●個人事業主・フリーランスの年末調整が必要なケース:従業員や青色事業専従者がいる場合。
●年末調整と確定申告の違い:年末調整は会社員向け、個人事業主は確定申告が基本。
●年末調整の手続きの流れと方法:必要書類の準備、紙ベース・電子申請の手順とメリットを解説。
●年末調整を怠るリスク:罰則や従業員との信頼損失の可能性。
「独立したけど年末調整は必要なの?」
「年末調整と確定申告の違いは?」
個人事業主やフリーランスになると、上記のような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。また、確定申告との違いについて悩んでいる方も少なくありません。
個人事業主・フリーランスは、原則として年末調整の対応は不要です。ただし、従業員や家族を雇っている場合は、雇用主として従業員分の年末調整を行う必要があります。
この記事では、個人事業主・フリーランスが押さえておきたい年末調整の対応要否や手続き、注意点などを解説します。また、2025年(令和7年)税制改正による最新情報も反映しているので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、確定申告とどちらをすべきかで悩んでいるで悩んでいる方には、創業手帳が提供している、確定申告の流れと最新情報を掲載した「確定申告ガイド」がおすすめです。個人事業主やフリーランスだけでなく、法人の経営者が読んでも重要なポイントを理解できます。無料で利用できますので、ぜひ活用してみてください。副業を始めた方にもおすすめです。
この記事の目次 ただし、会社員や公務員から個人事業主・フリーランスに転向した人が税金の計算をする場合は、別の手続きが必要です。以下に、年末調整を行うべき人の詳細や、個人事業主・フリーランスがとるべき対応について紹介します。また、従業員や家族を雇っている場合には、雇用者としての年末調整が発生するケースもあります。 以下の表で、自分がどの立場に該当するかを確認してみましょう。 このように、「自分が給与を受ける側なのか」「支払う側なのか」で、必要な手続きが変わります。次に、それぞれの立場ごとにどのような対応が必要なのかを詳しく見ていきましょう。 年末調整は会社員の所得税・住民税の計算に必要な手続きです。つまり、個人事業主・フリーランスは基本的に年末調整を必要としません。 会社員は、会社がまとめて税金の計算をして納税してくれるため、年末調整を行うことになります。 ただし、中には会社員でも年末調整が必要ない人、年末調整ではなく確定申告をすべき人もいるので、最終的には個々の状況で判断することが必要です。 会社員の年末調整にあたる個人事業主・フリーランスの手続きは、確定申告です。税務署に税金の計算をして届け出る手続きで、年間事業所得が20万円を超えたら必要になります。 会社員のように会社が取りまとめることはないため、個人事業主・フリーランスは一人ひとりが自分で税金の計算と届け出を行います。 確定申告が必要な人が申告を忘れると余分に課税されるなどのペナルティも発生するため、責任を持ち自分で管理して毎年申告する必要があります。 基本的に年末調整をしなくていい個人事業主・フリーランスですが、従業員を雇っている場合は従業員に対する年末調整が必要です。 個人事業主・フリーランスで雇用主となる場合は、アルバイトやパート、従業員に対して年末調整を行う義務があります。従業員に年末調整の書類を配布したり、所得税を正しく計算したりしなくてはなりません。 個人事業主・フリーランスの人は自分の年末調整ではなく、従業員に対する年末調整を忘れないように注意しましょう。 個人事業主・フリーランスで青色事業専従者の雇用主となる人も年末調整が必要です。 青色事業専従者とは、青色申告を用いて確定申告をしている場合に、配偶者や親族を従業員として雇う際の呼び名です。 青色事業専従者がいる個人事業主・フリーランスは、他の従業員と同じように年末調整を行いましょう。 年末調整は本来、給与所得者の税額を精算する手続きですが、これらのケースでは事業所得分の確定申告と合わせて2つの手続きが必要です。 それぞれのケースについて具体的に確認しましょう。 個人事業主・フリーランスがアルバイト収入を得た場合、年末調整が必要となります。これは、源泉徴収が義務付けられる月額8万8,000円超の給与収入を得ているケースです。 月額8万8,000円を超えたアルバイト収入があれば、毎月の給与から源泉徴収が行われます。年末調整の対象にもなるので、勤め先から書類を配られ次第記入・提出し、控除の適用や税金の還付を受けましょう。 年末調整と確定申告の両方をする場合、確定申告時に源泉徴収票が必要です。源泉徴収票からの情報を申告書に転記するので、年末調整が終わってから確定申告をすることになります。 アルバイト収入が月額8万8,000円未満であれば会社側は源泉徴収をする必要がありません。年末調整も行われない可能性が高いので、個人事業の確定申告のみを行いましょう。 個人事業主やフリーランスとして働いてきて、途中で会社員になった場合にも年末調整の対象となります。 この場合には、個人事業主・フリーランスとしての事業収入と、その後に会社員としてもらった給料の2つが課税対象となり、確定申告もしなければいけません。 会社では、雇用されてから年末まで働いた分を年末調整し、それ以前の事業収入は会社の年末調整後、源泉徴収票を持って確定申告に行くことになります。 令和7年度税制改正により2025年(令和7年分の)年末調整で変更された点をまとめました。 基礎控除・給与所得控除が引き上げられたため、課税所得が小さくなり、税負担の軽減で手取りが増える可能性があります。また、扶養親族・配偶者の所得上限が上がり、働き控えを抑えた働きやすい環境づくりにつながっています。 特定親族特別控除は、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族がいるものを対象にした控除です。従来の扶養控除が対象外となっていた親族の負担を軽減するために創設されました。 年末調整を行うにあたって知っておきたい基礎知識や、年末調整の流れなどを紹介します。 年末調整は、従業員の所得税を正しく納付するために欠かせない作業です。それだけでなく、住民税の算出にも深く関わっています。 年末調整が各税金にどう関係しているか、正しく理解しておきましょう。 年末調整は、所得税の過不足を調整したり、課税所得に見合った住民税を適用したりするための大切な作業です。 個人事業主・フリーランスで雇用主の場合は、従業員の年末調整を実施し、従業員が正当な税金額を納付できるよう努めなくてはなりません。 個人事業やフリーランスの雇用主が年末調整を行う際、全体のスケジュールから流れを把握するのがおすすめです。以下に年末調整に関わる作業をまとめました。 (特例適用事業者は1月20日まで) 毎月の給与からの源泉徴収に始まり、10月頃から本格的に年末調整の準備を進めていきます。書類の配布と回収、チェックから計算までを雇用主が行わなくてはなりません。 従業員の数や事業の忙しさによってスケジュールを調整し、余裕を持って年末調整に取りかかりましょう。 年末調整では、従業員に記入してもらう書類の準備が必須です。 従業員に記入・提出を求める年末調整の主な書類は以下となります。 住宅借入金等特別控除申告書、保険料控除申告書に添付する控除証明書は、従業員自身で準備し、提出してもらいます。当年に入社した従業員であれば、前職の源泉徴収票も出してもらいましょう。 また、2025年からは基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書として給与所得者の特定親族特別控除申告書が導入されます。この様式により、基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除・特定親族控除といった4つの控除申告を1つの書類で申告できます。 なお、「年末調整に係る定額減税のための申告書」は令和6年限定であり、令和7年は対応不要です。 年末調整は旧来通り紙ベースで行うか、電子申請の2種類からやり方を選択できます。各メリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を導入しましょう。 書類の準備から計算までを紙ベースで行う方法です。紙ベースの場合は配布・回収・確認といった工程に時間がかかるため、余裕をもって取り組む必要があります。 紙ベースのメリットは、従業員のITリテラシーを問わないことで、手続きのハードルを低くできる点です。電子申請は前提としてツールの利用方法を理解しなくてはならず、年末調整を億劫に感じる要因になります。 一方で、紙での申請は税務署に用紙をもらう・郵送してもらうといった手間が生じる方法です。配布のタイミングや回収が遅れると期日に間に合わない恐れがあるので、早めの準備が欠かせません。 年末調整は、電子申請でも対応できます。書類の廃止により、配布や回収にかかるコストを大幅に削減可能です。 年末調整に必要な情報がデータで送受信でき、計算も自動化されるので、従業員と会社の双方で確認・計算の手間が省けます。電子化によって入力漏れなどの人的ミスの抑制にも効果的です。 反面、ソフトのインストール、保険会社との電子データ連携など、従業員側に求める導入手続きも増えます。ITに不慣れな従業員には負担になりかねません。 個人事業主・フリーランスの場合は小規模であるケースが多いので、電子化にかかる費用や手間が見合っているかも踏まえて検討した方がいいでしょう。 個人事業主・フリーランスであっても、雇用している従業員がいる場合は年末調整の実施義務があります。仮に忘れた場合、どんなリスクが考えられるのでしょうか。 年末調整は、所得税法で定められた雇用主の義務であるため、正当な理由なく拒否すれば罰則が課せられる可能性があります。場合によっては10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはそれらが併科されることもあるのです。 個人事業主やフリーランスが従業員を雇用する場合は、年末調整の義務について正しく理解し、必要性を十分に把握しておきましょう。 年末調整を忘れたり拒否したりすると、従業員から法律による義務を怠るような事業主であると判断されます。結果起こりやすくなるのは、信頼関係の悪化や離職です。 個人事業主やフリーランスの場合、少数精鋭の事業展開も珍しくありません。事業を支える従業員の信頼を損ねてしまえば、今後の発展に致命傷となるでしょう。 事業の発展を妨げる原因を作らないためにも、従業員の年末調整は欠かさず実施してください。 両者を混同してしまうケースも少なくないため、どのような違いがあるかを明確にしておきましょう。 年末調整と確定申告は、それぞれ誰が行うべきものなのかが違います。年末調整は従業員を雇っている会社や個人事業主・フリーランス、確定申告は所得がある個人事業主・フリーランスがすべきものです。 個人事業主・フリーランスがどちらをすべきか迷う場合も、誰が行うものであるかから判断すれば容易に判別できます。 従業員の雇用者がいれば年末調整が必要になり、自分一人しかいなければ確定申告だけで構いません。 年末調整と確定申告で適用される所得控除には、一部違うものがあります。年末調整で適用されない場合、個人で確定申告が必要です。 年末調整で適用されず、確定申告のみでしか使えないのは以下の控除です。 寄附金控除のうち、ふるさと納税で支払った分はワンストップ特例制度に申請できます。申請が通れば年末調整で控除を受けることが可能です。 年末調整では処理できない控除については確定申告が必須となります。個人事業主・フリーランスの雇用主は従業員への説明を徹底しましょう。 個人事業主やフリーランスから寄せられる、年末調整に関するよくある質問をまとめました。 原則として、個人事業主・フリーランスは自分で確定申告を行うため、年末調整は不要です。 ただし、従業員や青色事業専従者に給与を支払っている場合は、雇用者として従業員分の年末調整を行う必要があります。 アルバイトにより給与を受け取っている場合は、給与所得に該当するため、勤務先で年末調整が行われます。ただし、フリーランスとしての収入である事業所得は確定申告です。 また、1年に給与所得と事業所得の両方がある人は、勤務先での年末調整と自分の確定申告をそれぞれ行いましょう どちらも所得税に関わる手続きですが、大きな違いは「誰が」行う手続きかです。 年末調整は雇用主(会社や個人事業主)が、従業員の代わりに所得税額の過不足を計算します。一方で、確定申告は個人事業主・フリーランスである本人が、自ら所得税の金額を確定させるために行う手続きです。 個人事業主・フリーランスにとって年末調整は基本的に必要ありませんが、例外的に必要な人もいます。 一年の途中で給与所得が発生した場合は、年末調整が必要になるため注意してください。また、従業員を雇用する個人事業主は、従業員の分を年末調整する必要があります。 年末調整は会社員のものと思われがちですが、必要となった際に慌てないためにも、自分に無関係とは思わないほうがいいでしょう。 また、確定申告の全体の流れと最新分の申請時に知っておくべき情報を盛り込んだ「確定申告ガイド」を作成いたしました。個人事業主やフリーランスの方はもちろん、法人社長もこの確定申告ガイドで大まかな流れや注意点を押さえておくことができます。無料でご覧いただけますのでぜひご活用ください。 (編集:創業手帳編集部)

 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
個人事業主・フリーランスは基本的に年末調整は必要ない

個人事業主やフリーランスの方は、原則として年末調整を行う必要はありません。年末調整は、基本的に雇用されている会社員向けの手続きであるためです。
状況
年末調整の要否
対応方法
自分一人で事業
不要
確定申告
従業員を雇っている
必要
雇用者として従業員分の年末調整
青色事業専従者がいる
必要
専従者を従業員として年末調整
アルバイトなど給与所得がある
源泉徴収ありの場合に必要
勤務先にて年末調整+自分でも確定申告を行う
年の途中で会社員に復帰
必要
勤務先にて年末調整+個人で確定申告を行う場合もある
会社員は年末調整が必要
個人事業主・フリーランスは確定申告が必要
個人事業主・フリーランスで従業員がいる場合は年末調整が必要
青色事業専従者がいる場合は年末調整が必要
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」個人事業主・フリーランスでも自分の年末調整が必要になるケース
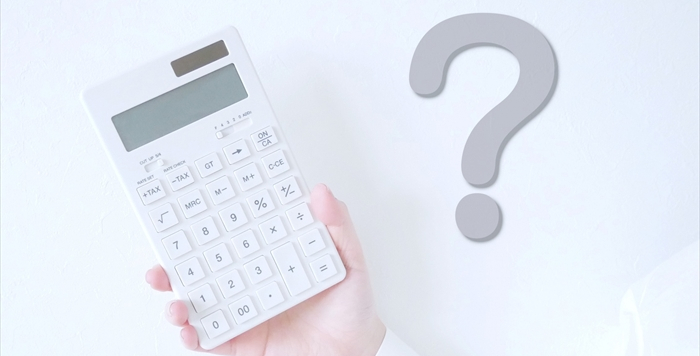
前の表で紹介したとおり、個人事業主やフリーランスでも、アルバイトなどで給与所得を得ている場合や年の途中で会社員に戻った場合には、自分自身の年末調整が必要になることもあります。源泉徴収ありのアルバイトをした場合
年の途中で会社員に戻った場合
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」【2025年】年末調整の変更点・注意点
項目
変更点
基礎控除
合計所得金額に応じて段階的に見直され、最大95万円に引き上げ
給与所得控除
最低保障額が55万円から65万円に引き上げ
扶養控除
合計所得金額が48万円以下から58万円以下へ変更
配偶者控除
合計所得金額が48万円超〜133万円以下から、58万円超〜133万円以下に引き上げ
特定親族特別控除
創設
個人事業主・フリーランスの雇用主が年末調整をするには?基本や流れ
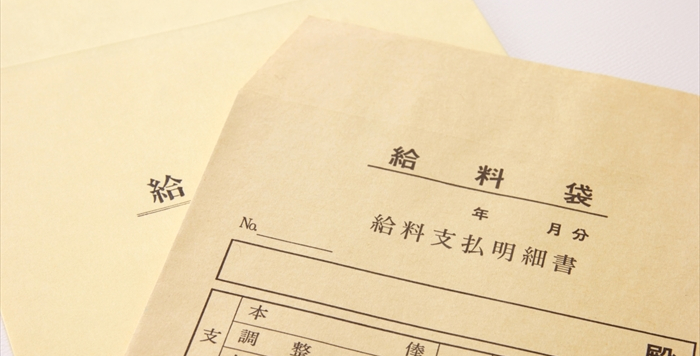
雇用主の立場にある個人事業主・フリーランスは、自分の収入に対してではなく、従業員の年末調整を行います年末調整の基本的な仕組み
税金
年末調整との関係
所得税
給与から源泉徴収されている税金。年末調整で1年間の所得税を改めて計算し、過不足を調整した上で正しい額を納税する。
住民税
前年の課税所得に基づいて決まる税金。課税所得は各種控除が適用されたあとの金額であるため、年末調整による控除の適用がなければ課税所得が増え、住民税も高まる恐れがある。
年末調整の流れとスケジュール
時期
概要
1月~
毎月の給与から源泉徴収する
10月~11月
年末調整に必要な各申告書を従業員に配る
11月上旬まで
当年入社の従業員から前社の源泉徴収票を回収する
11月中
各申告書を従業員から回収し、内容を確認する
12月中旬まで
従業員ごとの所得税を計算する
12月中の給与支給日
源泉徴収票の配布と、所得税の過不足を還付または徴収する
翌年1月10日まで
所得税徴収高計算書(納付書)を作成し、所得税を納付する
翌年1月31日まで
税務署に給与の源泉徴収票と法定調書合計票を、市区町村へ給与支払報告書をそれぞれ提出する
年末調整に必要な書類
年末調整のやり方
年末調整を紙ベースで行う場合
年末調整を電子申請で行う場合
個人事業主・フリーランスが従業員の年末調整を怠るリスク
罰金や罰則が生じる恐れがある
従業員との信頼関係が崩れる
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」個人事業主が知っておきたい年末調整と確定申告の違い
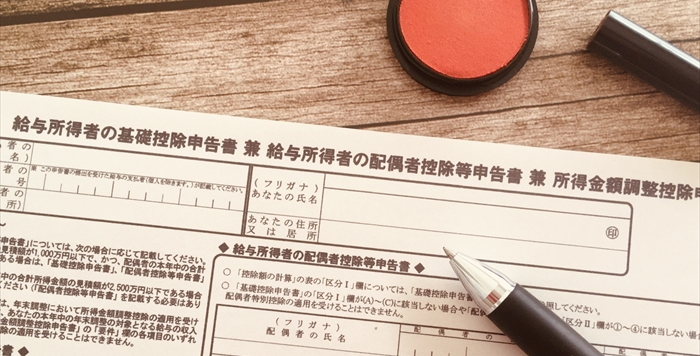
個人事業主やフリーランスには基本的に年末調整は必要なく、確定申告をしなくてはなりません。誰が行うかの違い
適用される控除の違い
控除
概要
医療費控除
最高で200万円まで、自己負担した年間医療費の一部に相当する額が控除される
寄附金控除
ふるさと納税を含む寄附金の一部に相当する額が控除される(ワンストップ特例の適用者であればふるさと納税分は年末調整の対象になる)
雑損控除
災害、盗難、横領により対象資産が損害を受けた際に一定金額が控除される
個人事業主・フリーランスの年末調整に関するよくある質問
個人事業主にも年末調整は必要ですか?
フリーランスがアルバイトしている場合、年末調整は必要ですか?
年末調整と確定申告の違いは簡単は何ですか?
 【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の変更点も記載!「確定申告ガイド」まとめ・個人事業主でも年末調整が必要な場合があるため注意!