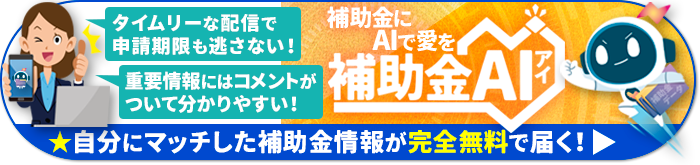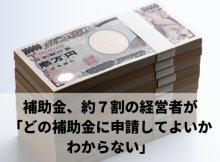健康保険料が2026年にも値上げ!子ども・子育て支援金の負担を解説
2026年4月から「独身税」がスタートする予定

2026年4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。社会全体で子ども・子育て世帯を支援するための財源に充てられる予定で、少子高齢化に歯止めをかける役割が期待されています。
子ども・子育て支援金は、公的医療保険に上乗せされる形で徴収される予定です。社会保険料の負担が増えるうえに、子どもがいない世帯にとっては給付を受けられないことから、「独身税」とも呼ばれています。
今回は、健康保険料が2026年に値上げされる要因である「子ども・子育て支援金」の概要や、具体的な負担額などを解説します。企業が取り組むべきことも解説するため、負担増に負けない事業運営にお役立てください。
創業手帳では、社員の育児支援や正社員化にも使える「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布中です。採用だけに限らず、雇用に関する助成金を社労士が厳選しました。はじめてでもわかりやすく解説しています。詳しくは以下のバナーから。
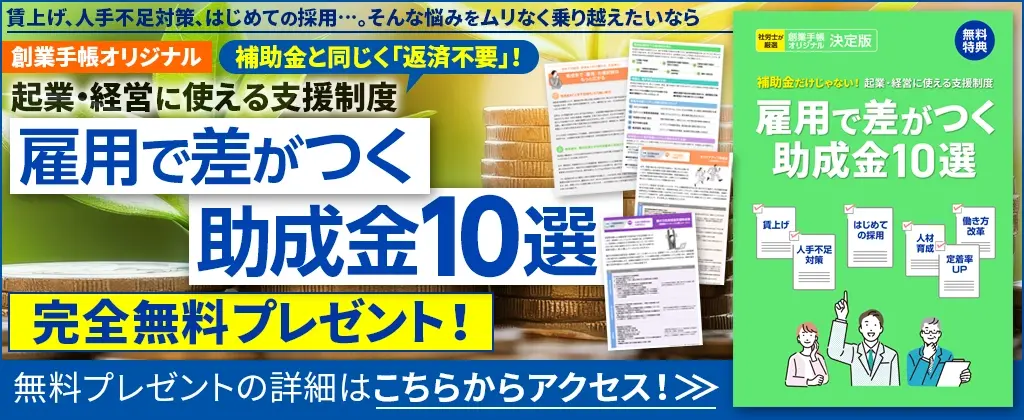
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
子ども・子育て支援金(独身税)とは何か

日本は少子高齢化が進展しており、経済の停滞や国力の減退、社会保険制度の改悪などが問題視されています。「子ども・子育て支援金制度」は少子化対策を強化する目的で創設され、全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるための制度です。
子ども・子育て支援金は、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。現役世代だけでなく、高齢者や企業を含むすべての世代と経済主体が負担します。支援金は児童手当の拡充や妊婦のための支援給付、共働き・共育てを推進するための経済支援などの財源に充てられる予定です。
すべての世代と経済主体が支援金を負担する一方で、受給者は子育て世帯に限られるため、「独身税」とも呼ばれています。
ただし、給付を直接受けない方も、ただ単に負担を強いられるだけではありません。少子化が改善して経済・社会システムや地域社会の維持につながれば、安心して医療を受けたり年金を受給できたりする結果につながるためです。
子ども・子育て支援金を負担する対象者

子ども・子育て支援金を負担する対象者は、全世代・全経済主体です。全国民・全企業が、医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金を拠出します。
| 被用者保険の加入者(会社員、公務員など) | 従業員(被保険者)事業主が保険料を折半して負担する |
| 国民健康保険の加入者(自営業者など) | 国民健康保険料とあわせて負担する(子どものいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳までの子どもに係る支援金の均等割額は軽減) |
| 後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の高齢者) | 後期高齢者医療保険料とあわせて負担する(低所得者軽減措置が講じられる) |
企業(事業主)も、被用者保険に加入している従業員の支援金を折半で負担します。
子ども・子育て支援金は、社会全体で子育て世帯を支援して、少子化を抑制するための制度です。そのため、特定の世代や経済主体に限定されることなく、医療保険の加入者全体で負担する仕組みとなっているのです。
子ども・子育て支援金が導入された背景

少子化を放置すると、ますます経済の停滞や国力の減退が進んでしまいます。企業としても労働力を確保するのが困難になり、経済に悪影響が出てしまうでしょう。
以下で、子ども・子育て支援金が導入された背景を具体的に解説します。
少子化・人口減少に対応するため
日本は深刻な少子化と人口減少に直面しており、国力の減退や社会保険制度の改悪など、さまざまな問題が顕在化しています。政府は2030年代に入るまでの期間を「少子化傾向を反転できるかのラストチャンス」と認識しており、子育て支援の強化に力を入れています。
社会全体で子どもや子育て世帯を応援する環境を整備すれば、子育てに対してポジティブな感情が生まれ、出生率が上向く可能性が期待できるでしょう。
少子化・人口減少に歯止めをかければ、経済・社会システムを維持でき、国民皆保険制度を持続できます。全国民が安心して生活できる環境を作るためにも、全世代・全経済主体が連帯して負担する仕組みとして子ども・子育て支援金が導入されました。
子育て世帯への給付を拡充するため
令和5年12月に閣議決定された「こども未来戦略」において、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」が取りまとめられました。
子ども・子育て支援金は、児童手当の抜本的な拡充や妊婦のための支援給付など、子育て世帯への経済的支援に充てられる予定です。経済的な支援を行うことで、経済的な理由で出産を諦めている世帯が減り、出生率の上昇につながる可能性があります。
他にも、未就園児を保育施設で時間単位で預けられる「こども誰でも通園制度」のように、仕事と育児を両立するための制度作りにも充てられます。一連の支援を通じて、子育て中やこれから結婚・子育てを考える若い世代が、出産や子育てに対して前向きになることが期待できるでしょう。
子ども・子育て支援金の負担額

子ども家庭庁の資料によると、子ども・子育て支援金の負担額は、以下のように試算されています。
| 全制度平均 | 被用者保険(会社員、公務員など) | 国民健康保険(自営業者など) | 後期高齢者医療制度(75歳以上の高齢者) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者 | 被保険者 | 加入者 | 被保険者 | |||||
| 2026年 | 月額約250円 | 月額約300円 | 月額約450円 | 月額約250円 | 月額約350円(※) | 月額約200円 | ||
| 2027年 | 月額約350円 | 月額約400円 | 月額約600円 | 月額約300円 | 月額約450円(※) | 月額約250円 | ||
| 2028年 | 月額約450円 | 月額約500円 | 月額約800円 | 月額約400円 | 月額約600円(※) | 月額約350円 | ||
※国民健康保険は1世帯あたり
なお、年収によって負担額は変動します。2028年度における、会社員・公務員の負担額を年収別にまとめました。
- 年収200万円:月額約350円
- 年収400万円:約650円
- 年収600万円:約1,000円
- 年収800万円:約1,350円
- 年収1,000万円:約1,650円
全制度平均で見ると、年間の負担額は3,000~5,400円程度です。しかし、年収が高い方の場合は年間で1万円を超える負担増となります。
子ども・子育て支援金は何に充てられるのか

実際に、徴収された子ども・子育て支援金は、どのような施策に充てられるのかを見ていきましょう。
児童手当の抜本的な拡充
2024年10月より、以下のように児童手当が拡充されています。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象期間の延長(中学生までだった支給対象期間が、高校生年代(18歳年度末まで)まで延長)
- 第3子以降の支給額を、年齢に関わらず月額3万円に増額
経済的支援の拡充により、子育て世帯の経済的な懸念を払しょくすることが目指されています。子どもが3人いる家庭の場合、児童手当の支給額は総額で最大400万円増となり、1,100万円となる試算も示されています。
なお、「拡充」とは異なりますが、児童手当の支払いが年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されました。
妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金の制度化)
妊娠期の負担を軽減するために、妊婦のための支援給付が盛り込まれています。妊娠・出産時から切れ目のない支援を行うための給付として、2025年4月より以下のような給付が始まりました。
- 妊娠届出時に「出産応援給付金」として5万円を支給
- 出産後には子育て応援給付金(5万円×子の人数)を支給
全体として、妊娠・出産時に10万円の経済支援が行われるとされています。産前産後休業中や育児休業中は収入が減少してしまいますが、これらの給付金には収入減少期の負担を軽減する目的もあります。
乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
「こども誰でも通園制度」とは、保護者の就労要件を問わず、保育所を利用できるようにする制度です。保育所に通っていない生後6ヶ月から3歳未満の子どもがいる場合、月一定時間までの利用限度額の中で、柔軟に通園が可能になります。
2025年度に制度化され、2026年度より全国の自治体で実施される予定です。
保育所に子どもを預けられないと、育児休業期間を延長したり、場合によっては退職を余儀なくされることがあります。働ける意思と能力を持っているにもかかわらず、保育所を利用できないことで諦めてしまうのは、企業にとっても国にとっても損失です。
そこで、柔軟に子どもを保育所に預けられる制度を整備し、仕事と家庭の両立を支援する枠組みが整備されました。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付とは、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付の上乗せとして支給される給付金です。育児休業給付と合わせて手取り10割相当となるように給付率が引き上げられ、子育てに関する経済的な不安を軽減する目的があります。
2025年4月から開始されており、給付期間は最大で28日間です。男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得したとき、給付金の対象となります。
育児時短就業給付
育児時短就業給付とは、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。短時間勤務になると収入が減少しますが、その間の収入減の一部を補填する役割があります。
また、妊娠や育児などを理由に従業員が離職してしまうことを防ぐ役割も期待されています。短時間勤務を選択しやすくし、柔軟な働き方の実現を支援することにより、就労の継続を実現できるでしょう。
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置」とは、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度です。
育児期間中、収入が減少している中で国民健康保険料を納めるのは、決して小さくない負担です。そこで、子が1歳になるまでの期間は国民年金保険料を免除し、経済的な負担を軽減する制度が2026年10月から開始される予定です。
子ども・子育て支援金の徴収方法

子ども・子育て支援金の徴収は、2026年度から始まります。医療保険の保険料とあわせて徴収する仕組みとなっており、健康保険料や国民健康保険料を納めるとき、上乗せとして子ども・子育て支援金もまとめて納める仕組みです。
加入している医療保険の医療保険者が、健康保険料や介護保険料とあわせて徴収するため、個人で納める必要はありません。
健康保険料の値上げに対して企業が取り組むべきこと

企業にとっても、少子化対策の推進は労働力の確保や生産性の維持という観点から重要なポイントです。
以下で、子ども・子育て支援金の導入に備えるにあたって、企業が取り組むべきことを解説します。
積極的な賃上げを行う
子ども・子育て支援金は労使折半とはいえ、従業員にとっては手取り収入が減少する要素となります。従業員の生活を守るためにも、企業としては積極的な賃上げが求められるでしょう。
賃上げによって社会保険料の負担を軽減できれば、実質的な負担は生じないことになります。国が企業に対して積極的な賃上げを求めているのも、「家計に子ども・子育て支援金の実質的な負担を生じさせないため」です。
継続的な賃上げにつながれば、従業員の満足度を高められるメリットも期待できます。その結果、優秀な人材を雇用・確保して生産性を向上させ、さらに事業投資を行うという好循環を生み出せるでしょう。
出生後休業支援給付・育児時短就業給付の制度を周知する
出生後休業支援給付・育児時短就業給付は、2025年4月から始まったばかりの制度です。従業員の中には、制度の存在を知らないという方もいるかもしれません。
企業としては、女性・男性に関係なく安心して育児休業を取得してもらうためにも、出生後休業支援給付・育児時短就業給付の制度を周知するとよいでしょう。
事業投資による経営の効率化を目指す
子ども・子育て支援金の制度が導入された目的からもわかるとおり、日本は少子化に伴って労働力人口が減少しています。企業としては、当初の想定通りに人材採用が進まないケースを見越して、省人化・省力化などの事業投資を進める必要性があるでしょう。
特に、労働集約型の企業が省人化・省力化に遅れてしまうと、利益率の低下や競争力の弱体化をもたらす可能性があります。生産性が乏しい業務は機械やAIに任せて、自動化・効率化を図ることにより、従業員一人当たりの生産性を向上させることが可能です。
具体的に挙げられる事業投資は、AIやIoTなど先端技術への投資です。初期投資を要するものの、業務効率化と人件費の抑制につながれば、長い目で見たときにメリットをもたらしてくれます。
経費の適正化を意識する
経費の適正化とは、無駄な支出を削減することです。経費を削減し、社会保険料の増加を相殺できれば、企業の経営に悪影響が出る事態を防げます。
さらに、経費の適正化によりキャッシュフローが改善されれば、経営の安定性が高まるでしょう。財務基盤を強化できれば、社会保険料の負担増や社会構造の変化などが起きても、事業継続性を確保できます。
創業手帳では、23の経費科目についてそれぞれ「削減する」方法と「節税する」方法と2パターン解説した「経費で損しないためのチェックリスト」を無料でお配りしています。こちらもあわせてご活用ください。
まとめ:2026年も健康保険料の値上げに備えよう
2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策のために全世代・全経済主体が負担し、子育て世帯を支援する新たな仕組みです。
医療保険料に上乗せされる形で徴収され、健康保険の加入者は月額数百円の負担増となります。企業と従業員の双方にとって負担増となるため、早い段階から備えを進めるとよいでしょう。
企業としては、従業員の生活を守るために積極的な賃上げを行ったり、事業投資による経営効率化、経費の適正化などに取り組んだりすることが効果的です。
今後の人口動態を考えると、今後も社会保険料負担の増加は避けられないため、「従業員を大切にして生産性を維持すること」「企業体質を強化し、持続可能な経営を実現すること」を意識してみてください。
創業手帳では、資金繰り改善に活用できる「キャッシュフロー改善」をご用意しています。資金調達だけでなく、資金管理に関するコツを掲載しているため、昨今のようなコスト増加が続いている状況で役立つはずです
また、最適な専門家を無料で紹介するサービスも行っております。税金・社会保険・助成金など、経営に関するお悩みがあるときは、ぜひあわせてご活用ください。
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。