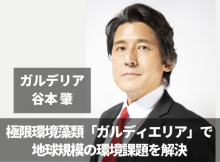連続起業家 熊谷芳太郎|シリコンバレーでFitbitなど多くの事業を成功に導いた日本人が語る、スタートアップ成功の秘訣
創業メンバーとして携わったFitbitが大ヒットしGoogleが3,000億円で買収

シリコンバレーで多くのビジネスを立ち上げ、「伝説の日本人起業家」と呼ばれる熊谷芳太郎さん。中でもウェアラブルデバイスの先駆けであるFitbitは大ヒットし、最終的にGoogleに21億ドル(約3,000億円)で買収されました。
現在も空飛ぶクルマを開発するスタートアップに参画するなど、新たなビジネスに取り組む熊谷さん。今回はアメリカに渡ったきっかけやFitbitがヒットした理由、アメリカと日本のスタートアップの違いなどについて、創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

連続起業家
1969年法政大学工学部機械学科卒業後、三菱鉱業セメントに入社。半年後アメリカに渡り、ジョージア州立大学理数学部へ編入。卒業後はミシンや家電のメーカーであるSingerへ入社。その後カメラメーカーVivitar社の社長などを経て、50歳で会社員としてのキャリアに終止符を打つ。
その後もシリコンバレーで多くのスタートアップに参加、2011年にはウェアラブルデバイスの開発製造を行うFitbit社の創業メンバーとなる。Fitbitはニューヨーク証券取引所へ上場後Googleが3,000億円で買収するなど、多くの事業を成功に導く。現在は「空飛ぶクルマ」とも言われるeVTOL(電動垂直離着陸機)のスタートアップASKA社に参画。

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
会社を半年で辞め、1000ドルを握りしめてアメリカへ

大久保:アメリカで多くのビジネスを手掛けてきた熊谷さんですが、そもそもどんなきっかけで渡米したのでしょうか?
熊谷:もともと海外志向というわけではなく、大学を卒業した後は三菱鉱業セメントへ入社しました。でもいろいろあって、半年くらいでその会社を辞めました。それから実家に戻って板前でもやろうかなと思っていたところ、父親が海外を見てこいと言ってくれて、1,000ドルだけ持ってアメリカへ行ったんです。
そこでたまたま日本食のレストランでスタッフを募集していまして、そちらは得意だったから働くことにしました。しばらく働いてお金が貯まってきた頃、アメリカで勉強したいなと思うようになったんです。
ただ当時私は全く英語ができなかったので、ESL(※留学生が英語を習得するために履修する科目)を受けて、それからジョージア州立大学に3年生から編入しました。当時は編入できる仕組みがあったので。
アメリカに遊びに来て、そのままいついてしまったという感じですね。
大久保:アメリカの大学を卒業された後も、そのまま現地で就職されたんですよね。
熊谷:ラッキーなことに、当時アメリカで大企業だったSingerという会社に入ることができました。日本ではミシンで知られるSinger社ですが、当時はミシンの他に飛行機のフライトシミュレーターを作ったり、家電製品を作っていたり、いろいろなことをしていました。今でいうGEのような、アメリカの中でもかなり大きな企業だったんですよ。
といってもSinger社は自社で全部作るのではなく、日本などにある他の会社が作ったものをOEMで売っていました。ですから私はシンガポールや香港、日本などで駐在員をしていた経験もあります。Singer社には4年くらいいて、その後はアメリカにある製紙会社のMead社に転職しました。
大久保:製紙会社というのは、ちょっと意外ですね。
熊谷:Mead社では将来紙が使われなくなるのではという考えがあって、当時からデータベース事業に取り組んでいました。「LexisNexis」という法律や特許などのデータベースを構築していて、今アメリカにいる多くの弁護士に使われています。
それからアメリカのVivitarというカメラメーカーの社長をしばらくやって、50歳でリタイアしました。
創業から参加したFitbitが大ヒットした理由とは

大久保:そこから起業家として多くの事業を手掛けてきたわけですね。その頃はスタートアップという概念はまだなかった時代だったと思います。
熊谷:そうですね。私の場合はたまたま友人に手伝ってほしいと言われ、現像した写真のデータをインターネットで送り、プリントするシステムを作りました。今の若い人は写真の現像という仕組みを知らないかもしれませんが。そのシステムを当時世界的な写真用品メーカーだったKodak社が評価してくれて、150億円で買い取ってくれたんです。
それからしばらくぶらぶらしていたのですが、今度は写真ではなく動画に目を付けました。当時は動画を撮っても他の人とシェアするのがすごく難しかったんですよね。そこで小型ビデオカメラに動画をシェアできるソフトを入れたものを開発しました。
それをCiscoが650億円で買い取ってくれました。今はルーターなどで知られるCiscoですが、当時はコンシューマーマーケットに入ろうとしていたんです。
大久保:その後熊谷さんはウェアラブルデバイスで知られるFitbit社に入ったそうですが、どんなきっかけだったのでしょうか?
熊谷:この時も、友人に誘われるかたちで2021年にFitbit社に入りました。当時は創業者と一緒になって、何でもやっていましたね。Fitbitではアプリの開発もしましたし、日本市場の開拓などもやりました。
大久保:Fitbitはウェアラブルデバイスの中でも当時かなり高い人気を誇っていましたね。
熊谷:Fitbitが売れた理由は、アプリが使いやすかったからじゃないでしょうか。もともとは万歩計を作ろうという発想がスタートだったので、シンプルで使いやすいということを意識したんです。
やはり力を入れたのはアプリでした。当時競合となるプロダクトもいくつかありましたけど、Fitbitの方が人気はありましたね。
ただOSは自分たちで持っていなかったので、他の会社を丸ごと買い取ってOSを手に入れたこともあります。何でも自分たちで作ればいいというわけでもない。そういう合理的なやり方は、スタートアップがスピード感をもって成長していくために必要だと思いますよ。
そうやってFitbitは成長して上場も果たし、最終的にGoogleに3,000億円で買収されました。
大久保:大きな成功をおさめた後もアメリカでさまざまな事業を立ち上げた熊谷さんですが、現在はどんなことをされているのでしょうか?
熊谷:今は空飛ぶクルマを開発するASKA社でアドバイザーなどをやっています。あとは東北大学の客員教授もやっているんですよ。私は宮城県仙台市の出身なので、地元の役に立ちたいという思いがあり、こうした活動も行っています。
失敗の経験がビジネスの原動力になる。だからアメリカの起業家は失敗を恐れない

大久保:アメリカと比べると、まだまだ日本のスタートアップは数も規模も大きくありません。シリコンバレーで活躍されてきた熊谷さんから見て、どのあたりに課題があると思われますか?
熊谷:まず日本とアメリカではマーケットの大きさが圧倒的に違います。例えば日本では2億円、3億円の売上で成功と言えますが、アメリカではその何十倍の売上で成功とみなされますから。そこは仕方がないかなと思います。
報酬の違いも大きいですよね。日本では結構稼いでいる会社でも、社員の報酬はおそらくアメリカの1/3くらいじゃないでしょうか。僕が今いるシリコンバレーでも、年収1,500万円とか2,000万円という人は珍しくありません。
報酬が圧倒的に違うので、世界の優秀なエンジニアがなかなか日本に来ない。アメリカとか、シンガポールなど海外に行ってしまう状況はあると思います。
環境とか文化の違いもあると思いますね。シリコンバレーっていつも晴れていて、青空が気持ちいい。箱根をイメージした庭園もあって、すごくいい環境です。だから新しいアイデアが生まれやすいのかもしれない。
あとこれが一番重要なことですが、シリコンバレーには失敗を経験した人がたくさんいます。失敗って、実は財産なんですよね。失敗があるから、常識にとらわれず新しいイノベーションを起こせる。つまり失敗の経験が、ビジネスの原動力になるわけです。
シリコンバレーでは、失敗することよりも挑戦せずチャンスを見逃してしまう方がダメなんですよ。「失敗は恥ずかしい」という日本とは、意識が大きく違います。
とはいえ、もちろん日本の良さもあります。技術力はやはり高いと思うし、最近私はいろいろなところで講演しているのですが、いつも「日本のおもてなしは世界に誇れる」と話しています。
日本には日本の良さがある。起業するにしても、アメリカの真似をするのではなく日本の良さを活かすビジネスをした方がいいでしょう。ただし、失敗を恐れずチャレンジして失敗の経験を糧にしていく姿勢は、ぜひアメリカに学んでほしいですね。
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。
(取材協力:
連続起業家 熊谷芳太郎)
(編集: 創業手帳編集部)