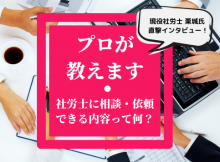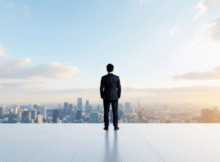ダブルワーク従業員の社会保険の取り扱いは?事業主が行うべき手続きを解説
働き方の多様化に伴ってダブルワーカーは増加傾向

副業解禁の流れを受けて、複数の会社で働くダブルワーカーが増えています。
ダブルワークの場合、社会保険の加入パターンは「一社のみ」「二社で加入」「いずれも加入しない」という3つに分かれます。特に二社で加入する場合は、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、保険料を按分するという手続きが必要です。
本記事では、ダブルワーク従業員を雇用する事業主が知っておくべき社会保険の取り扱いと、具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ダブルワークと社会保険の基本
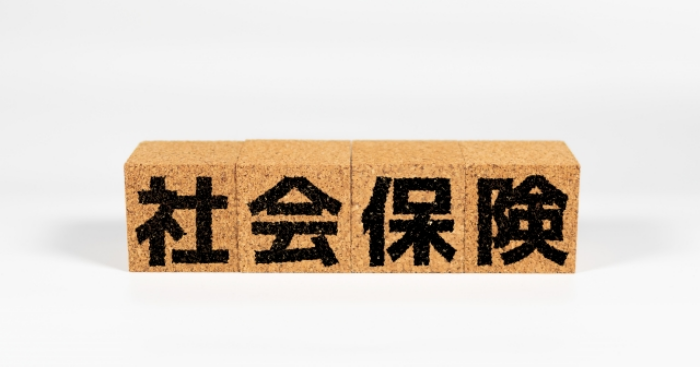
ダブルワーク従業員の社会保険を適切に管理するには、まず基本的な定義と加入条件を理解しておく必要があります。ここでは、ダブルワークの定義と、社会保険に加入する条件について確認していきましょう。
ダブルワークの定義
ダブルワークとは、1人の労働者が2つ以上の企業と雇用契約を結び、同時に複数の職場に勤務する働き方を指します。「副業」や「兼業」とも呼ばれます。
重要なのは、いずれの勤務先でも「雇用契約」が結ばれているという点です。個人事業主として業務委託契約で働く場合は、雇用関係ではないため、社会保険には加入しません。
雇用契約を締結している労働者の場合、各勤務先での労働時間や報酬額によって、加入義務が発生するかどうかが判断されます。そのため、ダブルワーク従業員を雇用する事業主は、自社での勤務条件が加入要件を満たすかを確認しなければなりません。
社会保険に加入する条件
社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入条件は、労働時間と労働日数によって決まります。原則として、以下の条件を満たす労働者は、社会保険への加入が義務付けられています。
| 雇用形態 | 社会保険への加入条件 |
| 正社員 | 基本的に加入 |
| 短時間正社員 | ・労働契約書や就業規則、給与規程に「短時間正社員」に関する規定がある ・雇用契約が期間の定めのない無期雇用契約である ・時間あたりの基本給や賞与、退職金などの計算方法が、同じ事業所で働く同種のフルタイム正社員と同等 |
| パート・アルバイト | 労働時間・労働日数が一般社員の4分の3以上である |
| パート・アルバイト(勤務先が特定適用事業所) | ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上) ・雇用期間が2か月を超える見込みがある ・学生でない |
ダブルワークの場合、それぞれの勤務先で上記の条件を満たすかどうかを個別に判断します。一方の勤務先だけが条件を満たす場合もあれば、両方の勤務先で条件を満たす場合もあります。
ダブルワークで社会保険に加入するパターン

ダブルワーク従業員が社会保険に加入パターンは、各勤務先での労働条件によって3つに分類されます。それぞれのパターンで事業主が行うべき手続きや保険料の負担方法が異なるため、自社の従業員がどのパターンに該当するかを正確に把握することが重要です。
| 条件 | 保険料負担 | 事業主が行うこと | |
| 一社で加入 | 一社のみで加入条件を満たす | 加入先企業が負担 | 加入先企業が加入手続き |
| 二社で加入 | 双方で加入条件を満たす | 両方の企業が報酬を按分して負担 | ・主たる事業所:「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出する ・従たる事業所:「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出する |
| いずれも加入なし | 両社とも条件を満たさない | 無し | 手続き不要 |
一社で加入するケース
片方の勤務先だけで社会保険の加入条件を満たし、もう一方では満たさない場合、加入条件を満たす企業のみで社会保険に加入します。具体例は、以下のとおりです。
- A社:週4日勤務、1日8時間(週32時間)→ 加入条件を満たす
- B社:週1日勤務、1日5時間(週5時間)→ 加入条件を満たさない
この場合、A社のみで社会保険に加入し、保険料もA社での報酬額のみを基に計算されます。A社は通常の社会保険加入手続きを行い、被保険者資格取得届を年金事務所に提出します。
なお、B社では特に手続きは不要です。
二社で加入するケース
両方の勤務先で社会保険の加入条件を満たしている場合、従業員は両社で同時に社会保険に加入します。
- A社:週3日勤務、1日8時間(週24時間)、月額報酬20万円 → 加入条件を満たす
- B社:週3日勤務、1日7時間(週21時間)、月額報酬12万円 → 加入条件を満たす
どちらの勤務先でも加入義務が発生するケースでは、それぞれの会社で加入手続きと、保険料の按分計算が必要です。
この場合、従業員は両方の報酬を合算した額(32万円)をもとに標準報酬月額が決定されます。そのうえで、各社の報酬額に応じて保険料が按分されるという仕組みです。たとえば、標準報酬月額が32万円と決定された場合、A社は20万円分、B社は12万円分の保険料を負担します(保険料は労使折半)。
いずれも加入しないケース
両方の勤務先とも社会保険の加入条件を満たさない場合、厚生年金保険・健康保険には加入しません。
- A社:週2日勤務、1日6時間(週12時間)、月額報酬7万円→加入条件を満たさない
- B社:週2日勤務、1日5時間(週10時間)、月額報酬6万円→加入条件を満たさない
どちらも週20時間未満であり、月額賃金も8.8万円未満のため、社会保険の加入義務は発生しません。企業側での手続きは不要で、従業員自身で国民年金と国民健康保険に自分で加入します。
社会保険の加入判断は、あくまで各事業所単位で行われます。たとえ合計で週30時間働いていても、それぞれの事業所で加入条件を満たさなければ、厚生年金保険・健康保険には加入しません。
二社で加入する場合の流れ

両方の勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合、通常とは異なる特別な手続きが必要です。手続きの流れは、以下の4つのステップで進みます。
- 被保険者が、各事業所にかかる医療保険者や管轄の年金事務所を選択し、届出を行う
- 選択された医療保険者・年金事務所で各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を定める
- 各事業所が負担する保険料(事業主負担分・被用者分)を算出し、選択された医療保険者・年金事務所から各事業所に通知
- 各事業所が毎月の保険料を納付する(報酬から天引き)
具体的に、どのような手続きが発生するか見ていきましょう。
被保険者が事業所と保険者を選択し、届出を行う
まずは従業員(被保険者)自身が、どちらの事業所を「選択事業所」とするかを決定します。選択事業所とは、社会保険の手続きを主に行う事業所のことです。
健康保険については加入する保険者(協会けんぽや健康保険組合)を、厚生年金保険については管轄の年金事務所を選びます。
実務上は、従業員が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を記入し、選択した事業所を経由して管轄の年金事務所へ提出します。
選択した事業所では、健康保険の被保険者資格情報を登録しなければなりません。「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の作成と提出も、忘れずに行いましょう。
選択された医療保険者・年金事務所で標準報酬月額を決定する
届出を受けた年金事務所または医療保険者は、両方の事業所での報酬月額を合算して、標準報酬月額を決定します。たとえば、A社で月額20万円、B社で月額15万円の報酬を受けている場合、合算額の35万円をもとに標準報酬月額等級表に当てはめて決定します。
各事業所が負担する保険料を算出し、通知される
決定した標準報酬月額をもとに、各事業所が負担すべき保険料額が計算されます。計算方法は、標準報酬月額に保険料率をかけた総額を、各事業所の報酬月額に応じて按分するという方法です。
計算式は以下のとおりです。
| 各事業所の保険料=標準報酬月額×保険料率×(当該事業所の報酬月額÷合算した報酬月額) |
先ほどの例で具体的に計算してみましょう。
- 標準報酬月額:36万円
- 厚生年金保険料率:18.3%(令和7年度)
- A社の報酬月額:20万円
- B社の報酬月額:15万円
| A社の厚生年金保険料 | 36万円×18.3%×(20万円÷35万円)=37,577円 |
| B社の厚生年金保険料 | 36万円×18.3%×(15万円÷35万円)=28,183円 |
この保険料額(事業主負担分と被保険者負担分の合計)が、選択事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所に「保険料額変更通知書」として通知されます。
各事業所が毎月の保険料を支払う
通知された保険料額に基づいて、各事業所で毎月の保険料を納付します。被保険者負担分(従業員負担分)は、自社で支払う報酬から天引きし、事業主負担分と合わせて年金事務所または健康保険組合に納付しましょう。
二社で社会保険に加入する従業員がいるときに企業がやるべきこと
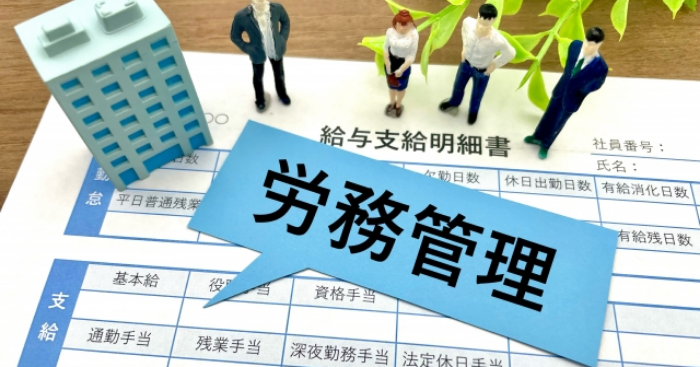
両方の勤務先において社会保険の加入条件を満たす従業員を雇用する場合、事業主には通常とは異なる対応が求められます。ここでは、企業側が具体的に行うべき手続きについて、期限や提出先、必要書類を解説します。
被保険者資格情報の登録
従業員が二社で社会保険に加入する場合、まず「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の手続きが必要です。この届出は、従業員本人が主体となって行いますが、実務上は主たる勤務先(選択事業所)を経由するケースが一般的です。
| 提出書類 | ・健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届※ ・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
| 提出期限 | ・健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届:従業員が二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:雇い入れた日から5日以内 |
| 提出先 | 従業員が選択した事業所(選択事業所)の所在地を管轄する年金事務所 |
※主たる事業所のみ提出する
選択事業所では、健康保険の被保険者資格情報を登録する必要があります。選択事業所で資格情報が登録され、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)が利用できます。
報酬月額に基づいて社会保険料を徴収する
二社で社会保険に加入する場合の保険料計算は、通常とは異なるため注意が必要です。決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ「二以上事業所勤務被保険者保険料額決定通知書」という形で通知されます。
具体的な保険料の計算方法を見てみましょう。
【前提条件】
- A社での報酬月額:24万円
- B社での報酬月額:16万円
- 標準報酬月額:41万円
- 厚生年金の総保険料額:41万円×18.3%=75,030円
- 健康保険の総保険料額:41万円×10.0%=41,000円
| A社負担分 | B社負担分 | |
| 厚生年金保険料額 | A社の負担分=75,030円 × (24万円÷40万円) = 45,018円 事業主負担:22,509円 被保険者負担:22,509円 |
B社の負担分=75,030円×(16万円÷40万円) =30,012円 事業主負担:15,006円 被保険者負担:15,006円 |
| 健康保険料額 | A社の負担分:41,000円×((24万円÷40万円)=24,600円 事業主負担:12,300円 被保険者負担:12,300円 |
B社の負担分=41,000円×(16万円÷40万円)=16,400円 事業主負担:8,200円 被保険者負担:8,200円 |
このように、各事業所は自社での報酬額の比率に応じて保険料を負担します。
事業主として重要なのは、年金事務所からの通知書を保管し、毎月の給与計算時に正しい保険料額を控除することです。通知された保険料額に変更があった場合は、速やかに給与計算システムに反映させましょう。
雇用保険は「主たる賃金を受ける」一社で加入

社会保険(厚生年金保険・健康保険)とは異なり、雇用保険は原則として一つの事業所でのみ加入します。ダブルワークで複数の勤務先がある場合でも、雇用保険の被保険者資格は「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」にある事業所でのみ取得します。
なお、雇用保険の加入条件は以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 学生ではないこと
主たる賃金を受ける事業所において、この条件を満たしていれば雇用保険に加入します。他方の事業所では、たとえ上記の条件を満たしていても雇用保険には加入できません。
「主たる賃金を受ける事業所」は、基本的には報酬額が多いほうの勤務先です。たとえば、A社で週30時間・月額25万円、B社で週10時間・月額10万円で働いている場合、通常はA社で雇用保険に加入します。
自社が主たる賃金を受ける事業所となる場合は、通常どおり雇い入れた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。
| 提出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 提出期限 | 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
他社が主たる賃金を受ける事業所となる場合は、自社では雇用保険の加入手続きは不要です。
まとめ
ダブルワークをしている従業員の社会保険手続きは、通常の加入手続きとは異なる点があるため、注意しましょう。
社会保険の加入パターンは、各勤務先での労働条件によって「一社のみ加入」「二社で加入」「いずれも未加入」の3つに分かれます。特に二社で加入するケースでは、両社の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各社の報酬額に応じて保険料を按分するという手続きが必要です。
働き方の多様化が進むなか、ダブルワーク従業員は今後さらに増えていくでしょう。優秀な人材を柔軟に活用しつつ、適法な社会保険の手続きをするためにも、正しい知識を持つことが欠かせません。
創業手帳では、事業主の方がやるべき手続きだけでなく、事業の発展に役立つ情報を無料でお届けしています。補助金や助成金、AIの活用などさまざまな情報をお届けしているので、是非お役立てください。
(編集:創業手帳編集部)