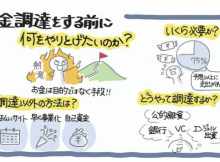短期融資と長期融資の違いとは?基礎知識から選び方までわかりやすく解説!
短期融資と長期融資の違いを理解して融資を申し込もう

事業を運営していくうえで、資金調達は避けて通れない重要な課題です。融資には「短期融資」と「長期融資」の2種類があり、返済期間や使いみちの違いを理解した選択が重要です。
本記事では、短期融資と長期融資の基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、効果的な使い分け方までをわかりやすく解説します。
読み終えるころには、適切な融資を選びやすくなり、安定した経営基盤づくりに役立つでしょう。
この記事の目次
短期融資と長期融資の違いは?
短期融資と長期融資は、主に3つの点で大きく違います。
- 返済期間の違い
- 融資審査の通りやすさの違い
- 融資を受けた後に行う帳簿のつけ方の違い
これら3点を理解しておくことで、自社にとって適切な資金調達方法を判断しやすくなります。それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。
返済期間の違い
| 項目 | 短期融資 | 長期融資 |
|---|---|---|
| 返済期間 | 1年以内 | 1年を超える |
短期融資と長期融資を分ける違いは返済期間であり、会計ルールである「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」に基づいています。
例えば短期融資は納税や仕入など、一時的な資金不足を補う資金に利用されます。一方で長期融資は、長期的な投資となる設備資金や事業継続に必要な運転資金が対象です。
資金の使いみちと返済の原資となる利益を考慮し、適切な返済期間の融資を選択しましょう。
融資審査の通りやすさの違い
一般的に、短期融資の方が長期融資よりも審査に通りやすい傾向にあります。金融機関から見ると、返済期間が短いほど回収リスクが低くなるためです。
短期融資は、資金繰り表などで返済原資となる入金予定を示せます。金融機関は回収が確実視でき、審査を通す判断の一つになるでしょう。
一方、長期融資は継続的な返済能力が問われるため、収支予想を含めた具体的な事業計画書の作成が重要です。金融機関は実現性を厳しく確認し、継続的に返済できるかどうかを慎重に審査します。
融資を受けた後に行う帳簿のつけ方の違い
| 項目 | 短期融資 | 長期融資 |
|---|---|---|
| 帳簿のつけ方 | 短期借入金 | 長期借入金 |
会計処理にも明確な違いがあり、返済期間同様に会計ルールである「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」に基づいて帳簿をつけます。短期融資は流動負債の短期借入金、長期融資は固定負債の長期借入金です。
なお、長期借入金でも返済期限が1年以内に迫った金額分は、短期借入金に振り替える必要があります。
融資の主な種類

融資は短期と長期だけでなく契約形態によっても分類できます。それぞれの特徴が異なるため、資金の使いみちや緊急度に応じて最適な方法の選択が大切です。
ここでは、企業がよく利用する代表的な融資種類を解説します。
証書貸付
証書貸付は、主に長期融資で利用される契約形式です。金銭消費貸借契約書という契約書を金融機関と交わして融資を受けます。
契約書には、以下の内容が明記されています。
- 融資金額
- 借入金利
- 返済期間
- 返済方法
- 利払い方法 など
最近は多くの金融機関で電子契約が始まっており、紙の契約では必要だった収入印紙の貼り付けが不要です。
当座貸越
当座貸越は、あらかじめ「極度額」と呼ばれる借入の上限額を設定した融資枠を設定し、必要なときに借入できる短期融資の方式です。
設定した融資枠内であれば、必要な金額を所定の書類で申し込むと、借り入れできる利便性が大きな特徴です。
急な仕入れの増加や売掛金の入金遅れなど、突発的な資金不足にも柔軟に対応できます。
一度契約すると、極度額の範囲内で繰り返し借入と返済ができるため、経常的に発生する短期運転資金の確保が可能です。
電子記録債権(でんさい)
電子記録債権は、手形に代わる新しい資金調達方法で、電子記録により発生・譲渡される金銭債権です。インターネット上で完結する新しい決済・資金調達手段として誕生しました。
紙の手形と違い、発行や保管の手間がなく、紛失・盗難リスクもありません。さらに収入印紙も不要です。電子記録債権での資金調達方法は、2つあります。
| 資金調達方法 | 具体的な内容 |
|---|---|
| でんさい貸付 | 電子記録として発生したでんさいを担保として融資 |
| でんさい割引 | 受け取ったでんさいを金融機関に譲渡して現金化 |
金融機関と手形のやり取りがなくなり、手形を利用していた際の短期融資より手間もコストもかからなくなりました。
政府は2026年度末までに紙の手形を廃止する方針を掲げており、中小企業にも利用が広がっています。金融機関からも積極的に利用を推進しており、利用の拡大が見込まれる方法です。
手形貸付・手形割引
手形貸付と手形割引は、かつて短期融資の主流だった方法ですが、現在は廃止に向かっています。ここでは現行制度として解説します。
| 資金調達方法 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 手形貸付 | 自社を振出人とする約束手形を金融機関に担保として差し入れ、融資を受ける方法 |
| 手形割引 | 取引先から受け取った「受取手形」を、支払期日が来る前に金融機関に買い取ってもらうことで現金化する方法 |
いずれも証書貸付より手続きが簡単で、資金調達が早い点が特徴です。前述したでんさいの普及により、実務上でも減少しつつあります。
短期融資のメリット・デメリット

短期融資はスピーディーに資金を調達できる一方で、返済負担や借り換えリスクも伴います。ここでは、それぞれの具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
短期融資のメリット
短期融資には、主に3つのメリットがあります。
- スピーディーに資金を調達できる
- 返済期間が短く、支払いコストを抑えることができる
- 借り換えにより実質的な延長ができる
最大のメリットは、急な資金需要にも迅速に対応できる点です。手形や借入申込書へ記載する簡単な手続きが多く、審査通過後から入金まで早くすみます。
また1年以内の借り入れになるため、金利負担が軽減でき、支払いコストを抑えた調達が可能です。
一括返済の場合、返済期日に同額の新たな融資を受ける「借り換え」という手続きもあります。実質的に借入期間を延長し、運転資金が継続利用できます。返済期日まで余裕をもって金融機関へ事前相談すると、取り組みやすいでしょう。
短期融資のデメリット
短期融資は、返済負担が重くなりやすいなどのデメリットもあるため、利用前に理解しておく必要があります。
- まとまった返済資金が必要になる
- 借り換えができないリスクがある
- 投資回収が長期になる計画には使えない
短期融資は、期日に元金を一括返済する条件が多くなる傾向です。返済期日までにまとまった資金を用意する必要があり、資金繰りを圧迫する要因になりかねません。
また借り換えや当座貸越の1年ごとの契約更新が保証されていない点も理解しておきましょう。自社の業績悪化などにより、資金調達ができなくなるリスクがあります。
資金調達の目的に合わない方法を選ぶと、かえって資金不足に陥りかねないでしょう。たとえば、設備投資は返済資金の利益が出るまでに長い年月がかかります。そのため、借入後1年で返済期限になる短期融資では資金不足を確保できません。
長期融資のメリット・デメリット
長期融資は、資金繰りを安定させやすい反面、社会環境の変化で返済が重荷になるリスクを抱えます。ここでは、長期融資のメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
長期融資のメリット
長期融資には、企業の事業基盤を支える大きなメリットがあります。
- 毎月の返済額を抑え、資金繰りが安定する
- 長期的な視点で経営計画が立てやすくなる
- まとまった資金で、大規模な投資が可能になる
最大のメリットは、返済期間を長く設定できるため、月々の返済額を少なく抑えられる点です。手元資金に余裕が生まれ、資金繰りの安定につながります。
借入期間を長くできるため、数年先を見越した事業計画を立て、安心して経営に取り組むことが可能です。
また、経営計画の実現には大規模な投資が必要となる場合もあります。長期融資なら大規模な資金を長期間で調達できるため、短期融資では難しい工場建設や新規事業にも取り組めます。
長期融資のデメリット
長期融資にも慎重に検討すべきデメリットが存在するため、内容を把握しておきましょう。
- 総支払利息が多くなる
- 審査が厳しく、時間がかかる
- 経営環境の変化に対応しにくいリスクがある
月々の返済額負担が軽減される一方で、返済期間が長い分、支払利息の総額は短期融資より多くなる傾向があります。
金融機関にとっては貸出期間が長いほど貸倒れリスクが高まるため、審査は短期融資より厳しくなります。事業の将来性や収益性を事業計画書で示す必要があり、融資実行までに手間と時間がかかる点もデメリットです。
コロナ禍のように経営環境が急変すると、計画通りの収益が上がらず、返済が困難になるリスクもあります。
短期融資と長期融資の使い分け方

融資を成功させるポイントは、資金の使いみちに合わせた短期と長期の使い分けです。一方だけに頼るのではなく、事業の状況に応じて選択する必要があります。
短期融資が向いているケース
短期融資が向いているケースは、短い期間で返済のめどが立つ資金需要です。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 急な大口受注に伴う仕入資金
- 季節的な売上減少を乗り切るための資金
- 大口の売掛金が回収できるまでの「つなぎ資金」
共通点は、売上入金や繁忙期の実績など、返済資金を確保できる見込みが明確にあることです。短期融資は一時的か資金不足を防ぐ役割として機能します。
長期融資が向いているケース
長期融資が向いているケースは、設備投資や創業期の運転資金など、成長や安定化を目的とした長期的な資金需要です。代表的なケースは、以下のとおりです。
- 工場や店舗、大型機械などの設備投資
- 新規事業や、事業拡大に伴う運転資金
- 創業時期の運転資金
長期融資に対応する設備計画や事業計画では、利益から事業継続に影響しない範囲で返済資金を確保していく必要があります。また、創業時には、売上が安定するまでを支える余裕資金も欠かせません。長期的な事業継続に向けた資金調達として長期融資が適しています。
返済が厳しくなったときの対処法

予期せぬ事態で返済が厳しくなった際には、放置せず早めに金融機関へ相談することが最優先です。早めの対処により資金繰りを改善できる可能性は十分にあります。
ここでは、万が一の際に取るべき具体的な対処法を解説します。
金融機関へ相談する
返済が難しくなりそうと分かった時点で、返済期日前に金融機関へ相談しましょう。連絡なく返済を遅延させてしまうと、金融機関との信頼関係が崩れ、今後の取引関係の悪化につながります。
現状を伝え、収支改善による返済の意思表示が重要です。金融機関も事業継続を支えるため、返済条件の見直しなど柔軟に対応してくれる可能性があります。
返済期日に借り換えする
返済期日に新たな融資で借り換え、実質的に返済を延長する方法です。ただし、借り換えができるかどうかは、自社の業績や金融機関の審査判断に大きく左右されます。
期日まで余裕をもって事前に金融機関へ相談しましょう。必ずしも借り換えできる保証はないため、相談しないまま資金繰りに含むことは危険です。
なお「短期継続融資」という言葉を見かけますが、正式な商品名や制度ではありません。短期融資を繰り返し借り換える状態を指す俗称と理解しておくとよいでしょう。
返済条件を見直してもらう
返済が難しい場合は、返済条件そのものを見直す交渉も選択肢です。一般的に「リスケジュール(リスケ)」や「返済条件変更」と呼びます。
代表的な返済条件の見直し方法は、以下のとおりです。
- 返済猶予による返済額の減額
- 返済猶予による元金棚上
- 最終期限の延長
当面の資金繰りが改善でき、経営を立て直す時間を確保できます。ただし、実現可能性の高い経営改善計画を策定し、収支改善の姿勢を金融機関へ示すことが重要です。
返済条件の見直しについて、以下の記事で詳しく解説しています。
短期融資と長期融資に関するQ&A
短期融資と長期融資に関して、経営者の方々からよく寄せられる質問をまとめました。
短期融資と長期融資で違うポイントは?
最大の違いは、返済期間が1年以内か、1年を超えるかという点です。返済期間が長くなるほど金融機関のリスク度合いが大きくなるため、一般的に長期融資の方が厳しくなります。
また、長期融資は必ず金銭消費貸借契約書を締結しますが、短期融資では手形貸付のように簡便な手続きで済む場合もあります。
運転資金はどちらで借りるべきか?
運転資金は資金需要に応じた選択が必要です。
| 融資分類 | 主なケース |
|---|---|
| 短期融資 |
|
| 長期融資 |
|
返済資金の入金が見込める場合は短期融資、長期的に返済していく場合は、長期融資が適しています。
創業したばかりならどちらを選ぶべき?
創業期は、長期融資制度の利用が一般的です。日本政策金融公庫をはじめとして各金融機関が創業融資制度を提供しています。
創業期は事業実績がなく売上が安定しないため、数か月分の運転資金をまとめて確保し、経営基盤の安定化が最優先です。
事業が軌道に乗り実績ができてから、必要に応じて短期融資の利用を検討すると良いでしょう。
日本政策金融公庫の創業融資については、以下の記事でも解説しています。
まとめ:あなたに合った融資で安定した資金繰りを実現しよう

短期融資と長期融資は役割の違いを理解して使い分ければ、資金繰りの安定につながります。
融資を選ぶ際は、借りやすさや金利よりも、返済資金をどこから確保できるかを重視しましょう。一般的には、短期資金は入金見込み、長期資金は利益からの返済資金確保が多くなります。
会社の状況と調達の目的を冷静に見極め、最適な融資種類を選択すれば、資金繰りが安定した経営につながるでしょう。
融資には、基本とノウハウなど知っておくべきポイントがあるので、わかりやすくまとめた無料ガイド『はじめての資金調達手帳』をご用意しました。資金調達を検討する際に、お役立てください。
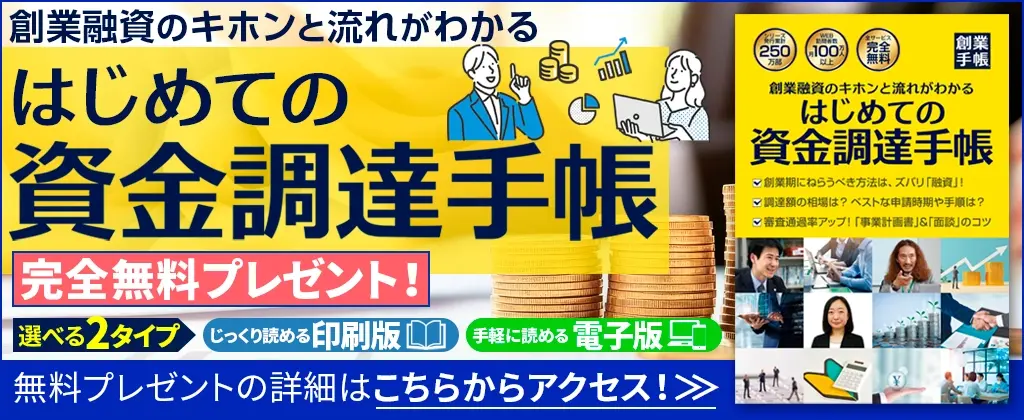
(編集:創業手帳編集部)