マンションオーナーになるには?メリットや注意点、手順まで詳しく解説!
マンション経営は条件を満たせば節税対策にも活用できる

将来の安定収入や資産を得るための手段として注目を集めているのが「マンション経営」です。
条件を満たせば所得税や相続税の節税対策にもつながるため、会社員や自営業者をはじめ、相続を見据える人からも注目されています。
しかし、初めての人にとっては「どのような手順で始めれば良いのか」「本当にメリットがあるのか」「リスクや注意点はないのか」といった不安も多いものです。
そこで今回は、マンションオーナーになるまでの流れや得られるメリット、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
マンションオーナーとは?概要と役割を解説

マンションオーナーとは、マンションを所有・経営しながら収益を得る人を指します。
入居者の満足度を高めるための工夫を凝らし、長く入居してもらえるよう環境を整えることが主な役割です。
建物の老朽化が進めば入居者からの不満も出てきやすいかもしれませんが、定期点検やメンテナンスによって快適な住環境を維持できます。
また、入居者の募集や契約更新、家賃回収、退去時の原状回復に対する手配なども、オーナーの役割です。
なお、オーナーはこれらの業務を不動産管理会社に委託することが可能です。
マンションオーナーになるメリット

ここからは、マンションオーナーになるメリットを解説します。
ローンの活用で少ない自己資金から始められる
マンションを購入するためには多額の資金が必要です。
区分マンションなら数百万円以上、1棟マンションを購入する場合は中古物件でも数千万円~数億円以上の資金が必要となります。
しかし、マンションを購入する際には基本的に不動産投資ローンを組むため、自己資金が少なくても問題ありません。
金融機関から借入れすることになりますが、マンションの家賃収入から返済できれば、自己資金を減らさずに現物資産を増やせることになります。
実物資産としての価値が残る
投資には様々な種類がありますが、株式や債券、暗号資産は発行元の会社や金融機関が破綻することで価値がなくなってしまうリスクがあります。
一方、不動産投資の場合、不動産自体の価値が下がっても実物資産としての価値は残ります。
貸す相手がいなかければ自分が住んだり、友人や知人に安い金額で貸したりすることも可能です。
また、マンションを1棟買いする場合には、マンションの土地の所有権も所持します。そのため、土地の価値が大きく変動することは少ないです。
さらに、まとまった資金が必要になった際には土地を売却したり、マンションとは別の用途で活用したりすることもできます。
生命保険・年金代わりになる
不動産投資ローンを組んで購入した場合、団体信用生命保険に加入するケースが多いです。
団体信用生命保険とは、ローンの契約者が万が一死亡または高度障害者となってしまった場合に、ローンの残債が補償される保険になります。
遺族はローン残債がなくなったマンションを相続し、マンション経営を続けたり、売却したりすることでまとまったお金を手に入れられます。
また、不動産投資を年金代わりに活用することも可能です。
近年は少子高齢化の影響を受けて財源不足に陥っており、年金の負担額は増えているにもかかわらず、受給額は減少傾向にあります。
不動産投資を早いうちに始めておくと、ローン返済を家賃収入で補いつつ、長期的に安定して資産を形成していくことも可能です。
定年までにローンを完済すれば、公的年金だけでなく家賃収入分も私的年金代わりとして受け取れます。
税制優遇を活用して節税できる
マンションオーナーになれば、税制優遇を活用して節税することも可能です。主に、相続税と所得税・住民税を節税できます。
相続税
相続税は、相続した財産が多ければ多いほど税率が高くなる税金です。そのため、税負担を抑えるためには相続する財産の評価額を下げることが重要になります。
相続税評価額を下げる方法として、分譲マンションの購入や所有する土地にマンションを建てることなどが挙げられます。
現金や預貯金だと額面がそのまま評価されますが、分譲マンションを購入した場合は実勢価格(時価)に比べて相続税評価額が低くなりやすいです。
また、所有する土地にマンションを建てた場合、土地とマンションの両方で相続税評価額が下がりやすくなります。
土地は路線価をもとに評価されますが、時価の8割程度で評価される可能性が高いです。
さらに、賃貸マンションを建てた場合は貸家建付地となるため、借地権割合と借家権割合を用いて評価され、減額につながります。
建物は新築でも建築費の5割~7割程度の評価となり、賃貸に出している分が減額されるため、土地と建物の両方で有利になります。
所得税・住民税
マンションオーナーになった場合、所得税・住民税も節約できます。
マンション経営によって不動産所得が赤字になった場合、損益通算が行えます。損益通算とは、赤字分から黒字の所得を差し引き、相殺することです。
給与所得がある場合、マンション経営の損失分を給与所得から控除することで、すでに源泉徴収されていた所得税が還付されます。
住民税は定額の「均等割」と、前年の所得額に応じて納付額が高くなる「所得割」から構成されているため、損益通算で所得税が還付されれば住民税を抑えられます。
また、マンション経営にかかった費用は経費として計上でき、課税所得額を小さくすることも可能です。
固定資産税や減価償却費、管理会社への委託費用、入居者募集で使った広告宣伝費、共用部分の水道光熱費などは、すべて経費として計上できます。
計上できる経費が高くなれば、その分申告する所得額も低くなるため、節税につながります。
マンションオーナーになるには?手順を解説
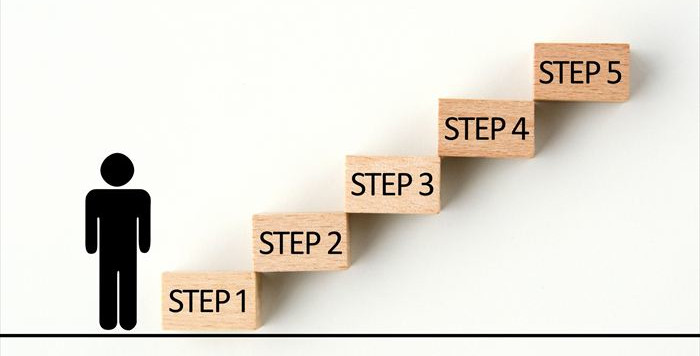
ここからは、マンションオーナーになるための手順について解説します。
1.マンションを選定する
マンションオーナーになるためには、マンションを選定することから始めます。
予算なども考慮しつつ、理想の土地やマンションの条件などを決めていき、物件情報を絞り込んでいきます。
投資目的でマンションを購入する場合には、収益性があるかどうかもチェックすることが大切です。
ただし、「高利回り」とアピールしているマンションには注意が必要です。
立地条件や築年数、周辺環境、需要などを加味した上で、安定した収益を得られる可能性が高いマンションを見極めてください。
2.不動産会社に相談する
気になるマンションがいくつか見つかったら、不動産会社へ相談します。
投資用マンションの購入を検討している旨を伝えると、物件の概要に関する資料だけでなく、維持費や固定資産税評価額などが明記された資料を用意してもらえる場合もあります。
資料に書かれた情報をもとに、マンションの収益性を見極めてください。
また、不動産会社の担当者と一緒に現地に足を運んでみることも大切です。インターネットの情報や資料だけではわからなかった部分が見えてくることもあります。
例えば、日当たりの良さや共用部分の清潔さ、周辺環境の治安や利便性などです。入居者の立場になり、「入居したい」と思えるマンションを選ぶことが大切です。
3.資金計画を立てる
購入するマンションが決まったら、資金計画を立てていきます。
マンションを購入する場合、仲介手数料や登記費用、税金、火災保険料などの初期費用が発生します。
初期費用を洗い出し、どれくらいの費用がかかるのか把握することも大切です。
また、ランニングコストがどれくらいかかるのかも計算してください。ランニングコストとして、管理費や修繕積立金、固定資産税、管理委託料などが挙げられます。
これらの費用に加え、空室リスクや家賃の下落リスクも考慮してシミュレーションを行います。
資金計画の内容が甘いと、途中で資金ショートに陥ってしまう可能性もあるため、綿密な資金計画を立てることが重要です。
4.金融機関でローンを申し込む
資金計画を立てたら、金融機関でローンの申し込みを行います。
金融機関により金利や条件などは異なるため、複数の金融機関に融資条件を出してもらい、慎重に比較・検討をしてください。
ローンを申し込むと審査が行われますが、最初に行われる審査は仮審査で、本審査は売買契約の締結後でないと申し込めません。
審査では申し込んだ人の属性や信用情報、マンションの収益性、担保価値などを評価し、融資の可否や条件を決めます。
5.売買契約を締結する
ローンの仮審査が通ったら、不動産会社から重要事項説明を受けます。
重要事項説明とは、物件の権利関係や取引条件、管理状況などの重要事項を、宅建士が買主に説明することを指します。
重要事項説明を受けている時に疑問点やわからないことが出てきたら、必ず尋ねるようにしてください。
重要事項説明を受けて疑問点を解消したら売買契約に移ります。売買契約書には売買価格や引き渡し時期、マンションの状態などが記載されていることを確認してください。
6.管理委託契約を締結させる
売買契約を締結したら、マンションの管理を任せる管理会社を選び、管理委託契約を締結させます。
マンション管理は、共用部分の点検やメンテナンス、修繕手配などを担う「建物管理」と、入居者の募集や契約手続きなどを担う「賃貸管理」の2つに大きく分けられます。
マンションを購入した場合は、管理会社が対応するケースが多いです。
管理会社によってサービス内容や手数料なども異なってくるため、複数の管理会社から見積もりを取り、比較・検討をしてください。
7.金銭消費貸借契約を締結させる
売買契約後に金融機関で本審査が行われますが、本審査を無事に通過できたら金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。
金銭消費貸借契約書には金利や返済期間、返済方法などが記載されているため、十分確認して契約を締結させてください。
8.決済・引き渡しを行う
金銭消費貸借契約を締結すると融資が実行されるため、物件の決済を行います。決済日にはオーナーだけでなく不動産会社や金融機関、司法書士なども集まります。
実際に決済が行われる前にマンションの状態や不具合などを確認し、問題がなければ決済手続きを行う流れです。
この日に決済ができなければ違約金が発生する可能性があることに注意してください。
マンションオーナーになる前に把握したい注意点

マンションオーナーになると長期的に安定した収益を得ることも期待できますが、注意すべきポイントもあります。
ここで、マンションオーナーになる前に把握したい注意点を解説します。
継続的にコストが発生する
不動産投資では、物件を購入する初期費用に加え、継続的なコストも発生します。
固定資産税や定期点検・メンテナンスにかかる費用、共用部分や入居する部屋の修繕対応などです。
固定資産税や定期点検・メンテナンスの費用はある程度予測して準備できるものの、修繕費用は突発的に生じる可能性があるため、事前に資金を確保しておかなければ対応が遅れてしまうことも考えられます。
また、収益が下がってもローン返済費や損害保険料などは支払うことになるため、キャッシュフローが赤字になる恐れもあります。
マンションオーナーになる前にランニングコストがどれくらいかかるものなのかを調べることも重要です。
様々なリスクで収入が減る可能性がある
マンションオーナーになる前に、様々なリスクによって収入が減る可能性があることを理解しておく必要があります。
例えば、空室リスクがあります。空室リスクは物件に入居者がなかなか入らないことで、想定していたよりも家賃収入を得られないリスクを指します。
ローンの返済期間中に空室が発生すると、貯金や本業の給与からローン返済に充てなくてはなりません。
また、入居者が家賃を滞納するリスクや、自然災害によってマンションが大きなダメージを受けるリスク、不動産価値が下落して家賃収入を下げざるを得なくなるリスクなどもあります。
いつ発生するのか予測が困難なリスクが多いことから、あらかじめ対策を講じておくことが大切です。
不動産の流動性が低い
株式や債券などの投資商品を比較した場合、不動産には流動性が低いというデメリットがあります。
株式であればインターネットやアプリを活用して、1日に何回も売買をすることが可能です。
しかし、不動産売却は買主を探すことから始まるため、売買契約を締結させるまでに数カ月かかってしまうことも珍しくありません。
また、購入してから売却するまでの間に値崩れを起こしたり、周辺環境が大きく変わったりして資産性がなくなることもあります。
流動性の低さによってマンションが売れない可能性があるため、購入する前から売却も視野に入れた戦略を考えておいてください。
まとめ・マンションオーナーになるために不動産経営の知識も身につけよう
マンションオーナーになるためには、融資を受けるための個人的な信用情報とマンションの収益力の高さが必要となります。
また、不動産投資には様々なリスクが付き物になってくるため、前もって不動産経営の知識を十分に身につけておくことも大切です。
税金については“もっと早く対策していれば…”と後悔するケースは少なくありません。
創業手帳が作成した『税金チェックシート』には、法人税を含め、納税額が数十万円単位で変わることもある重要な注意点を整理しています。事前にチェックして、余計な税負担を防ぎましょう。

(編集:創業手帳編集部)




































