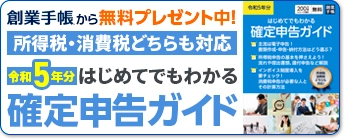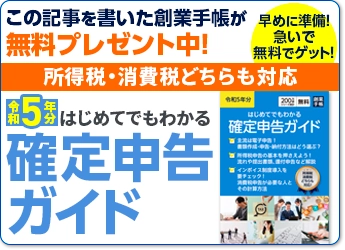税務調査で指摘されやすい“やってはいけない経費処理”とは?
やってはいけない経費処理はペナルティのリスク

経費処理をしていると、経費に入れていいのか迷うこともあるでしょう。経費処理の判断は、個人事業主や経営者にとって悩みどころです。
間違った処理をしてしまうと税務調査で指摘を受け、追徴課税やペナルティにつながることもあります。
本記事では、税務調査で特に見られやすい“やってはいけない経費処理”を解説します。事前に確認して経費処理のミスを起こさないようにしましょう。
税務調査で問題になりやすいのは、「確定申告の誤り」や「記帳・計算のミス」です。創業手帳では、こうしたトラブルを防ぐための基礎知識をまとめた『確定申告ガイド』を無料で提供しています。申告の流れ、必要書類、よくある間違い、注意点まで一冊で整理できます。
調査リスクを下げたい方は、ぜひご活用ください。
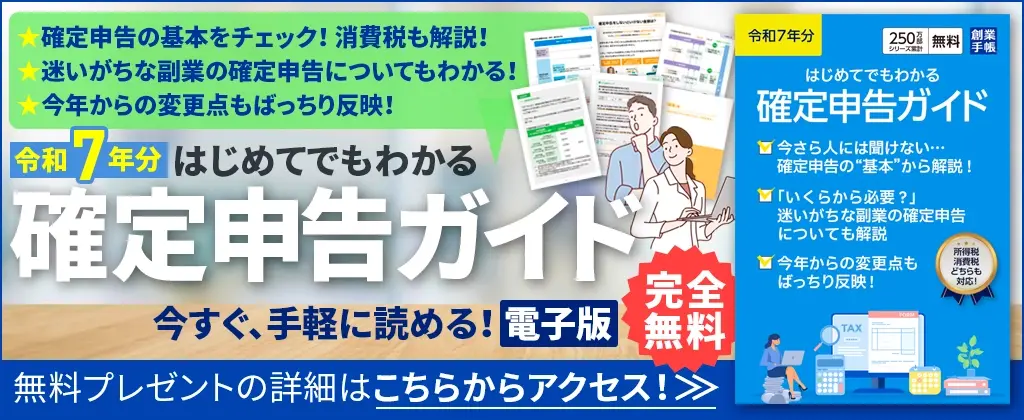
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ経費処理が税務調査で重視されるのか?

「せっかく利益が出ても税金で差し引かれて目減りしてしまう」と多くの事業者が感じているかもしれません。
節税のためには税制優遇を利用するほかに経費を増やす方法がよく使われています。
所得は収入から経費を差し引いて計算するため、経費が多ければ課税対象になる所得が小さくなって税金も少なくなります。
しかし、経費処理は税務調査で最初にチェックされる部分です。
経費の過大計上は所得隠しに直結するため、税務署は重点的に確認します。
その中でも家事関連費や交際費などは事業用と私用の区別が曖昧になりやすく、不正でなくても計上間違いが多発してしまいます。
故意の所得隠しや悪意でなくても証憑不足や処理の誤りが誤解を招き、調査対象として注目されてしうかもしれません。
税務調査であらぬ疑いをかけられないためにも正確で適正な処理が求められます。
やってはいけない経費処理の典型例
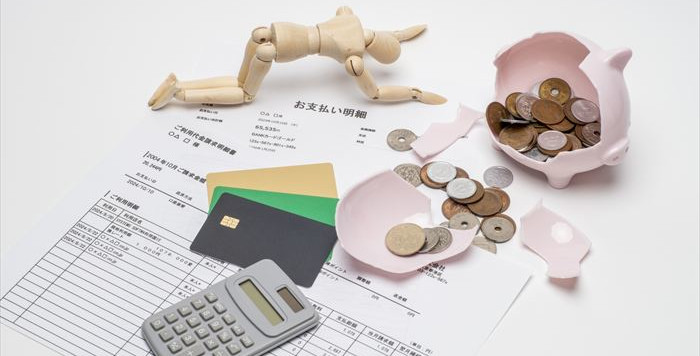
会計処理は細かい規定が多くあるため、間違いも多く発生してしまいます。ここではやってはいけない経費処理の典型例をまとめました。
以下のような経費処理をしていないかチェックしてみてください。
1. 家事関連費をそのまま経費にする
個人事業主が経費を計上する時に問題となるのが、プライベートでも使用していて事業でも使っているものへの支出です。
具体的には、自宅家賃や水道光熱費、車両関連費があります。自宅で仕事をしている場合には、自宅家賃や水道光熱費の一部を経費として計上可能です。
しかし、支出全額は経費にできず、合理的な方法で事業使用分を按分しなければいけません。
また、プライベートと事業で使用しているスマートフォン代やインターネット費用も私用部分を除外しなければ、経費不認定となります。
国税庁も「家事関連費の必要経費算入」については間違いが多く厳格に判断するため、安易な全額計上は危険です。必ず合理的な基準で家事按分するようにしてください。
2. 接待交際費をプライベート飲食に流用する
交際費は事業に関連する取引先との会食などに限定されていて、私的な飲食は経費として認められません。
取引先との打ち合わせやミーティングなどであれば経費として計上できます。
同じ忘年会であっても取引先との忘年会は接待交際費ですが、プライベートでの忘年会は経費計上できません。
友人や家族との飲食を交際費で処理すると、領収書があっても事業に関連する実態がないので否認されます。
交際費の経費算入は法人の場合上限がありますが個人事業主には上限がなく、国税庁は特にプライベート流用を重点調査する傾向があります。
接待交際費を計上する時には、どのような目的で誰と飲食したのかを記録しておくようにしてください。
3. 領収書がない出費を経費に計上する
費用を会計処理するためには、支出を証明する領収書が必要です。しかし、紛失してしまった場合や割り勘した時のように領収書がないケースもあります。
領収書がない支出は証拠能力が低く、経費算入が否認される可能性があります。国税庁の指針でも「支出の事実を証明する書類の保存」は義務です。
やむを得ない場合でも、クレジットカード明細やレシートなど客観的な証拠を残すようにしてください。
出金伝票を作成すれば経費計上が認められることがあります。
出金伝票には、支払いの日付と支払った相手、金額と商品、サービスの内容を記載しましょう。
専用の用紙もありますが、必要な情報が記載されていれば自社独自の書式のものも使用可能です。
4. 個人的な買い物を事業経費にする
事業に関連していれば、プライベートでも使用するものの支出も経費として計上できます。しかし、個人的な買い物でもすべて経費にできると考えるのは間違いです。
例えば、衣服や装飾品など生活用品は事業との関連性が弱く、経費にすると不自然と判断されてしまうことがあります。仕事以外でも使用する生活必需品は経費にはなりません。
具体的には、仕事にしか使わない制服やユニフォームであれば経費計上可能です。スーツは私服にもできるため経費にならないと判断されるケースが多いです。
会社に置いて商談や会議出席の時にだけ着用するといった、使い道が絞られたものであれば経費計上できる可能性があります。
5. 実態のない外注費や架空人件費を計上する
所得を少なくするために実態がない外注費、架空の人件費を計上して経費を増やすケースもあります。
しかし、親族に実態のない給与を支払った場合は経費として認められない上に、同時に贈与税が課税される可能性も生じてしまうので避けてください。
架空外注費を計上すると重加算税や刑事罰の対象になり得ます。国税庁の調査事例でも、架空人件費や外注費は重点的に確認される典型的な不正処理です。
架空の経費は国税庁が裏を取ればすぐに露見してしまう不正であり、悪質と判断されてしまうことが多いので絶対に計上しないようにしてください。
税務調査でよく確認される経費項目

税務調査では、調査員が不正や間違いが起きやすい項目を重点的に調べます。どのような経費項目がチェックされるのか紹介します。
旅費交通費
旅費交通費はプライベートでの支出と混同されやすいため、税務調査でもよく確認されます。
出張に私用を混在させた場合、旅費交通費として全額経費算入することは認められません。
経費にできるのは出張や業務に関する目的での支出です。交通費や宿泊費は領収書と関連する書類の保存が必須であり、証憑がない支出は経費に認定されないことがあります。
旅費交通費が発生した時には日程表や出張報告書を保存し、事業に必要な出張であることを証明する必要があります。
車両費
事業のために自家用車を使った場合、そのガソリン代は経費計上できます。しかし、プライベートでの使用は経費として計上できません。
私的利用分を除外せずにガソリン代全額を経費計上すると否認されてしまうので、家事按分して事業で使った分のガソリン代を計算してください。
ガソリン代は走行記録を基に事業使用割合を算出すると、合理的に按分できます。車両リース料や減価償却費も事業利用割合に応じた計上が必要です。
事業用に車を所有して事業のためにだけ使ったほうが会計処理は簡便です。
しかし、車の使用頻度や資金面の問題から事業用の車を購入するのは合理的でないケースも多くあります。
車にかかる経費には個人や家族利用分は含められません。
事業で使った時にはそれがわかるように何の目的で使用したのか、どこからどこまで移動したのかといった情報も記録しておくようにしてください。
通信費
スマートフォンやインターネット回線は私的利用と事業利用が混在するケースが多いです。事業で使った分だけを経費にできるので、適切な按分処理が求められます。
スマートフォンを事業用に用意したり法人契約したりするケースであっても、従業員の私的利用が含まれてしまうとその部分を経費に含めることはできません。
通信費の領収書や利用明細を保存しておくだけでなく、どのような時に通信を使用しているのか事業関連性を明確にして説明できるようにしておいてください。
消耗品費
事務用品や備品の購入は事業に必要な範囲でのみ経費算入でき、私物の購入は認められません。
しかし、文具や消耗品はプライベートでも使いやすく軽い気持ちで私用なのに消耗品として計上してしまうケースがあります。
領収書を残さず処理した場合、消耗品費は私的利用と疑われやすく経費否認のリスクが高くなるでしょう。
さらに、パソコンやカメラのように高額なものは消耗品費ではなく固定資産として計上するケースがあります。
消耗品は、原則取得価額10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものです。
そうでない場合には固定資産として工具器具備品などそれぞれで処理して減価償却しなければいけません。
交際費
交際費は事業との関連性が曖昧になりやすく、私的利用が混ざると経費として認められないことがあります。
取引先との会食や贈答であっても領収書を保管して参加者・目的を明確に記録しなければいけません。
さらに法人の場合は交際費の損金算入に上限があるため、制度に沿って処理するようにしてください。
福利厚生費
個人事業主は自分の福利厚生費を経費として計上できません。
福利厚生費は、従業員の生活の向上やモチベーションアップのために事業主が負担する費用です。経営者である事業主本人とその家族への支出は福利厚生費になりません。
事業に家族以外の従業員がいて、その従業員のためへの支出であれば条件を満たすことで経費計上が認められます。
具体的には食事代や社員旅行費、健康診断や家賃補助などがあります。
外注費・人件費
外注費や人件費は、一定の業務の対価として支払う費用です。外部に委託した時の費用や従業員に支払う人件費は、不正が発生しやすい科目です。
親族など身近な人に支払ったことにして経費計上するといったやり口が使われます。
経費を不正に水増しして所得税を減らす手口は多いため、税務調査ではその経費に実態がともなっているかが厳しく確認されます。
さらに、架空計上が露見すれば重加算税の対象です。
不正が疑われやすいため、本当に外注費や人件費を親族へ支払った時にも注意しなければいけません。
勤務実態や労務内容を証明できなければ否認される可能性があります。
相手が身近な人物でも支払調書や契約書を整備し、客観的な証拠を残すことが調査時の防御につながります。
やってはいけない経費処理をするとどうなる?税務上のペナルティ

経費として計上できるのは事業に関連する支出だけです。もしも経費計上に不正があればペナルティを受ける可能性もあります。
どのようなペナルティがあるのか以下で紹介します。
過少申告加算税
経費の誤りで申告所得が少なくなった場合、追徴課税に加えて過少申告加算税が課されます。
税務調査の事前通知の後に修正申告した場合は、加算税は新しく納める税金のほかにその税金に5%を乗じた金額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額、もしくは50万円のいずれか多い金額を超えた場合には超えた部分は10%で計算します。
税務調査後に修正申告した場合には、原則10%で新たに納める税金が当初の申告納税額もしくは50万円のいずれか多い金額を超えている場合、超えている部分については15%です。
事前通知の前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかかりません。過少申告に気づいた場合には、早めに相談することをおすすめします。
重加算税
重加算税は架空経費や隠蔽など悪質な経費処理を行った場合に、過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税に代えて課される税金です。
重加算税は本税の35%から40%とされ、通常の加算税よりも大幅に重い制裁です。さらに隠蔽や仮装を繰り返した時には、10%の加算税が徴収されます。
延滞税
追徴課税が生じた場合、納付期限から完納までの期間に応じて延滞税が加算されます。
延滞税は原則年7.3%と延滞税特例基準割合+ 1%」の いずれか低い割合です。
国税庁のHPでは延滞税がいくらになるのか計算することができます。納付が長引くほど利息のように膨らむため、早期納付が重要です。
青色申告の取消し
悪質な経費処理が発覚すると、青色申告承認が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されると、特別控除や赤字繰越のメリットは当然利用できません。
一度承認を失うと再度申請が必要となり、事業経営に大きな影響を与えます。
将来的に事業を継続するためにも不正を避け、ミスや間違いがあるときには速やかに修正してください。
もし税務調査で指摘を受けたら?

税務調査で誤りを指摘された場合は速やかに修正申告を行うことで、加算税や延滞税の負担を軽減できます。
会計処理に不安がある時には税理士に相談し、指摘事項の事実確認や是正対応を専門家の助言に基づき進めてください。
調査後に改善策を講じ、経費処理ルールや証憑保存体制を強化することが再発防止につながります。
受けた指摘を活用し、どのように会計処理や手続きを適正化できるのかを考えましょう。
まとめ:正しい経費処理が事業を守る
税務調査で特に指摘されやすいのは「家事関連費」「交際費」「証憑不足」です。
日頃から透明性のある経費処理と適切な証憑管理を徹底することが、追徴課税のリスクを減らします。
正しい経費管理を行うことは事業の信頼性を高め、安心して継続できる基盤をつくることにつながります。
指摘されることがないように普段から適正な経費管理に努めてください。
「気づかないうちに“やってはいけない処理”をしていた…」というケースは少なくありません。こうしたトラブルを避けるための基礎知識を掲載した『確定申告ガイド』を無料プレゼント中!詳しくは以下のバナーから!
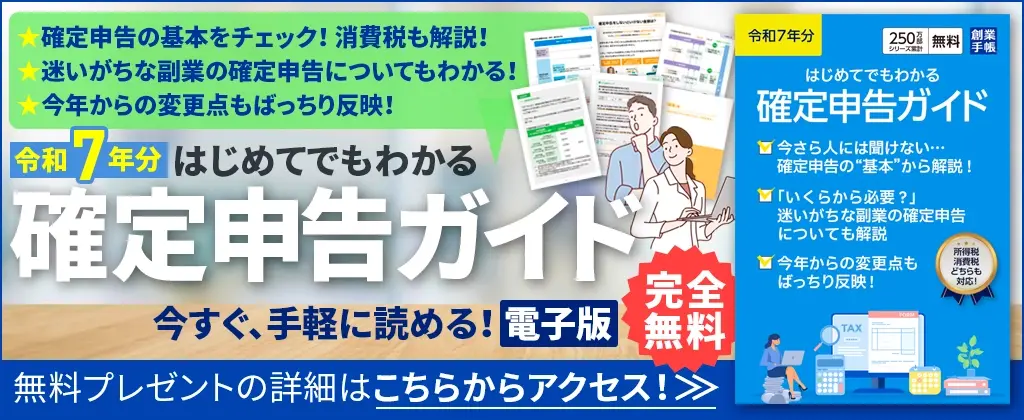
(編集:創業手帳編集部)