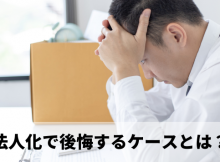法人化すべきタイミングはいつ?判断基準とシミュレーションで徹底解説
法人化のタイミングは所得と事業規模で判断

事業が安定して売上や所得が増えてきた個人事業主にとって「法人化すべきかどうか」は大きな悩みどころです。
法人化のタイミングは単なる金銭面のメリット・デメリットだけでは判断できません。
同じ事業内容であったとしても個人であるか法人化であるかによって、経営や会計が大きく違います。
法人化するかどうかを判断するためには多くの要素が関わるため、多面的な視点を忘れないようにしましょう。
本記事では、税負担のシミュレーションや事業の成長ステージごとの視点から、法人化の適切なタイミングについてまとめました。
法人化するかどうかで悩んでいる人も参考にしてください。
法人設立後の流れ、専門家への相談先まで網羅されており、個人事業から法人へのステップアップを検討している方に最適です。無料でお取り寄せいただけます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ「法人化のタイミング」が重要なのか?
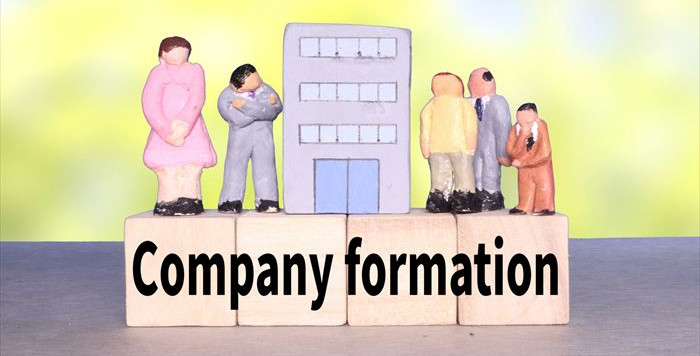
法人化のタイミングがいつでも問題ないと考えるのは間違いです。法人化の時期は税負担や資金繰りに直接影響するため、適切な判断が求められます。
同じ所得水準の個人事業主であっても、法人化のタイミングが早いか遅いかによって累積コスト差が数百万円規模になる場合もあります。
さらに、個人事業主として働いてきたものの、取引先との契約や融資を受ける条件で法人格を求められることもあります。
タイミング次第では、ビジネスチャンスを失ってしまうかもしれません。
法人化のタイミングは、経営ビジョンと同じように戦略的に考慮すべき問題です。
法人化のシミュレーション:個人事業主 vs 法人

法人化のタイミングを決める基準のひとつに税額が挙げられます。所得金額ごとの個人事業主と法人の税負担比較は以下の通りです。
あくまで概算なので参考として考えてください。
| 年間所得 | 個人事業主(所得税+住民税+事業税) | 法人(法人税+住民税+事業税+社会保険) |
| 500万円 | 約90〜100万円 | 約120〜130万円 |
| 800万円 | 約190〜200万円 | 約200〜210万円 |
| 1,200万円 | 約330〜350万円 | 約300〜320万円 |
上記では年間所得ごとに個人事業主の場合と法人の場合のコストをまとめています。上記の金額はあくまで目安です。
さらに計算の前提条件は以下の通りです。併せて確認してください。
個人事業主:課税所得(青色申告控除や基礎控除を差し引いた後の額)をベースに所得税・住民税・事業税を試算
※個人事業主の事業税は年収290万円超から課税される
法人:役員報酬を全額損金算入、法人税+地方法人税+住民税・事業税+社会保険料(会社+個人負担分)を合計
※社会保険料は「報酬額」次第で変わるため、表にある法人側の金額は役員報酬を「所得と同額」と仮定している
・社会保険料は大まかに「報酬の30%程度」で計算
実際の課せられる税額は、控除、役員報酬の設定、扶養状況など、個々の状況によって大きく変動します。正確な金額を知りたい場合は、必ず税理士にご確認ください。
所得500万円の場合
所得が500万円の場合、個人事業主では所得税・住民税・事業税で約90〜100万円の負担となります。
法人化した場合は法人税等と社会保険料を合計して約120〜130万円の負担です。
個人事業主の場合の所得税は、(事業所得−青色申告特別控除−所得控除)×所得税率−控除額で計算できます。住民税は、(所得金額−所得控除)10%-税額控除です。
個人事業税は、(事業所得-事業主控除) × 法定税率で計算します。法定業種の事業をおこなっていて前年度の所得が290万円を超えた場合には、事業税が課されます。
税率は事業の種類によって異なるので、どの税率が適用されるかホームページで確認しまてください。
所得500万円前後の水準では、法人化した時の社会保険料負担が大きくなり、設立費用を負担して法人化しても節税効果はあまりありません。
所得800万円の場合
所得が800万円では、個人事業主の所得税等の合計が約190〜200万円に達します。 所得としては大きく増えているものの、手取りは所得ほどは大きく増えません。
法人化した場合に、法人税等と社会保険料で約200〜210万円と負担が拮抗するのが所得800万円前後です。
この水準では法人化による節税効果が出はじめます。すぐには難しくても将来を見据えて法人化を考えておくタイミングです。
所得1,200万円の場合
所得1,200万円では税負担が約330〜350万円となり、所得に対する負担の割合が大きくなります。これは所得税の税率が上がっていることが理由です。
所得税は超過累進税率が適用されるので、所得が増えるとその分の税率が高くなります。
所得が500万円、800万円だった時に比べて負担が大きくなったように感じるかもしれません。
所得が1,200万円の時の所得税の税率は33%であり、控除額はあるものの税率でいえば法人税よりも高くなります。
法人化したケースを計算すると、税と社会保険料の合計が約300〜320万円程度です。
この所得水準から法人化による節税効果が明確に表れはじめます。法人化するためにコストがかかったとしても法人化の判断が有利になりだすタイミングです。
キャッシュフロー視点で考える法人化

節税効果から法人化を検討する人は多いでしょう。しかし、実際にはより複雑な条件を加味しなければいけません。
ここからは、キャッシュフロー視点で法人化のタイミングを考えていきます。
均等割・社会保険料による固定負担
節税効果を試算する時は、事業によって利益が出続ける前提でシミュレーションしました。しかし、事業をしていて利益が出ない、赤字になる年もあるかもしれません。
赤字になった時にどのような負担が生じるかも考えておいてください。
所得税の場合は所得から税額を計算するため、所得がゼロであれば所得税もゼロです。法人も赤字の場合には法人税などの所得にかかる税金はゼロになります。
しかし、赤字でも法人住民税の均等割が課されるので、最低でも年間7万円の負担が発生します。
さらに個人事業主であれば、従業員が5人未満であれば厚生年金と健康保険への加入は強制されません。
法人は、社長ひとりの会社であっても社会保険への加入が義務です。社会保険料は報酬の約30%が会社・個人双方で負担となり、固定的な支出増となってしまいます。
利益が少ない時期に法人化すると、固定費の負担が資金繰りを圧迫するリスクがあります。赤字になるリスクも考えて資金面での体力を付けておくようにしてください。
節税効果と資金繰りのバランス
一定以上の所得があれば、法人化すると適用される税率は下がります。しかし、同時に社会保険料などの支出が増えるため、税率だけで判断するのは危険です。
ただし、法人になるメリットは節税だけではありません。
法人化によって社会保険に加入すれば短期的な手残りが減っても、中長期的な資産形成で有利になるケースは多くみられます。
資金繰りのシミュレーションを行って、税金と保険料の総額を比較検討した上で、将来の事業成長に貢献する事業形態を選択してください。
事業投資と資金調達の観点
法人化するメリットには資金調達が容易になる点もあります。一般的に法人格を持つと金融機関からの融資枠が広がり、資金調達しやすくなります。
これから新規投資を計画している事業者は、資金繰りを安定させる目的で法人化を選択肢に入れることを検討してください。
起業の成長期には資金需要が高まります。この時期に法人化することで、節税と調達の両面で効果を得られるでしょう。
取引先・制度利用から見る法人化のメリット

法人化は、行っている事業にとっても大きな転換点になります。取引先や制度利用といった外部評価では法人化はどのようなメリットがあるのでしょうか。
取引先拡大につながる
大手企業や自治体は個人事業主では契約ができない場合があるため、法人化によって取引先が増えるケースがあります。
中でも信頼性が契約条件に直結する業種では法人化が必須です。個人事業主でいると、見積もりや入札の時点で断られることも考えられます。
法人化で評価が変わるのは新しい取引先だけとは限りません。同じ取引先であっても法人格を持つことで契約単価が上がり、継続的な取引きにつながる可能性もあります。
法人対象の制度が利用できる
資金調達や設備投資の時には、補助金や助成金が心強い味方になります。しかし、補助金や助成金は、法人を対象に優遇しているケースが多くあるのです。
こうした法人対象の制度が利用できることで、資金調達や投資の幅を広げることが可能です。
金融機関の融資審査でも、法人格のほうが有利に扱われる傾向があります。お金を調達したいと考えてから法人化すると必要なタイミングに間に合わないかもしれません。
制度活用や金融機関からの融資を見込む事業者は、法人化の早期検討が合理的です。
法人化による社会保険加入がもたらす影響

法人化により社会保険加入が義務となり、負担が増えます。
個人事業主は、国民健康保険と国民年金ですが、法人化すれば健康保険と厚生年金、さらに労災保険と雇用保険、子ども・子育て拠出金に切り替わります。
共通するのは介護保険です。
単純に社会保険の負担が増えると聞くと、避けたいと感じるかもしれません。しかし、法人の社会保険のほうが個人事業主よりも手厚い保障が受けられます。
例えば国民年金は、年金の1階部分のみの支給なので厚生年金と比較して老後の受給額は少なくなります。また、障害年金や遺族年金の保障も手薄です。
将来的な年金受給額が増加するため、法人のほうが老後資金形成の面では有利といえます。
加えて、法人の健康保険は、疾病手当金や出産手当金があってより手厚くなっています。
これらの社会保険の違いは福利厚生の充実でもあり、求人する時にも有利です。従業員募集の際に社会保険完備は大きな採用力となり、優秀な人材確保につながります。
業種別の法人化タイミング

法人化のタイミングを考える時には、業種も要素となります。ここでは業種別に法人化のタイミングについて考えます。
フリーランス(デザイナー・ITエンジニア)
デザイナーやエンジニアといったフリーランスとして働く人も法人化可能です。フリーランスの法人化のタイミングは、所得水準が800万円を超えるころが目安です。
大手のクライアントは法人格を契約条件とすることが多いため、フリーランスの個人事業主から法人になることで仕事の幅を広げやすくなります。
節税と信用獲得の両面から一定規模に達した段階での法人化が有効です。
飲食・小売業
飲食や小売業は雇用や設備投資を見据えて早めに法人化を検討するようにします。店舗や設備投資には資金が必要なため、融資面で法人化したほうが有利です。
従業員を雇用をする場合は社会保険加入義務があります。小規模からスタートする場合でも、事業拡大を視野に入れて早期に法人化を検討してください。
コンサル・士業
コンサルや士業は、資格や実績を武器に仕事をしているため個人事業主のイメージがあるかもしれません。
信用力や契約条件で法人格が有利になる場合は、法人化することで取引先の拡大につながります。
所得水準よりも信用や事業拡大の要件で法人化を選択するケースが多いのがコンサルや士業の特徴です。株式発行や増資での大規模な資金調達も視野に入れてください。
法人化しないリスクも知っておこう

事業の拡大や節税のように法人化には多くのメリットがあるものの、個人事業主で続けてきたからそのままでいいと感じる人もいるかもしれません。
しかし、法人化しないことによって発生するリスクもあります。どういったリスクがあるのかまとめました。
累進課税による税負担増
個人事業主を続けるリスクとして、税負担の増大があります。個人事業主は所得が増えるほど税率が上がり、所得から手取りが大きく減少してしまいます。
所得税の最高税率は45%であり、高所得層では法人税率より大幅に不利です。
法人化を遅らせると、法人税に切り替える節税機会を失って累積で数百万円単位の差が出る可能性もあります。
事業承継・拡大の制約
個人事業は事業用資産がすべて個人所有であるため、誰かに承継したい時に困難です。法人格を持たない場合、第三者への引継ぎや株式譲渡の仕組みが使えません。
事業を拡大していきたいと考えている場合も個人事業主であることが足かせになることがあります。
法人化していないと、金融機関や投資家からの支援が受けにくく拡大が制限されてしまうかもしれません。
信用力不足による機会損失
大手企業や自治体は法人格を契約条件とするケースが多いため、個人事業主では受けられない仕事があります。
法人格を持たないと事業規模に見合った信用評価が得られず、取引機会を失ってしまいます。
事業を大きくして信用を得ようとしても、個人事業主は金融機関からの融資審査で不利となり、必要な資金を確保できないかもしれません。
ビジネスチャンスを有効に使うには事前に法人化が必要なケースがあります。
まとめ:数字+事業計画で法人化のベストタイミングを見極める
法人化は節税だけでなく、信用・資金調達・社会保険など複数要素の判断が必要です。
所得シミュレーションと業種特性を踏まえて、事業計画に沿った最適な時期を見極めるようにしてください。
シミュレーションの結果や制度を活用して、経営全体にとって有利な法人化タイミングを選択することが重要です。
数字と事業計画の双方を把握した上でベストタイミングを見極めてください。
(編集:創業手帳編集部)