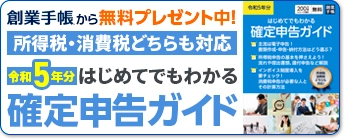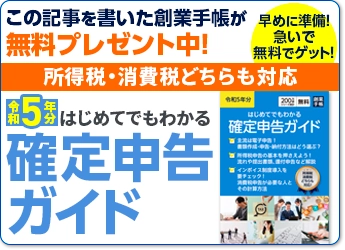確定申告でやりがちな10のミスと回避法|個人事業主のための実践ガイド
確定申告ではうっかりミスが起きやすい

個人事業主にとって確定申告は毎年の大仕事です。慣れていても「うっかりミス」が発生しやすく、余計な税負担やペナルティにつながることもあります。
本記事では、税務調査でも指摘されやすい典型的なミスと、今日から実践できる防止策を徹底解説します。
初めての確定申告で不安がある人も、どのようなミスが起きやすいのか知っておいたほうが良いです。ミスを防ぐためのチェックリストも用意しているので活用してください。
確定申告の不安を解消する最新版「確定申告ガイド」をリリース!確定申告の基本情報だけでなく、今年の変更点もわかりやすく解説。確定申告のミスを防ぐために最適です。ぜひご一緒にご活用ください。
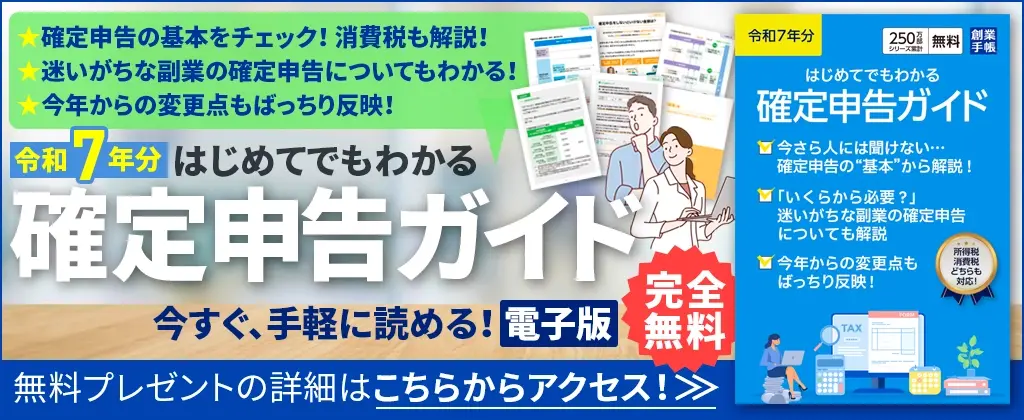
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ確定申告でミスが起こるのか?

個人事業主として一定以上の収入がある場合、確定申告が義務付けられます。しかし、個人事業主の確定申告ではミスが起こることは決して珍しくありません。
ミスが増える理由として、個人事業主だと個人の財布と事業主としての財布が混同しやすい点が挙げられます。
経費と私費の線引きが曖昧であると、結果的に経費過大計上や控除漏れが生じやすくなります。事業が忙しくなると、会計処理やバックオフィス業務が後回しになりがちです。
日常的な記帳や領収書整理が遅れることで、記憶が曖昧になり間違いや処理漏れが増加してしまいます。
さらに、税制の改正もあります。会計担当者や専門部署がいれば税制改正も把握できるものの、個人事業主だと自分だけで手が回らないことがあるでしょう。
税制改正や制度変更を把握できないと、インボイスなどの新制度に対応できず申告誤りを招きます。
確定申告でやりがちなミスと回避法10選

ここからは確定申告でやってしまうことが多いミスとその回避法をまとめています。初めて確定申告する人も事前に確認してください。
ミス1:経費処理の誤り
経費とは、事業所得を計算する時に差引が認められている支出をいいます。個人事業主で多いのが、差し引くことができない個人の支出を経費として計上しているケースです。
家事費、家事関連費は、個人事業主が支払う家賃や水道などの支出です。会計処理では事業で使用した支出のみを経費計上するために家事按分をしなければいけません。
家事関連費を全額経費に計上すると、否認され追徴課税を受けるリスクが高まります。
プライベートの支出を混在させると、税務調査で不適切と判断される可能性が高いので普段の会計処理から経費の区分を徹底してください。
さらに正しく計上しても、領収書やレシートを紛失すると経費の証明ができず結果的に控除対象から外れてしまいます。
<回避法>
経費処理の誤りを回避するには、経費の按分ルールを事前に定めておくと良いでしょう。
毎回同じ基準で処理することで一貫性を保ちやすく、早めに税務調査に対応する準備ができます。
領収書の管理や会計処理に不安がある場合には、クラウド会計ソフトを利用し、証憑データをデジタル保存することで証明力を強化できます。
ミス2:売上の記載漏れ
売上の申告漏れは、発生しやすいミスです。現金売上を記録し忘れると、無申告所得とみなされ重加算税の対象となる恐れがあります。
また、インターネットショップやプラットフォーム経由の売上を記載し忘れると、帳簿不整合が生じてしてしまうかもしれません。
通帳記録と帳簿の突合わせを怠ると、振込入金が漏れて売上計上に誤りが生じてしまいます。通帳記録と帳簿が整合しているかどうか定期的にチェックしてください。
<回避法>
売上データを定期的にCSVで取込み、帳簿と照合することで記載漏れを防止できます。
通帳やレジ記録を月単位で突合するようにルールを導入すれば、ミスがあっても早期発見可能です。
ミス3:控除の申告漏れ
所得控除は、納税者の事情などを考慮して税負担を調整するために設けられた制度です。所得控除が適用されれば、課税対象になる所得が少なくなるので税負担を軽減できます。
青色申告であっても白色申告であっても、必要な条件を満たしていれば控除の適用が受けられるのです。
具体的には、社会保険料を支払った時の社会保険料控除や小規模企業共済の掛金を支払った時の小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除や地震保険料控除があります。
また一定額以上の医療費を支払った時には医療費控除が受けられるので、医療費の領収書は必ず保管してください。
控除は確定申告で申告しなければ適用されません。どういった所得控除があるのかを知って申告漏れがないようにしてください。
<回避法>
国税庁HPでは受けられる控除を一覧にして紹介しています。事前に確認することで、見落としを未然に防ぐようにしてください。
会計ソフトには、質問に答えながら各種控除や所得税の金額を自動計算できるものもあります。
案内に従って必要書類を揃えながら漏れなく申告できるので積極的に活用してください。
ミス4:添付書類の不備
確定申告は、確定申告書だけでなく添付書類も必要です。添付書類は、副業の収入の有無や年金の有無など条件によって異なります。
年末調整をしていない場合に生命保険料や地震保険料の控除証明書を添付し忘れると、控除が適用されなくなります。
さらに医療費控除や雑損控除も明細書や領収書が必要です。
<回避法>
確定申告の前に必要書類を分類・保管し、申告直前の慌ただしい時期に備えるようにしてください。
国税庁HPでは、確定申告の手引きとして添付、提示書類をまとめて紹介しています。
所得の種類や控除ごとに必要な書類がまとめられているので、ひとつずつ添付書類を確認してください。
ミス5:納付の遅れ
確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をして、所得税を納付するように定められています。
申告書を期限内に提出しても納付を忘れると、遅れた日数に応じた延滞税が課されます。
金融機関の窓口納付のみを頼りにすると、休業日や混雑により納付が遅れる可能性があります。申告をした後に税務署から納付期限について別途案内されることはありません。
コンビニや現金での納付も選択可能ですが、口座振替やe-Tax納付を設定しないと、納付期日を失念しやすいので注意してください。
<回避法>
納付の遅れを回避するには、振替納税やダイレクト納付を活用し、オンラインで確実に支払うようにします。
支払い手続きが後になる場合には、納付日をカレンダーやリマインダーに登録し、期日を忘れない工夫を徹底してください。
ミス6:青色申告承認申請を忘れる
青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。青色申告承認申請の期限は、原則申告しようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2カ月以内に提出します。
青色申告承認申請書を出していない場合には、その年は青色申告ができないので白色申告をして、翌年以降に青色申告承認書を提出して青色申告をします。
青色申告にすると、青色申告特別控除が受けられるなど税制面での優遇が適用されるのです。節税効果を得るために青色申告承認申請は忘れないようにしてください。
<回避法>
青色申告承認申請を忘れないためには、開業した段階で開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出してください。
青色申告承認申請書の提出は開業届と同じで税務署への窓口提出や郵送です。また、e-taxでも提出可能です。
後にすると忘れてしまう可能性があるので、開業の段階でまとめて提出するようにおすすめします。
ミス7:帳簿付けの不備・遅れ
個人事業主になると、日々の取引きの帳簿付けも自分でしなければいけません。しかし、経営で忙しくなれば帳簿付けもおろそかになりがちです。
帳簿付けをまとめて行うと記憶が曖昧になり、誤りや漏れが発生しやすくなります。
事業を行っている人は、記帳、帳簿の保存が義務付けられ、青色申告の場合には複式簿記による記帳が必要です。
仕訳帳や総勘定元帳の整備が不十分だと、青色申告特別控除の要件を満たさなくなってしまいます。
さらに、領収書や請求書を適切に整理しないと、証憑の欠如で経費計上が認められなくなるリスクがあります。
不備や遅れが発生しないように、こまめに記帳して書類を整理するようにしてください。
<回避法>
帳簿付けの不備や遅れを防ぐためには、週1回程度の定期的な記帳習慣を持ち、データを溜め込まないようにします。
会計ソフトや会計アプリでは自動読み取り機能が搭載されているものがあります。入力や証憑管理の手間を削減できるので導入を検討してみてください。
ミス8:インボイス制度への対応不足
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式です。
一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が発行して、その適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除が適用されます。
適格請求書として認められるには、一定の要件を満たさなければいけません。
請求書フォーマットをそのまま変更なく利用すると、インボイス制度要件を満たさなくなってしまうことがあります。
必ず適格請求書の要件を満たしているかどうか確認してください。
適格請求書発行事業者の登録番号を請求書に記載しないと、仕入税額控除が否認されてしまいます。
加えてインボイス発行事業者ではない免税事業者からの仕入れを誤って控除すると、税務調査で修正申告を求められます。
証憑管理と会計処理のどちらも慎重に手続きが必要です。
<回避法>
インボイス制度が始まって以降は、適格請求書と免税事業者が混在する可能性があります。
仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを確認し、控除対象の可否を明確に管理しなければいけません。
混同せずに会計処理できるように処理のルールを決めておいてください。
また、適格請求書を発行する場合には、発行時に登録番号を自動反映できるシステムが便利です。
適格請求書を受け取った場合と発行する場合の両方のケースを理解してミスがないようにしてください。
ミス9:事業専用口座を作っていない
開業した時に、事業用の専用口座を作っておくのがおすすめです。私用口座と事業資金を混在させると、収支の明確な管理が困難になってしまいます。
通帳の中にプライベートと事業の取引きが混在すれば、会計処理が複雑化して記帳誤りの原因になるリスクがあります。
さらに税務調査時にも通帳記録が事業とプライベートで混在していると、不要な追及を受けやすくなります。
<回避法>
開業時に事業専用口座を開設し、事業用収支を一元管理するようにしたほうが良いでしょう。
売上や経費の資金の流れをすべて専用口座に集約することで、処理が効率的になり会計の透明性を高められます。
ミス10:過去の繰越控除を忘れる
青色申告を選択すると事業で生じた赤字を翌年度以降に繰り越して、将来の黒字と相殺することが認められます。
この欠損金の繰越控除は、黒字になった時の負担を軽減できる節税策です。
繰越控除は原則として3年間可能なものの、うっかり過去の繰越控除を忘れてしまうケースがあります。繰越控除の適用が漏れてしまうと正しい所得計算ができません。
会計ソフトや税理士に依頼すれば控除を反映してくれますが、自分で手入力していると控除の自動反映を見落とす場合があります。必ず前年の確定申告書を確認してください。
<回避法>
繰越控除を忘れないためには、前年分の申告書控えを手元に置き、控除情報を転記してチェックすることが有効です。
また、会計ソフトの繰越控除自動反映機能を利用し、申告漏れを防止できます。
税務調査で特に狙われやすい項目

確定申告で間違いや不明瞭な部分があれば、税務調査が実施される可能性があります。
売上の規模が大きくなるほどミスも発生しやすくなるので、事業が成長段階の個人事業主は特に注意しなければいけません。
どういった項目が見られているのか以下でまとめています。
交際費
交際費は業務関連か私的支出かの線引きが曖昧で調査で重点確認されやすい項目です。
その食事が事業に関係しているのかどうか、社内のものであるか外部の人とのものであるかまで細かくチェックされます。
それが社外の人間との打ち合わせであれば交際費ですが、従業員全員が対象である場合には福利厚生費に該当します。
区別できない場合には、経費計上が否認され追徴課税の対象です。
旅費交通費
旅費交通費は業務関連性が不明確な場合、私用とみなされて否認されるリスクがあります。
特に、宿泊費や航空券の領収書に同行者や行程が不明な場合、経費性が疑われてしまうのです。日帰り出張でも記録簿や目的地の明細がなければ、調査で指摘されます。
旅費交通費が発生した時には、何の目的の出張なのか、同行者や商談相手が誰かまで記録しなければいけません。
車両費
車両費は私用利用と事業利用が混在しやすく、按分処理が不十分だと否認されてしまいます。
車両に関わるガソリン代や減価償却費を全額経費計上すると、税務調査で修正を求められる可能性があります。
事業でもプライベートでも使用する支出は、家事按分といって事業に関する支出を分けて経費計上しなければいけません。
プライベートでも使用するものの費用は、利用目的を証明できるように準備するとともに、どのようにして家事按分を計算しているかを説明できるようにしてください。
車両に関わる費用であれば、事業で使った走行距離や時間を基準とする方法があります。
消耗品費
消耗品費は範囲が広く、私的利用を含めやすいため、調査で注目される科目です。取得価額が10万円未満であれば減価償却なしに経費計上可能です。
しかし、10万円未満の物品でも、事業関連性が不明確だと経費として認められないことがあります。
使用目的を明らかでないと税務調査で否認されやすいので事務用品や備品購入の領収書に記載しておくようにしてください。
【チェックリスト】確定申告前に確認しておきたいこと

確定申告前に確認しておきたいことのチェックリストは以下の通りです。
まとめ:確定申告では小さなミス防止が大きな安心につながる
確定申告の多くのミスは、知識不足や準備不足だけではなく「うっかり」に起因するものも多くあります。
ヒューマンエラーをゼロにするのは困難ですが、日常的な仕組み化と期限管理を徹底することで、申告の正確性と安心を確保できます。
早めの準備とチェックリスト活用が、余計なトラブルや税務リスクを未然に防ぐために効果的です。
ミス回避策の中には、すぐにはじめられるものも多いのでぜひ実践してください。
確定申告でミスを防ぐには、日ごろから経費の扱いを正しく整理しておくことが大切です。
最新版「確定申告ガイド」では、確定申告をどのように進めるべきかお悩みの方に最適なガイドです。ぜひ合わせてご活用ください。
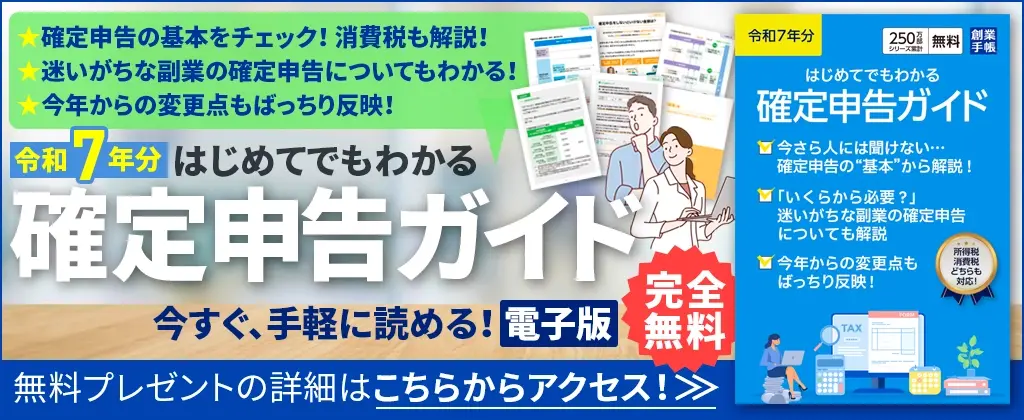
(編集:創業手帳編集部)