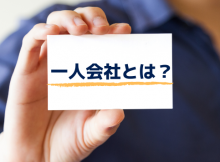起業するなら個人事業主?法人?あとから後悔しない「起業スタイル」の選び方とは
起業スタイル選びで迷わないためのポイント

働き方やニーズが多様化し、起業が選択肢のひとつとして挙げられるようになりました。
起業する時に考えなければならないのが「個人事業主と法人のどちらがいいのか?」ということです。
設立コストや社会保険、税金、信用力、節税・資金調達の観点で比較することで、自分に最適な起業形態が明確になります。
個人事業主と法人のどちらで起業するかを早めに判断することは、事業運営や税務処理の負担を減らすためにも重要です。
この記事では個人事業主・法人のどちらで起業すればいいのか、判断のポイントを開設します。
会社設立をご検討中の方は、まずは『創業手帳(無料)』をチェック!開業・設立・資金計画まで、起業の基本がこの1冊でわかります。
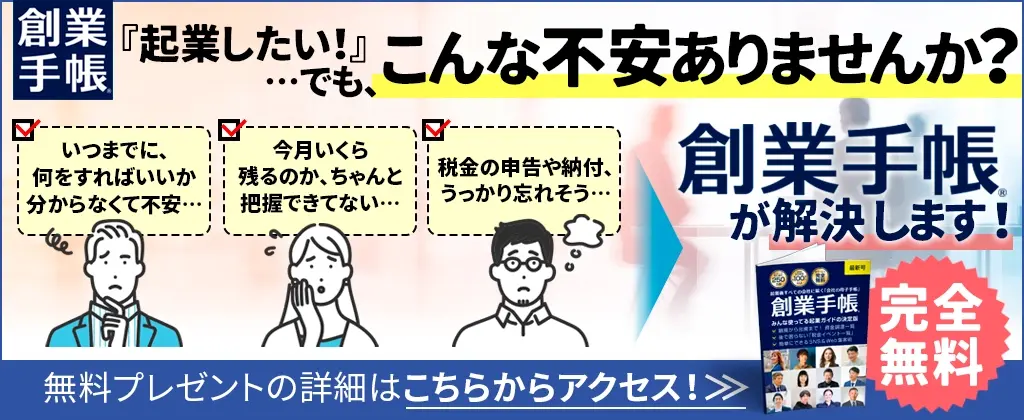
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主と法人どっちで起業すべきか?悩む理由

起業を検討する時、多くの人が「個人事業主で始めるか法人を設立するか」で迷う状況に直面するでしょう。
しかし、どちらで起業すべきかの情報は多く出回っているものの、比較の軸や自分に合う判断基準がそもそもわからないケースもあります。
そのため、「どちらがいいのか判断が難しいから」と決断を先送りしてしまうケースも多いかもしれません。
正しい判断をするには、単なる情報収集だけでなく、自分の事業規模や将来計画を踏まえた状況整理が必要です。
ここでは個人事業主と法人のどちらがいいのかハッキリと決められない理由を紹介していきます。
情報が多すぎて比較が難しい
昔は個人事業主と法人のそれぞれの始め方について情報を集めるのが大変でした。
しかし、インターネットの発展によって多くの情報を短期間に集められるようになっています。
ところが調べやすくなった結果、インターネット上には個人事業主と法人のメリット・デメリット情報が大量に存在するため、正しい判断がしにくい状態が発生するようになりました。
情報源によって内容が異なることがあるので、どれを信頼して比較すべきか迷う場合もあります。
体系的に整理された比較ポイントがないと、自分に合った起業形態の判断が困難です。
あれこれと情報を集め続けるのではなく、自分に合った情報を選定して見つけるようにしなければいけません。
将来の事業規模や収益を予測しにくい
起業時点では、これから始める事業の売上や成長スピードが不明確です。
どれだけの利益が出るのかが把握できなければ、税金や社会保険の負担がどちらに有利か判断できません。
例えば、起業する時に初期費用が少ない個人事業主で始めたとします。
事業規模が大きくなったら法人化しようと考えていると、売上が想定以上に増え、法人化するタイミングやコストを見誤ってしまい法人化しないままコストが膨らむケースも考えられます。
無計画に決定すると後から手間や費用が増える可能性があるので、あらゆる要素を考えて事業規模や収益予想を立てなくてはいけません。
手続きやコスト感が把握しにくい
個人事業主と法人では設立手続きや初期費用に大きな差があります。法人は手続きも費用も大きくなるため、起業前にまとまった資金を用意しておかなければいけません。
しかし、起業しようとしている人の中には、法人設立の具体的なコスト感を理解していないケースが散見されます。
法人設立にかかる費用や手続きの煩雑さを把握していないと、後で費用や手間の負担が大きくて後悔するかもしれません。
個人事業主と法人の比較ポイントを整理した上で、これから発生する設立手続きや費用の見通しを持つことが、迷わず選ぶための鍵といえるでしょう。
「とりあえず個人で…」が落とし穴になることも

起業する人の中には「まずは手軽に個人事業主で始めよう」と考える人もいるでしょう。もちろんそれ自体は間違いではありません。
しかし、後になってから「もっと早く法人にしておけば…」と後悔するケースもあります。ここでは法人化のタイミングや知っておきたいコストについて紹介します。
将来的な法人化に手間と費用がかかる
起業するときに個人事業主と法人のどちらか悩んだ時、法人のほうが費用がかかるからと個人事業主を選んだ人もいるかもしれません。
しかし、個人事業主から法人に変更する場合でも、変更のタイミングで登記手続きや定款作成といった費用がかかり、20万円前後は用意が必要です。
加えて、法人化にともなって過去の会計処理や税務申告の修正が必要になれば、その手続きに時間と労力がかかります。
個人の資産や負債を適正に法人に引き継げているかどうか、売上や経費の計上にずれが発生していないかなど法人化のタイミングはミスが起きやすくなるので、税務調査を受ける可能性もあります。
事業開始時に法人化しておけば、これらの追加負担は避けられます。後から負担が発生することを考えれば早めに法人化しておいたほうが有利かもしれません。
税金や社会保険の負担が変化する
個人事業主から法人化すると税金や社会保険の負担も変化します。
個人事業主に課せられる所得税は累進課税で所得が大きくなれば税率が上がる仕組みです。法人化すると比例課税方式である法人税の対象になります。
法人税は所得の大小にかかわらず規模に応じた一定の税率で課税されます。
事業が大きくなって所得が増えれば個人での所得税負担が高くなるので、一定の税率である法人税のほうが節税できる場合もあるでしょう。
しかし、法人化すれば税金だけでなく社会保険の扱いが変わります。
それまで加入義務がなかったとしても、社会保険に強制加入になります。つまり、法人化して節税しても社会保険料の費用を新しく支払うことになるのです。
どちらのほうがコストが下がるかは、実際に試算しなければわかりません。
将来の収益予測を踏まえて、早めに将来の税負担を見通した起業形態を選ぶことが後悔を防ぐ手段です。
資金調達や信用力の制約がある
個人事業主で起業するデメリットのひとつが信用力の低さです。金融機関や取引先からの信用が法人に比べて低く、大口取引や融資で不利になる場合があります。
事業を拡大するタイミングで法人化しても、信用力の獲得には時間がかかり、資金調達のタイミングを逃すリスクがあります。
事業を大きくしたいと考えるのであれば初期段階で法人化を検討してください。法人で起業することで事業の拡大や融資申請をスムーズに進めやすくなります。
個人事業主か法人か迷わないために必要な「判断の軸」

自分の事業スタイルや将来像に合った起業形態を選ぶためには、比較ポイントを整理することが重要です。
ひとつの要素で決めるのではなく、個人事業主と法人それぞれの設立コストと税金・社会保険、信用力、節税・資金調達の柔軟性など、複数の観点で比較しなければいけません。
判断の軸を明確にすることで、直感や安易な選択ではなく納得感のある決断につなげることができます。
ここからは個人事業主と法人のそれぞれの判断の軸について紹介します。
設立コスト
個人事業主で始めるか、法人を設立するかの大きな違いが設立コストです。
個人事業主は、税務署に開業届を提出するだけで完了するため、費用も手間もほとんどかかりません。
一方で、法人を設立するには、法務局で法人登記が必要です。法人登記には多くの書類を準備するほか、法定費用や資本金も用意しなければいけません。
個人事業主であれば事業にかかる備品や仕入れ費用を除けばほぼ費用が発生しないのに対して、法人は設立する会社形態に応じた費用が発生します。
株式会社で約22万円、合同会社で約10万円が最低でも必要です。会社印の購入や社会保険への加入を考慮すれば費用はより大きくなります。
税金と社会保険の仕組み
個人事業主と法人では課せられる税金が異なります。個人事業主に課せられるのは、所得税と個人住民税、消費税、個人事業税です。
一方で、法人は法人税と法人住民税、消費税と法人事業税が課せられます。
所得税は、所得が多くなれば税率が上がります。法人税は、法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が決まる仕組みです。
所得税は所得金額が小さければ低い税率が適用されるものの、所得金額が大きくなれば法人税よりも高い税率となります。
一方で、所得税は事業が赤字であれば課税されないのに対して、法人に課される法人住民税は、赤字であっても均等割り部分が課税されます。
そのため、利益が少ないうちは個人事業主にしておいて、所得額が大きくなってくると法人化を検討するケースが多いです。
個人事業主の社会保険は、従業員が5人未満であれば加入義務がありません。法人は自分1人であっても社会保険に加入する義務があり、費用や事務負担が発生します。
どのような形で起業するかによって課せられる税金と社会保険が異なります。それぞれのケースをシミュレーションして、どちらが有利であるか判断してください。
信用力と取引のしやすさ
法人は設立するための負担が大きい分、社会的信用が高く取引先や金融機関からの契約や融資が比較的スムーズに行える点がメリットです。
個人事業主は信用力が法人に比べて低いため、大口取引や長期契約で不利になるケースがあります。取引先によっては、個人事業主とは取引をしないケースもあります。
取引の信頼性や資金調達の容易さを重視するのであれば、法人設立のメリットは大きいでしょう。
一方で、個人事業主であってもすでに有力な取引先がある場合や、資金調達の目途が立っている場合には個人事業主でも問題ない可能性もあります。
節税や資金調達の柔軟性
法人は経費の計上範囲や退職金制度の活用など、節税手段が多様で事業成長に応じた対策が可能です。 補助金や融資などの制度は個人事業主でも利用できます。
しかし、一般的には法人が利用できる制度のほうが柔軟で資金調達の幅は広いといわれています。
例えば、株式会社であれば株式や社債を発行して資金を調達することが可能です。
クラウドファンディングなら個人でも法人でも挑戦可能ですが、社会的な信用面で個人事業主では不利になるケースがあります。
事業拡大や長期的な利益確保を考える場合は、節税手段と資金調達の自由度が重要な判断材料になります。将来の戦略も考えてどちらにするか判断してください。
事業の将来計画と成長シナリオ
起業後の売上規模や事業拡大の見通しがあれば、個人事業主か法人かの適切な形態を判断することができます。
将来的に従業員を雇ったり、複数拠点で事業を展開する可能性がある場合は、早くに法人にしておくほうがスムーズに進むでしょう。
一方で、スモールビジネスからスタートして市場の反応次第では撤退するようなケースでは、個人事業主のほうが撤退までの手間やコストは少なくなります。
個人事業主にするか法人にするか考える時には、成長シナリオや資金調達の計画を軸にしてください。
長期的視点で考えることで、後から形態を変更する際の手間やコストを最小化できます。
リスク管理と責任範囲
個人事業主と法人ではリスクと責任の扱いも異なります。
個人事業主は無限責任で、事業で発生した損失や借入金を個人ですべて負う責任があります。つまり、事業に失敗して借金を作った時には、自分で返済しなければいけません。
一方で、法人は有限責任で個人財産と事業財産を分離でき、万が一の損失リスクを限定できる点がメリットです。
会社が倒産して借金があっても個人として責任を負うのは出資額までです。
安定して経営し続けるためには、万が一の事態も考えて個人としてどこまでの責任とリスクを負えるのか、リスク許容度に応じて起業形態を選ぶようにしてください。
働き方やライフスタイルとの相性
起業する時には、確保できる作業時間や家庭との両立を考慮してください。自分にとって負担が少なく、運営しやすい形態はどちらかイメージしてみましょう。
個人事業主は働き方の自由度が高い点が魅力です。法人は業務や手続きの負担が増えてしまうものの、法人を大きくしたいとモチベーションが高まるケースもあります。
その人のライフスタイルや性質に合わせた選択をすることが大切です。
長期的な働き方のイメージを軸にすることで、起業後のストレスやギャップ、後悔の減少につながります。
契約・雇用の柔軟性
従業員を雇用する予定がある場合は、法人化することで社会保険加入や給与支払処理などがスムーズに行えます。
ただし、従業員を雇用している法人の場合、廃業時の手続きが複雑になる点に注意してください。
個人事業主であっても従業員は雇用できますが、法人より社会的信用が低いため、人材の確保に苦労するかもしれません。
将来的に事業を大きくして従業員を増やす場合には、法人化しておくことも検討してください。
「あとから法人に変えることもできるけど…」よくある失敗例と注意点

個人事業主で始めて、後から法人に切り替えることは可能です。ただしその際に手間やコストが発生し、「もっと早く決めておけば…」と後悔することもあるでしょう。
事前に知っておきたい注意点を紹介します。
① タイミングを誤ると発生する負担
個人事業主から法人化する際には、登記・社会保険加入・税務処理などの手間が一度に重なります。
会社が成長するタイミングは、事業拡大に集中したいと考える経営者が多いはずです。このタイミングに切り替えるとあまりに負担が大きく、後悔するかもしれません。
個人事業主として一定期間運営した後に法人化すると、事業成長にともなう税務や会計手続きが複雑化するほか、社会保険加入や登記手続きなどの事務負担が大きくなるケースが発生します。
事業開始時点で法人化の必要性とタイミングを検討しておいて後からの手間やコストを最小限にしてください。
② 経理・税務の引き継ぎで起きやすいトラブル
個人事業主での経理内容を法人に引き継ぐ時には、過去の確定申告や帳簿の修正が求められる可能性があります。
経理の修正作業はミスが起きやすく、専門家のサポートや追加費用が発生する場合もあるでしょう。
事前に法人化することで、会計や税務処理の二重管理を避け、効率的に運営できます。
③ 信用力・資金調達の機会を逃すリスク
個人事業主として信用力が十分でない段階で法人化すると、融資や大口取引で有利に進められない場合があります。
後から法人化したとしても、そこから信用を確立するには時間がかかり、事業拡大の機会を逃してしまうケースもあるかもしれません。
早期に法人化することで、信用力を確保し、融資や契約をスムーズに進めやすくなります。限られたビジネスチャンスをうまく掴むために早期法人化を検討してください。
まとめ:自分に合った起業スタイルを選ぶために
自分に合った起業スタイルを選ぶためには、個人事業主と法人の違いやメリット・デメリットを理解し、自分の事業規模や将来像に合わせて選択することが重要です。
様々な要素をばらばらに考えるよりも、設立コスト、税金・社会保険、信用力、節税・資金調達の柔軟性など、比較ポイントを軸にして判断することで将来の後悔を避けやすくなります。
早めに最適な起業形態を決めることで、手続きや資金調達の負担を抑え、事業拡大をスムーズに進めてください。
起業の準備を考え始めたら、『創業手帳(無料)』をチェックしてみましょう。
会社設立の流れや資金調達、開業後の実務まで、起業前に知っておきたいポイントを一冊に凝縮。
さらに、スケジュール管理に役立つ『創業カレンダー(無料)』を使えば、起業前後1年間でのやることリストが一目でわかるカレンダー形式でまとまっています!
(編集:創業手帳編集部)