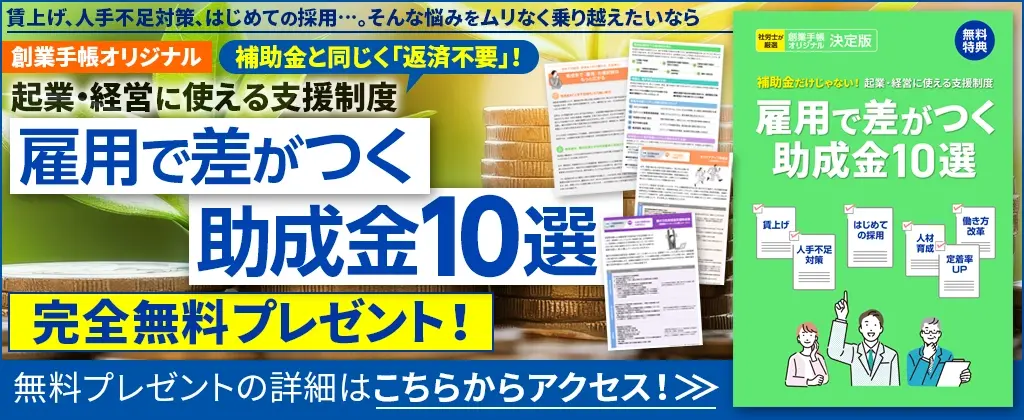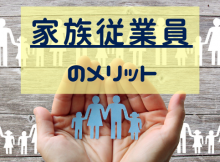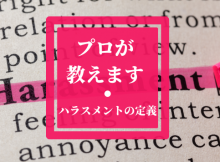【2025年最新】最低賃金は東京都で1226円に!生活への影響と事業主が備えるべきことを解説
最低賃金は全国平均で66円アップ!2026年3月までに順次改定
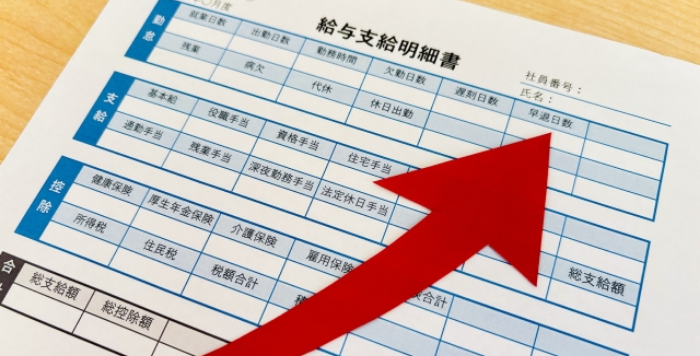
2025年度の最低賃金は、前年度比6%という大幅な引き上げとなる予定です。この引き上げは、物価上昇が続く中で国民の生活水準を改善する狙いがある一方、事業主にとっては人件費の増加という経営課題をもたらしています。
最低賃金の上昇は、中小企業の経営圧迫や雇用機会の減少といったリスクも伴います。生産性向上を伴わない中での賃金上昇は、企業の倒産・廃業の増加を招く可能性があるため、事業主は戦略的な対応を検討しなければなりません。
本記事では、2025年度の最低賃金上昇が、従業員と事業主に与える具体的な影響について詳しく解説します。
2025年度の最低賃金の上昇額
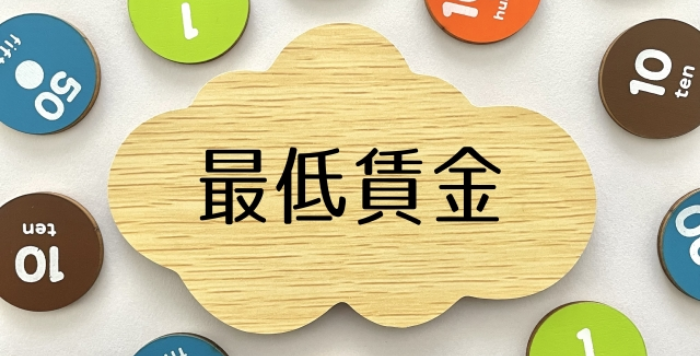
2025年8月4日に、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、令和7年度地域別最低賃金額改定について答申しました。答申内容によると、全国加重平均で最低賃金は時給1,118円となりました。
最低賃金は都道府県の経済実態に応じてランク分けされており、A・Bランクが63円、Cランクが64円となっています。この引き上げにより、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みです。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ額(円) | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 1068 | 64 | 2025-10-01 |
| 新潟 | 1050 | 65 | 2025-10-02 |
| 長野 | 1061 | 63 | 2025-10-03 |
| 東京 | 1226 | 63 | 2025-10-03 |
| 千葉 | 1140 | 64 | 2025-10-03 |
| 宮城 | 1038 | 65 | 2025-10-04 |
| 北海道 | 1075 | 65 | 2025-10-04 |
| 神奈川 | 1225 | 63 | 2025-10-04 |
| 兵庫 | 1116 | 64 | 2025-10-04 |
| 鳥取 | 1030 | 73 | 2025-10-04 |
| 滋賀 | 1080 | 63 | 2025-10-05 |
| 石川 | 1054 | 70 | 2025-10-08 |
| 福井 | 1053 | 69 | 2025-10-08 |
| 富山 | 1062 | 64 | 2025-10-12 |
| 茨城 | 1074 | 69 | 2025-10-12 |
| 大阪 | 1177 | 63 | 2025-10-16 |
| 山口 | 1043 | 64 | 2025-10-16 |
| 愛知 | 1140 | 63 | 2025-10-18 |
| 岐阜 | 1065 | 64 | 2025-10-18 |
| 香川 | 1036 | 66 | 2025-10-18 |
| 鹿児島 | 1026 | 73 | 2025-11-01 |
| 埼玉 | 1141 | 63 | 2025-11-01 |
| 静岡 | 1097 | 63 | 2025-11-01 |
| 広島 | 1085 | 65 | 2025-11-01 |
| 和歌山 | 1045 | 65 | 2025-11-01 |
| 奈良 | 1051 | 65 | 2025-11-16 |
| 福岡 | 1057 | 65 | 2025-11-16 |
| 宮崎 | 1023 | 71 | 2025-11-16 |
| 島根 | 1033 | 71 | 2025-11-17 |
| 青森 | 1029 | 76 | 2025-11-21 |
| 京都 | 1122 | 64 | 2025-11-21 |
| 三重 | 1087 | 64 | 2025-11-21 |
| 佐賀 | 1030 | 74 | 2025-11-21 |
| 岡山 | 1047 | 65 | 2025-12-01 |
| 山梨 | 1052 | 64 | 2025-12-01 |
| 岩手 | 1031 | 79 | 2025-12-01 |
| 愛媛 | 1033 | 77 | 2025-12-01 |
| 高知 | 1023 | 71 | 2025-12-01 |
| 長崎 | 1031 | 78 | 2025-12-01 |
| 沖縄 | 1023 | 71 | 2025-12-01 |
| 福島 | 1033 | 78 | 2026-01-01 |
| 徳島 | 1046 | 66 | 2026-01-01 |
| 熊本 | 1034 | 82 | 2026-01-01 |
| 大分 | 1035 | 81 | 2026-01-01 |
| 群馬 | 1063 | 78 | 2026-03-01 |
| 秋田 | 1031 | 80 | 2026-03-31 |
例年であれば、改定時期は10月頃です。しかし、各都道府県の地方最低賃金審議会での審議を経て最終決定されるため、実際の発効日は都道府県によって異なります。
企業の負担を考慮し、年明け2026年になってから新しい最低賃金を適用する都道府県もあるようです。
【従業員側】最低賃金が上昇するメリット

最低賃金の上昇は、従業員にさまざまなメリットをもたらします。物価上昇が続く現在の経済環境において、生活を改善する効果が期待できるでしょう。
生活水準の向上と経済的安定
最低賃金の引き上げによる直接的なメリットは、可処分所得(手取り収入)の増加です。2025年度の6%という大幅な引き上げにより、時給1,000円で働いていた労働者の場合、時給が1,060円となります。
年間の労働時間を1,800時間と仮定すると、年収は180万円から190万8,000円となり、10万8,000円の増加です。この所得増加により、食料品や電気・ガス料金など、家計の負担軽減効果が期待できるでしょう。家計に余裕が生まれれば、教育費や老後資金といった将来への投資にも充てることもできます。
経済的安定性の観点から見ると、最低賃金の上昇は低所得層の消費拡大を促し、地域経済の活性化にもつながります。つまり、個人の生活改善だけでなく、社会全体の経済循環にも良い影響を与える効果が期待されるのです。
仕事へのモチベーション向上
適正な賃金水準を実現することで、仕事に対する意欲や責任感が向上します。報酬が増えるという経済的なインセンティブはもちろん、「自身の価値が認められた」という実感をもたらし、やりがいを感じられるでしょう。
仕事のモチベーション向上は、自己実現とも密接に関係しています。熱心に業務を行い、組織への貢献度が高まれば、達成感を得られるはずです。
社会保障の恩恵
最低賃金の上昇により、新しく社会保険に加入する人が出てきます。特定適用事業所に勤務している場合、年収が106万円を超えると、社会保険に加入します。これにより、健康保険制度から手厚い給付(傷病手当金や出産手当金)を受けられるようになり、さらに将来受け取れる年金額も増加します。
年収の壁を超えると、「手取りが減る」というネガティブな意見を持たれがちです。しかし、働けなくなった場合の所得保障を得られたり、老後の長生きリスクに備えたりするうえで、社会保険への加入は効果的です。
【従業員側】最低賃金が上昇するデメリット

一方で、最低賃金の上昇は従業員にとってデメリットも伴います。特に、企業の経営状況によっては、労働環境の悪化や雇用機会の減少といったリスクが生じる可能性があります。
雇用機会の減少リスク
最低賃金上昇の恩恵を受けられるのは、当然ですが「雇用されている場合」です。
最低賃金の上昇は、人件費負担の増大をもたらします。財務的な基盤が弱い中小企業では、採用抑制や既存従業員のシフト削減につながる可能性があります。そのため、結果的に収入が思ったほど伸びない、という事態が起こり得るのです。
飲食業やサービス業といった業界では、人件費が売上に占める割合が高い傾向にあります。急激な賃金上昇に対応するため、営業時間の短縮や店舗数の削減を余儀なくされるケースが起こり得るでしょう。
また、企業によっては業務の自動化や省力化投資を加速させることで、省人化の動きが強まる可能性もあります。セルフレジの導入拡大やAIによる顧客対応システムの普及などは、雇用機会の減少をもたらす要因となり得るでしょう。
業務負担の増加
人件費の上昇に対応するため、少数精鋭での運営にシフトする企業が増えると考えられます。この場合、一人あたりが担当する業務範囲の拡大や、これまで以上の効率性を求められることになるでしょう。
従来は複数人で分担していた業務を、一人で担うことが求められるかもしれません。これにより、個々の従業員にかかる責任と負担が増大し、ストレスや疲労の蓄積につながる可能性があります。
年収の壁を超えることによる負担増
最低賃金が上昇しても、社会保険の壁である106万円や130万円の壁に変更はありません。
106万円の壁を超えると、勤務先の社会保険に加入することになります(特定適用事業所に勤務している場合)。130万円の壁を超えると、親族の扶養から抜けなければなりません。
なお、最低賃金の上昇に伴って、週20時間就労すると「106万円の壁」を超えやすくなります。たとえば、時給1,100円で毎月80時間(週20時間)働いた場合、月給が88,000円となり、106万円の壁を越えます。
実質的に106万円の壁の存在意義がなくなるため、政府は年収の壁の撤廃について、当初の予定よりも早める方向で調整しています。早ければ2026年度から撤廃される可能性があり、実現すれば多くのパート従業員が社会保険に加入しなければなりません。
その結果、社会保険料の納付義務が生じ、手取り収入が減ってしまう事態が起こり得るでしょう。
【事業主側】最低賃金が上昇するメリット

最低賃金の上昇は、事業主にとって人件費増加という負担をもたらす一方で、中長期的にはプラスの効果も期待できます。
人材定着による採用コスト削減
最低賃金の上昇により、企業の人材獲得・定着力が向上します。適正な賃金水準は、従業員の離職率低下に直結し、結果的に企業の採用コスト・研修コストの削減につながるためです。
労働市場が売り手市場となっている現在、優秀な人材の確保は、企業の競争力を左右する重要な要素です。従業員の待遇改善により、他社への転職を検討していた人材の流出を防げる効果が期待できます。
なお、新規採用の際には、以下のようにさまざまなコストが発生します。
- 求人広告費
- 面接や選考にかかる人事担当者の時間コスト
- 新人研修費用
- 戦力化になるまでの生産性の低下など
人材の定着率向上により、これらの隠れたコストを大幅に削減することが可能です。
顧客サービスの向上
従業員のモチベーション向上により、顧客に対するサービス品質の改善が期待できます。適正な賃金を受け取ることで、従業員の職務満足度や帰属意識が高まるためです。従業員の「もっと貢献したい」という意識が高まれば、丁寧な顧客対応を実現できるでしょう。
また、離職率の低下により経験豊富な従業員が定着することで、サービスの安定性と専門性の向上も期待できます。熟練した従業員による高品質なサービスは、顧客のリピート率向上や口コミによる新規顧客獲得につながり、売上増加に寄与します。
業務の効率化
人件費増加の圧力は、業務効率化やDX投資を促進するきっかけになるかもしれません。「省人化してコストを抑えつつ、生産性を高める」という方向で事業を進めれば、これまで人手に頼っていた作業の自動化や、ITツールの導入による業務プロセスの見直しが加速するでしょう。
単なるコスト削減にとどまらず、従業員の過重労働を抑えつつ、より付加価値の高い業務に集中できる環境整備にもつながります。その結果、従業員の健康維持やスキルアップ機会の提供にもつながり、労使双方の満足度が高まります。
【事業主側】最低賃金が上昇するデメリット

最低賃金の上昇は、特に中小企業に対して深刻な経営上のデメリットをもたらします。具体的な影響を見てみましょう。
人件費の増加
最低賃金の上昇による最も直接的な影響は、人件費の増加です。
月に100時間勤務するパート従業員を雇用している場合、月額換算で6,000円以上の負担増となる計算です。雇用している従業員数次第では、毎月の人件費負担が数十万円規模で増加することになります。
社会保険料の企業負担分も忘れてはいけません。賃金の上昇に伴い社会保険に加入する従業員がいると、健康保険料や厚生年金保険料の企業負担分も比例して増加します。生産性向上を伴わない中で人件費負担が重くなると、企業の倒産・廃業につながりかねません。
価格転嫁の必要性
人件費の増加分を企業収益で吸収することが困難な場合、販売する商品やサービス価格への転嫁をしなければなりません。
しかし、中小企業の多くは、大企業との取引において価格決定権を持たない立場にあります。取引先や顧客離れを防ぐために、コストの上昇分を販売価格に完全に転嫁できないケースもあり得るでしょう。
消費者向けビジネスにおいても、価格競争が激しい市場では、安易な値上げは顧客離れを招く可能性があります。近隣の競合他社が価格を据え置いた場合、売上の大幅な減少につながるリスクもあるでしょう。
年収の壁への配慮
パートタイム労働者の中には、年収の壁を超えないような就業調整をしている方もいるでしょう。最低賃金改定後も「扶養の範囲で働きたい」という希望を持っている場合、企業はこれらの従業員の労働時間調整に配慮しなければなりません。
手取り収入の減少を避けるため、労働時間の短縮を希望するケースが増加すると、人手の確保も難しくなります。つまり、最低賃金の改定は優れた人材を定着させるメリットが期待できる反面、就業調整により人手不足に陥るリスクも孕んでいるのです。
事業主が進めるべき対策

最低賃金の上昇が迫っている中で、中小企業は戦略的な対応を進めなければなりません。単純に人件費増加を受け入れるだけでは企業経営に深刻な影響を与えるため、多角的なアプローチによる対策が必要です。
省力化への取り組み
業務の自動化とデジタル化は、人件費上昇への対応として効果的な手段の一つです。
たとえば、勤怠管理システムの導入により、タイムカードの集計作業や給与計算の手間を大幅に削減できます。クラウド会計システムの活用により、経理業務の効率化と正確性向上が図れるでしょう。
予約・注文システムのオンライン化により、電話対応や受付業務の人的負担を軽減し、より付加価値の高い業務に人員を配置することが可能になります。飲食業やサービス業では、セルフオーダーシステムやモバイル決済の導入により、接客効率の大幅な向上が期待できます。
業務効率化への取り組み
業務プロセスの見直しに着手すれば、投資コストをかけずに効率化を実現できる可能性があります。無駄な工程の排除や作業手順を見直し、同じ作業時間でより多くの成果を上げる方法がないか検討しましょう。
事務業務においては、承認フローの簡素化や書類のペーパーレス化により、処理時間の大幅な短縮が可能です。また、前例踏襲的に行われてきた業務に関しては、抜本的に見直す余地がないか検討してみてください。
従業員への投資
取引先や顧客からの信頼を得るためには、従業員が高いパフォーマンスを発揮できる環境作りが欠かせません。あわせて、従業員の能力開発やスキルアップなどを通じて、一人あたりの生産性向上を図りましょう。
従業員の定着率向上と採用力強化を図るために、福利厚生の充実化も効果的です。たとえば、柔軟な勤務制度の導入により、子育てや介護を抱える従業員の離職を防ぐことが可能です。
賃金アップを単なるコスト増として捉えるのではなく、従業員のやりがいやキャリア形成と結びつけ、生産性向上への意識改革を促しましょう。
人材の活用の最適化
人件費を抑えるためには、人材配置の最適化が欠かせません。需要予測に基づく精密な人員配置により、無駄な人件費を削減しましょう。
たとえば、POSシステムのデータ分析により、時間帯別・曜日別の売上パターンを把握できます。これにより、繁閑の差にあわせて最適な人員配置を計画できるでしょう。
「ジョブローテーション制度」を導入し、一人が複数業務をこなせるよう育成することも効果的です。販売員が在庫管理や商品発注も担当できるようになれば、少数精鋭での運営を実現でき、専門スタッフの配置を削減できます。
人的リソースに限りがある場合は、外部人材を活用しましょう。スポット的な専門業務を外部委託することで、業務の質を維持しつつ、コスト効率を向上させることが可能です。
付加価値の向上と差別化戦略の立案
自社のサービスや商品を購入してもらうためにも、付加価値の向上と差別化戦略の立案は欠かせません。競合に負けないこと、市場に受け入れられることを念頭に置き、商品開発を行う必要があります。
単純な値上げは顧客離れを招くリスクがあるため、顧客の納得感を得られる工夫が必要です。サービスや商品の付加価値を高めることで、価格改定への理解を得られるでしょう。
付加価値が高い商品を開発・提供すれば、人件費増を売上増で吸収することが可能です。顧客のニーズを詳細に分析し、競合他社にはない独自の価値提案を行い、独自の事業領域を構築しましょう。
支援制度の活用
厚生労働省や経済産業省が行っている助成金・補助金制度の活用も効果的です。人材採用や事業投資をする際に有効活用できるため、積極的に検討しましょう。
たとえば、「業務改善助成金」は生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)や賃上げを行った場合、費用の一部を助成する制度です。「キャリアアップ助成金」を活用すれば、非正規労働者の正社員化や処遇改善の取組みを実施したとき、助成金を受けられます。
「IT導入補助金」を活用すれば、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)などのITツールを導入する際、かかる経費の一部について補助を受けられます。
最低賃金法違反による罰則

最低賃金法に違反すると、罰則が適用されるため注意が必要です。
地域別最低賃金以上の給与を支払わない場合、最低賃金法40条に基づき50万円以下の罰金に処されることになります。特定(産業別)最低賃金以上の給与を支払わない場合、労働基準法24条の賃金支払いの5原則に反するため、同法120条に基づき30万円以下の罰金が課されます。
新しい最低賃金が適用される時期は、従業員に支払っている賃金が最低賃金を下回っていないか、特に注意しましょう。最低賃金法に違反すると、「最低賃金以下で働かせる企業」というイメージを持たれてしまうリスクがあります。その結果、採用活動が難しくなったり取引先・顧客から評価を失ったりして、事業継続に重大な影響を与えるかもしれません。
まとめ
2025年度の最低賃金は前年度比6%という大幅な引き上げとなり、従業員と事業主の双方に大きな影響をもたらします。
最低賃金の引き上げにより、事業主は業務効率化・省力化への取り組みに注力する必要性が高まります。人件費を抑えるために、人材配置の最適化やIT・DX活用による自動化などを、積極的に検討しましょう。
最低賃金の改定に備えるなら、助成金を賢く使うことがカギ。創業手帳が提供する 「雇用で差がつく助成金10選」 は、社会保険労務士のアドバイスをもとに“本当に使える”助成金を厳選し、支給対象や助成率、申請の流れまで一目でわかる便利な一冊です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。