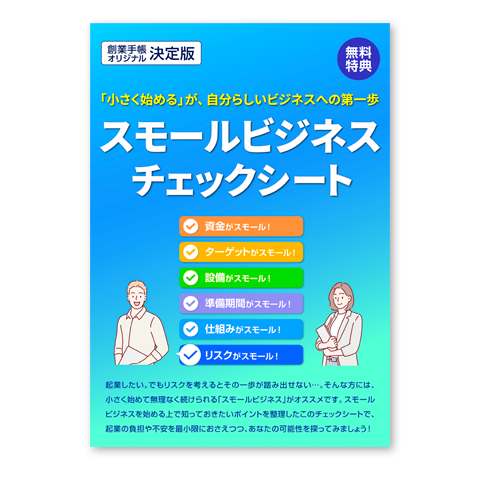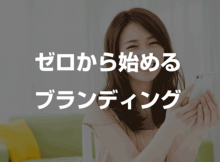中小企業の平均年収はどれくらい?従業員の年収を決めるポイントも解説
中小企業の平均年収を参考に従業員の給与を設定しよう

中小企業の経営者は、自社で働く従業員に労働の対価として給与を支払う義務があります。
給与は最低賃金額以上で設定することになりますが、具体的にどのくらいの金額を設定すべきか悩むところです。
そのような時は中小企業の平均年収を参考に、従業員の給与を考えてみるのもひとつの方法です。
今回は、中小企業の平均年収や給与の決め方やポイント、賃上げのメリットなどについて紹介します。
一般的な年収額を知りたい人や、給与設定のポイントについて知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
中小企業の平均年収は352万~373万円

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、中企業の平均賃金は31万1,400円、小企業では29万400円です。
これを年収に換算すると、中企業は約373万円、小企業では約352万円となります。
企業によっては賞与などがプラスさせるため、実際にはもう少し高い年収を得ている人も多いことが考えられます。
なお、大企業の平均賃金は34万6,000円です。大企業と中小企業の賃金格差は、大企業を100とした時、中企業は90.0、小企業では85.0です。
令和2年の数値は、中企業は87.0、小企業では81.7であるため、令和5年の数値と比べると大企業との格差は少なくなっています。
男女別平均年収
中小企業の平均年収は、性別によって異なります。男性の平均賃金は、中企業で34万1、600円、小企業で31万9,800万円です。
年収に換算すると、中企業は約409万円、小企業では約383万円となります。
一方、女性の平均賃金は、中企業で26万2,500円、小企業では24万8,400円です。年収に換算すると、中企業は約315万円、小企業は約298万円となります。
男女どちらの年収も、小企業より中企業のほうが高めです。
平均年収を男女で比べると、中企業は94万円、小企業では85万円ほどの差があり、男性のほうが年収は高いです。
年齢別平均年収
中小企業の年齢別(男女計)の平均賃金と年収換算は以下のとおりです。
| 年齢 | 中企業 | 小企業 | ||
| 平均賃金 | 年収換算 | 平均賃金 | 平均換算 | |
| ~19歳 | 18万8,900円 | 約226万円 | 18万6,700円 | 約224万円 |
| 20~24歳 | 22万900円 | 約265万円 | 21万4,700円 | 約257万円 |
| 25~29歳 | 25万3,400円 | 約304万円 | 24万5,600円 | 約294万円 |
| 30~34歳 | 27万7,600円 | 約333万円 | 26万9,000円 | 約322万円 |
| 35~39歳 | 30万5,800円 | 約366万円 | 29万1,000円 | 約349万円 |
| 40~44歳 | 33万1,600円 | 約397万円 | 30万6,600円 | 約367万円 |
| 45~49歳 | 35万300円 | 約420万円 | 32万2,000円 | 約386万円 |
| 50~54歳 | 36万1,100円 | 約433万円 | 33万円 | 約396万円 |
| 55~59歳 | 36万7,500円 | 約441万円 | 32万6,400円 | 約391万円 |
| 60~64歳 | 30万5,900円 | 約367万円 | 29万8,800円 | 約358万円 |
| 65~69歳 | 27万1,300円 | 約325万円 | 26万5,100円 | 約318万円 |
中企業・小企業ともに、歳が上がるごとに平均年収が高くなる傾向にあります。
その一方で、中企業では60歳から年収が下がります。
これは定年退職後に再就職すると、非正規雇用として新しく契約したり、役職手当が支給されなくなったりすることが原因です。
小企業でも、55歳以降は年収が減少傾向にあることがわかります。
地域別平均年収
中小企業の平均年収は、地域によっても異なります。全国計の平均賃金は、31万8,300円です。
この全国計よりも平均賃金が高い5つの都道府県は以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 | 年収換算 |
|---|---|---|
| 東京都 | 36万8,500円 | 約442万円 |
| 神奈川県 | 35万400円 | 約420万円 |
| 大阪 | 34万円 | 約408万円 |
| 栃木 | 32万3,000円 | 約387万円 |
| 愛知 | 32万1,800円 | 約386万円 |
最も平均賃金が高い都道府県は、東京都の36万8,500円です。年収に換算すると約442万円になります。
従業員の年収(給料)の決め方

企業が支払う給与は、一貫した体系を決める必要があります。給与は従業員の生活に関わるものであり、従業員が納得のいく給与制度を構築しなければなりません。
ここで、従業員の年収・給与を決める基本的な流れや計算方法を紹介します。
従業員の給与の決め方については、こちらの記事もご覧ください。
基本的な流れ
従業員の給与を決める基本的な流れは以下のとおりです。
1.給与相場の調査する
2.最低賃金をチェックする
3.残業代や有給休暇への影響を考える
4.社会保険料など給与以外の支出について考える
まずは、職種ごとに給与の相場を調査します。相場以下の給与に設定してしまうと、従業員が不満を持つ可能性が高いです。
また、給与が相場以下という理由で人材の確保が難しくなることもあることに注意しなければなりません。
さらに、都道府県ごとに定められている最低賃金を確認することも大切です。
最低賃金以下の給与は罰則の対象です。
なお、給与は残業代や有給休暇、社会保険料など、給与以外の支出にも影響を与えます。どのような影響が出るのか考慮しながら、給与・年収の設定が求められます。
計算方法
従業員の給与を決める場合、以下の公式を使用します。
従業員の給与=基本給+諸手当+評価給
基本給は賞与・残業代・退職金などに影響を与えるため、高く設定すると人件費全体の高騰につながります。そのため、高くしすぎないように注意してください。
基本給を抑える代わりに、中小企業に貢献してくれた従業員に対しては賞与を還元するのがおすすめです。
なお、実際に給与を支払う際は控除額を差し引いた手取り額が支給されます。手取り額を計算する方法は以下のとおりです。
手取り額=総支給額÷控除額
総支給額の計算は、勤務時間・増務賃金・各種手当に基づく必要があります。
控除額では、社会保険料や所得税・復興特別所得税、住民税を総支給額から差し引かなければなりません。
従業員の平均年収アップ(賃上げ)させることのメリット

可能であれば、従業員のために賃上げして平均年収をアップさせることをおすすめします。
賃上げをすることには、企業にとって以下3つのメリットがあります。
従業員のモチベーションアップ
賃上げをするメリットは、従業員のモチベーションを向上させられることです。生活していくためにはお金が必要で、お金を稼ぐためには仕事をしなければなりません。
賃金が少なかったり年収が増えなかったりすると不安を感じ、仕事に対するモチベーションも下がりやすいです。
しかし、賃上げによって月収・年収が増えることで、従業員の満足度は高まり、働く意欲や会社への愛着も強くなっていきます。
優秀な人材確保・定着
優秀な人材の確保や定着につながることも賃上げのメリットです。
職種や勤務形態などが同じ条件であっても、月収・年収の高さが職場を選択する決め手となるケースは珍しくありません。
給与が高いことは、求職者にわかりやすく好条件であることを伝えられます。
そのため、自社で求めるスキルや経験を持つ人材を雇いたい時、高い給与を提示することで、採用の成功率を高めることが可能です。
また、月収や年収に従業員が満足すれば離職率が下がり、人材の定着にもつながります。
生産性や経営戦略の改善
賃上げにより、生産性や経営戦略の改善につながるメリットがあります。
給与が上がることで働く意欲が高まれば、一生懸命仕事をして企業に貢献したいと考えるようになる従業員が増えます。
従業員が自ら進んで仕事をすれば生産性が高まり、企業の業績が上昇する可能性が高いです。
従業員の年収を適切に設定するためのポイント

従業員の給与は、企業への愛着や仕事へのモチベーションなどに大きく関わります。
しかし、適当に給与を設定してしまうと、資金繰りの悪化や従業員のやる気の低下につながるかもしれません。
ここで、従業員の年収を適切に設定するためのポイントを7つ紹介します。
業界の相場と比較する
年収を設定する際は、業界の相場を調査して比較してみてください。業界の水準よりも給与が低ければ、人材の確保が難しくなります。
一方、水準よりも高い給与であれば優秀な人材を確保できますが、企業の財政を圧迫する可能性があることに注意が必要です。
従業員や求職者を満足させた上で、企業にとって効果的かつ負担の少ない年金に設定するためには、業界の相場よりも少し高い程度が良いといえます。
業界の水準は国税庁のホームページなどで確認することが可能です。
自社の売上と利益比率を考慮する
年収を設定する際には、自社の売上と利益比率も考慮してください。労働分配率という指標を使うことで、適切に分配された人件費かどうかを判断できます。
労働分配率とは、企業活動の中で創出された付加価値のうち、人件費をどのくらい分配したのかを示すものです。
労働分配率が高ければ、高い人件費により従業員のモチベーションの向上などにつがっている反面、コストが経営を圧迫していると判断できます。
なお、労働分配率は「人件費÷付加価値額(粗利益)」で算出可能です。人件費には社会保険料や福利厚生費なども含みます。
自社の労働分配率を把握し、人件費と売上・利益とのバランスに問題がないかチェックしてみてください。
経済産業省のHPで業種ごとの労働分配率の平均値が掲載されているので、バランスの良し悪しの判断にチェックするのがおすすめです。
成果やスキルなどの評価基準を定める
従業員の成果やスキルなどに対して明確な評価基準を定めることも大切です。明確な評価基準があれば、支給されている給与の妥当性がわかり、従業員も納得できます。
また、従業員のモチベーション向上や、規律の取れた組織運営が可能です。
評価基準は、行動・成果・能力の3つを軸に決めるのが一般的です。従業員全員に頑張った分だけ報われると思ってもらえるように、適切な評価基準を設定してみてください。
できるだけ賞与を出す
賞与を出すことで、従業員の平均年収をアップできます。
給与とは別に支給される賞与は、従業員にとっては嬉しい収入です。起業や仕事に対する満足度を高める効果に期待できます。
賞与は、給与連動型と業績連動型の2種類に分けられます。このうち、業績連動型は従業員の業績を反映した賞与を支給することが可能です。
業績連動型は「基本給×支給月数×評価係数」で計算でき、評価係数によって賞与が増減される特徴があります。
この仕組みを採用して社内に周知させれば、従業員は業績を上げるために努力してくれるようになり、企業にとっても大きなメリットが生まれるでしょう。
社会保険料への考慮
年収の設定では、社会保険料への考慮が必要です。企業側は従業員の社会保険料の50%を負担する義務があります。
社会保険料は給与や賞与の金額が上がるほど増えていくため、企業側の負担も大きくなる可能性が高いです。
従業員の満足度を高めるために年収を上げても、社会保険料の負担が大きくなりすぎると経営が立ち行かなくなる恐れがあるので、バランスに考慮して年収を設定してください。
残業代の想定は必須
年収の設定では、残業代の支払いも考慮しなければなりません。トラブルの発生や繁忙期など、様々な理由から残業が発生することがあります。
企業側は残業代を支給しなけれなりません。 残業代は必要コストと考え、従業員の時間給に応じて定められた割増額を支給してください。
また、残業を見込めるようであれば、みなし残業として事前に給与の中に残業代を含んでおくのがおすすめです。
有給休暇の取得
年収の設定は、有給休暇の取得を前提に考えてください。
従業員が有給休暇を取得した際に支払う金額は、就業規則に従って平均賃金・通常の賃金・健康保険法上の標準報酬日額相当額の3つから選びます。
どの方法を選ぶかは、業務内容に合わせて決めることがポイントです。
「賃上げ促進税制」で節税と年収アップを両立!

賃上げ促進税制とは、賃上げや人材育成への投資に取り組む企業が利用できる、所定の所得控除を受けられる制度です。
中小企業の場合には、給与などの増加分の一部を法人税や所得税から控除できます。
賃上げ促進税制を活用することで、節税効果によって負担を抑えながら従業員の年収をアップすることが可能です。
その結果、従業員のモチベーションアップや人材の定着、企業のイメージアップなどにつながるでしょう。
賃上げ促進税制について詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ・従業員のモチベーションを上げつつ経営を圧迫させない年収設定をしよう
年収は従業員のモチベーションに大きく関わる要素です。しかし、過度に給与を上げてしまうと、経営を圧迫する可能性があります。
従業員に満足してもらい、経営に負担をかけないようにするためにも、給与体系は慎重に決めるようにしてください。
負担を軽減して賃上げをしたい時は、賃上げ促進税制についてもチェックしておくことをおすすめします。
創業手帳(冊子)では、経営の基本やノウハウについて紹介しています。最新のビジネス情報も掲載しているので、創業のサポートにご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)