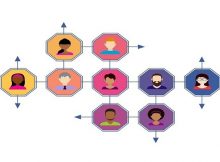ホワイトペーパーの作り方を解説│ゼロから成果につなげる構成・手順
ホワイトペーパーを作成して新規顧客の開拓につなげよう

企業が見込み顧客に対して、自社の商品・サービスの利用を促したい場合、「ホワイトペーパー」が活用されるケースがあります。
ホワイトペーパーを活用したマーケティング手法は、大手企業も導入しており、中小企業が実施しても効果が期待できる方法です。
そこで今回は、ホワイトペーパーの作り方から作成する時のコツ、さらに作成を時短化する方法まで解説します。
ホワイトペーパーを作成し、新規顧客の開拓につなげたい人はぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ホワイトペーパーとは?作る目的・効果・特徴

ホワイトペーパーとは、自社の商品・サービスに関連している有益な情報をお届けするコンテンツです。
例えば、企業による市場調査のレポートや最新の業界トレンド、自社製品と他社製品の比較情報などです。
自社の商品・サービスを一方的に売り込むものではなく、見込み顧客の育成(リードナーチャリング)や顧客との信頼関係を構築する目的で提供します。
また、ホワイトペーパーはダウンロードをするのに顧客情報を入力してもらうため、見込み顧客の企業名や担当者名、メールアドレスなどの情報を手に入れやすいという特徴もあります。
ホワイトペーパーの作り方

ホワイトペーパーを実際に作成するためには、どのような手順で行えば良いのでしょうか。ここで、ホワイトペーパーの作り方について解説します。
1.課題を設定する
まずは自社の商品・サービスによってどのような課題を解決できるのかを設定します。
1つのホワイトペーパーを作成する際に、取り上げる課題は1つまでに絞り込んだほうが内容もわかりやすいです。
例えば、CRMシステムを取り扱っていた場合、解決できる課題として以下が挙げられます。
-
- 顧客の個人情報や購入履歴、対応履歴などのデータがまとめて管理できる
- 顧客情報を分析し、一人ひとりに対してきめ細やかな対応ができるようになる
- 顧客満足度が高まり、顧客のLTV(ライフ・タイム・バリュー)の向上が期待できる など
2.目標を決める
課題を設定したら、次にホワイトペーパーを読んで顧客がどのような行動を取ってほしいのか目標を決めます。
例えば、「課題に対して解決する方法を知り、その解決のために必要な商品・サービスの購入を検討してもらう」などが挙げられます。
検討する段階にまで至らなければ商談に進めることはできません。そのため、抽象的な目標よりも具体的なアクションを目標に設定してみてください。
3.ターゲットを明確にする
課題と目標に加え、ターゲットを明確にすることも重要なポイントです。
老若男女を問わず役立つ資料を作ることも大切ですが、そうなると結局誰に向けた資料なのかがわかりづらくなり、内容も抽象的になりやすくなります。
より具体的でわかりやすい資料にするためにも、誰に向けた資料なのかを明確にすることが大切です。
ターゲットが明確になれば、どのような情報を掲載すれば良いのか、どのようなデザイン・表現方法を採用すれば良いかなども自然と定まってきます。
ターゲットを決める時はペルソナを設定してください。ペルソナで設定する項目は、例えば、企業の業種や規模、課題解決に向けて月にどれくらいの予算をかけられるか、などです。
4.構成を考える
ターゲットも決まったら、次にテーマと構成を決めていきます。ターゲットの悩みとなっている課題を解決するために役立つテーマを設定した上で、構成を決めます。
構成はそのテーマやターゲットなどによっても異なりますが、一般的な構成は以下のとおりです。
1.目的
2.導入文
3.問題の提起
4.解決方法の紹介
5.商品・サービスの紹介
6.結論
あらかじめどの項目にどれくらいページを割くのかも決めておくと、その後の原稿作成もしやすくなります。
5.原稿を作成する
ホワイトペーパーに掲載するデータなどを収集できたら、いよいよ原稿の作成に入ります。
データは最新のものだけでなく、過去に蓄積されたデータなどもあれば分析することで活用できる場合もあります。
また、データはできれば自社が調査したものでまとめるのが良いですが、情報を引用したい場合は信頼性の高いものを選ぶことが大切です。
出典元も必ず明記した上で引用するようにしてください。
文章を作成する時は、先に結論を提示してから詳細な説明を加えることで、読者の関心を引きます。
複雑かつ冗長な表現は避け、シンプルでわかりやすい言葉を使い説明してください。
さらに、読者が何を知りたいのか、何を求めているのかを常に意識して文章を構成すると、読者の課題解決につながる内容に仕上がります。
6.デザインやレイアウトを決める
原稿を作成できたら、デザインやレイアウトについても決めていきます。具体的にはフォントや文字の大きさ、配色、使用するグラフなどが挙げられます。
フォントは誰でも読みやすいものを選び、フォントサイズもページごとにバラバラにならないように気を付けてください。
配色は全体的に統一感を持たせることで、見やすくデザイン性の高いホワイトペーパーに仕上がります。
ホワイトペーパーに使用するカラーはベースカラー(文字に使う色)・メインカラー(見出し・ボックスの背景に使う色)・アクセントカラー(強調させたい箇所に使う色)の3つに絞り込んでください。
また、たくさん情報を紹介しようとしてテキストを詰め込みすぎると、かえって読みづらくなってしまいます。
グラフにできるところはグラフにして紹介したり、イラストなども取り入れたりしながら、わかりやすい資料作成を心がけてください。
7.校正・チェックをする
ホワイトペーパーが一通り完成したら、校正・チェックを行います。
一度公開してしまうとダウンロードされた資料は修正できないため、必ず誤字脱字・表記ゆれ・出典元などの確認を行ってください。
また、見込み顧客をターゲットに設定する場合が多いホワイトペーパーですが、専門用語・社内用語を多用すると、理解しづらい資料になってしまいます。
そのような点にもきちんと配慮できているかチェックすることも大切です。
確認する際には担当者1人だけでなく、必ず複数人から校正・チェックに入ってもらうことで、間違いにも気付きやすくなります。
高品質なホワイトペーパーを作成する時のコツ

高品質なホワイトペーパーを作成するためには、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか。
ここでは、高品質なホワイトペーパーを作成する時のコツについて解説します。
ターゲットに合わせて内容を設計する
ホワイトペーパーは読み手の課題や関心にフィットしないと、そもそもダウンロードしてもらえません。
そのため、「誰に向けたものか」を最初に明確にすることが重要となります。
課題や目標、ターゲットに合わせて、ホワイトペーパーの種類やテーマを変えて作成することも大切です。
例えば、商品・サービスについて認知させたい層や現在自社の商品・サービスに対して興味・関心を抱いている層、購入を視野に他社の商品と比較・検討している層は、それぞれ目標なども異なることから、別のホワイトペーパーを作成することになります。
ターゲットに合わせて内容を設計する際には、表現方法にも注意しなくてはなりません。
専門用語を使いすぎてしまうと、「ハードルが高い」と思われてしまう可能性があります。離脱リスクを防ぐためにも、わかりやすい表現を使うことが大切です。
自社の強み・独自性を盛り込む
ホワイトペーパーを作成する際に、自社の強みや独自性を盛り込むことも大切です。
自社がこれまでに蓄積してきたデータや独自で調査を行い判明した情報など、独自性の高い情報は内容に説得力を持たせ、信頼度を向上させてくれます。
また、自社ならではのデータが入ることで、類似したテーマでホワイトペーパーを作成している企業との差別化を図ることも可能です。
ただし、いくら自社の強み・独自性を盛り込みたいからといって、自社の商品・サービスを必要以上に強調するのは避けてください。
ホワイトペーパーは見込み顧客に有益な情報を提供するための資料であり、営業用の資料ではないことを理解した上で作成しましょう。
根拠のあるデータや事例を活用する
資料に説得力を持たせるためにも、根拠のあるデータや事例を活用することもポイントです。
例えば、事例紹介系のホワイトペーパーなら、実際に自社の商品・サービスを導入した企業に対してインタビューを行い、導入したきっかけや効果などをホワイトペーパーで紹介してください。
これにより、今現在導入を検討している企業も事例から実際に導入した際のイメージがしやすくなり、購入につながる可能性が高まります。
逆に根拠のないデータ、信頼できない引用データなどを活用してしまうと、信頼度が下がってしまう可能性があります。
根拠のないデータなどは情報として間違っている可能性があり、トラブルに発展する恐れもあるので情報の取り扱いには十分に注意しなくてはなりません。
出典元の記載は必ず行うようにしてください。
視覚的に見やすくする
図表やグラフ、箇条書きなどを用いることで、読者のストレスを減らせます。単調な文章だけだと読了されない可能性もあるので注意してください。
図表やグラフ、箇条書き以外で読みやすくする工夫としては、それぞれのページに見出しをつけ、どのような内容を紹介しているのかわかりやすくしたり、重要な文章には太字・マーカーを活用したりするなどです。
パッと見ただけでどのような内容が書かれているのかわかるくらい、直感的に理解しやすいホワイトペーパーを意識してください。
ホワイトペーパーの作成を時短化する方法

ホワイトペーパーを作成しようとすると、データの収集・分析から原稿・レイアウトの作成まで、様々な作業を必要とすることから、ある程度の時間と手間が必要です。
そこで、ホワイトペーパーの作成を時短化するための方法についても解説していきます。
AIやテンプレートを活用する
ホワイトペーパー作成の時短化を図るなら、AIやテンプレートの活用がおすすめです。テンプレートを活用すれば、原稿を考えてレイアウトを適宜調整するだけで完成します。
また、近年はホワイトペーパーを制作できるツールにAI機能も搭載されるようになりました。
AI機能を活用するとスライドの自動生成なども可能となり、資料を作成する手間が大幅に軽減されます。
AIやテンプレートをうまく活用すれば、大幅にリソースを割かなくても自社でホワイトペーパーの作成も可能になるため、導入を検討してみてください。
セミナー・ウェビナーの資料を活用する
これまで自社で開催したセミナーやウェビナーの資料をもとに、ホワイトペーパーを作成するのもおすすめの時短方法です。
セミナー・ウェビナーで使われた資料は、これまでに何度も手直しが加えられ、信頼性の高い資料に仕上がっている場合もあります。
この資料を活用すれば、信頼性の高いホワイトペーパーを作成することも可能です。
また、ホワイトペーパーをダウンロードした人に対して一般公開されていないセミナー時の動画を限定公開するなど、特典として活用することもできます。
この場合、動画の公開期間を1週間以内などに限定することで、エンゲージ率の向上につながります。
制作代行サービスを利用する
「AIやテンプレートを活用しても十分なリソースがない」「ホワイトペーパーを作るノウハウがない」といった場合は、自社で作成するよりも制作代行サービスに依頼したほうが良い場合もあります。
制作代行サービスは、ホワイトペーパーの戦略設計から制作、活用支援に至るまで、ホワイトペーパー制作に関する様々なサービスを提供してくれます。
ホワイトペーパー制作のプロが担当してくれることから、高品質なホワイトペーパーに仕上がる可能性が高いです。
また、社内のリソースを抑えられるため、従業員はコア業務に専念でき、さらにホワイトペーパーのリリースもできるようになります。
ただし、制作代行サービスを利用すると自社で作成するよりコストがかかってしまうこと、専門性が劣る可能性があることなどのデメリットも挙げられます。
サービスを利用するメリット・デメリットを理解した上で、自社は制作代行サービスを活用したほうが良いのか検討してみてください。
まとめ・コツを押さえて効果が出るホワイトペーパーを作ろう!
ホワイトペーパーは課題や目標、ターゲットの選定から構成決め、原稿の作成、デザイン・レイアウトの決定など、各フェーズでポイントを押さえることで、高品質なホワイトペーパーを作成することが可能です。
自社の状況に合わせて内製か外注かを検討しつつ、効果が出るホワイトペーパーを作成しましょう。
創業手帳(冊子版)は、中小企業に向けてマーケティングに関する様々な情報もお届けしています。自社はどのようなマーケティングを行えば良いのか、より効果的なマーケティングをするにはどうすれば良いのか検討している人は、ぜひ創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)