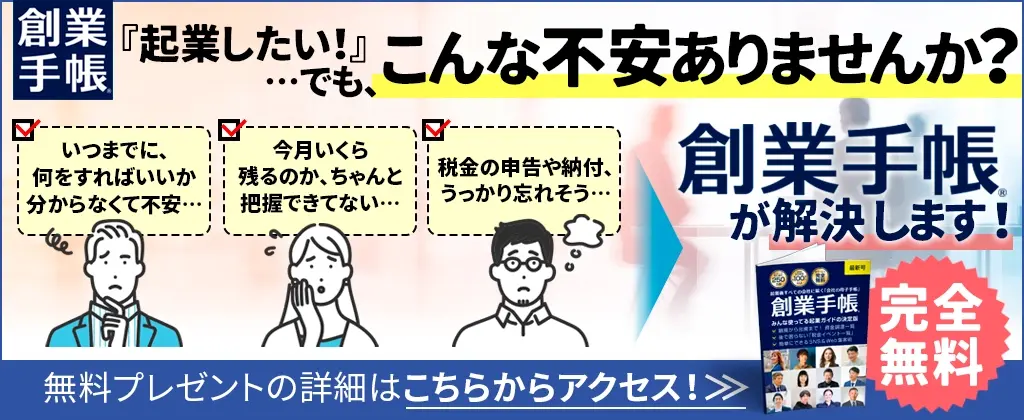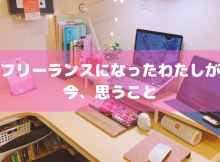起業後すぐにやっておくと得するお金の習慣5選
小さな習慣が大きな差を生む、起業家のお金管理法

起業後しばらくは、メインの事業から事務作業に至るまで様々な業務をこなす必要があることから、毎日忙しい日々が続きます。
しかし、この起業直後の段階で、習慣化しておくべきお金の動きがあります。
ここでお金の習慣を身につけておかないと、「売上げはあるのに手元にお金が残らない」「確定申告で慌てて作成することになる」などの事態を招いてしまうかもしれません。
そこで今回は、後から困らないためにも優先度の高い順に“得するお金の習慣”を5つ紹介します。
起業直後だからこそ習慣化しやすいものばかりなので、ぜひ今回の記事を参考にしつつ取り入れてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ「お金の習慣」が起業初期に大切なのか?

起業してしばらく経ってからお金の習慣を身につけるよりも、忙しくても起業初期に身につけたほうが良いでしょう。
なぜなら、起業初期は業務フローがまだ固まっていない段階で、習慣が定着しやすい時期だからという理由が挙げられます。
最初に作った仕組みはその後の事業運営の土台となるため、ここで良いお金の習慣を身につけておくべきです。
起業初期にお金の習慣が身についていないと、確定申告や融資の申請時に「必要な記録がない」「資料を揃えられない」などの問題に発展するケースは少なくありません。
仕事とプライベートの分別が不十分だったり、記録ができていなかったりすることで、本来受けられるはずだった節税メリットを逃す恐れもあります。
一度悪い習慣が身についてしまうと、後々軌道修正を図るのに多大な労力が必要となってしまうことから、起業初期に正しいお金の習慣を身につけることが大切です。
開業直後に身につけたい5つのお金の習慣

開業直後に身につけたいお金の習慣について紹介します。いずれの習慣も、今やっておけば後で楽になるものばかりです。
完璧を目指そうとせず、まずはできるものから1つずつ始めてみてください。
1. 事業用口座とプライベート口座を分けて管理する
まずは事業用口座とプライベート口座を分けて管理する習慣です。この習慣はすべての会計管理において基盤となる重要な習慣といえます。
「まだ売上げが少ないから分けなくても良いだろう」と考えていると、後から仕訳作業をするのに多くの手間をかけなくてはいけなくなります。
今のうちから習慣化しておくのがおすすめです。
なぜ重要?
事業用口座とプライベート口座を分けて管理するのが重要な理由は、事業で使った経費とプライベートで使ったお金を一緒の口座で管理すると、帳簿や資金繰りが複雑になってしまうためです。
確定申告の際も「これは事業で使ったものか、それともプライベートで使ったものか」がわからなくなってしまいます。
金融機関からの信用を得るためにも、事業用口座とプライベート用口座は分けて管理したほうが良いでしょう。
おすすめのやり方
事業用口座とプライベート用口座を分けるために、まずは銀行で事業用の口座を開設してください。
事業用口座が開設したら、売上や経費、税金の出入金をすべてこの口座にまとめます。事業用のクレジットカードも作成しておくと、経費を支払う際に便利です。
また、プライベートでの支出は事業用口座で行わないよう、財布やカードの使い分けなどを徹底しましょう。
得られるメリット
事業用口座とプライベート用口座を分けると、会計処理が楽に行えるようになります。
また、お金の流れが可視化され、今どのような経営状況にあるのかも判断しやすいです。
事業用口座が作られていることから金融機関からの信用も上がり、融資における審査がスムーズに進む可能性もあります。
さらに、すでにある程度仕訳された状態になっていることから、確定申告にかかる手間も大幅に軽減されます。
2. レシート・領収書はその日のうちに記録&保管
レシートや領収書はその日のうちに記録・保管する習慣も起業直後に身につけておくべきです。後でまとめて記録しようとすると、失敗する可能性があります。
また、感熱紙タイプのレシートや領収書は時間が経つと文字が消えてしまい、何にどれくらいお金がかかったのかわからなくなる恐れもあります。
なぜ重要?
レシートの文字が消えてしまったり、領収書を紛失したりすると、本来経費として計上できたものができなくなってしまいます。
経費の取りこぼしは直接的な損失でもあるため、注意が必要です。
また、もしレシートや領収書がどこにあるのかわからなくなってしまった場合、確定申告の際に探す手間が増え、より時間がかかってしまうことになります。
おすすめのやり方
レシートや領収書をその日のうちに記録・保管する習慣を身につけるには、会計ソフトの電子帳簿保存法対応機能の活用がおすすめです。
電子帳簿保存法によって、スマートフォンやスキャナで読み取ったレシート・領収書の電子データを保存できるようになりました。
これにより、その日のうちにレシートをスマートフォンで撮影し、会計ソフトに読み込ませることで手軽に記録・保管できるようになっています。
何に使った経費なのかわかりやすくするために、メモ欄に記録しておくのもおすすめです。
得られるメリット
レシートや領収書をその日のうちに記録・保管することで得られるメリットは、帳簿への記帳や確定申告などがスムーズになる点です。
また、経費の取りこぼしを防ぐことができ、節税効果を高めることもできるでしょう。
年度末に書類を整理しなくてはいけない時間も大幅に短縮され、事業に集中しやすいというメリットもあります。
さらに、税務調査が入った時にもすぐに記録を見せられるため、慌てずに済みます。
3. 毎月1回、収支を振り返る“お金の日”をつくる
毎月1回は収支を振り返る“お金の日”をつくることで、問題の早期発見に役立ちます。
「気付いたときには赤字だった」という事態も防げるため、習慣化しておくのがおすすめです。
なぜ重要?
収支を振り返るお金の日をつくっておくと、売上げが増えても利益が残らないといった事態を防げるようになります。
定期的に収支を振り返る時間を設けないと、今手元にどれくらいの資金があるのかがわかりづらくなり、問題の発見も遅れてしまいます。
そうなると資金繰りの予測が立てにくくなったり、経営の舵取りがうまくいかなかったりするので注意が必要です。
おすすめのやり方
収支を振り返るお金の日をつくるためには、月初または月末に必ず「お金の日」を設定するのがおすすめです。
当日は会計ソフトやスプレッドシートから前月の収支を確認し、支出の分析から改善点を見つけ、翌月のお金の使い方に活かしてください。
このとき、会計ソフトのレポート機能・グラフ機能などを活用すると、売上げや経費、利益の推移が可視化でき、より把握しやすくなります。
得られるメリット
お金の日をつくって定期的に収支を見直すメリットとして、経費の使い過ぎや売上げの不足などにすぐ気付ける点が挙げられます。
今どれくらい売り上げているのかが一目でわかるようになり、資金繰りの予測精度や経営判断のスピードも向上するでしょう。
4. 請求書はテンプレ+スケジュール化して自動運用
請求書発行の遅れや漏れがあった場合、キャッシュフローにも直接悪影響が出てしまう可能性があります。
そのため、請求書のテンプレ活用とスケジュール化の習慣により、うっかりミスを防ぐ仕組みづくりをしておくことが大切です。
なぜ重要?
請求書のテンプレ活用とスケジュール化が重要とされる理由に、入金を遅れないようにすることが挙げられます。
すべて手作業で一から請求書を作成していると、人的ミスや漏れが発生してしまう可能性が高まります。
請求書にミスがあると、クライアントや取引先との信頼関係にもヒビが入ってしまう恐れがあるため、ミスを防ぐためにも自動運用させるのがおすすめです。
おすすめのやり方
おすすめのやり方として、まず請求書のテンプレートを作成しておきます。
テンプレートはMisocaやfreee請求書、Excelのテンプレート(無料)などを活用すると、スムーズに作成できます。
さらに請求書の発行を忘れないように、締め日・送付日・入金確認日をGoogleカレンダーなどのスケジュールアプリを活用してリマインド設定してください。
また、支払い条件を「月末締め・翌月末払い」などに統一したり、請求書番号の管理ルールを最初に決めておいたりするのもおすすめです。
得られるメリット
請求書のテンプレート作成とスケジュール化によって、請求自体を忘れてしまうこともなくなり、さらにテンプレートによって作成時間の短縮につながります。
また、スケジュール化によっていつ入金されるのか予定が立ちやすくなり、資金繰りも安定しやすいです。
ミスをなくすことができれば、クライアントや取引先からの信頼度も向上します。
5. 目標利益から逆算して「使っていい金額」を決める
上記で紹介した習慣が身につき、収支を把握できるようになったら、戦略的な支出管理を行うことも大切です。
感覚で使うのではなく、目標利益から逆算して「使っていい金額」を決めるようにしてください。
なぜ重要?
使っていい金額を決めたほうがいい理由としては、目標を設定していない状態での支出は無駄な経費につながっている可能性が高いためです。
利益率を意識して経費を使わないと、いくら売上げが上がったとしても手元にお金が残らなくなってしまいます。
投資したほうがいい金額・削減したほうがいい金額を判断するためにも、あらかじめ使っていい金額を決めておくべきです。
おすすめのやり方
使っていい金額を決める際には、まず月次で必要な経費と残りたい利益を逆算しておきます。
次に目標となる利益率を設定し、その利益率に基づいて使える金額の上限を計算してください。
使っていい金額が決まったら、固定費・変動費・投資費用の3つに分けて予算を管理していきます。
また、お金を使うときは「この支出によって本当に利益につながるのか」と、一度立ち止まって考える習慣も身につけてください。
得られるメリット
使っていい金額を決めるメリットは、何といっても経費の使い過ぎを防げる点です。無駄遣いを防ぎ、利益率の向上も目指せます。
また、使っていい金額を明確にすることで、どこにお金をかけると利益につながりやすいのかもみえてきます。
起業後のお金の管理を続けるためのコツと、管理をしなかったときの後悔例

起業直後は頑張ってお金の管理をしていたものの、うまく習慣化ができず続けられなかったというケースもあるかもしれません。
お金を管理する上で、やり方を細かく覚えるよりもまずは習慣化させることが重要となってきます。
ここで、続けるためのコツと管理しなかった場合の後悔例について紹介します。
続けるための3つのコツ
お金の管理を続けるためには、小さく始めて徐々に精度を高めていくことがポイントになります。いきなり完璧な状態を求めず、少しずつでも続けていくことが大切です。
完璧を目指さず「月1回」から始める
最初から毎日記帳・仕訳などを行おうとすると、事業で手一杯になったときに続けられなくなり、そのままズルズルとやらなくなる可能性があります。
まずは月に1回まとめてお金を振り返る日を決めておき、その日は徹底して収支の見直しを図るようにしてみてください。
月1回に慣れてきたら週に1回、さらに慣れてきたら毎日の記録に移行しましょう。
自動化できる部分はツールに任せる
自分ですべてやろうとすると、やることが多くなりすぎて途中で挫けてしまうものです。
途中で挫折しないためにも、自動化できる部分はツールなどを活用してみてください。
例えば、レシートの読み取り機能を活用して手入力を最小限に抑えたり、請求書のテンプレートやリマインド機能を活用したりするなどです。
自力でやることを最小限に抑えれば、自分で行う負担も減り、継続しやすくなります。
習慣化は「行動+タイミング」のセットで決める
習慣化を目指すなら、習慣化したい行動とタイミングを1セットで考えることも大切です。
例えば、「外出先から帰宅したら、真っ先にレシートを撮影する」「17時からはほかの仕事をせず、レシートを保管する時間をつくる」などです。
カレンダーアプリのリマインド機能も活用すると、忘れにくくなり気付いたら習慣化されます。
管理をしなかった人によくある後悔例
続いて、きちんとお金の管理をしなかった人にみられる後悔したケースを紹介します。
どれも最初に少しずつやっていれば防げるものばかりなので、少しずつでも始めてみることが大切です。
経費のレシートをなくしてしまい、申告できなかった
後でまとめて記録しようとしたところ、経費に使ったレシートをなくしてしまい、確定申告で経費計上できなかったケースです。
このミスによって本来経費として計上できたものができなくなり、税負担が大きくなってしまいます。
1回にかかった金額は小さくても、何度もミスを繰り返していくうちにどんどん金額も膨れ上がっていきます。
請求書の発行が遅れて、入金が1カ月遅れた
請求書の発行が遅れてしまい、入金が1カ月以上遅れてしまうと、資金繰りに悪影響が出てしまいます。
手元にお金が届くまで時間がかかってしまうため、入金が遅れないようにスピーディーに請求書発行を行うべきです。
また、請求書発行が遅れてしまうことにより、クライアントや取引先からは良い印象を持たれないので注意してください。
確定申告直前にまとめて記帳しようとして苦労した
確定申告は1年間の収支をまとめて記録し、期限内に提出する必要があります。
確定申告の締切直前にまとめて記帳しようとすると、1年分のレシートや領収書を整理することになるため、数十時間はかかってしまうかもしれません。
自分だけでは対応できないからと税理士に依頼しようと思っても、高額な費用が発生してしまいます。
申告期限に間に合わなければ延滞税が発生してしまうため、慌てて記帳しなくてもいいように日頃から記帳することが大切です。
まとめ|お金の流れは「習慣」で決まる。最初が肝心!
起業直後は感覚でお金を使う人も少なくありません。しかし、今のうちにお金の習慣を身につけておくと、未来の資金力につながる可能性があります。
いきなり完璧を目指そうとするとかえって挫折する恐れがあるため、できそうなものから1つずつ始めていくようにしましょう。
創業手帳(冊子版)は、これから起業する人や起業したものの悩みを抱えている人に向けて、ビジネス・経営に役立つ情報をお届けしています。ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)