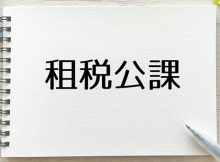お中元やお歳暮は経費にできる?勘定科目や注意点を徹底解説!
お中元やお歳暮は取引先との関係の円滑化を図る手段に使われる
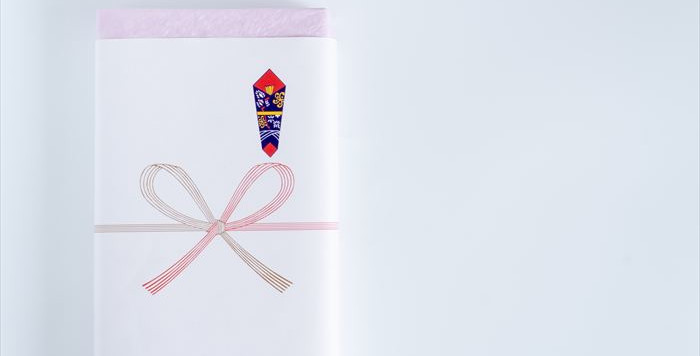
ビジネスシーンにおいて、お中元やお歳暮は単なる季節の挨拶にとどまらず、取引先との信頼関係を深め、円滑な関係を築くための重要なツールとして活用されています。
こうした文化は、企業のイメージアップや長期的な取引きの継続にもつながる可能性がある一方で、「経費として計上できるのか?」という疑問を抱く人も少なくありません。
そこで今回は、お中元やお歳暮が経費にできるかどうか、仕訳の際の勘定科目、さらに注意すべきポイントについてわかりやすく解説していきます。
お中元やお歳暮を贈ろうと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、経費の取り扱い方についてわかりやすくまとめた『経費で損しないためのチェックリスト』を作成。このチェックリストでは、経費を「人件費」「交際接待費」「広告宣伝費」など23の経費科目ごとに分解し、それぞれの「経費削減のポイント」と「節税につなげる」ポイントを整理しています。無料でお配りしていますのでぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
お中元やお歳暮は経費計上できる?
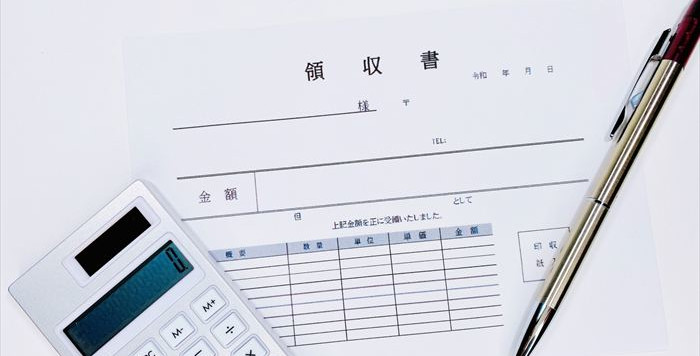
そもそもお中元やお歳暮は経費として認められているかどうかですが、結論からいえば事業を行う上で必要と判断できるお中元・お歳暮に関しては経費計上が可能です。
例えば、日頃お世話になっている取引先に贈るお中元・お歳暮は、経費として計上できます。
ただし、経営者のプライベートな付き合いしかない人にお中元・お歳暮を贈っても、事業をする上で必要ないと判断され、経費にはなりません。
また、場合によっては贈答品の受け取りを断っている企業もあります。先方には事前にお中元・お歳暮を贈っても問題ないか確認しておくと安心です。
お中元やお歳暮の勘定科目や仕訳方法
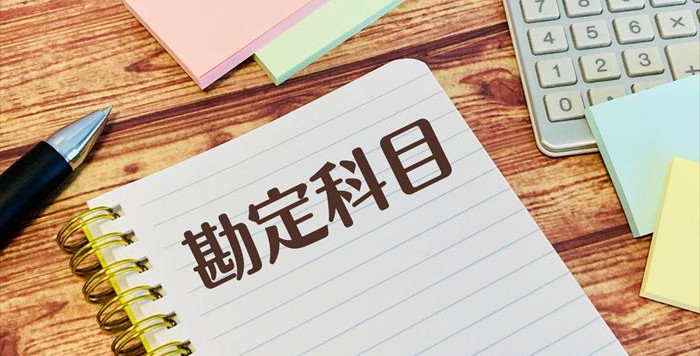
お中元やお歳暮を経費として計上する場合、勘定科目や仕訳方法はどのようになるのでしょうか。ここで、3つの勘定科目と仕訳方法を解説します。
| 勘定科目 | 使い分けの目安 | 金額の目安 |
| 接待交際費 | 基本的な勘定科目として使用 | 1社あたり5,000円~1万円 |
| 広告宣伝費 | 企業や店舗名を広める目的で贈る場合 | 全体の贈答品代 数万円~10万円以上 |
| 福利厚生費 | 全社員に平等に贈答品を配る場合 | 1人あたり5,000円~3万円 |
接待交際費
お中元やお歳暮を取引先に贈る場合、基本的には接待交際費として処理することがほとんどです。
接待交際費は企業が得意先や仕入れ先、その他事業の関係者などに接待や供応、慰安、贈答などの支出が含まれます。
お中元やお歳暮は得意先や仕入れ先などに対する贈答となるため、接待交際費で処理をします。
例えば、お中元の品を現金1万円で購入した場合、仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 接待交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
広告宣伝費
お中元やお歳暮は取引先などへ贈る際に、日頃の感謝の意を伝える目的で贈られることが多いですが、企業や店舗名などを広める目的で贈った場合は広告宣伝費としての処理が適しています。
例えば、自社の名前が入ったカレンダーや手帳などを不特定多数の人に贈るなどです。
ただし、広告宣伝費として注意したいのが配布対象です。特定の取引先にのみ配る場合は交際費と判断される可能性が高まります。
広告宣伝費として処理する場合は、配布対象が不特定多数であることが前提です。
例えば、店舗のキャンペーンで期間中、顧客全員に店名が入った品物を贈答したとします。
この贈答品を制作するのに合計10万円かかり、普通預金から支払いました。この場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 広告宣伝費 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
福利厚生費
お中元やお歳暮を贈る相手が従業員だった場合、接待交際費ではなく福利厚生費として扱われます。
また、お中元やお歳暮だけでなく、親族のお祝いや不幸などがあった際に支給されるもの(結婚祝い・出産祝い・香典など)も、福利厚生費です。
福利厚生費として処理する場合、贈答品をすべての従業員に対して平等に配られるものである必要があります。
例えば、結婚祝いや香典などはすべての従業員が該当した場合に支給されるものであり、従業員によって贈る人と贈らない人に分けていると、福利厚生費として扱われません。
むしろ、特定の人に対して贈り物をすると給与扱いになる可能性が高いです。
例えば、結婚した従業員に結婚祝いとしてお祝い品を贈答していたとします。この贈呈品を現金1万円で購入した場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 福利厚生費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
お中元・お歳暮はいくらまで経費になる?

お中元やお歳暮はいくらまでなら経費として計上できるのか、気になる人も多いはずです。
そこで、お中元やお歳暮はいくらまで経費になるのか、法人・個人事業主別に解説していきます。
法人の場合
贈答品の勘定科目は接待交際費・広告宣伝費・福利厚生費に分かれますが、基本的には接待交際費として処理することがほとんどです。
法人の場合、会社の規模によって接待交際費に上限が設けられています。
-
- 資本金1億円未満:接待飲食費の50%または年間800万円まで
- 資本金1億円以上:接待飲食費の50%まで
- 資本金100億円以上:損金算入は認められていない
資本金1億円未満の中小企業だと、接待飲食費の50%または年間800万円までなら損金算入が認められています。
例えば、接待飲食費に使った金額が合計1,000万円だった場合、1,000万円×50%=500万円になるため、年間800万円まで選んだほうが300万円分多く経費として処理できるでしょう。
上限が設けられていることから、贈答品を贈る得意先・取引先が多い場合には使いすぎに注意してください。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、法人とは違って接待交際費の上限は設けられていません。事業に関する支出であれば、無制限で接待交際費として計上できます。
ただし、あまりに高額な接待交際費や事業上必要と判断しにくい場合、税務調査で否認される可能性があるので注意が必要です。
上限がないからこそ、接待交際費として計上したい場合には事業に関する支出であることを証明できるようにすることが大切です。
お中元やお歳暮を経費にする際に気を付けること

お中元やお歳暮などを経費計上する際に、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
注意点を押さえておかないと、税務調査で否認される可能性もあるため、事前に確認しておいてください。
贈った記録を残しておく
お中元やお歳暮を経費にする際に、特に気を付けておきたいのは証拠を残しておくことです。
得意先や取引先に贈った証拠がないと、税務調査で否認されてしまい、経費として計上できなくなるリスクがあります。
贈答品を購入した際に受け取った領収書は必ず保管し、領収書の裏側などに贈る企業名や品物などを記録してください。
また、プライベートでもお中元・お歳暮を贈る予定がある場合、企業で贈る分と混同しないよう、あらかじめ送り先リストを準備しておくと安心です。
宅配便の送り状や領収書などもまとめておくと、誰に何を送ったのか記録として残せます。
高額すぎる贈り物は避ける
お中元やお歳暮の相場は5,000円~1万円程度といわれていますが、上限が1万円に決められているわけではありません。
ただし、あまりにも高額すぎる贈り物をして経費計上すると、税務調査の際に疑われてしまう可能性があるので注意してください。
特に贈答品が5万円以上する場合、個人的な支出として否認されるリスクが高まります。
また、どのような贈答品を贈るのかも注意が必要です。
例えば、1万円以上するような高価な貴金属・アクセサリーなどは、自分用または換金目的で買ったのではないかと税務署から指摘を受ける可能性があります。
税務署にから指摘を受けないようにするためにも、相場の5,000円~1万円の範囲内で贈答品を選ぶようにしてください。
勘定科目は統一する
お中元・お歳暮を経費計上する際に、接待交際費や広告宣伝費、福利厚生費といった勘定科目に分類されますが、これらの科目は社内で統一することが重要です。
例えば、「接待交際費」と記載する人もいれば、「交際費」とだけ記載する人もいます。
勘定科目の名称が異なっていると、会計処理の際に混乱を招いてしまうリスクが高いです。そのため、勘定科目は社内またはグループ全体で統一を図るようにしてください。
そもそも勘定科目には「継続性の原則」と呼ばれる法則によって、一度仕訳したものには同じ勘定科目を使い続けることが求められます。
正確に経理業務をこなすためにも、勘定科目は統一するようにしてください。
商品券は脱税につながる恐れがある
取引先などに贈るお中元・お歳暮の定番といえば、会社で手軽に味わえる焼き菓子や米菓、缶ジュースなどが挙げられます。
しかし、中には商品券や金券、ネットショッピングなどに使えるギフトカードのほうが使いやすいため、贈りたいと考える人もいるかもしれません。
商品券や金券、ギフトカードなども取引先などに贈答した場合には接待交際費として認められるものの、換金性が高く贈答した際に受領書などの証憑書類を受け取ることがないため、脱税を疑われる可能性が高いです。
絶対に贈ってはいけないというわけではありませんが、脱税と疑われないためにも別の贈答品を選んだほうが良いでしょう。
もしお中元・お歳暮用に1万円分の商品券を現金で購入した場合、仕訳例は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 接待交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | A社に贈る商品券 |
なお、贈答用の商品券を使用した場合は、経費処理を行わなくても問題ありません。これは、購入時に接待交際費としてすでに処理をしているためです。
お中元やお歳暮を贈ってはいけない相手は?

日頃からお世話になっている得意先・取引先に感謝の意を込めて、お中元やお歳暮を贈ろうと考える人もいますが、中には贈ってはいけない相手もいます。
お中元やお歳暮を贈る前に、相手が贈ってはいけない相手なのかどうか確認しておくことも大切です。
収賄と捉えられる相手
お中元やお歳暮を贈ることによって、収賄と捉えられてしまう可能性のある相手には贈らないほうが良いでしょう。
例えば、政治家や国家公務員・地方公務員、裁判官、警察官などが挙げられます。
公務員は基本的に利害関係者から金銭・物品を受け取ることを禁止しているため、会社として贈答するのはやめましょう。
また、利害関係にないプライベートであったとしても、万が一トラブルに発展する可能性も考慮して、事前にお中元やお歳暮を贈っても良いか確認してください。
なお、公務員以外でも医師や病院の職員は、「お中元・お歳暮を贈った人を贔屓するかもしれない」と不信感を持たれやすいことから、受取を拒否している病院もあります。
この場合も事前に病院側にお中元・お歳暮を贈っても問題ないか確認しておいてください。
自社の役員や従業員に対しての贈与
自社の役員や従業員全員に対して、平等にお中元・お歳暮を配った場合は福利厚生費として計上できます。
しかし、特定の役員や従業員に贈与した場合は、福利厚生費ではなく給与所得としてみなされる可能性が高いです。
給与所得としてみなされてしまうと、経費として計上できないのはもちろん、課税対象となってしまいます。
個人的に特定の従業員に対してお中元やお歳暮を贈り、経費として計上しないのであれば問題ありません。
贈答を禁止している企業
取引先によっては、贈答を禁止している企業もあります。
会社の方針として贈答を禁止しているため、お中元やお歳暮を贈ったとしても受け取りを拒否されてしまうでしょう。
贈答を禁止している理由として、受け取ることで利害関係が生まれることを防いだり、形式的な儀礼を排除するルールを設けていたりするなど、各社によって様々な理由が挙げられます。
お中元やお歳暮を贈る前に、まず先方が贈答の受け取りを禁止しているかどうかをリサーチしておくことが大切です。
忌中の相手
相手が喪中にある場合でも、熨斗や水引は使わずに、白無地の奉書紙や短冊に「お中元」「御中元」と書いて贈れば問題ありません。
ただし、相手が忌中だった場合は、お中元・お歳暮を贈ってしまうとマナー違反になるので注意が必要です。
忌中とは、仏式だと忌日(故人が亡くなった日)から四十九日法要が終わるまでの期間、神式だと忌日から五十日祭までの期間を指します。
忌中は遺族が法事や手続きなどで忙しくしており、なおかつ故人を失ってから日が浅いためまだ悲しみに暮れている時期です。
また、忌中に贈り物をするとお中元ではなく、香典と勘違いされる可能性もあります。こうした理由から、忌中の時期は避けたほうが良いでしょう。
まとめ・お中元やお歳暮の処理の仕方やマナーを正しく理解しよう
お中元やお歳暮は贈る側から感謝の気持ちを届ける文化です。一方で、経費として計上する場合にはルールに基づいて処理をする必要があります。
「何を」「どのような目的で」「いくらかかったのか」を記録したり、領収書をきちんと管理したりすることで、税務調査で疑われた際にも迅速に対応できます。
処理の仕方やマナーを正しく理解して、お中元やお歳暮を準備することが大切です。
創業手帳では、経費を「削減」するコツと、「計上」するコツ、2つを23の科目において解説した『経費で損しないためのチェックリスト』を無料でお配りしています。あわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)