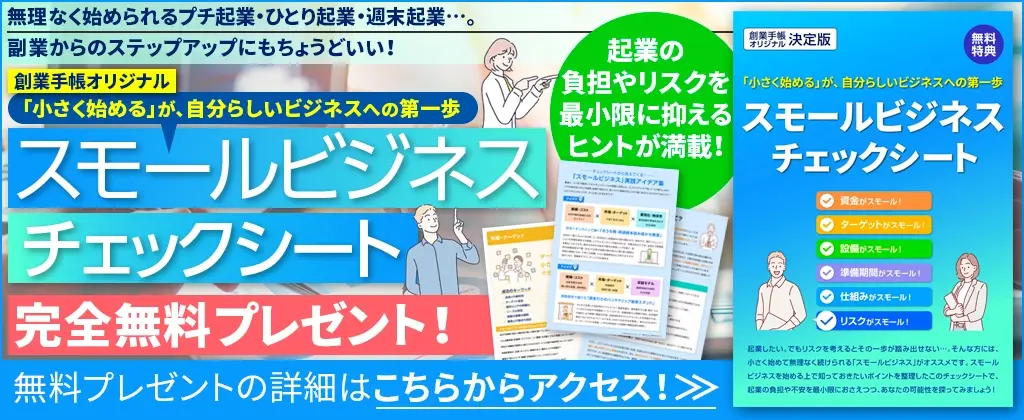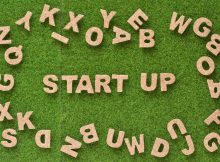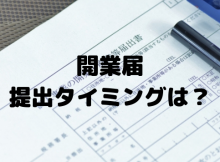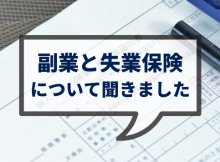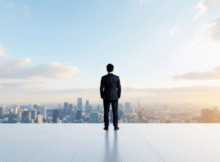公務員の副業はどこまでOK?許可されやすい範囲や事例、仕事選びの注意点を解説
公務員でもルールを守れば副業ができる時代になってきている
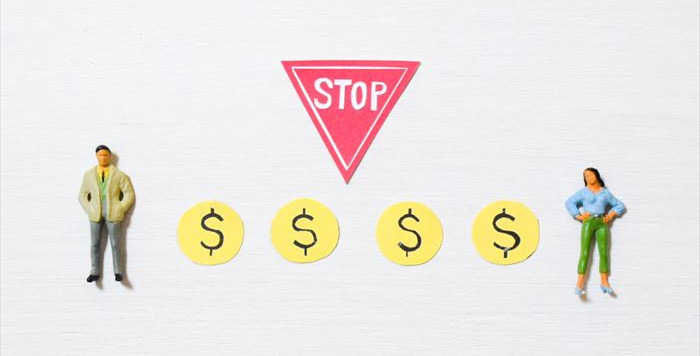
「公務員は副業が禁止されている」と思っていませんか?
厳密には公務員は副業が全くできないわけではなく、法律の順守や許可申請が必要などの制限があります。自己判断で勝手に副業すると、減給や停職などの処分を受けるかもしれません。
どのような副業であれば認められるかを知り、ルールを守って副業を始めましょう。国家公務員と地方公務員の違い、業種の選び方の目安なども解説します。
公務員でも認められる副業の形を選ぶうえで大切なのは、無理なく続けられる準備を整えることです。創業手帳では、副業や小さな事業を始める前に確認しておきたいポイントをまとめた「スモールビジネスチェックシート」を無料公開しています。安心して副業をスタートしたい方は、ぜひご活用ください。
創業手帳が無料提供している「創業カレンダー」で副業・起業の第一歩を踏み出しましょう。ややこしい各種届出や、資金準備など、まずは何から準備すべきなのかを分かりやすく整理。やり忘れていることがないか、お守り代わりに備えておきましょう。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
副業はできる?国家公務員と地方公務員との違い

多くの企業が副業を解禁しているものの、原則として公務員の副業には制限があり、場合によっては許可申請が必要です。
国家公務員法と地方公務員法では、公務にまつわる多くの決まりが定められており、中でも次の原則は副業の制限にも関わっていると解釈できます。
-
- 信用失墜行為の禁止
- 職務専念の義務
- 守秘義務
これらの原則では、職員としての仕事に支障が出るような行為をしたり、情報の流出があったりしてはならないことなどが示されています。
国家公務員と地方公務員とでは、規制する法律や具体的な内容が異なるので、さらに詳しくみていきましょう
国家公務員の副業制限
国家公務員は、次のような国家公務員法に基づき副業が制限されています。
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
出典:e-GOV 法令検索「国家公務員法」
営利企業での役員や自営業での副業は原則として認められておらず、許可を得た場合のみしかできません。
営利企業ではない会社での仕事でも、報酬を得る場合は許可が必要なほか、勤務時間などについては次の要件を満たす必要があります。
| 項目 | 主な要件 |
|---|---|
| 勤務時間 | 週8時間以下、1カ月30時間以下、平日(勤務日)3時間以下であること |
| 報酬 | 兼業報酬として社会通念上相当と認められる程度を超えない額であること |
| 業種の範囲 | 非営利団体での勤務(国、地方公共団体、自治会・町内会等) |
地方公務員の副業制限
地方公務員も、地方公務員法「営利企業への従事等の制限」などで副業の制限が定められています。
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。……
出典:e-GOV 法令検索「地方公務員法」
原則として許可なく副業を行うことはできません。
また就業している自治体ごとの許可基準にも従う必要があります。
2025年6月から地方公務員の副業規制に緩和の動き

2025年6月11日に「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知(以下、通知)」が各地方公共団体に通知されました。
通知により、地方公務員の副業許可の基準について指針が示されたことで、任命権者の個別判断を促し、結果的に副業を許可しやすい環境になることが期待されています。
具体的にどのような変化が期待されるか、通知の前後における地方公務員の副業の考え方を比較しました。
| 比較項目 | 通知後 | 通知前 |
|---|---|---|
| 基本ルール | 許可制 | 許可制 |
| 許可対象の副業 | 営利企業や自営業も、基本原則を満たば許可対象となり得ることが明確化 | 非営利の副業が中心で、営利目的のものは慎重な扱い |
| 許可判断の基準 | 3つの基本原則に基づく基準を推奨 | 自治体による |
| 報酬の基準 | 社会通念上相当であることが原則 | 自治体による |
| 労働時間の基準 | 週8時間、月30時間などの目安を設けることを推奨 | 自治体による |
これまでは判断の基準が曖昧だった自治体も、通知を参考に明確な基準を定めることで、公平な許可につながっていくと期待されます。
副業を考えている職員側も、許可基準が明確になることで両立のための調整や工夫がしやすくなるでしょう。
どこまでならOK?公務員の副業範囲の目安

通知により、これまで国家公務員向けの明示にとどまっていた、兼業の「労働時間」「報酬」などの制限についても、各自治体で基準を明確にする動きが出ているようです。
通知の内容などをもとに、公務員の副業がどこまで許可されるようになるのか、考え方の目安を具体的に紹介します。
あくまでも目安であるため、特に地方公務員の場合は各自治体が提示する基準にしたがってください。
労働時間は何時間まで?
地方公務員の副業の労働時間については、本業との時間を通算して判断するよう示されています。特にパートやアルバイトなど雇用契約が必要な副業は、労働基準法で定められている規制範囲(本業・副業通算で1日8時間、週40時間)への考慮が必要です。
では、労働基準法の制限が直接適用されない個人事業主としての仕事や自営業などの場合はどうでしょうか。
地方自治体の事例では、副業の許可において「週8時間以下、1カ月30時間以下、平日(勤務日)3時間以下」を基準の一つとするケースがいくつかあります。これは、国家公務員の兼業の許可基準と同じような内容です。
つまり、労働基準法の規制のような指針がない業種では、国家公務員と同等の要件を目安にするという考え方もできます。
また、地方公務員の副業が認められたケースでは、週休日や年次有給休暇を使って活動した事例もあるので、参考にしてください。
収入は月何円まで?
地方公務員が副業で得る収入の目安について、通知の中で「社会通念上相当と認められる範囲であること」と触れられています。これも、国家公務員の兼業についての指標で定められている内容の一部とほぼ同じです。
明確な基準でこそないものの、同種の事例における報酬額を参考とすることなどが示されているため、業種や他の職員のケースから慎重な判断が求められるでしょう。
職員側は、業界の平均報酬や各自治体で許可された例などから、報酬の妥当性を示せるような客観的な根拠を用意しておくといいかもしれません。
業種の範囲は?
業種の範囲は明確化されていません。ただし「営利企業の役員等の地位を兼ねる兼業」「自ら営利企業を営むこと」「報酬を得て行う事業または事務への従事」について、一定の条件下で認めることが可能であると、通知で示されました。
具体的には、基本的な原則を満たす場合に、各任命権者の判断において許可がおりる可能性があります。職務への影響や職員の品位が保たれるかなどがポイントです。
国家公務員でも、営利目的の副業については許可が必要となります。地方公務員も同様ですが、通知で具体例が明示されたことで、許可のための基準や判断軸の設定がわかりやすくなったといえるでしょう。
基本的な原則を満たせば、これまで社会貢献活動が中心だった地方公務員の副業に、民間企業でのアルバイトやパート、自営業といった選択肢の広がりが見込まれます。
公務員の副業が認められた事例

一部の地方自治体では、営利企業との兼業を認めている許可基準の例もあるなど、地方公務員の副業の選択肢が広がり始めています。
ここでは地方公務員の兼業が認められた事例について、職員のフィードバックとともに紹介しましょう。
山形県新庄市|商業活性化支援
山形県新庄市の事例では、主任級の職員が地元NPO法人「アンプ」の理事長となり、補助金に頼らない商店街活性化に取り組んだことが挙げられます。
具体的には、商店街全体を100円ショップに見立てる「100円商店街」イベントを企画、開催しました。週休日や年次有給休暇を使って年に50回ほど活動し、報酬は月に3万円程度です。
職員は商店街を活性化するためのアドバイザーとして各地を巡っていたことから、地元住民とのコミュニケーションで得られた知識や経験が公務にも役立っていると感じています。
佐賀県佐賀市|障がい者支援
佐賀県佐賀市の副業が認められた事例は、主事級の職員が共生社会の実現を目指して、任意団体「○○(まるまる)な障がい者の会」の代表として活動したことです。
報酬は月間2万円程度、週休日や年次有給休暇を使って週2~3回程度活動し、ラジオ番組の制作と発信のほか、障がい者交流事業(いきいきサロン)を実施しました。
市民活動の中で当事者の想いに寄り添って、それぞれの視点に立って考えることを学んだ姿勢が公務に役立っているとのことです。
A県B市|無料学習塾の講師
地方公務員の副業が教育分野に及ぶ事例もあります。この事例では、主査級および技師職の職員が、中学生の無料学習塾の学習支援員補助として活動したケースです。
主に数学の講師として、中学生の学力向上や学習習慣の確立を目指して働いています。月に3回程度、土曜日に活動し、報酬は日額6,000円程度でした。
中学生の指導を通じて、人に説明を行う技術の向上や部下への指導方法の改善につながるとして、職員自身も公務に役立つ体験だったと実感している事例です。
公務員でもできる可能性が高い副業8選

公務員の副業はどのようなものであれば認められるのか判断が困難です。ここでは、公務員でも認められている副業を8つ紹介します。
なお、ここで掲載している8つの副業は、人事院による「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」を参考に、国家公務員における考え方をベースにしたものです。地方公務員は原則として、自治体ごとの定めを基準としてください。
家業の手伝い
実家で農業や飲食店を営んでいる場合で、無報酬で家業の手伝いをする場合、公務員が副業できることがあります。報酬を得る場合は上司や職場などの許可が必要です。
許可が出たとしても、公務員の副業における三大原則は遵守しなければいけません。
家業が忙しくて本業に集中できなくなると、職務専念の義務を果たしていないと判断され禁止される可能性があります。
小規模農業
小規模の農業かつ自給目的であり、営利を目的としていない場合は、公務員の副業として選択できます。このケースで報酬もなければ、原則として許可は不要と考えられるでしょう。
ただし、作物を人に売ったりお店に卸したりした場合は営利目的の副業とみなされます。経営耕地面積によって規模が判断されることもあるので、事前に確認してください。
NPO活動
NPO活動は、許可を得ていれば公務員でも可能です。NPO法人は特定非営利活動法人であり、営利目的ではありません。そのため、許可さえあれば公務員も取り組めます。
特に、公益性が高い事業や地域に貢献する活動は認められやすくなります。
不動産投資
公務員の副業として、不動産投資も条件付きで認められる場合があります。
小規模な不動産投資は申請不要とされていますが、賃貸収入が年間500万円以上などの大規模な場合は許可を得なくてはなりません。
条件を超える利益や規模になりそうな時には上司に相談しましょう。不動産投資を始める前にどういった条件が提示されているのか確認しておいてください。
株式投資
株式やFXなどの所有・売買は資産形成のための行為であるため、公務員の副業・兼業の規制に抵触しません。ただし、一定以上の株式を所有する場合は報告が必要な可能性があるため、詳細は任命権者などに確認しましょう。
公務員として働く業務の中で一般企業の機密を知ってしまう可能性はあります。その情報を知った上で、その会社の株式を売買すればインサイダー取引となってしまうので注意してください。
執筆活動
執筆や講演といった活動も、公務員の仕事に支障がなければ許可される可能性が高い副業です。仮に単発の仕事で報酬を受け取っても、継続性がなければ国家公務員法第104条の”兼業”とはみなされません。
ただし、執筆したものを販売した時の印税は継続性のある報酬といえるため、許可が必要です。また、執筆内容が信用失墜行為の禁止や守秘義務に当てはまることがあれば活動が禁止されます。
アンケートモニター、ポイ活
アンケートモニターやポイ活について、公務員の兼業になり得るかは明示されていませんが、一般的にこれらの活動は副業ではなく節約の一環と考えられます。
アンケートに回答すると謝礼としてポイントを受け取れるなど、ポイント経由で報酬に還元するシステムがほとんどです。継続的かつ営利性のある事業活動とみなされることはほぼないといえるでしょう。
稼げる額は大きくありませんが、昼休みや通勤時間といったスキマ時間を利用しやすい稼ぎ方となります。
不用品の販売・フリマ
不用品の販売やフリーマーケットの出店は、営利目的ではなく副業にはなりません。ただし、転売になってしまえば営利目的となり、許可が必要な可能性が生じます。
フリマアプリで仕入れたものを販売する行為は、一般的に営利目的の転売です。許可が不要なのは、あくまでも不用品を手放した際の収入のみとなります。
公務員が避けたほうがいい副業は?微妙な業種の考え方

公務員ができる副業がある一方で、避けたほうが良いものも、判断に迷うものも多くあります。どのような副業を避けるべきか、迷う業種における考え方などをまとめました。
YouTuber・インフルエンサー
YouTuberやインフルエンサーは、比較的新しい副業です。YouTubeやSNSで発信して収益化したり、企業からの案件を受けたりして報酬を受け取ります。
趣味で行う分には問題なくても、継続的に収益を得ると営利目的の副業になってしまう可能性があります。
性質上気をつけなくてはならないのが、公務の信用失墜リスクです。失言や炎上などの恐れがつきまとうことから、許可を得ることは事実上難しいと言わざるを得ず、副業として行うのは避けたほうがいいでしょう。
アフィリエイト
アフィリエイトは、SNSやブログで商品を紹介してクリックや商品が購入されると報酬が発生する、成果報酬型ビジネスです。
アフィリエイト収入を得ているというだけで、ただちに兼業とみなされるわけではありません。一方、継続性や反復性のある場合や規模によっては公務員の兼業に当てはまる可能性があります。
趣味のブログ執筆やSNSの投稿であれば問題ないものの、継続して一定以上の収入があるなど兼業と見なされるようなケースでは許可が必要です。
イラストレーター
イラストレーターは、イラストをSNSや専用サイトで販売したり、イラストを受注して報酬を受け取ります。
イラストレーターは、通知の別添資料で触れられている「職員個人のスキルや地域の実情を踏まえた自営兼業」に該当する可能性が考えられます。スキルを活かして人手不足の会社にイラストを納品することなどが、想定できる仕事の例です。
報酬を得て活動する場合は許可が必要なことに変わりありませんが、営利目的だから一概に認められないわけではないため、公務員法や自治体ごとの基準を守る前提で許可申請を検討してください。
データ入力
データ入力はドキュメントソフトなどを使用して、指示されたデータを入力する仕事です。
収入を目的としている、つまり営利目的であるため、原則として許可がなければ認められません。単なるデータ入力は多くの場合公益性があるとはいえないことから、許可が認められにくいことが想定されます。
公務員の副業がバレるとどうなる?原因と注意点

許可が必要にもかかわらず無許可でしていた副業がバレたなど、公務員法に違反するような場合には、懲戒処分の対象になり得ます。
国家公務員であれば、次のような処分のいずれかです。
- 免職:職を失う
- 停職:1日以上1年以下の期間、職務に就けない
- 減給:1年以下の期間給料が減額となる
- 戒告:文章や口頭で注意を受ける
軽いものであれば厳重注意で済むこともありますが、評価や出世に影響するかもしれません。実際に副業がバレて懲戒処分となった事例もあるので注意してください。
どのようなルートからバレてしまうのか、原因や注意点を知っておきましょう。
公務員の副業がバレる主な原因
公務員の副業がバレる主な原因として、次のようなことがあげられます。
- 住民税や確定申告がきっかけになる
- 住民や同僚に見つかってしまう
- 第三者に話してしまう
副業の年間収入が20万円を超えると確定申告が必要になり、確定申告を通じた所得の増加によって支払う住民税も増えます。
一般的に住民税の金額は経理担当者が把握していることから、副業がバレてしまうのです。
副業しているところを住民や同僚に見つかったり、第三者に話してしまったりしてバレるケースもよく起こります。
近年は、SNSに身元がわかるような投稿を含めていることからバレるケースもあるでしょう。
公務員が副業する時の注意点
公務員が制限のある副業を許可なく行なっていた場合、厳しい処分がくだる恐れもあります。次の注意点を参考に、自己判断だけで副業をしないよう気をつけてください。
- 許可を得てから始める
- 上司に相談する
- 公益性のある副業を選ぶ
大前提として、営利性のある仕事など制限のある副業は、事前の許可を得ることが必要です。
地方公務員は自治体ごとの基準を遵守し、不明点があれば必ず上司に相談しましょう。曖昧にせず、細かな点まで確認しておくと安心です。
営利企業での兼業が全く認められないわけではないものの、公務員という立場上、公益性のある副業のほうが比較的認められやすい傾向にあります。
具体的には地域で開催されるスポーツ教室の指導員やNPO法人でのボランティア活動、専門知識を活かした非常勤講師などが公益性のある副業の例といえるでしょう。
まとめ:ルールを守って公務員も副業を始めよう
公務員が営利を目的とした副業を行う場合、原則として多くの制限があります。しかし、内容や性質から公務員でもできる副業もあるほか、地方自治体ごとに副業許可の基準を明確化する動きも出てきました。
公務員で副業を始めたいと思っている方は、隠れてバレないように始めるのではなく、ルールを守って公務員でもできる副業を始めましょう。
公務員の副業が少しずつ認められ始めた今、働き方や人生設計を見直す人が増えています。再設計の選択肢として起業を考えたとき、全体像の見える化をしておくと安心です。
副業を「やってみたい」で終わらせず、実際に成果につなげるには、事前のチェックが欠かせません。創業手帳の「スモールビジネスチェックシート(無料)」では、限られた時間や資金でも成功につながる準備のポイントを整理しています。副業を安心して進めたい方は、ぜひご活用ください。
また、「創業カレンダー(無料)」を使えば、起業前後の流れが時系列でわかるほか、カテゴリ別のチェックリストや手続き一覧も活用できます。
まずは副業から始める場合でも、将来的な選択のお守りとして持っておくと、いざというときの未来の行動が変わるはずです。
出典:
内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について(概要)」
総務省「(別添3)兼業許可基準を設定する際のポイント等」
内閣人事局・人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」
e-GOV 法令検索「国家公務員法」
e-GOV 法令検索「地方公務員法」
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。