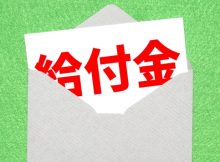個人事業主が失業時に受け取れる給付金とは?失業前の対策も紹介!
個人事業主は廃業しても失業保険を受給できない

会社を退職した後に受け取れる「失業保険(正式には雇用保険の基本手当)」は、実は個人事業主には適用されません。
その理由は、個人事業主が雇用保険や労災保険の対象外だからです。
廃業して無収入になったとしても、雇用保険に加入していなかった場合は、失業保険の受け取りはできません。
また、早期の再就職で支給される「再就職手当」も対象外となります。
自営業やフリーランスとして働く人にとっては、廃業や収入減少に備えて国の給付金制度や支援制度についての正しい知識が必要不可欠です。
そこで今回は、個人事業主が失業した場合に受け取れる給付金や、失業前の対策について解説します。
創業手帳では、登録した地方自治体の補助金・助成金情報を月2回メールで配信する「補助金AI」サービスを無料で提供しています。あわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主は「失業保険」を受け取れる?
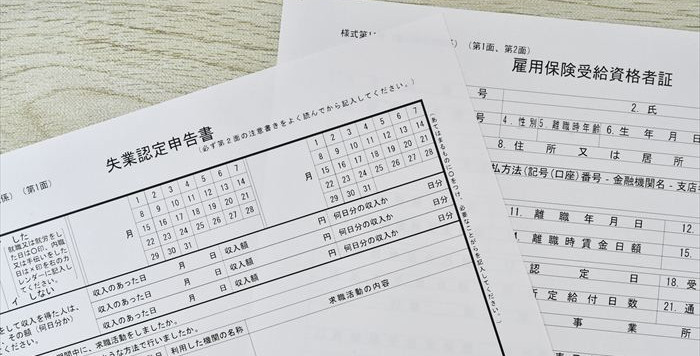
失業保険は、仕事を辞めてから再就職するまでの間、経済的な支えになる保険制度です。
失業中でも収入を得られるため、じっくりと転職先を探せます。ここからは、個人事業主でも失業保険を受け取れるかどうか解説します。
原則、雇用保険の適用外
失業保険の受け取りには、基本的に雇用保険への加入が必要です。雇用保険に加入できない個人事業主は失業保険を受けることができません。
個人事業主が雇用保険に加入できない理由として、仕事をする・しないを自分で決められるためと考えられています。
働く期間も自由に決められ自己責任になることから、廃業しても失業保険を受給できないのです。
例外として受け取れるケースはある?
個人事業主やフリーランスは、原則として雇用保険に加入できず、失業保険を受け取れません。
ただし、「会社員として働いていた人が、個人事業主として開業することになった場合」「過去に会社員として雇用保険に加入していた」場合など、一部のケースでは失業手当の対象になる可能性があります。
個人事業主が失業しそうな時に受け取れる給付金や補助金

失業保険を受けられなければ、失業(廃業)した場合に収入面で大きな不安につながるでしょう。ただし、個人事業主でも受け取れる給付金や補助金制度はあります。
住居確保給付金
住宅確保給付金とは、生活困窮者自立支援法に基づく給付金制度で、一定の要件を満たす人に住まいを確保するための給付金です。
住居確保給付金は住まいの確保を目的としていることから、「家賃の補助」と「転居費用の補助」に利用可能です。
家賃の支払いに悩んでいる人は、経営改善に向けた活動のサポートを受けるなど、様々な要件を満たすことで家賃額が補助されます。
また、家賃が安い住居に転居したくてもその費用を用意できない場合には、転居費用が補助されます。
要件
要件は、家賃の補助と転居費用の補助で若干異なります。
【家賃の補助】
収入と資産が以下の①と②を満たしていれば家賃の補助が受けられます。
①収入が基準額(住まいがある自治体によって金額が異なる)+家賃額(限度額あり)よりも少ない
②資産(預貯金や手持ち金)などの合計が、基準額の6倍以下(金額が100万円を超えた場合100万円以下)
【転居費用の補助】
以下の要件を満たすと、転居費用の補助が受けられます。
-
- 収入と資産の要件は家賃の補助と同様
- 家計改善の支援で、転居によって家計の改善が認められる
支給額
家賃の補助は各市区町村によって定められた金額が上限になりますが、実際の家賃額は原則3カ月間(延長は2回まで・最大9カ月間)支給されます。
原則として、住宅の貸主の口座に自治体からお金が直接振り込まれます。
一方、転居費用の補助で支給されるのは、転居にかかる費用です。上限や補助対象外(敷金や前家賃など)になる経費もあります。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的にサポートするための制度です。
個人ではなく世帯の自立を支援する制度であるため、世帯全体の状況を調査や審査を受ける必要があります。
生活福祉資金貸付制度にも様々な種類がありますが、個人事業主でも利用できるものは「総合支援資金」と「緊急小口資金」です。
総合支援資金は、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などに対する資金制度です。
一方の緊急小口資金は、一時的に生計を維持するのが難しくなった際に貸し付ける少額の制度を指します。
求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職や転職、スキルアップなどを目指す人に向けて、生活を支援するための給付金を支給しながら、職業訓練を受講するための制度です。
失業保険を受給できない個人事業主でも利用できます。
主な支援内容として、毎月の給付金と無料の職業訓練、さらにハローワークでの就職サポートが挙げられます。
テキスト代などは自己負担となりますが、給付金の支給要件を満たさなかった場合でも職業訓練を受けることは可能です。
また、就職サポートは、訓練の開始から終了までサポートしてもらえるので安心です。
要件
訓練を受講するための要件と、給付金を受け取るための要件は異なります。
- 【訓練を受講するための要件】
-
- ハローワークに求職の申し込みをしている
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではない
- 労働の意思と能力を持っている
- 職業訓練などの支援を行う必要があると、ハローワークが認めている
- 【給付金を受け取るための要件】
-
- 本人の収入が月8万円以下である
- 世帯全体の収入が月30万円以下である
- 世帯全体の金融資産が300万円以下である
- 現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない
- 訓練実施日にすべて出席する
※やむを得ない理由で職業訓練訓練を欠席する際には、証明できる場合でも8割以上は出席する
支給額
毎月支給される金額(職業訓練受講手当)は10万円です。受講中は、要件を満たせば1カ月ごとに支給されます。
また、以下も支給されます。
-
- 訓練施設へ通う際に必要な定期乗車券などの通所手当(月上限42,500円)
- 訓練施設へ通うために同居の配偶者や子ども、父母と別居して訓練施設に付属している宿泊施設やアパートなどに入居する場合に支給される寄宿手当(月10,700円)
自治体による制度の確認
国からの給付金や補助金制度のほかにも、各自治体が手がけている制度もあります。居住する自治体で利用できる制度を確認することが大切です。
例えば、以下のような制度が挙げられます。
・北海道苫小牧市「事業承継推進事業」
後継者がいない市内の中小・小規模事業者や個人事業主の廃業を防ぐために用意された、事業承継の取組みを支援する事業です。
事業承継をした経営者に対して100万円が支給されます。令和6年度分は、2025年3月31日で申請は終了しています。
・熊本県菊池市「菊池市事業承継推進事業補助金」
菊池市内で後継者問題を抱える事業者が事業を継続し、技術やサービス、雇用の喪失を防ぎつつさらなる地域経済の活性化を推進する目的でつくられました。
申請受付は2024年4月1日から随時行っていますが、予算上限に達している場合もあるため、利用したい場合は事前に確認してください。
なお、経営革新事業の補助上限額は2分の1以内で100万円まで、企業価値診断事業は2分の1以内で30万円が上限です。
給付金・補助金を受けるポイント

個人事業主が給付金・補助金を受ける際に、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
申請期限の確認
申請期限の確認は重要なことです。個人事業主が利用できる給付金や補助金制度は多くありますが、それぞれに申請期限が設けられています。
期限までに必要書類を準備して提出しなければ、申請は受けられません。
特に、複数の補助金制度を利用したいと考えている人は、申請期限を確認してスケジュールを立ててください。
受給までの期間を確認
給付金・補助金制度の申請が通った場合でも、すぐにお金が支給されるわけではありません。
制度によってタイミングは異なるものの、基本的には申請から受給に至るまで数カ月間の時間が必要です。
すぐにお金が支給されないことを念頭に置いて、申請する時期を考えてください。
【失業する前の対策】収入確保のために備える制度

個人事業主は失業保険を利用できないため、事前の備えが必要です。ここでは、収入を確保するために利用できる制度を紹介します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分が拠出した掛金を運用して資産形成を行う私的年金制度です。個人事業主の老後資金を確保するために活用できます。
掛金の額は自分で決めることができ、運用商品も自分で選択できます。
受け取りは原則60歳以降ですが、年金として分割で受け取るか、一時金としてまとめて受け取るか選択することが可能です。
なお、掛金は全額所得控除になり、利息や運用益なども非課税になるため、税金に対するメリットは大きいといえます。
ただし、原則60歳まで資産を引き出せない点には注意してください。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、国の機関でもある中小機構が運営する制度です。個人事業主や小規模企業の経営者・役員などの退職金制度として活用できます。
掛金は1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、加入後も自由な増減が可能です。また、全額課税対象所得からも控除されることから、節税効果に期待できます。
さらに、小規模企業共済を利用していれば、低金利の貸付制度も利用できます。掛金の範囲内で事業資金の貸付が可能であり、低金利かつ即日での貸付にも対応可能です。
貸付制度の種類には、一般貸付や緊急経営安定貸付、事業承継貸付、廃業準備貸付などがあります。
就業不能保険
就業不能保険は、病気やケガなどが原因で長期間働くことが難しくなり収入が減ってしまった際に、生活費をサポートするための保険です。
個人事業主は国民健康保険に加入できますが、企業の健康保険とは異なり、傷病手当金が給付されません。
そのため、働けなくなってしまった場合の負荷が大きく、収入面は不安定な状態に陥りやすいです。
一方、就業不能保険に加入しておけば働けなくなった場合の収入減少に対応でき、病気やケガの治療にも専念できます。
在宅療養や長期間にわたる入院費もカバーできます。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産リスクに備えた共済制度です。
個人事業主や中小企業は、取引先の数が少なかったり、取引先の財務情報を知るのが難しい状況にあったりすることなどから、取引先の倒産による影響を受けやすい傾向にあります。
経営セーフティ共済に加入していれば、取引先が倒産した場合に、貸付制度を利用して無担保・無保証人で資金を借入れることが可能です。
資金を借入れて取引先の倒産の影響を防げれば、連鎖的な倒産リスクも回避できます。なお、掛金は損金として計上でき、解約する際には解約手当金を受け取れます。
ただし、個人事業主の場合、加入するためには1年以上事業を継続していなければなりません。
また、12カ月以内に解約してしまうと、掛け捨てになってしまうことに注意してください。
労災の特別加入制度
労災は労働者を守るための制度であり、事業主に分類される個人事業主であれば基本的には利用できません。
一方、特別加入制度を活用すれば、個人事業主でも労災に加入できます。
労災の特別加入制度を利用すれば、仕事や通勤中にケガを負い働けなくなってしまった場合でも、保険金が給付されます。
なお、特別加入制度の対象となるのは、仕事の性質的に体を負傷しやすいと考えられる事業を展開する個人事業主です。
例えば、自動車を使って旅客または貨物運送を手がける事業や土木・建築などの事業、漁船による採捕事業などが挙げられます。
2024年11月からは業務委託を担うフリーランスの人も対象に含まれるようになり、特別加入制度を利用できる個人事業主も増えました。
ただし、労災の特別加入制度を利用するためには、個人事業主は直接申請することはできず、労働保険事務組合に加入する必要があります。
まとめ・個人事業主は失業前の対策と給付金制度について理解しておこう
個人事業主は、会社員のように失業保険に頼ることができません。
そのため、事業が不調になった場合に備えて、早めに公的支援制度や給付金の情報を収集しておくことが重要です。
例えば、小規模事業者向けの持続化補助金や生活福祉資金貸付制度など、条件を満たせば利用可能な支援策も存在します。
また、任意で加入できる雇用保険の特例制度(雇用保険の任意加入)や、民間の所得補償保険などを活用するのも方法のひとつです。
いざという時に慌てないよう、自分に合った備え方を考えておくことが安心につながります。
公的支援制度を早めにキャッチアップできるように、創業手帳では登録した地方自治体の補助金・助成金情報を月2回メールで配信する「補助金AI」サービスを無料で提供しています。あわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)