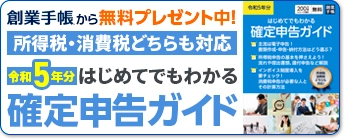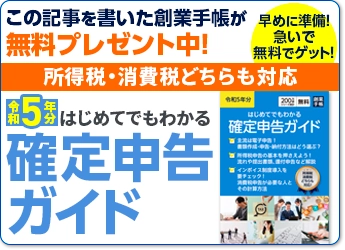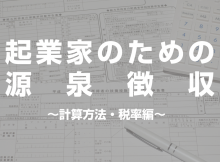【2026年最新】確定申告は5年以上前もさかのぼって申告できる?時効とペナルティを解説
確定申告はさかのぼって申告することも可能!

個人事業主やフリーランスは毎年、確定申告が必要です。しかし、「過去の申告を忘れていた」「経費の計上漏れがあった」というケースも少なくありません。確定申告は過去5年分(悪質な場合は7年分)までさかのぼって申告や修正が可能です。
現状を把握するためにも、以下の早見表を確認してみてください。
| 目的 | 遡れる期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 還付申告 (税金が戻る) |
5年 | 1日でも過ぎると受取不可 |
| 期限後申告 (払い忘れ) |
5年 | 放置すると罰金が重くなる |
| 修正申告 (間違いの修正) |
5年 | 税務調査前ならペナルティが軽い |
| 悪質な隠ぺい | 7年 | 税務署が過去7年分まで調査・徴収 |
放置期間が長いほど、「無申告加算税」などのペナルティが重くなる仕組みです。特に2024年(令和6年)以降、高額な無申告に対してペナルティが強化されています。
この記事では、過去分の申告期限や最新のペナルティ、過去データの確認方法などを紹介します。さかのぼって確定申告が必要になっている可能性がある人は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、確定申告の基本から解説した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。どのような時に確定申告が必要なのか、今年の変更についてなど、はじめて確定申告する方から毎年対応している方もご活用いただけます。ぜひご利用ください。
この記事の目次 すでに提出した申告内容を修正する場合も、5年以内ならさかのぼって修正可能です。ただし、期間に余裕があると放置するのは危険です。 税務署の指摘を受ける前に自主申告することで、ペナルティが軽減される特例があるため、気付いた時点ですぐに行動しましょう。 原則は5年前までさかのぼれますが、6年以上前の確定申告や修正は時効となり、申告できません。これは、国税通則法によって更正・決定できる期間が5年と定められており、この期間を過ぎると課税処分ができなくなるためです。 ただし、仮装・隠蔽などの不正行為が認定された場合、更正・決定できる期間が5年から7年に延長されるケースもあります。 申告義務があるのにしていなかった場合は、すぐ期限後申告を行ってください。期限後申告は申告義務のある所得税の申告・納税を期限後に行うことを指します。 しかし、税務署から指摘される前に自ら期限後申告を行うことで、ペナルティとなる無申告加算税の税率が5%に軽減されます。逆に税務署から指摘されるまで放置すると税率が上がるほか、所得の隠ぺい・偽装などが疑われ、さらにペナルティで最大40%の重加算税が課されかねません。 税金を納め過ぎてしまった場合、還付申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。 還付申告では確定申告書の中に必要事項を記載し、税務署に提出することで完了します。還付申告にペナルティは発生しません。ただし、還付申告の期限(対象となる年の翌年1月1日から5年間)を過ぎてしまうと還付を受けられなくなるため、早めの手続きが大切です。 過去の申告内容に誤りがあり、納税額が少なかった場合は修正申告が必要です。修正申告では確定申告書の第一表・第二表を修正内容で作成し、提出する必要があります。 修正申告は不足分の税金に加え、納付が遅れた日数分の延滞税も納めます。ただし、税務調査によって過少申告がわかった場合、過少申告加算税が上乗せされますが、自主的な修正申告なら、過少申告加算税はかかりません。 納める税金が多すぎた、または還付される税金が少なすぎた場合は「更正の請求」を行います。事実内容を認めてもらうために、請求の根拠になる控除証明書の再発行分や領収書などの書類も一緒に提出してください。 例えば、医療費控除の金額を過少申告していた場合、根拠となる病院からの請求書などを用意することで、税務署が過少申告だったのかを判断します。認められた場合、納めすぎた税金が還付されます。 延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた利息です。延滞した日数に応じて税率も変動し、長くなるほど税率も上がっていきます。延滞税の税率は原則として、納税期限から2カ月以内は年7.3%、2カ月を超えると年14.6%です。 ただし、特例措置により実際に適用される税率はこれより低くなっています。例えば、令和8年(2026年)の場合、納税期限から2カ月以内は年2.8%、2カ月を超えると年9.1%です。特例税率は毎年変動するため、国税庁のウェブサイトで最新の税率を確認してください。 納税期限を過ぎていることがわかったら速やかに納めることが大切です。 無申告加算税とは、確定申告の申請期間後に申告した場合に発生する税金です。2024年(令和6年)1月以降の改正によって、以下の税率へ引き上げられました。 ただし、税務署から指摘される前に自主的な期限後申告を行うと、税率は5%まで軽減されます 近年の改正により、「前年・前々年も無申告」であった場合(3年連続の無申告)は、上記の税率にさらに10%が加算される仕組みが導入されています。常習的とみなされると、最大で納税額の40%(重加算税を除く)近い負担になるリスクがありますので、注意が必要です。 なお、以下の事例に該当している場合、無申告加算税は発生しません。 重加算税とは、無申告加算税・過少申告加算税に対して追加で発生する税金です。故意に所得や控除額の隠ぺいを図ろうとした場合、税務署からの指摘を受けて重加算税が課されます。具体的には、本来の税額に以下の条件で税率がかけられます。 また、隠ぺいを図ろうとしていなかったとしても、わざと申告していなかったのであれば重加算税の対象です。 過少申告加算税とは、確定申告の税額を過少申告していた場合にかかる税金です。すぐに間違いに気付いて修正申告を行っていれば過少申告税が課されることはありません。しかし、税務署の調査によって申告額が誤っているなど指摘された場合は課税対象となります。 なお、過少申告加算税は本来の税額との差額に対して、10%が課されます。ただし、差額のうち「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分には15%が適用されます。 法人が対象になりますが、2期連続で確定申告を期限内に申告していない場合、青色申告の承認を取り消されてしまいます。 青色申告の承認が取り消されることで、最大65万円の青色申告特別控除や3年間の赤字繰越が適用できなくなります。青色申告の承認を再度得るためには、取消通知を受けた日以降1年間は再申請ができないことから、期限内に申告するようにしてください。 ここでは手元に控えがない場合の確認方法を解説します。 e-Taxを活用すれば、過去分の申告書などをPDF形式で取得可能です。確定申告を紙で提出していた場合もe-Taxから取得できます。 ただし、取得できるデータは2020年以降直近3年分のみが対象となります。 閲覧申請は、納税者本人または代理人が税務署の窓口で直接申告書を閲覧するための申請手続きです。税務署に設置、または国税庁のホームページからダウンロードして取得できる「申告書等閲覧申請書」を記入して窓口に提出します。 この時、本人確認も行われるので、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証なども持参してください。なお、申告書の内容を写真に収めたり、手で書き写したりすることは可能ですが、コピーで持ち帰ることはできません。 過去の確定申告書で写しが欲しい場合は、開示請求を行います。開示請求は税務署の窓口または郵送で行えます。具体的な手続きは、次のとおりです。 ただし、開示請求を窓口で行った場合でも、その場で写しを受け取れません。確定申告書の写しは後日税務署まで取りに行くか、郵送してもらいます。郵送してもらうには住民票と返信用切手の提出が必要なので、郵送を希望する場合は事前に用意しましょう。 過去分をさかのぼって確定申告を行う場合、申告方法や必要書類などは通常の確定申告と同じものを提出します。期限後申告だからといって提出書類や記載しなければいけない項目は増えません。 また、申告方法に関しても税務署の窓口に直接提出する方法か郵送、e-Taxの3種類から選べます。自分が申告しやすい方法を選んで、確定申告を行ってください。 申告期限が過ぎていた場合や過去に申告忘れが発覚した場合は、できるだけ早めの申告・修正が大切です。自主的な申告か指摘後の申告かで税率は変わります。 特に納税額が300万円を超える無申告には無申告加算税率が最大30%かかるため、早めに申告・修正を行いましょう。 無申告の状態が続いていて、自分ひとりではどうすればいいかわからない場合は税理士に相談するのがおすすめです。税務調査が行われる期間は過去5年間ですが、不正行為が続いている場合は7年間まで延長されるケースもあります。 ペナルティが増えることで事業へ影響をおよぼす可能性が高いため、すぐ申告・修正ができるように税理士に相談してみてください。なお、税理士に相談すれば申告・修正のサポートに加え、税務調査への対応から資金繰りに関する部分までアドバイスをもらうことが可能です。 確定申告はさかのぼって申告・修正できますが、ペナルティも発生します。特に2024年以降は無申告へのペナルティが強化されており、放置するリスクが大きくなっています。少しでも影響を抑えるためには、税務署から指摘される前に、速やかな申告・修正が大切です。 自分ひとりで対応するのが難しい場合や不安なことがある場合は、税理士に相談してみましょう。 創業手帳では無料で「確定申告ガイド」をお配りしています。ぜひご活用ください。 (編集:創業手帳編集部)

 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
確定申告は何年前までさかのぼって申告できる?原則5年・例外7年

確定申告はさかのぼって申告可能ですが、原則として過去5年分です。通常の確定申告期限を過ぎても「期限後申告」として、5年前までさかのぼって申告できます。6年以上前の確定申告は可能?
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」さかのぼって確定申告をしたほうが良いケース

過去分を確定申告したほうが良いケースは、以下のとおりです。それぞれのケースについて詳しく解説していきます。確定申告をし忘れていた場合(期限後申告)
申告した所得税を払い過ぎた、または適用できる控除を申告していなかった場合(還付申告)
提出した確定申告の内容を修正したい場合(修正申告)
所得税を多く申告した場合や還付される税額を過少申告していた場合(更正の請求)
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」さかのぼって申告した場合のペナルティ

過去にさかのぼって申告した場合、以下のペナルティが課されます。2024年の改正により厳罰化しているので注意しましょう。延滞税
無申告加算税
重加算税
過少申告加算税
青色申告の承認取り消し
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」過去の確定申告の内容を確認するには?

一度提出した確定申告書は控えなども返ってこないため、過去の申告内容を見返したい場合は提出前のコピーやデータの保管が欠かせません。しかし、控えを作っておかなかったり、データが紛失したりする場合もあります。e-Tax(申請書等情報取得サービス)で手軽に確認ができる
「閲覧申請」で確定申告書類の原本を確認
「開示請求」で確定申告書類を再発行
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」確定申告をさかのぼって申告・修正する際のポイント

確定申告をさかのぼって申告・修正する場合、以下のポイントも押さえておくことが大切です。申告方法や必要書類は確定申告と同じ
できるだけ早めに申告・修正を行う
無申告の状態が長く続いている時は税理士に相談する
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」まとめ・税務署から指摘される前に速やかに確定申告を行おう