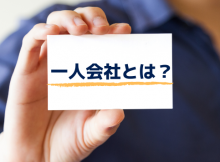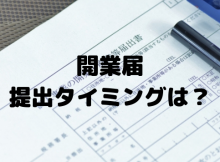開業届は収入0円でも提出すべき?メリットや提出方法も併せて解説!
収入なしや赤字でも開業届は出したほうがいい!

開業届は、新たに事業を開始してから1カ月以内に提出するように定められた書類です。
ただし、開業届は提出しなくても事業者に対して罰則はありません。そのためわざわざ提出しなくてもいいと考える人もいるかもしれません。
しかし、開業届を出すメリットはたくさんあります。収入なしの場合でも開業届を出すようにおすすめします。
事業計画を立てる時には、どのタイミングで開業届を提出するのか、青色申告にするかどうかも併せて考えておくようにしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
開業届を出すか出さないかで迷うその理由は?

個人事業主が提出する開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。
国税庁によると、新たに事業を開始した時や事業所を新設、増設、移転、廃止した時、または事業を廃止した時に行う手続きです。
しかし、実際に事業をはじめようとしていても開業届を出すかどうかで悩んでしまう人も少なくありません。どうして開業届で悩むのかその理由を説明します。
事業開始日に明確な定義はない
開業届が必要な事業は、事業所得と不動産所得、山林所得のうちいずれかの所得が生じる事業をいいます。
事業は一般的に対価を得る取引きで反復して行うものを指す言葉です。例えば、不要な生活用品をフリマで売った時などの一時的な取引きは該当しません。
では商品販売事業をスタートしたとして、事業を開始したのは商品を仕入れた時か、それとも売上げた時かそれ以前なのでしょうか。
開業届は、事業の開始日から1カ月以内に提出するように定められているものの、事業開始日について明確には定義していません。
実際に事業をはじめた日を事業日として扱うため、取引きや売上げが発生していない場合や収入なし、実績がない場合でも事業開始日にできます。
事業日は自由に設定できる一方で、開業してから2カ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければ初年度の青色申告はできません。
開業届と青色申告承認申請書をまとめて提出することもできるので書類を準備おいてください。
開業届を提出しなくても罰則はない

開業届は事業開始から1カ月以内に提出するように定められ、提出すると個人事業主として登録されます。
前述しましたが、開業届を提出しなかったとしても罰則はありません。税務署から開業届を提出するように催促されることもなく、確定申告も白色申告で受け付けられます。
そのため、開業届をわざわざ出さなくても良いと考えるかもしれません。
しかし、開業届を提出して得られるメリットも多いので、収入なしでも事業をはじめたら開業届を提出するようにおすすめします。
開業届を収入なしでも提出したほうがいい理由

開業届は収入なしだとしても提出するようにおすすめします。どうして提出したほうがいいのか、開業届を提出するメリットを以下でまとめました。
青色申告なら赤字の繰り越しや特別控除などが受けられる
開業届を提出することによって、確定申告で青色申告を選択できるようになります。
青色申告にすると、最大65万円の控除が受けられるほか、様々な税制優遇が知用可能です。
具体的には、家事按分で経費計上しやすくなり、青色申告専従者給与を計上できるといった税制優遇が受けられます。加えて、青色申告では、最大3年間の赤字繰越が可能です。
収入なしで赤字だけある場合にも青色申告であれば、その赤字を翌年の利益から差し引けます。
青色申告を選択しない場合には、自動的に白色申告となりますが、青色申告の控除は受けられません。
青色申告を選択するには、開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出してください。
事業名義の口座を開設できる
開業届の提出時には屋号を登録でき、個人名義の銀行口座とは別に屋号の銀行口座を開設できるようになります。個人の口座をそのまま事業に使うことも可能です。
しかし、個人事業主は、事業の支出とプライベートの支出が混同しやすく、会計処理に手間取ることがあります。
個人事業主の会計処理をより簡便にしてミスを防ぐには、事業名義の口座を作っておくことをおすすめします。
事業名義の口座であれば、事業のための入金と出金であることが明確でお金の流れがわかりやすくなるでしょう。
事業用のクレジットカードや口座を用意して支払いをまとめておけば会計の手間も少なくなります。
金融機関から融資が受けやすくなる
個人事業主として開業届を提出すると、より社会的に信用されやすくなり金融機関からの融資が受ける時に有利になる可能性があります。
融資を受ける際には、事業関連の書類以外に開業届の控えの提出が求められることもあります。
開業届は、事業を行っていることを客観的に証明できる書類として活用されています。
開業届の控えは、開業届を提出した窓口で受け取り可能です。郵送の時には、返信用封筒を同封しておくと返送してもらえます。
控えは事業を行っていることを示す書類になるので、紛失することがないようにしてください。e-Taxで開業届を提出する場合には、受信通知が控えの代わりとなります。
個人事業主を対象とする助成金・補助金も申請できる
開業届を提出すると、個人事業主を対象にした助成金や補助金へ給付申請ができます。
個人事業主を含む小規模事業者向けの助成金は幅広く、属性や条件に合わせて選択可能です。
例えば、小規模事業者持続化補助金やものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金などの制度を利用できます。
小規模事業者持続化補助金は、制度変更に対応するため販路開拓等の経費の一部を補助するものになります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は制度変更に対応するための設備投資をサポートするものです。
開業したてで融資を受けにくかったり、資金難で準備が進まない時にも助成金や補助金のサポートがあれば心強いでしょう。
補助金や助成金を申請する可能性があるのであれば、事前に開業届を提出しておくようにしてください。
小規模企業共済に加入できる
開業届の提出は、事業だけでなく個人事業主本人のためにも役立ちます。小規模企業共済は、個人事業主が自分で積み立てできる退職金制度です。
小規模企業経営者や個人事業主は、自分で準備しなければ退職金を受け取ることができません。そこで積立金を自由に設定できる小規模企業共済が利用されるようになりました。
小規模企業共済の共済金は、一括と分割のどちらでも受け取れます。さらに掛金は所得から控除できるので高い節税効果もあります。
将来に備えとして小規模企業共済制度も検討してみてください。
開業届を提出することによる影響は?

開業届を提出することによるメリットは多数あります。しかし、開業届を提出する影響はそれだけではありません。
ここからは、開業届を提出した時に注意してほしいポイントについてまとめました。
失業給付を受けられなくなる
失業給付は、会社で雇用保険に加入していた人が失業した場合に受給できます。失業給付は生活や雇用の安定を目的とした給付であり、開業届を出してしまえば受給できません。
開業届を提出したことによって、事業をはじめた、つまり開業したことになるため、失業とはいえず失業給付は受けられなくなります。
もしも、失業給付を給付中に開業届を出すか悩んだ時には提出のタイミングを見直してください。
早期に再就職した時には再就職手当の支給が受けられることがあります。再就職手当の受給資格も調べておくようにしてください。
健康保険の扶養から外れる可能性もある
もしも、配偶者の扶養に入っている場合には、開業届を提出する前に確認しておいたほうが良いでしょう。開業届を提出することで健康保険の扶養から外れる可能性があります。
健康保険組合によって、扶養対象者の範囲は違います。
開業している場合には扶養に入れないケースもあれば、収入が一定額を超えなければ扶養に入れるケースもあるのでまずは問い合わせてみてください。
扶養から外れると自分で保険料を納付することになります。
一定以上利益が出ていて扶養を外れる場合であれば問題ありませんが、収入なしの状態で扶養を外れればただ負担だけが増えてしまいます。
扶養となる範囲を確認してから開業届を出すかどうか検討するようにしてください。
確定申告が必要かどうかは個別に判断する
開業届を提出していてもしていなくても、一定額以上の所得があれば確定申告は必要です。開業届を出していない場合でも一定以上の所得が生じたら確定申告をしてください。
ただし、売上げがない時や、赤字を出してしまった場合でも確定申告をしたほうが良いケースもあります。
これは、事業用の備品や機械などの必要経費が生じている場合です。
青色申告では、赤字を繰り越し可能なので、その翌年に利益が出た場合に赤字を差し引いて計算できます。
つまり、確定申告で赤字を計上しておくことで翌年度以降の所得税を減らすことができます。
ただし、青色申告は、ほかにも様々な税制優遇が受けられる一方で白色申告よりも帳簿記入が増える点にも注意が必要です。
青色申告では、複式簿記で帳簿をつける上、提出する書類も増えます。
専門的な知識が必要になるため、不安がある場合には専門家に依頼するか、青色申告に対応した会計ソフトを導入するようにしてください。
開業届の提出方法

開業届を提出しようとしても、そもそもどうやって提出すればいいのかわからない人も多いはずです。ここでは開業届を提出する方法ついてまとめました。
複数の方法があるので、自分に合った提出方法を選択してください。
開業届を提出する方法は3つから選べる
開業届の提出方法は3つあります。ひとつは税務署の窓口で提出する方法、さらに郵送での提出とe-Taxです。
記入方法や内容に不安があって直接税務署の職員に問い合わせたい場合には窓口提出がおすすめです。郵送やe-Taxは、忙しくて税務署に出向けない場合に適しています。
郵送提出では郵送費用がかかりますが、e-Taxであれば自宅からのオンライン提出なので費用もかかりません。
e-Taxで提出するためには、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを用意してください。
開業届の提出に必要なもの
開業届を提出する時に必要なものは提出方法によって違いますが、開業届はどの提出方法でも記入します。
税務署の窓口で開業届の用紙を受け取ってその場で記入することも可能ですが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
マイナンバーカードは、書面でマイナンバーカードを記載した上で窓口でも確認が求められるので忘れずに持参して提示してください。郵送の場合には写しを添付します。
e-Taxでの提出では、カードリーダーやスマートフォンでの読み込みが必要です。
開業届の記入方法
開業届を提出する時には、届出の区分にある開業に〇をして必要事項を記載します。マイナンバーや職業といった必要事項を記載してください。
屋号とフリガナを記入する欄もありますが、決まっていない場合には空欄で問題ありません。事業の概要には、事業の内容についてわかりやすく記載します。
開業届の形式は見慣れていないに人には難しく感じられるかもしれません。開業届は会計ソフトの機能を使って作成する方法もあります。
会計ソフトであれば、質問された項目を埋めるだけで開業届を作成可能です。青色申告承認申請書も同時に作成できる点もメリットです。
e-Taxで開業届を提出する時には、まずマイナンバーカードを使って電子証明書を取得してください。利用者識別番号を取得も必要です。
e-Taxソフトのインストールは、国税庁のホームページから実施します。税目プログラムから「所得税」を選択しインストールして利用してください。
申請・申告等一覧に「個人事業の開業・廃業等届出書」があるので必要事項を入力してから電子署名を付与して送信します。
送信してからメッセージボックスに受信通知が届くので、確認してください。
開業届と一緒に提出したほうがいい書類
開業する時の事業内容や確定申告の種類によって、開業届以外にも必要な書類があります。具体的には以下の書類です。
-
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
青色申告承認申請書は、青色申告を選択する時に必要な書類で原則開業から2カ月以内に提出します。
また、配偶者や子どもなど家族を雇って給与を支払って経費に計上する場合には、青色事業専従者給与に関する届出書も提出します。
青色事業専従者給与に関する届出書は、原則必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出してください。
もしも開業する事業で社員やアルバイトを雇うのであれば給与支払事務所等の開設届出も提出しなければいけません。
これは従業員を雇う事務所を開設した日から1カ月以内ですが、開業届の「給与等の支払の状況」欄を記載していれば提出不要です。
従業員の給与から源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに税務署に納付します。
しかし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、半年分まとめて納税できる特例を適用できます。
適格請求書発行事業者の登録申請書は、インボイス制度に対応するために必要な書類です。登録希望日の15日前までに提出してください。
自分にとってどの書類が必要になるのか、いつまでに提出しなければならないのか把握して提出のスケジュールを決めておくようにしてください。
まとめ・事業を開始したら収入なしでも開業届を提出しよう
開業届は、事業開始から1カ月以内に提出する義務があるものの提出しなくても罰則はありません。開始した後で開業届はさかのぼって提出することもできます。
すでに事業所得を得ているが開業届を出していない場合には、早めに提出するようおすすめします。
収入なしの場合には問題ありませんが、事業所得の確定申告が必要なのに無申告の状態だと無申告加算税が課される可能性もあるからです。
開業届を提出するタイミングによって税制面などに影響することもあります。どのタイミングが良いか個々の事情で判断してください。
創業手帳では、起業、開業の準備をどのように進めていいのかわからない方のために『創業カレンダー』をご用意致しました。やることが書かれたTODOカレンダーを無料でお届けしますので、そちらに起業予定日を記入すれば、前後1年間のやることを見える化!ぜひあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)