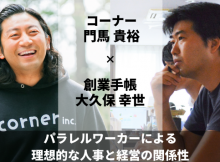JX通信社 米重克洋|日本の報道を「自動化」で変える!
新聞やテレビが情報を独占していた時代は終わった!「記者ゼロ」の通信社が22億円の資金調達をできた理由

新聞やテレビが情報を独占していた時代とは異なり、今や時代は「1億総カメラマン」。
事件が起これば記者よりも一般人のSNSのほうが速報となり得る、そんな時代です。中学生のときに航空業界に興味を持ち、高校を卒業したら起業すると決めていたというJX通信社代表取締役の米重氏に、事業内容や起業の経緯、心構えなどについてお聞きしました。

株式会社JX通信社 代表取締役社長、CEO、報道研究者 @kyoneshige
1988年8月、山口県生まれ。2007年、私立聖光学院高等学校(横浜市)卒業後、学習院大学経済学部に進学。2008年1月に当社設立。中学・高校時代に航空業界専門のニュースサイトを運営した経験から「ビジネスとジャーナリズムの両立」という課題に着目。
出演等:AI防災協議会理事、Yahoo!ニュース個人オーサー、共同通信コラム『デジタルジャーナリズム研究』連載、「『2021 Forbes JAPAN 100』選出」、「『MIT Technology Review Innovators Under 35 2021』選出」、WIRED Audi INNOVATION AWARD 2018受賞、Business Insider Game Changer 2019グランプリ受賞。

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ニュース速報は記者よりもSNSが重要ソース

大久保:どんな事業内容なのでしょうか。
米重:テクノロジーやデータインテリジェンスを使用して、報道を自動化する試みをしています。具体的にはニュース速報や世論調査、選挙情勢の調査などを手掛けています。
新聞やテレビなどの今までの報道機関がアナログな人海戦術に頼ってきた部分を、インターネット上に集まるビッグデータをAIを活用しながら分析し、どこよりも速いニュース速報を実現させています。
大久保:今までのメディアってやはり記者の力に頼っていた部分が大きいですよね。知識も必要ですし、人件費もそれなりにかかりますし。
米重:そうですね。報道機関が従来のやり方で今後もやっていくのは難しいのかなという考えがあり、問題解決のためにテクノロジーが使えないかな、自動化できるところはないかな、という思いがありました。
大久保:わたしはもともとデータを扱うeコマース出身なので、記事を書いてみたら工程が複雑で、こんなに面倒なのかと驚いた記憶があります。情報をデータ化することで、記事の品質の向上にもつながりますよね。
米重:そうですね。ニュースって、正しい事実が書かれているというだけでなく、速さも品質のうちなんです。情報処理やデータの速さに関して言えば、間違いなく人間よりも機械のほうが優れていますから。そのメリットを生かしていくことによって、コストは下げながら品質は上げていくことが可能なんです。
大久保:人間が書くとどうしても多少のバイアスがかかるという問題もありますよね。無意識に自分の主義主張に沿う事実ばかり取り上げてしまうということもありそうです。
米重:報道には大きく分けてふたつあって、ひとつがどこで何が起きたかというストレートニュース、もうひとつが事件の裏側などを調べて報道する調査報道と言われているんですが、少なくとも前者のストレートニュースに関しては、バイアスがかかりにくい内容であり、自動化も容易です。
大久保:新聞社の記者がいくら張り込みしても、明らかに街を歩いている人のスマートフォンの数にはかなわないですよね。
大久保:ライブドアにいた頃、災害のときにネットの報道が報道機関よりも早かったことに衝撃を受けた記憶があります。ネットの力ってすごいなと。それがどんどんシステマティックになっていっているということですよね。
米重:これだけスマートフォンが流通すると、情報の発信自体がどんどん容易になっていくんですよね。個人がニュースバリューを持つことができるようになり、世の中の仕組み自体が変わってきているという状況は、報道機関としても対応していくべき課題です。「報道機関よりも消費者のほうが早くて正しい情報を知っている」という認識になってしまうことは、報道産業側としても避けたい事態ですよね。
大久保:報道機関としても、現場の疲弊感はありそうですよね。バブル時代なんかは、テレビも予算をかけて攻めたことをやっていましたけど、今はあまり予算も使えないでしょうし。
米重:マスメディアだけが情報を独占するという時代は終わりました。ひとりひとりが使える時間は限られているので、YouTubeやTikTokなどはテレビの滞在時間を奪う競合ということになります。広告費も奪い合っているんですよね。ということは、今までよりも少ないコストで、どのようにお客さんの心をつかむのかを考えなければならないということです。
中学生の頃から「いつか起業したい」と思っていた

大久保:子どもの頃から「会社を作りたい」と思っていたとお聞きしましたが、本当ですか。
米重:そうですね。たまたま中学生のときに航空業界に目覚めたんです。飛行の仕組みではなく、航空行政の方ですね。当時はLCCなどはなく、運賃も高くて最低でも3万円ぐらいはしました。そのうち8000円ぐらいは税金ですよね。各県に空港が作られて、空港ができると路線が作られて、でも採算が合わないと公的資金が使われる。そういうマッチポンプ的な使われ方をしていて国民が割りを食うんだな、と知りました。
「構造的な問題があるなら、問題点を解決できないかな」と感じ、いつか航空会社を作りたいと思ったんです。ものすごくお金がかかる話なので、もちろんすぐには難しいですけど、今でもその夢を諦めてはいません。ヴァージン・アトランティック航空を作ったリチャード・ブランソンもレコード業界から航空業界に参入しましたし。
高校生になって、高校を卒業したら会社を作ろうと思い、大学1年のときに報道機関向けのサービスを提供する会社を作ったんです。
大久保:それはまた早いですね。なぜ報道の分野で起業したのでしょうか。
米重:自分が課題意識を持ち続けていられるのはどの分野かなと考えた結果ですね。もともと報道ニュースオタクだったんです。その当時、オンラインのニュースメディアがどんどんできては数年でつぶれていきました。あのタイプのニュースメディアはもうからないと感じ、成り立つようにするにはどうすればいいのか?と考えた結果、コンテンツ制作をすればいいのかもとひらめいたんです。『R25』などのフリーペーパーが話題になり、クロスメディアでのコンテンツ作りが脚光を浴び始めた頃です。
大久保:会社が立ち上がって、ずっとそのまま突っ走るケースって実はあまりなくて、皆さん大なり小なり事業内容や方向を変えたりしている印象なんですが、そのあたりはいかがでしたか?
米重:そうですね。最初から順風満帆というわけではなく、2回ぐらいはピボットしていますね。
2011年頃にVingow(ビンゴー)というニュースアプリをローンチしたんです。ニュースをタグでフォローすれば、自動で自分の興味があるニュースが表示されるというものだったんですが、自分でタグづけをしなければニュースが表示されないという欠点があり、後発のグノシーやスマートニュースに追い抜かされてしまいました。ニュースオタク相手の、自分勝手なプロダクトだったなと反省しました。
ビンゴーの反省をいかし、「NewsDigest(ニュースダイジェスト)」というニュースアプリをリリースして、今の形になったのは2016年頃ですね。速報性に優れており、災害情報などをいち早く入手できる点が特徴です。
その後、「NewsDigestの速報性を可能にする技術を使って、BtoBとして災害や事故、事件の情報をいち早く感知するシステムを作れないか」というご相談を共同通信さんからいただき、「FASTALERT(ファストアラート)」が誕生しました。このリリースをきっかけに共同通信さんと資本業務提携を結び、その後NHKさんをはじめ、民放キー局全局にFASTALERTを採用していただきました。
また、選挙における情勢調査も行っており、好評いただいています。
大久保:まだ33歳なのに、いろいろと経験されていることに驚きました。まさに共同通信さんとのオープンイノベーションですね。どのような技術が使われているのでしょうか。
米重:データマイニングという技術ですね。ビッグデータから有用な情報だけを取り出す技術で、我々のほぼ全てのサービスのコアな部分です。報道価値があるものをいち早く見つけるということが非常に重要になります。
「何時何分にどこそこで何がありました!」というような情報を一般の方が流すことはまずありません。目の前で事件や事故が起こった場合、「やばい」とか「びっくりした」などのシンプルな言葉に、ものすごいインパクトのある写真が添付されているというケースがほとんどです。
そういったケースを機械に学習させて見つけ出していきます。
大久保:精度はどのようなものなんですか。
米重:データの蓄積量が大切になってきますので、最初の頃は苦労しました。ただ、今は基本的にはもう関係ない情報というのはほぼ入ってこない精度になりましたね。昔の新聞社では、24時間担当の人が待機していて、警察と消防に電話したり、無線傍受したりしていたんですよね。今は傍受することはできないですけど、昔はアナログ無線だったので。それをビッグデータで機械化できたので、かなりコストカットできているんじゃないでしょうか。
企業や個人ひとりひとりに向けてのニュースを届けたい

大久保:現在は、何人ぐらいの組織なんですか。
米重:約70人ですね。エンジニアは半分弱で、記者はいません。あと半分は営業やマーケティングですね。フレックスやリモート制度も使えますし、働き方としては自由度が高いと思います。
大久保:通信社なのに記者がいないとは、革新的ですね。資金調達で22億円を調達したとお聞きしましたが、調達したお金は何に使っているのでしょうか。
米重:このような事業内容なので、何かを仕入れてというわけではなく、エンジニアの開発にかかる費用だったり、広告宣伝費、人件費などですね。
今後、事業をスケールさせるためにいかに大きく先行投資できるかということに賛同いただいた投資家や事業会社さんに資金を出していただいています。
大久保:なるほど。今後の展望をお聞かせください。
米重:今後もデータマイニングのテクノロジーを生かして情報収集し、顧客の課題を解決していくのが事業体としては一番重要だと考えています。報道機関というのは、マスに対して発信する組織というイメージでしたが、今後はそうではなくなっていくと考えています。各企業や個人ひとりひとりにとって、有用な情報をパーソナライズしてどう届けるかが課題となっていくのではと思います。
データインテリジェンスを使ってビッグデータを有効活用する報道が、21世紀にあるべき姿だと思っています。
公開されている情報をどう分析するか、報道倫理に基づいてどう掘り下げるのかも重要ですね。フェイクニュースを除外したり、情報の価値判断をしてどう伝えるのかというところで、選ばれる理由が出てくるのだと思います。
日本では、長い間新聞が情報プラットフォームの中核でした。もちろんニュースを見るときも新聞でしたし、買い物に行く時も昔は折り込みチラシを見るのが普通でしたよね。今まではそれでよかったけれど、今は情報コミュニケーションの形が変わったということです。朝晩玄関に届く紙よりも、30cm手を伸ばせば届くスマートフォンに読みたい情報が集まってくるならば、そちらの方を選ぶ人が増えているのです。
長年このような状況にあったので、新聞社の方々は「なぜ新聞が売れないんだろう」と考えたときに「コンテンツをよくしよう」とか「もっと読まれるテーマを探そう」という結論にたどりつきがちです。
大久保:そういう頭になってしまっているんですね。問題はそこではないのに。
米重:そうですね。もちろんそれはどんな組織でもあると思うのですが。やはりそこは第三者的な目で、客観的に作り直すプレーヤーが必要だと思っていて、まさにそれが我々がやりたいことだと考えています。
大久保:起業を考えていたり、起業したばかりの読者に向けて、これだけは気をつけてほしいというメッセージはありますか。
米重:まず、仮説通りに行くことは絶対にないということを肝に銘じていただきたいです。心を強く持つことが大事です。「仮説と違う」とあきらめるメンタルでやると大変なことになります。
大久保:会社やってると本当にいろいろありますね。常に何かしらの問題が出てきたり。
米重:そうですね。もう、そういうものだというのを前提にしてます。問題が出てきたことに対して、いちいち怒っているともたないですから。
また、いい予感は当たらないけど、悪い予感は当たるんです。「これを放置したら問題が起こるだろうな」と思ったら放置せず、原因を潰すことを心がけていますね。諦めずにやり続けることが何よりも大切です。
(取材協力:
JX通信社代表取締役 米重 克洋)
(編集: 創業手帳編集部)