外国人雇用に必要な手続きや流れとは?雇用の注意点も解説
外国人雇用には職種に合った在留資格の申請が必要!

外国人を雇用する企業も増加している現在、新たに雇用を検討する企業もあるでしょう。
しかし、外国人雇用を行うためには、職種に合った在留資格を申請しなければいけないので、日本人を雇用するよりも手間がかかります。
そこで今回は、外国人雇用には就労に必要な可能な「在留資格」とは何か、外国人求人の募集方法はどうするのか、外国人雇用に必要な手続きにはどのようなものがあるか、などを解説していきます。
外国人の雇用を考えている企業の担当者は、ぜひ活用してください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
外国人雇用の就労に必要な「在留資格」とは?

外国人雇用をするためには、在留資格が必要になります。まずは、外国人雇用を行うなら把握しておかなければいけない在留資格について解説していきます。
在留資格の種類は以下のとおりです。
| 在留資格 | 該当する職業 | 在留期間 |
| 外交 | 外国政府の大使や公使、総領事などとその家族 | 外交活動の期間中 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員などとその家族 | 5年・3年・1年・3カ月・30日または15日 |
| 教授 | 大学の教授など | 5年・3年・1年または3カ月 |
| 芸術 | 作曲家や画家など | 5年・3年・1年または3カ月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | 5年・3年・1年または3カ月 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者やカメラマン | 5年・3年・1年または3カ月 |
この他にも、医療や研究、介護などの就労資格があります。
外国人を雇用する求人のポイントと募集方法

外国人雇用をする際、求人の出し方などが異なります。続いては、外国人雇用する求人のポイントと募集方法についての解説です。
求人の多言語化
外国人雇用をするのであれば、求人の多言語化が必要になります。
すでに来日し、日本国内の企業で働いている外国人をターゲットの募集をするならビジネスレベルの日本語を理解できるケースが多いので、日本語表記でも問題ありません。
しかし、海外在住の外国人をターゲットに求人を出す場合は、該当する外国人の母国語や英語で表記した求人票も用意すべきです。
求人サイト・自社サイトの活用
募集方法として多くの企業が採用しているのが、求人サイトや自社サイトです。
自社サイトであれば、コストを抑えた求人掲載が可能となります。変更点が出てきた場合も、柔軟に対応できることが自社サイトを活用する大きなメリットです。
しかし、自社の存在をすでに知っている外国人にしかアプローチできません。
より多くの外国人にアプローチしたいなら、求人サイトの活用がおすすめです。外国人採用に特化した求人サイトもあります。
公的機関の活用
ハローワークなどの公的機関を活用するケースもあります。
ハローワークは、無料で求人を掲載でき、申し込みをすれば外国人雇用管理アドバイザーへの相談も可能です。
外国人向けの新規求人数も増加傾向にあるので、ハローワークに相談することで適切なサポートを受けられる可能性も大いにあります。
専門学校・大学の求人情報の活用
外国人雇用を考えているのであれば、専門学校や大学の求人情報を活用することも1つの方法です。
アルバイトや新卒採用で日本国内の企業に勤めたいと考えている外国人を集めやすいことが特徴です。
日本語学校や留学生が多い大学では、外国人のキャリア支援や就職ガイダンスに力を入れているケースもあるので、協力を得られれば求人情報を拡散しやすくなります。
外国人に特化した人材派遣の活用
人材派遣会社の中には、外国人に特化しているところもあります。
人材派遣会社では、企業が求めている人物像を細かく設定できるので、高精度なマッチングが可能となります。
ビザの申請やチェック、住まいの紹介、日本語教育などのサポートを行っている人材は会社もあるので、前向きに利用を検討してみてください。
外国人からの紹介
知り合いに外国人がいる場合は、紹介してもらうという方法もあります。
外国人同士のネットワークは非常に発達しているので、すでに社内で働いている外国人に紹介してもらうことなどができます。
現在働いている外国人と同じ国の人を雇用したいと考えているのであれば、特におすすめの方法です。
外国人を雇用する場合に必要な手続き方法・流れ
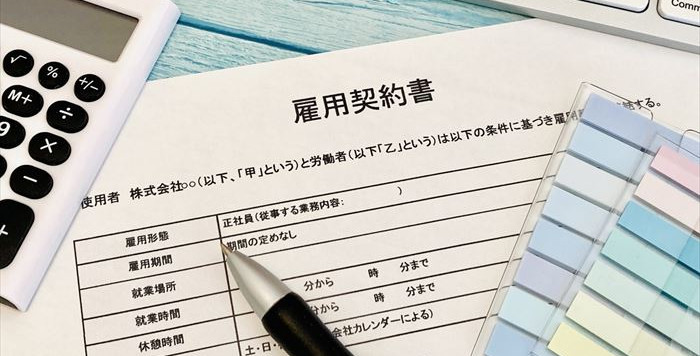
外国人を雇用する場合、日本人とは異なる手続きが必要です。次は、必要となる手続きの方法や流れについて解説していきます。
1.就労ビザを取得できるかの見込み調査
外国人を雇用する場合、まずは就労ビザを取得できるか確認するための見込み調査を行います。
見込み調査は、面接や内定を出すために実施するものです。なぜなら、内定を出しても就労ビザを取得できなければ、日本国内で仕事ができないからです。
ビザを取得できない外国人に内定を出したとしても、実際には勤務できず無駄になってしまいます。
無駄な労力を削減するためにも、就労ビザを取得できるか確認するための見込み調査は必要不可欠です。
2.採用後の雇用契約書の作成
面接して内定を出したら、雇用契約書を作成します。
雇用契約書は、就労ビザを申請する時に必要となる書類の1つなので、就労ビザを申請する前に作成する必要があります。
基本的には日本人を雇用する際の契約書と同じ内容で問題ありません。
ただし、外国人自身が理解できる言語で作成することや日本の法律に則った雇用契約書であること、などは注意しなければいけないポイントです。
3.就労ビザの申請
雇用契約書の作成が完了したら、就労ビザの申請を行います。外国人が日本で働くための必要不可欠なものなので、申請を怠ってはいけません。
就労ビザの申請方法は以下のとおりです。
留学生を正社員として新卒採用したい場合
留学生を正社員として新卒採用したい場合は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければいけません。
在留資格を変更する時は、在留資格変更許可申請が必要です。
新卒の外国人だと、卒業する前年の12月に申請の受付が始まります。この時期は申請が重なって混雑するので、結果がわかるまで3カ月程度かかってしまう場合もあります。
4月1日入社を目指すなら、1月下旬頃までに申請を完了するようにしてください。
日本滞在の外国人を正社員として雇用したい場合
日本に滞在している外国人を正社員として雇用したい場合は、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行います。
在留期間更新許可申請は、転職前後の職種が同じ場合に行われるものです。
在留資格変更許可申請は、採用予定の外国人が従事する業務に該当する在留資格を得るための手続きです。
いずれも、必ず申請が通るという保証はありません。
海外在住の外国人を海外で採用して日本で雇用したい場合
海外在住の外国人を現地採用し、日本で雇用したいといったケースもあります。
そのような場合は、内定後すぐに企業が入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請し、発行されたら海外にいる求職者に送付します。
書類を受け取った求職者が現地の日本大使館へ就労ビザ申請し、許可が下りれば就労ビザが取得できるという流れです。
在留資格認定証明書は、発行されてから3カ月以内に日本へ入国しないと無効になってしまう点に注意が必要してください。
外国人をアルバイトとして雇用したい場合
外国人をアルバイトとして雇用したい場合は、資格外活動許可の申請が必要です。ただし、週28時間という労働時間の制限が付きます。
「永住者」や「日本の配偶者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合は、就労に制限がないので資格外活動許可は必要ありません。
一方、「留学」や「家族滞在」、「特定活動」などは就労先に関係なく許可の申請が可能です。
「文化活動」の在留資格を有している場合は、就労先が内定を出した段階で個別に申請をしなければいけないので、混同しないように気をつけてください。
4.就労ビザの審査を通過したら雇用開始
就労ビザを取得するための審査を通過したら、雇用開始となります。就労ビザの審査期間は1~3カ月程度となっていますが、許可が下りないケースもあります。
許可が下りない理由には、外国人にとってオーバーワークとみなされる部分がある、会社の実態がない、現場労働である、などです。改善すれば再申請できる場合もあるので、入国管理局に不許可理由を聞いて修正や再申請を行ってください。
無事に許可が下りた場合は、受け入れ準備を整えて、雇用開始となります。
雇用後は、ハローワークへの届け出や更新時期の管理を忘れないように注意しなければいけません。
外国人雇用するメリット

外国人雇用をすることで企業側が得られるメリットはいくつもあります。ここでは、4つピックアップしてご紹介します。
労働力を確保できる
外国人雇用をすることで、労働力を確保できるのは企業にとって大きなメリットです。
超少子高齢化社会となっている現在、人手不足に悩む企業は少なくありません。そのため、日本国内にいる優秀な人材を雇用したいと考えるケースが多いです。
特に、新卒のエンジニアに関しては、海外から採用する企業が増加傾向にあります。
外国人はモチベーションが高い人も多いことから、積極採用を行うケースが増えていると考察できます。
優秀な人材を雇用できる
日本で働きたいと考えている外国人は、優秀な人が多いです。母国語以外の言語圏で働くとなるとある程度のレベルを習得しておかなければいけません。
日本語は世界的に見ても難易度が高い言語だと言われているので、それを仕事のための習得するやる気や実力があるということは、優秀な人材だと言えます。
企業にとって重要な役割を担う可能性も大いにあります。
海外からの顧客に対応できる
日本語以外に英語や中国語などを母語とする人材を幅広く雇用すると、海外からの顧客に対応できるようになります。
日本に足を運ぶ外国人旅行客は非常に多く、政府は2030年までの訪日外国人観光者数を6,000万人と想定しています。
インバウンド需要に応えるためにも、外国人雇用を行って海外からの顧客に対応できるようにすることは重要です。
企業のグローバル化が図れる
外国人を雇用することで、社内が活性化します。日本人だけでは思いつかないような発想が生まれる場合もあります。
仕事のやり方に関しても、外国人ならではの感性が加わって活性化しやすくなるといったメリットも期待できるでしょう。
価値観の異なる労働者が同じ仕事をすることで、企業のグローバル化や活性化を目指せる点も、大きなメリットです。
外国人雇用する時の注意点

外国人雇用によって得られるメリットはたくさんあります。しかし、注意点があることも知っておくことが大切です。最後に、どのような注意点があるのかご紹介していきます。
偽造の在留資格を保有していないか確認
外国人を雇用する場合、仕事に関する在留資格を保有していることが必要不可欠です。
日本で働くために偽造の在留資格を保有しているケースもあるので、本物かどうか確認しなければいけません。
認められていない業務をさせてしまうと、企業側も罰せられる可能性があります。
不法就労助長罪による摘発は毎年のようにあるので、採用する時はしっかりと在留資格を確認するようにしてください。
言葉や文化の違いによるトラブルに注意
出身国が異なれば、言葉や文化の違いがあります。どちらの方が良いとか悪いといったことはないので、ギャップがあることを理解しておくことがポイントになります。
例えば、海外ではネイルやアクセサリーをしたままでも飲食店で働けるケースもあるので、「食べ物に異物混入するリスクがある」などと明確な理由を伝え、理解してもらうために歩み寄るようにしてください。
雇用手続きや労務管理に注意
外国人を雇用する場合、手続きや労務管理が複雑になります。海外在住なのか、日本在住なのかによって採用フローが異なります。
海外在住だと、在留資格認定証明書の申請をしなければいけないためです。
雇用する外国人の数が10人以上になる場合は、雇用労務責任者の選任も厚生労働省の指針で決まっているので守らなければなりません。
雇用労務責任者は、外国人人材の募集や採用の適正化、安全衛生の確保、適正な労働環境の確保などを担います。
同一労働同一賃金制度・最低賃金を厳守
同一労働同一賃金制度・最低賃金を厳守することも重要です。日本人と同じように守らないと違法とみなされ、不足分を支払わなければいけなくなります。
また、給与水準が日本人よりも低いと、在留資格の取得ができない場合もあるため、同一労働同一賃金制度・最低賃金は遵守してください。
入管では企業内で同じ業務を行う日本人の給与水準もチェックするので、隠し通すことは基本的にできません。
他の従業員の理解を得ることも大切
外国人を雇用するなら、他の従業員の理解を得ることも大切な要素になります。
理解を得られないままだと、コミュニケーションがうまくとれず、仕事に支障をきたしてしまう可能性もあります。
お互いのことを理解できず、対立してしまう可能性もないとは言い切れません。
お互いの理解を深めるために食事会を開催したり、レクリエーションを行ったりするのもおすすめです。
そして日本のマナーや職場のルールについて外国人側の理解が深まれば、お互いに歩み寄りやすくなります。
まとめ・外国人雇用をするなら募集や手続きから採用後のコストも考慮しよう
人手不足が顕著になっている現在、外国人を雇用する企業も増加傾向にあります。外国人雇用を前向きに考える企業も増えているので、今後はさらに多くなると考えられます。
しかし外国人雇用をするためには、在留資格や採用の手続きなどについてきちんと把握しておかなければなりません。
創業手帳(冊子版)では、その他採用に関する情報も多数掲載しています。最近スタートアップ界隈ではアウトソーシングで業務を遂行していくスタイルが増えています。アウトソーシングを活用するメリットや、業務の切り分け方など参考にしていただき、是非事業を成功へと導いていただけたらと思っています。創業手帳は無料でお取り寄せ可能です。
(編集:創業手帳編集部)




































