起業したら会社成長のために企業理念を定めよう
起業家のための企業理念入門①:なぜ企業理念を定める必要があるのか(前編)

ビジネスは数字で評価されるものだが、数字だけを追うだけでは企業の成長は長続きしない。「自分がいまやっていることが何につながっているのか?」「その数字を達成することにどんな意味があるのか?」、すなわち、働く意義が分からなければ、人はモチベーションが上がらないものだ。だからこそ、企業理念を定め、社員が自社で働く意味を定義する必要がある。
これから連載で、創業ベンチャーが大きく成長するために重要になる「企業理念(経営理念)」について取り上げていく。まず第1回・第2回の2回に分けて、企業理念を定めることの必要性について述べる。次に第3回では、企業理念の具体的な定め方について説明する。最後の第4回では、一度定めた企業理念を社内外に継続的に浸透させていくにはどうすればよいかを解説していく。
第1回の今回は、企業理念を定めることの必要性を取り上げよう。
会社の経営では「目に見えないもの」も大切
会社というのは決して目に見えるものだけではなく、目に見えないものによっても、その成否が大きな影響を受ける。
例えば、レストランを想像してみてほしい。
美味しい料理を提供してくれて、内装もお洒落だったら、あなたはそのレストランのリピーターになるだろうか?決して、それだけではリピーターにはならないはずだ。居心地の良さや、心温まるサービスを感じてこそ、はじめてリピーターになりたいと思うのではないだろうか?
逆に、どんなに料理が美味しかったとしても、接客で不愉快な思いをさせられたり、支払った料金に見合った満足感を得られなかったりしたら、二度とそのレストランへは行きたくないと思うはずだ。
レストランに限らずだが、サービスというのは、人が作り出すもだ。どんな業種であれ、気付き、気配り、丁寧さ、臨機応変な対応、そういったことができる社員がいなければ、お客様の心をつかむことはできず、会社が成長することもできない。
では、どうすれば、そのようなことができる社員が育つのだろうか?
社員の成長は「心構え」がキーワード
もう少し、レストランの話を続けよう。
そのレストランで働いているウェイターが、自分の仕事に対して「料理を運ぶこと」という認識しかなければ、厨房から出てきた料理を指定されたテーブルに運んで、以上終了となる。料理が崩れていたり、皿にゴミが入っていたりしても気がつかない(気がつこうともしない)し、お客様の食べるスピードを無視して不適切なタイミングで料理を出してしまったりするかもしれない。
これでは、お客様は二度とこのレストランには来てくれないだろう。
しかし、ウェイターが、自分の仕事を「お客様に楽しく食事をしてもらうこと」と、より高い次元で認識していれば、厨房から出てきた料理が崩れていたり、ゴミが入っていたりしたら、「こんな料理はお客様に出せるはずがない!」と、すぐに気がつくはずだ。
つまり、心構えひとつで、サービスのレベルは、天と地ほど変わってくる。
企業理念(経営理念)が社員の力を引き出す
前置きが長くなったが、そろそろ「企業理念(経営理念)」という言葉を登場させよう。
会社は営利法人なので、「お金儲けをするため」に存在していることは間違いない。しかし、お客様からお金をいただくことと引き換えに、何らかの「価値」をお客様へ提供しているはずだ
その「価値」を、経営者の魂を込めた言葉で表したものが「企業理念(経営理念)」である。
例えば、ラーメン屋さんであれば、「何でもいいから、とりあえずラーメンを出す。」といって開業をする人はいない。自慢のスープをひっさげて、「最高の一杯で、お客様から最高の笑顔を引き出すぞ!」という気持ちで起業をするはずだ。それがまさに企業理念である。
そんな経営者の熱い気持ちが込められた企業理念を社員と共有することができれば、社員もその会社で働くことの意味を理解し、「お客様から最高の笑顔を引き出すために、自分が与えられた役割において何をすべきか?」を真剣に考えて行動してくれるようになる。そして、その結果としてサービスの質も高まっていく。つまり、企業理念が社員の心構えを、より高い次元へ引き上げてくれるのである。
企業理念によって働く意味が分かると、モチベーションも高まるし、その職場で働くことが楽しくなるので、社員も定着してくれることは間違いない。
逆に、企業理念がない会社では、社員にとっての仕事は、「給料を稼ぐ」という意味しか持たない。社員と会社の関係は「労働力を提供し、賃金を支払う」という、ただそれだけの冷え切った関係になってしまう。社員も定着せず、常に人が出入りするせわしない会社になるだろう。その結果、サービスの質も上がらずに、会社は勢いに乗ることができず、ジリ貧状態になっていく。
まとめ
このように、企業理念は、起業家と社員が一体となってベンチャーを大きくしていくために、絶対に欠かせないものだ。
企業理念を作ることは決がして難しいことではない。起業家自身がなぜ起業をしようと思ったのかということを振返り、それを飾らずに、素直な気持ちで社員と共有できるような分かりやすい言葉に置き換えてみるとよいだろう。
そうすれば、その言葉に共感してくれる、やる気に満ち溢れた社員が集まり、経営者といっしょになって会社を引っ張っていってくれるはずだ。
(つづく)
(監修:あおいヒューマンリソースコンサルティング 代表 榊 裕葵)
(編集:創業手帳編集部)
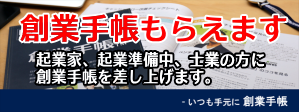
|
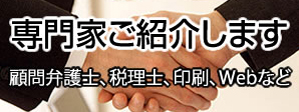
|






































