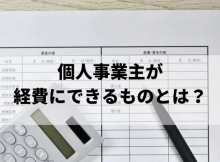個人事業主が支払う家族給与は経費になる?要件・手続き・注意点などを解説
家族に支払う給与は正しい手続きを踏むことで経費にできる!

個人事業主として事業を営む中で、家族に手伝ってもらう場面は少なくありません。
しかし、「家族に給与を支払っても経費として認められないのでは?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。
実は、家族への給与も一定の要件を満たし、正しい手続きを踏めば経費として計上することが可能です。
この記事では、家族給与を経費にするための要件や手続き、注意しておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
家族に支払う給与を経費にしたい人は、ぜひ参考にしてください。
家族への給与だけでなく、他の経費でも「どこまでが認められるのか」「どう活用すれば節税につながるのか」に迷うことは多いものです。
創業手帳の 「経費チェックリスト」 では、人件費・交際費・広告宣伝費など23の経費科目ごとに、経費削減のポイント と 節税につなげる工夫 を整理。
無料でダウンロードできますので、経費処理の見直しや税務対策にお役立てください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主の経費と所得税の基本
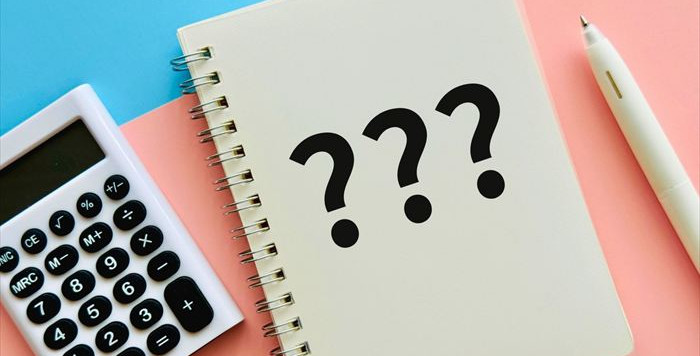
そもそも家族に支払う給与を経費として認めるかどうかは、所得税の考え方が大きく影響してきます。
所得税は個人が納めるべき税金です。しかし、事業所得に関しては家族がひとつになって事業を営み、得た所得として扱われます。
そのため、家族に支払う給与は事業の経費でもなければ、家族の課税所得にも当てはまらないのです。
この所得税の考え方は給与以外の場面にも当てはまります。
例えば配偶者が名義人となっている不動産で事業をスタートさせた場合、通常であれば配偶者に家賃を支払うことになりますが、家賃は事業の経費にならず、さらに配偶者の収入にも該当しません。
このように、所得税の考え方によって家族に支払う給与は原則経費の対象外となっています。
家族への給与を経費にするには?

家族に支払う給与は原則経費の対象外であることを紹介しましたが、要件を満たすことで経費にすることは可能です。
具体的にどのような要件だと給与を経費にできるのか、解説します。
生計を一にしない家族への給与は経費にできる
上記で原則経費の対象外となっているのは、「生計を一にする家族」です。しかし、生計を一にしない家族に支払う給与は、他の従業員と同じく経費として認められます。
家族に支払う給与を経費として計上できれば、個人事業主の所得金額が減るため税金の負担を抑えることが可能であり、節税対策につながります。
「生計を一にしない家族」とは?
生計を一にしない家族とは、同居をしていない、または同居をしていたとしても生活費や家計を別で分けている家族です。
生計を一にする家族と、一にしない家族の具体例は以下のとおりです。
- 【生計を一にする家族の例】
-
- 同じ家で暮らし、同じ財布で生活費を共にしている
- 共働き夫婦がそれぞれ生活費を出し合い、同じ家で暮らしている
- 成人した子どもが両親を養っている
- 遠方に住んでいる親または子に仕送りをしている
- 【生計を一にしない家族の例】
-
- 別居をしており、生活費のやり取りもしていない成人の子ども
- 仕送りなどを受けておらず、独立して生活している親や兄弟姉妹
- 同居をしていても、家賃・食費・光熱費などを完全に自分で負担している家族
- 両親は年金で暮らしており、子どもは生活費を支援していない
- 同棲や事実婚、シェアハウスで一緒に暮らしている
生計を一にしない家族のポイントとしては、同居や別居で判断されるものではなく、生活費のやり取りや家計の状況が重視されています。
「青色事業専従者給与」なら生計を一にする家族への給与も経費にできる
生計を一にしない家族であれば給与を経費として扱うことができますが、実は生計を一にする家族でも、「青色事業専従者給与」であれば経費にすることは可能です。
青色事業専従者給与として認められるためには条件を満たす必要があるため、事前に条件をクリアしているかどうか確認しておきましょう。
青色事業専従者給与の条件・手続き

生計を一にする家族の給与を経費にしたい場合、青色事業専従者給与を活用するのがおすすめです。
青色事業専従者給与とは、青色申告をしている個人事業主が青色専従者に対して支払う給与を経費にできる制度を指します。
青色事業専従者給与の条件
家族を青色専従者にするには、以下の条件を満たす必要があります。
-
- 青色申告者と生計を共にする配偶者または親族
- 経費にしようとする年の12月31日時点で15歳以上
- 1年間のうち6カ月以上は家族の事業で働いている
- 税務署へ事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している
- 届出書に記載されている方法で、かつ記載されている金額の範囲内で給与を支払っている
青色事業専従者として認められるためには、そもそも家族が個人事業主の事業を手伝っている必要があります。
この場合、単に手伝っているだけでなく、6カ月以上は専従していなければ青色事業専従者給与として認められません。
例えば別の企業で働いており、土日だけ手伝っているなどは6カ月以上働いていたとしても青色事業専従者として認められないので注意してください。
また、事業を手伝っている家族に対して給与を支払わなければなりません。
青色事業専従者給与に関する届出書には、給与の支払い方法や金額について記載する欄があります。
ここで記載した金額をきちんと支払わないと、青色事業専従者給与として認められないこととなっています。
特に金額に関しては、労務の対価として相当と認められるものでなければなりません。
例えば同業種ではありえないほど高い給与を支払っていると、経費にならないので注意してください。
青色事業専従者給与による節税効果
青色事業専従者給与にすると、どれくらいの節税効果を得られるのか気になる人も多いでしょう。
まず、事業主の年収を1,000万円、青色事業専従者の給与年額を200万円、その他経費の合計が300万円、各種控除の合計が100万円だったとします。
事業所得の計算式は「(年収-必要経費-各種控除)×税率-控除額」になるため、ここに上記の数字を当てはめると、青色事業専従者給与を支払っていない場合の所得税は以下になります。
(1,000万円-300万円-100万円)×20%-427,500円=772,500円
税率と控除額は国税庁「No.2260 所得税の税率」に記載されているため、自分に当てはめて計算する際にこちらも確認してください。
一方、青色事業専従者給与を支払っていた場合の所得税は、以下のとおりです。
(1,000万円-(300万円+200万円)-100万円)×20%-427,500円=372,500円
家族に支払う給与を経費にできた場合とできなかった場合で、約40万円も納める金額に違いがあることがわかります。
青色事業専従者給与を経費にするための手続き
青色事業専従者給与を経費にするためには、事前に税務署へ届出を提出する必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族への給与を必要経費に算入したい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業または新たに専従者が加わった人はその日から2カ月以内)に提出しなくてはなりません。
届出書はPDFファイルをダウンロードして入力・印刷することも可能ですが、e-Taxから提出することもできます。
なお、届出書に記載した内容とは別で給与規定を定めている場合は、その写しも添付して提出する必要があります。
白色申告だと「事業専従者控除」が受けられる

上記は青色申告をしている場合となりますが、白色申告でも条件を満たすことで「事業専従者控除」が認められる場合もあります。
ここで、白色申告の事業専従者控除を解説します。
白色申告の事業専従者控除とは
事業専従者控除とは、白色申告の事業者が生計を一にする家族への給与を一定額、事業所得から差し引くことができる制度です。
白色申告の場合、以下のいずれか低いほうの金額が経費としてみなされ、事業所得から控除できます。
1.事業専従者が事業主の配偶者なら86万円、配偶者以外だと1人につき50万円
2.事業所得を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
例えば白色申告者の所得金額が200万円で、事業専従者が配偶者1人だった場合、200万円÷(1+1)=100万円になります。
100万円は86万円よりも大きい金額になるため86万円が適用され、控除額は年間86万円ということになります。
青色事業専従者給与は支払った給与額分がすべて控除できるため、青色事業専従者給与のほうが節税効果は高いです。
しかし、白色申告でも一定額の控除が受けられるため、条件を満たしているなら活用したほうが良いでしょう。
事業専従者控除の条件
事業専従者控除は白色申告者なら誰でも受けられるわけではありません。
基本的には、上記で紹介した青色事業専従者給与とほとんど同じ条件を満たしている必要があります。
-
- 白色申告者と生計を共にする配偶者または親族
- 経費にしようとする年の12月31日時点で15歳以上
- 1年間のうち6カ月以上は家族の事業で働いている
- 確定申告書に事業専従者控除を受ける旨とその金額など、必要事項が記載されている
事業専従者控除を受けるための方法
事業専従者控除を受けるために、青色事業専従者給与のように税務署へ事前に届出書を提出することはありません。
しかし、控除を受けるには必要事項を記載した確定申告書と収支内訳書を、確定申告の期間内に提出が必要です。
まず収支内訳書では、1ページ目にある「専従者控除(20)」の欄には専従者ごとの控除額を計算してその合計額を記入し、「事業専従者の氏名等」の欄には専従者の氏名と年齢、続柄、従事月数、延べ従事月数を記入します。
確定申告書では第一表の「その他」にある「専従者給与(控除)額の合計額(58)」に、収支内訳書に記入した合計控除額を転記します。
次に、第二表の「事業専従者に関する事項(59)」で、専従者の氏名とマイナンバー、続柄、生年月日、従事月数、程度、仕事内容などを記載し、さらに控除額の内訳も記入しましょう。
あとは確定申告の期間内(例年2月16日~3月15日頃)に提出することで、事業専従者控除が受けられるようになります。
家族に支払う給与額を決めるポイント

青色事業専従者給与だと支払った給与額分がすべて経費として計上できるため、たくさん給与を支払えば、その分課税所得額を減らせるのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、青色事業専従者給与は常識の範囲内で金額を決めないと、青色事業専従者給与として認められず、結局経費として計上できないというケースも考えられます。
そこで、家族に支払う給与額はどのようにして決めれば良いのか、解説していきます。
妥当な給与水準にする
まず気を付けたいのが、妥当な給与水準にすることです。妥当な給与水準を知るためにも、同業・同職種の一般的な賃金を参考にしてみてください。
給与額の相場は業種や職種以外に、仕事内容や地域によっても異なってきます。
求人サイトを活用する際は、現在家族にお願いしている仕事などでできるだけ近しい条件の求人を探し、給与額を参考にします。
また、事業主の収入と比較してバランスが適正かどうかもチェックすることが大切です。
例えば事業主の収入が500万円なのに対して、仕事内容は異なるのに家族も同等の給与をもらっていれば、バランスは適正ではないと判断される可能性が高いです。
社会保険などの加入金額も意識する
青色事業専従者給与は、家族に支払った給与を経費にすることで事業主の課税所得を減らせる制度です。
しかし、給与額によってはかえって世帯の負担が増えてしまう可能性があります。
社会保険の適応事業所(常時5人以上の従業員を雇用)になっている場合は、個人事業主でも社会保険に加入しています。
それにより個人事業主の配偶者など家族も社会保険の不要に入ることが可能です。
ただし、配偶者などに支払う給与が月額88,000円を超えるなど条件を満たすと、社会保険の扶養対象から外れ、個別で社会保険に加入する必要が出てきます。
すると、社会保険料の負担が増大し、事業主の課税所得は減らせても社会保険料の負担が上がってしまう可能性が高いです。
そのため、社会保険などの加入金額も意識しながら、適正な給与額を設定する必要があります。
個人事業主が家族給与を経費にする際の注意点

個人事業主が家族給与を経費にする場合、いくつか注意すべきポイントがあります。ここで注意点について解説します。
配偶者控除・扶養控除の対象外となる
家族の給与を経費として計上した場合、給与を支払った配偶者や親族に関して配偶者控除や扶養控除が利用できなくなってしまいます。
配偶者控除だと一般の控除対象配偶者で最大38万円の控除額が受けられますが、青色事業専従者になるとこの控除が受けられません。
つまり、青色事業専従者給与で配偶者控除以上の控除を受けられない場合(年間給与が38万円以下)は、青色事業専従者給与よりも配偶者控除を利用したほうが良いでしょう。
業務内容・労働時間は必ず記録する
配偶者や親族だと、他の従業員に比べて管理が曖昧になりやすいです。
どれだけの時間を働いているのか、どんな仕事をしているのかなどが第三者からわかりづらくなってしまいます。
税務署から指摘される可能性もあるため、配偶者や親族でも他の従業員と同様に、業務内容や労働時間は必ず記録することが大切です。
まとめ・個人事業主は家族給与を経費にして賢く節税を
個人事業主が家族に支払う給与は、「生計を一にしているかどうか」で扱いが異なります。
生計を一にしていない家族は、通常の従業員と同じ扱いで給与を経費に計上することが可能です。
ただし、生計を一にしている家族でも、要件を満たし「専従者給与」として認められれば経費にできます。
いずれの場合も、就労の実態や支払いの根拠を明確にし、必要な手続きをきちんと行うことが大切です。
家族への給与以外にも、経費を上手に活用すれば利益を守る工夫ができます。
23の経費科目ごとに「削減」と「節税」のポイントをまとめた 創業手帳の無料「経費チェックリスト」 を使って、
あなたの経費をもう一度見直してみませんか?

(編集:創業手帳編集部)