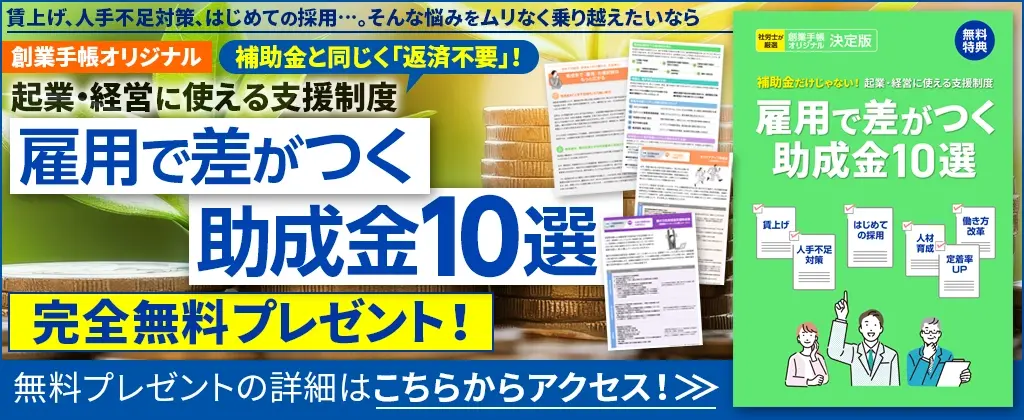東京都が行う「年収の壁」対策の支援とは。「年収の壁突破総合対策促進奨励金」を解説
2つのコースを活用して優れた人材を確保しよう
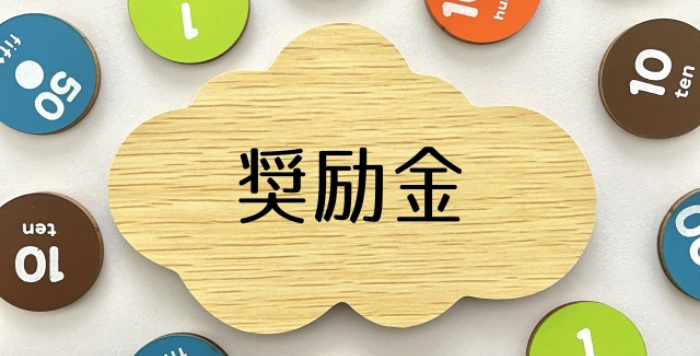
東京都は「年収の壁」を超えて働く従業員や事業主を支援するため、「年収の壁突破総合対策促進奨励金」を創設しました。パート・アルバイトで働く方が106万円や130万円の壁を意識せずに働けるよう、事業主に対して最大50万円の奨励金を支給しています。
人手不足の深刻化が続く中、この制度を活用することで、従業員のモチベーション向上と企業の人材確保を同時に実現することが可能です。今回は、東京都が行っている「年収の壁突破総合対策促進奨励金」について解説します。
「年収の壁」対策のように、国や自治体は人材確保や雇用安定を目的に様々な支援策を用意しています。
創業手帳の 『雇用で差がつく助成金10選』 では、事業者が活用できる代表的な助成金を一覧で解説。支給対象や申請方法をまとめて確認できます。ぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
東京都が行う年収の壁対策の支援

東京都の最低賃金は全国で最も高く、2024年10月から1,163円となっています(2025年10月3日からは1,226円)。このため、パート・アルバイトで働く従業員は他の地域よりも「年収の壁」に達しやすく、事業主にとって人材確保の課題となっています。
年収の壁とは、パート・アルバイトで働く従業員が社会保険料の負担増加を避けるために、収入を抑えようとする年収のボーダーラインです。「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、これらを超えると自身で社会保険に加入したり、親族の扶養から抜けたりする必要が生じます。
| 壁の金額 | 超えたときの影響 |
|---|---|
| 106万円の壁 | 勤務先の社会保険に加入する(特定適用事業所の場合) |
| 130万円の壁 | 親族の扶養から抜ける |
多くの事業主が直面している問題は、人手を確保したくても、従業員が年収の壁を意識して働き控えを行うケースです。東京都の奨励金制度は、こうした課題を解決し、事業主が安定した人材確保を行えるよう支援しています。
国も「年収の壁・支援強化パッケージ」という支援を行っていますが、東京都は独自の支援策を展開しています。
奨励金額
奨励金額は、1事業主30万円です。社会保険加入促進コースと配偶者手当見直しコースの2コースがあり、両方に取り組む場合は50万円が支給されます。
この奨励金を活用することで、事業主は人手を確保しつつ、従業員への手当支給や労働環境の改善に必要な資金を確保できます。また、専門家による個別相談を受けられるため、労務管理の見直しや就業規則の整備について専門的なアドバイスを受けることも可能です。
社会保険加入促進コース

社会保険加入促進コースは、新たに社会保険に加入する従業員に対して、手当を支給する事業主を支援するコースです。このコースを活用することで、従業員の社会保険加入に伴う負担を軽減し、年収の壁を意識せずに働ける環境を実現できます。
趣旨
社会保険に加入することで、従業員は将来の年金受給額の増加や健康保険からの保障(傷病手当金や出産手当金など)を得られるなど、さまざまなメリットを享受できます。一方で、保険料の発生により手取り収入が一時的に減少するため、従業員が社会保険加入を敬遠するケースが少なくありません。
事業主にとって、優秀な人材が年収の壁を理由に労働時間を制限することは、人手不足の大きな要因となっています。このコースを活用することで、従業員の手取り収入が減少する不安をなくし、人手不足を軽減できます。
対象事業者
社会保険加入促進コースの対象事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 都内で事業を営んでいる事業者であること
- 都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること(都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること)
- 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
- 新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
まず、都内で事業を営んでいる事業者であることが基本要件です。都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用しており、そのうち1名は6か月以上継続して雇用していることが求められます。
就業規則を労働基準監督署に届出ていることも必須要件の一つです。また、就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないことが条件となります。
さらに、新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいることが必要です。申込み以前に、既に見直しを行っている企業は対象外となる点に注意しましょう。
奨励対象となる取組
事業主に求められる取組は、以下の5つです。
- ア:取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設する(手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと)
- イ:社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、アの手当の受給対象となる計画を作成する
- ウ:アについて労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること(常時雇用する労働者数が10 人未満の事業者も含む)
- エ:社内周知及びアに関連する社内研修を行うこと
- オ:ア~エを実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1 時間程度)利用する
なお、特に注意が必要な取組項目を以下の表にまとめました。
| 取組項目 | 実施内容 | 実施期限 | 重要な注意点 |
| ①労使協定の締結 | 新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等について、労働者代表との間で合意を形成 | 交付決定から3か月以内 | 就業規則改正より先に実施すること |
| ②就業規則の改正 | 労使協定の締結後、就業規則に手当等の規定を追加し、所轄の労働基準監督署に届出 | 交付決定から3か月以内 | 必ず「①→②」の順番で実施(手順相違は対象外) |
| ③社内周知・研修の実施 | 全従業員を対象とした社内研修を実施し、整備した制度の内容や年収の壁についての情報提供を行う | 交付決定から3か月以内 | パート・アルバイト等の非正規雇用者も含む全従業員が対象 |
| ④専門家による個別相談窓口の利用 | 東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士との個別相談をオンライン(Zoom)で実施 | 1回目:交付決定から1か月以内 2回目:交付決定から3か月以内 |
取組期間内に合計2回(各回1時間程度)の利用が必須 |
なお、社内研修では新設した社会保険料手当の内容や支給条件、申請方法などを説明する必要があります。厚生年金、健康保険加入による将来的なメリットも解説すれば、理解を得やすくなるでしょう。
配偶者手当見直しコース

配偶者手当見直しコースは、配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直しを行った事業主を支援するコースです。このコースを活用することで、特に女性の就業調整を解消し、働く意欲のある人材が能力を十分に発揮できる環境を整備できます。
趣旨
多くの企業では、配偶者手当の支給要件として「配偶者の年収が103万円(130万円)未満」などの収入要件を設けています。扶養とは概念が異なるものの、実質的な「年収の壁」として機能しているのが実情です。
実際に、配偶者が手当を失わないよう就業時間を抑制するケースが多く見られ、企業の人材確保にも影響を与えています。このコースを通じて制度を見直すことで、配偶者手当を理由とした就業調整を防ぎ、女性の活躍促進と企業の人材確保を同時に実現できます。
対象事業者
配偶者手当見直しコースの対象事業者となるための要件は、以下のとおりです。
- 都内で事業を営んでいる事業者であること
- 都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること(都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること)
- 就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること
- 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
- 事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと
基本要件として、都内で事業を営んでいる事業者であることが必要です。都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用しており、そのうち1名は6か月以上継続して雇用していることが求められます。
就業規則を労働基準監督署に届出ていることも必須条件です。さらに、事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある家族手当」の支給実績があることが求められます。
なお、申し込み以前に既に見直しを行った企業は対象外となります。この制度は新たな取り組みを促進することを目的としているため、過去の取り組みは評価対象とならない点に注意が必要です。
奨励対象となる取組
奨励対象となる取組は、4つの要素で構成されており、これらすべてを交付決定から3か月以内に実施する必要があります。
| 取組項目 | 実施内容 | 重要な注意点 |
| ①労使協定の締結 | 配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直しについて、労働者代表との間で労使協定を締結する | 以下のいずれかの見直しに取り組む ア 配偶者手当の収入要件を撤廃する イ 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える ウ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる |
| ②就業規則の改正 | 労使協定の締結後、見直し内容を就業規則に反映し、所轄の労働基準監督署に届出 | 必ず「①→②」の順番で実施(手順相違は対象外) |
| ③社内周知・研修の実施 | 全従業員を対象とした社内研修を実施し、見直しした制度の内容や年収の壁についての情報提供を行う | 制度変更の理解促進と働き方に対する意識向上が目的 |
| ④専門家による個別相談窓口の利用 | 東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士との個別相談をオンラインで実施 | 取組期間内に合計2回(各回1時間程度)の利用が必須 |
制度の理解を深めるために、社内研修の実施は欠かせません。研修を通じて、配偶者手当の廃止により不利益を被るわけではない点を、丁寧に解説しましょう。
「年収の壁突破総合対策促進奨励金」を活用するメリット

東京都の「年収の壁突破総合対策促進奨励金」は、単に奨励金を受給できるだけでなく、事業主にとって多面的なメリットをもたらします。人材確保や企業価値の向上など、具体的なメリットを見ていきましょう。
信用保証料の補助や利率優遇を受けられる
奨励金の交付決定を受けた中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となります。融資を受けるときに信用保証料の2/3補助や、利率優遇を受けることができます。
女性活躍推進融資では、融資限度額2億8,000万円(組合4億8,000万円)、融資期間15年以内(据置期間2年以内を含む)の条件で資金調達が可能です。融資利率は都制度融資「働き方改革支援」から0.4%優遇され、責任共有対象の場合で1.45%~1.95%以内となっています。
人手不足解消や従業員の定着率向上につながる
年収の壁を意識せずに働ける環境を整備することで、従業員の働き控えを解消し、実質的な労働力の確保につながります。繁忙期に必要な労働時間を確保できれば、業務の停滞や提供するサービスや商品の品質低下を防げます。
社会保険加入促進コースを活用すれば、従業員が安心して社会保険に加入できる環境を整備できます。健康保険の加入に伴う保障の充実や、将来の年金増などのメリットが、従業員の満足度向上と定着率の改善につながることが期待できるでしょう。
配偶者手当見直しコースの活用を通じて、性別に関わらず能力を発揮できる公平な職場環境を構築できます。従業員の家族が年収を気にせず働けるようになることで、結果的に世帯全体の収入安定に寄与し、経済的な余裕を生む結果につながります。
優秀な人材を採用できる
優秀な人材を採用するうえでも、年収の壁対策は効果的です。特に、将来的なキャリアアップを目指したい非正規労働者や、配偶者の働き方を重視する求職者から好印象を持たれるでしょう。
雇用が流動化している現代の人材市場では、給与水準だけでなく働きやすさや将来性を重視する傾向が強まっています。年収の壁対策を講じている企業は、柔軟な働き方に対応しているイメージを持たれやすく、人材確保の競争力を高めることができます。
企業イメージが向上する
奨励金制度を活用して職場環境の改善に取り組めば、女性活躍推進や働き方改革に積極的に取り組む企業として認知されます。東京都の認定を受けた企業として、取引先や顧客からの信頼度向上、対外的なイメージ向上も期待できるでしょう。
SDGs(持続可能な開発目標)の「ジェンダー平等の実現」や「働きがいも経済成長も」といった目標に貢献する企業として、ESG経営の観点からも評価されます。昨今は企業の社会的責任の観点が厳しく見られているため、職場環境の改善は意義深い取り組みです。
専門家による個別相談を受けられる
取組期間中には、東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士との個別相談を合計2回(各回1時間程度)利用できます。これにより、労務管理の専門知識を活用した制度設計と運用が可能となります。
「もっと働きやすい環境をつくりたい」「自社の実情に応じた福利厚生制度を導入したい」「外部の専門家から客観的なアドバイスを受けたい」と考えている方にとって、役立つ支援です。
個別相談では、企業の実情に応じた最適な制度設計のアドバイスを受けられます。労使協定の締結方法や就業規則の改正手続き、従業員への説明方法など、実務面での具体的な指導を受けることができます。
さらに、年収の壁対策以外の労務管理上の課題についても相談できるため、総合的な職場環境の改善につなげることが可能です。専門家の知見を活用することで、法令遵守を確保しながら効果的な制度運用を実現できるでしょう。
手続きの流れ

「年収の壁突破総合対策促進奨励金」の申請には、事前エントリーが必要です。令和7年度は全10回の事前エントリー期間が設定されており、各回の受付期間終了後に抽選を行い、当選した事業主が交付申請を行える仕組みとなっています。
なお、手続きの流れは以下の通りです。
| フェーズ | 期間目安 | 主な実施者 | 重要ポイント |
|---|---|---|---|
| 事前エントリー | 各回約2週間 | 事業主 | 年10回の募集、1事業主1回限り |
| 抽選・通知 | 約5営業日 | 東京しごと財団 | 当落に関わらずメール通知 |
| 交付申請 | 当選から1か月 | 事業主 | 期限厳守、書類不備に注意 |
| 審査・交付決定 | 約1か月 | 東京しごと財団 | 審査状況により前後 |
| 取組実施 | 交付決定から3か月 | 事業主 | 個別相談を2回実施 ・1回目:交付決定日から1か月以内 ・2回目:交付決定日から3か月以内 |
| 実績報告 | 取組完了後 | 事業主 | 取組結果の詳細報告 交付決定日から4か月以内 |
| 奨励金受給 | 審査完了後 | 事業主 | 指定口座への振込 |
まず、公益財団法人東京しごと財団の特設ウェブサイトから事前エントリーを行います。事前エントリーは、1事業主につき1回限りです。
事前エントリー期間終了後、概ね5営業日以内に抽選結果がメールで通知されます。当選した場合は、当選メール送信日から1か月以内に交付申請を行う必要があります。交付申請は、郵送または電子申請(jGrants)で行いましょう。
交付決定後は、3か月以内に奨励対象となる取組(労使協定の締結や就業規則の改正、社内研修の実施など)をすべて完了しなければなりません。個別相談は1回目を交付決定から1か月以内、2回目を3か月以内にオンライン(Zoom)で実施します。
取組完了後は実績報告書を提出し、審査を経て指定口座に奨励金が振り込まれます。
提出書類

交付申請時に必要となる、主な提出書類は以下の通りです。
- 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金交付申請書
- 事業所一覧
- 就業規則見直し計画書
- 誓約書
- 雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主控)の写し
- 雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
- 印鑑(登録)証明書原本(発行日から3か月以内のもの(電子申請の場合は不要))
- 納税証明書原本(交付申請日時点で、納期が確定した直近のもの)
- 会社概要がわかるもの
- 交付申請日時点で直近の就業規則一式(別規程を含む)
- 賃金台帳の写し(配偶者手当見直しコースのみ)
- 法人都民税納税証明書(法人の場合)
- 法人事業税納税証明書(法人の場合)
- 個人都民税(居住地分)納税証明書(個人事業主の場合)
- 個人都民税(事業所地分)納税証明書(個人事業主の場合)
- 個人事業税納税証明書(個人事業主の場合)
また、奨励対象事業の実施期間内(交付決定日から4か月以内)には、実績報告として以下の書類を提出する必要があります。
- 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金実績報告書
- 就業規則見直し報告書
- 労使協定の写し(記名押印又は署名のあるもの)
- 改定後の就業規則(全文)、その他社内規程
書類の不備により審査に遅延が生じる場合があるため、事前に募集要項で詳細を確認することが重要です。
まとめ
東京都の「年収の壁突破総合対策促進奨励金」は、深刻化する人手不足の解決と女性活躍推進を同時に目指せる支援制度です。事業主にとって最大50万円の奨励金受給はもちろん、融資優遇や専門家による個別相談など、総合的なメリットを享受できます。
奨励金制度を活用することで、従業員が安心して働ける環境を整備し、持続的な企業成長の基盤を築けます。人材確保に課題を抱える事業主の方は、年収の壁を気にすることなく働ける職場環境の実現を目指しましょう。
創業手帳では、事業主の方に役立つ補助金や助成金、奨励金制度などを紹介した「補助金ガイド」を無料でお渡ししています。補助金の最新情報が自動でタイムリーに届く「補助金AI(ほじょアイ)」も無料で利用できるため、ぜひご活用ください。
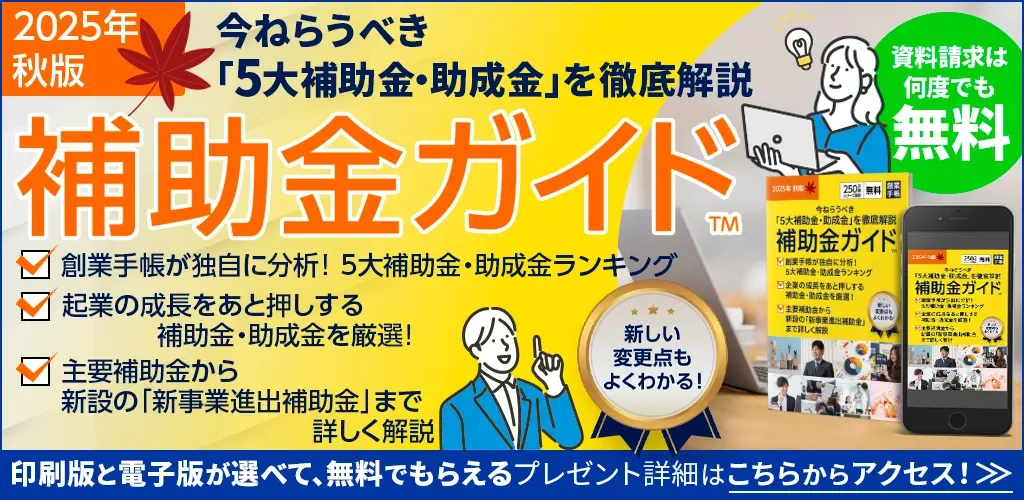
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。