資金繰りの改善方法とは?原因別の対策と資金調達のコツなどを解説
資金ショートを防ぐための基本をまとめました
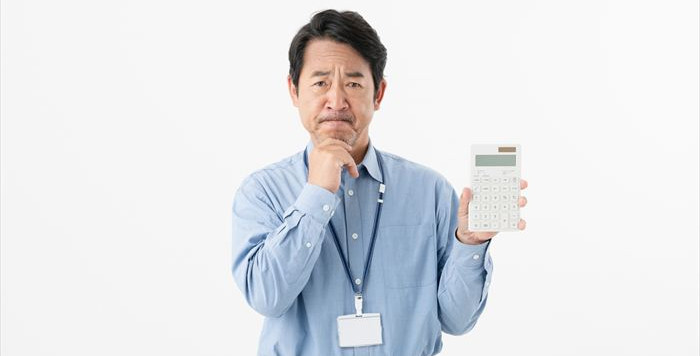
事業を継続していく上で、最も重要な要素のひとつが「資金繰り」です。どれほど売上があっても、手元資金が不足すれば黒字倒産に陥るかもしれません。
特に中小企業や個人事業主の場合、売掛金の回収遅延や予期せぬ支出があると、あっという間に資金ショートの危機に直面してしまいます。
そこで今回は、基本となる資金繰りの改善方法や、資金繰りが悪化する原因と対策、改善につながる資金調達方法などを解説します。
経営の安定化を図るために、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
まずは資金繰り表を作成しよう|現状把握が改善の第一歩

資金繰りを改善するためには資金繰り表を作成し、現状を把握することが大切です。
ここで、資金繰り表の作成方法や、「見える化」によってわかる改善のヒントを解説します。
資金繰り表とは?
「資金繰り表」とは、一定期間内の現金や預金の収入・支出をまとめた表を指します。
資金繰り表を作成することで、「いつまでに」「どれくらい」入金や支払いがあるか把握し、お金がどのように動いているのか見える化することが可能です。
お金の流れを見える化できる点ではキャッシュ・フロー計算書と似ていますが、キャッシュ・フロー計算書はあくまで現時点におけるお金の流れを把握することが目的です。
一方の資金繰り表は、将来の予測を含めたお金の流れを見ることが目的であり、今後資金不足に陥りそうなタイミングを察知できます。
資金繰り表の作成手順と活用ポイント
資金繰り表は、可能であれば週次・日次で更新するほうが常にお金の流れを把握でき、資金不足も予測しやすくなります。
以下の項目で構成し、Excelや専用のツールなどにまとめていきます。
-
- 前月からの繰越金額
- 収入計
- 支出計
- 財務収支計
- 翌月の繰越金額
資金繰り表で将来の収入・支出を見積もるためには、販売計画や設備投資計画などの資料も準備しておく必要があります。
また、財務データを正確に反映させるために、決算書や会計帳簿なども準備してください。
「見える化」でわかる改善のヒント
資金繰り表の作成でお金の流れを把握できれば資金繰り対策が可能になり、経営戦略も立てやすくなります。
資金繰り表を作成して終わりにするのではなく、現在の状況に合わせて柔軟に修正していくことが重要です。
例えば、数カ月後に資金が不足することを予測できたら、事前に金融機関へ融資を申し込みます。
資金が不足するタイミングで融資を受ければ、健全な財務体質を保持することが可能です。
創業手帳の「資金シミュレーター」を使えば、金融機関に提出できる形式の資金繰り表をかんたんに作成できます。
開業資金や目標売上額を入力するだけで初期値が自動で反映され、あとは実際の計画内容を画面に沿って入力すれば完成。
資金繰りの見通しを立てたい方は、ぜひご活用ください。
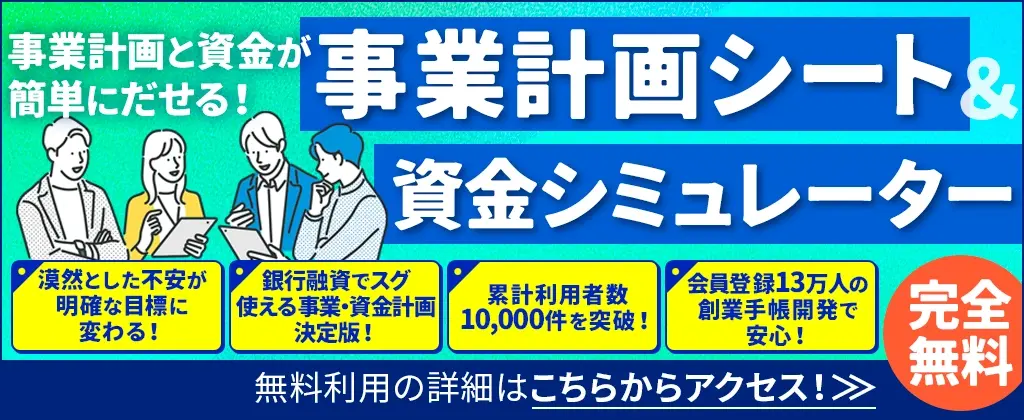
資金繰りの改善方法|基本的な取組み

資金繰りを改善するためには、基本的なことから取組むことが大切です。ここで、資金繰りの改善方法を紹介します。
固定費・変動費の見直し
まずは固定費・変動費を見直すところからスタートします。
固定費・変動費の見直しは即効性が高い改善方法であり、少額しか削減できなくても年間で見れば大きな削減効果を生む場合もあります。
固定費・変動費を見直す際には、資金繰り表も参考にしながら削減できる項目がないか探してみてください。
売上や資金の獲得に貢献していない遊休資産があれば、資金化することで資金繰りの改善につながる場合もあります。
売掛金・買掛金の管理強化
売掛金を回収するまでの期間が長くなるほど、資金繰りは悪化してしまいます。
そのため、売掛金の発生時期を把握し、請求が遅れないようにしながら回収漏れのないようにすることが大切です。
買掛金も同様に、支払いを少しでも遅らせることで、資金繰りの悪化を防ぐことができるでしょう。
また、請求書を早期に発行したり支払期日をできるだけ短縮したりすることや、前払い契約・分割払いを導入することで対策できます。
買掛金の場合は支払いサイトを延長できないか、支払い方法を変更できないかなどを取引先と交渉します。
ただし、有利な条件で交渉しようとすると、取引関係が悪化する可能性が高いです。
支払いサイトの延長を希望する代わりに一括で発注したり長期契約を結んだりするなど、双方にとってメリットのある関係になることを意識することが大切です。
過剰在庫の圧縮・回転率の向上
機会損失にならないように、できるだけ多くの在庫を確保したいと考える事業者もいるかもしれません。
しかし、商品の仕入れや在庫の保管には費用が生じるため、在庫が多いとコストも高くついてしまいます。
在庫をすべて捌けられれば問題ありませんが、過剰在庫になれば資金繰りの悪化につながるでしょう。
過剰在庫を圧縮させるためには、商品ごとに在庫・売上を管理する「単品管理」がおすすめです。
単品管理だと商品ごとの在庫数や売上が把握できるため、人気・不人気商品がわかり、売上に合わせて適切な発注を行えます。
すでに不良在庫が発生している場合は、価格を下げて販売を促進したり、他の商品とセットで販売したりするなどの工夫が必要です。
廃棄することも視野に入れつつ、極力現金化できるようにしてください。
入手金タイミングの最適化
入出金のタイミングを最適化させることも、資金繰りの改善につながります。
タイミングを最適化させるためには、どの時期にいくらの入出金があるかを把握しなくてはなりません。
上記でも解説した資金繰り表を使えば入出金のタイミングを予測し、最適化を図ることも可能です。
また、経費の支払いタイミングを少しずらしたい場合には、経費の支払いをクレジットカード払いにして、翌月に先延ばしさせる方法もあります。
翌月に支払いを先延ばしにしている間に売掛金を回収することで、資金繰りの改善も期待できます。
資金繰りが悪化する原因と対策
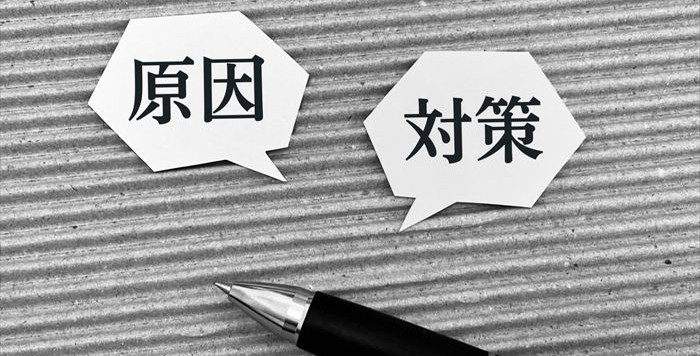
資金繰りが悪化する原因は多岐にわたります。改善させるためにはそれぞれの原因に合わせた対策も必要です。
ここで、資金繰りが悪化する原因と対策方法について解説します。
入金が遅く、支払いが先に来る
売掛金回収が遅れているタイミングで支払いのタイミングが訪れると、資金繰りが悪化して手元の現金がなくなってしまう恐れがあります。
状況を改善させるためには、取引先と支払いサイトの延長や前金制の導入などについて交渉してみてください。
また、どうしても現金が不足する場合にはファクタリングの活用がおすすめです。
ファクタリングは売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうことで、現金化できる仕組みです。
最短即日で資金を確保でき、担保や経営者保証なども原則不要であるため、中小企業も利用しやすいメリットがあります。
売掛金や在庫が滞留している
売掛金や在庫が滞留している状態が続くことでも、資金繰りの悪化につながります。売上の入金が行われるのは1~2カ月後になるケースが多いです。
また、商品は多くある状況にもかかわらず、手元に現金がない状態に陥ってしまうこともあります。
在庫自体は資産に分類されますが、滞留する在庫はキャッシュフローを圧迫している負債になることに注意が必要です。
売掛金の滞留をなくすためには、回収ルールの厳格化が必要です。新規取引先と契約する際には、できるだけ資金回収に有利な条件を設定するようにしてください。
また、売買契約書や売買基本契約書の中に「期限の利益喪失条項」を含めておくと、万が一取引先からの支払いが遅れた場合に、相応の補填を受けられるようになります。
在庫の滞留を防ぐためには、在庫管理の適正化を図ることが大切です。在庫管理システムを導入すれば、適正化を図れるだけでなく業務の効率化にもつながります。
支出が読みづらく、計画的にコントロールできていない
支出を予測しにくいと、計画的にコントロールができなくなってしまい、資金繰りが悪化する可能性もあります。
支出を予測するためには資金繰り表の作成が必要です。
資金繰り表は基本的に月次で作成しますが、すでに資金繰りが厳しい状況にある時は、週次または日次でより細かく資金の流れを把握しておいてください。
また、コストのコントロールがしやすいように、固定費の柔軟化も検討しましょう。
固定費の中で大部分を占める人件費を変動費に変えることで、売上に合わせて活用する体制を整えれば、資金繰りの改善に期待できます。
人件費を変動費にするためには、アウトソーシング・業務委託の活用や非正規雇用との組み合わせなどもおすすめです。
売上の変動が激しく、資金に波がある
売上の変動が激しいと資金に波ができてしまい、一時的に資金不足に陥る可能性もあります。
また、急激に売上が増加した場合、一見資金繰りは改善するように見えるかもしれません。
しかし、仕入れ費や人件費が先行してかかってしまい、実際の入金までにタイムラグが発生することで資金繰りの悪化につながりやすいです。
売上の変動が原因で資金繰りが悪化しないようにするためには、安定収益源の確保が重要です。
一時的なものではなく、継続的に収入が入ってくる仕組みを構築することで、資金繰りも安定化します。例として、会員制度やサブスクリプションの導入などが挙げられます。
また、上記でも紹介した変動費化の促進や、販促活動を強化することでも資金繰りの安定につながります。
外部要因(金利・為替など)の影響を受けやすい
金利や為替の変動、原材料価格の高騰など、外部要因の影響を受けて資金繰りが悪化してしまう場合もあります。
また、主要な取引先の業績悪化によって発注がなくなったり支払いの遅延が起きたりすることでも、自社の資金繰りは悪化してしまいます。
外部要因からの影響を少しでも減らすためには、金利の見直しやリスクを分散する形で仕入れルートを見直すことが必要です。
仕入れルートを分散させることで、取引先で何らかのトラブルが発生したとしても、自社が受ける影響を最小限に抑えられます。
資金繰り改善につながる資金調達方法

手元の資金が不足している場合には、資金を調達する必要があります。ここからは、資金調達方法について解説します。
日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫から融資を受けることで、資金調達が行えます。日本政策金融公庫は政府系の金融機関であり、中小企業・創業者向けに低金利の融資を提供しています。
金融機関から融資を受ける際には担保や保証人が必要になるケースが多いです。しかし、日本政策金融公庫の融資なら無担保・無保証人で利用できる場合もあります。
また、信用保証協会による審査を経由していないため、実際に着金されるまでのスピードが早いのも大きな特徴です。
一般的な金融機関であれば2~3カ月程度かかりますが、日本政策金融公庫であれば平均1カ月程度で着金されるので、資金繰りを改善したい場合にもおすすめです。
国や地方自治体の補助金・助成金
国や地方自治体は中小企業やベンチャー企業の経営を支援して地域の振興を図るために、補助金・助成金制度を設けています。
企業支援を目的としているため、創業間もない企業でも資金調達を行えるのはメリットといえます。
また、補助金・助成金は返済を求められないことが多く、負債になりません。
ただし、制度ごとに予算が決まっているため、必ず制度を利用できるわけではないということには注意してください。
なお、補助金・助成金制度の中には、交付後に経過・結果などを報告書にまとめて提出しなくてはいけない場合もあります。
ビジネスローン
ビジネスローンは、金融機関やノンバンクなどが法人・事業者向けに提供している融資商品です。
設備投資資金や運転資金、取引先に支払うための資金など、事業に関わる資金として活用できます。
公的融資や銀行融資に比べて審査に時間がかからず、最短で即日、遅くても1週間~10日前後で融資が受けられます。
ただし、ビジネスローンは金利が高かったり、借入可能額が数十万円~数百万円程度と比較的低かったりすることに注意が必要です。
増資・社債の発行
株式非公開の中小企業であれば、既存株主の額面価額による株主割当増資を行うことで、資金調達が可能になります。
増資による資金調達は配当金のコストは発生するものの、借入金とは異なり元金の返済は不要です。
また、社債を発行することでも資金調達ができます。社債は企業が発行する債券で、投資家から資金を募ることが可能です。
増資とは異なり元金の返済は必要となるものの、企業側の事情を考慮した返済条件を設定しやすくなっています。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する方法です。
プロジェクトとして資金の使い道を説明し、その内容に賛同を得た人が投資をする仕組みです。
クラウドファンディングには、資金を支援してもらったお礼にリターンを送る「購入型」、リターンがない「寄付型」、株式・新株予約権をリターンとして送る「投資型」があります。
資金調達を成功させるためには、「応援したい」と思えるプロジェクトを設計しなくてはなりません。
ファクタリング
ファクタリングは、自社が保有する売掛債権を売却し、資金を調達する方法です。すぐに資金が必要にもかかわらず、入金に時間がかかる場合などに適しています。
ファクタリングを活用すれば素早く現金を入手できますが、割引率に応じて手数料が発生してしまうため、本来得られるはずだった売上が下がってしまう点に注意してください。
また、何度も利用すると手数料がかさむため、頻繁に利用するのは避けたほうが良いです。
M&A
M&Aは、企業の合併・買収のことです。一般的には企業を売却するイメージが持たれがちですが、事業の一部だけを売却するケースもあります。
例えば、不調に陥っている事業や主力事業とシナジーが薄い事業を売却することで、まとまった資金を得られるようになります。
買い手との交渉を経て契約手続きを行うことから、すぐに資金を調達することは難しいでしょう。しかし、赤字が出ている事業でも高額で売却できる場合もあります。
まとめ・資金繰りの改善は「把握→見直し→実行」を積み重ねよう
資金繰りを改善させるためには、まず手元の資金がどれくらいあるのかを正しく把握してください。
資金繰り表を作成して、手元の資金や数カ月先の入出金タイミングを見直し、悪化する前に対策を講じることが大切です。
資金繰りの改善には日々の管理だけでなく、「必要な時にどう資金を調達するか」を知っておくことも重要です。
公的融資や制度融資など、起業家にとって心強い選択肢をわかりやすくまとめた無料ガイド『はじめての資金調達手帳』をご用意しました。ぜひ事業の安定と成長にお役立てください。
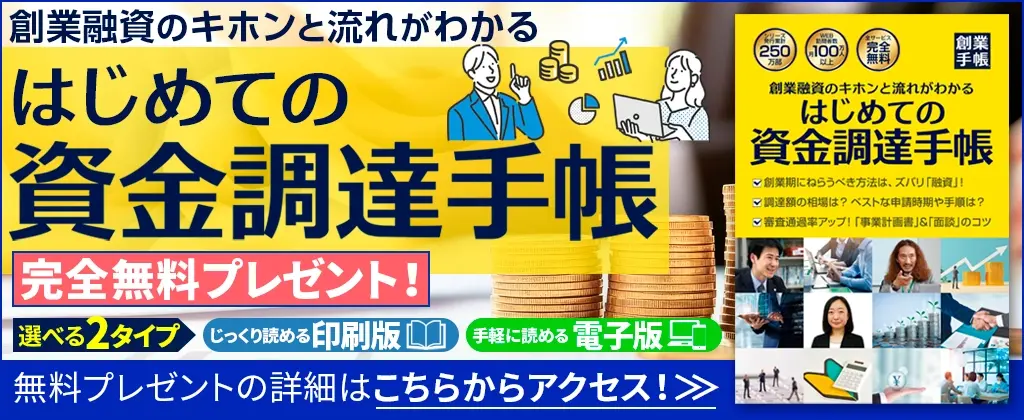
(編集:創業手帳編集部)





































