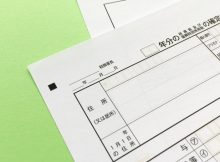経費で落ちるものの条件とは?経費に落ちるもの一覧(リスト)と注意点について解説
この費用って経費で落ちる?経費で落ちるものの一覧リスト。それぞれの費用ごとの勘定科目リストもご紹介

事業を営む上で「経費で落とせるもの」を正しく理解することは、節税効果を最大化し、適切な税務処理を行うために非常に重要です。しかし、どのような支出が経費として認められるのか、プライベートとの境界線はどこにあるのか、多くの事業主が悩むポイントでもあります。
本記事では、経費として認められる基本的な条件から始まり、交通費・通信費・消耗品費など11の主要カテゴリーごとに具体例を交えて詳しく解説します。さらに、家族との食事代やプライベート兼用の支出など、経費計上に注意が必要な項目についても取り上げ、税務調査で問題とならないための判断基準をお伝えします。
また、領収書の保存方法やクラウド会計ソフトの活用法、確定申告での記載方法まで、実務に直結する情報も網羅しています。この記事を読むことで、経費に関する正しい知識を身につけ、自信を持って確定申告に臨むことができるでしょう。
創業手帳の「経費チェックリスト」では、経費を「人件費」「交際接待費」「広告宣伝費」など23の経費科目ごとに分解し、それぞれの「経費削減のポイント」と「節税につなげる」ポイントを整理しています。無料でご利用いただけますので、ぜひあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
経費で落ちるものとは?
経費で落ちるものに必要な条件を以下でご紹介します。
事業関連性と必要性
経費として計上できる支出について正しく理解することは、事業運営において非常に重要な要素となります。まず基本的な原則として、経費として認められるためには「事業に関連性があり、事業のために必要な支出」であることが最も重要な条件となります。
この「事業関連性」とは、その支出が直接的または間接的に事業の売上向上や業務遂行に寄与するものでなければならないということです。単に個人的な趣味や生活に関わる支出は、たとえ事業主が支払ったものであっても経費として認められません。また、「事業のために必要」という要件については、その支出が事業を円滑に進めるために合理的に必要であったかどうかが判断基準となります。
証拠書類の適切な保存管理
また、経費として計上する際には、証拠書類の保存も絶対に欠かせない要件となります。具体的には、領収書やレシート、クレジットカードの利用明細など、支払いの事実を証明できる書類を適切に保管する必要があります。
これらの書類を保存する際には、単に書類を保管するだけでなく、何のための支出だったのか、どのような事業目的で使用したのかを明確に説明できるよう整理しておくことが重要です。税務調査が入った際には、税務署の職員に対してその支出の必要性と事業関連性を具体的に説明できなければなりません。そのため、日頃から支出の目的や経緯をメモに残しておく、関連する資料と一緒に保管するなどの工夫が求められます。
事業とプライベートが混在する支出の適切な按分(あんぶん)
実際の事業運営においては、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちな支出が数多く発生します。代表的な例としては、自宅を事務所として使用している場合の光熱費や家賃、営業活動に使用する車両の私的利用分などが挙げられます。
このような支出については、事業で使用した部分のみを合理的な基準によって按分し、その分だけを経費として計上することが原則となります。按分の方法については、使用面積の割合、使用時間の割合、使用頻度など、客観的で合理的な基準を設定することが重要です。
例えば、自宅兼事務所の場合であれば、全体の床面積に対する事務所として使用している部分の面積割合で按分したり、営業車の場合であれば走行距離の中で事業に使用した距離の割合で按分したりする方法が一般的です。このような按分計算についても、その根拠となる資料や計算過程を明確に記録し、保存しておくことが必要となります。
経費で落ちるもの一覧(一般的なもの)

以下では、経費で落ちるものの一般的な項目についてご紹介します。
1. 交通費・出張費
- 電車・バス・タクシー代
- 出張時の宿泊費・飛行機代
- ETC料金・高速代
電車・バス・タクシー代
電車やバス代については、事業目的での移動であれば経費として計上することができます。取引先への訪問、商談や会議への参加、仕入れ先や卸売市場への移動、銀行や税務署などの公的機関への移動、業界セミナーや研修会への参加などが典型的な事業目的として認められます。
これらの交通機関は通常領収書が発行されないため、適切な記録方法が重要になります。ICカードの利用履歴を印刷して保存する方法や、出金伝票に日付・区間・金額・目的を明記する方法が一般的です。定期券を使用している場合は、事業利用分を合理的に按分する必要があります。例えば、自宅兼事務所を使用している場合や、事業用と私的利用が混在する定期券については、使用頻度や距離に基づいて事業用分のみを経費計上します。月20日勤務のうち15日が事業関連の移動であれば、15/20=75%を事業用として按分することが可能です。
タクシー代については、領収書が必ず発行されるため、証拠書類の保存は比較的簡単です。ただし、電車やバスと比較して高額になりがちなため、利用の必要性がより厳しく審査される傾向があります。深夜・早朝の重要な商談や会議への移動、大量の商品サンプルや資料を持参する際の移動、公共交通機関が利用できない場所への移動、急病や事故などの緊急時の移動、重要な取引先への訪問で時間に余裕がない場合などは経費として認められやすいケースです。一方で、通常の営業活動で電車・バスが利用可能な場合や、個人的な都合による利用、過度に高額な長距離移動については注意が必要です。
出張時の宿泊費・飛行機代
出張時の宿泊費は、事業目的の出張であれば経費として計上できますが、社会通念上相当と認められる範囲内である必要があります。一般的なビジネスホテルであれば5,000円から15,000円程度、シティホテルなら10,000円から25,000円程度、地方都市での宿泊なら3,000円から10,000円程度が適切な目安とされています。
遠方の取引先との商談のための前泊・後泊、展示会や見本市への参加時の宿泊、研修や講習会参加時の宿泊、出張先での作業が深夜に及ぶ場合の宿泊、早朝からの重要な会議に備えるための前泊などは、経費として認められる宿泊の具体例です。宿泊費を計上する際は、宿泊施設の領収書を必ず保存し、出張の目的と期間を明確に記録することが重要です。朝食付きプランの場合、食事代部分も含めて宿泊費として計上可能ですが、家族同伴の場合は事業主分のみを経費計上し、スイートルームなど過度に豪華な部屋は避けるべきです。
飛行機代についても、事業目的の移動であれば経費として計上できます。国内出張だけでなく、海外出張の場合も同様です。座席クラスについては、エコノミークラスは基本的に問題なく経費計上可能で、ビジネスクラスは長時間フライトや重要な商談の場合は合理的とされますが、ファーストクラスは特別な事情がない限り経費として認められにくい傾向があります。
海外の取引先との商談や契約締結、国際展示会への参加、海外工場や支店の視察、国内の遠方支店への出張、緊急性の高い業務での移動などが経費として認められる飛行機利用の具体例です。航空券を購入する際は、航空券の控えと領収書を必ず保存し、出張報告書に飛行目的と成果を記録することが大切です。航空券のキャンセル料も事業上やむを得ない場合は経費計上可能ですが、マイレージは個人の利益となるため適切に管理する必要があります。
ETC料金・高速代について
ETC料金については、営業車両での事業関連の移動であれば経費として計上できますが、私的利用分との按分が必要になる場合が多くあります。ETC利用照会サービスに登録して利用明細を定期的に確認・印刷し、各利用について訪問先・目的・同行者を記録することが重要です。私的利用分は除外して事業用分のみを計上し、月末に利用明細を整理して事業用・私用を明確に区分する必要があります。
取引先への訪問時の高速道路利用、商品の配送や納品時の利用、展示会や研修会場への移動、仕入れ先への移動時の利用、営業エリア拡大のための遠方への移動などが事業用として認められる利用例です。
ETC以外の現金やクレジットカードでの高速道路料金支払いについても、同様に経費計上が可能です。料金所で発行される領収書を必ず保存し、通行区間・利用目的・訪問先を記録することが必要です。レンタカー利用時の高速代も事業目的であれば経費計上可能で、回数券や割引券利用時も領収書の保存が必要です。
営業車両を私的にも利用する場合の按分計算について具体例を挙げると、月間走行距離1,000kmのうち事業用800km、私用200kmの場合、按分率は800km÷1,000km=80%となります。月のETC利用料金が30,000円の場合、30,000円×80%=24,000円を経費計上することになります。
2. 通信費
- 事業用スマホの料金
- Wi-Fi・プロバイダ契約
- オンライン会議サービスの利用料
事業用スマホの料金
事業用のスマートフォン料金は、基本的に通信費として経費計上することができます。ただし、事業専用で使用している場合と、私的利用も含む場合では処理方法が異なるため、使用実態に応じた適切な処理が必要です。
事業専用のスマートフォンを契約している場合は、月額基本料金、通話料、データ通信料、端末代金の分割払い、各種オプション料金などを全額経費として計上できます。取引先との連絡、営業活動中の情報収集、顧客対応、緊急時の連絡手段として使用する場合が該当します。また、事業用のアプリケーション利用料、セキュリティソフトの月額料金、クラウドストレージの利用料なども通信費または消耗品費として計上可能です。
一方、個人のスマートフォンを事業にも使用している場合は、使用実態に基づいた按分計算が必要になります。按分の方法としては、通話時間による按分、通話回数による按分、データ使用量による按分、時間による按分などが考えられます。例えば、月の通話時間100分のうち60分が事業関連であれば60%を事業用として計上する方法や、平日の日中8時間を事業用、それ以外を私用として按分する方法があります。
按分計算を行う際は、その根拠となる資料を保存しておくことが重要です。通話明細書やデータ使用量の記録、業務日報などを活用して、合理的な按分基準を設定し、継続的に同じ基準を適用することが求められます。税務調査の際には、この按分の根拠について詳しく説明できるよう準備しておく必要があります。
スマートフォンの端末代金についても、事業用であれば経費として計上できます。一括購入の場合は消耗品費または器具備品として処理し、分割払いの場合は月々の支払い分を通信費に含めて処理することが一般的です。ただし、10万円以上の高額な端末については減価償却の対象となる場合があるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
Wi-Fi・プロバイダ契約
インターネット接続に関する費用は、現代の事業運営において必要不可欠な支出として、通信費で経費計上することができます。自宅兼事務所の場合と、専用事務所の場合で処理方法が異なりますが、いずれの場合も事業に必要な支出として認められます。
専用の事務所でのインターネット契約については、プロバイダ料金、回線使用料、Wi-Fi機器のレンタル料金、工事費用などを全額経費として計上できます。光ファイバー、ADSL、ケーブルインターネットなど、回線の種類に関わらず事業用であれば経費処理可能です。また、モバイルWi-FiルーターやポケットWi-Fiの料金についても、営業活動や出張時の業務に使用する場合は通信費として計上できます。
自宅兼事務所でインターネットを使用している場合は、事業用と私用の按分が必要になります。按分の基準としては、使用時間による按分、使用面積による按分、利用目的による按分などが考えられます。例えば、1日12時間のうち8時間を事業に使用している場合は8/12=約67%を事業用として按分することができます。また、自宅の延床面積100平方メートルのうち20平方メートルを事務所として使用している場合は、20%を事業用として按分する方法もあります。
インターネット関連の機器についても、事業用であれば経費計上可能です。Wi-Fiルーター、モデム、LANケーブル、ネットワークハブなどの購入費用は消耗品費または器具備品として処理します。セキュリティソフトやファイアウォールソフトの年間ライセンス料、ウイルス対策サービスの月額料金なども通信費または消耗品費として計上できます。
プロバイダ契約時の初期費用や工事費についても、事業用であれば経費として処理できます。ただし、高額な工事費については、その効果が複数年にわたる場合は繰延資産として償却処理することもあります。契約時に支払う保証金については、契約終了時に返還される性質のものであるため、敷金・保証金として資産計上し、返還されない部分のみを経費処理します。
オンライン会議サービスの利用料
近年のテレワークの普及に伴い、オンライン会議サービスの利用料も重要な通信費の一部となっています。Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype for Business、Cisco Webexなどの有料プランの利用料は、事業目的であれば通信費として経費計上できます。
基本的な月額料金だけでなく、追加機能の利用料、参加者数の拡張料金、録画機能の追加料金、セキュリティ機能の強化料金なども事業用であれば経費として認められます。また、オンライン会議に必要な周辺機器の購入費用も関連する経費として計上可能です。高品質なWebカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、照明機器などが該当します。
複数のオンライン会議サービスを併用している場合でも、それぞれが事業目的であれば全て経費として計上できます。例えば、社内会議用にMicrosoft Teams、顧客との商談用にZoom、セミナー開催用にWebexを使い分けている場合、全ての利用料を通信費として処理することができます。
オンライン会議サービスを私的にも利用している場合は、他の通信費と同様に按分が必要になります。利用時間、利用回数、利用目的などを基準として事業用分を算出し、その部分のみを経費計上します。例えば、月30回の利用のうち24回が事業関連であれば、24/30=80%を事業用として按分することができます。
年間契約で割引を受けている場合の処理方法としては、年額を一括で支払った場合でも月割りで経費計上することが原則です。ただし、金額が少額の場合は支払時に全額を経費処理することも認められます。一般的には、年間10万円未満であれば支払時の一括経費処理が可能とされています。
オンライン会議サービスの利用料支払いに使用したクレジットカードの明細書や、サービス提供会社からの請求書、利用明細書などは全て保存しておく必要があります。また、どのような事業目的で利用したかを説明できるよう、会議の議事録や参加者リスト、会議の目的などを記録しておくことが重要です。
3. 消耗品費
- 文房具
- プリンターのインク
- マスクやアルコールなど衛生用品
文房具
文房具類は事業運営において日常的に使用される基本的な消耗品として、ほぼ全ての業種で経費計上が認められています。ボールペン、シャープペンシル、鉛筆、消しゴム、マーカー、蛍光ペン、定規、カッター、ハサミ、ホッチキス、クリップ、付箋、ノート、コピー用紙、封筒、ファイル、バインダーなど、業務に使用する文房具は基本的に消耗品費として処理できます。
文房具の購入時期についても特に制限はなく、必要に応じてまとめ買いをした場合でも、合理的な範囲内であれば購入時に全額を経費計上することができます。例えば、年度末にコピー用紙やボールペンをまとめて購入し、翌年度に使用する予定であっても、事業用であることが明確であれば購入時の経費処理が可能です。ただし、あまりにも大量で長期間使用する予定の文房具については、期間按分を求められる場合もあります。
高額な文房具については注意が必要です。一般的に10万円未満の文房具は消耗品費として処理できますが、高級万年筆や特殊な製図用具など、10万円以上の文房具については器具備品として減価償却の対象となる場合があります。また、事業の規模や性質に見合わない過度に高額な文房具は、税務調査で事業関連性を問われる可能性があります。
文房具を購入する場所についても制限はありません。文房具店、ホームセンター、コンビニエンスストア、100円ショップ、オンラインショップなど、どこで購入したものでも事業用であれば経費計上できます。ただし、購入時の領収書やレシートは必ず保存し、何を購入したかが分かるようにしておく必要があります。レシートに商品名が印字されていない場合は、購入した商品名をメモしておくことが重要です。
デザイン業や建築業など、特殊な文房具を使用する業種では、専門的な製図用具、色鉛筆、マーカー、定規、コンパス、カッターマットなども消耗品費として計上できます。これらの専門用具についても、業務に必要であることが説明できれば問題なく経費処理可能です。
プリンターのインク
プリンターのインクカートリッジやトナーカートリッジは、事業で使用するプリンターの消耗品として経費計上することができます。純正品、互換品、詰め替え用インクなど、種類を問わず事業用であれば消耗品費として処理できます。レーザープリンター用のトナーカートリッジ、インクジェットプリンター用のインクカートリッジ、大判プリンター用の特殊インクなども同様に扱われます。
インクの購入タイミングについても、実際の使用時期と購入時期にずれがあっても問題ありません。プリンターインクは消耗品の性質上、まとめ買いによる割引を活用したり、頻繁に交換が必要な色だけを多めに購入したりすることが一般的であり、このような購入パターンも合理的な事業判断として認められます。
自宅兼事務所でプリンターを使用している場合は、事業用と私用の按分が必要になります。按分の方法としては、印刷枚数による按分、使用時間による按分、印刷内容による按分などが考えられます。例えば、月間印刷枚数500枚のうち350枚が事業関連の印刷であれば、350/500=70%を事業用として按分することができます。按分の根拠となる印刷ログやコピー機のカウンター数値などを記録しておくことが重要です。
プリンター本体とインクを同時に購入した場合の処理については、プリンター本体は器具備品として減価償却し、インクは消耗品費として即時経費処理するのが一般的です。ただし、プリンター本体が10万円未満の場合は、本体も消耗品費として一括経費処理することができます。
複数台のプリンターを使用している場合や、異なる用途で使い分けている場合でも、それぞれが事業用であればすべてのインク代を経費計上できます。例えば、カラー印刷用とモノクロ印刷用を分けて使用している場合、営業資料用と経理処理用で使い分けている場合などが該当します。
メンテナンス用品についても消耗品費として計上できます。プリンターヘッドクリーニング液、用紙詰まり除去用具、プリンター清掃用クロスなど、プリンターの維持管理に必要な用品は事業の継続的な運営に必要な支出として認められます。
マスクやアルコールなど衛生用品
使い捨てマスク、布マスク、フェイスシールド、手指消毒用アルコール、除菌スプレー、除菌シート、手洗い用石鹸、ペーパータオル、使い捨て手袋、体温計、パーティション用アクリル板などが消耗品費として計上可能です。これらの用品は、事業所内での感染防止対策として合理的に必要と認められる範囲内であれば、業種を問わず経費処理できます。
購入数量についても、一定期間の備蓄として合理的な範囲内であれば問題ありません。感染症対策用品は供給不安定になる可能性があるため、数か月分をまとめて購入することも合理的な事業判断として認められます。ただし、明らかに事業規模に見合わない過大な購入量については、税務調査で説明を求められる可能性があります。
店舗や事務所を運営している場合は、顧客用と従業員用の衛生用品を区別して購入することもありますが、いずれも事業運営に必要な支出として消耗品費で処理できます。例えば、店舗入口に設置する顧客用の手指消毒液、従業員が使用するマスクや手袋、共用部分の清掃・除菌用品などがすべて経費対象となります。
在宅勤務を行っている従業員に支給する衛生用品についても、事業上の必要性が認められれば消耗品費として計上できます。在宅勤務用のマスク、手指消毒液、除菌シートなどを従業員に配布する費用は、労働安全衛生の観点から合理的な支出として扱われます。
衛生用品の購入場所についても制限はありません。薬局、ドラッグストア、ホームセンター、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインショップなど、どこで購入したものでも事業用であれば経費計上可能です。ただし、購入時の領収書やレシートは必ず保存し、商品名と数量が明確に記載されていることを確認する必要があります。
業種による特殊な衛生用品についても、事業上の必要性が認められれば消耗品費として計上できます。例えば、食品関連業では食品用手袋や髪の毛をカバーするネット、医療関連業ではサージカルマスクや医療用手袋、美容関連業では使い捨てタオルや施術用手袋などが該当します。
4. 接待交際費

- 取引先との飲食代
- 手土産や贈答品
取引先との飲食代
取引先との飲食代は、事業の維持・発展を目的とした支出として接待交際費で経費計上することができます。ただし、接待交際費には法人と個人事業主で異なる制限があり、特に法人の場合は厳格な損金算入限度額が設定されているため、慎重な管理が必要になります。
個人事業主の場合は、接待交際費に金額的な上限はありませんが、事業の規模や内容に見合った合理的な範囲内である必要があります。取引先との関係維持や新規開拓を目的とした飲食であることが明確であれば、基本的に全額を経費として計上することができます。具体的には、既存取引先との定期的な情報交換を目的とした食事会、新規取引先の開拓を目的とした商談での食事、契約締結を祝う食事会、年末年始の挨拶を兼ねた懇親会などが該当します。
飲食代を接待交際費として計上する際に最も重要なのは、その飲食が事業目的であることを明確に証明できることです。単なる友人との食事や家族との食事は、たとえ事業の話題が出たとしても接待交際費としては認められません。領収書には参加者の氏名、所属会社、食事の目的を明記し、可能であれば商談の結果や今後の予定についてもメモを残しておくことが重要です。
飲食の場所や金額についても、事業の規模や取引先との関係性に見合った適切なレベルである必要があります。過度に高額な料亭での接待や、明らかに事業規模に見合わない豪華な食事は、税務調査で問題となる可能性があります。一般的には、一人当たり5,000円から20,000円程度の範囲内であれば、多くの業種で合理的な接待費として認められることが多いです。
同伴者の扱いについても注意が必要です。事業主本人と取引先だけでなく、自社の従業員や取引先の複数名が参加する場合もありますが、参加者全員分の飲食代を接待交際費として計上できます。ただし、参加者の中に事業と関係のない家族や友人が含まれている場合は、その人数分を除外して計算する必要があります。
頻度についても合理性が求められます。同じ取引先との飲食が毎週のように続いている場合や、明らかに過度な頻度での接待は、税務調査で事業関連性を疑われる可能性があります。取引の規模や重要性、業界の慣習などを考慮して、適切な頻度を保つことが重要です。
アルコールを伴わない食事についても、事業目的であれば接待交際費として計上できます。ランチミーティング、カフェでの商談、朝食会なども、取引先との関係構築や情報交換を目的としたものであれば問題なく経費処理可能です。
手土産や贈答品
手土産や贈答品は、取引先との良好な関係を維持・発展させるための重要な手段として、接待交際費で経費計上することができます。ただし、贈答品については社会通念上相当と認められる範囲内である必要があり、過度に高額な贈り物は税務上問題となる可能性があります。
季節の贈答品として一般的なお歳暮、お中元、年始の挨拶品などは、取引先との関係維持を目的とした合理的な支出として認められます。また、取引先の創立記念、新店舗オープン、重要な契約締結などの祝い事に対する祝品や花輪なども、事業上の儀礼として接待交際費で処理できます。地方の特産品、銘菓、高級茶葉、果物、酒類などが一般的な贈答品として選ばれることが多いです。
手土産については、取引先への訪問時に持参する菓子折りや地域の名産品などが該当します。商談や会議の際の心遣いとして、または遠方から訪問する際の地元の特産品として持参するものは、取引先との関係性を良好に保つための必要な支出として認められます。一般的には一件当たり3,000円から10,000円程度の範囲内であれば、合理的な手土産費として扱われることが多いです。
贈答品の金額については、一人当たり年間3,000円以下の物品については、税務上特別な扱いが受けられる場合があります。ただし、これは主に従業員への贈り物に関する規定であり、取引先への贈答品については、事業の規模や取引先との関係性に見合った適切な金額であることが重要です。
贈答品を購入する際の注意点として、のし紙や包装紙に会社名や事業主名を明記することが重要です。これにより、個人的な贈り物ではなく事業上の贈答品であることが明確になります。また、購入時の領収書には、誰に対する贈答品なのか、どのような目的での贈り物なのかを明記しておく必要があります。
贈答品の種類についても、事業の性質や取引先の業種を考慮した適切な選択が求められます。例えば、食品関連の取引先には高品質な食材や調味料、建設関連の取引先には実用的な事務用品や工具類、小売業の取引先には季節商品や話題の商品などを選ぶことが一般的です。
冠婚葬祭に関する支出についても、取引先との関係維持を目的としたものであれば接待交際費として計上できます。取引先の結婚祝い、出産祝い、新築祝い、昇進祝いなどの慶事に対する祝金や祝品、また取引先の不幸に対する香典や供花なども、事業上の儀礼として合理的な範囲内であれば経費処理可能です。
5. 地代家賃・水道光熱費
- 事務所の家賃(自宅兼用の場合は按分)
- 電気・ガス・水道代の事業分
事務所の家賃(自宅兼用の場合は按分)
専用の事務所や店舗を賃借している場合は、その家賃全額を地代家賃として経費計上することができます。月額賃料だけでなく、賃貸借契約に関連する初期費用についても、その性質に応じて適切に経費処理することが可能です。
賃貸契約時に支払う敷金については、将来返還される性質のものであるため、支払時には資産として計上し、実際に返還されない部分が確定した時点で経費処理します。一方、礼金については返還されない費用であるため、支払時に地代家賃として経費計上するか、その効果が複数年にわたる場合は繰延資産として数年にわたって償却処理することになります。仲介手数料についても、賃貸借契約の締結に直接関連する費用として地代家賃または繰延資産として処理します。
更新料についても、賃貸借契約の継続に必要な支出として地代家賃で経費計上できます。通常は支払時に全額を経費処理しますが、金額が高額で複数年の契約更新の場合は、契約期間にわたって按分処理することも可能です。また、契約更新時に発生する火災保険料についても、事業用資産の保険として保険料勘定で経費計上できます。
駐車場代についても、事業用車両の駐車や来客用駐車場として使用している場合は、地代家賃として経費計上可能です。月極駐車場の料金、時間貸し駐車場の利用料、事務所に併設された駐車場の使用料などが該当します。ただし、従業員の通勤用駐車場については、従業員への給与として扱われる場合もあるため、その目的を明確にしておくことが重要です。
自宅の一部を事務所として使用している場合は、家賃または住宅ローンの利息について、事業用部分を合理的な基準で按分して地代家賃として計上することができます。按分の方法については、税務署に対して合理的な説明ができることが最も重要で、一度決めた按分基準は継続的に適用することが求められます。
最も一般的な按分方法は面積按分です。自宅全体の床面積に対する事務所として使用している部分の面積割合で按分する方法で、客観的で説明しやすいという利点があります。例えば、自宅の総面積が100平方メートルで、そのうち20平方メートルを事務所として使用している場合は、20%を事業用として按分します。この場合、月額家賃10万円であれば2万円を地代家賃として経費計上することになります。
電気・ガス・水道代の事業分
電気代については、事業で使用するパソコン、プリンター、照明、エアコン、暖房器具などの電力消費が対象となります。専用事務所の場合は電気代の全額を水道光熱費として経費計上できますが、自宅兼事務所の場合は事業用分を合理的に按分する必要があります。
電気代の按分方法としては、使用時間による按分が最も一般的です。1日24時間のうち何時間を事業用として電気を使用しているかで按分します。例えば、平日8時間×22日=176時間、休日4時間×8日=32時間で、月間208時間を事業用として使用している場合、208時間÷(24時間×30日)×100=約28.9%を事業用として按分することができます。
コンセント別按分という方法もあります。事務所部分で使用しているコンセントの数と全体のコンセント数の比率で按分する方法です。ただし、この方法は実際の電力消費量を正確に反映しない場合があるため、使用機器の消費電力も考慮した按分が望ましいとされています。
事業用機器の消費電力による按分では、パソコン、プリンター、FAXなど事業専用機器の消費電力と、家庭全体の契約電力や平均使用電力を比較して按分率を算出します。この方法はより実態に即した按分が可能ですが、各機器の消費電力や使用時間を詳細に記録する必要があるため、管理が複雑になる傾向があります。
ガス代については、事業での使用が限定的な場合が多いため、按分が困難なケースもあります。事務所でガスを使用する主な用途としては、暖房、給湯、調理などがありますが、自宅兼事務所の場合は主に暖房用途での按分が中心となります。暖房については、事務所部分の面積按分や使用時間按分で計算することが一般的です。
飲食店や美容院など、事業でガスを多用する業種の場合は、事業用ガス機器の使用時間や使用頻度に基づいた按分が可能です。例えば、美容院でシャンプー用の給湯に使用するガス代、飲食店で調理に使用するガス代などは、営業時間や使用実態に基づいて合理的に按分することができます。
水道代については、一般的な事務作業では使用量が少ないため、按分率も低くなる傾向があります。手洗い、トイレ使用、清掃、植物への水やりなどが主な用途となります。面積按分や使用時間按分を適用することが多いですが、実際の使用実態を考慮して、電気代よりも低い按分率を設定することが合理的とされています。
6. 広告宣伝費・販促費
- チラシ・看板の制作費
- Web広告・SNS広告費
チラシ・看板の制作費
チラシや看板の制作費は、事業の認知度向上や売上拡大を目的とした支出として、広告宣伝費で経費計上することができます。これらの制作費には、デザイン料、印刷費、設置費用、メンテナンス費用など、広告媒体の企画から実施までに関わる全ての費用が含まれます。
チラシの制作費については、デザイン会社や印刷会社に支払うデザイン料、レイアウト料、校正費用、印刷費用のすべてが広告宣伝費として計上可能です。チラシの配布費用についても同様に経費処理できます。新聞折込み広告の手数料、ポスティング業者への委託費用、郵送での配布における郵便料金、配布スタッフへの人件費なども広告宣伝費に含めることができます。
チラシの種類や配布方法に関わらず、事業の売上向上を目的としたものであれば経費として認められます。新規開店時の告知チラシ、セール情報の案内チラシ、新商品・新サービスの紹介チラシ、イベント案内チラシなど、様々な目的のチラシ制作費が対象となります。また、季節商品の販促チラシ、年末年始の営業案内、移転・リニューアルの告知なども事業に直接関連する広告として扱われます。
看板の制作費については、その耐用年数と金額によって経費処理の方法が異なります。一般的に、制作費が10万円未満の看板については広告宣伝費として一括経費処理が可能です。一方、10万円以上の看板については器具備品として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却することになります。看板の法定耐用年数は材質によって異なり、金属製であれば18年、木製であれば8年程度が標準とされています。
看板の設置に関連する費用も経費として計上できます。看板設置のための工事費用、電気工事費、基礎工事費、足場設置費などが該当します。また、看板設置に必要な許可申請費用、道路使用許可申請費、建築確認申請費なども広告宣伝費として処理可能です。これらの費用についても、看板本体と同様に金額によって一括経費処理か減価償却かを判断します。
看板のメンテナンス費用については、継続的に発生する修繕費として広告宣伝費または修繕費で経費計上できます。電球の交換費用、清掃費用、塗装の補修費用、台風や雪害による軽微な修理費用などが該当します。ただし、看板の大規模な改修や全面的な作り直しについては、その内容によって修繕費ではなく資本的支出として資産計上が必要になる場合があります。
Web広告・SNS広告費
Google広告(旧Google AdWords)の利用料は、最も一般的なWeb広告費として広告宣伝費で経費計上できます。検索連動型広告、ディスプレイ広告、YouTube広告、ショッピング広告など、Google広告の各種サービス利用料はすべて経費対象となります。クリック課金制、インプレッション課金制、コンバージョン課金制など、課金方式に関わらず実際に発生した広告費用を経費として計上します。
Facebook広告やInstagram広告などのSNS広告費についても同様に経費処理できます。これらのプラットフォームでの広告配信費用、ブースト投稿の費用、スポンサー投稿の費用などが対象となります。また、Twitter広告、LinkedIn広告、TikTok広告、Pinterest広告など、各種SNSプラットフォームでの広告費用もすべて広告宣伝費として計上可能です。
Yahoo!広告(旧Yahoo!プロモーション広告)の利用料についても、Google広告と同様に経費計上できます。検索広告、ディスプレイ広告、ショッピング広告などのサービス利用料が対象となります。また、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどのECモール内での広告費用も、売上向上を目的とした支出として広告宣伝費で処理します。
Web広告の運用を代理店に委託している場合の手数料についても経費計上可能です。広告代理店への運用手数料、コンサルティング費用、レポート作成費用、戦略立案費用などが該当します。一般的に、これらの手数料は広告費の15%から20%程度に設定されることが多く、広告費本体と合わせて広告宣伝費として処理します。
ホームページやランディングページの制作費用については、その性質と金額によって処理方法が異なります。一般的に、30万円未満のホームページ制作費については広告宣伝費として一括経費処理が可能です。一方、30万円以上の大規模なサイト制作については、その効果が複数年にわたることを考慮して繰延資産として数年間で償却処理することが適切とされています。
SEO対策費用についても広告宣伝費として計上できます。SEO業者への月額委託費用、コンテンツ制作費用、被リンク対策費用、キーワード調査費用などが対象となります。また、SEO対策ツールの月額利用料、アクセス解析ツールの利用料、順位チェックツールの利用料なども継続的に広告宣伝費として処理します。
動画広告の制作費についても経費計上可能です。YouTube広告用の動画制作費、企業紹介動画の制作費、商品紹介動画の制作費、アニメーション制作費などが該当します。動画制作に関わる撮影費用、編集費用、ナレーション費用、音楽利用料、出演者への謝礼なども含めて広告宣伝費として処理できます。
メール配信サービスの利用料についても、顧客への情報発信を目的とした広告活動として広告宣伝費で計上できます。メルマガ配信システムの月額利用料、HTMLメール作成ツールの利用料、配信数に応じた従量課金などが対象となります。また、LINE公式アカウントの有料プランやプッシュ通知サービスの利用料なども同様に処理します。
7. 人件費・人材にかかる費用
- 給料賃金:従業員への給与
- 役員報酬:経営者への報酬
- 福利厚生費:健康診断・慶弔費・飲み物代など
- 法定福利費:社会保険料の事業主負担分
給料賃金:従業員への給与
従業員への給与は、事業運営において最も基本的かつ重要な経費項目として、給料賃金で経費計上することができます。正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず、労働の対価として支払う給与はすべて経費として認められます。
基本給については、従業員との雇用契約に基づいて支払われる固定給与として、毎月の支払い時に給料賃金で経費計上します。時間給の場合は実際の労働時間に基づいて計算された給与額を、月給制の場合は契約で定められた月額給与を経費として処理します。試用期間中の給与についても、実際に労働サービスの提供を受けている以上、正式採用後の給与と同様に経費計上可能です。
各種手当についても給料賃金として経費計上できます。役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、残業手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、危険手当、地域手当などが該当します。これらの手当は給与の一部として所得税や社会保険料の計算対象となり、従業員にとっては給与所得、事業主にとっては経費となります。
賞与・ボーナスについても、従業員の労働に対する対価として支払われるものであれば給料賃金で経費計上できます。定期賞与、決算賞与、業績賞与、特別賞与など、名称や支給方法に関わらず、従業員への労働対価として支払われるものはすべて経費対象となります。ただし、賞与については所得税の源泉徴収や社会保険料の計算が通常の給与と異なるため、適切な処理が必要です。
退職金についても、従業員の過去の労働に対する後払い的な給与として給料賃金または退職給付費用で経費計上できます。退職一時金、退職年金、中小企業退職金共済制度への掛金、確定拠出年金の事業主拠出分などが該当します。退職金については税務上の特別な取り扱いがあり、適正な金額であれば全額経費として認められますが、過大な退職金については一部が経費として認められない場合があります。
役員報酬:経営者への報酬
役員報酬は、法人の役員に対して支払われる報酬として、法人税法上特別な規定が設けられています。個人事業主の場合は事業主自身への給与は経費になりませんが、法人の場合は役員への報酬を一定の条件下で経費として計上することができます。
定期同額給与については、毎月同額を継続的に支払う役員報酬として、最も一般的な支給方法です。事業年度開始の日から3か月以内に金額を決定し、その後は原則として同額を継続的に支給する必要があります。期中での金額変更は原則として認められませんが、業績悪化などのやむを得ない事情がある場合は例外的に減額が認められることがあります。
事前確定届出給与については、賞与などの不定期な役員報酬を支給する場合に適用される制度です。支給日と支給額を事前に税務署に届け出て、その届出内容と完全に一致する形で支給した場合のみ経費として認められます。届出内容と異なる金額や時期で支給した場合は、全額が経費として認められなくなるため、慎重な計画と実行が必要です。
利益連動給与については、同族会社以外の法人において、株主総会の決議に基づいて利益に連動した役員報酬を支給する制度です。ただし、この制度は上場企業などの大規模法人を想定したものであり、中小企業では実質的に利用が困難な制度となっています。
役員報酬の金額については、同業他社の水準、会社の業績、職務内容などを総合的に勘案して決定する必要があります。過大な役員報酬については、その過大部分が経費として認められない場合があります。また、税務調査では役員報酬の決定過程や金額の妥当性について詳しく確認されることが多いため、取締役会議事録や株主総会議事録などの決定根拠資料を適切に保存しておくことが重要です。
福利厚生費:健康診断・慶弔費・飲み物代など
福利厚生費は、従業員の勤労意欲の向上や職場環境の改善を目的として事業主が負担する費用として、適切な範囲内であれば経費計上することができます。ただし、福利厚生費として認められるためには、全従業員を対象とした制度であることや、社会通念上相当な金額であることなどの条件があります。
健康診断費用については、労働安全衛生法に基づく定期健康診断や生活習慣病検診などの費用を福利厚生費として計上できます。従業員の健康管理は事業主の義務でもあるため、合理的な範囲内の健康診断費用は全額経費として認められます。人間ドックや特殊健康診断についても、業務上の必要性があれば経費計上可能です。ただし、従業員の家族分については原則として経費にならないため注意が必要です。
慶弔費については、従業員やその家族の結婚、出産、病気、死亡などに際して支給する祝金や見舞金を福利厚生費として計上できます。ただし、金額については社会通念上相当な範囲内である必要があり、過大な支給は給与として課税される可能性があります。一般的には、結婚祝い金1万円から5万円、出産祝い金5千円から3万円、香典1万円から5万円程度が相当額とされています。
飲み物代については、職場で従業員が飲用するお茶、コーヒー、ウーターサーバーの利用料などを福利厚生費として計上できます。これらは従業員の労働環境改善を目的とした支出として合理的に認められます。ただし、アルコール類については一般的に福利厚生費としては認められず、接待交際費として処理する必要があります。
社員旅行費用についても、一定の条件を満たせば福利厚生費として計上できます。参加者の過半数が参加していること、旅行期間が4泊5日以内であること、参加者一人当たりの費用が10万円程度以下であることなどが条件とされています。これらの条件を満たさない場合は、参加者への給与として課税される可能性があります。
法定福利費:社会保険料の事業主負担分
法定福利費は、法律で事業主の負担が義務付けられている社会保険料の事業主負担分として、確実に経費計上できる費用です。これらの負担は法的義務であるため、適切に計算・納付されていれば税務上問題となることはありません。
健康保険料の事業主負担分については、従業員の健康保険料の半額を事業主が負担する仕組みとなっています。健康保険料率は都道府県によって異なりますが、概ね給与の約5%程度を事業主が負担することになります。40歳以上65歳未満の従業員については、介護保険料も合わせて負担する必要があります。
厚生年金保険料の事業主負担分については、従業員の厚生年金保険料の半額を事業主が負担します。厚生年金保険料率は全国一律で、現在は給与の約9.15%を事業主が負担することになっています。厚生年金保険料は将来の年金給付の原資となるため、従業員の老後の生活保障としても重要な制度です。
雇用保険料の事業主負担分については、業種によって保険料率が異なります。一般の事業では給与の約0.6%、建設業では約0.8%、農林水産業では約0.7%を事業主が負担します。雇用保険は失業時の給付だけでなく、育児休業給付や高年齢雇用継続給付などの財源としても活用されています。
労災保険料については、全額を事業主が負担します。労災保険料率は業種によって大きく異なり、事務職中心の事業では給与の約0.25%、建設業では約0.6%から1.8%、製造業では約0.25%から8.8%程度となっています。労災保険は業務上の災害や通勤災害に対する補償制度であり、従業員の安全確保の観点からも重要な制度です。
8. 外注費・業務委託費

- デザイン・ライティングなどの外注
- コンサル・税理士などへの業務委託
デザイン・ライティングなどの外注
デザインやライティングなどのクリエイティブ業務を外部に委託する費用は、外注費として経費計上することができます。これらの業務は専門的な知識や技術が必要であり、自社で対応するよりも外部の専門家に委託することで、より高品質な成果物を効率的に得ることができるため、事業上の合理性が認められやすい支出です。
Webデザインの外注費については、ホームページのデザイン制作、ランディングページの制作、バナー広告のデザイン、ロゴデザイン、名刺やパンフレットなどの印刷物デザインなどが該当します。これらのデザイン制作費は、企業の顔となる重要な要素であり、事業の売上向上や企業イメージの構築に直接貢献するため、全額を外注費として経費計上できます。デザイン費用の相場は案件の規模や複雑さによって幅がありますが、ロゴデザインで3万円から30万円、ホームページデザインで10万円から200万円程度が一般的です。
ライティング業務の外注費については、Webサイトのコンテンツ制作、ブログ記事の執筆、商品説明文の作成、プレスリリースの作成、メルマガの原稿作成、SNS投稿用コンテンツの制作などが対象となります。これらのライティング費用は、SEO対策や顧客とのコミュニケーション向上を通じて事業の発展に寄与するため、外注費として適切に経費処理できます。ライティングの単価は文字数や専門性によって異なりますが、一般的なWeb記事で文字単価1円から10円程度、専門的な記事ではより高単価になることもあります。
コンサル・税理士などへの業務委託
コンサルティングや税理士などの専門家への業務委託費用は、事業の専門性向上や法的コンプライアンスの確保を目的とした支出として、外注費または支払手数料で経費計上することができます。これらの専門家サービスは、事業主だけでは対応が困難な高度な専門知識を要する業務を委託するものであり、事業の発展や適切な運営のために必要不可欠な支出として認められます。
税理士への報酬については、税務申告書の作成、記帳代行、税務コンサルティング、税務調査の立会い、節税対策の提案などが主な業務内容となります。税理士報酬は事業規模や業務内容によって異なりますが、個人事業主の場合で年間10万円から50万円程度、中小法人では年間30万円から200万円程度が一般的です。月次顧問契約の場合は月額1万円から10万円程度で、決算申告料は別途10万円から50万円程度が相場とされています。税理士報酬は支払手数料または外注費として経費計上し、源泉徴収が必要な場合は適切に処理する必要があります。
公認会計士への報酬については、財務諸表の監査、内部統制の構築支援、株式公開準備支援、企業価値評価、M&Aアドバイザリーなどが主な業務内容です。公認会計士の報酬は業務の専門性や責任の重さを反映して高額になることが多く、監査業務では年間数百万円から数千万円、アドバイザリー業務では案件の規模に応じて数十万円から数億円に及ぶ場合もあります。これらの報酬についても、事業の適切な運営や成長のために必要な支出として外注費または支払手数料で経費計上できます。
経営コンサルタントへの報酬については、経営戦略の立案、業務改善の支援、マーケティング戦略の策定、人事制度の構築、IT導入支援などが主な業務内容となります。コンサルティング料金は時間単価制、プロジェクト単価制、成果報酬制など様々な料金体系があり、コンサルタントの経験や専門分野によって大きく異なります。時間単価では1時間あたり1万円から10万円程度、プロジェクト単価では数十万円から数千万円まで幅広い価格帯があります。
9. 設備・維持・レンタル関連
- 修繕費:設備や事務所の修理・メンテナンス
- 賃貸料:車両・機器・ソフトウェアなどのリース費用
修繕費:設備や事務所の修理・メンテナンス
修繕費は、事業で使用する建物、設備、機械、車両などの維持管理や機能回復を目的とした支出として経費計上することができます。ただし、修繕費として認められるためには、既存の資産の原状回復や維持を目的とした支出であることが重要で、資産の価値を高めたり耐用年数を延長したりする支出については資本的支出として資産計上が必要になります。
建物の修繕費については、屋根の補修、外壁の塗装、雨漏りの修理、床の張り替え、壁紙の交換、給排水設備の修理、電気設備の修理、エアコンの修理などが該当します。これらの修繕は建物の機能を維持し、事業活動を継続するために必要な支出として修繕費で経費計上できます。ただし、建物の増築や大規模なリフォーム、設備の全面的な交換などは資本的支出として扱われ、減価償却の対象となります。
修繕費と資本的支出の区分は税務上重要なポイントです。一般的に、支出の金額が20万円未満の場合は修繕費として処理し、20万円以上の場合は修繕費と資本的支出の判定を行う必要があります。判定の基準としては、原状回復を目的とするか価値向上を目的とするか、通常の維持管理の範囲内か大幅な改良かなどが考慮されます。例えば、既存のエアコンの修理は修繕費ですが、より高性能なエアコンへの交換は資本的支出となる場合があります。
車両の修繕費については、定期点検費用、車検費用、オイル交換、タイヤ交換、ブレーキパッドの交換、バッテリー交換、事故による修理費用、板金・塗装費用などが対象となります。これらの費用は車両の安全性と機能を維持するために必要な支出として修繕費で経費計上できます。車検費用については、法定費用(自動車税、自賠責保険料、検査手数料)と整備費用が含まれますが、いずれも修繕費として処理できます。
賃貸料:車両・機器・ソフトウェアなどのリース費用
車両のリース料については、営業車、配送車、社用車などの事業用車両をリース契約で利用した場合の月額リース料が対象となります。オペレーティングリースの場合は月額リース料の全額を賃貸料として経費計上し、ファイナンスリースの場合はリース資産として資産計上してリース期間にわたって減価償却を行います。車両リースには車両本体のリース料だけでなく、メンテナンス付きリースの場合は整備費用も含まれており、これらも含めて賃貸料として処理できます。
機械設備のリース料については、製造機械、建設機械、医療機器、測定器、コンピュータなどをリース契約で利用した場合の費用が該当します。特に高額な機械設備については、購入ではなくリースを選択することで初期投資を抑え、最新の設備を利用できるメリットがあります。リース料には設備本体の利用料だけでなく、保守・点検費用が含まれている場合も多く、これらも含めて賃貸料として経費計上できます。
ソフトウェアのライセンス料については、業務用ソフトウェアの月額・年額ライセンス料、クラウドサービスの利用料、SaaS(Software as a Service)の料金などが対象となります。Microsoft Office、Adobe Creative Suite、会計ソフト、給与計算ソフト、顧客管理システム、プロジェクト管理ツールなど、事業運営に必要なソフトウェアのライセンス料は賃貸料として経費計上できます。これらのソフトウェアは継続的にアップデートされ、常に最新の機能を利用できるため、事業の効率化と競争力向上に寄与します。
10. 税金・保険などの行政関連費用
- 租税公課:個人事業税、印紙税、自動車税など
- 保険料:事業用保険(損害保険、火災保険など)
租税公課:個人事業税、印紙税、自動車税など
租税公課は、事業運営に関連して国や地方自治体に納付する税金や、法律に基づいて負担が義務付けられている公的な課金として、経費計上することができます。ただし、すべての税金が経費になるわけではなく、事業に直接関連する税金のみが租税公課として経費処理の対象となります。
個人事業税は、個人事業主が事業所得に対して都道府県に納付する税金として、租税公課で経費計上することができます。個人事業税は前年の事業所得に基づいて計算され、通常は8月と11月の2回に分けて納付します。税率は業種によって異なりますが、多くの業種で5%とされています。個人事業税は事業運営に直接関連する税金であるため、納付時に全額を租税公課として経費計上できます。ただし、所得税や住民税は個人の所得に対する税金であるため、経費として計上することはできません。
印紙税は、契約書や領収書などの文書に貼付する収入印紙の代金として、租税公課で経費計上することができます。事業に関連する契約書(売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書など)、領収書、手形、小切手などに貼付した印紙代は、文書作成に必要な費用として経費処理できます。印紙税額は文書の種類と記載金額によって決まり、例えば売買契約書では契約金額1万円以上100万円以下で200円、100万円超500万円以下で1,000円となっています。
自動車税および軽自動車税は、事業用車両に対して課税される税金として、租税公課で経費計上することができます。営業車、配送車、社用車などの事業専用車両については、自動車税の全額を経費として処理できます。一方、事業用と私用を兼用している車両については、使用実態に基づいて按分し、事業用分のみを経費計上する必要があります。按分の方法としては、走行距離による按分、使用日数による按分、使用時間による按分などが考えられます。
保険料:事業用保険(損害保険、火災保険など)
事業用保険の保険料は、事業運営に伴うリスクを軽減し、安定した事業継続を図るための必要な支出として、保険料勘定で経費計上することができます。事業に直接関連する保険であることが重要で、個人の生活に関わる保険については経費として認められません。
火災保険料は、事業用建物や事業用設備を火災から守るための保険として、最も基本的な事業用保険の一つです。事務所、店舗、工場、倉庫などの事業用建物および内部の設備、商品、原材料などを対象とした火災保険の保険料は、全額を経費として計上できます。自宅兼事務所の場合は、建物全体の火災保険料を事業用部分と居住用部分に按分し、事業用部分のみを経費計上します。按分の方法は地代家賃と同様に、面積按分や使用実態による按分を行います。
地震保険料についても、事業用資産を地震による損害から守るための保険として、保険料で経費計上できます。地震保険は通常、火災保険とセットで加入することが多く、事業用資産を対象としたものであれば経費として認められます。近年は大規模地震のリスクが高まっており、事業継続の観点から地震保険への加入は重要性を増しています。
損害保険料には様々な種類があり、事業に関連するものはすべて経費として計上できます。店舗総合保険、事務所総合保険、工場総合保険など、事業形態に応じた包括的な損害保険の保険料は全額経費となります。また、盗難保険、水災保険、風災保険など、特定のリスクに対する保険料についても、事業用資産を対象としたものであれば経費計上可能です。
自動車保険料は、事業用車両に関する保険として、自賠責保険料と任意保険料の両方が経費計上の対象となります。営業車、配送車、社用車などの事業専用車両については、保険料の全額を経費として処理できます。事業用と私用を兼用している車両については、使用実態に基づいて按分し、事業用分のみを経費計上します。自動車保険は車検時に支払う自賠責保険料と、民間保険会社に支払う任意保険料に分かれますが、いずれも事業用であれば経費として認められます。
11. その他よくある経費
- 書籍・新聞・セミナー受講費
- 事業用PC・ソフトウェア購入費
- 開業費(設立準備にかかった支出)
書籍・新聞・セミナー受講費
書籍代、新聞代、セミナー受講費は、事業に関連する知識やスキルの向上を目的とした支出として、研修費、図書費、新聞図書費などの勘定科目で経費計上することができます。これらの支出は事業の発展や競争力向上に寄与する投資的な性格を持っており、適切な範囲内であれば確実に経費として認められます。
事業関連書籍の購入費については、業務に直接関連する専門書、技術書、業界誌、実用書などが経費計上の対象となります。例えば、経理担当者が購入する会計や税務に関する書籍、営業担当者が購入するマーケティングや営業手法に関する書籍、技術者が購入する専門技術書やプログラミング関連書籍などが該当します。また、経営者が購入する経営戦略書、人事管理書、法律関連書籍なども、事業運営に必要な知識を得るための支出として経費計上できます。
電子書籍についても、紙の書籍と同様に経費計上が可能です。Kindle、楽天Kobo、Google Booksなどの電子書籍プラットフォームで購入した事業関連書籍は、購入時に図書費として経費処理できます。また、月額制の電子書籍読み放題サービスについても、事業に関連する書籍を主に利用している場合は、月額料金を経費として計上することができます。ただし、小説やエンターテイメント系の書籍が含まれる場合は、事業関連部分を合理的に按分する必要があります。
新聞購読料については、事業に関連する情報収集を目的とした新聞の購読料が経費計上の対象となります。一般紙(日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞など)、業界専門紙、地方紙などの購読料は、事業運営に必要な情報収集費として経費処理できます。デジタル版の新聞についても同様に経費計上可能で、スマートフォンやタブレットで閲覧する電子新聞の購読料も経費として認められます。
雑誌購読料についても、事業に関連する専門誌や業界誌であれば経費計上できます。業界の動向や技術情報を得るための専門雑誌、経営情報誌、マーケティング雑誌、IT関連雑誌などの購読料は、事業の競争力向上に必要な情報収集費として扱われます。月刊誌の年間購読料、週刊誌の定期購読料なども含まれます。
事業用PC・ソフトウェア購入費
事業用パソコンやソフトウェアの購入費は、現代の事業運営において必要不可欠な設備投資として、その金額や性質に応じて適切な勘定科目で経費計上することができます。金額によって一括経費処理か減価償却かが決まるため、購入時に適切な判断を行うことが重要です。
パソコン本体の購入費については、1台当たりの金額によって処理方法が異なります。10万円未満のパソコンについては消耗品費として一括経費処理が可能で、購入時に全額を経費計上できます。10万円以上30万円未満のパソコンについては、中小企業者等の少額減価償却資産の特例により、一括経費処理を選択することもできますが、通常は器具備品として資産計上し、法定耐用年数の4年にわたって減価償却を行います。30万円以上のパソコンについては、必ず器具備品として資産計上し、減価償却による費用処理が必要です。
ノートパソコンとデスクトップパソコンは、いずれも同じ扱いで処理されます。また、タブレット端末についても、事業用として使用するものであれば同様の処理が適用されます。iPad、Surface、Android タブレットなど、業務に使用するタブレット端末の購入費は、金額に応じて消耗品費または器具備品として計上します。
パソコンの周辺機器についても、本体と同様の基準で処理します。プリンター、スキャナー、外付けハードディスク、モニター、キーボード、マウスなどの周辺機器は、それぞれの購入価格に応じて消耗品費または器具備品として計上します。複数の機器を同時に購入した場合は、それぞれを個別に判定するのが原則ですが、一体として機能するシステムの場合は合計金額で判定することもあります。
ソフトウェアの購入費については、その性質と金額によって処理方法が決まります。10万円未満のソフトウェアについては消耗品費として一括経費処理が可能です。Microsoft Office、Adobe Creative Suite、会計ソフト、給与計算ソフトなど、一般的な業務ソフトの多くがこの範囲に該当します。10万円以上のソフトウェアについては、無形固定資産として資産計上し、法定耐用年数の5年にわたって減価償却を行います。
クラウドソフトウェアやSaaSの利用料については、継続的に発生する費用として支払時に経費計上するのが一般的です。Microsoft365、Adobe Creative Cloud、Salesforce、kintoneなどのクラウドサービスの月額・年額利用料は、賃貸料またはソフトウェア費として経費処理します。これらのサービスは所有権を取得するのではなく利用権を得るものであるため、減価償却の対象にはなりません。
開業費(設立準備にかかった支出)
開業費は、事業を開始するまでに支出した準備費用として、繰延資産に計上し、事業開始後に償却を通じて経費化することができます。開業費は個人事業主と法人の両方に適用される概念ですが、その範囲や償却方法については一定のルールがあります。
開業費として計上できる支出の範囲については、事業開始前に発生した事業準備のための費用が対象となります。具体的には、事業計画の作成費用、市場調査費用、事業用物件の下見費用、開業前の広告宣伝費、開業前の人材募集費用、開業準備のための交通費、事業に関する情報収集費用などが該当します。また、事業開始前に購入した消耗品、事務用品、事業関連書籍なども開業費に含めることができます。
事業用資産の購入費については、開業費と固定資産の区分を適切に行う必要があります。パソコン、机、椅子、事務機器などの固定資産については、開業前に購入したものであっても固定資産として計上し、減価償却を行います。一方、10万円未満の消耗品や事務用品については、開業費に含めて処理することができます。
開業前の家賃については、事業開始前に支払った事務所や店舗の家賃を開業費として計上できます。ただし、事業開始日を明確に定めることが重要で、事業開始日以降の家賃は通常の地代家賃として経費処理します。敷金については、将来返還される性質のものであるため開業費には含めず、別途資産として計上します。
開業前の人件費については、開業準備のために雇用した従業員への給与や、開業準備を手伝ってもらった人への謝礼などを開業費として計上できます。ただし、事業開始後の人件費は通常の給料賃金として処理し、開業費には含めません
これって経費で落とせる?注意が必要な支出とは

事業に関係ない支出や、プライベートと混同しやすい支出は経費にできません。以下のようなケースは注意が必要です。
家族との飲食・旅行代
家族との食事代や旅行費用は、たとえその場で仕事の話題が出たり、事業に関する相談をしたりしても、基本的には私的支出として扱われ、経費として計上することはできません。税務上では、支出の主たる目的が何であるかが重要な判断基準となり、家族との時間を過ごすことが主目的である場合は、事業関連性が認められません。
家族経営の事業であっても、家族が従業員として正式に雇用されていない限り、家族との食事を接待交際費として計上することは困難です。例外的に、家族が事業の重要な協力者として明確に位置づけられ、その食事が純粋に事業上の打ち合わせを目的としている場合は経費として認められる可能性もありますが、その立証は非常に困難で、税務調査では厳しくチェックされる項目の一つです。
家族旅行についても同様で、たとえ出張先で家族と合流したり、視察を兼ねた旅行であったりしても、家族の旅行費用を経費として計上することは原則として認められません。事業主本人の出張費用については適切に計上できますが、家族分については私的支出として除外する必要があります。また、家族を同伴する必要性について合理的な説明ができない場合は、事業主本人の費用についても疑義を持たれる可能性があります。
プライベート兼用のスーツや腕時計
スーツや腕時計、靴、バッグなどの身の回り品については、業務で使用していても「誰でも使える物」として、経費計上が認められにくい支出の代表例です。これらの品目は、業務時間外でも私的に使用できるものであり、事業専用品としての性格が薄いためです。
スーツについては、一般的なビジネススーツは私服としても着用可能であるため、経費として認められません。ただし、特定の業種で着用が義務付けられている制服や作業服については、事業専用品として経費計上が可能です。例えば、警備員の制服、調理師の白衣、建設作業員の作業服、医療従事者の白衣などは、明らかに業務専用であり、私的に使用することがないため、福利厚生費または消耗品費として経費計上できます。
腕時計についても、一般的な腕時計は私的にも使用できるため経費として認められませんが、業務上特別な機能が必要な専用機器については経費計上の可能性があります。例えば、ダイビングインストラクターの防水時計、パイロットの航空時計、医療従事者のナースウォッチなど、特定の業務に特化した機器であれば、器具備品として経費計上が認められる場合があります。
靴やバッグについても同様の考え方が適用されます。一般的な革靴やビジネスバッグは私的にも使用できるため経費になりませんが、安全靴、長靴、専用工具を入れる工具バッグなど、明らかに業務専用のものについては経費として認められます。
スマホやタブレット、PC
スマートフォン、タブレット、パソコンなどのIT機器は、現代のビジネスにおいて必要不可欠なツールですが、同時にプライベートでも使用されることが多いため、経費計上の際には慎重な判断が必要です。
事業専用として購入・使用している機器については、全額を経費として計上できます。例えば、事業用の専用電話番号で契約したスマートフォン、事務所でのみ使用するデスクトップパソコン、営業活動専用のタブレットなどは、明らかに事業用途であるため経費として認められます。
一方、個人のスマートフォンを事業にも使用している場合や、自宅兼事務所で使用するパソコンなどは、事業用と私用の按分が必要になります。按分の方法としては、使用時間による按分、通話時間による按分、データ使用量による按分などが考えられますが、その根拠を客観的に示すことが重要です。
スマートフォンの場合、通話明細やデータ使用履歴を分析し、事業関連の使用割合を算出する方法が一般的です。例えば、月の通話時間100分のうち70分が取引先との通話であれば、70%を事業用として按分することができます。ただし、この按分率を継続的に適用し、その根拠となる資料を保存しておくことが必要です。
ネットフリックスやAmazonプライムなどのサブスク利用費
動画配信サービス、音楽配信サービス、雑誌読み放題サービスなどのサブスクリプション利用料は、基本的には娯楽・エンターテイメント目的の支出として私的支出と判断されることが多く、経費計上には注意が必要です。
ただし、業種や使用目的によっては経費として認められる場合もあります。例えば、動画制作業者がNetflixやAmazonプライムビデオで競合作品の研究を行う場合、広告代理店がマーケティングの参考資料として各種コンテンツを視聴する場合、美容院や歯科医院の待合室で顧客サービスとして動画配信サービスを提供する場合などは、事業目的としての合理性が認められる可能性があります。
音楽配信サービスについても、飲食店やアパレル店舗でのBGM提供、ダンススクールでのレッスン用音楽利用、イベント企画会社での楽曲選定などの目的であれば、事業用途として経費計上できる場合があります。
重要なのは、そのサービスがなぜ事業に必要なのか、どのように事業に活用しているのかを明確に説明できることです。単に「情報収集のため」といった曖昧な理由では経費として認められない可能性が高く、具体的な業務への活用方法を示すことが求められます。
自宅の住宅ローン全額や家賃全額
自宅兼事務所として使用している場合でも、住宅ローンの全額や家賃の全額を経費として計上することはできません。居住部分と事業部分を合理的な基準で按分し、事業用部分のみを経費計上する必要があります。
住宅ローンについては、元本部分は経費になりませんが、利息部分については事業用部分を按分して経費計上することができます。例えば、自宅の総面積100平方メートルのうち20平方メートルを事務所として使用している場合、住宅ローンの利息の20%を地代家賃として経費計上できます。
家賃についても同様で、事業用部分の割合に応じて按分した金額のみを経費として計上します。按分の方法としては、面積按分が最も客観的で説明しやすい方法ですが、使用時間による按分や、併用按分(面積按分と時間按分の組み合わせ)を採用することも可能です。
重要なのは、一度決定した按分基準を継続的に適用することです。按分率を頻繁に変更することは恣意的な処理と判断される可能性があるため、合理的な基準を設定した後は継続して適用する必要があります。
個人の健康・美容目的の支出
ジム代、整体代、マッサージ代、エステ代などの健康・美容関連の支出は、基本的には個人的な支出として扱われ、経費として計上することはできません。これらの支出は個人の健康維持や美容向上を目的とするものであり、事業との直接的な関連性が認められないためです。
ただし、特定の業種においては例外的に経費として認められる場合があります。例えば、モデルやタレントのエステ代、プロスポーツ選手のトレーニングジム代、ダンサーの整体代などは、職業上の必要性が認められる場合があります。また、従業員の福利厚生として事業主が負担するジム代や健康診断費用については、一定の条件下で福利厚生費として経費計上が可能です。
美容師や理容師が自分の技術向上のために受ける施術代、エステティシャンが新しい技術を学ぶための研修としてのエステ代なども、業務上の必要性が明確であれば研修費として経費計上できる可能性があります。
重要なのは、その支出が純粋に事業上の必要性に基づくものであることを客観的に証明できることです。個人的な健康維持や美容向上が主目的であると判断される場合は、経費として認められない可能性が高くなります。
取引先との関係が不明な高額な贈答品
接待交際費として贈答品を経費計上する場合でも、社会通念上相当な範囲を超える高額な贈り物や、取引先との関係が不明確な相手への贈答品については、税務調査で問題となる可能性があります。
贈答品の金額については、贈る相手との関係性、取引の規模、業界の慣習などを総合的に考慮して、適切な水準であることが求められます。一般的には、一件当たり数千円から数万円程度の範囲内であれば妥当とされることが多いですが、明らかに高額すぎる贈答品は事業関連性を疑われる可能性があります。
贈答品の相手についても、取引先との関係を明確に説明できることが重要です。どのような取引関係にあるのか、なぜその贈答品が必要だったのか、今後の取引にどのような効果が期待されるのかなどを具体的に説明できるよう、記録を残しておく必要があります。
また、贈答品の内容についても適切性が求められます。事業に関連しない個人的な趣味の品物や、明らかに私的利用を想定した品物については、事業上の贈答品としての合理性が疑われる可能性があります。
所得税・住民税などの個人税
税金の中でも、個人の所得に対して課税される所得税や住民税、個人の財産に対して課税される相続税や贈与税などは、事業の経費として計上することはできません。これらの税金は個人の担税力に応じて課税されるものであり、事業運営とは直接的な関連性がないためです。
経費にするためのルール|確定申告に備えるには?

- 領収書・レシートの保存
- クラウド会計ソフトの活用
- 確定申告書の記載科目例
領収書・レシートの保存
経費として支出を計上するための最も基本的で重要な要件は、その支出を証明する領収書やレシートを適切に保存することです。税務上、経費として認められるためには支払いの事実を客観的に証明できる書類が必要であり、これらの証拠書類なしに経費計上を行うことはできません。
領収書の保存については、法定保存期間である7年間にわたって確実に保管する必要があります。この保存期間は、確定申告書の提出期限の翌日から起算されるため、実質的には7年以上の保存が必要になる場合もあります。保存期間中は、税務署からの求めがあればいつでも提示できる状態で保管しておかなければなりません。
領収書に記載されるべき必要事項については、日付、支払先の名称、支払金額、支払内容が明記されていることが重要です。手書きの領収書の場合は、これらの項目がすべて記入されていることを確認し、印鑑やサインがあることも望ましいとされています。レシートについても同様で、店舗名、日時、購入商品、金額が印字されていれば、領収書と同等の証拠能力を持ちます。
電子レシートやオンライン決済の明細については、紙の領収書と同等の取り扱いが可能ですが、電子帳簿保存法に定められた要件を満たす必要があります。具体的には、電子データのまま保存する場合は、改ざん防止措置、日付・金額での検索機能、ディスプレイ・プリンタでの出力機能などが求められます。これらの要件を満たさない場合は、電子データを印刷して紙で保存することも可能です。
領収書が発行されない支出については、出金伝票を作成して支払いの記録を残す必要があります。電車やバスの運賃、自動販売機での購入、冠婚葬祭の香典や祝儀などが該当します。出金伝票には、支払日、支払先、支払金額、支払内容、支払目的を明記し、可能であれば関連する資料(電車の切符、結婚式の招待状、通夜の案内状など)も一緒に保存しておくことが重要です。
クラウド会計ソフトの活用
現代の事業運営において、クラウド会計ソフトの活用は経費管理の効率化と正確性の向上に大きく貢献します。従来の手作業による帳簿作成と比較して、自動化機能や連携機能を活用することで、大幅な時間短縮と入力ミスの削減が可能になります。
主要なクラウド会計ソフトには、freee、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計オンライン、やよいの青色申告オンラインなどがあり、それぞれに特色と機能の違いがあります。これらのソフトは月額数百円から数千円の料金で利用でき、従来の会計ソフトのライセンス購入と比較して初期投資を大幅に抑えることができます。
銀行口座との連携機能は、クラウド会計ソフトの最も重要な機能の一つです。事業用の銀行口座を会計ソフトと連携させることで、入出金のデータが自動的に取り込まれ、勘定科目の提案や仕訳の自動生成が行われます。初期設定時に学習機能を活用して勘定科目を正しく設定しておけば、継続的に精度の高い自動仕訳が可能になります。
クレジットカードとの連携機能も、経費管理の効率化に大きく貢献します。事業用のクレジットカードを会計ソフトと連携させることで、カードでの支払いが自動的に記録され、領収書との照合も容易になります。特にオンラインでの支払いが多い事業では、この機能により大幅な作業時間の短縮が可能です。
レシート撮影機能は、紙の領収書やレシートをスマートフォンで撮影することで、自動的に金額や日付を読み取り、仕訳データとして登録する機能です。OCR(光学文字認識)技術の向上により、読み取り精度も大幅に改善されており、外出先でもその場で経費処理を行うことができます。ただし、読み取り結果については必ず確認し、必要に応じて修正を行うことが重要です。
電子帳簿保存法への対応も、クラウド会計ソフトの重要な機能の一つです。2022年の法改正により、電子取引データの電子保存が義務化されたため、メールで受信した請求書やオンラインでダウンロードした領収書などは、法律の要件を満たした方法で保存する必要があります。主要なクラウド会計ソフトはこれらの要件に対応しており、適切な設定を行うことで法令遵守が可能になります。
確定申告書の作成機能は、日々の仕訳データを基に自動的に確定申告書を作成する機能です。所得税の確定申告書だけでなく、青色申告決算書、収支内訳書、消費税申告書なども対応しており、手作業での転記ミスを防ぐことができます。また、電子申告(e-Tax)にも対応しており、申告書の提出まで一貫してオンラインで完結することが可能です。
確定申告書の記載科目例
それぞれの費用をどの勘定科目に入れれば良いのか、以下であらためて例をご紹介します。
売上原価
売上原価については、商品を仕入れて販売する事業の場合に記載する項目で、期首商品棚卸高、当期商品仕入高、期末商品棚卸高から計算されます。製造業の場合は、原材料費、労務費、経費を含む製造原価が該当します。サービス業の場合は、直接的にサービス提供に関わる費用のみが売上原価となり、一般的な事務費用は販売費及び一般管理費として計上します。
給料賃金
給料賃金については、従業員に支払った給与、賞与、退職金などを記載します。この項目には、事業主本人や事業主の家族に支払った給与は含まれません。個人事業主の場合、事業主への給与は経費として認められないため、青色事業専従者給与として別途記載するか、または経費として計上しません。
外注工賃
外注工賃については、外部の業者や個人に業務を委託した際の報酬を記載します。デザイン料、システム開発費、翻訳料、清掃費、警備費などが該当します。ただし、実質的に雇用関係にある場合は給料賃金として処理する必要があり、契約の実態に応じた適切な判断が求められます。
減価償却費
減価償却費については、建物、機械、器具備品、車両運搬具、ソフトウェアなどの固定資産を減価償却した金額を記載します。減価償却の方法は定額法が原則ですが、一部の資産については定率法を選択することも可能です。少額減価償却資産の特例を適用した場合も、この項目に含めて記載します。
地代家賃
地代家賃については、事務所や店舗の家賃、駐車場代、土地の借地料などを記載します。自宅兼事務所の場合は、事業用部分のみを按分して記載し、按分の根拠を明確にしておくことが重要です。敷金や保証金は原則として資産計上し、返還されない部分のみを地代家賃または長期前払費用として処理します。
旅費交通費
旅費交通費については、出張旅費、電車代、バス代、タクシー代、航空券代、宿泊費などを記載します。通勤費は原則として経費になりませんが、事業所と自宅以外の場所への移動費用は旅費交通費として計上できます。
通信費
通信費については、電話代、インターネット料金、郵便料金、宅配便代などを記載します。個人の携帯電話を事業にも使用している場合は、事業用部分を按分して記載します。
広告宣伝費
広告宣伝費については、新聞や雑誌への広告掲載料、チラシの制作・配布費用、看板の制作費、Web広告費などを記載します。継続的に発生する宣伝費用だけでなく、一時的な販売促進費用も含まれます。
接待交際費
接待交際費については、取引先との飲食費、贈答品代、ゴルフ接待費などを記載します。個人事業主の場合は金額的な制限はありませんが、事業との関連性と金額の妥当性が重要な判断基準となります。
消耗品費
消耗品費については、文房具、事務用品、10万円未満の器具備品などを記載します。パソコンやソフトウェアについても、10万円未満であれば消耗品費として一括経費処理が可能です。
経費で落ちるものと落ちないものを把握しましょう

以上、経費で落ちるものについてご紹介しました。ぜひ、勘定科目などについて理解し、あなたの事業の経理処理に活用してください。
経費の使い方次第で、会社の利益は大きく変わります。
無料の 「経費チェックリスト」 では、23の経費科目ごとに「削減ポイント」と「節税の工夫」を整理。明日から実務で使えるヒントをまとめました。こちらもあわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)