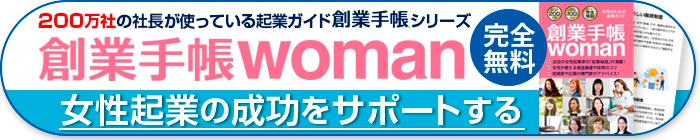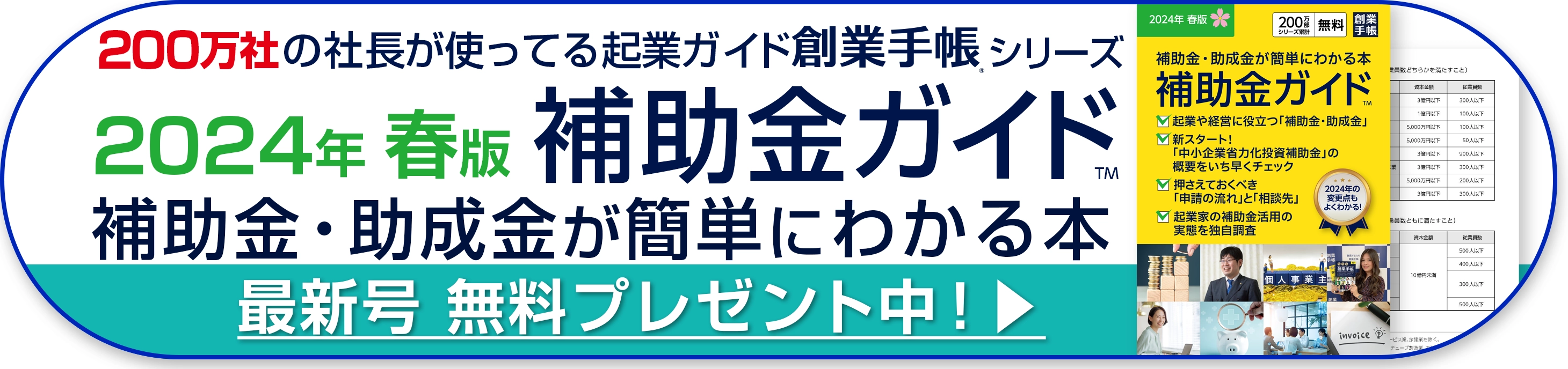【2026年最新】主婦におすすめの起業ランキング!成功事例と始め方を徹底解説
主婦の起業におすすめの業種は何?主婦起業ならではのメリットや補助金・助成金などまとめてご紹介

昨今、主婦の方でも起業を目指す方が少なくありません。しかし、「主婦という立場で起業することは難しいのではないか」とお考えの方もいるでしょう。実はそんなことはありません。主婦だからこその目線やメリットなどをフル活用することで、主婦起業を成功させている女性起業家もたくさんいます。
本記事では、これから起業したいとお考えの主婦の方向けにおすすめの業種ランキングと、女性の起業を支援してくれる各種制度などをまとめてご紹介します。
創業手帳では、起業を考えている女性の方むけに「創業手帳Woman」を発行しています。女性ならではの仕事と家庭との両立など、多くの女性起業家にインタビューを行い聞いていますので、ぜひあわせてお読みください。無料でお取り寄せ可能です。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
- 主婦の起業におすすめの業種は何?主婦起業ならではのメリットや補助金・助成金などまとめてご紹介
- 主婦の起業が注目されている理由とメリット
- 【2026年版】主婦におすすめの起業ランキングTOP10
- 成功している主婦起業家に共通する特徴
- 主婦起業家が直面する課題と解決策
- 主婦起業を応援してくれる制度・支援まとめ
- まとめ:あなたの強みを活かした主婦起業を始めよう
主婦の起業が注目されている理由とメリット

主婦の起業が注目されている理由とメリットをご紹介します。
なぜ今、主婦の起業が注目されているのか
なぜ今、主婦の起業が注目されているのでしょうか。以下で主な3つの理由をご紹介します。
働き方の多様化とデジタル化の進展
デジタル技術の進化により、場所や時間に縛られない働き方が可能になりました。特にコロナ禍を経て、リモートワークやオンラインビジネスの普及が加速し、自宅をベースにした起業のハードルが大幅に下がっています。SNSやECサイトなどのプラットフォームを活用すれば、初期投資を抑えながらも広い顧客層にアプローチできるようになりました。
家事・育児と両立できる柔軟な働き方の実現
従来の雇用形態では、時間的制約の厳しい家事や育児との両立が難しい面がありましたが、自分で事業を営むことで、家庭の状況に合わせた柔軟なスケジュール調整が可能になります。子どもの行事や急な体調不良にも対応しやすく、家族との時間を大切にしながら働けることが大きな魅力となっています。
自分の得意を活かせる仕事への期待
主婦の方々は料理、手芸、子育て、整理収納など、日常生活で培ったスキルや知識を持っています。これらを活かしたサービスや商品の提供は、同じような課題を持つ他の家庭にとって高い価値を持ちます。また、自分の関心や情熱を仕事にできることで、経済的なメリットだけでなく、自己実現や社会とのつながりといった精神的な充足感も得られます。
このように、テクノロジーの発展による起業障壁の低下、ワークライフバランスの実現、そして自分らしい働き方への希求が相まって、主婦の起業は今後もさらに注目され続けるでしょう。
主婦起業の4つのメリット

主婦起業の4つのメリットをご紹介します。
1.時間の自由度が高い
主婦の起業における「時間の自由度が高い」というメリットは、家庭生活との調和を実現する重要な特徴です。
会社勤めとは異なり、子どもの学校行事や家族の食事時間に合わせて仕事のスケジュールを自分で決められます。朝の家事が終わった後や子どもの昼寝中など、日常生活の合間を活用して効率的に業務を進められるのも大きな利点です。
2.家庭と仕事のバランスがとりやすい
主婦が起業するメリットとして、家庭と仕事のバランスがとりやすい点は特に重要です。自分自身が事業のオーナーであることで、家庭の状況に応じた柔軟な働き方が可能になります。例えば、子どもの学校行事や家族の予定を優先してスケジュールを組み立てることができるため、大切な家族の時間を犠牲にする必要がありません。
また、在宅で仕事ができる起業形態を選べば、通勤時間がなくなり、その時間を家事や育児に充てられます。家族の食事の準備や洗濯などの家事を仕事の合間に少しずつこなすことも可能で、一日の中で家庭と仕事の両方に適切な時間配分ができます。
急な家庭の事情、例えば子どもの体調不良や学校からの呼び出しなどにも、会社勤めよりも対応しやすいのも大きな利点です。その時々の家庭の状況に合わせて仕事量を調整できるため、家族の必要に応じて時間やエネルギーの配分を変えることができます。
3.自分の強みや経験を活かせる
主婦が起業するメリットとして、自分の強みや経験を活かせる点は非常に重要です。主婦の方々は日常生活の中で培った様々なスキルや知識を持っており、これらは貴重なビジネス資源となります。
家事や育児の経験から得た知識は、同じような課題を持つ他の家庭にとって大きな価値があります。例えば、効率的な家事の方法、子育てのコツ、家計管理のノウハウなどは、多くの人が求めるサービスや商品に発展させることができます。料理が得意な方はケータリングサービスや料理教室、整理収納が得意な方は片付けコンサルタント、手芸が好きな方はハンドメイド商品の販売など、自分の「好き」や「得意」を仕事にすることが可能です。
さらに、主婦として直面した課題から生まれたアイデアは、同じ課題を持つ顧客のニーズに直結します。「こんなサービスがあったら助かるのに」という自身の経験から生まれたビジネスは、リアルな問題解決につながり、市場での競争力を持ちやすいのです。
4.小資本から始められる選択肢が多い
主婦が起業する際の重要なメリットとして、小資本から始められる選択肢が多い点が挙げられます。これは特に家計を守りながら事業を立ち上げたい主婦にとって大きな魅力です。
デジタルテクノロジーの発展により、実店舗を持たないオンラインビジネスが普及しています。SNSやフリマアプリ、ECサイトなどを活用すれば、初期投資を最小限に抑えながらも広い顧客層にアクセスできます。例えば手作り雑貨や焼き菓子の販売、ウェブデザインやライティングなどのサービス提供は、自宅の設備と少額の材料費や道具代だけで始められることが多いです。
また、家にあるものを活用したビジネスも有効です。自宅の一室を使ったサロンやカルチャー教室、料理教室などは、大きな設備投資なしに始められます。育児や家事で培ったスキルを活かしたコンサルティングやコーチングサービスも、特別な設備を必要とせず、知識と経験を直接商品化できる形態です。
スモールスタートの利点は資金面だけではありません。リスクを抑えながら市場の反応を見られること、家庭との両立を図りながら徐々に事業規模を拡大できること、そして何より失敗しても家計への影響を最小限に留められることが大きな安心感につながります。
【2026年版】主婦におすすめの起業ランキングTOP10

主婦におすすめの起業ランキングをご紹介します。
1. ハンドメイド作家(平均月収:5〜30万円)
ハンドメイド作家は主婦の方が起業する際に特におすすめできる選択肢です。手芸やクラフトなどの創作活動は、家庭生活と無理なく両立でき、少額の初期投資で始められるからです。また、子育てや家事の合間に自分のペースで制作できるため、時間の融通が利きやすいという大きなメリットがあります。
始め方と必要資金
ハンドメイド作家としての起業は比較的低コストで始められます。
材料費は作品のジャンルによって異なりますが、アクセサリー制作なら5,000〜2万円程度、布小物なら1〜3万円程度から始められることが多いです。道具類も最初は基本的なものだけで構いません。写真撮影用のスマートフォンや簡易的な撮影ボックス(自作可能)があると作品の魅力を伝えやすくなります。
まずは自分が得意で楽しめるジャンルから始めるのがおすすめです。初期投資を抑えるため、家にある材料や道具を活用したり、少量ずつ材料を購入して試作を重ねながら商品ラインナップを考えていくとよいでしょう。
販売チャネルの選び方
ハンドメイド作品の販売チャネルは多様化しており、自分の作風や目標に合わせて選択することができます。minneやCreema、BASEといったハンドメイド専門のオンラインマーケットプレイスは、専門知識がなくても簡単に出店でき、ハンドメイド作品を求める顧客層に直接アプローチできる魅力があります。手数料は発生するものの、決済システムや配送管理などのインフラが整っているため、初心者でも安心して始められるでしょう。
また、InstagramやTwitterなどのSNSを活用した販売方法も人気です。これらのプラットフォームでは作品そのものの魅力に加え、制作過程や作家としての人柄も発信できるため、ファンを獲得しやすいという特徴があります。多くの場合、ダイレクトメッセージやプロフィール欄に記載したECサイトへのリンクから注文を受け付ける形式が採られています。
そして、地域のイベントやハンドメイドマーケットへの出店も有効な販路です。直接顧客と対話しながら商品を販売できる貴重な機会となり、出店料は一日あたり5,000円から1万円程度が相場ですが、その場で顧客の生の反応を見られるという点で非常に価値のある経験となります。
2. オンラインショップ運営(平均月収:10〜50万円)
オンラインショップ運営は主婦の方が起業する際に特におすすめできる選択肢です。最大の魅力は、実店舗と異なり場所や時間に縛られない点にあります。子育てや家事の合間にも商品登録や発送作業を行うことができ、家庭生活との両立がしやすいという大きなメリットがあります。
始め方と必要資金
オンラインショップを始める際の必要資金は、実店舗と比較すると格段に少ないことが特徴です。基本的な初期費用としては、ECサイト構築費用(無料〜月額数千円程度のものが多い)、仕入れ資金(最初は小ロットから始めて10〜30万円程度)、撮影機材(スマートフォンでも可能、周辺機材含め0〜5万円程度)、そして梱包材や事務用品(数千円〜)などが挙げられます。
まず販売したい商品のジャンルを決め、自分の関心や強みが活かせる分野を選ぶとよいでしょう。次に商品の調達方法を検討します。卸売業者からの仕入れ、メーカーとの直接取引、ハンドメイド商品の場合は自作、ドロップシッピングなど様々な方法があります。初期投資を抑えるなら、最初は少量仕入れや在庫を持たないドロップシッピングから始めるのも一つの方法です。
ECサイトの構築方法も重要です。BASEやShopifyなどのECプラットフォームを利用すれば、専門知識がなくても比較的簡単にオンラインショップを開設できます。スキルや資金に余裕があれば、独自ドメインでのサイト構築も検討できるでしょう。
商品選定のコツと在庫管理
主婦がオンラインショップを運営する際の商品選定と在庫管理のコツをお伝えします。
商品選定では、まず自分の知識や経験を活かせる分野から始めましょう。子育て経験があれば育児グッズ、料理が得意なら調理器具など、説得力のある商品紹介ができます。競合調査も大切で、類似店舗が扱っていない隙間的な商品を見つけることで差別化できます。初めは少数の商品に絞り、反応を見ながら徐々に拡大するのが安全です。
在庫管理では、家庭のスペースを考慮した商品選びが重要です。自宅で無理なく保管できるサイズの商品を選び、最小限の在庫から始めましょう。売れ行きを確認しながら追加発注する方が在庫リスクを減らせます。エクセルなどで入荷日・数量を記録し、定期的に実在庫と照合する習慣をつけることが大切です。
子どもの長期休暇など家庭が忙しくなる時期を予測し、その前に在庫を整えておく先手管理も効果的です。資金とスペースに余裕がない場合は、ドロップシッピングや受注生産方式の採用も検討できます。
3. Webライター・ブロガー(平均月収:8〜40万円)

Webライターやブロガーという職業は、主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の魅力は、場所や時間に縛られず完全に自宅で働けるという点にあります。子どもの寝ている時間や家事の合間など、自分のペースで仕事ができるため、家庭との両立がしやすいのです。
始め方と必要資金
Webライター・ブロガーとして起業する際の必要資金は比較的少額です。基本的な初期費用としては、パソコン(持っていれば流用可能、新規購入なら5〜10万円程度)、インターネット環境(月額4,000〜6,000円程度)、そして自分のブログを立ち上げる場合はドメイン・サーバー代(年間1〜2万円程度)などが挙げられます。ワードプレスなどのブログシステムは無料で利用できるものが多いため、総じて初期投資は10万円以下から始めることも可能です。
まずは自分が書きたいジャンルや得意分野を明確にし、それに関する基礎知識や情報をまとめておくとよいでしょう。Webライターとして活動する場合は、クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークスなど)に登録し、小さな案件から経験を積んでいくのが一般的です。一方、ブロガーとして収益化を目指す場合は、ワードプレスなどでブログを立ち上げ、継続的に記事を投稿していきます。
どちらの道を選ぶにせよ、最初はポートフォリオ作りが重要です。無料ブログサービスを利用して自分の記事サンプルを作ったり、クラウドソーシングの小規模案件でライティングスキルを磨いたりすることから始めると良いでしょう。
案件の取り方と継続のコツ
Webライターとして案件を獲得するには、いくつかの方法があります。まずクラウドソーシングサイトの活用が最も手軽です。初めは単価が低い案件でも積極的に応募し、実績とレビューを積み重ねていくことが大切です。次に、SNSやブログでの情報発信を通じて自分をアピールする方法も効果的です。特定の分野に関する情報を発信し続けることで、専門性をアピールできます。
継続して案件を得るコツは、納期を守る、丁寧なコミュニケーションを心がける、指示通りの品質で納品するなど、基本的な信頼関係の構築にあります。一度信頼を得られれば、リピート案件や単価アップにつながりやすくなります。
ブロガーとして収益化を目指す場合は、特定のテーマに絞った質の高い記事を継続的に投稿することが鍵です。アクセス数を増やすためのSEO対策やSNSでの情報拡散も重要になります。収益源としては、アドセンス広告、アフィリエイト、企業タイアップなど複数の方法を組み合わせるのが一般的です。
最後に、常にスキルアップを意識することが大切です。SEO知識やライティング技術の向上、トレンドの把握など、継続的な学習を通じて自分の市場価値を高めていくことが、長く安定して稼ぐための秘訣です。
4. 料理教室・お菓子教室(平均月収:10〜35万円)
料理教室やお菓子教室は主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の魅力は、日常的に培ってきた料理やお菓子作りのスキルを直接ビジネスに活かせる点にあります。家事として当たり前に行ってきた作業が、そのまま収入源になるという点は大きな強みです。
始め方と必要資金
料理教室やお菓子教室を始める際の必要資金は、どの規模で始めるかによって大きく異なります。自宅キッチンを活用する最小規模の場合、追加投資は調理器具の補充や材料費、少人数用の作業台などで10〜30万円程度から始められることもあります。一方、専用スペースをレンタルや購入する場合は、内装工事費や設備投資などで100万円以上の資金が必要になることも少なくありません。
まずは自分の得意な料理やお菓子のジャンルを明確にし、そこに特化したカリキュラムを作成することが大切です。例えば、時短家庭料理、子ども向けクッキング、グルテンフリーのお菓子など、特定のニーズに応えるレッスン内容を考えると差別化しやすくなります。
開業前に必要な準備としては、レシピの整理と標準化、テキスト作成、食品衛生責任者などの資格取得(自宅開業の場合は必須ではない場合もあります)、そして保険加入の検討などがあります。特に食品を扱うビジネスでは、安全面への配慮が非常に重要です。
集客方法と口コミを広げるコツ
料理教室やお菓子教室の集客には、いくつかの効果的な方法があります。まずはSNSの活用が基本です。InstagramやFacebookなどで料理やお菓子の写真、レッスンの様子などを定期的に発信することで、興味を持ってもらいやすくなります。見た目の美しい完成品だけでなく、作る過程や失敗談なども共有すると親近感が生まれます。
また、地域のコミュニティ活動への参加も重要です。地域の催しでの出店や試食会の開催、町内会や子育てサークルでのミニ講座など、実際に自分の料理やお菓子を味わってもらう機会を積極的に作りましょう。実際の味と人柄を知ってもらうことが、最も強力な集客につながります。
口コミを広げるコツとしては、レッスン内容の充実はもちろん、参加者が「誰かに話したくなる」要素を盛り込むことが大切です。例えば、写真映えするレシピ、珍しい調理法や材料の紹介、持ち帰り用のラッピング指導など、付加価値のあるサービスを提供すると良いでしょう。
生徒さんとのコミュニケーションも大切です。レッスン後のフォローアップメールや、SNSでの質問対応、季節ごとのお便りなど、継続的な関係構築を心がけることで、長期的なファンを増やすことができます。
また、地域の特性や参加者のニーズに合わせた柔軟なレッスン設計も重要です。例えば、平日昼間は主婦向け、週末は家族参加型、夜間は仕事帰りのOL向けなど、様々な層に対応できるメニュー構成を考えると良いでしょう。
料理教室やお菓子教室は、自分の情熱とスキルを直接伝えられるビジネスです。技術だけでなく、楽しさや温かさを伝えることができれば、自然と口コミが広がり、持続的な事業になっていくでしょう。
5. 整理収納アドバイザー(平均月収:15〜40万円)
整理収納アドバイザーは主婦の方が起業する際に特におすすめできる職業です。その最大の魅力は、日常的に行ってきた家事スキルを直接ビジネスに活かせる点にあります。主婦として培った住空間の整理や家族の暮らしを快適にするノウハウは、そのまま専門性として評価されるのです。
始め方と資格取得
整理収納アドバイザーとして活動を始めるには、特別な資格は法的には必須ではありませんが、信頼性を高めるために取得しておくと良いでしょう。代表的なものとして、NPO法人 ハウスキーピング協会が提供する「整理収納アドバイザー」資格があり、取得費用は2〜6万円程度です。
必要資金は比較的少額で済みます。資格取得費用のほか、名刺やチラシなどの販促物(1〜3万円程度)、ウェブサイトやSNSアカウント開設(無料〜数万円)などで、合計10万円程度から始められることが多いです。
まずは自分の強みを明確にしましょう。例えば「子育て世帯の収納」「小さなマンションでの暮らし方」「キッチン特化型」など、特定の領域に特化することで差別化しやすくなります。自分自身の経験や興味に基づいた専門性を打ち出すことが重要です。
サービス設計と価格設定
整理収納アドバイザーのサービスは主に以下のような形態があります。
訪問コンサルティングは、クライアントの自宅を訪問して問題点を分析し、アドバイスを行うサービスです。初回は2〜3時間程度で、料金は時間制が一般的です。相場は1時間あたり3,000〜8,000円程度で、経験や地域によって異なります。
実作業サポートは、クライアントと一緒に実際に片付けを行うサービスです。こちらも時間制で、1時間あたり5,000〜10,000円程度、あるいは半日パック(3〜4時間)で2〜3万円程度が相場です。
セミナー・ワークショップは、複数人に向けて整理収納のノウハウを教えるサービスです。公民館や企業などで開催でき、1回あたり1〜5万円程度の料金設定が一般的です。
価格設定については、自分のスキルレベルや地域相場を考慮しましょう。初めは少し控えめな価格から始め、実績を積みながら徐々に上げていく方法もあります。ただし、あまりに低価格では専門性を疑われる可能性もあるため、適切な価値設定が重要です。
6. SNSマネージャー(平均月収:10〜45万円)
SNSマネージャーは主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の魅力は完全なリモートワークが可能である点です。パソコンとインターネット環境があれば自宅で働けるため、子育てや家事と両立しやすいという大きなメリットがあります。
始め方と必要スキル
SNSマネージャーとして起業するための初期投資は比較的少額です。基本的にはパソコン(持っていれば流用可能、新規購入なら10万円前後)とインターネット環境(月額5,000円程度)があれば始められます。専門的なソフトウェアも必須ではありませんが、画像編集ツールなどを利用する場合は追加費用がかかることもあります。
必要なスキルとしては、まず各SNSプラットフォーム(Instagram、Twitter、Facebook、TikTokなど)の特性と最新トレンドへの理解が不可欠です。それぞれのプラットフォームで効果的なコンテンツ形式や投稿タイミングが異なるため、使用頻度が高いものから深く理解していきましょう。
また、基本的なライティングスキル、写真撮影や簡単な画像編集のスキルも重要です。難しいデザインは外注することもできますが、日常的な投稿については自分で対応できる方が効率的です。Canvaなどの無料ツールを使った簡単なデザイン作成方法を学んでおくと良いでしょう。
案件獲得のためのポートフォリオ作り
SNSマネージャーとして案件を獲得するには、実績を示すポートフォリオが欠かせません。まだ実績がない場合は、以下のようなステップでポートフォリオを作成していきましょう。
まず自分自身のSNSアカウントを強化することから始めるのが効果的です。特定のテーマ(例:子育て、料理、インテリアなど)に絞り、質の高い投稿を継続的に行い、フォロワーを増やしていきます。自分のアカウントがSNS運用のスキルを示す最初の実績となります。
次に、無償でも良いので知人の小さなビジネスや地域の店舗、NPOなどのSNS運用を手伝わせてもらいましょう。「フォロワー数が〇〇人増加した」「投稿のエンゲージメント率が〇〇%向上した」など、具体的な成果を数値で示せるようにします。
また、自分の専門性を示すためにSNSマーケティングに関する知識をブログやSNSで発信することも効果的です。「Instagram運用のコツ」や「効果的なハッシュタグの選び方」など、役立つ情報を共有することで、専門性をアピールできます。
これらの実績をまとめたポートフォリオサイトを作成しましょう。ワードプレスや無料のポートフォリオサイト作成サービスを利用すれば、専門知識がなくても作成可能です。サイトには具体的な成功事例、提供するサービス内容、料金体系などを明記します。
案件獲得のチャネルとしては、クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークスなど)からの受注、自身のSNSやブログからの問い合わせ、知人からの紹介など複数の方法を組み合わせると効果的です。特に初期は小規模案件でも積極的に受注し、実績と口コミを積み重ねていくことが重要です。
7.オンラインカウンセラー・コーチ(平均月収:15〜60万円)

オンラインカウンセラーやコーチという職業は、主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の魅力は、場所を選ばず自宅から働けるという点です。対面での接客が不要なため、子育てや家事の合間に自分のペースでセッションを組むことができ、家庭との両立がしやすいという大きなメリットがあります。
始め方と資格取得
オンラインカウンセラーやコーチとして活動するには、資格取得が重要なステップとなります。国家資格である「公認心理師」や「臨床心理士」は取得のハードルが高いですが、民間資格では比較的取得しやすいものもあります。例えば、日本カウンセリング学会認定カウンセラー、産業カウンセラー、メンタルヘルス・マネジメント検定などがあります。
コーチングであれば、国際コーチ連盟(ICF)認定資格、コーチ・エィ認定プロフェッショナルコーチ資格などが代表的です。これらの資格取得費用は10〜50万円程度、期間は半年〜1年程度かかることが一般的です。
必要となる初期投資としては、資格取得費用のほか、ウェブサイト制作費(5〜20万円程度、テンプレートを使えばより安価に)、オンラインセッション用の機材(ウェブカメラ、マイク、照明など:1〜5万円程度)などがあります。
オンラインセッションの運営方法
オンラインでセッションを行うには、いくつかの準備が必要です。まず安定したインターネット環境を整えることが最優先です。また、プライバシーが確保された静かな空間を確保し、良質なカメラとマイクを用意することで、クライアントに安心感と専門性を伝えることができます。
セッションのプラットフォームとしては、Zoom、Google Meet、Skypeなどのビデオ会議ツールが一般的です。予約管理システム(Calendly、Reservaなど)を導入すると、クライアントが自分で都合の良い時間を選んで予約できるため、管理の手間が大幅に削減されます。
セッション料金の相場は、経験や専門性によって大きく異なりますが、初心者であれば30分3,000〜5,000円、60分5,000〜10,000円程度から始め、経験を積むにつれて徐々に上げていくのが一般的です。
支払い方法としては、クレジットカード決済(Square、PayPalなど)、銀行振込、電子マネーなど複数の選択肢を用意しておくと、クライアントの利便性が高まります。
効果的なセッション運営のコツとしては、事前のインテーク(初回カウンセリング)で目標や課題を明確にすること、セッション中はクライアントの話をしっかり聴く姿勢を持つこと、セッション後のフォローアップを充実させることなどが挙げられます。特にオンラインでは対面よりも非言語コミュニケーションが制限されるため、より意識的に温かみのある対応を心がけることが大切です。
8. 子育て支援サービス(平均月収:12〜40万円)
子育て支援サービスは主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の強みは、自身の育児経験が直接ビジネスの専門性として活かせる点にあります。実体験に基づく知識やノウハウは、同じ悩みを持つ親たちにとって大きな価値があり、共感と信頼を得やすくなります。
始め方と必要資金
子育て支援サービスを始める際の必要資金は、サービスの形態によって大きく異なります。最も手軽なのは、ベビーシッターや託児サービスで、資格取得費用(5〜10万円程度)と基本的な備品購入(おもちゃ、絵本、安全対策用品など:5〜15万円程度)から始められます。
一方、専用施設を設ける場合(小規模保育所、子育てカフェなど)は、物件の賃貸料、内装工事費、設備・家具の購入などで数百万円以上の初期投資が必要になることもあります。
始める際に検討すべき資格としては、保育士資格、幼稚園教諭免許、ベビーシッター資格、チャイルドマインダー、育児セラピストなどがあります。法的に必須ではない場合もありますが、専門性と信頼性をアピールする上で取得しておくと有利です。
地域でのニーズ発掘と差別化
子育て支援サービスを成功させるためには、地域特有のニーズを把握し、既存サービスとの差別化を図ることが重要です。まずは地域の子育て環境を調査しましょう。保育施設の充足状況、待機児童の有無、子育て世帯の居住傾向などを把握します。
地域の親たちと直接交流する機会も大切です。子育てサークルへの参加、児童館や子育て支援センターでのヒアリング、SNSの地域コミュニティでのアンケートなどを通じて、実際のニーズを探りましょう。「〇時以降の延長保育」「病児保育」「送迎サービス」など、既存施設では対応しきれていない隙間ニーズを発見できる可能性があります。
差別化のポイントとしては、特定の教育方針(モンテッソーリ、シュタイナー、英語特化など)の導入、特別なプログラム(自然体験、食育、アート活動など)の提供、独自の保育環境(少人数制、異年齢交流、家庭的な雰囲気など)の構築などが考えられます。
また、働き方に悩む親へのサポート(緊急時の預かり、短時間・不定期利用の受入れ)、特別なニーズを持つ子どもへの対応(発達障害、アレルギー対応など)といった、きめ細かいサービスも差別化につながります。
9. ECサイト用商品撮影(平均月収:8〜35万円)
ECサイト用の商品撮影サービスは、主婦の方が起業するのに特に適したビジネスです。最大の魅力は、自宅という空間を活かして仕事ができる点にあります。撮影スペースを確保できれば、外出せずに家庭内で完結する仕事として、子育てや家事との両立がしやすい環境を作れます。
始め方と必要機材
ECサイト用商品撮影サービスを始めるための初期投資は、基本的な機材の購入から始まります。必要な機材には、以下のようなものがあります。
カメラは、一眼レフカメラやミラーレスカメラが理想的ですが、最初は高性能なスマートフォンからでも始められます。本格的なカメラを購入する場合でも、エントリーモデル(5〜10万円程度)で十分です。レンズは標準ズームレンズに加え、マクロレンズ(アクセサリーなど小物撮影用)があると便利です。
照明機材は非常に重要で、LED撮影ライト(1〜3万円程度)や、自然光を拡散させる反射板・ディフューザー(数千円)は基本的な装備です。背景紙や撮影ボックス(1〜2万円程度)も商品によって必要になります。
三脚は安定した撮影に不可欠で、しっかりしたもの(5千円〜1万5千円程度)を選びましょう。編集ソフトウェアは、Adobe Photoshopの月額プラン(月3,280円から)か、無料のGIMPやCanvaなどで始めることができます。
これらの機材を全て揃えると、初期投資は15〜30万円程度になりますが、段階的に購入していくことも可能です。特に始めのうちは、自然光を活用し、最小限の機材から始めることで、コストを抑えることができます。
ポートフォリオの作り方と案件獲得
ECサイト用商品撮影の仕事を獲得するには、魅力的なポートフォリオの作成が必須です。まだ実績がない場合は、以下のようなステップでポートフォリオを作り上げていきましょう。
自分の所有物や友人・知人から借りた商品を使って、様々なジャンルの商品撮影を練習します。アクセサリー、衣類、食品、雑貨など、異なるカテゴリーの商品を撮影すると、幅広い対応力をアピールできます。
地元の小さなお店やハンドメイド作家に無料または格安で撮影を提案するのも良い方法です。実際の商品を多く撮影することで、実務経験とポートフォリオの充実を同時に実現できます。
撮影した写真は、専用のポートフォリオサイトやInstagramなどのSNSで公開しましょう。ポートフォリオサイトは、Wixやポートフォリオ特化型のサービスを利用すれば、専門知識がなくても作成可能です。
ポートフォリオでは単に写真を並べるだけでなく、「撮影前と撮影後」の比較や、同じ商品の異なる表現方法を示すなど、自分の技術の価値が伝わる見せ方を工夫しましょう。
案件獲得の方法としては、クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークスなど)への登録、SNSでの情報発信、地域の小売店や作家への直接営業、知人からの紹介など、複数のチャネルを組み合わせるのが効果的です。
特に特定の商品ジャンルに特化することで、その分野での専門性をアピールできます。例えば「アクセサリー専門」「ハンドメイド作品専門」「食品専門」など、得意分野を明確にすると差別化しやすくなります。
10. オンライン講座・教材販売(平均月収:10〜50万円以上)
オンライン講座や教材販売は主婦の方が起業する際に特に適した選択肢です。最大の魅力は、一度作成したコンテンツが継続的に収入を生み出す「ストック型ビジネス」である点です。通常のサービス業と異なり、時間と収入が直結しないため、家事や育児の合間に効率的に収益を上げられます。
始め方とコンテンツ作成
オンライン講座や教材販売を始めるためには、まず自分の強みや専門性を明確にすることが大切です。自分が教えられる内容、解決できる問題は何かを考え、ターゲットとなる学習者像を具体的にイメージしましょう。
コンテンツのフォーマットには様々な選択肢があります。動画講座、電子書籍(PDF)、オーディオガイド、テンプレート集、オンラインコミュニティなど、教える内容や自分の得意なメディアに合わせて選びます。初めは一つのフォーマットから始め、徐々に拡大していくのがおすすめです。
コンテンツ作成に必要な機材としては、パソコン、スマートフォンやビデオカメラ(動画講座の場合)、マイク(クリアな音声のため)などがあります。動画編集ソフトは無料のものから始めることができ、徐々にスキルアップしていけば十分です。
教材内容は、学習者が具体的な成果を得られるよう設計することが重要です。例えば「忙しいママでも作れる時短料理10選」「子どもが片付けたくなる収納術」など、明確な価値提案ができるテーマが効果的です。また、ステップバイステップで学べる構成にすることで、学習者の成功体験を促しましょう。
集客と販売の自動化
オンライン講座や教材の集客には、様々な方法があります。最も効果的なのはSNSやブログでの情報発信です。教材のテーマに関連する有益な情報を無料で公開することで、潜在顧客の信頼を得て、ファンを増やしていきます。例えば、料理教材なら簡単レシピを投稿する、子育て関連なら育児のヒントを共有するなど、価値ある情報発信を継続しましょう。
メールマーケティングも重要な集客ツールです。無料の小冊子やチェックリストなどを提供して、メールアドレスを獲得し、定期的にニュースレターを送ることで、見込み客との関係を深めていきます。MailChimpやConvertKitなどのツールを使えば、自動配信の仕組みも構築できます。
販売プロセスの自動化は、主婦の起業において特に重要です。決済システム(PayPal、Stripeなど)と自動配信の仕組みを連携させれば、購入後に自動的に教材へのアクセス権が付与される仕組みを作れます。これにより、24時間いつでも販売が可能になり、夜中や外出中でも売上が発生します。
また、購入者向けのステップメール(自動配信メール)を設定しておくと、サポートの一部も自動化できます。よくある質問とその回答、補足情報、次のステップの提案などを自動的に送ることで、顧客満足度を高められます。
成功している主婦起業家に共通する特徴

成功している主婦起業家に共通する特徴をご紹介します。
家庭との両立を意識した無理のない事業計画
成功している主婦起業家は、家庭生活と事業のバランスを最優先に考えています。彼女たちは子どもの学校行事やライフステージに合わせた柔軟な勤務時間を設定し、自宅や近隣でのビジネス展開により移動時間を削減しています。また季節や学校行事に合わせた繁閑期の調整を行い、夏休みなどは仕事量を調整することも特徴です。急激な負担増を避けるために段階的に事業を拡大する計画的なアプローチを取り、家族の協力を得られる範囲でビジネスモデルを構築しています。
SNSやWeb活用によるマーケティング
デジタルツールを効果的に活用することで、場所や時間に縛られない集客を実現しています。子育て中の隙間時間、例えば子どもの就寝後や通学時間などを活用してSNSを運用し、実体験に基づいた共感を呼ぶコンテンツを作成しています。主婦の視点から解決策を提案する情報発信スタイルが特徴的で、費用対効果の高いSNS広告を活用しています。さらにオンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッドな販売戦略で顧客層を広げています。
主婦ならではの視点を強みに変える工夫
成功している主婦起業家は日常生活での経験や課題を事業機会に転換しています。家事や育児の中で見つけた「不便」を解決する商品やサービスを開発し、同じ立場の女性が抱える悩みへの共感力を活かした商品企画を行います。家庭管理のノウハウをコンサルティングやコーチングに活用したり、「主婦目線」を前面に出したブランディングを展開しています。また家族を「テストユーザー」として活用し、商品やサービスの改良プロセスに取り入れることも多いです。
コミュニティ形成による支援ネットワーク
同じ境遇の女性同士の繋がりを大切にしています。オンラインやオフラインでの主婦起業家コミュニティに積極的に参加し、子育てや家事の協力体制と事業支援を兼ねたネットワークを構築しています。相互紹介による顧客基盤の拡大や、スキルや知識を補完し合うコラボレーション関係を築いています。また、メンターや先輩起業家からのアドバイスやサポートを積極的に活用して、自身のビジネスを発展させています。
成功している主婦起業家は、家庭との両立を軸に、デジタルツールの活用、独自の視点、そして支援ネットワークを組み合わせることで、持続可能な事業成長を実現しています。彼女たちは限られた時間と資源を最大限に活用し、家庭を大切にしながらも自身の可能性を広げているのです。
主婦起業家が直面する課題と解決策

主婦起業家が直面する課題と解決策についてご紹介します。
時間管理の難しさとその対策
時間管理について、その対策をご紹介します。
育児・家事との両立テクニック
主婦起業家にとって育児・家事との両立は最大の課題です。効果的な対策としては、まず「時間のブロック化」が挙げられます。1日を細かく区切り、家事・育児・仕事それぞれに専念する時間帯を明確に設定することで、切り替えがスムーズになります。例えば朝の子どもが登校後の2時間を「集中仕事タイム」、夕方の帰宅後から夕食までを「家族時間」と決めておくことで、メリハリが生まれます。
また「家事の最適化」も重要です。すべてを完璧にこなそうとせず、優先順位をつけて一部を外注化や簡略化することも検討しましょう。食事準備は週末にまとめて作り置きする、掃除は最小限の場所に絞る、オンラインスーパーの定期便を活用するなどの工夫が有効です。
さらに「家族の巻き込み」も不可欠です。年齢に応じて子どもに家事を手伝ってもらう、パートナーと家事分担を明確にするなど、家族全体で協力体制を作ることで、主婦一人の負担を減らすことができます。特に仕事の繁忙期には事前に家族に協力を依頼し、理解を得ておくことが大切です。
タイムマネジメントツールの活用法
デジタルツールを活用した時間管理は主婦起業家の強い味方になります。まず「統合型カレンダーアプリ」の活用がおすすめです。Googleカレンダーなどで家族のスケジュール、子どもの学校行事、ビジネスの予定を一元管理し、色分けすることで予定の衝突を事前に防ぐことができます。家族全員で共有することで、互いの予定を把握しやすくなります。
「タスク管理アプリ」も効果的です。TrelloやAsanaなどを使って、仕事のタスクを「今日中」「今週中」「今月中」などと優先度別に整理します。特に主婦起業家の場合、15分や30分など短時間でできるタスクを「すきま時間タスク」としてリスト化しておくと、子どもの習い事の待ち時間などを有効活用できます。
また「時間記録アプリ」を使って、自分の時間の使い方を可視化することも重要です。TogglやRescueTimeなどで1週間程度記録すると、思わぬ時間の浪費が見つかることがあります。データに基づいて時間の使い方を最適化していきましょう。
効率的な作業環境の作り方
主婦起業家にとって作業環境は生産性を大きく左右します。まず「専用スペースの確保」が基本です。完全な個室が難しくても、リビングの一角や寝室の片隅など、「ここに座ったら仕事モード」と切り替えられる専用スペースを確保しましょう。このスペースには必要な書類や機材をすぐ手の届く場所に配置し、立ち上がる頻度を減らします。
「集中力を高める工夫」も重要です。ノイズキャンセリングヘッドホンの活用、スマホの通知オフ設定、家族に「集中タイム」を知らせる見える化(例:赤い旗を立てるなど)を取り入れましょう。また短時間でも集中力を最大化するために、ポモドーロテクニック(25分集中して5分休憩)などの時間管理手法を取り入れることも効果的です。
「モバイルワーク環境の整備」も主婦起業家には欠かせません。子どもの習い事の送迎時間や学校行事の待ち時間なども無駄にしないよう、タブレットやスマートフォンで仕事ができる環境を整えておきましょう。クラウドサービスを活用してどこからでもファイルにアクセスできるようにし、移動時間も有効活用できるようにします。
これらの対策を組み合わせることで、限られた時間の中でも家庭と仕事を両立させながら、ビジネスを着実に成長させることができるでしょう。最も重要なのは、完璧を求めすぎず、自分なりのバランスを見つけることです。
集客・マーケティングの壁
集客・マーケティングについてのポイントをお伝えします。
初期費用をかけない集客方法
主婦起業家が限られた予算で集客するためには、クリエイティブな手法が必要です。まず地域コミュニティを活用しましょう。ママ友ネットワーク、子どもの学校関係、地域の子育てサークルなど、既存の人間関係を大切にし、自然な形で自分のビジネスを知ってもらいます。ただし押し売りにならないよう、相手の悩みや関心に合わせて話題にする配慮が重要です。
無料で参加できるイベントやマルシェの活用も効果的です。地域の子育てイベントやフリーマーケット、公民館での展示会などに出展し、実際に顔を合わせながら信頼関係を構築できます。この際、商品やサービスの販売だけでなく、無料サンプルや簡単なワークショップなど、価値を提供する姿勢が集客につながります。
オンラインではメールマガジンの活用がコストパフォーマンスに優れています。興味を持ってくれた方に定期的に情報を届けることで、関係性を深めていけます。メルマガでは役立つ情報や体験談を中心に、時折ビジネスの紹介を織り交ぜる形が理想的です。無料のメルマガサービスを利用すれば初期費用ゼロで始められます。
また、他の主婦起業家とのコラボレーションも効果的です。相互に顧客を紹介し合ったり、共同イベントを開催したりすることで、新たな顧客層にアプローチできます。例えば、手作り石鹸を販売している方とアロマテラピーを提供している方が組んでリラクゼーションイベントを開催するなど、相乗効果が期待できます。
SNSを活用した効果的な情報発信
SNS活用では、まず「選択と集中」が重要です。全てのSNSに手を出すのではなく、自分の商品やサービスに合ったプラットフォームを1〜2つ選び、そこに注力しましょう。例えば、ビジュアル重視の商品ならInstagram、情報発信が中心ならX(旧Twitter)、詳しい解説が必要ならnoteやブログが適しています。
コンテンツ作成においては「自分の日常を織り交ぜる」戦略が主婦起業家には有効です。完璧な商品写真やプロフェッショナルな投稿だけでなく、主婦として商品開発に取り組む姿や、日常の中でどう自分のサービスが役立っているかなど、リアルな姿を見せることで共感を得られます。家事や育児の合間に商品を作っている様子や、子どもと一緒に商品をテストしている場面などは親近感を生みます。
投稿の一貫性も重要です。「毎週月曜は○○の日」など、定期的なコンテンツシリーズを作ることで、フォロワーに期待感を持ってもらえます。例えば「毎週水曜は時短レシピ」「毎月第一日曜は新商品発表」など、リズム感のある情報発信が理想的です。
さらに、ハッシュタグ戦略も効果的です。ビジネスに関連するハッシュタグだけでなく、主婦や子育てに関するハッシュタグも併用することで、同じ境遇の方々に見つけてもらいやすくなります。たとえば「#手作り石鹸」だけでなく「#子育てママ」「#敏感肌ベビー」などを組み合わせると効果的です。
口コミを広げるための工夫
口コミを促進するには「期待以上の価値提供」が基本です。商品やサービス自体の質を高めることはもちろん、丁寧な梱包や手書きのメッセージカード、購入後のフォローアップなど、予想外の喜びを提供することで、自然と人に話したくなる体験を創出します。例えば、ハンドメイド商品であれば商品の由来や制作秘話を添えたり、料理教室であれば受講生の名前入りレシピ集をプレゼントしたりするなど、記憶に残る体験を設計しましょう。
「シェアしやすい仕掛け」も重要です。商品パッケージやサービス体験の中に、SNSに投稿したくなるような工夫を盛り込みます。可愛らしいパッケージデザイン、インスタ映えするビジュアル、撮影スポットの設置など、顧客がSNSで共有したくなる要素を意識的に取り入れましょう。また、投稿してくれた方への特典を用意するのも効果的です。
「紹介特典プログラム」の導入も検討価値があります。既存顧客が新規顧客を紹介してくれた際、両者に特典を提供するシステムです。例えば「お友達紹介で次回10%オフ」などの特典を設けることで、口コミの動機付けになります。ただし、あまりに大げさな特典は逆に不信感を生むため、自然な形での紹介を促す程度の特典設計が理想的です。
そして「お客様の声の可視化」も効果的です。実際に商品やサービスを利用した方の感想を、許可を得た上でSNSやウェブサイトで紹介します。具体的なエピソードを含む生の声は、新規顧客の不安を払拭し、信頼構築に役立ちます。可能であれば、お客様の写真やビフォーアフターの画像なども添えると、より説得力が増します。
これらの施策を組み合わせることで、限られた予算と時間の中でも、主婦起業家ならではの強みを活かした効果的な集客・マーケティングが可能になります。大切なのは、数ではなく質を重視し、一人ひとりとの関係性を大切にする姿勢です。
モチベーション維持と孤独感の解消
主婦起業家がモチベーションを維持するためのポイントと孤独感を解消する上でのポイントをご紹介します。
主婦起業家同士のコミュニティ活用
主婦起業家にとって同じ境遇の仲間の存在は何よりの支えになります。コミュニティを活用する際はまず地域密着型のものから始めるとよいでしょう。地元の商工会や起業支援センターが主催する女性起業家向けの勉強会やネットワーキングイベントに定期的に参加することで、同じ地域で活動する仲間と出会えます。地域のつながりは、オンラインだけでは得られない実践的なサポートにつながることも多いです。
オンラインコミュニティも非常に有効です。FacebookグループやLINEオープンチャットなどで、主婦起業家や女性起業家向けのコミュニティを探してみましょう。「ママ起業家の会」「子育てしながら起業する女性の集い」などのキーワードで検索すると多くのグループが見つかります。参加する際は最初は情報収集から始め、徐々に自分の経験や知識をシェアしていくことで、より深い関係性を構築できます。
コミュニティ内では受け身にならず積極的に質問したり、自分の課題をオープンに共有したりすることが大切です。成功体験だけでなく、失敗や悩みも共有できる関係性こそが孤独感を解消し、実践的なアドバイスにつながります。また、定期的なオンライン朝活や作業会などに参加することで、日常的なモチベーション維持にもつながります。
業種を超えたつながりも視野に入れましょう。同業者だけでなく、異なる分野で活躍する主婦起業家との交流は新しい視点や発想をもたらします。例えばハンドメイド作家、コンサルタント、料理教室主宰者など、業種が異なる主婦起業家が集まるコミュニティは、互いに客観的なフィードバックができる貴重な場になります。
メンターの見つけ方
メンターとの出会いは偶然に頼るのではなく、戦略的にアプローチすることが重要です。まず先行する主婦起業家のブログやSNSをフォローし、共感できる人を見つけたら、まずはコメントやメッセージで丁寧にコミュニケーションを取り始めましょう。いきなり「メンターになってください」と頼むのではなく、具体的な質問から始め、少しずつ関係性を深めていくのがコツです。
起業支援イベントやセミナーの講師も潜在的なメンター候補です。参加したセミナーで共感できる講師がいれば、質問タイムを活用したり、終了後に個別に話しかけたりして接点を作りましょう。多くの成功者は自分の経験を次世代に伝えたいと考えているので、真摯な姿勢で接すれば応えてくれる可能性は高いです。
有料のメンタリングプログラムやコーチングサービスを活用するのも一つの手段です。初期費用はかかりますが、体系的なサポートを受けられるメリットがあります。特に主婦起業家向けのコーチングサービスは、家庭との両立を前提としたアドバイスが受けられるため効果的です。料金に見合う価値があるかを判断するために、無料相談や体験セッションを活用しましょう。
メンターに求めるものを明確にすることも大切です。技術的なアドバイス、人脈の紹介、精神的なサポートなど、何を求めているのかを整理し、それに合った人を探すことで、ミスマッチを防げます。また、一人のメンターに全てを求めるのではなく、領域ごとに異なるメンターを持つ「メンターボード」的な発想も有効です。
家族の理解と協力を得るコツ
家族の理解と協力なくして主婦起業の持続的な成功は難しいものです。まず家族会議を開いて、起業の目的やビジョンを共有しましょう。特に「なぜ起業するのか」という根本的な理由を家族に理解してもらうことが重要です。単に収入を得るためだけでなく、自己実現や社会貢献など、あなたの内面的な動機を伝えることで、家族の共感を得やすくなります。
具体的なメリットを家族にも示すことも効果的です。例えば「収入が増えれば家族旅行に行ける」「柔軟な働き方で子どもの行事に参加できる」など、家族にとっても良い変化があることを伝えましょう。また、起業によって家族に負担がかかる部分については正直に話し合い、協力してもらいたいことを具体的に伝えることが大切です。
家族との時間を意識的に確保することも重要です。どんなに忙しくても、「家族の日」や「デートの日」など、ビジネスから完全に離れて家族と過ごす時間を定期的に設けましょう。また、子どもの成長や家族の大切なイベントを優先する姿勢を示すことで、「家族を犠牲にしている」という不安や不満を軽減できます。
成果を家族と共有することも協力を得る上で効果的です。初めての売上や嬉しい顧客の声など、小さな成功体験も家族に報告し、一緒に喜びを分かち合いましょう。特に子どもには、「ママがどんな仕事をしているのか」を年齢に合わせて説明し、時には一緒に作業を手伝ってもらうことで、家族全体のプロジェクトとして捉えてもらえるようになります。
最後に、家族との約束は必ず守ることを心がけましょう。「この時間は仕事をしない」と決めたら、スマホをチェックしたり、メールに返信したりすることを避け、家族との時間に集中します。約束を守る姿勢が、家族からの信頼と長期的な協力につながります。
これらの対策を組み合わせることで、モチベーションを維持し、孤独感を解消しながら、家族の理解と協力を得て主婦起業を続けていくことができます。重要なのは、完璧を求めすぎず、自分のペースで着実に前進することです。
収益化までの道のり
主婦起業家の多くの方が悩むのは、収益化までの道のりでしょう。以下でそのポイントをお伝えします。
副業から始めて専業に移行するタイミング
主婦起業家が副業から専業へ移行する決断は慎重に行うべき重要なステップです。理想的な移行タイミングは、副業の月収が家計への必要最低貢献額を安定して上回るようになってからです。具体的には、最低でも6ヶ月連続で目標収入を達成できていることが一つの目安になります。この期間が長いほど、収入の安定性を確認できるため、より安全です。
また収入面だけでなく、ビジネスの将来性も重要な判断材料です。顧客からのリピート率や問い合わせの増加傾向、市場の成長性などを分析し、今後も成長が見込めるかを評価しましょう。単に現在の収入だけでなく、今後6ヶ月から1年の成長予測を立て、それが家計を支えるのに十分かを検討することが重要です。
家庭状況も考慮すべき要素です。子どもの教育費が増える時期や住宅ローンの返済額が変わる時期など、家計の変動要因を考慮に入れた上で判断しましょう。また、緊急時に備えた資金(最低でも生活費の6ヶ月分)を確保してからの移行が望ましいです。
専業化する前に試験的な期間を設けることも賢明です。例えば夏休みなど家族のサポートが得やすい時期に、1〜2ヶ月間「専業シミュレーション」を行い、時間管理や収益面での課題を事前に把握しておくことで、本格移行時のリスクを減らせます。
複数の収入源を持つ重要性
主婦起業家にとって複数の収入源を持つことは、単なるリスク分散以上の意味を持ちます。まず、家庭や子育ての状況に合わせて柔軟に対応できるようになります。例えば、子どもの長期休暇中は対面サービスを減らしてオンライン販売に注力するなど、状況に応じて収入源を調整できます。
複数の収入源を構築する際は、関連性のあるものから始めるのが効率的です。例えば、ハンドメイド作家であれば「作品販売」を主軸に、「作り方の講座開催」「材料キットの販売」「技術指導の電子書籍」など、同じ専門知識や技術を活用した収入源を増やしていくことで、新たな学習コストを抑えられます。
収入源の組み合わせにおいては、「即時収入」と「継続収入」のバランスも重要です。一回の取引で完結する商品販売やサービス提供に加えて、月額制のメンバーシップやサブスクリプションモデル、デジタルコンテンツの販売など、継続的に収入が見込める仕組みを取り入れることで、収入の安定性が高まります。
また季節や時期による変動も考慮しましょう。例えば、年末年始や夏休みなど家庭が忙しくなる時期に収入が減少するリスクを避けるため、その時期に自動的に収入が入る仕組み(事前予約の講座や季節商品の先行販売など)を用意しておくことで、年間を通じた収入の平準化が図れます。
安定した収益を得るための料金設定
主婦起業家が陥りがちな失敗の一つが、適正価格より低い料金設定です。価格設定においては、まず「時間単価」の考え方を取り入れましょう。商品制作やサービス提供にかかる直接的な時間だけでなく、準備や連絡対応、発送作業などの間接的な時間もすべて計算に入れ、時間あたりいくら稼げているかを把握することが重要です。
価格設定の基本として「原価の3倍」という考え方がありますが、これは原材料費だけでなく、あなたの労働時間も原価として計算すべきです。例えば、材料費が1000円で制作に2時間かかる商品の場合、あなたの時間単価を仮に1500円とすると、原価は「1000円+(1500円×2時間)=4000円」となり、販売価格は最低でも12000円が目安となります。
料金設定においては「顧客にもたらす価値」も重要な判断基準です。単に制作コストだけでなく、あなたの商品やサービスが顧客の問題をどれだけ解決するか、どれだけの喜びや便益をもたらすかによって価値は変わります。例えば、時短になる料理教室や子どもの特性に合わせた学習教材など、顧客の悩みを解決する度合いが高いものは、それに見合った価格設定が可能です。
初めから高価格帯で参入するのが難しい場合は、「価格上昇戦略」を検討しましょう。まずは適正価格よりやや低めでスタートし、顧客の反応や評価を集めながら、3〜6ヶ月ごとに段階的に価格を上げていく方法です。その際、「次回から価格改定します」と事前告知することで、駆け込み需要も期待できます。
料金設定においては「パッケージ化」も効果的です。単品で提供するよりも、関連サービスをセットにしたパッケージ商品を作ることで、客単価を上げられます。例えば、手作り石鹸教室であれば「基本レッスン+材料キット+レシピ集」をセットにした「スターターパッケージ」の提供などが考えられます。パッケージは単品よりも価値が伝わりやすく、全体の割引感があっても総額では高単価になりやすいメリットがあります。
これらの対策を総合的に検討し、自分のビジネスと家庭状況に合わせて収益化の道のりを計画的に進めていくことが重要です。短期的な収入よりも長期的な持続可能性を重視し、家庭とのバランスを保ちながら、段階的にビジネスを成長させていきましょう。
主婦起業を応援してくれる制度・支援まとめ

主婦の起業を力強くバックアップしてくれる、2026年度(令和8年度)の主要な補助金・助成金をご紹介します。
女性向けの補助金・助成金
【東京都】若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
都内商店街での開業を目指す女性を対象とした非常に手厚い助成金です。女性であれば年齢制限なく申請可能です。2026年度の募集については未定です。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
助成内容:
店舗工事費・設備購入費等・宣伝広告費:対象費用の3/4以内、上限400万円(宣伝広告費は上限150万円)
店舗賃借料(3年間):対象費用の3/4以内、1年目15万円/月、2年目12万円/月、3年目10万円/月
両立支援等助成金
仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主向けの助成金です。
主なコース:
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金):男性の育休取得支援(20万円~60万円)
介護離職防止支援コース:最大60万円(休業取得・復帰合計)〜110万円(有給休暇制度導入時)
育児休業等支援コース:30万円〜60万円(休業取得・復帰合計)
育休中等業務代替支援コース:最大140万円
柔軟な働き方選択制度等支援コース:20万円~25万円
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース:30万円
キャリアアップ助成金
非正規雇用の方を正社員化したり、処遇を改善したりする際に支給される助成金です。
主なコース:
正社員化コース:1人につき40万円~80万円
賃金規定等改定コース:1人につき3.2万~6.5万円
賃金規定等共通化コース:60万円/事業所(大企業の場合45万円/事業所)
賞与・退職金制度導入コース:40万円/事業所(両方導入でさらに加算)
社会保険適用時処遇改善コース:最大50万円/人
地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)
地域別に様々なファンドがあり、研究・商品開発や需要開拓の費用助成を受けられます。代表者が女性の場合、優遇措置のあるファンドも存在します。
お住まいの地域によって公募時期や詳細な条件が大きく異なります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する補助金です。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
- 一般型:通常枠(2/3・50万円)、インボイス特例(2/3・100万円)、賃金引上げ特例(2/3※・200万円)、災害支援枠(定額または2/3・100万円または200万円) ※赤字事業者は3/4
- 創業型:2/3・200万円(インボイス特例適用あり)
- 共同・協業型:定額または2/3・5,000万円
- ビジネスコミュニティ型:定額・50万円または100万円
デジタル・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)
ITツール導入を支援する補助金で2026年度より「デジタル・AI導入補助金」として再編が進んでいます。バックオフィス業務の効率化に加え、AIツールの導入支援が強化されました。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
- 通常枠:中小企業1/2、最低賃金近傍の事業者2/3・5万~450万円
- インボイス枠:対応類型と電子取引類型があり、補助率は条件により1/2~4/5・10万~350万円
- セキュリティ対策推進枠:中小企業1/2、小規模事業者2/3・5万~150万円
- 複数社連携IT導入枠:条件により1/2~4/5・10万~3,000万円
新事業進出・ものづくり補助金(旧ものづくり補助金)
革新的サービス開発や試作品開発、生産プロセス改善のための設備投資を支援する補助金です。
2026年度から「新事業進出補助金」と統合され、新しい市場への挑戦をより重視する制度になりました。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
- 製品・サービス高付加価値化枠:中小企業1/2、小規模事業者2/3・750万~2,500万円(大幅賃上げの場合850万~3,500万円)
- グローバル枠:中小企業1/2、小規模事業者2/3・3,000万円(大幅賃上げの場合3,100万~4,000万円)
事業承継・M&A補助金
事業承継や再編をきっかけとした新たな挑戦を支援する補助金です。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
- 事業承継促進:2/3または1/2・800万~1,000万円
- 専門家活用:買い手支援類型(Ⅰ型)2/3、売り手支援類型(Ⅱ型)1/2~2/3・600万~2,000万円
- PMI推進:1/2または2/3・150万~1,000万円
中小企業省力化投資補助金
深刻な人手不足を解消するため、ロボットやIoT、AI等の導入により業務の自動化・効率化を図る投資を支援する補助金です。
※以下は、2025年の情報です。最新情報が公開されましたら更新予定です。
- カタログ注文型:1/2・200万~1,500万円
- 一般型:1/2または2/3(一部条件で1/3)・750万~1億円
関連記事
https://sogyotecho.jp/fund-for-women/
起業支援センターや自治体の無料相談
起業支援センターや自治体の無料相談は主婦起業家にとって多くのメリットをもたらします。まず、起業の基礎知識や必要な手続き、資金計画など専門家からの具体的アドバイスを費用負担なく受けられる点が大きな強みです。特に家計への負担を抑えたい主婦起業家にとって、コストをかけずに質の高い情報が得られる貴重な機会となります。
また、地元の消費者ニーズや競合状況など、地域に根差した情報を得られることも重要です。子育てや家庭との両立を考える主婦起業家にとって、通勤時間の少ない地域密着型ビジネスの構築に役立つ情報が手に入ります。地域特性を活かしたビジネスモデルの構築は、限られた時間と資源で効率的に事業を展開するための鍵となります。
さらに、女性起業家向けの支援制度や地域限定の助成金など、一般に広く知られていない資金調達の情報を入手できることも大きなメリットです。申請書類の書き方など具体的なサポートも受けられるため、限られた時間の中でも効率的に準備を進めることができます。家庭との両立で時間的制約のある主婦起業家にとって、このようなサポートは貴重な時間節約になります。
起業支援センターが主催する交流会やセミナーを通じて、同じく主婦として起業した先輩や仲間との出会いがあることも重要です。家庭と事業の両立に関する実践的なアドバイスや協力関係の構築につながり、孤独感の解消やモチベーション維持にも役立ちます。同じ立場の人とのネットワークは、様々な課題解決のヒントを得る場になります。
創業融資やクラウドファンディングも選択肢に
創業融資とクラウドファンディングは、主婦起業家にとって異なる特性を持つ重要な資金調達手段です。
創業融資は主婦起業家に安定した事業資金をもたらします。特に日本政策金融公庫の女性起業家支援やマザーズ向け特例などは、主婦の起業を考慮した条件が設定されているため、通常よりも融資を受けやすい傾向があります。融資は計画的な返済が必要ですが、大型の初期投資が必要な事業や、安定的な収益が見込めるビジネスモデルに適しています。また、融資審査の過程で事業計画を精査されることで、計画の穴や弱点を発見できるメリットもあります。家庭の資産リスクを抑えつつ事業資金を確保できる点は、家計を預かる主婦起業家にとって大きな利点です。
一方、クラウドファンディングは主婦起業家にとって資金調達と同時に市場検証の機会を提供します。子育てや家事の経験から生まれたアイデアやサービスは、同じ悩みを持つ層からの共感を得やすく、支援につながりやすい特徴があります。また、事前に商品やサービスへの反応を確認できるため、本格展開前のリスク軽減になります。プロジェクト実施過程でSNSなどを通じた情報発信を行うことで認知度向上や顧客獲得にもつながり、時間的制約のある主婦起業家にとって効率的なマーケティング手段にもなります。融資と違い返済義務がない点も、家計への負担軽減という観点で魅力的です。
両者を組み合わせることで、例えば初期段階ではクラウドファンディングで市場検証と少額資金を集め、反応が良ければ創業融資で本格展開するといった段階的な資金調達戦略も可能です。どちらの方法も、事業計画の精緻化や説明能力の向上といった副次的効果をもたらし、主婦起業家のビジネススキル向上にも寄与します。限られた時間と資源を効率的に活用しながら起業を実現するための重要なツールとして、主婦起業家は状況に応じて適切に選択・活用することが望ましいでしょう。
まとめ:あなたの強みを活かした主婦起業を始めよう

以上、起業したい主婦におすすめの業種ランキングなどをご紹介しました。
創業手帳別冊版「創業手帳Woman」では、起業したい女性の多くが悩むことについて、すでに活躍している女性起業家の方にインタビューを通じてどのように対応されてきたかをお伺いしています。女性の起業失敗のリスクを軽減するためにも、ぜひこちらのガイドブックをあわせてお読みください。無料でお取り寄せ可能です。
(編集:創業手帳編集部)