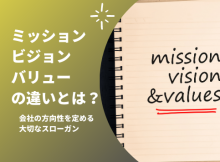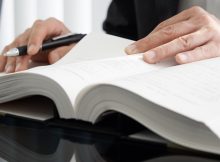競業避止義務とは?判断基準や防止策、罰則をわかりやすく解説!
競業避止義務はどこまでか明確化が必要

会社への損失を防ぐためにも、競業避止義務については十分な理解が必要です。特に人材が定着しきれていないベンチャーやスタートアップ企業では新しいノウハウを他で使われてしまう可能性もあります。しかし、双方の利害を調整するのは難しい問題です。
過度な内容は無効となるので、定め方にも注意しなければいけません。
そこで今回は、競業避止義務とはどういったものなのか、対象者と共に解説するほか、違反となる行動や判断するための基準などを紹介していきます。
さらに、違反を防止する方法や違反した人がいた時の対応についても説明していくので、正しい知識を身に付けたい人や深く理解したい人は、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
競業避止義務とは

まずは、どういった内容であるのか理解を深めるためにも、競業避止義務について解説していきます。
従業員や組織に対して課す義務
企業によっては、事業を継続するにあたってほかにはないような特別な知識やノウハウを従業員や役員に対して教育することもあります。
しかし、そうした社員が競業を営んでいる他社に転職してしまうと、自社が損失を被る恐れがあります。
競業避止義務は、契約締結によって競業にあたる事業を営んだり、同様の取引きを行ったりしないよう義務を課すことです。
自社で保有している機密情報や技術、営業といったノウハウの流出防止や商圏・顧客の確保が主な目的です。
競業避止義務の対象者
対象者となる人物は会社に勤める従業員だけではありません。取締役といった役員もその対象です。
さらに、すでにその企業を退職している人も、会社と競業する企業へ就職したり、競業する事業・取引を行なったりできません。
また、取引先に対しても課される時があります。
企業間取引において、取引相手と競業する事業を展開したり、取引相手の競合他社と同じような取引きをしたりすることはできないと義務付けられています。
競業避止義務に違反する行為とは

競業避止義務は、役員と社員とでは考え方が異なります。そこで、競業避止義務に違反する行為が役員・取締役と社員でどのような違いがあるのか解説します。
役員・取締役の場合
役員や取締役は、会社法に基づいて課せられています。法人と役員との契約は委任契約となるため、契約の内容として競業避止義務を負うことになります。
会社法第356条では、「競合および利益相反取引の制限」が定められており、自分や第三者の利益を図るために企業と取引をする際には、株主総会の事前承認なく行うことはできません。
取締役会設置会社では、重要な事実を取締役会に開示して承認を得る必要があり、加えて事後報告の実施も定められています。
これは、会社の業務を執行する役割を担う取締役や役員が、会社の利益を犠牲にし、自分や第三者に利益が渡るのを防ぐのが目的です。
委任契約後には、原則として取締役や役員の行動を会社は縛れません。
そのため、委任契約終了後についても、特定の期間や特定の場所での競業避止義務を課すよう、委任契約時に策定しているのが一般的です。
社員の場合
社員には、労働契約法に基づいた競業避止義務が課せられています。
例えば、勤務している企業と競合するような機密情報の漏洩や競合他社への顧客案内といった内容は違反とされやすいです。
そのため、働いている社員が競業行為を行った際には、何らかの処分が課せられることになり、事案によっては解雇となるリスクもあります。
退職後に関しては、原則として制限はありません。
しかし、退職時やそれ以前に競業避止義務について定めた誓約書などを締結していれば、違反となる行為があった際に処罰を課せます。
退職後の行動が悪質で自由競争の範囲を逸脱するような内容であれば、不法行為にあたるとして損害賠償請求が認められる場合もあります。
競業避止義務の6つの判断基準

誓約書や就業規則などで策定していたとしても、条件によっては無効となる時もあります。
無効にならないためにも、競業避止義務における6つの判断基準について説明していきます。
守るべき企業の利益
「守るべき利益があること」は規定の有効性を見定める上で重要です。当てはまる内容は以下の通りです。
-
- 営業秘密
- 顧客情報
- 技術
- 取引先との関係
営業秘密は、企業によって秘密管理がされており、有効性があり公然には知られていないものを指しています。
利益を獲得するためにかかる費用も判断する上で重要とされるポイントです。
ただし、他社でも容易に再現できる技術や広く知られている技術などは、利益があるとは評価されにくいです。
従業員の地位
競業避止を義務付ける必要のある地位にいる従業員であるかも判断する基準の1つです。
「従業員すべて」や「形式的な職位に就いている者すべて」など、対象者に合理的な理由がない時には認められにくいです。
例えば、課長や部長といった管理職でも、守るべき情報に接していないのであれば有効性は認められません。
しかし、機密情報を持っている社員や技術上の秘密を持っている可能性があるプログラマーやエンジニアなどは、有効と判断される傾向にあります。
過去には、企業のノウハウを持ちだしたとしてパート社員に対して認められた事例もあります。
地域的な限定
事業を提供しているエリアを踏まえて正当性があるかを判断する必要があります。
例えば、退職後に同じエリアや近隣で同事業を営めば、顧客を奪われるリスクがあるので事業に影響を与えかねません。
地域的な限定がなければ、日本のどこで事業を展開しても競業避止義務が課せられることになるので、範囲が過剰だとして無効になるケースも考えられます。
ただし、全国展開している事業であれば、広範囲に渡る地理的な制限が認められる場合もあります。
競業避止義務の存続期間
期間も重要なポイントです。義務を適用する期間に関しては、長くなればなるほど、その有効性は認められにくいです。
そのため、「生涯、同事業への転職を禁止する」といった制約内容は行き過ぎだと判断されます。
しかし、「○年以下」「○年以上」といった確定的な線引きはありません。様々な要素を踏まえて評価される仕組みです。
ただし、1年以内と策定すると認められやすいです。根拠のある期間を設定するようにしてください。
禁止される競業行為の範囲
競合企業への転職を一律で禁止しても合理性が認められないことは多いです。
そのため、「在職中に従事していた業務」や「在職中に担当した顧客との取引」など、範囲を決めると有効だと承認される可能性が高くなります。
ただし、在職中に得たノウハウが一部のみだったのであれば、有効性が認められない可能性があります。
代償措置
競業避止を義務付けるには適切な代償を提供しなければいけません。義務を課されることで生計を立てる手段が制約されるからです。
代償が提供されないのであれば、不当だとみなされる可能性もあります。
-
- 退職後の独立支援制度
- 退職金の増額
- 守秘義務手当の支給
- 高額な給与
などが当てはまります。
そのほかにも、物品の提供や住居の提供など、資金の提供以外でも経済的な支援によって代償措置をとることも可能です。
ただし、代償措置が取られていても、対価が少ないと判断されれば有効性は認められません。
競業避止義務違反を防止する方法

競業避止義務違反を防ぐための方法を解説していきます。違反行為を未然に防ぐためにも参考にしてください。
就業規則への明記
違反を防止するためにも、就業規則にあらかじめ競業避止義務について明記しておく必要があります。
在職中だけではなく、退職してからも競業避止を義務付けるためには具体的な内容を記さなければいけません。
従業員側も入社時から義務を理解することに役立ち、遵守すべき事項だと認識できます。
後々トラブルが起こったとしても、法的な強制力をもって義務の履行を求められるでしょう。
副業の許可制
違反を防ぐためにも副業の許可制を導入するのも有効な手段です。働き方改革によって副業や兼業が国によっても進められています。
そのため、副業を認めている企業も増えています。しかし、従業員が副業をするとなれば競業避止義務違反に該当する可能性もあるので注意が必要です。
副業を希望する従業員は事前に申請させ、副業を許可制にすれば違反となる行為に該当しないか調査できます。
問題がある場合には許可を出さないことで違反を未然に防げる仕組みです。
従業員教育の徹底
従業員が競業避止義務について理解していなければ無意識で違反となる行為をしてしまう可能性があります。
そのため、教育や研修を通じて競業避止義務の重要性や内容を周知する必要があります。
違反した時の法的リスクも交えて紹介すると、重大な事案だと認識されるでしょう。
教育や研修では口頭だけだと理解できないケースもあるため、書面の提示や国が公開している資料を引用するのもおすすめです。
誓約書の作成
雇用契約の際に競業避止に関する誓約書を取り交わすのも有効な手段です。
誓約書には、競業行為となる内容や期間、地域や違反した際のペナルティなどを明確に記載します。
契約書に関しては無効になるような内容であれば意味がありません。過去の判例をもとに有効な内容を作成してください。
その際には、誓約書の内容を理解してもらうことも大切です。
具体的な違反例や法的影響についてわかりやすく説明することも同時に実施し、理解してもらった上で署名捺印をしてもらってください。
遵守事項を記載した書面を見やすい場所に掲示すると、周知に役立ちます。
競業避止義務に違反した社員への対応

競業避止義務に違反した人がいた場合、企業はその相手に対してペナルティを課せられます。具体的にどういった対応をとることができるのか、解説していきます。
競業行為の差し止め請求
まず、競業避止義務に違反する行為が発覚したら、その行為の差し止めを請求できます。
一般的には、企業側が任意交渉を行って違反となる行為を停止するように求めることができます。
相手が応じない場合には法的措置を検討でき、訴訟や仮処分手続きを実施すると、裁判所の判決によって役員や従業員に行為の禁止を求めることが可能です。
訴訟手続きは判決が出るまでに1~2年ほどの期間を要するため、半年ほどの期間で判決が決まる仮処分手続きを要求するケースが多い傾向です。
退職金の減額
就業規則に違反した際の罰則として退職金の減額や不支給といった内容を定めていれば、違反した人に対してペナルティを適用できます。
しかし。規則によって定めていたとしても、必ずペナルティが課せられるわけではありません。
処分に値するだけの重大な違反行為として認められる必要があります。
損害賠償の請求
従業員や役員による競業避止義務違反によって事業に損害が出れば、違反者に対して損害賠償を請求することが可能です。
損害額に関しては事例によって異なりますが、違反行為によって失った利益や直接的な損害の補填を違反者に求められます。
契約書に違約金についての記載があれば、その条項に基づいて金額が請求されます。
損害賠償については、専門家でもある弁護士に相談して適切な額の請求となるようにしてください。
懲戒処分
在職中に違反行為があった場合には、就業規則に対する違反として懲戒処分を実施することも可能です。
懲戒処分には、以下のような内容があります。
-
- 注意
- 警告
- 減給
- 降格
- 解雇
懲戒処分の内容や程度は、あらかじめ詳細を規定に記しておくようにしてください。
そして、その違反内容や重大性、事前の警告の有無、従業員の勤務態度などを踏まえた上で処分内容を決定します。
重大な違反では懲戒解雇も視野に入れますが、懲戒処分の対象となる従業員から退職願を出された場合には、すぐに認めないようにしましょう。
万が一認めてしまうと、懲戒処分の手続きを進めるのが難しくなってしまいます。その場合は、退職を認めずに退職通知期間を考慮した上で処分を行うか判断してください。
まとめ・トラブルを未然に防ぐためにも適切な対策を講じよう
従業員や組織に対して課す義務となり、自分の会社の利益を保護するために競業避止を義務付ける契約を締結してください。
有効だと判断されるためには、就業規則への明記や誓約書の提出、教育の徹底などが求められます。
もし、違反した人がいれば退職金の減額や懲戒処分といったペナルティを課せられますが、手続きや裁判が必要になるケースもあり、企業側も負担が増えてしまいます。
そのため、違反行為が起きないように対策をとることが重要です。義務について正しく理解し、社内周知の徹底を心掛けてください。
創業手帳(冊子版)では、競業避止義務に関する情報以外にも、契約や副業など、事業運営に関わる様々な情報を提供しています。幅広い情報を理解するために役立つ内容なので、ぜひチェックしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)