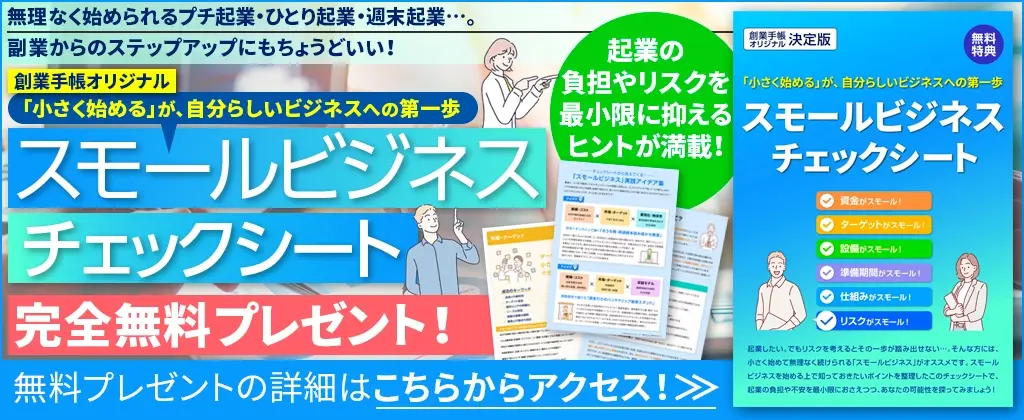田舎の起業で儲かるスモールビジネス成功例|地方起業アイデア12選
田舎・地方だからこそ儲かる商売、ビジネスアイデアを12選ご紹介!田舎のスモールビジネス成功例も

「田舎・地方でも起業したい」という方も少なくないでしょう。むしろ、田舎・地方だからこそできる起業のスタイルもあります。本記事では、田舎で起業したいという方向けに、田舎で起業できるスモールビジネスのアイデアと、実際の成功例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
田舎・地方でスモールビジネスを始めるときに大切なのは、「小さくても成り立つ仕組み」をしっかり作ることです。創業手帳では、副業や地域での事業を始める前に確認しておきたいポイントをまとめた 「スモールビジネスチェックシート」を無料配布しています。地方での新しい挑戦を考えている方は、ぜひご活用ください。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
田舎・地方のスモールビジネス起業成功例2選

田舎・地方でスモールビジネスを起業して成功した事例をご紹介します。
ブルーベリーファームおかざき(ブルーベリー観光農園)
ブルーベリー観光農園経営者の畔柳茂樹氏は、年間わずか60日の営業で2000万円以上の収益を上げるブルーベリー観光農園を経営しています。一般的に「キツい・汚い・危険」というイメージのある農業において、効率的なビジネスモデルを確立しました。
このビジネスの特徴は、ブルーベリーの特性と観光農園という業態を巧みに組み合わせている点です。ブルーベリーは病虫害に強く栽培が容易な上、水やりや肥料の管理も自動化が可能です。一方で、最大の課題である収穫の手間を、来園者に「観光体験」として提供することでビジネスモデル化しました。
これにより、農園側は収穫の人件費を削減でき、来園者は収穫を楽しみながら新鮮なブルーベリーを手頃な価格で楽しめるという、双方にメリットのある仕組みを作り上げています。
また、年間60日という限定的な営業期間は、他の収益機会を創出することを可能にしています。畔柳氏は空いた時間を活用して、ブルーベリー農園の始め方を教えるオンラインセミナーの開催や、カフェ経営、加工品販売など、複数の収益源を確立しています。
農業未経験者でも始められ、効率的な運営が可能なこのビジネスモデルは、新しい農業の形として注目を集めています。
レストレーション(グランピング施設運営)
グランピング施設運営会社「レストレーション」の森脇暉社長は下関出身で、地元を盛り上げるべく、下関でグランピング施設「グランドーム下関」を運営しています。
森脇社長は、都銀での経験を経て起業を決意。クラウドファンディングを活用した最初の事業は苦戦しましたが、グランピング事業がコロナ禍で好調だったことから、この分野に経営資源を集中。広島で第1号店を開業し、現在は広島県内3施設と下関の計4施設を運営するまでに成長しました。
2024年3月にオープンした「グランドーム下関」は、関門海峡を一望できる立地を活かし、バーベキューやサウナなどの設備を備えた施設です。地元・下関の魅力を国内外に発信することを目指しており、社名の「レストレーション」には「維新」の意味が込められています。
森脇社長は、グランピングを「食や風景、その土地の魅力を表現するプラットフォーム」と位置づけ、地方での事業価値の高さを強調しています。地元下関の活性化への思いを持ちながら、まずは他地域で実績を積んでから地元に進出するという戦略的なアプローチを取り、成功を収めています。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
田舎・地方だからこそスモールビジネスがおすすめ!田舎で起業するメリット
田舎でスモールビジネスを起業するメリットをご紹介します。
コストが安い
田舎では物件費用が大幅に抑えられます。都心部と比べて家賃・土地代が30-50%低く、光熱費も比較的安価です。人件費も都市部より低めに設定できるため、事業の初期投資と運営コストを削減できます。これは利益率の向上につながり、事業失敗のリスクも軽減されます。なおかつ、経費が少なく済むため新規事業への参入や事業拡大もしやすい環境といえます。
地域密着型の事業展開ができる
田舎で地域密着型サービスを展開すれば、顧客との頻繁な対面接触により深い信頼関係を築けます。日々の会話やフィードバックから顧客ニーズを詳しく理解でき、それに応じたサービス提供が可能です。また、田舎特有の口コミ文化により、良質なサービスの評判は地域全体に素早く広がります。これにより高額な広告費をかけることなく、安定した顧客基盤を構築できます。
競合企業が少ない
都市部にはビジネスチャンスを求めて起業家も集まりますが、田舎は市場規模が小さいこともあり、競合企業が少ないため、特定の商品やサービスを独占的に提供できます。これにより市場価格の決定権を持ち、適切な利益を確保できます。また、低コストでの事業開始が可能なため、新しいビジネスアイデアの試験的な展開にも適しています。成功すれば、そのビジネスモデルを都市部へ展開することも検討できます。
田舎・地方だからこその独自価値
田舎特有の地域資源を活用することで、独自の商品やサービスを生み出せます。地元の農産物を使った加工品、伝統工芸品のモダンなアレンジ、地域の観光資源と組み合わせた体験サービスなど、都市部では提供できない価値を創出できます。これらは観光客や都市部の消費者にとって魅力的な商品となり、高付加価値化が可能です。
行政からの支援も受けやすい
田舎のビジネスは地域活性化に直接貢献するため、行政からの支援を受けやすい環境があります。創業支援や設備投資の補助金、低金利融資などの制度を活用できます。また、地域住民との密接なつながりにより、従業員の採用や地域内での宣伝活動がスムーズです。住民自身がビジネスの支援者となり、地域全体で事業の成長をバックアップする体制が整いやすいのが特徴です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
田舎だからこそおすすめ!起業できるおすすめのスモールビジネスアイデア12選

田舎で起業できるおすすめのスモールビジネスアイデアをご紹介します。
民泊
田舎で起業できるスモールビジネスとして、民泊がおすすめです。
地方での民泊は、初期投資を抑えられるのが最大の魅力です。都会と比べて物件費用が安価で、空き家を活用できるため、大きな資金がなくても始められます。
また、地方ならではの観光資源や体験価値が強みになります。自然体験や農業体験、伝統文化など、都会では提供できない価値を提供できるため、差別化がしやすいのです。特に近年は、観光客がこのような本物の体験を求める傾向が強まっています。
インターネットの活用で、地理的なハンディキャップも解消できます。オンラインでの予約管理や情報発信で、世界中の観光客にアプローチが可能です。特にインバウンド需要の取り込みにも期待が持てます。
さらに、最近のワーケーション需要の増加も追い風となっています。地方の静かな環境は長期滞在に適しており、新たな顧客層を開拓できる可能性があります。
ワーケーション施設の運営
コロナ禍以降、企業のリモートワーク導入が加速し、場所を問わない働き方が一般化しています。特に都市部の企業や個人事業主が、静かな環境での業務や気分転換を求めてワーケーションを検討するケースが増加しています。
物件取得のコストが低いことも大きな魅力です。地方では都市部と比べて不動産価格が安く、空き家などの活用も可能です。そのため、比較的少ない初期投資で事業を始められます。改修費用についても、行政の補助金や助成金を活用できる可能性があります。
地方ならではの付加価値を提供できることも重要です。仕事の合間に自然体験や農業体験、地域の食文化を楽しめるなど、都市部のコワーキングスペースにはない魅力を打ち出せます。この差別化により、プレミアム価格での提供も可能になります。
また、長期滞在型の需要が見込めるため、安定した収益が期待できます。通常の観光と異なり、仕事をしながらの滞在となるため、1週間から1ヶ月といった長期の利用につながりやすく、客単価を高めることができます。
さらに、地域活性化に貢献できるビジネスとして、行政からの支援や地域住民との協力も得やすい点も特徴です。施設利用者の消費活動は地域経済への波及効果も期待でき、新たな関係人口の創出にもつながります。
野菜や農作物の栽培・販売
田舎は土地の確保が有利です。都市部と比べて農地の取得や賃借のコストが低く、広い面積を確保しやすいのが特徴です。そのため、野菜や農作物を栽培する土地がゲットしやすいです。遊休農地の活用も可能で、地域の課題解決にもつながります。
差別化が図りやすいことも大きな魅力です。珍しい野菜や高付加価値作物(ハーブ、エディブルフラワー、有機野菜など)の栽培に特化することで、都市部のレストランや専門店との直接取引が可能になります。特に、その土地でしか栽培できない特産品は、独自の市場価値を持ちます。
販路についても、インターネットの普及により地理的なハンディキャップが解消されています。ECサイトでの直販や、産地直送の定期便サービス、ふるさと納税の返礼品など、全国規模での販売が可能です。また、地域の直売所や道の駅との連携も効果的です。
さらに、地域の農家や先輩就農者からノウハウを学べる環境があることも利点です。技術指導や経験の共有を通じて、スムーズな事業立ち上げが可能になります。また、新規就農者向けの補助金や支援制度も充実しています。
インバウンド需要に特化したレストラン
その土地ならではの食材や郷土料理を提供することで、都市部のレストランにはない価値を提供できます。また、外国人観光客は日本の地方文化や本物の食体験を求める傾向が強く、独自の魅力を打ち出しやすいのです。
競争環境が有利です。都市部と比べて同様のサービスを提供する競合が少なく、インバウンド向けに特化したレストランはさらに希少です。また、地方では物件費用や人件費が比較的安価なため、コスト面でも優位性があります。
SNSによる情報発信で集客が可能です。インスタグラムなどのSNSを活用することで、外国人観光客に直接アプローチできます。写真映えする料理や店内装飾を工夫することで、口コミでの拡散も期待できます。
地域全体の活性化にも貢献できます。インバウンド観光客の誘致は地域の重要課題となっており、行政からの支援や地域の観光施設との連携も期待できます。また、地元の農家や生産者との取引を通じて、地域経済への貢献も可能です。
宿泊施設や観光施設との連携も有効です。近隣のホテルやゲストハウス、観光スポットと協力することで、安定した集客につながります。外国人観光客の動線を意識した立地選びも重要なポイントとなります。
地域資源を活かした食品加工
田舎なら、地域の農産物や特産品を直接生産者から仕入れることができ、新鮮で質の高い原材料を比較的低コストで確保できます。また、規格外品の活用など、都市部では難しい取り組みも可能です。
次に、他地域との差別化が図りやすいことが挙げられます。その土地ならではの特産品や伝統的な製法を活かすことで、独自性の高い商品開発が可能です。特に地方の食材や加工品は、都市部の消費者にとって希少性があり、高い付加価値を付けることができます。
販路についても、ECサイトやふるさと納税を活用することで、地理的なハンディキャップを克服できます。特にふるさと納税は、全国規模での販路開拓と認知度向上に効果的です。
さらに、初期投資を抑えられる点も魅力です。都市部と比べて設備や場所の確保にかかるコストが低く、小規模からスタートして徐々に事業を拡大することが可能です。また、地域の補助金や支援制度を活用できる可能性も高くなっています。
シニア向けサービス
地方でのシニア向けサービス事業は確実な需要が見込めます。地方は高齢化が進んでおり、シニア層の人口比率が高く、サービスを必要とする層が多く存在します。特に、買い物代行や家事支援、デジタル機器のサポートなど、日常生活に関連したサービスへのニーズが高まっています。
競争が比較的少ないことも魅力です。都市部に比べてサービス提供者が少なく、新規参入の余地が大きいため、市場に入りやすい環境にあります。
また、地域コミュニティとの関係性を活かしやすく、口コミでの顧客獲得が期待できます。シニア層は特に信頼関係を重視するため、地域に根差したサービスは受け入れられやすい傾向にあります。
さらに、初期投資を抑えられるのも特徴です。人的サービスが中心となるため、大きな設備投資が不要で、小規模な資金でスタートできます。行政の補助金や支援制度を活用できる可能性も高く、事業リスクを低く抑えられます。
地域特性を活かした体験型サービス

地域特性を活かした体験型サービスは、その土地ならではの価値を提供できることが最大の強みです。農業体験、森林セラピー、伝統工芸体験、郷土料理作りなど、都会では体験できないコンテンツを提供できます。特に近年は、本物の体験や地域との交流を求める観光客が増加しており、この需要を取り込むことができます。
初期投資を抑えられることも魅力です。地域にある既存の資源(農地、山林、古民家など)を活用できるため、大規模な設備投資が不要です。また、地域の職人や農家と連携することで、専門的な知識や技術を持つスタッフの確保も容易になります。
インターネットを活用した集客も効果的です。SNSでの情報発信やオンライン予約システムの導入により、全国の観光客にアプローチが可能です。特にインスタ映えするような体験プログラムは、口コミでの拡散も期待できます。
地域との協力関係も構築しやすい点が特徴です。体験サービスは地域の活性化につながるため、行政からの支援や地域住民との協力が得やすくなっています。また、観光施設や宿泊施設との連携により、安定した集客も見込めます。
ペット関連ビジネス
田舎は広いスペースを確保できることが最大の強みです。都市部では実現が難しい大型のドッグランや、ゆとりある空間のペットホテル、屋外トレーニング施設など、充実した設備を整えることができます。土地や建物の賃料も都市部と比べて安価なため、初期投資を抑えながら質の高いサービスを提供できます。
需要の高まりも追い風となっています。コロナ禍以降、ペット飼育世帯が増加しており、地方でもペットに関連したサービスへのニーズが高まっています。特に、ペットと一緒に過ごせる空間や、しつけ教室、トリミングなど、専門的なサービスの需要が伸びています。
競争環境も有利です。都市部と比べてペット関連サービスの提供者が少なく、質の高いサービスを提供することで、地域でのシェア獲得が見込めます。また、地方では口コミの効果が高く、信頼できるサービスとして認知されれば、安定した顧客基盤を築くことができます。
さらに、観光との連携も可能です。ペット同伴の旅行者向けに、一時預かりサービスや、ペットと一緒に楽しめるアクティビティを提供することで、新たな収益機会を創出できます。近隣の観光施設や宿泊施設との協力関係を築くことで、安定した集客も期待できます。
里山・空き家管理代行サービス
里山・空き家管理代行サービスも確実な需要が見込める点が大きな強みです。地方では高齢化や人口減少により、山林や農地、空き家の管理が行き届かない物件が増加しています。特に都市部に住む不在地主からの需要が高く、定期的な見回りや管理作業の依頼が期待できます。
次に、参入障壁が比較的低いことも魅力です。基本的な管理作業に必要な道具があれば始められ、大規模な設備投資は必要ありません。また、管理のノウハウは地域の先輩事業者から学ぶことができ、徐々にスキルを高めながら事業を拡大できます。
収益源の多様化も可能です。基本の管理作業に加えて、間伐材を活用した木工品製作、薪の販売、有害鳥獣の対策、古民家の活用提案など、様々な付加サービスを展開できます。また、行政の補助金や支援制度を活用できる可能性も高く、事業の安定性を高めることができます。
地域との信頼関係も築きやすい点が特徴です。里山や空き家の管理は地域の景観保全や防災にも貢献するため、行政や地域住民からの支持を得やすく、口コミでの顧客紹介も期待できます。
移住コンサルティング

移住コンサルティングサービスは、市場の成長性が大きな魅力です。コロナ禍以降、地方移住への関心が急速に高まっており、特にワーケーションの普及により、都市部から地方への移住を検討する人が増加しています。この流れは一時的なものではなく、働き方改革やデジタル化の進展により、今後も継続すると見込まれています。
参入コストが低いことも重要なポイントです。オフィスは自宅や空き家を活用でき、必要な設備も最小限で済むため、大きな初期投資なく始められます。コンサルティングの価値は、地域の情報や人脈、経験に基づく知見にあるため、地方在住者が強みを発揮できる事業といえます。
収益モデルの多様化も可能です。基本の移住相談に加えて、物件紹介の仲介手数料、移住後のサポート契約、オンラインセミナーの開催、地域の空き家バンクの運営受託など、様々な収入源を確保できます。また、行政の移住支援事業との連携も期待できます。
特に、地域との信頼関係を持つ地元在住者だからこそ提供できる価値があります。物件情報だけでなく、地域コミュニティへの橋渡し、生活情報の提供、教育環境の紹介など、移住検討者が本当に必要とする情報やサポートを提供できます。
除雪・庭木剪定サービス
除雪・庭木剪定サービスも確実な需要が見込めます。特に積雪地域では、高齢化に伴い除雪作業を必要とする世帯が増加しています。また、庭木の管理も高齢者には負担が大きく、定期的なサービスニーズがあります。このように、季節を問わず安定した需要が存在することが大きな強みです。
競争が比較的少ないことも魅力です。地方では、専門的なサービス提供者が不足しがちです。特に除雪作業は、適切な機材と技術が必要なため、新規参入の余地が大きく、地域に根差したサービスとして展開できます。
季節に合わせた収益構造を構築できます。冬季は除雪作業、春から秋は庭木の剪定や草刈りといった形で、年間を通じて収入を確保できます。また、定期契約による安定収入も見込めます。
さらに、口コミでの顧客獲得が期待できます。特に地方では、信頼できるサービス事業者の情報は地域コミュニティを通じて広がりやすく、一度信頼を得られれば、継続的な取引につながります。
ジビエ加工・販売
ジビエ加工・販売サービスは地域課題の解決と収益が両立できます。獣害は地方の深刻な問題であり、捕獲した野生動物の有効活用は社会的にも求められています。そのため、行政からの支援や補助金を受けやすく、地域からの協力も得やすい事業です。
市場の成長性も魅力です。近年、ジビエ料理への関心が高まっており、特に都市部のレストランや専門店からの需要が増加しています。また、ジビエの加工品は高付加価値商品として、ECサイトやふるさと納税の返礼品としても人気があります。
地方ならではの優位性があります。食肉処理施設を設置する際、都市部より低コストで広いスペースを確保できます。また、猟師との連携も取りやすく、新鮮な原材料の安定調達が可能です。
さらに、事業の多角化も可能です。食肉処理だけでなく、加工品の開発・販売、ジビエ料理の提供、解体体験教室の開催など、様々な収益機会を創出できます。また、観光との連携により、地域の特色ある産業として発展させることもできます。
「田舎で小さく始めて、持続的に続けられるか?」そんな不安を解消するために、無料特典 「スモールビジネスチェックシート」をご用意しました。
限られた資源でも利益につなげるための視点や、失敗を防ぐためのチェックポイントを整理しています。ぜひ、あなたのスモールビジネスに役立ててください。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
田舎・地方だからこそ使える補助金・助成金
田舎・地方だからこそ使える補助金・助成金をご紹介します。
地方創生起業支援事業
地方創生起業支援事業は、地域課題解決のための社会的事業の起業を支援する制度です。都道府県が選定する執行団体が、最大200万円(経費の1/2)の助成と伴走支援を提供します。対象は子育て支援、地域産品活用、買い物弱者支援、まちづくりなど、地域課題に応じた幅広い分野です。
申請には主に2つの対象があります。新規起業の場合は、東京圏外または東京圏内の条件不利地域で起業し、補助事業期間内に開業手続きを行い、起業地に居住(予定含む)することが条件です。事業承継・第二創業の場合は、同じく東京圏外または条件不利地域で付加価値の高い分野で実施し、期間内に手続きを完了し、事業実施地域に居住(予定含む)することが求められます。
移住支援金
東京23区から東京圏外への移住支援金制度では、在住または通勤者が地方へ移住し起業や就業を行う場合、都道府県と市町村が共同で交付金を支給します。世帯の場合は最大100万円(18歳未満の子一人につき最大100万円加算)、単身は最大60万円が支給されます。東京圏内の条件不利地域への移住も対象となります。
ローカル10,000プロジェクト
ローカル10000プロジェクトは総務省が主導する地域ビジネス創出支援制度で、民間事業者の初期投資に対して補助金を交付し、地域経済の活性化と雇用創出を目指します。
補助上限額は最大5,000万円で、地域単独事業でも最大1,500万円が交付されます。
補助対象は地域密着型起業の初期投資費用全般で、地域単独事業では広告宣伝費や商品開発費などのソフト経費も含まれます。
なお、本制度の利用には地域金融機関からの融資、地域活性化ファンドからの出資、または民間クラウドファンディングの活用が必須条件となっており、その融資額または出資額を上限として国費および地方費から交付を受けることができます。
日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫の新規開業資金は、新規事業者向けの融資制度で、設備購入費や事業運営費用をカバーします。
融資上限は7,200万円(うち運転資金4,800万円)で、返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内です。元金据置期間は両資金とも2年以内で、基準利率が適用されますが、条件により特別利率の適用も可能です。
日本政策金融公庫の新創業融資制度が2024年3月で廃止に!今後の資金調達方法や審査に通過するコツを解説
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
田舎・地方でスモールビジネスのアイデアを実践して起業しよう

以上、田舎で起業できるスモールビジネスアイデアをご紹介しました。
創業手帳では、地方自治体で出されている補助金・助成金について、登録された都道府県の情報のみを月2回メールで配信する「補助金AI」を無料でご利用いただけます。また経営者がよく活用されている補助金・助成金について厳選して解説した「補助金ガイド」も無料で配布しています。ぜひこちらもあわせてご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。