シニアマーケティングとは?重要視される理由や進め方、成功事例などをご紹介
シニアマーケティングの需要に対応しよう!

シニア層の増加をきっかけとして、幅広い分野でシニアマーケティングが注目されています。
平均寿命が延びて健康的なシニアが増えれば、これからも大きな需要が期待されます。
ここではシニアマーケティングの意味や導入する意義のほか、シニアマーケティングをスタートする時に押さえておきたいポイントをまとめました。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
シニアマーケティングとは
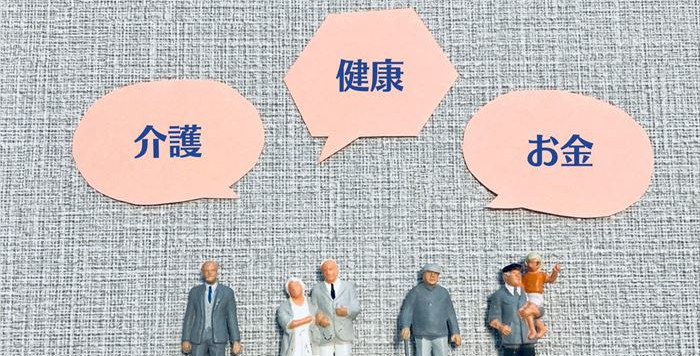
シニアマーケティングとは、シニア層を対象としたマーケティングを指す言葉です。「シニア」自体は英語で「年上」や「上位」を指します。
日本でシニアといった時には、高齢者ととらえるシーンも多いかもしれません。実は、高齢者に明確な基準はなく、企業や機関によって定義が違います。
世界保健機関(WHO)の基準では、65歳以上の人が高齢者とされています。内閣府や総務省の統計で採用されているのは高齢者を65歳以上とした定義です。
高齢者医療制度では、65歳から74歳までは前期高齢者、75歳以上は後期高齢者です。
上記のようにシニアと簡単にいっても、その定義や範囲は人によって違います。
シニアマーケティングを導入する時には、そこで使うシニアの定義や範囲も明確にしておいてください。
ここでは65歳以上をシニアとしてシニアマーケティングについて紹介しています。
シニアマーケティングが重要になっている理由

シニアマーケティングは、これから多くの企業で導入がすすめられると予想されています。
シニアマーケティングが重要視されるようになった理由のひとつが、シニア層の増加です。
シニアの割合は増加を続け、第2次ベビーブーム期に生まれた世代(1971~1974年)が65歳以上となる2040年には国民に3人にひとりがシニアであるといわれています。
割合が増えるとともに、2030年頃には60歳以上の消費が110兆円を超えるとも試算されています。
一方で日本全体の人口は減少しているため、今後は多くの市場が規模縮小すると考えなければいけません。
これから人数も割合も増加するシニアマーケットは企業にとってますます重要になると考えられます。
シニアマーケティングを取り入れるべき業界
シニア市場が急速に拡大する中で、特に拡大スピードが早いのが生活産業です。
シニアの割合が増加するとともに健康寿命も伸びて、健康でアクティブなシニアが増加しています。
経済的にも安定しているため、旅行やスポーツといった娯楽分野での拡大が注目されています。
ソニー生命がおこなった「シニアの生活意識調査2024」によると「現在の楽しみ」についての回答が1位が「旅行」で次いで「テレビ/ドラマ」、「グルメ」でした。
さらに「旅行」と回答した割合は、39.9%から45.3%と大きく上昇しています。
また、「シニアがこの1年のうちに体験してよかったこと」についての回答は、1位が「旅行」、2位は「コンサート・ライブ」、3位「登山・ハイキング」、4位が「ゴルフ」、5位が「温泉・銭湯」といった外出をともなうアクティビティが中心です。
シニアは、仕事を退職して余暇が生まれた人も多く、時間をより充実したものにしようという意欲が感じられます。
こういった需要を取り込むためにも、旅行やイベント、アウトドアや飲食店はシニアマーケティングをビジネスに取り入れる施策が有効な戦略です。
ターゲットとなるシニア世代の種類と特徴

シニア世代とまとめたとしても、様々なタイプがありアプローチも異なります。それぞれのシニアの特徴や傾向を把握することがシニアマーケティングのポイントです。
以下にシニアのタイプと特徴を紹介します。
アクティブシニア
年齢にとらわれることなく、アクティブに挑戦を続けるタイプがアクティブシニアです。
アクティブシニアの多くは経済的な余裕があり、趣味や健康に多くのお金を消費します。
消費にも積極的なため、シニアマーケティングにおいてターゲティングされることが多いシニア層です。
ディフェンシブシニア
ディフェンシブシニアは、活動する意欲はあっても消費にはやや消極的なシニアをいいます。
シニア層の中でも人口が多く贅沢や娯楽よりも生活必需品に関心を持つ傾向があります。
そのため、大きな出費をともなう娯楽よりも、日常の不便や不満を解消できる商品、サービスの提供が有効です。
ギャップシニア
ギャップシニアは、介護状態にないものの健康状態や将来への不安感が強いシニアをいいます。
活発な運動などできることが減っていて不安や孤独を感じやすいシニア層です。
積極的に情報収集をする意欲が少なく趣味に消極的なため、日常生活の悩みを解消できるようなものに関心を持ちます。
ケアシニア
ケアシニアは、要介護状態にあるシニアをいいます。ケアシニアは基本的な生活において家族や医療、介護スタッフからのサポートが必要です。
介護施設に入居していたり、商品やサービスの利用はできても判断は第三者が行うのが一般的になります。
介護や福祉サービスのターゲット層として設定されることが多いシニア層です。
シニアマーケティングの進め方

シニアが増えているといっても、やみくもにビジネスを展開しても成功は難しいかもしれません。
シニア市場を効力するために必要なシニアマーケティングの進め方を紹介します。
1.ターゲットを明確にしてペルソナを設計する
シニアマーケティングをスムーズに進めるために、ターゲットを明確にしてペルソナを設定します。
シニアに対する固定観念は強く、思い込みでマーケティングすると、実際のシニアとのギャップができてしまうことがあるのです。
シニアとひとくくりにするのではなく、年齢や性別、家族構成や仕事など明確にターゲティングします。
前述した4つのシニアのタイプも正確に把握してペルソナを設計してください。
2.価値観やライフスタイルなど顧客の理解を深める
設計したペルソナが何を求めているのか、どのような訴求が効果的なのかを把握するために、価値観やライフスタイルの理解を深めます。
理解を深めるためには、シニアの生の声を参考にしてください。実際にヒアリングするほか、リサーチ会社を活用する方法もあります。
具体的な例を挙げると、ケアシニアの理解を深めるには介護サービスを提供している会社にヒアリングするのが効果的です。
3.訴求方法や宣伝媒体を選ぶ
把握したペルソナに対して、どのような訴求方法が適しているのか宣伝媒体を選びます。
新聞や雑誌、折込チラシのほか、テレビやラジオ、交通広告などが一般的に使われています。
そのペルソナが活用している媒体を調べることで、よりターゲットに効果的にアプローチ可能です。
4.イベントやコンテンツを作成する
商品やサービスの訴求には、イベントやコンテンツが使われます。
オフラインのイベントとしては、「シニア向け○○体験会」「○○実食会」といった販促イベントは対面で商品の魅力を訴求できます。
イベントを開催することによって、シニアと直接話ができる点もポイントです。シニアの生の声を収集して、商品やサービスの開発したり改善したりするために役立ちます。
スマートフォンが普及しウェブ媒体を使いこなすシニア層も増えている一方で、スマートフォンや携帯電話に苦手意識を持つシニア層もいます。
両方の需要を取り込むために紙媒体のコンテンツとウェブ媒体のコンテンツの両方を用意しておいてください。
5.PDCAサイクルを回す
PDCAサイクルは、「Plan(計画)から始まって、Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の一連のプロセスをいいます。
このPDCAサイクルを繰り返すことによって、継続的に業務改善や効率化が可能です。
PDCAサイクルは、商品やサービスの課題や足りない部分を見つけるためにも有効です。ペルソナの設計が甘くないか、仮説が間違っていないかもチェックしながらサイクルを回してください。
シニアマーケティングを成功に導くための5つのポイント

シニアマーケティングは、コツをつかむまでは利益につながるまでに時間がかかってしまいます。
ここでは、シニアマーケティングを成功に導くために押さえておきたいポイントをまとめました。
シニア層の価値観を理解する
シニア層に限らず、世代によって特有の価値観があります。
価値観がわかるとどういったものに興味関心を持つか、消費傾向がどのようなものかといった方向性もわかります。
シニア層は、時間とお金に余裕がある人が多く、ソニー生命がおこなった「シニアの生活意識調査2024」でも現在の楽しみとして「旅行」がトップでした。
また、身体の衰えを感じはじめるタイミングでもあるため、健康や体力維持への関心も高い傾向があります。
データを活用してシニアの価値観を理解することが企業の戦略に役立ちます。
シニア層に考慮したクリエイティブを作る
同じクリエイティブなものを作るのであっても、シニアをターゲットにした時にはシニア層に対する配慮が必要です。
ただし、シニア層を考慮するといっても「高齢者向け」や「シニアへ」といった表現を使うと敬遠されてしまうことがあります。
「シニア」と表記すると自分が対象ではないと感じる場合もあるので「65歳以上」など年齢を記載する方法も検討してください。
また、シニア層に利用しやすいデザインとして、文字の大きさや色にも配慮します。商品やサービス説明は専門用語は避けて平易な言葉にします。
文字は大きく読みやすい書体にしてください。背景と文字はコントラストが際立つような色遣いを意識すると見やすくなります。
オフラインとオンラインを組み合わせる
シニア層に対する固定観念としてよくあるのが、シニアはインターネットは使わず対面でのコミュニケーションがメインであるというものです。
しかし、これは思い込みで実際にはインターネットを使いこなすシニアは決して珍しくありません。
総務省の「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、ソーシャルメディア系サービスの利用率として、60代の86.3%がLINEを使用しているほか、YouTubeは66.3%、X(旧Twitter)を19.6%が利用していると回答しています。
インターネットやソーシャルメディアを使うシニア層はこれからも増加すると予想されます。
一方で、オフラインの媒体も重要な地位を占めている点も無視できません。新聞や広報誌といったアナログ媒体は、シニア層からの支持も厚く長く愛されています。
オンラインかオフラインかのどちらかに偏るのではなくバランスを考えて両方を活用してください。
納得感を与えて消費行動を促す
シニア層は消費に対して慎重になりがちで、与えられる情報が信頼できるかどうかをよく吟味します。
口コミやレビューといった第三者の意見を参考にすることが多いので、マーケテイングへの導入がおすすめです。
口コミやレビューを活用することで、商品やサービスへの信頼度が上がるほか、自分が使った時のイメージもしやすくなります。
納得感を与えることで消費行動につなげられるようにしてください。
シニア層の子ども世代にもアプローチする
シニアマーケティングを成功させるためには、シニア層の子ども世代へのアプローチも重要です。
特にケアシニアだと、シニア自身が自分で商品やサービスを探せないケースもあります。シニアだけでなくシニアの息子、娘世代へのアプローチも検討してみてください。
シニア層の子どもにとって、どういうサービスが支持されるかを考えてアプローチすることが大切です。
シニアマーケティングの成功事例3選

シニアマーケティングは、多くの企業で導入されています。ここではシニアマーケティングの成功事例を3つ紹介します。
象印マホービン株式会社
象印マホービン株式会社が提供する「みまもりほっとライン」は、電気ポットを使用したシニアの見守りサービスです。
シニアが無線通信機内蔵のポットを使用すると家族が使用状況を受け取る仕組みです。
このサービスは、シニアの家族が遠方からでも変化に気づきたいというニーズから生まれました。
シニアにとって日常的に使いやすい商品とシニア層の子どもへのアプローチがうまくいった事例です。
株式会社ポケモン
スマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」を提供する株式会社ポケモンは、シニア層への普及も進めています。
運動不足に悩むシニアに向けて、雑誌やウェブ媒体で楽しみながら運動できることを訴求しました。
さらに、シニアマーケティングの中でゲームを利用するために必要なアカウント取得が難しいことがわかり、Googleアカウントの取得方法やスマートフォンの使い方を解説したガイドを作成しました。
その結果、多くのシニア層が「ポケモンGO」を利用しています。
イオンリテール株式会社
イオンリテール株式会社は、シニアの課題解決に向けた様々な取組みを提供しています。
ショッピングモール内をウォーキングコースとする取組みのほか、ラジオ体操といったイベントも開催中です。
加えて、リハビリデイサービス事業「イオンスマイル」を展開、さらにパッシブシニア向けに小分けのお惣菜やスイーツを販売しています。
これらのサービスはオンラインの告知だけではなく、チラシを配布するなどインターネットを使わないシニアにも対応しています。
地域のインフラとして多様なシニア層にアプローチしている事例です。
まとめ・価値観の理解がシニアマーケティング成功の鍵
シニア層は今後も増加が予想され、シニアマーケティングの質でビジネスの成否が決まるケースもあります。
シニアマーケティングを成功させるためには、シニア層の特性や需要を正しく把握しなければいけません。
シニア層の取込みは、新しいアイデアやビジネスの切り口になることもあります。成功事例も参考にして、企業に様々な価値観を取り込んでください。
創業手帳(冊子版)はマーケティングについての課題を解決する方法を多数掲載しています。ビジネスの手助けに創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)




































