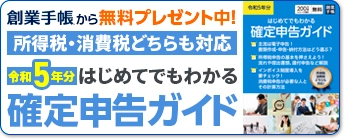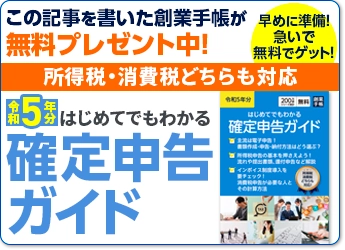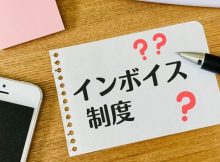消費税の仕訳方法とは?勘定科目や具体的な仕訳例などを徹底解説
消費税の勘定科目や仕訳方法をチェック!
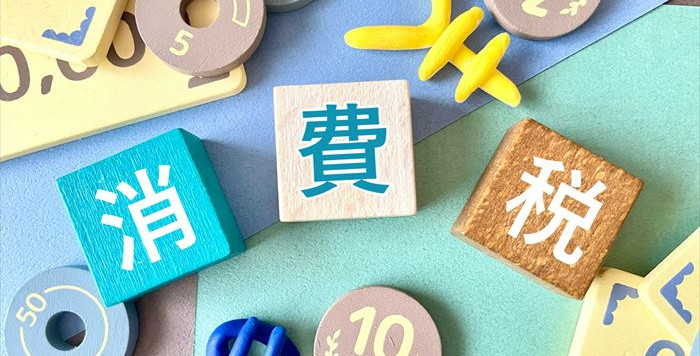
企業が事業を行っていると必ず税金にかかわる処理が発生します。
中でも日常的に発生する消費税は、発生時に適切に処理できるようにあらかじめ自社のルールを定めておくことが大切です。
消費税の会計処理で使う仕訳方式には2種類あります。それぞれメリット・デメリットがあるので、特徴を理解してから選択するようにしてください。
消費税にかかわる勘定科目や仕訳方法についてまとめました。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
消費税の仕訳方式は2種類

消費税の納税義務がある課税事業者は、取引きで発生した消費税の金額を把握して会計処理しなければいけません。
消費税の仕訳方法には2種類あり、企業は処理の簡便さや事業規模、業種などから選択しています。
ここでは税込経理方式と税抜経理方式のそれぞれの概要をまとめています。
税込経理方式
税込経理方式は、仕入れや売上といった取引きで商品、サービスの価格と消費税を合わせた金額で記帳する方法をいいます。
つまり、商品を売上げた時に発生した消費税額は「売上」に含まれ、仕入れの時に発生した消費税額は「仕入」に含めて計上します。
税抜経理方式
税抜経理方式とは、本体の価格と消費税を分けて計上する方法です。
そのため、「売上」や「仕入」に消費税は含まれません。消費税を計上する勘定科目として、「仮払消費税」「仮受消費税」などを使用します。
企業は、上記の税込経理方式を税抜き経理方式から任意で選択できます。ただし、原則として、すべての取引きで同一の方式を適用しなければいけません。
例外として売上や資産といったグループごとで方式を採用することは認められています。
これはあくまでグループごとなので、個々の取引きや固定資産ごとに異なる方式を採用することはできません。
消費税の仕訳で使用される勘定科目の種類

消費税を適切に仕訳するには、必要な勘定科目を適切に使用しなければいけません。
消費税の仕訳で使われる勘定科目は、租税公課に加えて仮払消費税と仮受消費税、さらに未払消費税と未収消費税の5つです。
それぞれの概要や使う場面を知っておいてください。
租税公課
租税公課は、確定申告で税金を計上する時に使う勘定科目です。
租税と公課を組み合わせた言葉で、租税は国に治める国税と地方に治める地方税の2つを指します。公課は地方公共団体に治める手数料や組合費を指す時に使う言葉です。
地方税で間接税に該当する消費税は、租税公課として処理します。
消費税以外にも固定資産税や印紙税、登録免許税、自動車税といった税金も事業にかかわるものは租税公課で処理を行います。
ただし、同じ税金であっても法人税や所得税は租税公課ではありません。租税公課の勘定科目を利用するのは税込経理方式を用いた場合です。
仮払消費税
仮払消費税は、税抜経理方式を選択した場合に仕入れや経費にかかった消費税に使う勘定科目です。
仕入時の仕入先に支払った代金のうち、消費税に相当する金額を仮払消費税として仕訳します。
税抜経理方式では、仮払消費税以外にも仮受消費税や未払消費税といった勘定科目も使用します。混同しないように違いを理解してください。
仮受消費税
仮受消費税は、税抜経理方式で経理処理している時に受け取った消費税に使用する勘定科目です。
商品を売上げた時、その一部は消費税なので確定申告で納税しなければいけません。
税込方式の場合では、仮受消費税は使わずに売上の中に消費税額も含めます。税抜方式では、仮受消費税を売上時に計上して処理します。
未払消費税
未払消費税は、決算で仮払消費税と未払消費税を相殺した時に支払うべき消費税がある場合に計上する勘定科目です。
未払消費税は、税込経理方式でも税抜経理方式でも使われます。
未払消費税が発生するのは、預かっている消費税が支払った消費税よりも多い時だけです。決算では流動負債の部に記載されます。
決算書類で未払い消費税をチェックすると、どれだけ消費税を支払わなければならないか把握できます。
未収消費税
未収消費税は、仮払消費税と仮受消費税を相殺した時に、還付される予定がある場合に計上する勘定科目です。
未収消費税は、貸借対照表では「流動資産の部」への計上です。確定申告をして還付を受けることになります。
税込経理方式でも税抜経理方式でも決算時に未収消費税を計上しますが、税抜経理方式では、仮受消費税・仮払消費税との間に差額が生じることがあります。
その場合、金額調整に使われるのは雑収入です。
【ケース別】消費税の仕訳の具体例

消費税は、取引きの段階ごとに発生します。ここでは税込経理方式と税抜経理方式それぞれの仕訳をケース別に紹介しています。
どういった違いがあるのか比較しながら把握してください。
売上高・仕入高に対する消費税の仕訳
まず商品を仕入れた時、売上げた時の仕訳を紹介します。商品11万円を仕入れた時と売上げた時それぞれを確認してください。
消費税10%として商品11万円の掛取引をした場合を、仕入と売上それぞれ紹介します。
〈税込経理方式・仕入〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 11万円 | 買掛金 | 11万円 |
〈税込経理方式・売上〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 11万円 | 売上 | 11万円 |
税込経理方式では、売上高や仕入高に消費税を含めます。
〈税抜経理方式・仕入〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10万円 | 買掛金 | 11万円 |
| 仮払消費税 | 1万円 | ||
〈税抜経理方式・売上〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 11万円 | 売上 | 10万円 |
| 仮払消費税 | 1万円 | ||
税抜経理方式では、消費税額を仕入や売上に含めずに仮払消費税や仮受消費税の勘定科目を使って処理します。
返品や値引きがあった時の消費税の仕訳
販売した商品やサービスの返品があったり、値引きするケースも考えなければいけません。消費税が10%の時に返品や値引きがあった時の会計処理を紹介します。
〈税込経理方式・値引・返品〉
商品11,000円の返品を受けた。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 11,000円 | 売掛金 | 11,000円円 |
〈税抜経理方式・値引・返品〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 売上 | 10.000円 | 売掛金 | 11,000円 |
| 仮受消費税 | 1,000円 | ||
値引きや返品は企業によって処理方法が違います。値引きや返品を直接差し引く方法と、仕入値引や売上値引といった別の項目として分ける方法です。
別の勘定科目を使った場合でも同じように仮受消費税や仮払消費税を差し引く処理を行います。
決算する際の消費税の仕訳
消費税は、決算で金額が確定してから納税を行います。ここでは消費税を納税する必要があるケースを紹介します。
〈税込経理方式・税金の計上〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 租税公課 | 5,000円 | 未払消費税 | 5,000円 |
税込経理方式では、消費税を租税公課として処理します。
ただし、納めるべき消費税額が確定しても、まだ消費税を納めていません。そのため、租税公課の相手科目として未払消費税を使用します。
〈税抜経理方式・税金の計上〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 仮受消費税 | 15,000円 | 仮払消費税 | 10,000円 |
| 未払消費税 | 5,000円 | ||
税抜き経理方式では、決算で仮受消費税と仮払消費税を処理します。それぞれの金額を出して差額は未払消費税として計上します。
消費税を納税する際の仕訳
消費税は確定してから期日までに支払います。納税した時の仕訳を紹介します。
〈税込経理方式・税金の納付〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払消費税 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
〈税抜経理方式・税金の納付〉
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払消費税 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
消費税納めた時には、決算で発生した未払消費税を消し込む処理を行います。
税込経理方式と税抜経理方式のどちらを選ぶべき?

消費税を納付する企業は、必ず税込経理方式と税抜経理方式からどちらかを選ぶことになります。
どちらの方式を選んでもメリット・デメリットがあります。自社にとってどちらが適しているか考えてみてください。
税込経理方式が向いているケース
税込経理方式は、計算や記帳にかかる作業負担を減らしたい場合に適した方法です。
税抜経理方式では、日々の取引きでも税抜で記帳する上使用する勘定科目も多くなります。
そのため、会計処理をシンプルにしたい場合には税込経理方式が適しています。
免税事業者から課税事業者になった事業者にとって、記帳の方式を変えたくないケースもあるはずです。
ただし、税抜経理方式でも、会計ソフトを導入すれば作業負担は大幅に軽減できます。
会計ソフトであれば、税込金額を入力しても自動で税抜にできるので、導入を検討してみてください。
税込経理方式は、消費税額を計算しないため、正確な損益が確定申告まで把握しにく点にも注意が必要です。
消費税込みでの損益を把握する場合には税込経理方式でも問題ではありません。
税抜経理方式が向いているケース
税抜経理方式は、一定の節税策を使う場合により有利になる方法です。固定資産の減価償却では、税抜経理方式を採用していると税抜金額で資産計上できます。
また、少額減価償却資産の購入時も税抜経理方式でも同様に税抜で判断できる税抜経理方式が有利です。
さらに資本金1億円以下の中小企業は800万円以下の交際費を経費計上できますが、この計算も、税抜きにすることで800万円を超えにくくなる税抜経理方式が有利です。
資産の購入や交際費の計上が多いと予想される企業においては税抜経理方式を採用したほうが節税しやすい可能性があります。
税抜経理方式は、損益の金額を把握しやすいほか、消費税額を期中でも把握しやすい点もメリットです。常に正確な損益を知りたい場合にも税抜経理方式をおすすめします。
消費税の仕訳・会計処理での注意点

消費税の会計処理は日常的に発生します。どういった点に留意して会計処理をおこなえばいいのか注意点をまとめました。
消費税の経費計上は租税公課を使った場合のみ
消費税と聞くと、費用だから経費計上できるとすぐに考えるかもしれません。しかし、消費税を経費計上できるのは税込経理方式で租税公課を使う場合だけです。
消費税は事業を運営するために必要な租税です。そのため、租税公課として経費計上できます。
インボイスとそれ以外は分けて処理をする
インボイス制度が導入されるようになり、普通の請求書だけでなく適格請求書(インボイス)の発行がはじまりました。
インボイス制度では、適格請求書がないと消費税に仕入税額控除が適用されません。そのため、企業によっては従来の請求書と適格請求書を分けて処理することになります。
また、分けて処理しなければいけないのは適格請求書だけではありません。複数税率の計算もあります。
現在、10%と8%の税率が混同しています。特に取引先が多い、適格請求書が混在するような企業においては、会計処理業務が煩雑になると考えて準備を進めておいてください。
3年ごとに変わる経過措置・控除割合に注意する
インボイス制度は2023年10月1日から始まった制度で、仕入税額校の経過措置が設けられています。
免税事業者と取引きが多い課税事業者にとって、急に仕入税額控除が廃止されてしまうと負担が大きくなってしまいます。
そこで設けられたのが6年間の仕入れ税額控除の経過措置です。
仕入税額控除の経過措置とは、適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定の割合で仕入れ税額控除を受けられるようにするものです。
具体的には、インボイス制度が開始した2023年10月1日から3年間は、免税事業者等からの課税仕入は80パーセント控除可能となりました。
さらに2026年10月1日から3年間は、50%の仕入税額控除が認められています。
仕入税額控除の経過措置を利用するためには、帳簿と要件を満たした請求書の保存が必要です。
請求書には必要事項として適用を受ける課税仕入れであることが記載されなければいけません。
経過措置期間中はその期間だけの会計処理も必要になるので、マニュアルとルールを準備しておくようにおすすめします。
まとめ・仕訳方式に合わせて消費税を正しく会計処理しよう
消費税にかかわる仕訳は税込経理方式と税抜経理方式があり、どちらかを選ぶことになります。
それぞれにメリットがあるものの、事業者の考え方やビジネスの形態によって適した処理方法は違うはずです。
会計にかかわる処理や仕訳は、煩雑ではあるもののインボイス制度の経過措置のように利用することで税負担を軽減できるケースもあります。
帳簿の書き方や仕訳方法請求書の保管といったルールを事前に決めてから対処するようにしてください。
創業手帳では、消費税の確定申告にもふれた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。今年からはじめての確定申告をする方はもちろん、毎年行っている方であっても変更点を確認するのに使っていただけるガイドブックとなっていますので、ぜひあわせてご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)